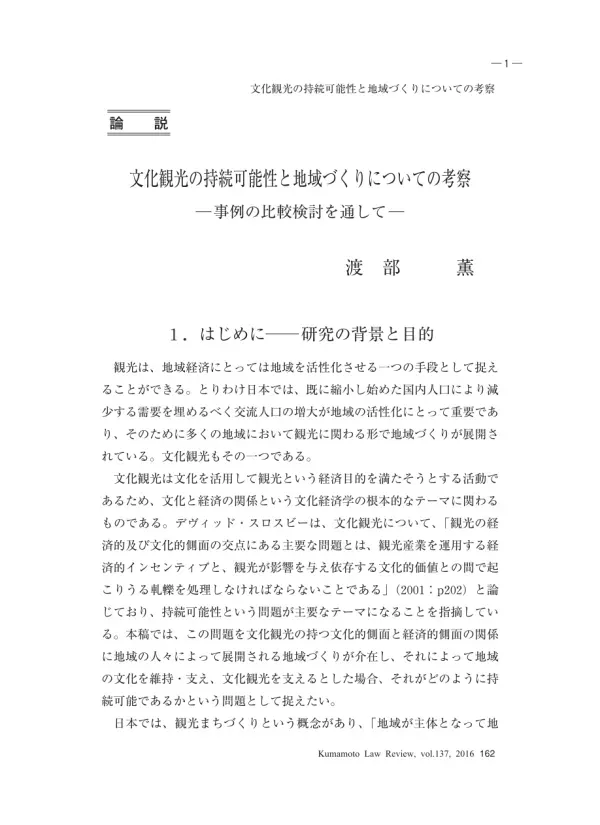
文化観光の持続可能性:地域づくりプラットフォーム
文書情報
| 著者 | 渡部 薫 |
| 専攻 | 文化観光学、地域開発学、もしくは関連分野 |
| 文書タイプ | 論文、考察論文、または研究報告 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 718.69 KB |
概要
I.文化観光の持続可能性 地域づくりとプラットフォームの役割
本稿は、文化観光の持続可能性をテーマに、地域住民による地域づくり活動がいかに重要な役割を果たすかを論じています。特に、明確な全体計画のない創発的な地域づくりに着目し、その活動を支えるプラットフォームの形成と再構成、そして社会的価値の創造・実現について分析しています。文化と経済の両立が文化観光の持続可能性に不可欠であり、地域固有の文化を維持・発展させるための地域づくりの重要性を強調しています。 David Slosbergの指摘する観光産業の経済的インセンティブと文化的価値の軋轢の問題を踏まえ、地域づくりプラットフォームがその調整役として機能すると論じています。
1. 文化観光の持続可能性における課題 文化と経済の両立
本稿は、文化観光の持続可能性を巡る根本的な問題を論じています。文化観光は、文化を経済目的である観光に活用する活動であり、文化経済学の核心テーマに直結します。 冒頭では、David Slosbergの論考(2001:p202)を引用し、観光産業の経済的インセンティブと、観光が依存する文化的価値の間の軋轢が、持続可能性にとって主要な課題であると指摘しています。観光資源となる地域の文化が、経済活動によって一方的に消費され、文化的価値が損なわれたり低下したりすれば、経済活動自体も打撃を受け、文化観光の持続可能性は脅かされます。そのため、文化観光の持続可能性には、地域文化が経済に貢献するだけでなく、経済によって支えられる、相互依存的な関係が不可欠です。この相互作用を促進し、文化と経済のバランスを保つための具体的な方策として、地域住民による地域づくり活動の役割に焦点を当て、その持続可能性を検証していきます。
2. 地域づくり活動の類型と社会的価値の創造
本研究では、地域づくり運動の中でも、民間主導、非行政主導、明確な全体計画のない創発的な、理念志向型の非利益主導型を対象としています。これは、予め計画されたシナリオに沿って活動を進めるのではなく、状況に応じて自発的に生まれる活動が地域全体を動かすようなスタイルを指します。営利目的ではなく、地域の公共的問題への取り組みを目的とした、公的志向性が強い活動に焦点を当てています。行政の関与を完全に排除するものではありませんが、民間主体の自発的な活動が中心です。 地域づくり活動の目的として、社会的価値の創造・実現という視点を導入しています。この社会的価値とは、単なる経済的利益ではなく、地域住民の生活の質の向上や地域社会の活性化といった、より広い意味での価値を指しています。 こうした活動の持続可能性を支える仕組み、すなわちプラットフォーム形成の重要性を強調し、その形成プロセスと機能について分析を進めていきます。
3. 地域づくりプラットフォームの形成と 場 の役割
地域づくり活動の持続可能性を支える重要な要素として、プラットフォームの形成が挙げられます。これは、個々の活動を育み、地域づくりの共同や連携を促進する社会的枠組みです。本稿では、このプラットフォームが、地域づくり活動の持続的な展開を支え、文化観光の発展へと繋がる重要な役割を果たすと考えます。プラットフォームは、必ずしも組織化されたり制度化されたりする必要はなく、アクター間の相互作用によって創発的に形成される、いわば「場」と言えるものです。 この「場」の概念については、野中郁次郎や伊丹敬之らの研究を参考に、アクター間の物理的、仮想的な、あるいは心理的な共有空間として捉え、相互作用を通じて知識創造や価値創造が行われる場であると説明しています。 「場」の形成には、アクター間の共通理解や連帯意識、目的やミッションの共有といった要素が重要であり、これらの要素が、アクター間の相互作用を促進し、プラットフォームの機能を高めていくと論じています。
4. コンテクスト転換と持続可能性 新たな価値の創造
アクター間の相互作用によって形成される「場」のダイナミズムを理解するために、コンテクスト(解釈枠組み)の概念を用います。寺本義也の知のマネジメントに関する研究を参考に、コンテクストは行為に意味を与え、同時に行為によって生み出される(コンテクスト再帰性)と捉えます。 コンテクスト転換は、参加者の関係性の変化や新たな参加者の加入などを通じて、相互作用によって既存のコンテクストが変化し、新たなコンテクストが創造されるプロセスです。このコンテクスト転換によって、既存のコンテンツに新たな意味や価値が生み出され、ひいては地域づくりの活動の持続可能性が支えられると論じています。 地域づくりの「場」においては、アクター間の情報集合の変化が共通理解の増進と心理的共振をもたらし、協働的行動、そして社会的価値の追求・実現へとつながります。 外部から新しいアクターや価値観が導入されることによってコンテクスト転換が起こり、新たな社会的価値を生み出し、地域づくりが持続する可能性が示唆されます。
II.民間主導の地域づくり活動の推進 動機とプラットフォーム
地域づくりの民間アクターの動機付けとして、地域への思いや課題への関心、地域アイデンティティ、シヴィックプライドが挙げられます。これらの関心から生まれる活動が、地域づくりプラットフォームの基礎となり、持続的な展開を可能にします。プラットフォームは、必ずしも組織化されたものではなく、アクター間の相互作用によって創発的に形成され、知識や価値を生み出します。コンテクスト(解釈枠組み)の概念を用いて、アクター間の相互作用がコンテクスト転換、ひいては社会的価値の創造につながることを示唆しています。
1. 民間アクターの活動推進力 地域への思いと課題意識
民間主導の地域づくり活動の推進力を探る上で、まず重要なのは、活動の動機付けです。多くの場合、地域への深い思いや、地域課題への強い関心が、活動の原動力となっています。 本文では、地域への愛着や関心、そして地域文化が持つ固有の価値が、人々の地域アイデンティティやシヴィックプライドを育み、活動への参加意欲を高めていると指摘しています。 地域アイデンティティは、地域への関心を高め、地域活動への参加を促進する重要な役割を担います。 地域課題の解決や、地域社会に対する理念・ビジョンの実現を目指した活動が、こうした地域への思いや関心から自然発生的に生まれてくる可能性を示唆しています。さらに、地域づくり活動には、自己表現欲求も含まれている可能性があり、その表現したい内容が活動で創造される価値として具体化すると考えられます。例えば、後述の別府市の事例では、アート団体代表の山出淳也氏が、芸術家としての自己表現を地域づくり活動を通じて実現している点が挙げられます。
2. プラットフォーム形成 アクター間の相互作用と持続可能な展開
地域づくり活動の持続可能性を支える上で、アクター間の関係性、そしてプラットフォームの形成が非常に重要です。 活動の初期段階では、関係の場、すなわちプラットフォームは必ずしも明確に存在するわけではありません。しかし、活動が展開されるにつれて、関係者間の相互作用の積み重ねを通じて、地域づくりにおける意義や重要性が明確化され、プラットフォームとしての機能が強化されていきます。これは、必ずしも組織化や制度化を意味するものではなく、アクター間の相互作用によって創発的に形成される「場」が、実質的にプラットフォームとしての機能を果たすことが重要です。 この「場」は、アクター間の物理的、仮想的な、あるいは心理的な共有空間であり、そこで相互作用を通じて知識や価値が創造されます。伊丹敬之の定義によれば、「場」とは、人々が参加し、相互に観察し、コミュニケーションを行い、相互に理解し、働きかけ合い、共通の体験をする状況の枠組みです。 この「場」の形成には、参加者間の共通の認識、解釈コード、情報伝達媒体、そして連帯欲求といった要素が重要です。これらの要素がコンテクスト(解釈枠組み)を形成し、アクター間の相互作用を促進する土壌となります。
3. 文化と協働関係 文化資源としての地域文化
地域文化は、協働関係の形成において重要な役割を果たします。地域文化は、人々に働きかけ、協働を促進する力を持っているとされています。竹口弘晃は、文化資源学の観点から、文化を「働きかけの対象となる可能性の束」と捉え、文化資源化のプロセスでは、アクター間の利害調整や交渉を通じた共通理解と協調的な関係構築が求められると論じています。 民間アクターによる自発的な取り組みにおいても、地域文化との関わりが協働関係形成の鍵となります。地域文化は地域固有の価値を体現し、地域アイデンティティやシヴィックプライドに働きかけ、地域への関心を高めます。 この地域文化への関与、そして地域課題への共通認識が、プラットフォーム形成の基礎となり、活動の持続可能性を支える重要な要素となります。 コンテクストという視点から見ると、地域文化はアクターの認知や行動を支える構造的前提であり、活動に意味を与え、同時に活動によって再構成されるダイナミックな要素であると言えるでしょう。
III.事例研究 長浜市と黒壁の活動
長浜市の中心市街地活性化の事例では、株式会社黒壁(笹原司朗氏、伊藤光男氏ら中心)の活動が鍵となっています。黒壁銀行の保存・活用を起点に、地域固有の文化(曳山まつり、街並み)を活かした事業展開を行い、観光客増加、空き家・空き店舗の減少に成功しました。黒壁は、地域づくりネットワークの中核として機能し、1996年の北近江秀吉博覧会開催を契機に、更なる地域づくりネットワークの拡大・複合化を促しました。この事例は、民間主導による地域づくりプラットフォームの成功例を示しています。
1. 株式会社黒壁の設立と事業展開 衰退する中心市街地の再生
滋賀県長浜市の中心市街地活性化の事例として、株式会社黒壁の活動が紹介されています。黒壁は、長浜市と地元民間企業の出資による第三セクターとして設立され、中心市街地の歴史的建造物である「黒壁銀行」の活用を目的としています。 中心人物は笹原司朗氏と伊藤光男氏で、中心市街地の商店主ではなく、郊外で非商業事業を営む事業家です。彼らは、黒壁銀行の売却と取り壊しの危機をきっかけに、買い戻し、保存・活用することで街の活性化を目指しました。 その動機は、長浜の伝統行事である「曳山まつり」の存続の危機感と、それに伴う街並みの衰退への危機意識でした。曳山文化と街並みの保存・再生のためには、街の活性化が不可欠だと考えたのです。 黒壁は、ガラス製品の製造・展示・販売という事業を選びました。これは長浜の地場産業ではなく、ガラスの歴史性、文化性、芸術性、そして国際的な発信力に着目した結果です。この事業は、伝統的な建物を再利用することで町並みの保存・整備を行い、新しい文化的魅力も同時に提供することを目指しました。 その後、他の事業者や市外の企業との連携により事業を拡大し、現在では34店舗にまで至っています。メディアによる報道も相まって、長浜への観光客は1989年の10万人から2000年には200万人に増加しました。
2. 北近江秀吉博覧会と地域づくりネットワークの形成 協働による活性化
黒壁は、中心市街地での事業拡大や空き家・空き店舗の解消だけでなく、地域づくり推進のネットワークの中核として機能しました。多くの市民活動組織も黒壁に触発されて誕生し、黒壁はそれらとネットワークを形成しました。このネットワークは、黒壁の事業ネットワーク、笹原氏らの人的ネットワーク、市や商工会議所などの組織的なネットワークと結びつき、拡大・複合化していきました。 しかし、それ以前は、商店街などの組織など、市内には他にも様々なネットワークが存在し、互いに連携していませんでした。 転機となったのは、1996年に開催された「北近江秀吉博覧会」です。 この大規模なイベントは、長浜の歴史や伝統を見直し、新たな発展の道を探ることを目的としており、「フィナーレからプロローグへ」というコンセプトのもとで、市民団体や1000人もの市民ボランティアが参加しました。 秀吉博は、それまで交流の少なかった商店の人々、市役所職員、市民活動団体、高齢者など、多様な人々の協働を促しました。特に、黒壁と商店街の関係が対立から交流へと変化したことが重要です。 秀吉博を通じて形成されたネットワークから、プラチナプラザ、出島まちづくり塾、まちづくり役場などの新たな組織が生まれ、それらは長浜の地域づくりの重要なアクターとなっています。これにより、黒壁中心のネットワークと秀吉博を契機に形成されたネットワークが結びつき、長浜の中心市街地の地域づくりが多面的に展開されるようになりました。
IV.事例研究 別府市の多様な地域づくり運動
別府市では、1990年代後半から温泉文化を活かした地域づくり活動が活発化。別府八湯竹瓦倶楽部、混浴温泉世界実行委員会などの活動が、多核的な地域づくりネットワークを形成しています。 2005年に設立されたアート団体**(団体名省略)は、アートによる新しい社会的価値を導入し、既存の地域づくりプラットフォームを再構成しました。 この事例は、コンテクスト転換による地域づくり**の持続可能性を示すものです。
1. 別府八湯まちづくり運動の展開 温泉文化と地域活性化
大分県別府市は、戦後、全国一の源泉数と湧出量を誇る温泉を基盤とした観光都市として発展してきました。しかし、社会の成熟化に伴い、従来型の観光業は衰退し、特に中心市街地に大きな影響を与えました。 1990年代後半から、温泉観光や温泉文化と結びついた地域づくり活動が活発化しました。 1998年、中心市街地のシンボル的存在であった竹瓦温泉の保存問題をきっかけに、観光産業研究会の主導で「竹瓦フォーラム」(正式名称:「よみがえるか竹瓦温泉 別府温泉再生の道」)が開催され、別府八湯竹瓦倶楽部が結成されました。 この倶楽部は、「別府八湯ウォーク」「別府八湯温泉博覧会」など、多くのプロジェクトを企画・実施し、鉄輪ゆけむり倶楽部、別府八湯トラスト、ハットウ・オンパク、自立支援センターなどの主要団体が誕生する基盤となりました。 これらの団体は連携し、別府八湯まちづくり運動として、新たな活動を生み出し、互いに影響を与えながら地域づくりを推進しています。インターネット上の「別府八湯メーリングリスト」も、情報共有のプラットフォームとして重要な役割を果たしました。 これらの活動は、地域住民の温泉文化への理解と愛着、そして地域課題への意識を高めることで、観光客の減少という危機感を共有し、それを克服しようとする強い意志が背景にあります。
2. アート活動団体の参入とプラットフォームの再構成 新たな価値の創造
2005年、アート活動団体(団体名省略)が別府市に進出し、既存の地域づくり運動に大きな影響を与えました。 この団体は、「アートの可能性を社会化し、多様な価値が共存する世界を創造する」というミッションのもと、アート活動を通じて地域社会に貢献することを目指しています。 代表の山出淳也氏は、パリで活動していたアーティストでしたが、別府市の地域づくり状況を知り、アートの社会的な可能性を試すため参入を決意しました。 この団体は、「混浴温泉世界」という国際的なアートイベントを企画・実施し、地域づくりメンバーも参加・協力することで、現代アートの地域における価値について議論を重ね、新たな活動スタイルを生み出しました。 これにより、既存の「場」にアートという新たな要素が加わり、コンテクストが再構成され、プラットフォームも変化しました。 別府八湯独立宣言、竹瓦フォーラム、そして別府八湯竹瓦倶楽部の設立は、有志メンバーの密接な相互関係に基づくネットワーク形成を促し、メーリングリストや中心市街地活性化協議会なども含め、多層的なネットワークが形成されました。 勉強会などの非公式な交流の場も、ネットワーク形成に貢献しています。 これらの活動は、社会的価値の創造・提供・実現を目的としており、新たな価値の創造とプラットフォームの形成・再構成は相互作用的な関係にあると解釈できます。
V.地域づくりの持続可能性 文化 アート そしてプラットフォームの役割
長浜市と別府市の事例から、地域づくりプラットフォームの形成と再構成、そして社会的価値の創造が文化観光の持続可能性に不可欠であることが示唆されました。地域固有の文化への愛着や関心が活動の原動力となり、プラットフォームにおけるアクター間の相互作用が新しい社会的価値を生み出します。アートなどの外部からの要素の導入も、コンテクスト転換を通じてプラットフォームの再構成と地域づくりの活性化に貢献する可能性があります。非営利活動と営利活動の循環的な関係も、持続可能性を支える重要な要素です。
1. 地域づくりのプラットフォームの機能と役割 共通認識と価値創造
長浜市と別府市の事例研究から、地域づくりにおけるプラットフォームの重要性が示されています。 関係者間の共通認識の形成や価値創造において、プラットフォームが重要な役割を果たすことが確認されました。プラットフォームは、必ずしも公式な組織として存在するわけではなく、様々な公式・非公式の交流の場がプラットフォームとして機能していることが、両事例に共通しています。 長浜市では、黒壁が主導する地域づくり運動のネットワークがプラットフォームの中核を担い、現在は多核化しつつあります。一方、別府市では、八湯独立宣言以降の中心メンバーが、比較的少数ながらも多核的にプラットフォームを構成しています。 プラットフォームの形成には、関係者間の相互作用や共通の体験の積み重ねが不可欠です。プロジェクトやイベントを通じて、関係者間の密な相互作用と共通体験が生まれ、それが「場」としての機能を獲得し、プラットフォームとして発展していくプロセスが確認できます。長浜市では、秀吉博覧会という大規模イベントが、複数のネットワークを結びつけ、新たな「場」とプラットフォームを形成する役割を果たしました。
2. 社会的価値の創造とプラットフォームの再構成 相互作用とコンテクスト転換
地域づくり活動の持続可能性を支える上で、社会的価値の創造が重要です。 長浜市の黒壁の事例では、創設者たちのビジョンから生まれた価値が、プラットフォームでのアクター間の相互作用を通じて新たな価値を生み出すインキュベーターとしての役割を果たしています。 別府市の事例では、既存のプラットフォームから多くのアイディアが生まれ、様々な活動が誕生しています。 特に、アート活動団体の参入は、既存の「場」のコンテクストを大きく変化させ、プラットフォームの再構成をもたらしました。 新しい価値の創造とプラットフォームの形成・再構成は相互作用的、あるいは補完的な関係にあり、新たな社会的価値の登場が地域づくり活動の持続可能性を支えていることがわかります。 コンテクスト転換の観点からは、新しい価値が外部から導入されることで、コンテクストの転換・再構成が起こり、そこから新たな社会的価値の実現を目指す活動が生まれ、地域づくりが持続する可能性が示唆されます。ただし、外部からの要因に依存する側面も存在し、内部的な循環的な関係とは異なる点に留意する必要があります。
3. 地域文化と公共圏 市民参加と文化観光の持続可能性
地域文化の持続可能性を確保するためには、文化と経済の間に公共圏を介在させることが重要です。非営利の地域づくり活動は、公共圏を支える上で重要な役割を果たします。 しかし、公共圏を効果的に機能させるには、一部のアクターだけでなく、広範な市民の参加が望ましいです。長浜市では、秀吉博覧会をきっかけに多くの市民が地域づくり活動に参加するようになりました。別府市でも、オンパクやアートイベントを通じて市民参加が進んでいます。 しかし、市民が活動に参加するだけでは、公共圏に関わっているとは言えません。地域づくりのプラットフォームに参加し、ガバナンスに何らかの形で関与することが必要です。両事例において、一般市民のプラットフォームへの参加は限定的であり、十分な公共圏が形成されているとは言えません。 長浜市では、黒壁の創設者たちの地域文化(曳山祭、街並み)への愛着が、地域課題への認識と活動のビジョン形成を導きました。一方、別府市では、観光業の衰退という危機感が出発点となっています。 両事例において、活動の持続可能性を支えるのは、公共目的に駆り立てられた非営利活動が地域の文化に投資し、その価値を高め、文化観光という営利活動を支え、その収益が再び非営利活動を支える、文化を媒介とした非営利と営利の循環的な相互依存関係です。
