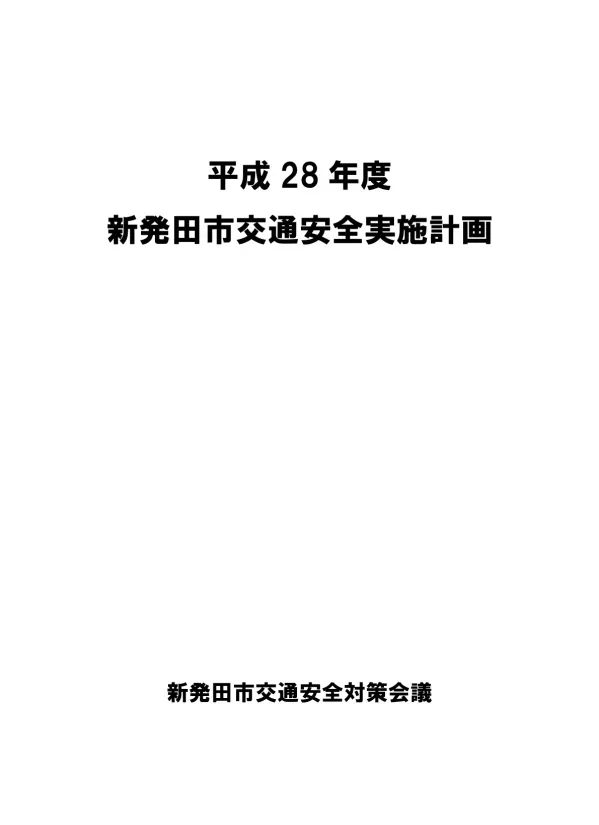
新発田市交通安全対策基本方針
文書情報
| 学校 | 新発田市 |
| 専攻 | 交通安全 |
| 出版年 | 2016 |
| 場所 | 新発田市 |
| 文書タイプ | 交通安全計画 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.56 MB |
概要
I.高齢者交通安全対策の推進
新発田市における高齢者交通事故防止のため、高齢者交通安全推進員との連携強化による交通安全教室の開催(加齢に伴う身体機能の変化への理解促進を含む)、高齢者世帯訪問による啓発活動(チラシ配布と個別指導)、運転免許証自主返納制度の周知徹底を重点施策とする。夜光反射材の活用促進も推進する。
1. 参加型交通安全教室の開催
地域の老人クラブ等を訪問し、参加型の交通安全教室を開催します。教室では、交通ルールの遵守と交通マナーの実践を習慣化するための指導を行い、「加齢に伴う身体機能の自覚」や「交通事故危険回避ゲーム」などを実施することで、高齢者の判断力や反射神経などの身体機能の変化が交通事故に及ぼす影響への理解を深めます。この取り組みを通じて、高齢者が自身の身体能力を正しく認識し、安全な交通行動を心がけることを促します。高齢者の交通事故防止対策として、実践的なスキルと知識の習得を重視した、参加型の教育プログラムを提供することで、より効果的な事故防止に繋げることが期待できます。高齢化社会における交通安全対策として、高齢者自身の積極的な参加と理解を促す、この参加型アプローチは非常に重要です。
2. 高齢者世帯訪問による啓発活動
高齢者の交通事故は、「慣れ・過信・油断」から発生することが多いため、高齢者世帯を直接訪問し、交通安全啓発チラシの配布を行います。単なるチラシ配布だけでなく、その場で事故防止方法について一言声をかけ、積極的な声掛けを行うことで、より効果的な啓発活動を目指します。交通死亡事故の多発地域や交通量が多く危険性の高い地域を重点的に訪問することで、ピンポイントな対策を講じます。この直接的なコミュニケーションを通じ、高齢者一人ひとりに交通安全意識の浸透を図り、安全な行動の促進を目指します。高齢者にとって身近な生活道路での事故が多いことから、この世帯訪問活動は、高齢者へのきめ細やかな対策として非常に有効です。
3. 高齢者交通安全推進員等との連携強化
高齢者交通安全推進員や老人クラブ等と連携し、地域に密着した交通安全対策を推進します。大型店舗等でのチラシ配布などの啓発活動を実施するほか、高齢者の利用が多い場所での啓発活動を強化します。高齢者交通安全推進員は地域に精通しており、高齢者の生活実態に即した啓発活動を行うことができます。彼らとの連携を強化することで、より効果的な交通安全対策を展開することが期待できます。地域住民との信頼関係を築き、地域全体で高齢者の交通安全を支える体制を構築することで、より安全で安心な地域社会の実現に貢献します。高齢者の特性を踏まえたきめ細やかな対応と、地域住民との協働による効果的な対策が重要です。
4. 運転免許証自主返納制度の周知徹底
運転に不安のある高齢者に対して、運転免許証の自主返納制度の周知を図り、返納しやすい環境整備を進めます。高齢者の交通事故防止対策として、自主返納を促進することは非常に重要です。運転に不安を感じながらも、返納をためらう高齢者に対して、制度の周知と相談窓口の設置など、安心して返納できるようサポート体制を整えることが必要です。高齢者の安全と安心を第一に考え、安心して生活できる環境づくりを進めることで、高齢者の尊厳と生活の質を高めることに繋がります。自主返納による事故防止と、高齢者の生活の質の向上を両立させるための施策が求められます。
5. 道路交通環境の整備と夜光反射材の活用促進
高齢者を取り巻く道路交通環境の整備を進め、運転者に対する高齢者保護意識の醸成を図ります。夜光反射材の活用を促進することで、高齢者の視認性を高め、事故を未然に防ぎます。高齢者の安全な通行を確保するため、道路標識の整備や視覚的な工夫など、高齢者の視覚能力や認知機能を考慮した道路環境の整備が重要になります。また、夜光反射材の積極的な活用を推進することで、特に薄暮時や夜間の視認性を向上させ、事故リスクの軽減を目指します。高齢者の安全確保と、運転者側の安全運転意識の向上を両面から支援する対策が求められます。
II.歩行者及び自転車の安全対策の推進
年齢層に応じた交通安全教育の体系化、幼稚園・保育園への教材配布、実践的な自転車教室の実施により、歩行者と自転車利用者の安全意識向上と交通ルール遵守を促進する。特に、夕暮れから夜間にかけての事故防止に注力する。
1. 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進
幼児から高齢者まで、年齢層に応じた段階的かつ体系的な交通安全教育を推進します。これは、交通事故の発生を抑制し、安全な道路環境を整備するために不可欠な取り組みです。教育内容は、年齢層ごとに適切な内容とし、正しい道路横断方法や自転車の安全な乗り方、歩行者への配慮など、交通マナーの向上と交通ルールの遵守を徹底的に指導します。特に、歩行者や自転車利用者の保護意識の啓発に力を入れることで、交通事故の発生リスクを低減させます。この教育プログラムは、単なる知識の伝達にとどまらず、実践的なスキルを習得させ、安全な行動を習慣化させることを目指します。年齢や状況に合わせたきめ細かい指導を行うことで、全ての市民が安全に暮らせる街づくりを目指します。
2. 幼稚園 保育園における交通安全教育
園児が交通マナーを実践する基本的な技術・知識を習得できるよう、交通安全関係機関・団体や交通安全指導員が、実技やゲームなどを用いた交通安全教育を実施します。また、幼稚園・保育園に交通安全紙芝居などの教材を配布し、遊びを通して交通安全意識の向上を図ります。楽しく学べる環境を提供することで、幼少期から交通安全への意識を育むことを目的としています。実践的な指導と、親しみやすい教材を用いることで、園児たちが交通ルールを自然と理解し、安全な行動を身につけることを促します。この早期教育は、将来にわたる交通事故防止に大きく貢献すると考えられます。
3. 自転車教室の実施による安全利用の促進
自転車の正しいルールとマナーの向上を促進するため、実践的な自転車教室を開催します。この教室では、自転車の安全な乗り方や交通ルールを学ぶだけでなく、自転車利用者としての責任や、歩行者への配慮など、社会的なマナーについても指導します。実践的なトレーニングやロールプレイングなどを交え、自転車の安全な利用方法を習得させます。自転車事故の防止には、正しい知識とスキルだけでなく、安全意識の向上も不可欠です。自転車教室を通して、安全な自転車利用の習慣を身につけさせることで、自転車事故の減少に貢献します。特に、近年増加傾向にある自転車事故の防止に重点を置いた教育を行います。
III.飲酒運転根絶対策の推進
新発田市では平成27年度に飲酒運転事故0件を達成したが、全国的な問題である飲酒運転の根絶に向けて、広報・啓発活動の強化、飲食店への協力要請、警察署への指導取締り強化を要請する。飲酒運転は重大な犯罪行為であることを啓発する。
1. 広報 啓発活動の強化
飲酒運転は重大な犯罪行為であり、その危険性と責任の重大性を市民に認識させるため、積極的な広報・啓発活動を展開します。具体的には、各季の交通安全運動、交通安全教室、交通安全推進大会などのあらゆる機会を通じて、広報紙、FMラジオ放送、市ホームページなどを活用し、飲酒運転の危険性を周知徹底します。家庭、地域、職場など、社会全体で飲酒運転を許さない雰囲気を作ることを目指し、多角的なアプローチで啓発活動を実施します。平成27年度は飲酒運転事故が0件でしたが、全国的には依然として飲酒運転事故が発生していることから、継続的な啓発活動が不可欠です。飲酒運転による事故の根絶に向けて、市民一人ひとりの意識改革を促すための徹底した広報活動に注力します。
2. 飲食店等への協力要請
飲酒運転は運転者だけでなく、アルコール類を提供する側にも責任があるという認識を促すため、飲食店組合等と連携し、繁華街等の飲食店を訪問します。訪問では、飲酒運転の防止に繋がるよう、車両での来店の有無の確認や、タクシー・運転代行サービスの利用促進を呼びかけます。アルコールを提供する立場からの協力も得ることで、飲酒運転を未然に防ぐための連携体制を構築します。飲食店側にも飲酒運転防止の責任があることを理解させ、協力体制を構築することで、より効果的な飲酒運転防止対策を推進します。地域社会全体で飲酒運転を抑制するための協調体制を構築し、安全な地域社会の実現を目指します。
3. 警察署への指導取締り強化要請
新発田警察署に対し、飲酒運転に対する徹底した指導と取締りを要請します。警察による厳格な取り締まりは、飲酒運転の抑止力として非常に有効です。警察の積極的な取り締まりと、市民への啓発活動を両輪として進めることで、飲酒運転による事故を減少させる効果が期待できます。飲酒運転に対する社会全体の意識改革と、厳格な法執行の両面からアプローチすることで、飲酒運転を根絶するための強力な対策を推進します。飲酒運転による重大な被害を未然に防ぐため、関係機関と連携した強力な対策を継続的に実施します。
IV.シートベルト チャイルドシートの着用対策の推進
交通安全運動、交通安全教室、世帯訪問等を活用し、シートベルトとチャイルドシートの着用徹底を図る。幼稚園・保育園での啓発活動も強化する。交通死亡事故削減に繋げる。
1. シートベルト着用徹底のための指導 広報 啓発活動
自動車乗車中の交通死亡事故において、シートベルト着用率が依然として低い状況にあることから、各季の交通安全運動、交通安全教室、世帯訪問などのあらゆる機会を通じて、シートベルト着用を徹底するための積極的な指導・広報・啓発活動を展開します。特に後部座席のシートベルト着用率とチャイルドシートの使用率の低さが課題となっているため、これらの着用促進に重点を置いた啓発活動を実施します。交通安全教育の一層の推進を通じて、正しい知識と安全意識の定着を図り、シートベルトとチャイルドシートの着用を習慣化させることを目指します。交通事故による死亡者数の減少、特に後部座席の乗員や幼児の安全確保を最優先に、効果的な啓発活動と教育プログラムの開発・実施に努めます。
2. チャイルドシート着用促進のための連携強化
チャイルドシートの着用促進のため、幼稚園・保育園の交通安全教室や園の送迎時において、新発田警察署、新発田地区交通安全協会、交通安全指導員、交通安全母の会など関係機関と連携し、保護者への指導・啓発活動を行います。特に、幼い子供たちの安全確保は最重要課題であり、チャイルドシートの正しい使用方法や重要性を保護者へ丁寧に指導します。関係機関との緊密な連携により、効果的な啓発活動を行い、チャイルドシートの着用率向上を目指します。具体的な啓発活動として、チャイルドシートの装着実演や、正しい使用方法に関するパンフレットの配布なども検討します。子供たちの安全を守るため、関係各所が協力して取り組むことで、交通事故から子供たちを守る安全な環境づくりに貢献します。
V.通学路の安全確保の推進
教育委員会、学校、保護者、道路管理者、警察署、自治会等による合同点検等を通じ、通学路の安全確保対策を継続的に実施する。
1. 通学路安全確保のための合同点検
通学路の安全確保を継続的に行うため、教育委員会、学校、保護者、道路管理者、新発田警察署、自治会などが参加する合同点検を実施します。この合同点検では、通学路の現状を詳細に把握し、危険箇所や改善すべき点を特定します。関係機関が連携して、通学路における課題を共有し、具体的な対策を検討します。点検結果に基づいて、道路の改良や、歩道・区画線・カーブミラーなどの交通安全施設の整備を行い、安全な通学路の環境整備を進めます。児童生徒の安全な通行を確保するため、関係機関が連携して取り組むことで、より効果的で安全な通学路環境を実現します。安全な通学路の確保は、子どもたちの安全を守る上で極めて重要です。
VI.交通ルールの遵守とマナー向上対策の推進
あらゆる機会を通じて交通ルールの遵守と正しい交通マナーの定着化を図る。関係機関・団体は模範を示し、市民全体のマナー向上に努める。交差点事故防止のため、交通安全施設の整備・充実も推進する。
1. 指導 広報 啓発活動の展開
交通安全の基本である交通ルールの遵守とマナーの向上のため、各季の交通安全運動、交通安全教室、交通安全推進大会など、あらゆる機会を通じて積極的な広報・啓発活動を展開します。市民一人ひとりが交通ルールを理解し、正しい交通マナーを実践できるよう、多様な媒体と方法を用いた啓発活動を行います。具体的な活動としては、広報紙、FMラジオ放送、市ホームページなどを活用した情報発信、街頭での啓発活動、交通安全教室の実施などが挙げられます。これらの活動を通じて、市民の交通安全意識の向上と、交通ルールの遵守、正しいマナーの定着化を目指します。交通安全意識の醸成は、交通事故の減少に繋がる重要な要素です。
2. 模範となる交通ルールの遵守
交通安全関係者、関係機関・団体の車両、交通安全指導車などの公用車が、率先して交通ルールを遵守することで、市民全体のマナー向上を図ります。公的機関が模範となる行動を示すことで、市民への啓発効果を高めることができます。交通ルールを厳守することは、交通安全の基本であり、市民に安心・安全な交通環境を提供するために不可欠です。関係機関が率先して交通ルールを守り、模範となる行動を示すことで、市民の交通ルールの遵守意識を高め、交通マナーの向上に繋げます。率先垂範による模範的な行動は、市民の交通安全意識向上に大きく貢献します。
VII.交差点における交通事故防止対策の推進
交差点事故減少のため、交通ルール遵守とマナー向上の推進、カーブミラー等の交通安全施設の整備・充実、警戒標識や警告看板の設置を推進する。
1. 交通ルールの遵守とマナー向上のための施策
交通事故の半数以上を占める交差点事故の減少を目標に、交通ルールの遵守とマナー向上を推進します。これは、交通安全の基本であり、市民一人ひとりが高い意識を持って安全行動を取れるよう、各季の交通安全運動、交通安全教室、交通安全推進大会など、あらゆる機会を通じて積極的な広報・啓発活動を展開します。具体的には、広報紙、FMラジオ放送、市ホームページなどを活用した情報発信や、街頭での啓発活動、交通安全教室の実施などが挙げられます。これらの活動を通じて、市民の交通安全意識の向上と、交通ルールの遵守、正しいマナーの定着化を目指します。交通事故の削減には、市民一人ひとりの意識と行動が重要です。
2. 交通安全施設の整備 充実
交差点における交通事故防止のため、カーブミラーなどの交通安全施設の整備・充実を推進します。また、交差点の車両通行環境に応じて、事故を未然に防ぐため「警戒標識や警告看板」を設置します。これにより、交差点における視認性を高め、ドライバーの安全運転意識を高めることを目指します。安全な道路環境の整備は、交通事故防止に大きく貢献します。特に、事故多発地点への対策を重点的に行い、安全な道路環境を整備することで、市民の安全・安心を確保します。安全な交通環境の整備は、交通事故の防止と交通の円滑化に不可欠です。
VIII.交通環境の整備
歩行者、自転車、自動車が安全に走行できる道路環境整備(歩道、区画線、カーブミラー等の整備、バリアフリー化を含む)を推進する。自転車放置防止対策も実施する。
1. 道路改良と交通安全施設の整備
歩行者、自転車、自動車などが安心して安全に走行できるよう、道路改良と交通安全施設の整備を推進します。具体的には、歩道、区画線、カーブミラーなどの整備を行い、交通事故の発生しにくい道路環境づくりを目指します。特に、高齢者や障害者、妊産婦など、歩行者が生活する上で行動の妨げとなる障壁をなくすため、バリアフリーな歩道の整備を推進します。安全で快適な歩行空間を確保することで、交通事故の発生率を抑制し、誰もが安心して通行できる道路環境の整備を目指します。安全な道路環境の整備は、交通事故防止に大きく貢献します。
2. 交通信号機等の適正な設置
交通信号機、横断歩道、一時停止標識などの設置については、交通事故多発地点を重点に、地域からの要望・意見を踏まえ、新発田警察署に上申を行い、適正な設置を推進します。これは、交通事故の防止と交通の円滑化を図るための重要な取り組みです。地域住民の意見を反映することで、より実効性のある対策を講じることができます。交通事故多発地点への対策を優先的に進めることで、効果的に交通事故を減らすことを目指します。安全でスムーズな交通の流れを確保することで、市民の生活の質の向上に貢献します。
3. 自転車放置防止対策
公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、市民の生活環境の保全と良好な都市環境の形成を推進します。自転車の放置は、通行の妨げとなるだけでなく、景観を損ねる原因にもなります。そのため、自転車の適切な駐輪場所の確保や、放置自転車に対する指導・取締りを強化します。放置自転車問題への対策は、市民生活の質の向上に繋がります。放置自転車を減らすことで、安全で快適な街づくりに貢献します。適切なルールとマナーの啓発を通して、市民一人ひとりが責任ある行動をとることを促します。
IX.救助 救急体制の充実
交通事故による負傷者の救命率向上のため、消防本部への協力要請、応急手当講習会開催(AED利用を含む)を推進する。
1. 救助 救急体制の整備
交通事故による負傷者の救助と救命を最優先事項とし、負傷者の救命率向上のため、新発田地域広域消防本部に対し、これまで以上の救助活動の円滑な体制づくりを依頼します。迅速で的確な救助活動体制の構築は、交通事故による被害を最小限に抑える上で極めて重要です。消防本部との連携を強化し、迅速な現場対応と、救急搬送体制の充実を図ります。関係機関との協力体制を構築することで、より効率的で効果的な救助・救急体制の構築を目指します。交通事故発生時の迅速かつ適切な対応が、人命救助に大きく貢献します。
2. 応急手当の普及促進
交通事故による負傷者への迅速かつ適切な応急手当を推進するため、応急手当の知識・技術の普及に努めます。具体的には、自動体外式除細動器(AED)を利用した心肺蘇生法を学ぶ応急手当講習会などを開催します。これにより、現場での初期対応の質を高め、救命率の向上を目指します。応急手当の知識・技術を市民に広く普及させることで、交通事故発生時の被害を最小限に抑えることができます。講習会を通じて、市民の救命スキル向上に貢献します。初期対応の迅速性と適切さが、負傷者の予後を大きく左右します。
X.運転者教育等の推進
安全意識の向上と安全運転行動の促進のため、自動車教習所への協力依頼、関係機関と連携した交通安全教室や事業所における企業内教育を積極的に推進する。危険予知運転の重要性を啓発する。
1. 市内自動車教習所等への協力依頼
変化する道路交通状況に適切に対応できる安全意識を身につけ、交通ルールを守り、思いやりを持った安全な運転行動ができる運転者の育成を図るため、市内の自動車教習所に協力を依頼します。具体的には、危険への対応能力を高める危険予知運転や、高速交通時代に対応した高速道路運転についての教習内容の充実を要請します。運転者教育の質を高めることで、安全運転技術の向上と、安全運転に対する意識の醸成を目指します。運転者側の不注意による事故が多い現状を踏まえ、安全運転技術の向上と安全意識の醸成に力を入れた教育体制の構築を図ります。安全な運転行動の普及は、交通事故防止に大きく貢献します。
2. 関係機関との連携による運転者教育
運転者側の不注意による事故が過半数を占めていることから、正しい交通マナーを実践する運転者教育を徹底するため、関係機関と連携し、交通安全教室や事業所における企業内教育などを積極的に推進します。安全運転管理者への研修会を通じ、交通事故の実態や交通法規の改正内容などの情報提供を行い、事業所における企業内教育を支援します。関係機関と連携することで、より効果的な運転者教育を展開し、交通事故の発生率を低減します。企業内教育の充実を通じて、職場における安全運転意識の向上を目指します。安全運転意識の向上は、交通事故防止に繋がる重要な要素です。
XI.交通安全思想の普及啓発
年齢層に応じた段階的・体系的な交通安全教育の推進、地域参加型の交通安全教室開催、家庭・地域・学校・職場における意識向上を図る。交通事故の実態を踏まえた広報活動を展開する。
1. 段階的かつ体系的な交通安全教育
交通事故は、交通安全意識とモラルの低下が大きく影響していることから、モラル向上を最重点に、自他の生命尊重の理念のもと、家庭、地域、学校、職場といった領域別、そして幼児から高齢者まで、成長過程に合わせた段階的かつ体系的な交通安全教育を推進します。年齢や発達段階に応じた適切な内容の教育を実施することで、交通安全意識と交通マナーの向上を目指します。市、市民、関係機関・団体が一体となって交通安全教育を推進し、計画段階から地域住民の参加促進を図り、対象者を拡大した地域参加型の交通安全教室の開催を推進します。教育機関や地域における自治会、老人クラブ等の交通安全教室開催にも、市と関係機関・団体が積極的に協力します。
2. 効果的な広報活動の展開
市民の交通安全への関心と意識を高めるため、関係機関・団体と密接に連携し、家庭、学校、地域などに、交通事故の実態を踏まえた効果的で日常生活に密着した内容の広報活動を行います。広報紙、ポスター、FMラジオ放送などを活用し、市民に交通安全の重要性を訴えます。交通事故の実態を分かりやすく伝え、市民が日々の生活の中で実践できる具体的な交通安全対策を提示します。また、交通事故により保護者が死亡、または重度の後遺障害者となった家庭の幼児・児童・生徒の健全な育成を支援するため、交通遺児等の支援事業の周知にも努めます。効果的な広報活動を通じて、市民の交通安全意識の向上を目指します。
XII.踏切道の安全対策
踏切事故防止のため、鉄道事業者への要望による構造改良、自動車運転者・歩行者への安全意識向上と緊急措置の周知徹底を図る。
1. 踏切道構造の改良
踏切事故の防止を図るため、自動車が通行する踏切道の幅員が接続する道路の幅員より狭いなど、危険性の高い踏切道については、地域住民からの要望・意見を踏まえ、鉄道事業者へ構造改良を要望します。これは、踏切事故を減少させ、交通の円滑化を図るための重要な対策です。地域住民の意見を反映することで、より効果的な対策を講じることができます。安全な踏切環境の整備は、交通事故防止に大きく貢献します。特に危険性の高い踏切道から順次改良を進めることで、安全性の向上を目指します。
2. 踏切道利用者への安全意識向上と緊急時対応の周知
踏切事故は、直前横断や落輪などが原因となることが多いことから、鉄道事業者と協力して、自動車運転者や歩行者など踏切道利用者に対する安全意識の向上を図ります。踏切事故発生時の非常ボタンの操作方法など、緊急時の適切な対応方法についても周知徹底を図り、広報活動などを強化します。安全な踏切利用のための知識と、緊急時の適切な行動を市民に周知徹底することで、踏切事故の発生を抑制します。鉄道事業者との連携を強化することで、より効果的な安全対策を展開します。市民の安全意識向上と、緊急時の適切な対応の普及が重要です。
