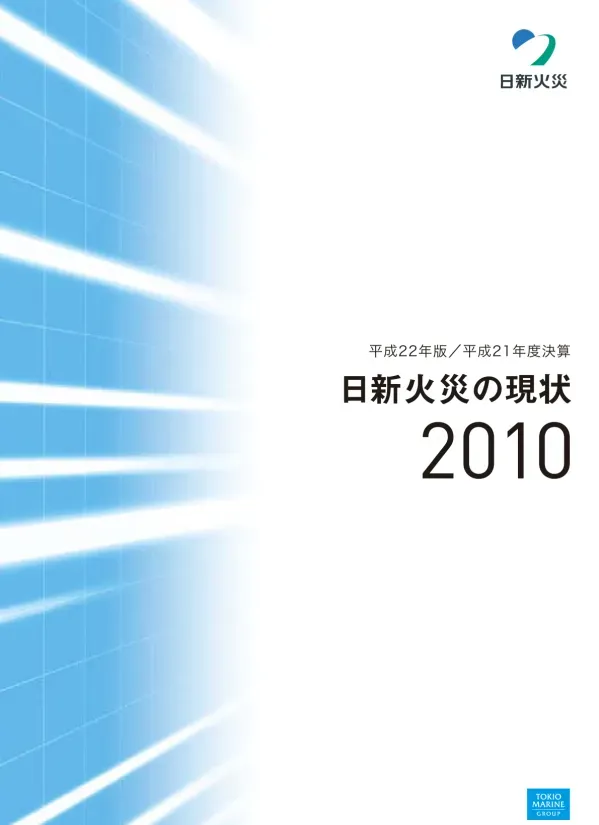
日新火災2010年ディスクロージャー誌
文書情報
| 著者 | 日新火災海上保険株式会社 |
| 会社 | 日新火災海上保険株式会社 |
| 場所 | 東京都千代田区 |
| 文書タイプ | ディスクロージャー資料(業務及び財産の状況に関する説明資料) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 7.60 MB |
概要
I.経営理念と中期経営計画 Management Philosophy and Medium Term Management Plan
日新火災海上保険株式会社は、「お客さま本位の安心と補償をお届けし、最も身近で信頼されるリテール損害保険会社を目指す」ことを経営理念に掲げています。2007年度から開始した5ヵ年の中期経営計画では、内部統制の強化と顧客満足度向上を軸に、東京海上グループの一員として国内リテール市場での成長を目指しました。2009年度からは「変革と実行 2011」計画に基づき、独自のビジネスモデルを磨き上げ、企業価値向上に繋がる取り組みを継続しています。 損害保険サービス業への進化を目指し、高品質で分かりやすい商品・サービス提供に注力しています。
1. 経営理念 顧客本位のリテール損害保険会社を目指して
日新火災海上保険株式会社は、その経営理念として『お客さま本位の安心と補償をお届けし、最も身近で信頼されるリテール損害保険会社を目指す』ことを明確に掲げています。この理念の実現のため、数々の施策を実行し、顧客満足度向上と信頼の構築に努めてきました。 顧客本位という考え方は、商品・サービス開発、組織運営、業務プロセスに至るまで、あらゆる側面に浸透しており、顧客の視点に立ったビジネスモデルの構築と発展が目指されています。顧客の声を真摯に受け止め、継続的な改善に取り組む姿勢が、この理念を支える重要な要素となっています。 企業として、誠実で真面目な運営、そして徹底した内部統制を敷くことで、顧客からの信頼をさらに深めていくという強い意志が示されています。 この理念に基づいた企業活動が、日新火災の事業展開の原動力であり、今後の成長戦略にも大きく影響を与えていると言えるでしょう。長期的な視点で顧客との信頼関係を構築し、顧客にとって真に役立つ保険会社を目指していることが、この経営理念から読み取れます。
2. 5ヵ年の中期経営計画 内部統制強化と顧客本位経営の推進
2007年度に開始された5ヵ年の中期経営計画は、『強固な内部統制を土台とした損害保険サービス業への再創造』と『お客さま本位における業界トップランナーの位置を占める企業となること』という二つの大きな目標を掲げていました。 この計画では、商品・サービス、組織構造、業務プロセスなど、あらゆる側面において顧客視点からの見直しが行われ、顧客本位のビジネスモデルの更なる発展を目指した様々な取り組みが展開されました。 計画期間中は、顧客のニーズを的確に捉え、それに対応する商品・サービスの開発、提供に重点が置かれ、顧客満足度の向上に繋がる施策が数多く実行されました。また、内部統制の強化も重要な柱であり、業務の効率性、財務報告の信頼性、法令遵守、資産保全といった側面から、企業運営の透明性と健全性を高めるための取り組みが積極的に行われました。これらの努力は、顧客からの信頼獲得、ひいては企業価値向上に大きく貢献するものと期待されていました。
3. 東京海上グループとの連携と今後の展望 国内リテール市場における成長戦略
2009年度からは、東京海上グループの新中期経営計画「変革と実行 2011」がスタートし、日新火災は国内リテール市場における成長を担う重要な役割を担うこととなりました。 東京海上グループとの連携を強化することで、グループ全体の企業価値向上に貢献するとともに、自社の独自のビジネスモデルを更に磨き上げ、成長性と生産性の向上を目指しています。 グループの資源やノウハウを活用することで、顧客へのサービス提供基盤を強化し、顧客サービス力の向上に繋げていく戦略が採られています。 今後の展望としては、コンプライアンスの徹底と適正な業務運営、そしてお客さまの声を反映した継続的な改善を通じて、顧客本位のトップランナー企業を目指し、全社一丸となって取り組んでいくことが明確に示されています。 東京海上グループの一員として、グループ全体の戦略と連携しながら、独自の強みを活かし、国内リテール市場での更なる発展を目指していくという強い意志が感じられます。
II.商品開発と顧客サービス Product Development and Customer Service
顧客ニーズに応える高品質な商品開発を継続し、2009年度には約100年ぶりの保険法改正に対応した商品改定を実施しました。家計向け火災保険では「罹災時安心サポート」などの新サービスを導入し、お客さま目線の開発に力を入れています。顧客問合せ窓口であるテレフォンサービスセンターは、迅速かつ丁寧な対応で高い顧客満足度を獲得し、質の高いサービス提供体制を構築しています。代理店向けには、商品説明スキル向上のためのコンテストを開催し、顧客への分かりやすい説明を重視した研修を行っています。
1. 高品質で分かりやすい商品開発
日新火災は、顧客に高品質で分かりやすい商品を提供することに重点を置いています。2009年度も、この方針に基づき、様々な取り組みが推進されました。特に、約100年ぶりの保険法改正への対応においては、保険契約者保護の強化という基本コンセプトと、自社の経営理念である『お客さま本位』の考え方を融合させ、商品の改定を実施しました。 具体的な例として、製造業のものづくりの知見を活かし、1月にリリースされた家計向け火災保険では、『罹災時安心サポート』という新たなサービスが導入されました。これは、顧客目線での商品開発を具体的に示す一例であり、顧客ニーズを的確に捉え、高品質化を図るための努力が継続されていることが分かります。 顧客にとって分かりやすく、かつ高品質な商品・サービスを提供することで、顧客満足度を高め、顧客との長期的な信頼関係を構築していくという戦略が見て取れます。保険法改正への迅速かつ適切な対応も、顧客保護への強い姿勢を示しています。
2. テレフォンサービスセンターの顧客対応と評価
顧客からの問合せ窓口であるテレフォンサービスセンターは、高い顧客満足度を獲得しています。 評価においては、「保険商品を検討する際の申し込み前の問い合わせ~初めて利用するために情報やサポートを得る」というテーマのもと、平均応答速度、通話時間、繋がりやすさ、初回コンタクト解決率、顧客満足度、サービス体制、コミュニケーション、対応スキル、対応処理手順、困難な対応といった様々な項目が総合的に評価されました。 その結果、「質問をよく吟味し、レベルに応じた対応を提供しようという姿勢が感じられた」という高い評価を得ています。 これは、顧客一人ひとりに合わせた丁寧な対応と、顧客のニーズを的確に把握し、適切なサポートを提供する体制が整っていることを示しています。顧客満足度向上のための継続的な努力が、この評価に繋がっていると言えるでしょう。
3. 代理店向け商品説明スキル向上コンテスト
日新火災は、代理店のお客さまに対する適切な商品説明スキルや販売スキルの向上を目的として、2007年度からコンテストを開催しています。 3回目の開催となった決勝大会では、全国9ブロックの予選を勝ち抜いたTALKクラブ会員9店が参加し、日新火災の火災保険新商品「住宅安心保険」を40分以内でいかに分かりやすく説明できるかを競いました。 審査は、「いかに分かりやすく伝わったか」というコンセプトのもと、全国の代理店代表者、日新火災役員、そして外部有識者である保険ジャーナリストの鬼塚眞子氏によって行われました。 審査項目は「テクニカルパート」と「コミュニケーションパート」で構成され、説明の正確性に加え、ユーモアや分かりやすさも評価対象となっています。 このコンテストは、顧客への分かりやすい説明を重視し、代理店のスキル向上を図ることで、顧客満足度向上に繋げるための取り組みです。審査員からの高い評価を得た優勝者のトーク内容は、代理店教材として活用される予定で、今後の販売ツール等の改善にも役立てられるとのことです。
III.内部統制とリスク管理 Internal Control and Risk Management
日新火災は、内部統制の強化に力を入れており、全社的な業務チェック、法令遵守、リスク管理の徹底、そして資産保全を重要な経営課題としています。システムリスクについては、IT開発リスク、IT運用リスク、IT基盤リスクを特定し、適切なリスク管理を実施。地震などの災害対策としてバックアップセンターも設置しています。また、コンプライアンス体制を強化し、相談窓口を複数用意することで、問題発生時の迅速な対応を可能にしています。
1. 内部監査体制の強化と定義
日新火災海上保険株式会社は、内部監査を「経営目標の効果的な達成を図るために、すべての業務を対象とした内部管理態勢(法令等遵守態勢・リスク管理態勢を含む)等の適切性、有効性を検証するプロセス」と定義しています。これは、単なる問題点の発見・指摘にとどまらず、内部管理態勢全体の評価を行い、改善方法の提言まで行うことを意味します。監査対象は、営業部門、損害サービス部門、本社部門(法令等に抵触しない範囲で子会社、関連会社、代理店および外部委託先を含む)など、全社を網羅しています。 定期的な取締役会への報告を通じて、内部管理体制の透明性を確保し、経営目標の達成に貢献しています。この厳格な内部監査体制は、企業の健全な運営と、顧客への信頼性の確保に繋がる重要な要素となっています。内部統制の基本方針に則った業務運営の徹底が、企業全体の信頼性を高める上で不可欠であるという強い意識が感じられます。
2. コンプライアンス体制の構築と情報公開
コンプライアンスの徹底のため、コンプライアンス推進スタッフを各事業本部・事業部に配置し、各部門のコンプライアンス遵守を徹底しています。コンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかにコンプライアンス業務部などに報告・相談することを義務付けています。 通常の報告・相談が困難な場合のために、「コンプライアンス相談窓口(コンプライアンス業務部長直通の専用電話)」、「コンプラ110番(社内イントラネットによるコンプライアンス業務部長へのEメール)」、そして社外ホットライン(東京海上グループや弁護士事務所)といった匿名での報告・相談も可能な複数チャネルを用意しています。 さらに、個人情報保護に配慮した上での苦情の公表や不祥事の公表など、マイナス情報も含めた情報公開にも取り組むことで、企業運営の透明性を高め、顧客からの信頼獲得を目指しています。これらの取り組みは、企業倫理の高さ、そして顧客保護への強いコミットメントを示しています。
3. システムリスク管理と災害対策
システムリスクについては、「IT開発リスク」「IT運用リスク」「IT基盤リスク」などに分類し、リスク特性に応じた適切なリスク管理を実施しています。具体的には、IT投資・開発に係る検討体制の強化、テスト・モニタリングの強化、社外とのネットワーク接続面も含めたセキュリティ対策の強化などが挙げられます。 地震などの有事・災害対策としてバックアップセンターを設置し、メインセンターが被災した場合の迅速なシステム復旧体制を構築しています。これは、システム障害による業務中断リスクを最小限に抑え、顧客へのサービス提供を継続するための重要な対策です。 システムリスクと災害リスクに対する綿密な対策は、事業継続計画(BCP)の一環として、企業の安定的な運営と顧客への信頼性を維持するために不可欠な要素となっています。これらの対策によって、顧客へのサービス提供を安定的に継続できる体制を構築しています。
IV.財務状況と運用 Financial Status and Asset Management
ソルベンシー・マージン比率は747.7%と非常に高く、保険金支払能力の充実を図っています。保険料収入の運用は、ALM(資産・負債総合管理)に基づき、保険負債とのバランスを考慮し、高格付債券を中心とした安定的な運用を行っています。貸付金に関しても、破綻先債権、延滞債権、要管理債権などの状況を把握し、適切な管理体制を敷いています。
1. ソルベンシー マージン比率と財務の健全性
公開されているデータによると、当社のソルベンシー・マージン比率は747.7%です。これは、巨大災害の発生や保有資産の大幅な価格下落など、通常の予測を超えて発生しうる危険に対する、資本金・準備金等の支払余力の割合を示す指標であり、行政当局が保険会社の経営健全性を判断する際に用いられる重要な指標の一つです。 数値が200%以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされていますが、当社の比率はその基準を大幅に上回っており、高い財務の健全性を示しています。これは、保険金支払能力の充実という観点からも、顧客への信頼性を高める上で大きなプラス要素となります。安定した経営基盤を維持することで、顧客への長期的な安心を提供できていると言えるでしょう。 この高い比率は、リスク管理の徹底と安定的な経営努力の結果であると考えられます。
2. 保険料収入の運用とALM
保険料として収受した金銭やその他の資金は、適切な運用が行われています。運用資産は、積立保険や長期火災保険等の複数年にわたる保険契約に対応する負債対応資産と、それ以外の資産に大別されます。 負債対応資産については、将来の保険金や満期返済金を確実にお支払いするために、保険負債とのバランスを考慮したALM(資産・負債総合管理)を実施しています。 ALMにおいては、保険負債が抱える金利リスクを適切にコントロールしつつ、高格付債券を中心とした運用を行い、安定的な剰余価値(運用資産価値-保険負債価値)の拡大を目指しています。 これは、顧客への保険金支払いの確実性を確保し、同時に安定的な収益の確保を図るための重要な経営戦略です。長期的な視点に立った、安全で効率的な資産運用によって、企業の安定的な成長と顧客への信頼性を高めることを目指していることが分かります。
3. 貸付金に関する状況とリスク管理
貸付金については、破綻先債権額、延滞債権額、3ヶ月以上延滞債権額、および貸付条件緩和債権額の合計額が3,586百万円であると報告されています。 内訳としては、破綻先債権が752百万円、危険債権、要管理債権なども存在します。危険債権は債務者の経営状態が悪化し、元本回収や利息受け取りが困難な可能性が高い債権であり、要管理債権は3ヶ月以上延滞している貸付金や貸付条件を緩和した貸付金です。 これらの債権の状況を詳細に把握し、適切なリスク管理を行うことで、貸付金に関するリスクを最小限に抑え、財務の安定性を維持する努力がなされていることが分かります。約款貸付については、時価開示の対象外とされていますが、これは将来のキャッシュフローを見積もることが困難なためです。これらの情報は、企業の財務状況を理解する上で重要な要素であり、透明性の高い情報開示がなされています。
V.人事 採用 社員育成 Human Resources Recruitment and Employee Development
日新火災は、「お客さま本位の最も身近で信頼されるリテール損害保険会社」の実現を目指し、地域に密着した営業活動を実践できる人材を求めています。コミュニケーション能力と責任感を持つ人材を採用し、8つの基本行動(チームワーク、挨拶、身だしなみ、コミュニケーション、行動、約束、感謝、仕事で学ぶ)を柱とした社員育成プログラムを実施し、真の意味でのお客さま本位の精神を浸透させています。
1. 採用方針 独自のビジネスモデルを担う人材を求めて
日新火災海上保険株式会社は、「お客さまに最も身近で信頼されるリテール損害保険会社」の実現を目指しており、そのためには、独自のビジネスモデルを実践できる人材が不可欠です。 積極的な採用活動を通して、日本国内における地域密着型の営業活動を行い、人と人との和を大切にする独自のビジネスモデルを理解し、実践できる人材を求めています。 具体的な人物像としては、「円滑な人間関係を築くことのできるコミュニケーション能力を持つ」「決定したことに対し、責任を持って最後まで執着して完遂させる粘り強さを持つ」点が重視されています。これらの能力は、顧客との良好な関係構築、そして業務遂行における高い責任感と粘り強さを求める、同社の企業文化を反映していると言えるでしょう。 顧客本位を重視する企業理念と、それを支える人材像が明確に示されており、採用活動においても、企業理念に共感し、それを体現できる人材の獲得に力を入れていることが分かります。
2. 社員育成体制 顧客本位を体現できる人材育成
日新火災の経営理念である「お客さま本位の最も身近で信頼されるリテール損害保険会社を目指す」ことを実現するための到達点を「お客さま本位における業界トップランナー」と明確に定めています。その実現のためには、あるべき社員像として「『ありがとう』と言っていただける人」を掲げ、その社員像の具現化を目的として8つの基本行動(チームワーク・挨拶・身だしなみ・コミュニケーション・行動・約束・感謝・仕事で学ぶ)を定めています。 これらの基本行動を柱に、体系的なプログラムに基づいた教育・研修・育成を実施することで、真の意味でのお客さま本位を自らの業務を通じて実践できる社員の育成に力を入れています。 これは、単なるスキルアップ研修ではなく、企業理念である顧客本位を社員一人ひとりが理解し、実践していくための意識改革と行動変容を目指した、より包括的な人材育成プログラムであると言えます。研修内容だけでなく、企業文化全体を通して顧客本位を浸透させるための取り組みが、この社員育成体制の根幹を成しています。
VI.個人情報保護 Personal Information Protection
個人情報保護法、関連法令、ガイドラインを遵守し、個人情報を適正に取り扱っています。特にセンシティブ情報については、お客さまの同意に基づき、業務遂行上必要な範囲でのみ利用しています。金融庁および社団法人日本損害保険協会の指針に従い、適切な安全管理措置を講じています。
1. 個人情報保護への取り組み 法令遵守と安全管理
日新火災海上保険株式会社は、個人情報保護の重要性を深く認識し、損害保険業に対する社会の信頼向上のため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)をはじめとする関連法令、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、社団法人日本損害保険協会の「損害保険会社に係る個人情報保護指針」、そして東京海上グループプライバシーポリシーを遵守して、個人情報を適正に取り扱っています。 安全管理についても、金融庁および社団法人日本損害保険協会の実務指針に従って、適切な措置を講じており、個人情報の漏洩や不正利用などのリスクを最小限に抑えるための体制を構築しています。これは、顧客からの信頼を維持し、社会的な責任を果たす上で極めて重要な取り組みです。 法令遵守はもちろんのこと、業界のベストプラクティスも取り入れ、常に高いレベルの個人情報保護体制を維持していくという強い姿勢を示しています。
2. センシティブ情報の取扱い 同意に基づく利用制限
顧客の健康状態や病歴などのセンシティブ情報については、その利用目的を厳格に制限しています。「保険業法施行規則第53条の10」及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第6条」に基づき、顧客の同意を得た上で、業務遂行上必要な範囲でのみ利用するという明確なルールを設けています。 これは、センシティブな個人情報の取り扱いにおいて、顧客のプライバシーを最大限に尊重し、不正利用や漏洩のリスクを回避するための重要な措置です。 顧客の同意なく、あるいは業務遂行上必要のない範囲でセンシティブな個人情報を利用することは一切ありません。 この厳格な情報管理体制は、顧客との信頼関係を構築し、維持していく上で不可欠な要素であり、顧客への配慮と責任感の高さを示すものです。法律やガイドラインを遵守するだけでなく、顧客のプライバシー保護を最優先に考えていることが分かります。
