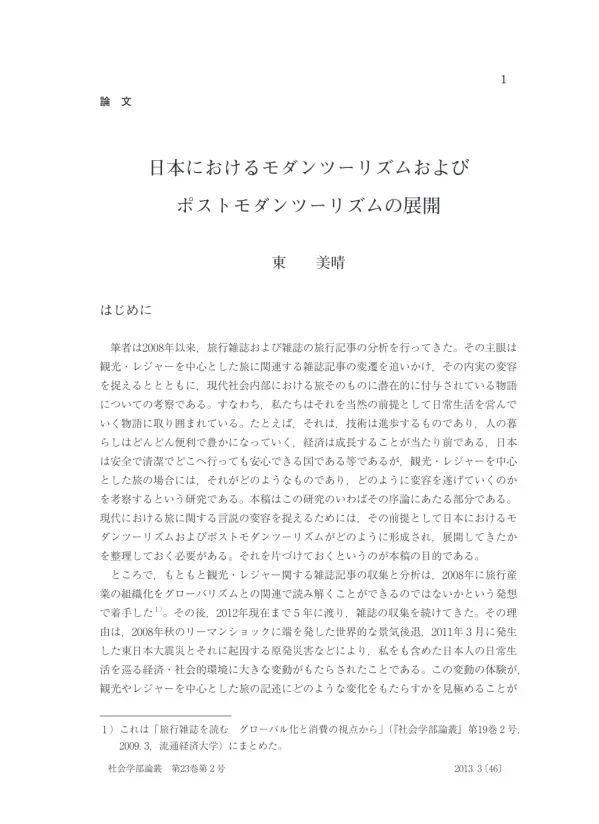
日本ツーリズム変遷:近代からポストモダンへ
文書情報
| 専攻 | 観光学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.08 MB |
概要
I.近代 ツーリズム の形成と展開 明治期から昭和初期
本稿は、日本の観光・レジャーを中心とした旅に関する言説の変容を分析する研究の序論です。明治期、欧米のツーリズムモデルが導入され、修学旅行(1886年開始)がツーリズムの萌芽となりました。避暑地(軽井沢、大磯、伊香保など)の開発、鉄道による団体旅行(高野山、伊勢神宮参拝など、南新助の日本旅行会が中心)が盛んになります。大正期には、観光関連団体(日本旅行文化協会など)が設立され、観光が徐々に国民的な活動になっていきます。この時代は、西洋的なリゾートやレジャーの概念が日本に定着し始めた重要な時期であり、近代ツーリズムの基盤が築かれました。
1. 近代ツーリズムの導入と初期の展開 明治期
明治時代、欧米諸国からの近代ツーリズムの概念が日本に導入され始めました。テキストでは、1886年(明治19年)に始まった修学旅行が、その初期の重要な事例として挙げられています。これは、単なる遠足ではなく、当時の高等教育機関(帝国大学、師範学校、女学校など)において、欧米のグランドツアーや青少年運動におけるキャンプといったレクリエーションや教育的側面を取り入れたものでした。 東京師範学校における修学旅行は、学術演習が組み込まれていた点で18世紀までのグランドツアーを彷彿とさせますが、一方で長途遠足という点では19世紀後半のイギリスにおけるキャンプ運動を想起させます。この修学旅行は、教育的側面とレクリエーション的側面を兼ね備え、近代ツーリズムの日本における最初の形態と言えるでしょう。また、この時代には、軽井沢、大磯、伊香保などの高原・海辺・温泉地が別荘地として開発され、避暑や保養のためのリゾート地としての性格も併せ持つようになりました。しかし、海水浴や温泉での湯治は明治以前から存在していた慣習であり、近代的なリゾートと伝統的な慣習が交錯する状況が生まれたことがわかります。 これらの事例から、明治期の日本においては、欧米の近代的なツーリズムモデルが導入されつつも、日本の伝統的な旅の文化と融合しながら独自のツーリズムが形成され始めたことが示唆されます。
2. ツーリズムの拡大と組織化 大正から昭和初期
大正時代に入ると、ツーリズムはさらに拡大し、組織化が進みます。1905年(明治38年)、草津駅の立売り業者であった南新助が高野山参詣団と伊勢神宮参拝団を組織、斡旋したことが、鉄道を用いた最初の団体旅行とされています。この事例は、当時の日本人にとって宗教的な巡礼が重要な旅行目的であったことを示しています。その後、南新助は日本旅行会を設立し、善光寺参詣団や西本願寺への団体旅行などを手掛け、団体旅行の斡旋を事業として確立しました。 1916年(大正5年)には、鉄道会社が主体となって、伊勢神宮や京都・奈良・大阪を巡る団体旅行が企画されるなど、鉄道による団体旅行が普及し始めました。1924年(大正13年)には、日本旅行文化協会が発足し、雑誌『旅』の発行、講演会開催、名勝地の調査などを行うなど、ツーリズムを促進する組織的な活動が始まりました。この協会には、鉄道省、ジャパン・ツーリスト・ビューロー、日本郵船といった交通事業会社や民間旅行団体が参加しており、官民連携によるツーリズムの推進体制が構築されつつあったことがわかります。 このように、大正から昭和初期にかけては、団体旅行の普及、ツーリズム関連団体の設立などを通して、ツーリズムが組織化され、国民的な活動へと発展していく過程が見て取れます。この時代は、近代ツーリズムの基盤が固まり、発展の礎となる重要な時代でした。
3. 国家による観光政策の推進 昭和中期
昭和30年代後半から、日本の観光は国家政策として本格的に推進されるようになります。1956年(昭和31年)、政府は観光事業振興計画5か年計画を策定しました。この計画では、外国人観光客30万人、消費額1億2000万ドルという目標が設定され、交通や施設の整備、宣伝活動の強化などが計画されました。国民旅行の促進も重要な政策目標とされ、国民宿舎の建設も開始されました。1957年(昭和32年)には総理府に観光連絡調査室が設置され、国民の観光旅行に関する世論調査が行われるなど、国民の旅行を促進する政策が積極的に展開されました。 この時代の観光政策は、単なる外貨獲得だけでなく、国民生活の向上や生活様式の近代化という観点からも重要視されていました。「国民旅行」、「国民宿舎」、「ソーシャルツーリズム」といった言葉からも、国民全体の幸福度向上に観光が貢献するという認識がうかがえます。 さらに、この頃には、特定地域の自然景観を国立公園に指定したり、社寺や仏像を国宝や重要文化財に指定したりするなど、観光資源の概念が確立され、観光産業の制度的な基盤が整備されていきます。温泉協会や観光地連合会の発足も、観光事業者の育成という観点から重要な出来事でした。この時代を通じて、日本のツーリズムは国家政策の下、近代的な産業として構造化、組織化されていったと言えるでしょう。
II.昭和期の ツーリズム 高度経済成長と 観光 政策
昭和31年(1956年)の経済白書で「もはや戦後ではない」と宣言された高度経済成長期には、政府主導の観光振興5か年計画が策定され、観光は国家プロジェクトとなりました。外国人観光客誘致と国民旅行の促進が目指され、国民宿舎の建設も開始されます。1970年代には、余暇開発センターが設立され、「余暇」という概念が定着し、レジャー産業が発展。オイルショック後も、観光・レジャー施設(ホテル、テーマパークなど)の整備が加速し、ツーリズムは国民生活に深く根付きました。この時代は、近代ツーリズムが成熟した時期と言えるでしょう。
1. 高度経済成長期における観光政策の展開 昭和30年代後半 40年代
昭和30年代後半から高度経済成長期においては、1956年の経済白書における「もはや戦後ではない」という宣言を背景に、観光振興が国家政策として本格的に推進されました。政府は観光事業振興計画5か年計画を策定し、1961年度の目標として外国人観光客30万人、消費額1億2000万ドル、国民旅行4.8億人回、消費額2800億円を掲げました。この計画では、交通・施設整備、宣伝活動強化、環境衛生・接遇改善などが重点事項とされました。国民宿舎の建設も開始され、国民旅行の促進が政策の中核をなしていました。 この時代の観光政策は、外貨獲得に加え、国民生活の向上や生活様式の近代化という観点からも推進されました。「国民旅行」「国民宿舎」「ソーシャルツーリズム」といった言葉からも、国民全体の生活水準向上に観光が貢献するという政府の強い意志が読み取れます。総理府に観光連絡調査室が設置され、国民の観光旅行に関する世論調査が行われたことも、国民参加型の観光政策を進める政府の姿勢を示しています。この期間は、観光が国家プロジェクトとして位置づけられ、本格的な産業として発展を遂げるための基盤整備が精力的に進められた時代と言えるでしょう。
2. 観光レジャー消費の拡大と社会構造の変化 昭和40年代後半 50年代
高度経済成長が進むにつれて、国民の観光レジャー消費は急速に拡大しました。1970年代には、通産省の発表した「わが国の余暇の現状と余暇時代への願望」という報告書をきっかけに、余暇開発センターが設立され、余暇産業の開発が国家レベルで推進されました。1972年には余暇開発センターが設立され、1974年には南太平洋余暇資源調査船を就航させ、1977年にはレジャー白書を発表するなど、余暇と観光を結びつける政策が展開されました。この頃には、「余暇」という概念が社会に定着し始め、観光は余暇活動の代表的なものとして認識されるようになりました。 この時代の観光レジャー消費の拡大には、社会構造の変化が大きく影響していました。宮本(1975)の指摘によれば、戦後増加した学生人口の国民宿舎やユースホステル利用、核家族化によるマイカー普及と家族旅行増加、そして温泉が湯治からレジャーの場へと変化したことなどが、観光レジャー消費拡大の要因として挙げられます。また、この時期は日本人の海外旅行の自由化が行われた時期でもあり、国内観光のみならず、海外への旅行も増加しました。 1970年代は、アトラクション、情報、宿泊、交通といった観光レクリエーション環境の整備が国家レベルで行われ、観光レジャー消費が急激に拡大した時代であり、日本における近代ツーリズムがある意味で完成した時期と言えるでしょう。 日本交通公社の旅行雑誌『るるぶ』の創刊も、この時代の観光レジャー消費拡大を象徴する出来事の一つです。
III.ポストモダン ツーリズム の到来 バブル期以降
バブル期以降、日本のツーリズムはポストモダンへと移行します。1983年の東京ディズニーランド開園は象徴的な出来事であり、テーマパーク型の観光開発が盛んになります。一方、「町並み保存」運動(妻籠など)は、アンチモダンな動きとして注目されます。また、セックスツーリズムの問題も浮上し、社会問題となります。近年は、エコツーリズムやグリーンツーリズムなど、多様なツーリズム形態への関心が高まっています。これは、脱工業化による地域経済の活性化という課題に対応する試みでもあります。そして、若者層における消費行動の変化も、ポストモダンツーリズムの新たな様相を示しています。
1. ポストモダンツーリズムの到来 バブル経済崩壊後
バブル経済崩壊後、日本のツーリズムはポストモダンへと移行していきます。この変化は、1983年の東京ディズニーランド開園を境に加速したと捉えられます。同時期に任天堂ファミリーコンピュータが発売されたことも、消費主義的なポストモダン大衆文化の醸成に大きく貢献しました。 ディズニーランドやコンピュータゲームは、脱工業化社会における新しい風景、新しい産業として、人々の日常生活に浸透し、子供たちはポストモダン消費主義文化の中で育ちました。 このポストモダンな消費文化の中で育った若者世代は、ポストモダンツーリストとして新たな観光のあり方を形成していきました。彼らは、テーマパーク型観光開発や都市の「ディズニー化」「スペクタクル化」といった現象を象徴する存在と言えるでしょう。具体的には、神戸市六甲アイランドの「スーパーフーパー」、横浜の「ワイルドブルーヨコハマ」、千葉県船橋市の「ららぽーとスキードームSSAWA」といった大規模レジャー施設の建設がその一端を担っています。これらの施設は、当時としては世界最大級規模を誇り、都市部における非日常的な空間を提供する役割を果たしました。
2. 博物館 レジャー施設の増加と都市のスペクタクル化
1986年から2000年にかけて、博物館・記念館・水族館などの施設が大量に建設されました。特に1994年以降は増加が顕著で、「昭和・平成家庭史年表」には「全国で博物館の建設ブーム」と記されています。 これらの施設の中には、「アンティーク・トイ・ワールド・ミュージアム」「魚のいない水族館」「おもちゃの王国」など、従来の博物館とは異なるタイプの施設も多く含まれており、これは都市における「ディズニー化」「スペクタクル化」の一つの表れとして捉えられます。 同様の傾向は、レジャー施設にも見られます。1990年代前半には、神戸市六甲アイランドのウォータースライダー、横浜の屋内ウォーターパーク、船橋市の人工降雪スキー場などが建設され、1997年には広島市にスノーボード専用の屋内人工降雪ゲレンデも開業しています。これらの施設は、都市部において非日常的なレジャー体験を提供する役割を果たし、都市のスペクタクル化をさらに推し進めました。 これらの傾向は、単に都市部だけに限らず、日本社会全体に広がる「ディズニー化」「スペクタクル化」の進行を示唆していると言えるでしょう。
3. ポストモダンのアンチモダン プレモダン回帰 21世紀への兆候
しかし、ポストモダンツーリストである都市の若者たちは、雇用の不安定化といった現実にも直面しています。そのため、シェアハウス居住や選択的消費といった、消費主義から距離を置く傾向も見られるようになってきました。2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災は、この傾向をさらに強める要因となりました。 このような状況下では、若者たちの観光行動にも変化が見られます。単に都市部のレジャー施設で時間を消費するだけでなく、アンチモダンやプレモダンへの回帰といった新たな傾向が表れ始めています。 21世紀に入ってからは、エコツーリズムやグリーンツーリズムへの関心が高まり、脱工業化による地域経済の空洞化や過疎化問題への対応策として、ツーリズム産業が注目されるようになりました。この流れの中で、ポストモダンツーリストを引き付けるため、エコツーリズム、グリーンツーリズムに加え、フラワーツーリズム、コンテンツツーリズム、フードツーリズムといった多様なツーリズム形態が模索されています。 町並み保存(妻籠など)も、このアンチモダン、プレモダン回帰の動きの一環として捉えることができます。1968年から始まった妻籠の町並み保存運動は、1974年には全国町並み保存連盟の発足に繋がり、全国的な広がりを見せました。
