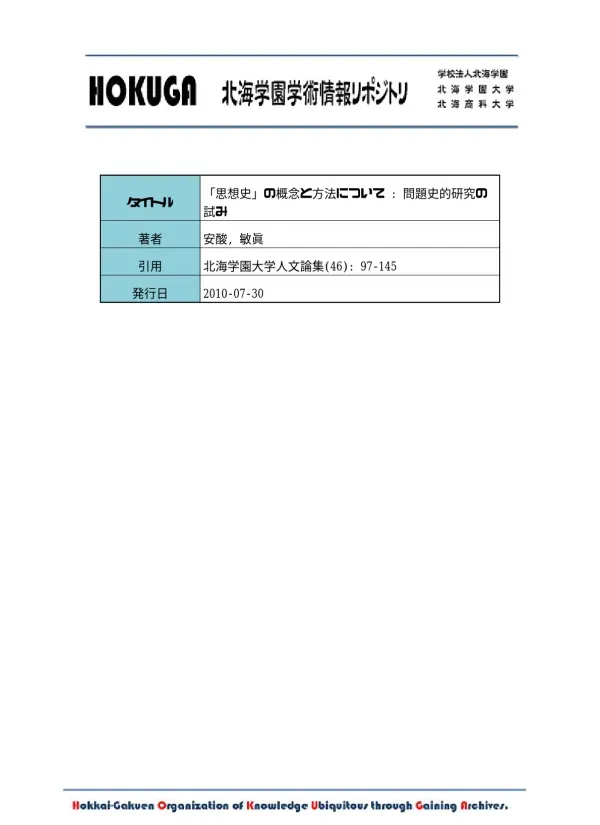
日本思想史概念と方法:問題史的研究
文書情報
| 著者 | 安酸 敏眞 |
| 学校 | 北海学園大学 |
| 専攻 | 思想史 |
| 場所 | 札幌市(北海学園大学の位置から推測) |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 915.88 KB |
概要
I.日本思想史の確立と主要人物
本文は、日本における「思想史 (Nihon Shisōshi)」の成立と発展を論じています。特に、東北帝国大学(現・東北大学)における日本思想史研究室の創設者である村岡典嗣の功績が強調されています。村岡は、国学、神道、儒教、キリシタン、洋学など多岐にわたる研究を行い、日本思想史学の開拓者として、多くの門下生を育成しました。彼の日本思想史講座は、日本の思想史研究の礎を築いたと言えるでしょう。さらに、津田左右吉、和辻哲郎といった著名な学者も、日本の思想史研究に大きな貢献をしました。
1. 日本思想史の学問分野としての確立
現代において「思想史」という用語は、もはや説明を必要としないほど一般的になっています。日本思想史学会の会則にも、日本思想史の研究を目的とする旨が明記されており、学会誌『日本思想史学』や『季刊日本思想史』、さらには『日本思想史辞典』といった出版物も存在するほど、日本思想史は確固たる学問分野として定着しています。この状況は、津田左右吉、村岡典嗣、和辻哲郎といった先駆者たちの尽力によるものであり、特に東北帝国大学(現・東北大学)に日本思想史講座を創設した村岡典嗣の功績は非常に大きいです。この講座は、1923年法文学部開設と同時に発足し、当初は文化史学第一講座でしたが、1963年に日本思想史学講座と改称されました。1997年には文学部の改組により、国文学講座と合併して日本文化学講座となりましたが、その歴史は日本の思想史研究における重要なマイルストーンとなっています。 日本思想史学会の活動や関連出版物の存在は、日本思想史研究が組織的かつ体系的に進められていることを示しており、この分野の成熟度を示す重要な指標となっています。
2. 村岡典嗣と東北大学日本思想史研究室
東北大学日本思想史研究室は、1923年の法文学部開設と同時に発足し、初代講座担当者である村岡典嗣が1924年から1946年まで在職しました。村岡典嗣は、日本思想史学の開拓者として知られ、国学、神道、儒教、キリシタン、洋学など幅広い分野を研究し、多くの弟子を育成しました。彼の研究と教育活動によって、東北大学日本思想史研究室は日本の日本思想史学研究の中核拠点となりました。研究室の公式ホームページによれば、講座名は当初「文化史学第一講座」でしたが、1963年に「日本思想史学講座」と改称され、その後1997年に文学部の改組に伴い国文学講座と合併して「日本文化学講座」となりました。この歴史的変遷は、日本思想史研究の進展と、その学問的枠組みの変化を反映しています。村岡の業績は、単なる学問的成果にとどまらず、日本の思想史研究の方法論にも大きな影響を与えたと評価されています。彼の研究室は、日本の思想史研究を大きく前進させる原動力となったのです。
3. 日本思想史研究におけるその他の主要人物
村岡典嗣に加え、津田左右吉(1873-1961)と和辻哲郎(1889-1960)も日本の思想史研究に多大な貢献をした傑出した学者として挙げられています。彼ら3人の業績は、日本思想史という学問分野の確立に大きく貢献しました。しかし、1960年代以降の日本の思想史に関する議論では、戦前の日本思想史、そして津田、村岡、和辻らの業績が、あまり考慮されていない点が指摘されています。これは、戦前の日本思想史研究が、必ずしも現代的な意味での「思想史」とは異なる側面を持っていたこと、また、学問的潮流の変化によって、過去の研究が再評価される必要性が出てきたことなどを反映していると考えられます。 これらの主要人物の研究内容や方法論を詳細に検討することで、日本思想史研究の歴史的発展をより深く理解することができ、現代の研究にも重要な示唆が得られると考えられます。
II.西洋思想史における諸概念と方法論 精神史 理念史 文化史
西洋の思想史研究に関しては、精神史(Geistesgeschichte) と理念史(Ideengeschichte) の概念が重要視されています。ヴィルヘルム・ディルタイは精神史の開拓者として知られ、彼の考え方は、ヘーゲルの絶対精神の哲学にまで遡ります。一方、理念史は、歴史的効力を持つ理念(Ideen) を研究する分野であり、ヴィルヘルム・フォン・フンボルトやE・R・クルツィウスらの研究が知られています。さらに、文化史(Kulturgeschichte)との関連も深く、特に近年の文化史研究における「新しい文化史(cultural history)」と「古典的文化史(Kulturgeschichte)」の対比が論じられています。ピーター・バークの著作が、この新たな文化史の潮流を理解する上で重要です。また、ミクロストリア(microhistory) の手法も紹介されています。
1. 精神史 Geistesgeschichte の概念とディルタイ
西洋思想史研究においては、精神史(Geistesgeschichte)という概念が重要な位置を占めます。特に、ヴィルヘルム・ディルタイ(Wilhelm Dilthey, 1833-1911)は、精神史研究の重要な先駆者として知られています。ディルタイは、ヘーゲルの「客観的精神」という概念を継承しつつも、その内実を大きく変容させました。ディルタイにおける客観的精神とは、個人の間に成立する共同性(言語や習俗など)が感覚的世界に客観化された多様な形式であり、道徳、法律、国家、宗教、文学、芸術、学問などは全てそれを反映すると考えました。ヘーゲルが絶対精神と区別していた芸術、宗教、哲学なども、ディルタイは客観的精神の枠組みの中に含めています。このように、ディルタイの精神史は、歴史的事実の背後にある精神的な力を重視し、芸術、学問、宗教などの文化現象を精神の歴史として考察するものです。彼の哲学は、ヘーゲルの絶対精神の哲学にまで遡る深い歴史的文脈を持っています。
2. 理念史 Ideengeschichte とその特徴
精神史と並んで、理念史(Ideengeschichte)も西洋思想史研究において重要な概念です。理念史とは、歴史的な効力を持つ「理念」(Ideen)を研究・記述する精神科学の一分野であり、哲学体系や文学作品のような個人的・精神的な創造物、あるいは公共生活上の精神的運動に着目します。ヴィルヘルム・フォン・フンボルトの歴史的理念説やランケの世界史理論などが、その背景にあります。学問的基礎づけにおいては、ディルタイの影響が大きいため、精神史とほぼ同義に捉えられる場合もありますが、歴史における「理念」の働きにより大きな重みを置いています。E・R・クルツィウスの『ヨーロッパ文学とラテン中世』などが、理念史研究の代表的な成果として挙げられます。理念史は、普遍史の不可欠な一部として、思索する人間が歴史的に体験した事柄から何を作り上げ、どのように精神的に克服し、どのような理念的帰結を引き出したかを考察します。重要な思想家のイデオロギーは、数多くの経験から抽出された精髄であり、人間は理念によって体験の重圧から解放され、新たな力を創造すると考えられています。
3. 文化史 Kulturgeschichte と新しい文化史 cultural history
文化史(Kulturgeschichte)は、思想史研究と密接に関連する概念です。しかし、古典的な文化史と、近年の新しい文化史(cultural history)の間には、扱う対象と研究手法に大きな違いがあります。古典的な文化史は、ブルクハルトやホイジンガといった学者によって代表され、「高級文化」(Hochkultur)を中心とした研究が特徴でした。一方、新しい文化史は、ピーター・バークの『文化史とは何か』に代表されるように、「低級文化」や民衆文化を含む、より広範な文化を対象としています。20世紀後半以降、文化という用語は日常生活の慣習、価値、生活様式などを指すようになり、文化人類学的な定義が支配的となりました。この変化は、歴史学と人類学の融合、そして「ミクロストリア」(microhistory)という新しい歴史ジャンルの台頭によって促進されました。ミクロストリアは、経済史や社会史の一般的な傾向描写に対する反発として、地域文化の多様性や特異性を重視するアプローチです。また、「大きな物語」(grand narrative)に対する批判も、新しい文化史の重要な背景となっています。
III.アメリカにおける思想史研究と亡命歴史家
アメリカにおける思想史研究の発展においては、アーサー・C・マッギファートによるキリスト教思想史(History of Christian Thought) の確立が挙げられます。さらに、ドイツからの亡命歴史家たちが、アメリカ合衆国における思想史研究に貢献したことも重要です。彼らは、フリードリッヒ・マイネッケの弟子であり、理念史の方法をアメリカに持ち込みました。ドイツ歴史学研究所の活動も、この文脈で重要な役割を果たしています。
1. アーサー C マッギファートとアメリカにおけるキリスト教思想史
アメリカにおける思想史研究においては、アーサー・C・マッギファート(Arthur Cushman McGiffert, 1861-1933)の貢献が非常に大きいです。彼はアメリカでキリスト教思想史という学問分野を確立する上で、最も重要な人物の一人と言われています。 彼の著作は、原始キリスト教からプロテスタントまで、キリスト教思想史全体を網羅しようとするものでした。日本語では「教義史」「教理史」「神学史」といった言葉が用いられることがありますが、マッギファートの著作はこれらのいずれにも完全に当てはまらず、そのため「思想史」という用語が最も適切であるとされています。 彼はUnion Theological Seminaryで「History of Christian Thought」という講座を開設し、その講座は後の研究にも大きな影響を与えました。 マッギファートのもとで学んだ有賀鉄太郎は、日本人として初めて神学博士号を取得し、同志社大学神学部長、京都大学基督教学講座教授を務めました。マッギファートの業績は、アメリカにおけるキリスト教思想史研究の基盤を築いたと言えるでしょう。
2. ヒストリー オブ アイディアズ 運動の影響
アメリカにおける思想史研究の発展には、「ヒストリー・オブ・アイディアズ」(History of Ideas) 運動の影響も無視できません。この運動の中心人物の一人であるアーサー・ラブジョイは、ヒストリー・オブ・アイディアズ・クラブを設立し、西欧の文献に表れた哲学的概念、倫理思想、美学上のファッションなどの歴史的発展と影響を研究しました。彼は、1940年には『Journal of the History of Ideas』という学術誌を創刊し、その最初の編集者となりました。 「ヒストリー・オブ・アイディアズ」は、intellectual historyの一つのアプローチであり、unit-ideasに着目して人間の諸観念の表現、意味、変遷、本質などを歴史的に探究するものです。哲学史、科学史、文学史などを深く関わる学際的研究であり、既成の学問領域を超えた斬新な研究アプローチとして評価されています。 ラブジョイ以外にも、スウェーデンのヨーハン・ヌルドストレーム(Johan Nordstrom)などが、「history of ideas and learning」という学科を設立するなど、この運動は西洋における思想史研究に大きな影響を与えました。
3. ドイツからの亡命歴史家とアメリカにおける思想史研究の発展
第二次世界大戦後、アメリカ合衆国における思想史研究の発展には、ドイツからの亡命歴史家たちの貢献も大きかったと本文では述べられています。 特に、フリードリッヒ・マイネッケの弟子たちは、ワシントンD.C.のドイツ歴史学研究所(German Historical Institute)の活動の中心を担い、マイネッケ直伝の理念史の方法をアメリカに持ち込みました。 このことは、戦後のアメリカにおける思想史研究の確立と発展に大きく寄与したと考えられます。 ドイツにおける文化史研究、特にJ・メーザーやJ・G・ヘルダー、そしてJ・ブルクハルトの影響なども、この文脈で言及されていますが、詳細な説明は省かれています。しかし、これらのドイツの学者の思想が、亡命歴史家を通じてアメリカに伝播し、アメリカにおける思想史研究に影響を与えたという点は重要な論点です。
IV.思想史研究の方法論 文献学と歴史的文化科学
思想史研究の方法論として、文献学(Philology)の重要性が強調されています。フリードリヒ・アウグスト・ヴォルフとアウグスト・ベークの文献学は、日本思想史研究にも大きな影響を与えました。村岡典嗣は、ベークの文献学を日本思想史研究に適用し、文献資料の精緻な分析に基づいた研究を推進しました。また、歴史的文化科学(historical cultural science) の概念も登場し、マックス・ウェーバーの思想や、ゲオルグ・ジンメルの仕事が、この方法論的枠組みにおいて議論されています。理解社会学(verstehende Soziologie)のアプローチも、思想史研究に有効な方向性を示唆しています。 歴史的文化科学は、文化の意義や歴史的連関を理解しようとする学問分野です。
1. 文献学 Philology の重要性とアウグスト ベーク
思想史研究においては、文献学(Philology)が不可欠な方法論的基盤となります。近代的な意味での文献学の確立には、フリードリヒ・アウグスト・ヴォルフ(Friedrich August Wolf, 1759-1824)の貢献が大きく、彼の弟子であるアウグスト・ベーク(August Boeckh, 1785-1867)はその体系化に成功しました。ベークの『文献学的諸学問のエンチクロペディーならびに方法論』(Encyklopadie und Methodologie der philologischen Wissenschaften)は、今日まで古典文献学の標準的な教科書として用いられています。文献学は、既存の認識や知識を前提として、それらを再認識することを目的とする学問です。歴史学と重なる部分も多いですが、文献学は出来事の記述ではなく、歴史記述の中に含まれる歴史認識を再認識することに重点を置きます。ベークは、一つの民族の認識が言語や文学だけでなく、その倫理的・精神的な全活動に表現されるとし、文献学は各民族の精神的発展全体、文化の歴史をあらゆる方向から記述する必要があると主張しました。 哲学が原初的に認識するのに対し、文献学は「再び知る」という再認識のプロセスを重視する点が特徴です。
2. 村岡典嗣と 史的文化学
村岡典嗣は、思想史を文献学的段階と史学的段階を含む「史的文化学」として構想しました。彼は、西洋のフィロロギーと同種の学問と見なせる本居宣長の国学が、思想の内面的発展を歴史的に考察する段階にまで至らなかった点を指摘し、文献資料と歴史的現実の相関関係を踏まえた研究方法を重視しました。 村岡は、歴史を政治史と文化史に大別し、文化史を「事象として文化を観る立場」、思想史を「意識として文化を観る立場」と定義しました。思想史は、文化史の意識的な側面であり、学問史や哲学史の前史でもあると位置づけています。 村岡のこの見解は、政治史と文化史の二項対立、そして「文化」の概念自体が、現代の視点からは単純化されているという批判を受けますが、文献学の伝統と歴史性を重視する彼の考え方は、思想史研究の方法論を考える上で重要な示唆を与えています。彼はベークの文献学を日本思想史研究に効果的に応用したことで知られています。
3. 歴史的文化科学 Historische Kulturwissenschaft とマックス ウェーバー
思想史研究の方法論をより深く考察するために、「歴史的文化科学」(Historische Kulturwissenschaft)という概念が取り上げられています。 この概念は、マックス・ウェーバー(Max Weber, 1864-1920)の研究に深く関係しています。ウェーバーは、価値理念への関係づけによって意義のあるものの総体を「文化」と定義し、人間生活の諸現象を文化意義の観点から考察する諸学科を「文化科学」と名付けました。彼の文化科学は価値理念に根ざしており、われわれが世界に対して意識的に態度を決め、意味を与える能力と意思を持つ「文化人」であることを前提としています。 ウェーバーは、「解明的理解」(deutend verstehen)と「因果的説明」(ursachlich erklären)を区別しつつ、それを結合しようとする歴史的文化科学を構想しました。これは、ディルタイが主張した「説明」と「理解」の相補的な関係を踏まえたものです。 O.G.エクスレ(Otto Gerhard Oexle)は、ジンメルとウェーバーの仕事に着目し、歴史的文化科学としての歴史学の可能性を探っています。ウェーバーの「理解社会学」(verstehende Soziologie)は、思想史研究において有力な方法論的枠組みとなる可能性を示唆しています。
V.思想史と文化史 そしてその範囲
本文では、思想史と文化史の関連性と相違点が詳細に論じられています。思想史は、哲学史と文化史の中間的な位置づけにあるとされ、哲学史よりも範囲が広く、しかしながら大衆文化を中心的対象とする新しい文化史とは異なる点が指摘されています。フランクリン・L・バウマーの見解が、この点に関して重要な示唆を与えています。 近年の文化史研究の拡大(例:漆の文化史、料理の文化史など)と、思想史の扱う範囲との違いについても言及されています。
1. 思想史と文化史の定義と関係性
本文では、思想史と文化史の関係性とそれぞれの範囲について論じられています。思想史は、人間の思想、つまり内的な世界に焦点を当てた研究分野です。「思想」という用語は幅広い意味を持つため、思想史は哲学史と文化史の中間的な位置づけにあるとされます。扱う範囲は哲学史よりも広いものの、大衆文化を主な対象とするわけではない点が、文化史との違いとして強調されています。 村岡典嗣は、歴史を政治史と文化史に分け、文化史を「事象として文化を観る立場」、思想史を「意識として文化を観る立場」と定義しました。思想は意識的発展の過程で、単なる思想から学問、そして哲学へと発展すると考え、思想史は文化史の意識的な側面、学問史や哲学史の前史であると位置付けています。しかし、この見解は、文化史と政治史の二項対立という図式的な捉え方や、文化概念の時代的制約といった点で批判の対象にもなっています。 20世紀後半以降、文化史研究は大きく変化し、「古典的文化史」(Kulturgeschichte)と「新しい文化史」(cultural history)では対象と手法が大きく異なっています。思想史は、新しい文化史よりも古典的文化史に近い位置づけにあります。
2. 文化史の変遷と 新しい文化史
ブルクハルトやホイジンガといった古典的文化史家は、「高級文化」(Hochkultur)を主な対象としていました。しかし、現代の文化史研究は大きく変化しており、ピーター・バークの著作『文化史とは何か』に代表されるように、「低級文化」や民衆文化も包含する広義の文化を対象とする「新しい文化史」が台頭しています。20世紀初頭までは、文化は精神性の高い芸術や科学を意味していましたが、後半からは民俗音楽、民衆的な芸術・科学、技芸、慣習行為なども含むようになりました。 バークは、1960年代から1990年代にかけての文化史研究において、人類学的方向への転回が顕著であったと指摘しています。歴史学と人類学の融合により、「歴史人類学」の時代が到来し、人類学的なアプローチが、文学、美術、科学などの歴史研究にも大きな影響を与えました。 この変化は、「ミクロストリア」(microhistory)という新しいジャンルの台頭にも繋がっています。ミクロストリアは、経済史のモデルに対する反発、人類学との遭遇、そして「大きな物語」(grand narrative)への批判という三つの要素から生まれた歴史記述の方法です。
3. 思想史の範囲と 大衆文化 との関係
思想史は、哲学や思想家といったエリート層の思想を扱うだけでなく、「書きあらわされない哲学」(the unwritten philosophy)や時代精神(Zeitgeist)、風潮、思潮、知的風土(climates of opinion)なども明らかにしようとする学問分野です。したがって、大衆文化に現れる風潮や時代精神を完全に無視することはできません。しかし、思想史の主要な課題は、「思想」や「観念」と呼ばれるものを、その潜在力と作用の実態に即して解明することです。 フランクリン・L・バウマーの見解によれば、思想史は「低級文化」(the lower culture)よりも「高級文化」(the higher culture)の思想に関心を寄せます。そのため、ピーター・バークが言う古典的文化史とは親和性がありますが、大衆文化を主な対象とする新しい文化史とは距離があると言えます。 近年、「文化史」を冠する書籍の急増は、文化史という概念の下方への拡大、いわば「学問の下流化」を反映していると言えます。これらの文化史研究の多くは、思想史研究とはほとんど接点を持たないものです。
VI.思想史研究に必要な要件
最後に、思想史研究に必要な要件として、語学力(特に古典語と近代ヨーロッパ言語)、哲学・文学・歴史学などの専門知識、そして心理学・社会学・経済学など幅広い学際的知識が挙げられています。文献学と歴史学の基本的技能も不可欠です。 文献学的批判の方法における徹底的な訓練が重要視されています。
1. 語学力と専門知識の必要性
思想史研究を行うためには、まず何よりも研究対象となる文献を読みこなせるだけの語学力が不可欠です。特に西洋思想史を研究する場合、古典語(ギリシャ語、ラテン語、ヘブライ語)と近代ヨーロッパ言語(英語、ドイツ語、フランス語など)の少なくとも2つか3つはマスターする必要があります。ファーストハンドの研究を行うには、これらの言語能力が不可欠だからです。 語学力に加えて、哲学、文学、歴史学といった専門分野の知識は当然のことながら必要です。しかし、それだけでは不十分で、心理学、社会学、経済学、法学、政治学、医学など、幅広い学際的な知識と教養が求められます。思想史研究は、単一の学問分野にとどまらず、多様な分野の知見を統合する学際的な性質を持つためです。 いずれにしても、文献学と歴史学の基本的な技能は不可欠であり、文献学的批判の方法に関する徹底的な訓練が求められます。これは、歴史学を近代的な学問にまで高めたランケの考え方を踏襲したものです。
2. 文献学と歴史学の技能
思想史研究においては、文献学と歴史学の基礎的な技能が不可欠です。 研究対象の文献を精読し、その内容を正確に理解するには、文献学的な訓練が必須となります。これは、単に文献を表面的に読むだけでなく、その成立過程、作者の意図、当時の社会状況などを考慮しながら、テキストを批判的に分析する能力を必要とすることを意味します。 また、歴史的文脈を理解し、研究対象を適切に位置づけるためには、歴史学の知識と方法論が不可欠です。 これは、歴史的事実を正確に把握するだけでなく、歴史解釈の多様性や限界を理解し、自らの歴史叙述における立場を明確にする能力を必要とすることを意味します。 文献学と歴史学の基本的な技能は、思想史研究の土台となるものであり、これらを習得することによって、より精緻で信頼性の高い研究成果を得ることが可能になります。
3. 思想史研究の主要課題と対象範囲
思想史研究は、哲学者や思想家といったエリート層の思想だけでなく、コーンフォードが言う「書きあらわされない哲学」(the unwritten philosophy)や、時代精神(Zeitgeist)、風潮、思潮、知的風土(climates of opinion)なども明らかにしようとするものです。 そのため、大衆文化の中に現れている風潮や時代精神を無視することはできません。しかし、思想史研究の第一義的な主要課題は、「思想」や「観念」と呼ばれるものを、その潜在力と作用の実態に即して解明することです。 思想史は、哲学史や文化史と密接に関連していますが、その対象範囲は、哲学史よりは広く、大衆文化を主な対象とする文化史よりは狭い位置づけにあります。 つまり、思想史はエリート層の思想から一般人の思想まで広い範囲を扱うものの、文化史のように習俗、慣習、神話などを網羅するわけではないのです。この点が、思想史と他の歴史学分野との重要な違いです。
