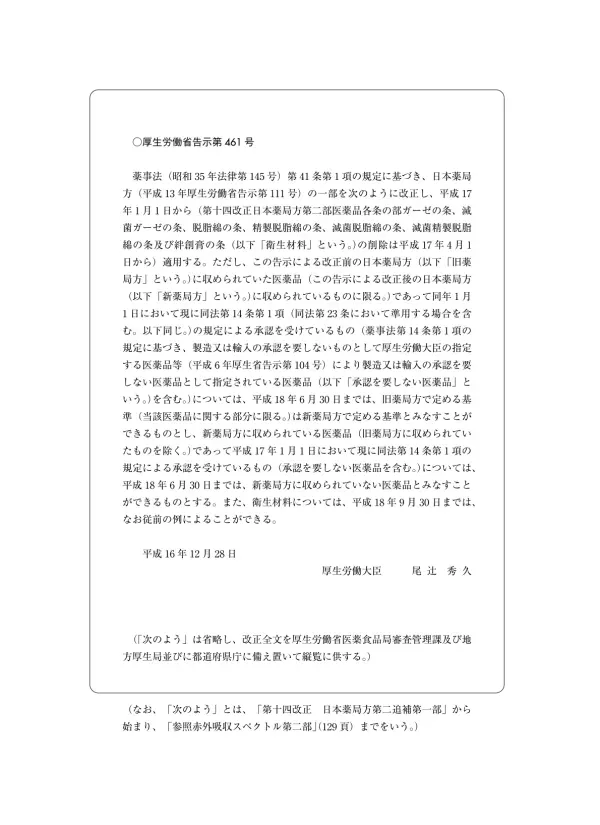
日本薬局方改正:医薬品基準とSEO対策
文書情報
| 著者 | 厚生労働省 |
| 専攻 | 薬学 |
| 文書タイプ | 告示 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.64 MB |
概要
I.日本薬局方第十四改正及びその一部改正に関する概要
この文書は、日本薬局方(JP)第十四改正とその後の部分改正について記述しています。改正の目的は、保健医療上重要な医薬品の品質確保、国際調和の推進、最新の分析法の導入、そして改正プロセスの透明性確保です。医薬品各条、一般試験法、生薬総則等の項目について、最新の科学技術と国際基準を反映した改正が行われました。特に、収載品目の選定には医療上の必要性、繁用度、使用経験などが考慮され、保健医療上重要な医薬品は迅速な収載を目指しています。日本薬局方収載規則も策定され、収載基準の明確化が図られました。改正された薬局方は、医薬品の品質保証のための公的基準を示すものであり、国民への情報公開と説明責任を果たす役割も担っています。
1. 第十四改正日本薬局方と第一追補の告示
改正方針に基づき、各委員会は日本薬局方(JP)の収載品目の選定、通則、製剤総則、一般試験法、医薬品各条等の改正審議を継続しました。平成14年12月には、第十四改正日本薬局方第一追補が告示されました。この改正は、最新の科学技術の進歩と国際調和への対応を目的としています。 その後も審議は継続され、生薬総則、一般試験法、医薬品各条については、平成14年3月から平成15年12月にかけて調査会審議が終了した分を、第十四改正日本薬局方の一部改正としてまとめられました。この一部改正の調査会原案は、平成16年9月に日本薬局方部会で審議され、同年12月に薬事・食品衛生審議会に上程、報告された後、厚生労働大臣に答申されました。これらの過程は、日本薬局方の改定における綿密な審議と手続きの厳格さを示しています。
2. 日本薬局方の作成方針 5本の柱
日本薬局方の作成方針は、「5本の柱」として示されています。具体的には、保健医療上重要な医薬品の全面的収載による充実化、必要に応じた速やかな部分改正と円滑な行政運用、国際調和の推進、改正過程の透明性確保と普及、そして最新の分析法の積極的導入と標準品の整備促進です。この5つの柱に基づき、関係部局の理解と協力を得ながら、様々な施策が講じられました。その目的は、日本薬局方が広く保健医療の現場で有効に活用されるようにすることです。この方針は、医薬品の品質に関する薬事行政の円滑かつ効率的な推進、そして国際的整合性の維持・確保に貢献することを目的としています。
3. 収載品目の選定と日本薬局方収載規則
収載品目の選定にあたっては、医療上の必要性、繁用度、使用経験などを指標として、保健医療上重要な医薬品は市販後できるだけ速やかに収載することを目指しています。さらに、収載意義と基準の明確化のための具体的な収載規則の検討が行われ、平成14年12月の薬事・食品衛生審議会答申「今後の日本薬局方のあり方について」において、日本薬局方収載規則が示されました。これは、収載基準の透明性を高め、薬事行政の効率性と予測可能性を向上させる重要なステップです。 この規則は、医薬品が日本薬局方に収載されるための明確な基準を提供し、関係者間の理解と共通認識の醸成に貢献しています。
4. 日本薬局方の役割と公共性
日本薬局方は、当時の学問・技術の進歩と医療需要に応じて、わが国の医薬品の品質を確保するために必要な公的基準を示すものです。医薬品全般の品質を総合的に保証するための規格と試験法の標準を示すとともに、医療上重要な医薬品の品質に関する判断基準を明確にする役割を担っています。多くの医薬品関係者の知識と経験が結集されており、関係者に広く活用されるべき公共の規格書としての性格を有しています。 同時に、国民に医薬品の品質に関する情報を公開し、説明責任を果たす役割も担っています。この公共性は、国民の健康を守る上で極めて重要な要素となっています。
II.収載医薬品とその試験法
改正された日本薬局方には、多数の医薬品が収載されています。文書中には、アジスロマイシン、エトポシド、トラネキサム酸、トリクロルメチアジドなどの具体的な医薬品名が挙げられています。これらの医薬品について、定量法、含量均一性試験、溶出性試験などの具体的な試験方法が詳細に記述されています。試験法には、紫外可視吸光度測定法、液体クロマトグラフ法、薄層クロマトグラフ法などが用いられています。これらの試験法は、医薬品の品質管理において極めて重要です。また、標準品や試薬の規定も改正され、試験の精度向上に貢献しています。
1. 収載医薬品の例と試験法の概要
このセクションでは、日本薬局方(JP)に収載されている医薬品とその試験法について記述しています。具体例として、アジスロマイシン、エトポシド、コハク酸メチルプレドニゾロン、シスプラチン、チアミラール、トラネキサム酸、トリクロルメチアジド、ニルバジピン、フロセミドなどが挙げられています。これらの医薬品は、様々な種類と剤形があり、それぞれに適切な試験法が適用されます。試験法は、医薬品の品質、純度、含量などを評価するために用いられます。文書中には、定量法、含量均一性試験、溶出性試験などが具体的に記述されており、それぞれに用いられる分析手法(例えば、紫外可視吸光度測定法、液体クロマトグラフ法)も詳細に説明されています。これらの試験法の正確性と信頼性は、医薬品の品質保証において極めて重要です。標準品の使用や試薬の精製なども、分析の正確性向上に大きく貢献します。
2. 具体的な試験法 定量法 溶出性試験 含量均一性試験
文書では、トラネキサム酸の定量法として液体クロマトグラフ法が記載されています。この方法は、試料溶液と標準溶液を液体クロマトグラフで分析し、ピーク面積を比較することでトラネキサム酸の含量を定量します。 また、トリクロルメチアジドの含量均一性試験についても記述があります。これは、個々の錠剤における有効成分の含量が均一であるかを検証する試験です。内標準物質を用いた液体クロマトグラフ法が用いられ、ピーク面積比から含量を算出します。さらに、チアラミドの溶出性試験が紹介されており、溶出試験法第2法を用いて、一定時間後の溶出率を測定します。これらの試験法は、医薬品の品質管理において、正確な定量と含量の均一性を確認するために不可欠な手段です。これらの試験法は、医薬品の品質管理において、正確な定量と含量の均一性を確認するために不可欠な手段です。それぞれの試験法には、具体的な手順、使用する機器、計算方法などが詳細に記述されており、正確な結果を得るための注意も記されています。
3. 一般試験法と標準品 試薬
文書には、第一部一般試験法の部における標準品、試薬・試液に関する記述があります。 具体的には、シクロヘキシルアミン、ジシクロヘキシルウレアなどの試薬に関する記述があり、これらの試薬の項目は改正されています。さらに、塩酸ピペリジン、6-ジンゲロール、クルクマ紙、水酸化カルシウム、チオグリコール酸培地、L-チロシン、1-デカンスルホン酸ナトリウム、ブドウ糖・ペプトン培地などの試薬や培地についても記載があり、一部の項目が修正または改定されています。これらの標準品や試薬は、医薬品の品質試験を行う上で基準となるものであり、その正確性と品質が試験結果の信頼性に直結します。そのため、標準品や試薬の精製方法、保存方法なども重要であり、それらに関する規定も日本薬局方に含まれています。
III.たんぱく質定量法とペプチドマップ法
このセクションでは、たんぱく質定量法とペプチドマップ法について解説しています。たんぱく質定量法としては、ローリー法やBradford法といった一般的な方法に加え、等電点電気泳動法が挙げられています。ペプチドマップ法は、特にバイオテクノロジー医薬品の確認試験に用いられる手法で、たんぱく質の一次構造や構造変化の検出に有効です。これらの試験法には、アミノ酸分析法、**質量分析法(MS)**などの高度な分析技術が用いられています。ペプチドマップの作成には、トリプシンなどの酵素による消化が用いられる場合が多く、クロマトグラフィーを用いた分離と検出が行われます。再現性と信頼性の確保のため、システム適合性試験の実施が強調されています。
1. たんぱく質定量法 ローリー法 Bradford法 紫外可視吸光度法
このセクションでは、たんぱく質の定量法について解説しています。ローリー法(Lowry法)は、Folin-Ciocalteu試薬を用いて、チロシン残基と反応する発色反応を利用した方法です。たんぱく質の種類によって呈色度に差が生じる可能性があるため、標準品との比較が重要です。また、妨害物質の影響を受けやすいので、試料の前処理が必要な場合があります。Bradford法もたんぱく質定量法として言及されており、これは銅-BCA試薬を用いた方法です。紫外可視吸光度法は、波長280nmにおける吸光度を測定することで、チロシンとトリプトファンの含量からたんぱく質量を推定する方法です。この方法は、緩衝液の吸光度を補正する必要があるなど、いくつかの注意点が記述されています。いずれの方法も、正確な測定のためには、試料の精製、希釈、そして標準物質との比較が必須となります。
2. 等電点電気泳動法
等電点電気泳動法は、たんぱく質を等電点の違いによって分離する手法です。たんぱく質は、ゲル内の等電点の位置で実効荷電が0となり、移動度がゼロになります。しかし、拡散作用による移動は認められます。通電によって形成されるpH勾配の中で、それぞれの等電点位置でたんぱく質の移動が停止し、濃縮されます。この濃縮効果をフォーカシングと呼びます。発生する熱を効率的に放散させるために、電圧には制限がありますが、試料量を減らし高電圧を用いることで分離度を向上させることができます。また、薄いゲルや冷却装置を用いることで、ゲルの発熱を抑え、良好なフォーカシングが実現します。この方法は、たんぱく質の分離・同定に有効な技術であり、医薬品中のたんぱく質分析に広く応用されています。
3. ペプチドマップ法 目的 範囲 手順 および注意点
ペプチドマップ法は、特にバイオテクノロジー医薬品において、たんぱく質の確認試験に用いられる手法です。たんぱく質を化学的または酵素的にペプチド断片に分解し、それらを分離・確認することで、たんぱく質の一次構造を確認したり、構造変化や製造工程の変動を検出したりします。この手法では、標準品/標準物質と同様の処理を行い、比較することでたんぱく質の同一性や純度を評価します。ペプチドマップは、たんぱく質の「指紋」として機能し、個々のペプチド断片の保持時間やピーク面積、ピーク高さを比較することで、たんぱく質の特性を明らかにします。しかし、断片数が多すぎると特異性が失われる可能性があり、適切な消化条件と分析条件の選択が重要となります。また、システム適合性試験を実施し、試験法全体の性能を評価することも不可欠です。変異たんぱく質の分析では、変異部分の分離が困難な場合、標準品との混合物を分析することで、より正確な評価が可能になります。
IV.その他分析法
文書には、アミノ酸分析法、微生物の迅速同定法など、その他の分析法についても言及があります。アミノ酸分析法は、医薬品のアミノ酸組成や含量を測定する方法です。加水分解法、誘導体化法、クロマトグラフィーなどを組み合わせた手法が用いられます。検出器としては、紫外可視検出器や蛍光検出器が用いられます。また、微生物の迅速同定法では、遺伝子解析技術が活用されています。これらの分析法は、医薬品の品質管理において重要な役割を果たしています。
1. アミノ酸分析法 原理と方法
このセクションでは、アミノ酸分析法について詳細に説明しています。アミノ酸分析法は、たんぱく質、ペプチド、その他の医薬品中のアミノ酸組成やアミノ酸含量を測定する方法です。たんぱく質やペプチドはアミノ酸残基が共有結合で重合した高分子であり、そのアミノ酸配列は特性を規定します。アミノ酸分析は、定量、同定、構造解析などに利用され、ペプチドマップ法におけるペプチド断片の評価や、異常アミノ酸の検出にも役立ちます。分析前に、たんぱく質やペプチドを加水分解して構成アミノ酸にする必要があります。加水分解後、クロマトグラフィーによる分離、誘導体化による検出、そして検出器(紫外可視検出器や蛍光検出器など)を用いた定量が行われます。近年では、自動クロマトグラフ装置が広く利用されています。分析の精度には、実験手順や機器の管理が大きく影響します。
2. アミノ酸分析法 加水分解 試料調製 測定
アミノ酸分析の前処理として、酸加水分解が一般的です。しかし、この方法ではトリプトファンが破壊され、セリンやスレオニンは部分的に破壊されるなど、いくつかのアミノ酸は分解されるため、分析結果に影響が出ます。そのため、真空下での加水分解や不活性ガス(アルゴン)の使用が推奨されます。また、イソロイシンやバリンを含む特定のアミド結合は完全に切断されない場合があります。アスパラギンやグルタミンは脱アミド化されるため、定量できるのは17種類のアミノ酸に限られます。正確な結果を得るためには、精製されたたんぱく質やペプチド試料が必要であり、緩衝液成分などの除去も重要です。試料調製の際には、汚染を最小限に抑え、回収率を高める工夫が求められます。 測定は、イオン交換クロマトグラフィーとポストカラム誘導体化法を組み合わせる方法が一般的で、ニンヒドリンやo-フタルアルデヒドが誘導体化試薬として使用されます。 しかし、プロリンなどの二級アミンは検出できないため、他の方法と組み合わせる必要がある場合もあります。
3. アミノ酸分析法 データの計算と解析 および注意点
アミノ酸分析のデータ解析においては、酸加水分解によるアミノ酸の分解を考慮する必要があります。特に、システイン、トリプトファン、スレオニン、イソロイシン、バリン、メチオニン、グリシン、セリンなどは、加水分解過程で分解または酸化を受けやすく、定量値に変動が生じやすいです。これらのアミノ酸の定量値の解釈には、より詳細な検討と考察が必要です。分析の再現性を確認するために、標準アミノ酸溶液を用いた繰り返し測定を行い、相対標準偏差(RSD)などを算出します。標準たんぱく質(例:ウシ血清アルブミン)を用いた分析も、再現性の評価に役立ちます。 また、毛細管電気泳動法を用いる場合、試料成分の吸着による分離効率の低下を防ぐため、緩衝液組成の工夫や毛細管内壁の修飾などの手法が用いられます。有機溶媒の添加による分離の改善も検討されていますが、高濃度ではミセル形成が阻害されるため、注意が必要です。
4. 微生物の迅速同定法 遺伝子解析
この文書では、遺伝子解析による微生物の迅速同定法にも触れられています。従来の方法と比較して、迅速かつ正確な微生物同定を可能にする技術として、遺伝子解析が注目されています。この方法は、微生物の遺伝子情報を解析することで、迅速に微生物の種類を特定することができます。従来の培養法に比べて、大幅な時間短縮が期待できます。遺伝子解析技術は、医療現場での迅速な診断や、食品・環境分野での微生物検査などに広く応用され、感染症対策や品質管理に大きく貢献しています。この手法は、日本薬局方においても、微生物試験の効率化に寄与する技術として位置付けられています。
