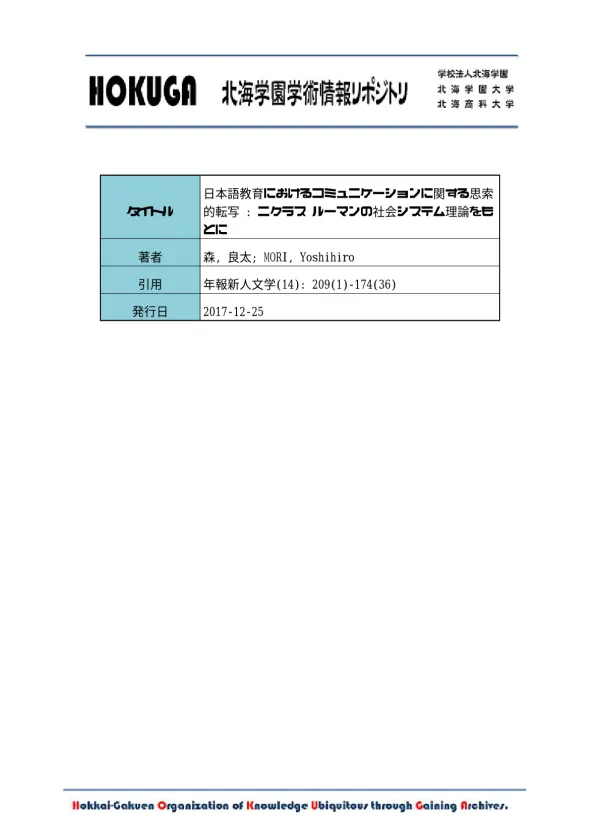
日本語教育とコミュニケーション:ルーマンの社会システム理論
文書情報
| 著者 | 森 良太 |
| 専攻 | 日本語教育 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 414.33 KB |
概要
I.日本語教育における社会概念の再考 ルーマンの社会システム理論の適用
本論文は、日本語教育における「社会」概念をルーマンの社会システム理論を用いて再検討する。従来の日本語教育研究では、社会は学習者の主観的認識に基づく内部イメージとして捉えられることが多かった。しかし、本研究は、コミュニケーションを社会の構成要素と捉えるルーマンの理論を導入することで、学習者が経験を通じてどのように社会を内部イメージ化していくのかを分析する。特に、コミュニケーションの連鎖としての社会、機能システムとしての社会の役割、そしてコミュニケーション・メディア(言語、ボディランゲージなど)の重要性に着目する。自己言及的な社会構築プロセスと、文化の本質主義批判の観点からの考察も含まれる。
1. 従来の日本語教育における社会概念
1980年代以降のコミュニカティブ・アプローチ導入以降、日本語教育では、言語運用文脈や文化的特性と学習者の関わりが注目されるようになった。ネウストプニー(1995)の社会的ネットワーク形成に基づくコミュニケーション能力伸長や、細川(1999)の文化の本質主義批判といった新たな概念が登場し、言語学習を通じた学習者の社会認識への注目が高まった。しかし、これらの議論における「社会」は、学習者個人の認識フレーム内で構築された内部イメージであり、日常生活における「社会性」「社会化」といった概念が持つ公共的な側面は必ずしも含んでいない。近年では、社会構成主義的な視点も注目を集めている。このような視点は、自己の認識に基づき動的に事象を捉え、その生成・変容を内的に意味づけることで社会を内部イメージ化しようとするものであり、学習者自身のコミュニケーションによる社会的ネットワーク形成と、自己言及的な社会・文化理解を目指すものである。これは、学習者個人の経験や認識の個別性・多様性を重視し、他者とのコミュニケーションを通して社会認識を構築していくことを目的とするアプローチと言える。既存の「日本社会」「日本文化」といった概念にとらわれず、学習者の日常生活における問題解決を通して形成される、より個人的・多様な社会認識を重視する点が特徴的である。
2. ルーマンの社会システム理論の導入 分析ツールの提示
本研究は、日本語教育における学習者の自己言及的な社会構築(内部イメージとしての社会)を分析するために、ニクラス・ルーマンの社会システム理論を援用する。ルーマンの理論に基づき、日本語教育における社会の捉え方に対しオルタナティブな視点を提示し、コミュニケーションの側面から社会を捉えることで、学習者が経験を通じて自己の内側に構築する社会のイメージ化システムを探る。従来の日本語教育研究では、「社会」というキーワードは用いられてきたものの、その本質的な定義については研究者間で多様な解釈が存在し、統一的な見解は得られていない。ルーマンの社会システム理論は、複雑で多様な社会において、個人が自由に振る舞うように見えるにもかかわらず、社会秩序がどのように成立するのかという問題意識から出発している。この理論を用いることで、従来の学習者中心のアプローチでは捉えきれない、社会システム全体における学習者の位置づけや、コミュニケーションの役割をより明確に分析できる可能性が示唆される。
3. 日本語教育における社会概念の変遷と課題
1950年代以降、日本の日本語教育カリキュラムでは、言語習得と社会・文化の関連性が議論されてきた。初期の教育実践では、社会・文化教育は知識教授型が中心であり、固定的な文化観の習得が重視されていた。しかし、こうした実践への疑問から、細川(1995)などの学習者主体論が台頭し、学習者の問題発見・解決プロセスが重視されるようになった。学習者主体論は、目標言語習得に加え、学習者の社会的文脈も重視する。コミュニカティブ・アプローチと共通する点もあるが、文化・社会の本質主義批判に基づいており、固定的な「日本社会」「日本文化」像を前提としない点が異なる。学習者は日常生活での問題解決を通して、自己の経験に基づく社会的認識を構築していく。ネウストプニー(1982)の「社会文化行動」概念は、日本語教育における社会的文脈の焦点化に貢献した。これらの様々な視点や概念は、文法・文型中心の教育からインターアクション重視型教育へのパラダイムシフトに大きく寄与した。しかし、「社会」概念の本質主義批判の後、個人の認識による社会観が注目されるようになったものの、それは「社会とは何か」という根本的な問いに十分な解答を与えているとは言い切れない。個人の認識は重要だが、他者性を帯びた「社会」概念を捉えるには、よりメタ的な視点が必要となる。
II.ルーマンの社会システム理論 概要と主要概念
ルーマンの社会システム理論は、社会をコミュニケーションの連鎖として捉える。コミュニケーションは「情報」「伝達」「理解」の三要素から成り立ち、コミュニケーション・メディア(流布メディア、相互作用メディア、成果メディア)によって連鎖する。個々のコミュニケーションは偶発的だが、システム全体は自己言及的に持続する(オートポイエーシス)。様々な機能システム(経済、政治、法、教育など)が並立的に存在し、相互作用しながら社会を形成する。教育システムにおいては、「良い/劣る」といったコードが学習者のキャリア形成に影響を与える。
1. 社会システム理論におけるコミュニケーション
ルーマンの社会システム理論において、コミュニケーションは中心的な概念である。しかし、これは一般的な言語を媒介とした意思伝達とは異なる。ルーマンは、コミュニケーションを「情報」「伝達」「理解」という三要素が揃った相互調整的な出来事と定義する。これは、話者側の意図的な発信行為ではなく、複数主体間で偶発的に発生する相互作用的な出来事を指す。例えば、Aが窓際にいる状況で、Bが「暑いね」と発言し、暑そうな表情で扇いでいる様子をAが理解したとき、コミュニケーションが成立する。このコミュニケーションは、言語コミュニケーションだけでなく、非言語的な「暑そうな表情」や「扇ぐ仕草」なども含む広義の概念である。ルーマンは、社会自体をコミュニケーションの連鎖として捉え、人間をその要素とは見なさない。この特異な視点は、社会システムの秩序が、個々の自由な行動にもかかわらずどのように成立するのかを説明しようとするものである。この理論の難解さは、人間を社会構成要素から排除するこの独特な視点にあると言える。
2. コミュニケーションの性質とオートポイエーシス
ルーマンの理論では、コミュニケーションは、ある事象における意味の選択として捉えられる。社会は人間が統制的に構築するのではなく、コミュニケーションによって自己言及的に生成・持続されると考える点が特徴である。システムの構成要素は、システム内部で自ら生み出され、次の構成要素の生成を促す。個々の構成要素は消滅するものの、新たな構成要素が生成されることでシステムは存続する。これは、マトラーナとヴァレラによる「オートポイエーシス」という生物学的概念を社会学的に応用したものであり、ルーマン理論の重要な基盤となっている。コミュニケーションは予期的文脈を与えるが、常に関連する出来事が後続するとは限らない。社会が安定的に見えるのは、コミュニケーションが常に同一ではなく、変容・入れ替わりながらシステムを再構成し続けるからである。このダイナミックなコミュニケーションの連鎖を理解することが、ルーマン理論を理解する上で重要となる。
3. コミュニケーション連鎖のためのメディアと機能システム
コミュニケーションが連鎖するためには、それを促進する「コミュニケーション・メディア」が機能する。ルーマンは、①流布メディア(通信技術、印刷技術など)、②相互作用メディア(広義の言語、ボディランゲージなど)、③成果メディア(真理、愛、権力など)の三種類を挙げる。流布メディアは時間・空間を超越してコミュニケーションを成立させ、相互作用メディアは相手の思考を伝え、成果メディアはコミュニケーションの受け入れやすさや後続する出来事の前提に影響を与える。これらのメディアは、コミュニケーションの偶発性を制御し、連鎖を促進する役割を果たす。さらに、ルーマンは社会を様々な機能システム(経済、政治、法、教育など)の集合体と捉える。各機能システムは自律的に働き、独自のコードを持つ。例えば、法システムでは「合法/違法」、教育システムでは「良い/劣る」といったコードが用いられる。これらのコードは、コミュニケーションの区別化と連鎖に重要な役割を果たし、社会全体の秩序維持に寄与する。ただし、各機能システムは独立しながらも相互に影響を与え合い、その影響を予測することは不可能である。
4. 教育システムと環境との関係性
教育システムは、教師と生徒の相互作用が円滑な場合にのみ機能する。教師は生徒の行動を観察し評価することはできるが、教育活動が生徒の内面にどのような質的変化をもたらすかを直接知ることはできない。教育の効果は、教育を受けた者が後続のコミュニケーションに関与することで初めて現れる。教育システムのコードは「良い/劣る」であり、これはキャリア形成や社会における選抜機能に関連する。ルーマンは、社会化は教育の前提条件ではあるが、両者はイコールではないとする。高度に複雑化した社会では、教育を通じた評価による資格・証明が重要となる。標準的な社会化に加え、意図的なカリキュラムによる教育的社会化が求められる。システムは、環境との境界において、内部要素と外部要素を区別する。システムは環境との関係性の中でしか存在できないが、内部的には自律的に作動する。環境は、システムの作動によって初めて成立し、システムによって異なる要素を含む。環境は、システムの作動を容易にする可能性を持つ。
III.日本語教育におけるコミュニケーションと社会化
日本語教育においては、コミュニケーションは学習者の社会認識構築に不可欠な要素である。学習者主体の視点から、学習者は他者とのコミュニケーションを通じて、自己の内部イメージとしての社会を構築する。細川(1995)などの学習者主体論や、ライフストーリー研究は、この自己言及的な社会構築プロセスを裏付ける。コミュニケーションにおける意味の縮減可能性の理解が、社会理解の鍵となる。学習者の社会化は、教育の前提ではあるが、教育とイコールではない。教育は、コミュニケーションに関与するための質的な変化に作用する。
1. コミュニケーションによる社会認識の構築
日本語教育におけるコミュニケーションの概念は、従来、話者の主体的な発話を中心に捉えられてきた。しかし、ルーマンの社会システム理論の視点を取り入れると、コミュニケーションは話者内部から発せられるものではなく、複数の主体間の相互作用によって生じる偶発的な出来事と捉えられる。例えば、「暑い」という発言と、それに伴う表情や仕草、そして窓を開けるという行為は、個人の内面ではなく、外部からの影響を受けて発生する可能性がある。ルーマン理論は、コミュニケーションをある事象における意味の選択と捉え、社会は人間が統制的に構築するのではなく、コミュニケーションによって自己言及的に生成・持続すると主張する。これは、人間が社会に関与する主体であることは認めつつも、社会を構成する要素としては考えない、従来とは異なる視点である。学習者は、他者とのコミュニケーションを通して、自己の内部に社会のイメージを構築していく。この過程において、言語コミュニケーションだけでなく、非言語コミュニケーションも重要な役割を果たす。
2. 学習者主体論と社会化 ルーマン的視点からの解釈
細川(1995)の学習者主体論は、学習者が他者とのせめぎ合いの中で自己の内側に社会的認識を構築していくという言語文化学習観を示している。川上(2007)や三代(2009)なども、学習者の社会化について言及している。これらの考え方は、ルーマンの社会システム理論から見ると、コミュニケーションにおける意味の縮減可能性について、言語学習の文法で記述したものと解釈できる。ある社会を理解するということは、その社会に属する人々の行為とその相互関係を意味づけできるようになることである。他者性を考慮した行為認識が、コミュニケーションの文脈で意味の縮減をもたらし、学習者は自らの行為の選択可能性と、後続するコミュニケーションにおける選択接続の可能性から、予期とその実現可能性を見出す。他者の予期を前提に振る舞うことができるとき、はじめてその行為は社会的であるとみなされる。ライフストーリー研究(三代(2011)、川上ら(2011)、桜井(2005)など)も、学習者の社会的ネットワークの学習への影響を分析し、学習者の経験に基づく社会認識の構築プロセスを明らかにしようとするものである。
3. 社会的文脈と行為の解釈 教育におけるコミュニケーション
学習者がコミュニケーションを実践する社会的文脈は、その解釈に大きな影響を与える。井庭ら(2013)や森(2013)のパターン・ランゲージを用いた問題発見解決アプローチも、個人と社会の関わりを基礎としている。これらの学習経験は、学習者の内側で繰り返し行われることで、行為や出来事に一定の意味づけが可能となり、通時的な観察を通して社会的意味づけを持った概念として捉えられるようになる。教師の行為も、学習者の他のコミュニケーションにおける行為選択に影響を与える可能性があり、学習者の行為解釈にも影響する。学習者の行為は、個人属性としてだけでなく、日本の教育機関や社会、日本人の特徴といったように、一般化されて解釈されることがある。「〇〇人学習者は…」「××語話者は…」といった帰属処理は、実践現場でしばしば見られる。教育における合理性を考慮すれば、このような帰属処理は、後続のコミュニケーションに予期的文脈を与えるという点で、必ずしもネガティブな影響だけを与えない可能性がある。
IV.社会システム理論と日本語教育実践 結論
ルーマンの社会システム理論は、日本語学習における社会概念の理解に新たな視点を提供する。学習者が経験を通じて構築する社会は、コミュニケーション(言語・非言語)によって内部イメージ化され、自己言及的に概念化される。このプロセスは、偶発的な出来事を連続的なシステムとして捉えることを可能にする。本研究は、社会構成主義などの多様な視点を取り入れることで、現代の複雑な社会に対応できる日本語教育のメタ理論構築に貢献する。重要な研究者として**細川(1995)、ネウストプニー(1995)、岡崎・砂川(1999)、牡川(2007)、三代(2009)、川上(2007)、三代(2011)、川上ら(2011)、桜井(2005)、井庭ら(2013)、森(2013)、森(2016)**などが挙げられる。
1. ルーマン理論による日本語教育実践への示唆
ルーマンの社会システム理論は、学習者が様々な経験から自己の内側に構築する社会を、言語コミュニケーションや非言語コミュニケーションを含むコミュニケーション全体によって内部イメージ化し、自己言及的に概念化していく過程を説明する枠組みを提供する。学習者は、先行する経験を参照し、予期的文脈の上でしか後続するコミュニケーションの偶発性に対処できない。学習者が経験を通じて自己の内側に社会を構築していく学びのプロセスは、コミュニケーションの側から捉えることで、偶発的な出来事を連続的なシステムの作動として捉える新たな視点を提供する。ルーマン理論は、このプロセスを理解する上で重要な一助となる。この理論を用いることで、日本語教育における「学んだ」とみなす基準を、環境に位置づけられた対象の現象学的解釈として捉え直すことができる。複数の解釈可能性が存在し、現象は意味的に多重性、時間的に多元性を持ちうる。この多様な解釈可能性を理解することで、より深い学習理解が可能となる。
2. 現代日本語教育における学際的研究アプローチの必要性
複雑で多様な現代社会に対応するため、ディシプリンの枠組みを超えた学際的なアプローチが求められている。日本語教育においても、社会構成主義などの他分野の研究成果を応用した研究が盛んに行われている。ルーマンの社会システム理論も社会学における基礎理論であり、日本語教育への応用可能性が高い。しかし、これまでの日本語教育研究では、ルーマン理論はほとんど扱われてこなかった。これは、ルーマン理論が「ヒト」を説明対象から除外するなど、日本語教育との学問的相性があまり良くない可能性があるためかもしれない。しかし、社会構成主義への関心の高まりから、日本語教育においても、社会の本質を踏まえた学習に関するメタ理論への需要が高まると予想される。ルーマン理論は、言語習得と人的ネットワーク形成の機能、そして学習者の内部表現としての社会イメージを説明する有力なツールとなりうる可能性がある。
3. 今後の研究課題と展望
本論文で示されたルーマンの社会システム理論の適用は、日本語教育における「社会」概念の理解を深めるための第一歩である。今後の研究では、より具体的な教育場面におけるコミュニケーションの分析や、学習者の社会認識の形成過程の詳細な解明が必要となる。また、ルーマン理論と他の理論(例えば、ヴィゴツキーの心理学理論)との統合的な枠組みを構築することで、より包括的な学習モデルを構築することも重要である。さらに、ルーマン理論を実際の日本語教育カリキュラム設計や授業実践にどのように応用できるのかについても、具体的な研究が必要である。これらの研究を通じて、現代社会のニーズに対応できる、より効果的で質の高い日本語教育のあり方が探求されることが期待される。特に、学習者の多様な経験と認識を尊重し、コミュニケーションを重視する学習環境の構築が重要となるだろう。
