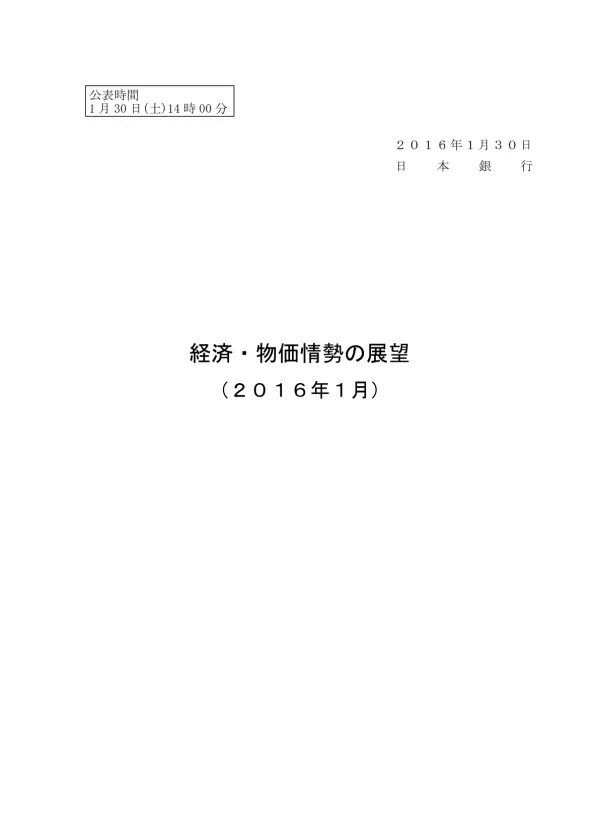
日本銀行経済・物価展望:物価目標達成時期
文書情報
| 著者 | 日本銀行 |
| 専攻 | 経済学 |
| 会社 | 日本銀行 |
| 場所 | 東京 |
| 文書タイプ | 経済報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 3.66 MB |
概要
I.物価見通しと景気動向
日本銀行の政策委員会は、消費者物価(除く生鮮食品)の前年比が当面0%程度で推移すると予想しているものの、物価の基調は着実に上昇し、2%(物価安定の目標)に向けて上昇率を高めていくとみている。エネルギー価格の下落が当面は下押し圧力となるものの、原油価格の緩やかな上昇を前提とすれば、2017年前半頃には消費者物価の前年比が2%程度に達すると予想される。景気は輸出・生産面に新興国経済の減速の影響がみられるものの、緩やかな回復を続けており、2017年度も緩やかな拡大が予想される。設備投資は企業収益の改善を背景に増加基調にあり、個人消費も底堅く推移するとみられる。輸出は新興国経済の回復を背景に緩やかに増加すると予想されている。消費税率の2017年4月引き上げとその反動の影響も考慮されている。 主要キーワード: 消費者物価, 物価安定の目標, エネルギー価格, 原油価格, 景気, 設備投資, 個人消費, 輸出, 消費税
1. 消費者物価見通し
消費者物価(除く生鮮食品)の前年比は、エネルギー価格下落の影響で当面0%程度と予想される。しかし、物価の基調は着実に高まり、2%(物価安定の目標)に向けて上昇率を高めると考えられる。原油価格が緩やかに上昇するという前提のもと、エネルギー価格のマイナス寄与は2016年度末まで残り、その後は次第に減少していくと試算される。このため、消費者物価の前年比が2%程度に達するのは2017年度前半頃と予想され、その後は平均的に2%程度で推移すると見込まれる。この見通しは、1月28、29日に開催された政策委員会・金融政策決定会合で決定されたものである。各政策委員は原油価格(ドバイ原油)を1バレル35ドルから40ドル台後半に緩やかに上昇すると想定し、その場合の消費者物価(除く生鮮食品)の前年比に対するエネルギー価格の寄与度は、2015年度で-0.9%ポイント程度、2016年度で-0.7~-0.8%ポイント程度と試算している。また、2016年度後半にはマイナス幅が縮小に転じ、2017年度前半には概ねゼロになると試算されている。物価安定の目標達成時期の予測は、原油価格の上昇という前提に基づいている点が重要である。
2. 景気動向と見通し
日本の景気は、輸出・生産面に新興国経済の減速の影響がみられるものの、緩やかな回復を続けている。2017年度までの展望では、家計と企業の両部門で所得から支出への前向きの循環メカニズムが持続し、国内需要が増加基調をたどり、輸出も新興国経済の減速からの脱却などを背景に緩やかに増加すると見込まれる。そのため、日本経済は基調として緩やかに拡大していくと考えられる。具体的には、国内需要では設備投資が企業収益の改善に伴い緩やかな増加基調にあり、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費も底堅く推移している。住宅投資も持ち直しを見せている。公共投資は高水準ながら緩やかな減少傾向にある。鉱工業生産は横ばい圏内の動きが続いている。金融環境は緩和した状態が続いている。2015年度下期から2016年度にかけては、輸出は持ち直しから緩やかな増加に転じ、設備投資も輸出・生産の持ち直し、過去最高水準の企業収益、金融緩和効果などを背景に増加を続けるとみられる。個人消費は、2017年4月の消費税率引き上げ前の駆け込み需要とその反動、設備投資の増加ペースの鈍化などの影響を受けるものの、輸出の緩やかな増加や緩和的な金融環境、成長期待の高まりなどを背景に底堅く推移すると予想される。2017年度は、設備投資の増加ペースの鈍化や消費税率引き上げの影響で成長率は減速するものの、プラス成長を維持すると見込まれる。
3. 消費税率引き上げの影響
2017年4月の消費税率10%への引き上げ(酒類と外食を除く飲食料品および新聞に軽減税率適用)は、景気動向に大きな影響を与える。消費税率引き上げ前には駆け込み需要によって家計支出を中心に実質GDPを押し上げる効果が発生し、引き上げ後には、駆け込み需要の反動と実質所得の減少によってGDPを押し下げる効果が発生する。軽減税率の導入は、実質所得の減少幅を縮小させることで家計支出を下支えする方向に作用すると考えられる。2017年度の成長率は、設備投資の循環的な増加ペースの鈍化に加え、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減や実質所得の減少効果のために、前年度から大きく低下すると見込まれる。しかし、輸出の緩やかな増加や、金融緩和効果、成長期待の高まり、オリンピック関連投資による押し上げ効果により、国内民間需要は基調的な底堅さを維持すると考えられる。そのため、2017年度もプラス成長を維持すると予想されている。 消費税率引き上げの影響については、2014年4月の増税時の2/3程度にとどまると見積もられ、軽減税率の導入効果も勘案されている。軽減税率導入によって駆け込み需要とその反動、実質所得減少効果は縮小すると考えられ、2017年度のマイナス効果は軽減税率が全く導入されない場合と比べて小さくなると予想される。
II.物価上昇率を規定する要因
物価上昇率を規定する要因として、①マクロ的な需給バランスの改善(労働需給の引き締め、設備稼働率の上昇)、②中長期的な予想物価上昇率の上昇(企業の価格改定スタンスの変化、賃金上昇)、③輸入物価への影響(円安と国際商品市況の下落の両面の影響)が挙げられる。特に、円安は輸入物価の上昇を通じた直接的な影響に加え、需給バランスの改善を通じた間接的な影響も持続的に与える。しかし、賃金の上昇は現状では鈍く、労働分配率も低下傾向にある点には留意が必要である。主要キーワード: 需給ギャップ, インフレ予想, 円安, 賃金, 輸入物価
1. マクロ的な需給バランス
物価上昇率を規定する第一の要因は、労働や設備の稼働状況を表すマクロ的な需給バランスである。新興国経済の減速による生産のもたつきはあるものの、労働需給は引き締まり傾向が続き、失業率は緩やかに低下して3%台前半で推移している。輸出・生産の持ち直しに伴い設備稼働率は上昇し、マクロ的な需給バランスは本年度末にかけてプラス(需要超過)に転じ、2016年度にはプラス幅が一段と拡大すると予想される。これにより、需給面からみた賃金と物価の上昇圧力は着実に強まっていくと見込まれる。しかし、2017年度にはプラスの水準で横ばい圏内の動きになると予想されている。労働需給の引き締め、設備稼働率の上昇といった需給バランスの改善が、賃金と物価上昇への圧力として作用すると考えられる。この需給ギャップの改善が、物価上昇にどのように影響するかを分析する上で重要な要素となる。
2. 中長期的な予想物価上昇率
物価上昇率を規定する第二の要因は、中長期的な予想物価上昇率である。近年は弱めの指標も見られるものの、長い目でみると上昇傾向にあると判断される。企業の価格・賃金設定スタンスは本年度入り後、明確に変化し、消費者も雇用・所得環境の改善を受け価格改定を受容する傾向にある。価格改定は拡がりと持続性を伴い、労使間の賃金交渉では、企業業績や労働需給に加え、物価動向が賃金に反映される動きが広がっている。日本銀行のマイナス金利付き量的・質的金融緩和政策も、実際の物価上昇率を高め、中長期的な予想物価上昇率の上昇に繋がるだろう。ただし、企業収益が過去最高水準にあるにもかかわらず賃金の改善が鈍く、労働分配率も低下傾向にある点は留意が必要である。インフレ予想の高まりが、企業の価格設定や賃金交渉に影響を及ぼし、物価上昇率を押し上げるメカニズムが注目される。
3. 輸入物価と円安の影響
物価上昇率を規定する第三の要因は輸入物価であり、為替相場の変動が大きく影響する。これまでの円安傾向は、輸入物価を通じた消費者物価の押し上げ要因として作用している。一方、原油価格をはじめとする国際商品市況の下落は、物価の下押し圧力となる。円安は、輸入物価の上昇という直接的な物価押し上げ効果に加え、マクロ的な需給バランスの改善を通じて実際の物価と予想物価上昇率を押し上げる、より持続的な効果を持つと分析される。円安の持続的な影響は、インフレ率にコストプッシュ効果をもたらすだけでなく、需給ギャップやインフレ予想の改善という間接的な効果も生み出すため、物価上昇に長期的な影響を与える可能性がある。国際商品市況の変動や為替レートの動向は、輸入物価を通じて消費者物価に影響を与えるため、注視すべき重要な要素である。
III.金融政策運営上のリスク
金融政策運営上のリスクとして、海外経済の動向を背景とした景気の下振れリスクと、中長期的な予想物価上昇率の不確実性による物価の下振れリスクが大きい。政府債務残高の累増と金融機関の国債保有残高の高水準も懸念材料である。主要キーワード: 金融政策, リスク, 政府債務
1. 経済見通しにおける下振れリスク
金融政策運営の観点から見た中心的なリスクは、経済見通しにおける下振れリスクである。これは主に海外経済の動向に依存しており、新興国経済の減速や資源価格の低迷長期化などが、日本経済の成長を阻害する可能性がある。特に、新興国・資源国の期待成長率の低下や資源価格の低迷長期化は、素材・エネルギー価格への影響を通じて、日本企業の収益や輸出に悪影響を及ぼす可能性があり、景気の下方リスクを高める。 これらの外部環境の不確実性は、企業の投資意欲を抑制し、設備投資や雇用創出の減速に繋がる可能性がある。さらに、原油価格の一段の下落や中国をはじめとする新興国・資源国経済の先行き不透明感は、金融市場に不安定な動きをもたらし、企業コンフィデンスの改善やデフレマインドの転換を遅延させるリスクもある。これらの要因は、日本経済の成長を抑制し、物価の基調に悪影響を及ぼす可能性があるため、金融政策運営上、重要なリスク要因となる。
2. 物価見通しにおける下振れリスクと不確実性
金融政策運営上、重視すべきもう一つのリスクは、物価見通しにおける下振れリスクである。特に、中長期的な予想物価上昇率の動向には不確実性が大きく、下振れリスクが顕著である。原油価格の下落が長引き、消費者物価の前年比が高まりにくい状況が続けば、予想物価上昇率の上昇ペースが影響を受けるリスクがある。賃金と物価の関係においては、今春の労使交渉での賃金上昇に、既往の基調的な物価上昇や先行きの物価見通しが適切に反映されることが重要となる。 また、企業の賃上げの動きが海外経済の動向など経営環境の不確実性から拡がりを欠く場合、消費者の物価上昇に対する抵抗感が強まる場合などは、物価上昇ペースが下振れるリスクとなる。さらに、食料工業品や耐久消費財の価格が需給ギャップの改善に比較的強く反応する一方、公共料金や一部サービス価格、家賃などは反応が鈍いため、消費者物価の上昇率の高まりを抑制する要因となる可能性がある。これらの要素は、物価上昇の勢いを弱め、物価安定目標の達成を困難にする可能性があるため、注意深く監視する必要がある。
3. 長期的な金融面の不均衡
より長期的な視点から金融面の不均衡について見ると、現時点では資産市場や金融機関行動において過度な期待の強気化を示す動きは観察されない。しかし、政府債務残高が累増する中で、金融機関の国債保有残高は全体として減少傾向が続いているものの、依然として高水準にある点は留意が必要である。政府債務の増加は、金融市場の安定性や金融政策の有効性に影響を与える可能性がある。 政府債務の増加は、国債市場の歪みを引き起こし、金融政策の伝達メカニズムに影響を及ぼす可能性がある。金融機関の国債保有残高の高水準は、潜在的なリスクを抱えていることを示唆しており、将来の金融市場の動向に影響を与える可能性がある。これらの長期的な金融面の不均衡は、将来の金融政策運営に不確実性を生じさせるリスク要因となるため、継続的な監視が必要である。
IV.消費税率引き上げの影響
2017年4月の消費税率10%への引き上げ(酒類と外食を除く飲食料品および新聞に軽減税率適用)は、駆け込み需要とその反動、実質所得の減少を通じて経済に影響を与える。軽減税率の導入は、実質所得の減少幅を縮小させ、家計支出を下支えすると予想される。主要キーワード: 消費税, 軽減税率, 実質所得
1. 消費税率引き上げのメカニズムと影響
2017年4月の消費税率10%への引き上げは、大きく分けて2つの経路で実体経済に影響を与えると考えられる。一つ目は、税率引き上げ前後の駆け込み需要とその反動効果である。これは、主に家計支出(個人消費と住宅投資)に影響を与えると考えられているが、設備投資においても簡易課税・免税事業者(個人・零細企業が中心)などに影響する可能性も考慮されている。二つ目は、税率上昇による物価上昇に伴う家計の実質可処分所得の減少である。この影響は、消費税率引き上げによる物価上昇が家計の購買力を低下させることで、個人消費の減少に繋がる。これらの影響は、消費税率引き上げ前後の駆け込み需要と、引き上げ後の反動、そして実質所得の減少という形で、経済成長率に影響を与える。消費税率引き上げによる成長率への影響は、2014年4月増税時の約2/3程度と見積もられ、軽減税率の導入効果も勘案されている。
2. 軽減税率導入の効果
消費税率引き上げにおいては、酒類と外食を除く飲食料品および新聞に8%の軽減税率が適用される。軽減税率の導入は、消費税率引き上げによる実質所得の減少幅を縮小させることで、家計支出を下支えする方向に作用する。軽減税率の対象となる飲食料品や新聞は非耐久財であるため、駆け込み需要とその反動の規模は限定的とみられる。しかし、軽減税率導入による物価押し下げは、家計の実質可処分所得を押し上げる効果を持つ。そのため、軽減税率が全く導入されない場合と比較して、2017年4月の消費税率引き上げが成長率に及ぼす影響、特に実質所得減少効果は小さくなると考えられる。2017年度のマイナス効果は、軽減税率導入によって幾分小さくなると予想されている。この軽減税率の導入が、消費税増税による個人消費への打撃をどの程度軽減できるかが、今後の経済動向を占う上で重要な要素となる。
3. 消費税増税とGDP成長率への影響
消費税率の引き上げは、駆け込み需要とその反動、そして実質所得の減少という二つの主要な経路を通じて、GDP成長率に影響を与える。具体的には、2017年4月の消費税率引き上げにより、設備投資の循環的な増加ペースが次第に鈍化する中で、駆け込み需要の反動減や実質所得の減少効果が発生するため、成長率は前年度から大きく低下すると見込まれる。しかしながら、輸出の緩やかな増加や、金融緩和効果、成長期待の高まり、オリンピック関連投資による押し上げ効果なども考慮すると、国内民間需要は基調的な底堅さを維持すると考えられる。これらの要因を総合的に考慮すると、2017年度は潜在成長率を幾分下回る程度に減速するものの、プラス成長を維持すると予想されている。消費税増税の影響は、軽減税率導入の影響も考慮に入れながら、慎重に評価する必要がある。
