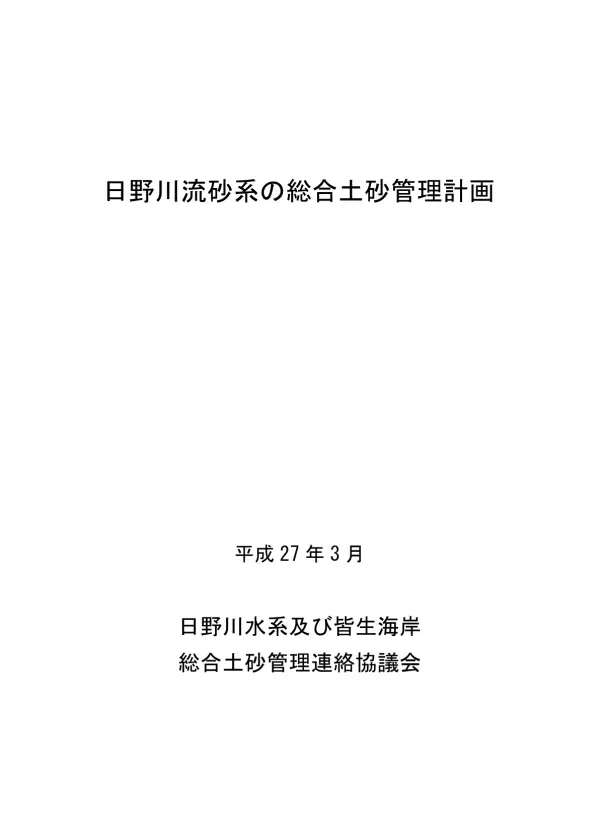
日野川流砂系総合土砂管理計画
文書情報
| 学校 | 鳥取県 (Tottori Prefecture)関係機関 |
| 専攻 | 土砂工学, 河川工学, 海岸工学 |
| 場所 | 鳥取県 (Tottori Prefecture) |
| 文書タイプ | 報告書 (Report), 計画書 (Plan) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 6.90 MB |
概要
I.日野川流砂系の現状と課題 Current Situation and Challenges of the Hino River Sediment System
鳥取県日野川流砂系では、大正時代後期に【鉄穴流し】の終焉以降、上流からの土砂供給減少により【海岸侵食】が深刻な問題となっています。特に【皆生海岸】では約300mもの砂浜後退が発生。昭和初期からの護岸工事や【突堤】、【離岸堤】、【人工リーフ】等の整備、そして【サンドリサイクル】などの対策が実施されてきましたが、依然として侵食は進行しており、沖合侵食による施設の損傷も課題です。 【大山】の解体期による土砂流出、砂利採取の禁止、ダム建設なども、河床低下や河口部への土砂供給減少に影響を与えています。これらの問題は個別に解決策が講じられてきましたが、【日野川流砂系】全体を捉えた総合的な【土砂管理】が不可欠となっています。
1. 鉄穴流しの終焉と海岸侵食の開始
日野川流砂系では、かつてたたら製鉄に伴う鉄穴流しが行われ、白砂青松の海岸が形成されていました。しかし、大正末期の鉄穴流しの終焉後、上流からの土砂供給が減少。その結果、秋季から冬季の波浪による海岸侵食が激しくなり、皆生海岸では約300mもの砂浜後退という深刻な事態が発生しました。この侵食に対処するため、鳥取県は昭和8年から様々な対策工事を開始しましたが、初期の護岸工事は数年で崩壊するなど、効果的な対策には至らず、皆生温泉は危機的な状況に陥りました。昭和22年には鳥取県漂砂対策協議会が発足し、昭和34年にかけて突堤群や護岸の建設が行われましたが、台風などの影響で被害を受け、継続的な改修や対策工事が求められる状況が続きました。昭和35年には全国で最初の直轄海岸工事区域に指定され、緩傾斜護岸、離岸堤、人工リーフの整備、そしてサンドリサイクルといった海岸保全事業が実施されるようになりました。これらの事業は海岸侵食の抑制に一定の効果を上げていますが、護岸の構造物下部や沖合では依然として侵食が進行し、離岸堤の先端部の洗掘や消波ブロックの沈下などの問題も発生しており、更なる対策が必要とされています。鉄穴流しの終焉が、この一連の海岸侵食問題の始まりであり、上流からの土砂供給の減少がその根本原因であることが示されています。
2. 大山山系の土砂流出と砂防事業
日野川流域には、解体期を迎えている大山が存在し、豪雨時にはしばしば土砂流出が発生しています。この問題に対処するため、鳥取県は昭和7年から大山山系の砂防事業に着手し、昭和49年には大山7渓流を直轄化。砂防堰堤等の整備により土砂災害の防止に努めてきました。大山山系以外にも鳥取県による砂防事業が実施されており、H24年度末までに流域全体で376基の砂防堰堤が整備されています。しかし、これらの砂防堰堤は土砂災害の防止に貢献する一方で、下流河道の河床低下や海域への土砂供給の減少をもたらすという問題点も抱えています。このため、直轄砂防事業では平成6年度から、砂防堰堤の堆砂容量の確保と平常時の下流域への土砂供給を目的として、透過型砂防堰堤の整備・改良を進めています。加えて、昭和15年以降、水利用や洪水調節のために6基の貯水ダムが建設されました。これらのダムでは現状では想定を下回る堆砂量ですが、将来的な河道断面の適切な維持管理が必要となるでしょう。大山からの土砂流出と、砂防堰堤建設による下流への土砂供給減少という相反する問題が、日野川流砂系の現状を複雑にしています。
3. 砂利採取禁止と河床変動
昭和48年までの砂利採取は、日野川河床の低下に大きく寄与しました。戦後の建設需要の高まりとともに、日野川での砂利採取量は昭和20年代から昭和40年代にかけて急激に増加しました。年間3万㎥から10万㎥以上にまで達した砂利採取は、鉄穴流しの終焉後減少した土砂供給と相まって、河床の低下を加速させました。砂利採取の禁止後、河床変動量は日野川堰改築工事による減少を除いて近年は概ね安定していますが、昭和40年代後半からは樹木繁茂による砂州の固定化と土砂の捕捉が進み、澪筋の局所洗掘が発生するようになりました。この局所洗掘は、海岸への土砂供給を減少させる要因の一つとなっています。砂利採取という人為的な影響と、自然現象である樹木の繁茂が複雑に絡み合い、河床変動や土砂供給量に影響を与えていることが分かります。鉄穴流し時代の大量の土砂供給とは異なり、現在の状況では、河川からの土砂供給を増加させることが、海岸侵食対策の重要な課題となっています。
4. 総合的な土砂管理の必要性と取り組み
日野川流砂系では、山地部の土砂流出、河道部の局所洗掘、河道内樹木の繁茂、そして海岸侵食など、様々な土砂関連の問題が複雑に絡み合っています。個々の問題への対策だけでは不十分であり、流砂系全体を捉えた総合的な土砂管理が不可欠です。そのため、鳥取県では平成13年に策定された「鳥取県沿岸海岸保全基本計画」を上位計画とし、山地から海岸までの流砂系全体を考慮した総合的な土砂管理を目指しています。平成20年8月には「鳥取県西部海岸管理協議会」が設立され、平成21年3月には「日野川水系河川整備基本方針」が策定され、海岸線を維持しつつ日野川からの土砂供給の増加を目指す目標が掲げられました。この目標達成のため、平成23年9月には関係機関からなる「日野川水系及び皆生海岸総合土砂管理連絡協議会」が発足し、流砂系の現状と課題の共有、対策についての議論が行われています。本書は、この連絡協議会の成果をまとめた「日野川流砂系の総合土砂管理計画」です。個別の対策ではなく、関係機関の連携による総合的な土砂管理の必要性が強く認識されています。
II.土砂動態の実態把握とシミュレーションモデル Understanding Sediment Dynamics and Simulation Models
本計画では、既存データ(横断測量、河床材料調査等)と【流砂量観測】、航空レーザ測量等の新たな手法を用いて【日野川流砂系】の土砂動態を詳細に分析しました。特に【海浜構成材料】(花崗岩質砂)に着目し、その挙動を解明。【流域土砂動態解析モデル】と【一次元河床変動計算モデル】を構築し、山地から河口までの土砂移動をシミュレーション。昭和60年から平成24年までの検証によりモデルの信頼性を確認しました。しかし、現状のデータと技術では、土砂動態を完全に解明するには至っていません。
1. 土砂動態の実態把握 既存データと新たな手法の活用
日野川流砂系の土砂動態の実態解明のため、本計画では既存データと新たな手法を組み合わせたアプローチが採られました。既存データとしては、長年にわたる定期横断測量や河床材料調査で蓄積されたデータが最大限に活用されました。これに加え、より詳細な土砂動態の分析を行うために、流砂量観測や航空レーザ測量といった最新の手法が導入されました。特に、海岸侵食問題の深刻さを考慮し、海浜構成材料(粒径0.1mm~2.0mmの花崗岩質砂)に着目した分析が行われています。これらの多様なデータと分析手法によって、日野川流砂系の土砂移動の実態をより正確に把握しようと試みられています。既存の調査データの分析に加え、より精度の高い最新の計測技術を導入することで、従来よりも詳細な土砂動態の把握を目指している点が重要です。この多角的なアプローチにより、日野川流砂系の複雑な土砂移動現象をより深く理解するための基盤が構築されています。
2. 土砂移動シミュレーションモデルの構築と検証
山地から河口までの流域全体を対象とした土砂移動をシミュレーションするため、流域土砂動態解析モデルと一次元河床変動計算モデルが構築されました。山地地域には流域土砂動態解析モデル、平野部(菅沢ダム下流河道、法勝寺川直轄管理区間)には一次元河床変動計算モデルがそれぞれ適用され、これらを組み合わせることで流域全体の土砂移動を解析する統合的なモデルが完成しました。河道内の植生繁茂による土砂堆積の影響を考慮するため、一次元河床変動計算モデルには植生消長モデルが組み込まれています。モデルの信頼性を確認するため、昭和60年初頭から平成24年末までの28年間のデータを用いた検証計算が行われ、モデルの精度が確認されています。しかし、長期間にわたる土砂移動現象の複雑さや、データの量と質、現在のシミュレーション技術の限界から、日野川流砂系の土砂動態を完全に解明するには至っていません。このモデルは、現時点で得られる情報を最大限に活用したものであり、今後のデータ蓄積と技術進歩によって、モデルの精度向上とさらなる土砂動態の解明が期待されます。
III.流砂系を構成する粒径集団と土砂供給源の変化 Grain Size Distribution and Changes in Sediment Sources
海岸域を構成する粒径は、日野川河口部を除き、0.1~2.0mmの砂が中心で、中砂が大部分を占めます。皆生海岸では西向きの【沿岸漂砂】が卓越し、西側へ向かうほど粒径が細かくなります。土砂供給源は、【鉄穴流し】時代は日野川上流域の花崗岩系白色砂が主体でしたが、現在は【大山】流域の安山岩系黒色砂の割合が増加しています。【大山】からの土砂流出は依然として課題であり、大規模な崩壊も発生しています。
1. 海岸域における粒径分布と沿岸漂砂
日野川河口部を除く海岸域では、粒径0.1~2.0mmの砂が主体であり、その中でも中砂(0.25~0.85mm)が大部分を占めています。皆生工区から両三柳工区にかけては粗砂(0.85~2.0mm)の割合がやや高く、西側の境港工区へ向かうにつれて細砂(0.075~0.25mm)の割合が増加し、粒径が細かくなる傾向が見られます。これは、皆生海岸において西向きの沿岸漂砂が卓越しており、粒径の細かい砂ほど移動しやすいという沿岸漂砂の特徴を反映していると考えられます。つまり、日野川河口部から西側へ移動するにつれて、より細かい粒径の砂が堆積する傾向があることを示しています。この粒径分布は、海岸侵食対策において、供給する土砂の粒径を適切に選択する上で重要な要素となります。特に、サンドリサイクルによる養浜においては、この粒径分布を考慮した対策が求められます。
2. 大山流域からの土砂供給と土砂組成の変化
日野川流域には、解体期を迎えている大山が存在します。大山山頂部付近には大規模な崩壊地があり、山麓斜面には侵食に弱い火山堆積物が厚く堆積しているため、豪雨時にはしばしば土砂流出が発生しています。大山環状道路は、大山源頭部の崩壊によって頻繁に通行止めになるほど、土砂流出の危険性が高いです。平成23年9月洪水では、斜面崩壊、護岸崩落、渓流からの氾濫が発生するなど、土砂災害の危険性が改めて認識されました。鉄穴流しの終焉後、主要な土砂供給源は上流域から大山流域へとシフトしています。鉄穴流し時代には、日野川上流域に広く分布する花崗岩系が主体の白色砂が供給されていましたが、現在は大山流域に広く分布する安山岩系(大山火山岩類)が主体の黒色砂が大部分を占めるようになっています。ただし、皆生海岸を構成する土砂の約20%は安山岩系の土砂であり、大山流域からの土砂も海岸線の維持に一定の貢献をしていると考えられます。土砂供給源の変化は、海岸侵食対策において重要な要素であり、土砂の供給量と組成の両方を考慮した対策が必要であることを示しています。
IV.河道域 河口域 海岸域の課題と対策 Challenges and Countermeasures in River Channel Estuary and Coastal Areas
【河道域】では、砂利採取禁止後の河床変動は概ね安定していますが、局所洗掘や樹木繁茂による河積阻害が問題です。【河口域】には発達した【河口砂州】があり、維持掘削が必要。その土砂は養浜材料として期待されます。【海岸域】では、【皆生海岸】の【海岸侵食】が最も深刻であり、継続的な【サンドリサイクル】等の対策が実施されていますが、侵食傾向は続いています。特に、細かい粒径の砂を使用するサンドリサイクルでは、歩留まりが悪く、粒径の粗い土砂の確保が課題です。 日野川からの土砂供給量の増加が、海岸侵食対策の鍵となります。
1. 河道域 河床低下と局所洗掘の問題
日野川の河道域では、戦後、建設資材需要の高まりから昭和48年まで盛んに行われていた砂利採取が、河床の低下に大きく影響を与えました。昭和20年代には年間3万㎥、昭和30年代には4~5万㎥、昭和40年代には5~10万㎥もの砂利が採取され、鉄穴流しの終焉による土砂供給減少と相まって、河床低下が顕著に進行しました。砂利採取禁止後は、日野川堰改築工事による減少を除けば、河床変動量は概ね安定していますが、昭和40年代後半からは、河道内の樹木繁茂による砂州の固定化と土砂の捕捉が顕著になり、澪筋の局所洗掘が進行しています。この局所洗掘は、下流への土砂供給を阻害し、海岸侵食を悪化させる可能性があります。河道内の植生管理や、局所洗掘対策が喫緊の課題となっています。また、洪水時の安全性を確保するため、河道の流下能力の維持と局所洗掘による災害防止策も必要不可欠です。現状では河床高は概ね安定していますが、砂州の樹林化と澪筋部の局所洗掘という新たな問題が発生し、海岸への土砂供給量の減少に繋がっています。
2. 河口域 河口砂州の維持管理と養浜への活用
日野川河口部には発達した河口砂州が存在し、洪水によって洗い流されても数ヶ月で復元するほど安定した地形を形成しています。しかし、内水被害防止のためには継続的な維持掘削が必要となります。この河口砂州の堆積土砂は、海浜構成材料よりもやや粗く侵食されにくい性質を持つため、海岸侵食部の養浜材料として活用できる可能性を秘めています。洪水時のフラッシュ後、数ヶ月で河口砂州が復元する様子は写真測量で確認されています。また、深浅測量の結果からは、洪水直後に河口部前面に堆積した土砂の一部は河口砂州に戻りますが、大部分は沿岸漂砂として移動していくことが示唆されています。河口砂州の維持管理と、その土砂を有効に活用した海岸侵食対策の両面からの検討が不可欠です。河口砂州の堆積土砂は、海岸侵食対策に役立つ可能性のある貴重な資源である一方、継続的な維持管理が必要な課題を抱えている点が重要です。
3. 海岸域 海岸侵食の現状と対策の課題
皆生海岸では、鉄穴流しの終焉以降、海岸侵食が深刻な問題となっています。大正時代後期から海岸線の後退が始まり、秋季から冬季の波浪により侵食は激化し、現在の護岸に至るまで最大で約300mの砂浜が後退したと言われています。昭和8年の護岸工事は数年で崩壊し、その後も突堤群や護岸の建設、サンドリサイクルなどの対策が続けられてきましたが、皆生工区、両三柳工区では依然として侵食が進行しています。特に、沖合侵食による離岸堤先端部の侵食や消波ブロックの沈下などが問題となっています。富益工区では昭和40年代から離岸堤整備を中心とした海岸保全が行われ、汀線の維持に努められていますが、平成6年以降は夜見・富益工区~境港工区でサンドリサイクルが実施されています。しかし、サンドリサイクルで用いられる砂は細かい粒径成分であり、対策後の歩留まりが悪く、粗い砂の確保が課題となっています。そのため、河口部の粗い砂の活用や日野川からの土砂供給量の増加が、海岸侵食対策の重要な課題です。現状の対策では、海岸侵食の進行を完全に抑制できていない点が大きな課題となっています。
V.総合土砂管理計画と今後の取り組み Comprehensive Sediment Management Plan and Future Initiatives
個別の対策では不十分なため、平成20年に設立された【鳥取県西部海岸管理協議会】を基盤に、関係機関が連携した総合的な【土砂管理】を進めています。【日野川水系及び皆生海岸総合土砂管理連絡協議会】では、各領域(ダム域、河道域、河口域、海岸域)における目標を設定。【透過型砂防堰堤】の整備・改良、ダム堆砂の有効活用、河道掘削土の有効利用、そして【サンドリサイクル】の継続的な実施など、多角的な対策を推進していきます。 今後もモニタリングを継続し、計画の見直しを行いながら、PDCAサイクルに基づいた持続可能な【土砂管理】を目指します。
1. 総合土砂管理計画の策定 関係機関の連携による取り組み
日野川流砂系における土砂問題は、個々の対策だけでは不十分であり、流砂系全体を考慮した総合的な土砂管理が必要不可欠です。そのため、鳥取県では平成13年に策定した「鳥取県沿岸海岸保全基本計画」を上位計画とし、山地から海岸までを一体的に捉えた、全国初の取り組みである「鳥取県沿岸の総合的な土砂管理ガイドライン」に基づいて、関係機関が連携した総合的な土砂管理を進めています。平成20年8月には「鳥取県西部海岸管理協議会」が設立され、平成23年9月には関係機関からなる「日野川水系及び皆生海岸総合土砂管理連絡協議会」が発足しました。連絡協議会では、日野川流砂系の現状と課題を共有し、目指すべき姿や土砂の流れの改善に向けた対策について議論が行われ、関係機関が連携して総合的に土砂動態の改善を図っていくことを確認しました。本書は、この連絡協議会の成果を「日野川流砂系の総合土砂管理計画」としてとりまとめたものです。この計画は、関係機関の連携と、流砂系全体の土砂動態を考慮した、長期的な視点に立った土砂管理を目指しています。
2. 各領域における土砂管理対策 ダム域 河道域 河口域 海岸域
総合土砂管理計画では、ダム域、河道域、河口域、海岸域のそれぞれの領域において、具体的な土砂管理対策が検討されています。ダム域では、適正なダム機能を維持しつつ、下流への土砂供給の増加・回復を目指します。河道域では、洪水に対する安全性を確保(流下能力の維持、局所洗掘による災害防止)するとともに、安定的に下流へ土砂を移動させることを目標としています。河口域では、河口閉塞を防ぎ、河口砂州の適切な高さを維持することで、必要河積を確保することが課題です。海岸域では、海岸侵食の防止、汀線位置の維持、港湾や漁港の埋没防止といった課題への対策が中心となります。特に、皆生海岸の侵食対策として、サンドリサイクルが継続的に実施されていますが、使用砂の粒径が細かいため、歩留まりが悪く、粗い砂の確保が課題となっています。各領域における対策は、流砂系全体の土砂動態を考慮し、関係機関が連携して実施されることが重要です。 土砂は有限な資源であることを認識し、各機関の連携による効率的な対策が求められます。
3. 今後のモニタリングと計画の見直し PDCAサイクルによる継続的な管理
総合土砂管理計画は、策定後も継続的にモニタリングを行い、対策効果の評価と計画の見直しを繰り返すPDCAサイクル型の管理計画として運用されます。連絡協議会は定期的に開催され、土砂に関する情報共有を図り、毎年1回程度の頻度で情報交換が行われます。概ね5年サイクルで事後評価を行い、今後の目標設定を見直します。必要に応じて、広報誌やインターネットなどを活用した情報公開を行い、地域住民への理解と協力を得ながら、継続的な土砂管理体制を構築していくことが目指されています。土砂管理対策の効果や影響は、治水、利水、環境といった幅広い観点から検討する必要があり、現時点の技術的知見に基づく検討成果には課題も残されています。そのため、今後も土砂移動のモニタリングを継続し、データの蓄積を図り、得られた知見に応じて計画の見直しを適宜行っていくことになります。長期的な視点に立った継続的なモニタリングと計画の見直しによって、効果的で持続可能な土砂管理体制の構築を目指します。
