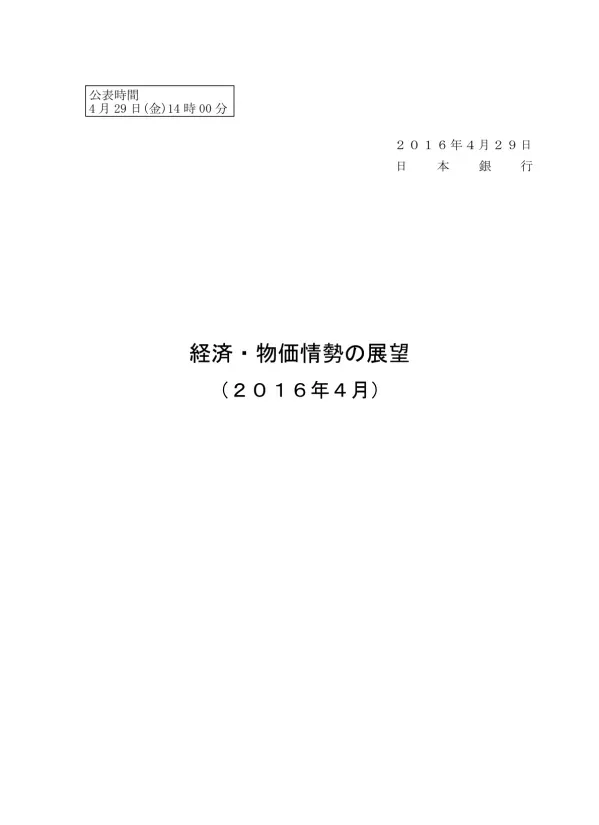
日銀経済・物価展望:2016年4月
文書情報
| 著者 | 日本銀行 |
| 専攻 | 経済学 |
| 会社 | 日本銀行 |
| 場所 | 東京 |
| 文書タイプ | 経済報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 3.75 MB |
概要
I.日本の経済 物価の現状と見通し 2016年度以降
日本経済は、新興国経済の減速の影響を受けながらも緩やかな回復基調にあるものの、輸出・生産面には鈍さが残る。【景気】は基調として緩やかな拡大が見込まれるが、輸出は足元で持ち直しが一服しており、個人消費は底堅いが一部に弱めの動きも。設備投資は企業収益の高水準を背景に緩やかに増加。住宅投資と公共投資は減少傾向。鉱工業生産は横ばい圏内。【消費者物価(除く生鮮食品)】の前年比は0%程度と低迷しているが、物価の基調は着実に高まり、エネルギー価格下落の影響が剥落していくにつれて、2%の【物価安定の目標】に向けて上昇すると予想される。2017年度中には2%程度に達すると見込まれ、その後は平均的に2%程度で推移すると予想される。
1. わが国の経済 物価の現状
2016年度時点の日本経済は、新興国経済の減速の影響を受け、輸出と生産面で鈍化が見られるものの、緩やかな回復基調にあると分析されています。海外経済は緩やかな成長を続けるものの、新興国を中心に減速傾向にあり、日本の輸出も持ち直しが一服している状況です。国内需要面では、企業収益の高水準を背景に設備投資は緩やかな増加基調を示しています。個人消費は雇用・所得環境の改善により底堅く推移していますが、一部に弱めの動きも確認されます。住宅投資と公共投資は持ち直しが一服し、減少傾向にあります。これらの内外需要を反映して、鉱工業生産は横ばい圏内の動きが続いており、足元では地震の影響も確認されています。企業の業況感は良好な水準を維持しているものの、新興国経済の減速の影響から慎重化している様子がうかがえます。金融環境はきわめて緩和した状態が続いており、物価面では消費者物価(除く生鮮食品)の前年比が0%程度と低迷しています。予想物価上昇率は、長期的な視点では上昇傾向にあるものの、直近では弱含んでいます。このセクションでは、マクロ経済指標を中心に、日本経済の現状を詳細に分析し、今後の見通しへの影響を検討しています。
2. 消費者物価 除く生鮮食品 の動向と物価安定目標
消費者物価(除く生鮮食品)の前年比は、エネルギー価格の下落により、当面は0%程度で推移すると見込まれています。しかし、物価の基調は着実に高まっており、2%の物価安定目標に向けて上昇率を高めていくと予想されています。原油価格が現状程度の水準から緩やかに上昇していくことを前提とすると、エネルギー価格の寄与度は、現在のマイナス1%強から次第に剥落していくものの、2017年度初めまではマイナス寄与が残ると試算されています。この前提に基づくと、消費者物価の前年比が2%程度に達する時期は、2017年度中になると予想され、その後は平均的に2%程度で推移すると見込まれています。このセクションでは、消費者物価の現状と将来予測を、エネルギー価格の動向との関連性を含めて詳細に分析しています。特に、物価安定目標達成までの時間軸と、その達成後の物価推移予想が重要な論点となっています。エネルギー価格の変動が消費者物価に及ぼす影響の定量的な試算も含まれており、政策決定に重要な情報となっています。
3. わが国の経済 物価の中心的な見通し 2016年度以降の展望
2016年度以降の日本経済は、当面輸出・生産面での鈍さが残ると予想されますが、家計と企業の所得から支出への好循環が持続することで、国内需要が増加基調をたどり、輸出も新興国経済の回復を背景に緩やかに増加すると見込まれています。このため、日本経済は基調として緩やかに拡大すると予想されています。この見通しの背景には、日本銀行のマイナス金利政策の継続による緩和的な金融環境があり、実質金利はマイナスで推移すると想定されています。新興国経済の減速からの脱却、企業収益の増益基調の継続、雇用・所得環境の改善、エネルギー価格下落による実質所得の押し上げ効果なども、経済成長を後押しする要因として挙げられています。さらに、2017年4月の消費税率引き上げ前の駆け込み需要も、国内民間需要を押し上げると予想されています。このセクションでは、将来の経済成長率や、その要因となる主要経済指標の動向を詳細に予測しており、政策決定者にとって重要な情報源となっています。特に、金融政策、消費税率変更、新興国経済の動向が経済予測に与える影響が詳細に分析されています。
II.経済見通しの背景 金融政策と需給バランス
経済見通しの背景には、日本銀行による【マイナス金利付き量的・質的金融緩和】の継続による緩和的な金融環境と、新興国経済の回復期待がある。【金融政策】は景気に刺激的に作用すると想定。マクロ的な需給バランスは、新興国経済の減速を背景に横這い圏内だが、労働需給の引き締まりと輸出・生産の持ち直しにより、2016年度後半以降は改善が見込まれる。消費税率引き上げ前の駆け込み需要とその反動も考慮が必要。【賃金】の上昇と物価上昇率の緩やかな高まりというメカニズムは着実に作用していると考えられるが、企業収益の高水準と比較して賃金の改善が鈍い点には留意が必要。
1. 金融政策の現状と経済への影響
経済見通しの重要な前提として、日本銀行による『マイナス金利付き量的・質的金融緩和』の継続が挙げられています。この金融政策により、見通し期間を通じて実質金利はマイナスで推移すると想定され、金融環境はきわめて緩和した状態が続くものとされています。この緩和的な金融環境は、景気に対して刺激的に作用すると予想されており、設備投資の増加や個人消費の底堅い推移を支える重要な要因となると考えられています。特に、実質金利の一段の低下効果は、設備投資の増加基調を継続させる上で大きな役割を果たすと分析されています。ただし、長期的な視点から金融面の不均衡についても検討されており、現時点では資産市場や金融機関行動において過度な強気化は観察されていませんが、低金利による金融機関収益の下押しや政府債務残高の累増といったリスク要因についても言及されています。このセクションでは、日本銀行の金融政策が経済全体、特に設備投資や個人消費に与える影響を詳細に分析しています。また、金融政策の潜在的なリスクについても考察し、経済予測の不確実性を示唆しています。
2. マクロ的な需給バランスと物価上昇率
物価上昇率を規定する主要因として、マクロ的な需給バランスが分析されています。労働や設備の稼働状況を表すこのバランスは、新興国経済の減速を背景に製造業の設備稼働率の改善が遅れる一方、労働需給は引き締まっているため、全体として横這い圏内の動きとなっています。しかし、今後失業率が緩やかに低下するなど、労働需給の引き締まりが続けば、パート時給を含む賃金への上昇圧力が強まり、設備稼働率も輸出・生産の持ち直しに伴い上昇すると予想されています。そのため、マクロ的な需給バランスは、2016年度後半以降、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要も加わり、プラス幅を拡大していくと見込まれています。 市場の予想物価上昇率は弱含んでいるものの、企業は前向きな価格設定スタンスを維持し、消費者も価格改定を受容している状況です。生鮮食品とエネルギーを除く消費者物価の前年比は30ヶ月連続でプラスであり、賃金上昇を伴う物価上昇メカニズムは着実に作用していると考えられています。しかし、企業収益の高水準と比較して賃金改善が鈍い点、労働分配率の低下傾向は、今後の物価上昇への影響について不確実性を残しています。このセクションでは、需給ギャップの現状と将来予測、賃金上昇と物価上昇の関係、そしてそれらが経済見通しに及ぼす影響を詳細に分析しています。
3. その他の経済見通しに影響する要因
経済見通しには、消費税率引き上げの影響、企業・家計の中長期的な成長期待、国際金融資本市場の不安定性なども影響すると分析されています。消費税率引き上げは、駆け込み需要とその反動、実質所得減少など、消費者マインドや雇用・所得環境、物価に多様な影響を与えます。企業・家計の成長期待は、規制・制度改革、イノベーション、雇用・所得環境などによって左右され、企業の潤沢なキャッシュフローの活用方法も重要な要素となります。国際金融資本市場の不安定性は、企業のコンフィデンスに影響を与える可能性があり、米国経済動向、欧州債務問題、地政学的リスクなどもリスク要因として挙げられています。これらの要因が顕在化した場合、経済の上下振れが生じ、物価にも相応の影響が及ぶと予想されます。特に、企業や家計の中長期的な予想物価上昇率の動向は重要であり、賃金上昇を伴う物価上昇率の高まりが、人々の予想物価上昇率の上昇、ひいては「物価安定の目標」である2%への収斂に繋がると想定されています。しかし、エネルギー価格の低迷が長期化する場合は、賃金や予想物価の上昇ペースへの影響に不確実性があります。このセクションは、金融政策や需給バランス以外の、経済予測における不確実性要因を網羅的に分析し、将来予測におけるリスクを明確にしています。
III.主要支出項目の動向 個人消費 設備投資 住宅投資
【個人消費】は、雇用・所得環境の改善、エネルギー価格下落、年金給付金支給などを背景に底堅く推移するものの、消費税率引き上げの影響を考慮すべき。2016年度は駆け込み需要、2017年度は反動減、2018年度は再び増加すると予想。【設備投資】は、高水準の企業収益、緩和的な金融環境、成長期待を背景に緩やかな増加基調が続くと見込まれる。【住宅投資】は、雇用・所得環境の改善と低金利を背景に持ち直すと予想される。
1. 個人消費の動向と将来展望
個人消費は、雇用・所得環境の着実な改善、エネルギー価格の下落、年金生活者向け給付金の支給などを背景に、底堅く推移しているものの、一部に弱めの動きも見られます。将来展望としては、消費税率引き上げの影響が大きく、2016年度は年初来の株価下落による負の資産効果があるものの、雇用者所得の増加、臨時給付金、エネルギー価格下落による実質可処分所得の増加、下期を中心とした消費税率引き上げ前の駆け込み需要拡大により、高めの伸びが期待されます。しかし、2017年度は駆け込み需要の反動減と実質所得減少により減少に転じると予想され、2018年度には実質可処分所得の増加に伴い再び増加すると見込まれています。消費性向は消費税率引き上げによる影響を均せば概ね横ばい推移すると予想されており、実質可処分所得の動きが個人消費の基調を決定づける重要な要素となっています。内閣府の消費総合指数や消費活動指数は横ばい圏内ですが、消費財総供給は緩やかに増加、小売店売上高は暖冬の影響や消費者マインドの慎重化、株価下落の影響を受けています。耐久消費財は乗用車にサプライチェーン問題の影響が見られますが、家電は横ばい、サービス消費は増加傾向です。
2. 設備投資の現状と将来予測 企業収益と金融環境の影響
設備投資は、企業収益の高水準を背景に緩やかな増加基調にあります。将来予測としては、高水準の企業収益、低金利・緩和的な貸出スタンスといった金融環境、期待成長率の改善などを背景に、緩やかな増加基調が続くと見込まれています。ただし、2016年度上期は海外経済の減速により、製造業大企業を中心に下押し圧力がかかると予想されます。設備投資計画は製造業を含め堅調で、GDPに近い全産業の設備投資計画は2015年度に前年比+7.3%と高い伸びを示し、2016年度計画も過去平均並みです。機械受注や建築着工・工事費予定額も増加基調です。しかし、一致指標である法人企業統計の設備投資は緩やかな増加傾向である一方で、資本財総供給は横ばい圏内です。これは、受注から出荷までのラグが長い機械投資案件の増加が原因と考えられます。資本ストック循環の観点から見ると、資本ストックは潜在成長率と同程度の期待成長率で緩やかに増加し、今後も緩和的な金融環境とオリンピック関連需要により、潜在成長率を若干上回るペースで蓄積されると見込まれています。
3. 住宅投資の現状と今後の見通し 雇用 所得環境と金融政策の影響
住宅投資は、マンション価格高騰による分譲需要の伸び悩みから持ち直しが一服している状況です。しかし、今後の見通しとしては、雇用・所得環境の着実な改善、消費税率引き上げ前の駆け込み需要、そしてマイナス金利付き量的・質的金融緩和導入による住宅ローン金利の低下が後押しとなり、再び持ち直していくと予想されています。マンション価格の高騰が分譲需要の伸び悩みに繋がっている点は、今後の住宅投資の動向を予測する上で重要な要素となります。雇用・所得環境の改善は、住宅購入意欲を高め、住宅ローン金利の低下は購入コストを抑制する効果が期待されます。消費税率引き上げ前の駆け込み需要も、住宅投資の増加に寄与する可能性があります。これらの要因が、住宅投資の回復を後押しすると考えられています。ただし、マンション価格の高騰やその他の市場要因が、この回復のペースに影響を与える可能性がある点には留意が必要です。
IV.物価の先行き エネルギー価格とインフレ期待
【消費者物価(除く生鮮食品)】の前年比は、エネルギー価格の下落の影響が次第に薄れ、需給ギャップの改善と【インフレ期待】の高まりを背景に、2%程度に向けて上昇率を高めていくと予想される。エネルギー価格のマイナス寄与は2016年度上期に-1%強であったが、2017年央には概ねゼロになると試算される。企業は前向きな価格設定スタンスを維持しており、消費者も価格改定を受容しているため、賃金上昇によるコスト増加が価格に転嫁されると考えられる。
1. エネルギー価格の動向と消費者物価への影響
消費者物価(除く生鮮食品)の前年比は、エネルギー価格の下落の影響を受け、当面0%程度で推移すると見込まれています。しかし、このエネルギー価格の下落の影響は一時的なものであり、原油価格が緩やかに上昇していくとの前提に基づくと、エネルギー価格の消費者物価へのマイナス寄与は次第に減少していくと予想されています。2017年度初めまではマイナス寄与が残ると試算されていますが、その後は、エネルギー価格の影響が薄れていくため、物価上昇率は高まっていくと予想されます。消費者物価全体へのエネルギー価格の影響度合いを定量的に示しており、エネルギー価格の動向が消費者物価の将来予測に及ぼす影響を具体的に分析しています。この分析は、将来の物価上昇率を正確に予測するために重要であり、エネルギー価格の変動が消費者物価に与える影響を理解する上で不可欠な情報です。エネルギー価格の変動は、消費者物価の変動幅に直接影響を与えるため、この分析は政策決定者にとって非常に重要な情報となります。
2. 需給ギャップとインフレ期待 物価上昇メカニズムの分析
物価上昇率を規定する要因として、需給ギャップが挙げられています。現在、需給ギャップはゼロ%近傍で横ばい圏内にありますが、2016年度後半には輸出・生産面の改善や消費税率引き上げ前の駆け込み需要によりプラス幅を拡大すると予想されています。しかし、2017年度上期には駆け込み需要の反動減で一旦悪化するものの、同下期以降は再びプラス幅を拡大すると見込まれています。この需給ギャップの改善は、物価上昇への圧力となります。さらに、企業はエネルギー価格下落にもかかわらず前向きな価格設定スタンスを維持しており、消費者も雇用・所得環境の改善を受けて価格改定を受容していることから、賃金の上昇を伴いつつ物価上昇率が緩やかに高まっていくメカニズムが着実に作用していると分析されています。ただし、企業収益の高水準と比較して賃金の改善が鈍い点、労働分配率の低下傾向には留意が必要であり、これらがインフレ期待や実際の物価上昇率にどう影響するか、不確実性も残されています。このセクションでは、需給ギャップとインフレ期待の動向が、物価上昇率にどのように影響するかを詳細に分析しています。賃金上昇と物価上昇の関係も重要な論点であり、日本の物価上昇メカニズムの理解に役立つ重要な知見が提示されています。
3. 物価上昇率の将来予測とリスク要因 2 目標達成への展望
消費税率引き上げの影響を除き、消費者物価(除く生鮮食品・エネルギー)の前年比は現状程度のプラス幅を維持した後、需給ギャップの改善とインフレ期待の高まりを背景に、賃金上昇によるコスト増がサービス価格を含む幅広い価格に転嫁されることで、2%程度に向けて上昇率を高めていくと予想されています。消費者物価(除く生鮮食品)の前年比は2016年度上期は0%程度ですが、エネルギー価格のマイナス寄与が減少することで、上昇に転じると予想されています。しかし、企業や家計の中長期的な予想物価上昇率、エネルギー価格の低迷の長期化などは、賃金や予想物価の上昇ペースに影響を与える不確実性要因として挙げられています。企業の本年度における価格改定、賃金の動向、消費者の値上げに対するスタンスが、今後の物価上昇率に大きく影響すると考えられます。このセクションでは、2%の物価安定目標達成に向けた具体的な物価上昇率の将来予測を示し、その予測の根拠となる経済指標や要因を詳細に説明しています。同時に、物価上昇率予測における不確実性要因についても言及し、将来予測の精度を高めるための課題を示唆しています。
V.金融市場動向とリスク要因
【金融市場】は不安定な動きが続く可能性があり、リスク要因としては、海外経済(特に新興国経済)、為替円高、株価下落、米国経済動向、欧州の債務問題、地政学的リスクなどが挙げられる。長期金利は日本銀行の【金融政策】により低水準で推移する見込み。企業の資金需要は増加しているものの、金融機関の貸出姿勢は積極的である。政府債務残高の累増には留意が必要。
1. 国際金融資本市場の動向とリスク要因
国際金融資本市場は不安定な動きを続けており、企業コンフィデンスなどに影響を与える可能性があるため、継続的な警戒が必要です。2月中旬までは原油価格の下落や中国経済の不透明感からリスク回避姿勢が強まりましたが、その後は原油価格の上昇、中国当局の政策に対する不透明感の後退、米国の利上げペースの緩和予想などから、幾分落ち着きを取り戻しています。しかし、新興国経済を中心とした海外経済の下振れ、為替円高、株価下落といった金融市場の不安定な動きは、日本経済に影響を与える可能性が依然として高く、リスク要因として認識されています。 米国経済の動向とその金融政策、欧州の債務問題の展開、景気・物価のモメンタム、地政学的リスクなども、国際金融資本市場の動向、ひいては日本経済に影響を与える可能性のあるリスク要因として挙げられています。これらのリスク要因は、経済の上下振れを引き起こし、物価にも影響を与える可能性があるため、継続的な監視と分析が重要です。特に、海外経済の動向は、日本の輸出や企業収益に大きな影響を与えるため、注意深く観察する必要があります。
2. 金利動向と金融機関の状況
長期金利(10年物国債利回り)は、日本銀行のマイナス金利付き量的・質的金融緩和政策の影響で低下し、マイナス領域で推移しています。米国では、一時的な上昇の後、再び低下傾向にあります。ドイツでは、ECBによる追加緩和を背景に低下傾向です。一方、円を見合いとしたドル調達プレミアムは需給環境のタイト化から高めの水準を維持していますが、邦銀の外貨調達に量的な制約は生じていません。企業の資金需要は運転資金、企業買収、設備投資などにおいて増加しており、銀行貸出は増加傾向にあります。大企業・中小企業ともに前年比プラスを維持していますが、CP・社債合計の発行残高はマイナスです。CPは金利低下により発行環境は改善していますが、資源関連企業の運転資金調達の減少によりマイナスが続いており、社債も金利低下と発行体の手元資金の潤沢さ、銀行の積極的な貸出姿勢からマイナスとなっています。このセクションでは、金利動向、金融機関の貸出状況、企業の資金調達状況などを分析し、日本の金融市場の現状とリスクを評価しています。特に、金融政策と金融市場の動向の関連性、政府債務残高の増加が金融機関に及ぼす影響などが重要な論点となっています。
3. 株価と不動産市場の動向
株価は、投資家のリスク回避姿勢の強まりを受けて2月中頃に大きく下落しましたが、その後は海外株価の上昇などを受けて上昇に転じています。不動産投資信託(J-REIT)市場では、長期金利の低下などを背景にJ-REIT価格は上昇しています。これらの市場動向は、投資家のリスク選好度や市場心理を反映しており、経済の将来予測に重要な情報を提供しています。 しかし、国際金融資本市場の不安定性や、海外経済の減速、為替変動などは、株価や不動産市場に大きな影響を与える可能性があり、これらのリスク要因を継続的に監視する必要があります。特に、中国経済の動向や、米国による金融政策運営の変化は、国際金融市場に大きな影響を与え、日本の金融市場にも波及する可能性があります。このセクションでは、株価、J-REIT、そして国際金融市場の動向を分析し、今後の金融市場におけるリスクと機会を評価しています。これらの市場動向は、日本の経済全体に影響を与える可能性があるため、この分析は政策決定者にとって非常に重要な情報源となります。
