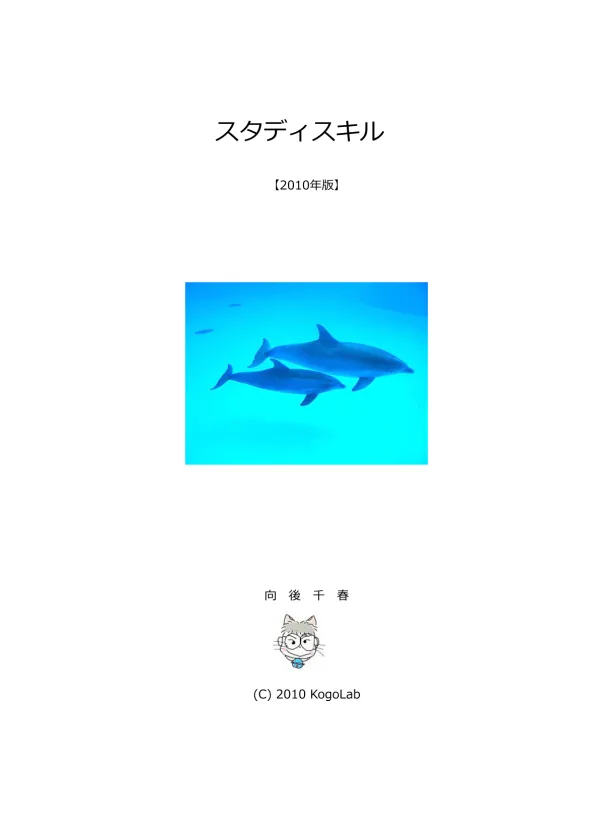
早稲田大学 スタディスキル入門
文書情報
| 著者 | 向後千春 |
| 学校 | 早稲田大学人間科学部 |
| 専攻 | 人間科学 |
| 文書タイプ | スタディスキルテキスト |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 8.37 MB |
概要
I.早稲田大学における効果的なeラーニングと学習方法
本資料は、早稲田大学人間科学部 eスクール 生と通学生に向けた、大学における効果的な学習方法を解説しています。特にオンデマンド授業 の活用、コースナビ を用いた学習管理、そしてアカデミックな文章 の書き方を重点的に説明しています。レポート作成 や論文引用、効果的なノートの取り方(コーネル式ノート など)といった実践的なスキル習得のための具体的な方法も提示しています。 タイムマネジメント の重要性と、先延ばし症候群 を克服するためのアドバイスも含まれています。オンラインツールとして、Gmail、Googleドキュメント、Dropbox、Evernote、Skype などが紹介されており、これらの活用が学習効率の向上に繋がることを示唆しています。約5万人の学生が利用する早稲田大学独自のLMSであるコースナビの有効活用が強調されています。
1. 早稲田大学独自の学習管理システム コースナビ
早稲田大学では、5万人規模の学生が利用する独自の学習管理システム(LMS)であるコースナビが導入されています。これは国内でも類を見ない規模のシステムであり、学生は履修登録、課題提出、テスト受験など、学習活動の全てをコースナビ上で行うことができます。コースナビを使いこなすことは、大学生活を円滑に送る上で必須と言えるでしょう。近年では、コースナビを活用した「フルオンデマンド授業」や、教室授業とオンデマンド授業を組み合わせた「ブレンド型授業」が増加しており、早稲田大学はeラーニングの先進的な取り組みを行っている大学の一つと言えます。 オンデマンド授業は、自分のペースで学習を進められる利点がありますが、一方で、先延ばし症候群に陥ることなく、時間管理能力を磨くことが求められます。 効率的な学習のために、コースナビの機能を熟知し、適切に活用することが重要です。
2. オンラインサービスの活用 学習環境の拡張
パソコンの故障やデータ損失のリスクを軽減するために、オンラインサービスの積極的な活用が推奨されています。具体的には、Googleドキュメントを用いたレポート作成、Evernoteによるメモ管理、Dropboxによるファイルのバックアップと共有などが挙げられます。Googleドキュメントは、Microsoft Office製品に代わる手軽な文書作成ツールとして利用でき、インターネット環境さえあれば、場所を選ばずに作業を継続できます。Evernoteは、テキストデータ、画像、音声データなど、様々な情報を一元管理できるため、学習内容の整理やアイデアの保存に役立ちます。Dropboxは、重要なファイルのバックアップや、複数のデバイス間でのデータ共有を容易にします。これらのサービスは無料である点が大きなメリットです。さらに、Gmailは容量が大きく迷惑メールフィルタリング機能も充実しているため、大学のメール管理に最適なツールと言えます。
3. 効果的な学習のための時間管理と学習方法
オンデマンド授業では、1科目あたり平均3時間(視聴90分、課題・復習90分)の学習時間を要します。週末に学習を集中させるのではなく、曜日ごとに学習科目を決め、毎日少しずつ学習を進めることが重要です。 集中力を維持するために、1日に長時間学習するよりも、短時間ずつ複数回に分けて学習する方が効率的です。特に課題やBBSへの投稿が求められる科目は、週の前半に視聴し、空き時間に課題に取り組む計画を立てることが推奨されています。 また、シラバスや教員への確認を通して試験やレポートの期日を確認し、スケジュールに組み込むことで、期日までに余裕を持って学習を進めることができます。社会人の場合は、仕事の都合で学習時間が変動する可能性があるため、早めの準備が重要です。 受講日誌を作成するなど、学習状況を記録し、モチベーションを維持する工夫も有効です。
4. 効果的なノートの取り方と学習内容の定着
大学授業では、90分間の長時間の講義が一般的です。退屈に感じることがありますが、授業はエンターテイメントではなく、集中力と論理的思考力を要するものです。効果的なノートの取り方として、コーネル式ノートが紹介されています。これは、ページを3つの領域に分割し、右側に講義の要点、左側に疑問点やコメント、下部にサマリーを書き込む方法です。この方法を用いることで、講義内容の理解度を高め、レポート作成の効率を向上させることができます。 箇条書きを用いることで講義内容を構造化し、全体像を把握しやすくなります。疑問点やコメントを記録することで、講義内容を深掘りし、レポート作成のアイデア出しに役立てることができます。授業後に行うサマリー作成は、講義内容の要点を簡潔にまとめる能力を養うのに役立ち、試験対策にも有効です。
II.オンラインサービスの活用による学習効率の向上
学習においては、様々なオンラインサービスの活用が推奨されています。 Googleドキュメント は、ワードやエクセル、パワーポイントの代替としてレポート作成などに利用できます。Evernote は、メモやアイデア、Webページ、画像などを一元管理するのに役立ちます。Dropbox はファイルのバックアップと共有に便利です。Skype は、オンラインでのディスカッションやゼミ、グループワークに有効です。これらの無料サービスを活用することで、場所やデバイスを選ばずに学習を進めることができます。 また、Gmail は、容量が大きく迷惑メールフィルタリング機能も優秀なため、大学生活でのメール管理に適しています。
1. 文書作成ツールとしてのGoogleドキュメント
レポート作成などの際に、Microsoft Office製品(Word、Excel、PowerPoint)の代わりにGoogleドキュメントを活用することを推奨しています。GoogleドキュメントはWebブラウザ上で文書、スプレッドシート、プレゼンテーションを作成できる無料サービスです。高額なMicrosoft Officeを購入する必要がなく、インターネットに接続できる環境であれば、どのパソコンからでも作業を継続できる利便性があります。Wordファイル提出が求められるレポートでも、Googleドキュメントで下書きを作成し、最終的にWordに変換するというワークフローが提案されています。これは、パソコンの故障やデータ消失のリスクを軽減する上で有効な方法です。
2. 情報整理 保存のためのEvernote
Evernoteは、様々な情報を一元的に管理できるオンラインサービスです。ちょっとしたアイデア、Webページのクリップ、画像、書きかけの原稿など、テキストデータ、画像データ、音声データといった多様な情報をまとめて保存・整理できます。日々の学習や研究において、多くのメモや資料を扱う学生にとって、Evernoteは非常に便利なツールと言えるでしょう。 情報を効率的に整理・管理することで、学習効率の向上や、レポート作成といった課題への取り組みをスムーズに行うことができます。様々なデータ形式に対応しているため、幅広い用途で使用可能です。
3. ファイルバックアップとデータ共有のためのDropbox
ノートパソコンでのファイル管理において、外付けハードディスクやUSBメモリへのバックアップは煩雑で、紛失リスクも伴います。そこで、オンラインストレージサービスであるDropboxの活用が提案されています。Dropboxを利用することで、重要なファイルをオンライン上に保存し、パソコンが故障した場合でもデータの損失を最小限に抑えることができます。 クラウドコンピューティングの概念に基づき、場所やパソコンを問わず、常に最新のファイルにアクセスできます。 Dropboxは、ファイルのバックアップだけでなく、共同作業やデータ共有にも役立ちます。パソコンのデータは、ハードディスクの故障などで突然消失する可能性があるため、Dropboxのようなオンラインストレージサービスを用いたバックアップは必須と言えるでしょう。
4. コミュニケーションツールとしてのSkype
Skypeはインターネットを利用した無料のテレビ電話サービスです。音声通話だけでなく、テキストチャット機能も備えており、学習に関する相談やグループでのディスカッション、ゼミ活動などにも活用できます。 テレビ電話機能に加え、テキストチャットやファイル転送機能も備えているため、単なる会話だけでなく、共同作業や情報共有にも利用できます。最大10名までの同時通話が可能なため、オンラインゼミなどにも適しています。音声通話の品質は回線速度に依存しますが、一般の電話よりもクリアで臨場感のある通話が可能です。Skypeを利用するには、公式サイトからアプリケーションをダウンロードしてインストールする必要があります。
5. その他のオンラインサービス GmailとGoogleグループ
メールサービスとしてGmailの利用が推奨されています。Yahoo!セカンドメールサービス終了以前から多くの人が利用しており、迷惑メールフィルタリングの精度や大容量(執筆時7GB)といった点がメリットとして挙げられています。Gmailアカウントを取得することで、大学生活におけるメール管理を効率的に行うことができます。 また、メーリングリストサービスとしてGoogleグループが紹介されています。多くの無料サービスが存在する中で、Googleグループは手軽に利用できる一つの選択肢です。ただし、メーリングリストへの返信方法には注意が必要です。メンバー全体に配信される場合と、特定の相手にのみ配信される場合があるので、返信前に配信先を確認することが重要です。
III.効果的なレポート作成とアカデミックライティング
大学レベルのレポート作成には、明確な主張 が必要です。トゥールミンの三角ロジック を用いて、データ、ワラント(根拠)、主張を明確にすることで、論理的で説得力のあるレポートを作成できます。レポートは、序論、本論、結論の3部構成が一般的です。 論文引用 は必ず行い、参考文献リストをきちんと作成することが重要です。参考文献リストは著者名(ローマ字表記)のABC順に作成します。Webページを引用する際は、参照日も明記する必要があります。日本と欧米のコミュニケーションスタイルの違いについても触れられており、主張を明確にすることの重要性が強調されています。
1. レポート作成における明確な主張の重要性
レポート作成においては、明確な主張が不可欠です。主張とは、レポート作成者自身の立場や意見であり、正誤は関係ありません。 日本と欧米のコミュニケーションスタイルの違いが例示されており、日本人は状況説明から始め、暗黙のうちに主張を伝える傾向がある一方、欧米ではまず主張を明確にしてから根拠を説明することが一般的です。 レポートでは、この欧米型の明確な主張を意識することが重要であり、読者に分かりやすく伝えるために、自身の立場を明確に示す必要があります。 主張を明確にすることで、レポート全体の構成や論理展開が明確になり、読者への理解度も向上します。 そのため、レポートのテーマについて、まず自身の立場を明確に示し、それを裏付けるデータや根拠を提示することが重要です。
2. トゥールミンの三角ロジックによる論理展開
論理的なレポート作成のために、「トゥールミンの三角ロジック」が紹介されています。これは、データ、ワラント(根拠)、主張の3要素から構成される論理モデルです。 データは、事実や統計など客観的な情報、主張はレポートで伝えたい結論、ワラントはデータと主張を繋ぐ論理的な根拠です。 単純な主張とデータだけで構成されるレポートは少ないため、複雑な要因が絡むテーマではワラントを詳細に記述する必要があります。 また、入手できるデータや考えられるワラントは常に不完全であることを理解した上で、これらの不完全さを最小限に抑えることで、主張をより頑健なものにすることができます。 例えば、「窓を開ければ室温が下がる」という主張に対して、「なぜ窓を開けると室温が下がるのか?」という疑問が生じた場合、外気温と室温の差、空気の流れといったワラントを提示することで、主張をより裏付けることができます。
3. レポートの基本構成と適切な分量
レポートは、序論、本論、結論の3つの部分で構成されます。これは、アカデミックな文章だけでなく、企画書や報告書などにも共通する基本的な枠組みです。 序論では、レポートのテーマを導入し、背景や問題点を説明します。全体を1000字とすると、序論は約250字程度が適切です。 本論では、主張を展開し、データや根拠を提示します。結論では、本論で述べた内容を要約し、結論を明確に示します。 1000字程度のレポートは、短くまとめる必要がある分、良い視点と十分な推敲が求められ、書くのが最も難しいと言えます。だらだらと書くのではなく、明確な視点を持って簡潔にまとめることが重要です。
4. 参考文献リストの作成方法
レポートで引用した文献は、必ず参考文献リストとしてレポートの最後に記載する必要があります。 参考文献の種類(論文、書籍、Webページなど)に関わらず、著者名のアルファベット順(日本語の場合はローマ字表記)に並べます。 著者名が複数いる場合は中黒「・」で繋ぎます。雑誌記事の場合は、巻数はゴシック体または下線付きで表記します。 Webページを引用する場合は、公開年が記載されていない場合でも、参照日を必ず記入します。これは、Webページが予告なく削除される可能性があるため、参照日時点での存在を明確にするためです。 正確な引用と参考文献リストの作成は、学術的な倫理と信頼性を確保するために必須です。レポートの信頼性を高めるためにも、正確な情報と適切な引用方法を理解しておくことが重要です。
IV.効果的なプレゼンテーションスキル
プレゼンテーションでは、姿勢 を正しくし、適度なジェスチャーを取り入れることが重要です。スライドは、Steve Jobs のように簡潔にすることで、聴衆の集中力を維持することができます。時間厳守も必須です。リハーサルを行い、時間内に発表を終えるよう心がけましょう。
1. スライド作成における文字量の重要性
プレゼンテーションのスライド作成においては、スライドに表示する文字量を最小限に抑えることが重要であると述べられています。 Steve Jobs のようにスライドに文字を極力少なくすることで、聴衆はスライドを読むことに時間を奪われず、プレゼンターの話に集中することができます。 一方、Bill Gates のようにスライドに多くの文字を入れると、聴衆はスライドの文字を読みながら話を聞くという二重の作業を強いられることになり、理解度が低下する可能性があります。 聴衆の集中力を維持するためには、スライドは視覚的な補助として利用し、重要なポイントのみを簡潔に提示することが効果的です。 そのため、スライドの内容は簡潔に、かつ視覚的に分かりやすくまとめることが重要です。
2. 効果的なプレゼンテーションのための姿勢とジェスチャー
プレゼンテーションを行う際の姿勢は、聴衆への印象を大きく左右します。 上体が揺れたり、落ち着きのない姿勢では、聴衆に不安感を与えてしまう可能性があるため、常に姿勢を正しく保つことが重要です。 また、一箇所に留まるだけでなく、適度に場所を移動したり、両手を用いて強調したりすることで、ジェスチャーを効果的に取り入れることが推奨されています。 ジェスチャーは、プレゼンテーションの内容を強調したり、聴衆の注意を引きつけたりする効果があり、聴衆にとってスピーチの力点を理解する上で重要な手がかりとなります。 適切な姿勢とジェスチャーを用いることで、プレゼンテーションの内容がより分かりやすく、説得力のあるものになります。
3. 時間厳守の重要性
プレゼンテーションにおいて最も重要な点として、時間厳守が挙げられています。 決められた時間を超過することは、聴衆の質問時間を奪うだけでなく、次の発表者の時間を圧迫することにも繋がるため、絶対に避けなければなりません。 時間内に発表を終えるためには、事前のリハーサルが不可欠です。 何度も練習を行い、発表内容をしっかりと時間内に収まるように調整する必要があります。 時間ぴったりに発表を終えることは、聴衆に良い印象を与え、プレゼンテーション全体の評価を高めることに繋がります。 時間管理能力は、プレゼンテーションスキルにおいて非常に重要な要素の一つです。
文書参照
- Googleドキュメント
