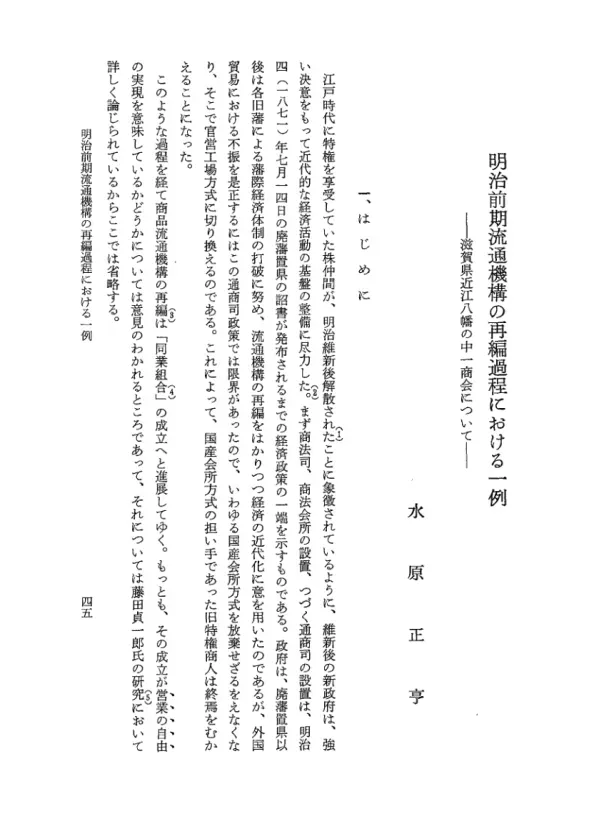
明治前期流通機構再編と中一商会
文書情報
| 著者 | 水原正亨 |
| 学校 | 滋賀大学 |
| 専攻 | 経済学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.58 MB |
概要
I.明治維新と 株仲間 の解体 そして 同業組合 の勃興
本稿は、明治維新後の経済政策、特に流通機構の再編過程における変化を分析します。まず、江戸時代の特権的商人集団である株仲間が明治維新によって解散されたことを示します。これは、新政府による近代的経済活動基盤整備の強い決意を示す象徴的出来事です。廃藩置県(1871年)以降、政府は藩際経済体制の打破と流通機構の再編に尽力しましたが、当初の国産会所方式は限界を迎え、官営工場方式への転換を余儀なくされました。この過程で、旧特権商人は衰退していきました。その後、同業組合が形成され始めますが、それが営業の自由を実現したものか否かについては、藤田貞一郎氏の研究を参照する必要があります。同業組合は、全ての商人を加入させ行動を制限する側面と、一方で保守的な前近代的な側面を持つ組織であったと捉えることも可能です。作道洋太郎氏の指摘のように、経営史的な検討も必要となります。
1. 株仲間の解体 明治維新と経済政策
明治維新後、新政府は近代的経済活動基盤の整備に強い決意をもって取り組みました。その象徴として、江戸時代から特権を享受していた株仲間の解散が挙げられます。まず、商法司、商法会所の設置、そして通商司の設置は、1871年7月14日の廃藩置県詔書に至るまでの経済政策の一端を示しています。廃藩置県後は、旧藩による藩際経済体制の打破、流通機構の再編が推進され、経済近代化が目指されました。しかし、外国貿易の不振是正には通商司政策だけでは限界があり、国産会所方式から官営工場方式への転換が行われ、旧特権商人は終焉を迎えることになります。この政府主導による経済政策と流通機構の再編は、後の同業組合の成立へとつながる重要な転換期となります。 宮本又次の研究(『日本ギルドの解放―明治維新と株仲間』など)は、株仲間の解散と明治維新の関係を深く分析しており、天保期説と明治維新期以後説が存在するものの、近江八幡の干鰯屋仲間の例では天保の解放令による段階的な解散を示しています。
2. 同業組合の成立とその性格 営業の自由と保守性
商品流通機構の再編過程を経て、同業組合が成立しました。しかし、その成立が営業の自由を実現したかどうかは議論の余地があり、藤田貞一郎氏の研究が詳細に論じています。同業組合は、すべての商人を加入させ、その行動に制限を加え罰則規定を設けることで組織を維持する側面がありました。このため、営業の自由というよりも、保守的・前近代的な団体であったという意見も存在します。 同業組合の成立は、すべての商人を包含する点で営業の自由を実現したと解釈される一方で、その行動を制限し罰則を設けることで保守的な側面も持っていたという、相反する見解が存在します。この点に関して、作道洋太郎氏の指摘のように、経営史的な視点からの検討が必要であることが示唆されています。 よって、同業組合の成立は、単に営業の自由化を意味するものではなく、その性格は多面的であり、歴史的文脈の中で多角的に検討する必要があると考えられます。様々な研究(由井常彦、岡田与好、上川芳恥部らの研究など)が同業組合の形成過程やその性格について論じています。
II.近江商人の事例 西川家 と北海道
西川家は近江国(滋賀県)出身の商人一家で、寛永3年(1626年)に初代伝右衛門昌隆が誕生しました。当初は行商から始め、次第に北海道(蝦夷地)に進出し、松前藩御用達商人となりました。西川家は北海道での漁業経営、海運業で財を成し、明治期には十代目貞二郎が八幡銀行設立など近代化に貢献しました。 北海道での事業展開は、初代伝右衛門の松前への移住(慶安3年、1650年)から始まり、代々蝦夷地での活躍が続きます。三代目伝右衛門は西蝦夷地の寺入場所請負人となり、五代目は千石積船を所有するなど、海運業でも成功を収めました。
1. 西川家の起源と北海道進出
西川家は、寛永3年(1626年)近江国蒲生郡南津田村に初代伝右衛門昌隆が生まれたことから始まります。その後、八幡の仲屋町に移り住み、近江出身の商人が全国で活躍する中、西川家も当初は父と共に奥羽・北越方面へ荒物や菓子などを仕入れて行商をしていました。しかし、次第に高級品の呉服・太物などを扱うようになり、利益が増加すると、越後の知人から松前・蝦夷(北海道)の話しを聞き、慶安3年(1650年)、24歳の時に松前福山へ移住しました。当時、松前には既に近江商人の岡田弥三右衛門や田付新助などが店舗を構えていましたが、伝右衛門は元手が少なかったと言われています。しかし、松前藩の家老の屋敷に身を寄せ行商を続け、順調に利益を蓄積し、寛文元(1661)年には城下小松前町に日印住吉屋を創業しました。寛文7年(1667)には船を2隻建造し、北海道の産物を本州に運び、日用品を持ち帰る交易を始めました。初代伝右衛門は、47年間で松前と江州の本店間を数十回往復したと言われ、松前藩御用達商人として藩に貢献した功績から、元禄14年(1701)には御先手格となり、苗字帯刀を許され、20人扶持を与えられました。
2. 西川家の北海道における事業展開と明治期の活動
初代伝右衛門は「子孫たる者、郷里において田畑を買い、或いは事業を起こすべし。財産あれば必ず北海事業の振興刷新に投ぜよ。我が家は松前に於て興る」という遺訓を残し、宝永6年(1709年)に83歳で亡くなりました。その後も代々の当主は初代の遺訓を守り、蝦夷地で活躍を続けました。三代目伝右衛門は延享2年(1745年)夏から文化14年(1817年)まで西蝦夷地の寺入場所の請負人を務め、五代目は千石積船を4隻建造し、所有船数を6隻に増やし、海上輸送で活躍しました。七代目は文政13年(1830年)から23年間磯谷・歌棄両場所を譲り受け、八代目は天保8年(1837年)エトロフ場所を請け負いましたが、利益が上がらず天保12年(1842年)には返上しました。箱館店は西川家の単独経営として存続し、商号を変えて呉服類の販売を専業としました。近世を通じて忍路高島場所での漁業経営、海運業によって財を成した西川家は、明治に至り、十代目貞二郎は、様々な献金・寄付、道路開削などに財産を投じ、近代化過程での地方事業家として八幡銀行を設立し頭取となり、商船会社や綿織物会社の設立・投資にも関与しました。
III. 中一商会 共同購買組合と肥料改良
明治19年、西川家十代目貞二郎は、滋賀県知事中井弘氏の勧誘を受け、中一商会を設立しました。これは、肥料の共同購買組合であり、大阪や敦賀の問屋を通さず、生産者から直接肥料を仕入れ、廉価で良質な肥料を農家に供給することを目的とした模範事業です。中一商会は、組合員である農家と直接取引するのではなく、総代を通じて一括注文を受ける仕組みを採り、中間マージンを削減しました。設立にあたっては、定款と規約が作成され、滋賀県令中井弘氏の認可を得ています。高田義甫が支配人を務めました。 中一商会の倉庫は県内に複数設置され、代金支払いは米穀収穫時期に行われ、それまでの期間は銀行貸付利子のみを徴収するなど、農家の負担軽減に配慮した運営がなされました。
1. 中一商会の設立目的と背景 肥料流通の改善
明治19年7月、資本金10万円で設立された中一商会は、滋賀県内の肥料流通改善を目的とした共同購買組合でした。それまで滋賀県内の肥料は、大阪や敦賀などの問屋を経由し、地方肥料商を経て農家に至る流通経路を取っており、その過程で品質の粗悪化や価格の高騰、不正な商法などが問題となっていました。県知事の中井弘氏は、魚肥生産者からの直接購入による流通経路の改革を提唱し、近江出身の西川伝右衛門家の当主である貞二郎がこれに賛同して中一商会を設立したのです。中一商会の主眼は、漁業家と農家を直接連結させ、従来の商人による手数料を省略することで、廉価で純正な魚類肥料を供給することにありました。これは、肥料価格の変動による農業経営の不安定さを解消しようとする試みでもありました。具体的には、県内に倉庫を設置し、米穀収穫期に代金支払いを行うなど、農家の負担軽減に配慮した仕組みが構築されました。
2. 中一商会の運営体制 共同購買と代理店制度
中一商会は、組合員である肥料購買農民に直接販売するのではなく、組合員の需要を総代がまとめて代理店に一括注文する仕組みを取っていました。代理店は前年度に予約を取り、翌年に商品を供給する役割を担っていました。中一商会は、代理店との取引のみを行うことで運営の効率化を図りました。明治17年12月には、商会設立用の土地を取得し、明治18年5月15日には定款を制定、同年5月21日に滋賀県令中井弘氏に認可申請を行い、9月8日に認可を得ています。定款では資本金20万円、営業期間15年と規定され、県・郡・代理店組合員の帳簿閲覧の自由が明記されていました。肥料改良規約では、肥料の品質管理、価格の公開、代理店との契約条件などが詳細に定められていました。代理店は手数料を得、米穀を肥料代として受け取った場合は自由な売却を認められ、差益を得ることもできました。 中一商会設立にあたり、西川家は明治17年12月に敷地を購入し、翌年には隣接地も取得しています。高田義甫が中一商会の創設準備を引き受け、その後支配人となっています。
3. 中一商会の運営開始と普及への取り組み
中一商会は、明治19年3月2日に改良規約に但し書きを追加する認可を受け、同年4月には県下の肥料商および需要者に対し、中一商会定款および規約草案を配布し、肥料購入を呼びかけました。この際に、同年は試験的に肥料輸入量を1万石として取引を行う旨を伝え、需要者側にも経験を積ませることを意図していました。高田義甫は、八幡の旧株仲間納屋嘉兵衛家の当主であり、中一商会の支配人として創立事務を引き受けました。明治19年3月には高島郡役所へ、同年6月には複数の個人や商店へ書状を送付し、肥料改良規約への参加を呼びかけています。 中一商会の倉庫は、煉瓦造りの平屋建てで、建坪64坪、総工費6,793円20銭をかけて完成しました。そして、明治19年7月20日、資本金10万円で中一商会は開業しました。開業後も組合員と代理店の獲得に努め、代理店との契約は冊子形式の「代理店規約」で行われました。この規約は、注文受付から代金回収、在庫管理、顧客対応までを詳細に規定していました。
IV. 中一商会 の運営と代理店制度
中一商会は、代理店制度を通じて肥料を販売しました。代理店との契約は詳細に規定され、手数料、在庫管理、顧客対応などが明確化されています。代理店は、組合員からの注文をまとめ、中一商会に一括発注する役割を担っていました。価格設定は公開され、翌年度の需要予測に基づいて取引が行われました。苗村喜兵衛店との取引記録などが残されており、中一商会の運営実態の一端がわかります。中一商会は、廉価と高品質で農家の利便性を向上させ、近隣の府県にも販路を拡大しました。しかし、同業組合との関係や、中一商会自体の存続期間など、未解明な点も残されています。
1. 代理店制度の構築と契約内容
中一商会は、直接農家と取引するのではなく、代理店制度を通じて肥料を販売しました。この代理店制度は、効率的な流通と販売網の構築を目的としていました。代理店との契約は、冊子形式の「代理店規約」によって行われ、その内容は非常に詳細でした。規約には、受注から配送、代金回収、顧客対応に至るまで、代理店の業務内容が明確に規定されています。例えば、肥料の注文受付は、改良規約に則り、受付番号付与、請求書目録への記入、請求書の添付といった手順で行われ、需要者自らが請求書を作成できない場合は代理店が代筆し、請求者に捺印させることになっていました。また、代理店は取扱手数料を獲得し、肥料代として米穀を受け取った場合は自由に売却でき、肥料代以上の差益を収益とすることが認められていました。この詳細な規約は、中一商会の運営の効率性と透明性を確保するための重要な要素でした。 契約期間は本店営業期間と同じで、違約や妨害行為があった場合は、代理店契約を解除し、相当の償いをさせることも規定されていました。
2. 代理店の業務と責任 詳細な規定と報告義務
代理店規約では、代理店の業務内容が詳細に規定されています。例えば、代理店は担当区域を巡回する際は、巡回する者の住所、氏名、年齢、職業などを事前に本店に届け出る必要がありました。また、需要者から臨時査定価格での買置請求があった場合は、定められた抵当または手金を預かり、請求書を添付して売仕切書を発行し、必要に応じて物品の交付を行う必要がありました。さらに、貨物の倉庫への保管期限は60日以内と定められ、貨物の損傷や紛失があった場合は、その状況を詳細に報告する義務がありました。代理店の業務状況や営業状況について、必要と判断された際には本店支配人へ親展で報告する義務もあったなど、代理店には明確な責任と報告義務が課せられていました。これらの規定は、中一商会が目指した効率的で信頼性の高い流通システムを維持するための重要な要素であったと考えられます。 価格の明示と翌年度の需要予測に基づく受注体制も、代理店との取引を円滑に進めるための重要な要素でした。
3. 中一商会の成果と課題 流通機構改革と今後の研究
中一商会は、低廉な価格と純正な品質で農家の利便性を高め、伊賀、伊勢、美濃、山城などの隣接府県に販路を拡大しました。その結果、他の肥料商も不正な手段を是正せざるを得ない状況となり、不当な利益を追求する風潮は減少していきました。農家も中一商会から価格算定の知識を得るなど、良い影響を与えました。しかし、中一商会の存続期間は明示されておらず、定款では資本金20万円で15年間の営業と規定されていたものの、実際は不明です。また、明治25年に八幡の肥料商同業組合が誕生していますが、その規則内容は準則組合とは程遠く、むしろ大阪の肥料組合との結びつきが強まっているなど、未解明な点も多く残されています。 これらの事実は、中一商会が明治前期の流通機構改革に貢献した一方で、同業組合との関係性や長期的な持続可能性といった課題も抱えていたことを示唆しています。今後の研究では、これらの点について更なる調査と分析が必要となるでしょう。
