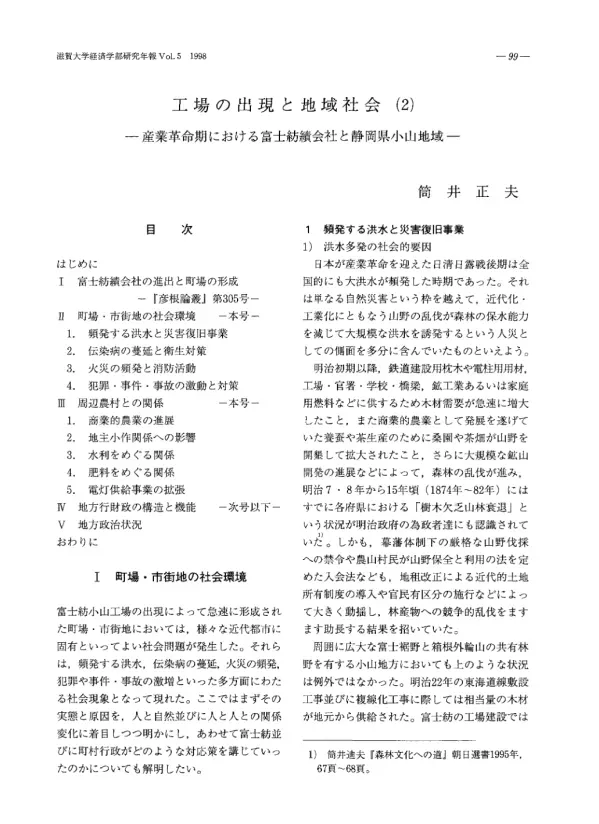
明治期小山町洪水災害と富士紡
文書情報
| 学校 | 大学名(本文からは特定できません) |
| 専攻 | 歴史学、経済学、社会学など(本文からは特定できません) |
| 出版年 | 不明(明治~大正時代) |
| 場所 | 不明(本文からは特定できません) |
| 文書タイプ | 論文、研究報告書など(本文からは特定できません) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.30 MB |
概要
I.明治期小山町における富士紡績社の進出と地域社会への影響
本稿は、明治29年(1896年)の創業から大正時代にかけて、静岡県小山町における富士紡績株式会社の進出が、地域社会に与えた多大な影響を分析します。特に、産業革命期における急激な近代化と人口増加が、地域社会の構造、経済、生活、そして環境問題にどのような変化をもたらしたのかを検討します。富士紡績の工場建設は、雇用創出や経済活性化をもたらしましたが、同時に、水質汚染、伝染病の蔓延、犯罪増加などの問題を引き起こしました。労働争議や農村との水利問題、肥料問題なども発生し、地域社会と富士紡績との間で複雑な関係が形成されたことがわかります。
1. 富士紡績進出以前の小山町の状況 森林資源の衰退と入会権の変容
明治7~15年頃(1874~1882年)には、既に各地で「樹木欠乏山林衰退」が深刻な問題となっていました。これは、明治政府による地租改正と官民有区分の施行によって、従来の入会権制度が大きく揺らぎ、林産物の競争的な乱伐が助長されたためです。近世以来、村落間の共有地であった山林は、地租改正による官有地編入などで境界線が曖昧になり、入会争論が激化しました。その後、山林組合や村落共有による管理運営が整備され、乱獲の抑制が進められていましたが、増加する木材や薪炭材の需要は、これらの規制を無力化し、競争的な乱伐を招きました。特に炭焼きは、火鉢の普及で需要が増大し、『静岡民友新聞』の記事にも小山地方からの薪炭供給が東京にまで及んでいたことが記されています。この時代の森林資源の衰退は、後の富士紡績進出による環境問題と深く関わる重要な背景となります。
2. 富士紡績工場建設と地域インフラへの影響 水利利用と環境問題
明治29年(1896年)から始まった富士紡績工場の建設は、周辺地域に大きな変化をもたらしました。須川からの取水は、既存の水路や農業用水に影響を与え、飲料水にも問題が発生しました。富士紡績は、道路や橋梁の修繕費用を負担し、水利権に関する補償として周辺村落に金銭的な寄付を行いました。しかし、河川の水質汚染も深刻化し、工場排水による汚染は住民の生活に影響を与え、排水口の変更などを求める住民との対立が発生しました。これは、明治39年(1906年)の須川発電所建設の際に特に顕著に見られました。工場の排水問題は、地域住民と富士紡績との間で長期にわたる摩擦を引き起こす要因の一つとなったのです。さらに、大正3年(1914年)の大洪水は、工場施設の損壊に加え、深刻な伝染病蔓延を招き、その対応に富士紡績と地域住民が協力する一方、改めてインフラ整備の脆弱性を浮き彫りにしました。
3. 富士紡績工場と周辺農村の経済的相互作用 農業構造の変化と商品経済への移行
富士紡績工場の建設と発展は、周辺農村の農業構造にも変化をもたらしました。工場の需要増加に伴い、野菜や養鶏などの商業的農業が盛んになり、大根、ジャガイモ、サツマイモなどの新品種導入が進みました。北郷村では、富士紡績工場への野菜供給が大きく増加し、養鶏も盛んになり、多くの卵が工場に納められました。一方で、自給自足の穀物類の作付面積は減少傾向にあり、食生活も粟や麦中心から、野菜や卵などを含む多様なものへと変化しました。小作制度においても、小作料の代金納が増加し、労働力の不足から小作地を減らす農家が増え、富士紡績への転職が増えるなど、農業から工場労働への移行が進む様子が見て取れます。このことは、農村における商品経済化と、伝統的な自給自足型経済からの転換を示しています。
4. 富士紡績進出による社会問題 犯罪の増加と治安維持への取り組み
富士紡績工場の進出によって、小山町には多くの労働者が流入し、それに伴い犯罪が増加しました。特に、工女をターゲットとした誘拐事件が複数発生し、これは富士紡績と地域社会双方にとって深刻な問題となりました。工場の周辺には、多くの単身赴任者や職人などが居住しており、それらの人々と工女との間で様々な事件や犯罪が発生しました。それらに対応するため、富士紡績は工女の保護監督に力を入れると共に、警察への巡査増員要請などを行い、地域社会と協力して治安維持に努めました。しかしながら、犯罪の増加と多様化は、地域の秩序維持を困難にする大きな課題となりました。特に、明治39年以降は、殺人事件や暴行事件も発生し、治安維持への強い必要性が高まりました。 警察の電話設置への寄付なども行われ、警察との連携強化が図られました。
II.富士紡績と労働問題 労働環境と労働運動
富士紡績は、急激な工場拡張に伴い、過酷な労働環境、低賃金、労働災害といった問題を抱えていました。これに対して、工女を中心とした労働運動が活発化し、賃上げ要求や労働条件改善を求める示威運動が発生しました。会社側は、購買会設立などの対策を講じましたが、労働問題は深刻な課題として、富士紡績の経営や地域社会の安定に影を落としました。工女の自殺や逃亡事件も多く発生し、富士紡績はそれらの対策にも苦慮しました。労働者の数は約6000名に達し、拡張工事従事者を含めると20000名以上の出入がありました。
1. 富士紡績における労働環境と労働者の生活
富士紡績工場では、労働環境の悪さと低賃金が大きな問題でした。特に夏場は「盛夏七八月ノ交、労務梢モスレバ怠惰ニテ監督常二困難ナルニ当季ハ逆蛸著シク、職工ノ欠乏ヲ生ジ苦慮経営而モ踏台二三ニシテ止マラス、成績甚ダ不良ノ状態二有之候」とあり、労働者の怠惰や不足が経営を圧迫していたことがわかります。こうした状況の中、工女の自殺や工場からの逃亡が頻発していました。文書には、工女の逃亡事件が7件、自殺(未遂を含む)が7件あったと記録されています。 会社側は、こうした問題に対応するため、寄宿工女の外出制限の緩和や見張り番の撤廃といった労務管理対策を実施していましたが、効果は限定的だったようです。明治39年から始まった10か年拡張計画は、増資と工場建設を推進し、高率の株式配当をもたらしましたが、労働者の生活改善には必ずしも繋がっていなかったことが伺えます。工場は、約6000人の男女工と拡張工事従事者などを含め、20000人以上の出入りがありました。
2. 労働運動の発生と会社側の対応 賃金要求と労働条件改善
劣悪な労働環境に対する不満から、工女を中心に賃金引き上げを求める示威運動が発生しました。明治45年5月には第2工場で賃金引き上げ要求の示威運動が起こっています。会社側は、こうした労働運動への対応として、和田専務が推進したとされる労働環境改善策を実施しました。具体的には、請負法による綿糸部工女の日給引き上げ、短期皆勤賞与、新人男女工員の日給引き上げ、食事の改善、娯楽室の設置、運動会の開催などが挙げられます。しかし、これらの対策にもかかわらず、工女の自殺や逃亡は依然として続き、労働問題が完全に解決されたわけではなかったことがうかがえます。 また、会社は購買会を設立し、日用品や米などを廉価で販売する事業を開始し、浴場経営も行いました。しかし、購買会の拡大は、地元商店の経営を圧迫し、購買会縮小の請願書が提出される事態にまで発展しました。これは、会社と地域経済との摩擦も示しています。
3. 伝染病の流行と対策 衛生問題と地域社会との連携
大正3年(1914年)の大洪水は、未曾有の伝染病蔓延を引き起こしました。腸チフス、パラチフス、赤痢などが流行し、富士紡工場では230名以上(うち死亡2名)、小山町内では49名(うち死亡3名)もの患者が発生しました。特に夏場は「勢ヒ狙獺iシテ容易二減退セズ七、八月盛夏ノ候殆ド空前ノ大流行ヲ極メ」とあり、空前の流行規模だったことが分かります。富士紡工場内での伝染病発生は、町内への拡大が懸念され、菅沼・六合両村と富士紡、警察・町村吏が協力して大規模な消毒を実施しました。対象は家屋内の便所・台所、会社内の寄宿舎・便所、下水・河川などに及び、総戸数1300戸以上に達し、費用は1000円以上にも上ったと記録されています。 この大規模な伝染病流行は、工場の労働環境や衛生状態の課題を改めて浮き彫りにする出来事となりました。
III.富士紡績と周辺農村 水利 肥料問題と地域協調
富士紡績の工場建設と発展は、周辺農村と密接に絡み合っていました。工場建設に伴い、水利権をめぐる争いや、工場排水による水質汚染、肥料としての人糞尿の利用など、様々な問題が発生しました。しかし、名望家層の仲介により、富士紡績と農村の間で利害調整が進み、趣意金の支払いや肥料の供給を通して、一種の協調関係が築かれていきました。一方で、水田やわさび田の減少など農村への負の影響も無視できません。特に、須川発電所の建設による阿多野貯水池の造成は、わさび栽培に大きな打撃を与えました。
1. 水利をめぐる関係 富士紡績と周辺農村の利害調整
富士紡績工場の建設は、周辺農村の水利利用に大きな影響を与えました。工場建設にあたり、須川の水を分水して使用することになったため、農業用水や飲料水に影響が出ました。富士紡績は、菅沼村に1000円の寄付を行い、道路や橋梁の修繕費用も負担しました。しかし、水利をめぐっては、当初から摩擦が生じました。特に、明治39年の須川発電所建設では、水路建設、土地買収、わさび田の損壊補償などをめぐって、富士紡績と地域住民との間で激しい対立が発生しました。北郷村棚頭の名望家、小野勇逸の日記によると、趣意金の増額要求や、関係各区からの趣意金支払いの要求などが、交渉を長引かせました。また、地権者と借地人、富士紡の間で対立が起きたり、土地買収に応じない地主もおり、利害調整は容易ではありませんでした。しかし、最終的には、地元の名望家層が奔走し、利害を調整することで、富士紡績と周辺農村との間で水利利用に関する契約が締結されました。この契約締結には、富士紡側への協力や情報提供を行った岩田蜂三郎などの地元名望家の貢献が大きかったことが、小野勇逸の日記からわかります。
2. 肥料をめぐる関係 人糞尿の有効活用と小山肥料組合の設立
富士紡績工場では、増加する従業員の排泄物処理が課題となり、当初は神奈川県平塚まで運搬していましたが、費用と手間がかかりました。そこで、人糞尿を肥料として周辺農村に提供する案が浮上しました。人糞肥料の有効性を周辺農村に示すことで、地元農村との協力関係構築を目指したのです。明治39年7月には、六合村、菅沼村、足柄村組合村、北郷村の農会と小山区が小山肥料組合を組織し、富士紡績と下肥肥料の払い下げに関する契約を締結しました。汲み取り料金は、工場従業員100名につき月90銭、通勤者では45銭と決められ、毎月25日までに支払われました。悪疫流行時には、消毒薬の撒布・投入が義務付けられました。この小山肥料組合の設立は、富士紡績と周辺農村の間で、廃棄物処理という問題を、相互に利益をもたらす関係へと転換させた成功例と言えるでしょう。この取り組みは、工場の廃棄物を地域資源として有効活用する、循環型社会の萌芽とも言えます。
3. 電力供給と地域協調 富士紡績と各区との協定
富士紡績は、電力供給においても周辺農村と関わりを持っていました。電灯事業は町営化されず、各区が富士紡績と協定を結び、電力を供給を受けていました。その条件は地域によって異なり、富士紡績進出当時から水利問題で対立があった藤曲区では、大正8年に電灯供給を受ける際に覚書を交わしました。覚書では、特別の料金を適用しないこと、そして藤曲用水の利用範囲を更に制限することが合意されました。これは、長年の対立関係を経て、互いの妥協点を見出し、共同利用へと進んだ事例と言えます。富士紡からの電力供給は、周辺農村の生活水準向上に貢献しましたが、同時に、水利利用などに関して、富士紡との関係性の複雑さを示す一例ともなっています。このように、水利や肥料、電力といった資源の利用において、富士紡績と周辺農村は、対立と協調を繰り返しながら、複雑な関係性を築いていったと言えるでしょう。
IV.富士紡績進出による小山町の社会変化 犯罪増加と治安対策
富士紡績の進出によって、小山町には多数の労働者が流入し、それに伴い犯罪が増加しました。殺人事件、強盗事件、誘拐事件などが発生し、特に工女を狙った誘拐事件は深刻な問題となりました。町は、警察の増員や警備強化などの対策を講じましたが、犯罪の多様化、凶悪化に対処するには限界がありました。 富士紡績も、工女の監視や保護に力を入れましたが、犯罪増加は、地域社会の治安を大きく脅かすものとなりました。
1. 富士紡績進出による人口増加と犯罪の増加
富士紡績工場の進出は、小山町の人口を急激に増加させました。多くの労働者や関連従事者が流入した結果、町場の拡大は「急速に御殿場的状況が小山地域にも広がっていった」と表現されるほどでした。しかし、この人口増加は、同時に犯罪の増加をもたらしました。日露戦争後、小山町域では殺人事件2件(未遂1件)、暴行事件1件が発生し、凶悪犯罪が増加傾向にあったことが分かります。殺人事件は、六合村小山で発生し、一方は料理店兼旅館の雇女と博徒の痴情のもつれ、もう一方は米穀商を襲った強盗殺人でした。また、工女の逃亡事件も発生しています。これらの犯罪の増加は、急激な人口増加と、教育や秩序に欠けた「旅渡りの単身者」の増加が背景にあったと推測されます。 これらの犯罪は、従来の町村の自警組織だけでは対処できない規模であり、近代的な警察組織の強化が求められる事態となりました。大正3年10月には、小山町は警察分署の設立と巡査の増員を県に請願しています。
2. 工女の逃亡と誘拐事件の多発 工場と地域社会の治安問題
富士紡績工場の工女をターゲットにした誘拐事件が7件も発生しました。犯人たちは、工女を巧みに誘い出し、あるいは暴力的に誘拐した上で、他の紡績会社や山梨・沼津方面に売春婦として売ろうとしたのです。犯人の多くは同業の前科者で、各地を転々としていました。工女の逃亡願望の強さも背景にありました。工女の逃亡は7件、自殺(未遂を含む)も7件と、深刻な状況でした。こうした状況を受け、富士紡績は工場内外に監視役を配置するなど、逃亡防止策を講じていましたが、明治34年以降は和田豊治による労務管理対策の中で、寄宿工女の外出制限は緩和され、見張り番も撤廃されたとあります。しかし、『静岡民友新聞』の記事からは、巡査の活動と並んで、富士紡績も監督人、外勤係、女工警戒員などを配置して、工女の保護監督、自殺者救助、誘拐犯の探索などに尽力していたことが分かります。さらに、建設工事中の土工による騒擾も懸念され、警察への巡査派遣を繰り返し要請していました。
3. 治安対策 警察の強化と地域住民の協力
増加する犯罪に対処するため、小山町では警察の強化が図られました。警察分署の設立と巡査の増員が請願され、富士紡績は警察電話の架設に際し、電話器や架設材料を寄付しています。これは、警察と地域社会、そして富士紡績の連携強化を示しています。一方、地域住民も、独自の治安維持に努めました。例えば、茅沼区では、工女の逃亡防止のための番人の配置、帰社時間の厳守、不審な行動の通報、営業者の取り締まり、損害賠償責任の規定など、詳細な規約が作られ、厳しい罰則も設けられていました。これは、地域住民が、外来者による犯罪や風紀の乱れを強く懸念していたことを示しています。遊郭の設置を希望する動きもありましたが、これは却下され、懸念された風紀の乱れは現実のものとなりました。 このように、犯罪増加への対策は、警察の近代化と地域住民の自主的な取り組み、そして富士紡績による協力体制の構築という多様なアプローチで行われました。
V.富士紡績と小山町の農業 商業的農業の発展と伝統的農業の衰退
富士紡績の進出は、小山町の農業にも大きな影響を与えました。工場の需要に応えるため、野菜や養鶏などの商業的農業が発展しました。しかし、一方で、伝統的な自給自足型の農業は衰退し、食文化や技術の伝承にも影響が出ました。小作制度も変化し、小作料の代金納が増加しました。農作物の種類も変化し、大豆から野菜類への転換が見られました。富士紡績の労働者へ転職する小作人も増加しました。
1. 富士紡績工場建設の影響と農業用地の変化
富士紡績工場の建設は、小山町の農業に大きな変化をもたらしました。工場建設のために水田や耕地の一部が失われ、明治39年の須川発電所建設に伴う阿多野貯水池の造成ではわさび田が消失するなどの直接的な被害が発生しました。 これらの土地の喪失は、農家の生活に直接的な打撃を与えたと考えられます。さらに、工場の建設や、それに伴うインフラ整備工事によって、農業用水路や用水量にも影響が出た可能性があります。文書からは具体的な被害額などは明示されていませんが、農家にとって重要な耕地や水源を失ったことは、大きな損失であったと考えられます。特に、長年栽培され、明治10年代には盛んに栽培されていたわさび生産への打撃は大きかったようです。一方で、富士紡績工場の建設によって、周辺地域の人口が増加したことは、農産物の需要増加につながった可能性も考えられます。
2. 商業的農業の発展 野菜栽培と養鶏の増加
富士紡績工場の進出は、周辺農村の農業形態を変化させました。工場従業員への食糧供給という需要の高まりから、野菜類の栽培が盛んになり、特に、北郷村では「小山町富士紡績会社ノ設立以来年々需要ヲ増スニ従ヒ産出高多クナリタリ」とあり、根菜類の生産高が増加したことがわかります。水菜は、冬季の水田裏作として盛んに生産され、漬け物にして小山町や富士紡績工場に販売されました。養鶏もまた、北郷村、足柄村、小山町で盛んになり、北郷村では富士紡績工場に月1万2千~1万3千個もの卵が供給されていました。ジャガイモ、サツマイモ、大根なども新品種が導入され、消費量が増加しました。これらの野菜や卵などは、工場労働者の食生活を支える重要な役割を果たしたと考えられます。このように、富士紡績工場の進出は、周辺農村において商業的な畑作物の生産を促進する役割を果たしました。
3. 伝統的農業の衰退 自給的穀物類の減少と農民の転職
商業的農業の発展と並行して、従来の自給自足的な農業は衰退していきました。畑作においては、「従来ノ畑ノ小作料ハ大豆ヲ以テセラレタルモ当作物ハ天候二支配セラル・コト多ク」とあり、大豆などの穀物類の生産は天候に左右されやすく、不作の年には現物での納入が困難でした。富士紡績の設立以降、需要の変化によって栽培作物も変化し、大豆以外の作物への転換が進みました。小作料の支払いも、現物から代金への支払いへと移行し、その割合は4割を占めるようになりました。田の収穫高に対する実価小作料の割合(小作料率)は50%~60%に達していましたが、工場労働者の収入と比較して農業の収益性が低いことから、小作人が減少する傾向が見られました。結果的に、小作人の中には富士紡績の工場労働者への転職を選ぶ者も増え、農業から工業への労働力移動が進行したことがわかります。これは、農村社会の構造変化と、近代的な商品経済への移行を示しています。
