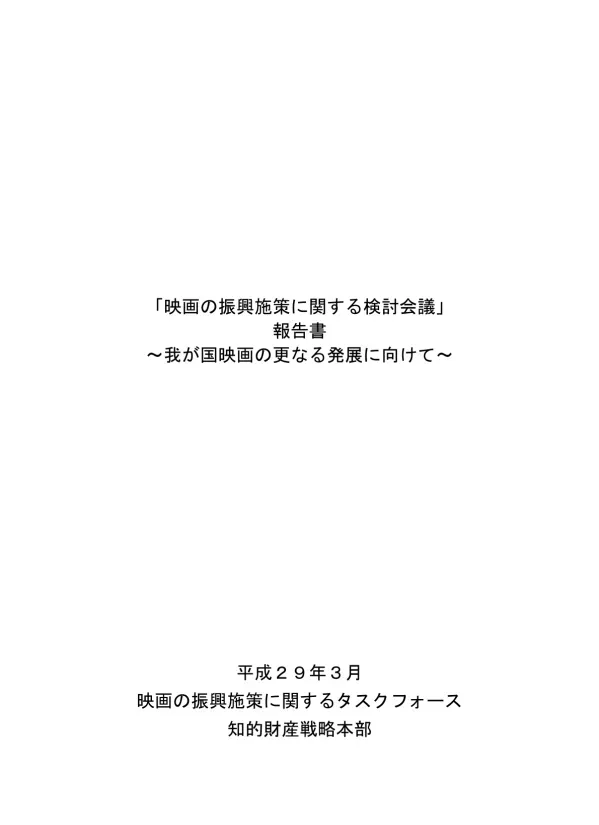
映画振興施策:日本映画の未来戦略
文書情報
| 著者 | 中村伊知哉 |
| 学校 | 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 |
| 専攻 | メディアデザイン |
| 会社 | 知的財産戦略本部 |
| 場所 | 東京 |
| 文書タイプ | 報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.11 MB |
概要
I.日本の映画産業の現状と課題 市場変化と国家戦略
日本の映画産業は、ビデオソフト市場の縮小と動画配信サービスの隆盛により大きな変化に直面しています。市場規模は約2,000億円規模で推移しており、かつては世界第二位でしたが、近年は中国市場にその地位を譲りました。しかし、2016年には過去最高の興行収入を記録するなど、依然として大きなポテンシャルを秘めています。政府は「クールジャパン戦略」の一環として、映画を含むコンテンツ産業の振興に力を入れており、「文化GDP18兆円」という目標を掲げています。 この目標達成には、魅力的な映画制作の維持・強化と、海外展開の抜本的な強化が不可欠です。特に、急成長する中国市場への進出が重要課題となっています。
1. ビデオソフト市場の縮小と動画配信サービスの台頭
従来、映画ビジネスの基盤であったビデオソフトの売上減少と、動画配信サービスの急激な普及という市場環境の劇的な変化が指摘されています。この変化は、映画製作における資金回収方法に大きな影響を与えています。具体的には、映画興行収入に加え、ビデオソフト、テレビ放送、そして近年では動画配信サービスなど、多層的な流通構造からの収益を総合的に勘案して製作費の回収を行う必要性が生じています。インターネットを活用した動画配信サービスの登場は、映画産業のビジネスモデルを大きく変容させる要因の一つとなっています。日本の映画産業の市場規模は約2,000億円とされ、アメリカに次ぐ世界第二位の市場として長らく君臨していましたが、近年は中国市場の台頭に押されつつある状況です。しかしながら、2016年には過去最高の2,355億円の興行収入を記録し、映画館入場者数も42年ぶりに1億8,000万人台に回復するなど、映画市場の潜在力は依然として高いことが示されています。この好調の裏には、『君の名は。』などの大ヒット作品の存在も大きく貢献しています。これらの作品は国内のみならず、中国や韓国など海外でも大きなブームを巻き起こし、経済効果だけでなく、日本の文化やイメージの海外への浸透という点でも大きな影響を与えています。
2. 国内市場の縮小と海外展開の必要性
中長期的な視点に立てば、日本の人口減少に伴い、国内映画市場そのものの縮小が懸念されています。この縮小傾向に対応するためには、魅力的な作品作りを維持・強化し、国内市場の拡大を図ることに加え、海外展開を積極的に強化することが不可欠です。海外市場の開拓は、資金回収の基盤を維持・拡大するための重要な戦略となります。政府もこの課題を認識しており、『戦後最大の名目GDP600兆円』の実現を目指す成長戦略の一環として、コンテンツ産業の振興、特にクールジャパン戦略を推進しています。これは、日本の経済成長を促進すると同時に、日本の文化芸術を世界に発信し、多様な文化芸術立国を実現するための重要な取り組みです。知的財産戦略本部もこの流れを受け、映画産業の振興施策に関するタスクフォースを設置し、具体的な課題解決に向けて議論を進めています。このタスクフォースの議論は、今後の政府や業界関係者の取り組みにおける重要な指針となるでしょう。そして、その成果は『知的財産推進計画2017』に反映されることが期待されています。
3. 映画産業の国家戦略における位置づけ
政府の成長戦略において、映画を含むコンテンツ産業への期待は非常に大きくなっています。『日本再興戦略2016』では、文化芸術資源を活用した経済活性化が明記され、2025年までに文化GDPを18兆円に拡大するという具体的な目標が掲げられています。映画や映像コンテンツは、日本の魅力を海外に発信し、日本のファンを拡大する上で重要な役割を担うと期待されています。その波及効果は、関連産業への経済効果にとどまらず、異業種における商品・サービスの海外展開や、インバウンド需要の拡大といった広がりをもたらすと考えられています。映画は、原作、音楽、映像、アニメーションなど様々な要素を融合した総合芸術であり、その特性から各分野への波及効果も大きいとされています。「観光立国」、「文化芸術資源を活用した経済活性化」、「クールジャパン戦略」といった国家戦略を実現する上でも、映画の発展と海外発信は不可欠な要素となっています。 文化庁による「日本映画製作支援事業」なども、こうした国家戦略を支える取り組みの一つです。
II.映画制作と資金調達 課題と対策
多額の製作費を必要とする映画制作においては、資金調達が大きな課題です。多くの中小制作会社は製作委員会に依存しており、自主的な資金調達を行う機会が少ないのが現状です。政府支援としては、文化庁による「日本映画製作支援事業」がありますが、支援額は限られています。 フランス等の諸外国では、企画開発段階や製作費への支援も充実しており、我が国も制作領域への支援強化を検討する必要があります。さらに、クラウドファンディングや海外事業者からの資金調達といった新たな資金調達手段の活用も重要です。税制・会計制度の整備も、民間事業者の自助努力を促進する上で不可欠です。
1. 映画制作における資金調達の課題
映画制作は多額の資金を必要とするため、資金調達は大きな課題となっています。 多くの映画は、製作委員会方式によって製作されており、中小制作会社やクリエーターは、自ら資金調達を行う機会が少なく、製作委員会からの下請けとして制作に関わるケースが多いのが現状です。そのため、自主的な企画立案や制作を行うための資金調達手段の確保が困難であり、クリエイターの自主性や多様な作品を生み出す環境整備が阻害されている可能性が示唆されています。 ハリウッドなどでは、全世界展開を前提とした大規模な資金調達体制が確立されており、独立系制作会社でも高予算映画の制作が可能となっています。これと比較して、日本の映画産業における資金調達手段の多様性や規模の小ささは、課題として挙げられています。 この状況を改善するためには、中小制作会社やクリエーターが自ら資金調達できる機会を増やすための支援策が求められています。具体的には、政府による支援や後押し、新たな資金調達スキームの導入などが検討されています。
2. 資金調達のための政府支援策と課題
政府は、文化庁による「日本映画製作支援事業」など、映画制作への支援を行っていますが、支援額は限られており、より充実した支援策が必要とされています。 フランスなど諸外国では、企画開発段階や製作費への支援も充実しており、日本の支援策についても、制作領域への支援強化が検討課題となっています。 具体的には、諸外国の制度を参考に、助成制度の拡充・強化が求められています。 また、公的制度の客観性を確保する観点から、「選択補助制度」に加え、「自動補助制度」の導入も検討されています。「自動補助制度」は、実績のある監督やプロデューサーに対して、前作の成果を基に次回作への補助金を自動的に決定する制度です。ただし、この制度導入にあたっては、財源の確保や他産業との公平性の確保といった課題も検討する必要があります。さらに、新人発掘を目的とした助成制度と、実績のあるクリエイター向けの制度を分類して、より効果的な制度設計を行う必要性も指摘されています。
3. 新たな資金調達手段の活用と制度整備
新たな資金調達手段として、クラウドファンディングや海外事業者からの資金調達の活用が重要視されています。クラウドファンディングは、新たな映像製作の機会創出に繋がり、海外事業者からの資金調達は海外展開の強化に繋がる可能性があります。また、ヨーロッパなどで行われている国際共同製作も、製作費調達の手法として有効です。 さらに、民間事業者の自助努力を促すための制度整備も必要です。税制・会計制度や投資関連法制を含め、継続して映画制作ができるような環境を整備していくことが求められています。 これらに加え、多様性のある映像作品を継続的に生み出すための支援も重要です。興行的な成功を優先すると切り捨てられがちなストーリーや表現技術の育成にも目を向け、支援策を検討する必要があります。 政府は、これらの課題に対応するため、既存施策の見直しや新たな施策の導入を積極的に検討していく必要があるでしょう。
III.海外展開戦略 市場開拓と課題克服
日本映画の海外展開は、国内市場の縮小を補い、製作費回収の基盤を拡大するために不可欠です。 アニメーションは国境を越えやすい特性を持つため、中国市場を中心としたアジア市場への進出が期待されています。 しかし、ハリウッド映画のように全世界をターゲットとするには、マーケティング戦略の高度化と、国際共同製作といった新たな手法の活用が必要となります。また、海賊版対策や、契約慣行の違いによるトラブル防止のための体制強化も重要です。政府は、市場開拓の基盤づくり、規制への対応、海賊版対策などを支援する役割を担います。具体的には、文化交流事業の強化、法制・会計面の専門家による支援体制の構築などが挙げられます。 日本の知的財産(IP)保護も重要な課題です。
1. 海外展開戦略の必要性とターゲット市場
日本映画産業は、国内市場の縮小という課題に直面しており、海外展開の強化が不可欠となっています。2016年には過去最高の興行収入を記録するなど、国内市場にも潜在力はありますが、人口減少という長期的な課題を考慮すると、海外市場への進出は、製作費の回収と産業の持続的な発展のために必須です。検討会議では、今後の海外展開戦略について議論が行われ、中国を中心としたアジア市場への進出が重要視されました。アジア圏、特に中国市場は日本映画を受け入れる潜在力があるとされ、アニメーション分野での選択と集中が戦略として提案されています。具体的には、アニメフェアやコミコンなどのイベントを集中開催し、ビジネスにつなげるアプローチが有効だと考えられています。一方、北米市場においては、従来の日本映画そのままの輸出ではなく、企画段階からのアプローチが必要と指摘されています。ハリウッド映画の成功事例から、全世界をターゲットとしたマーケット拡大の重要性も強調されています。
2. アニメーションと実写映画の海外展開戦略の違い
アニメーション映画は、実写映画と比べて国境を越えやすいという特性があります。そのため、急成長する中国市場の取り込みに加え、全世界をターゲットとした展開が期待されています。配信プラットフォームの積極的な活用や、マーチャンダイズとの連携による収益拡大も有効な戦略となります。一方、実写映画の海外展開は、アニメーションと比べて難易度が高いとされています。 海外展開の手法としては、日本市場向けの映画をそのまま輸出する方法と、グローバル市場向けに新たに制作する方法の2つがあります。後者には、日本原作のリメイクやアダプテーション、国際共同製作などが含まれます。 国際共同製作は、製作費調達手段の一つとして有効ですが、日本側から出資を申し込んでも、国内興行への制約などを理由に断られるケースもあることが指摘されています。中国市場への進出においては、政府の後押しが期待されています。
3. 質的 量的拡大に向けた課題と政府の役割
日本映画の海外展開を質的・量的に拡大するためには、新たな市場開拓、規制への対応、海賊版対策など、政府による支援が不可欠です。 具体的には、日本映画の認知度向上のための文化交流事業の強化などが有効だと考えられています。また、海外展開を行う事業者に対するサポート、法制・会計面の専門家による支援体制の構築などが提案されています。 日本のコンテンツの海外展開における課題として、権利保有者の分散や海外展開先のコントロール不足などが指摘されています。そのため、海外展開を目指すコンテンツについては、権利を一元管理する仕組みや、売上を一元管理する取り組みなどが重要となります。 さらに、海賊版対策も重要な課題です。政府は、諸外国との連携強化、中国などの外国政府・機関への働きかけなどを継続していく必要があります。中小制作会社が海外展開を行う際に起こりうるトラブルを未然に防ぐため、契約慣行の違いや関係法令に関する専門家によるサポート体制の強化も重要です。
IV.撮影環境と地域活性化 フィルムコミッションの役割
映画撮影においては、良好なロケ環境が不可欠です。全国に約300存在するフィルムコミッションは、撮影支援を行うことで地域活性化に貢献しています。しかし、許認可手続きの煩雑さや、諸外国に比べてインセンティブ(製作費の助成や税額控除)が不足している点が課題です。 政府は、許認可手続きの円滑化、オープンセットの整備、国民の理解促進などを通して、撮影環境の改善に取り組む必要があります。また、ポスプロ施設の強化も重要です。 海外作品誘致のためのインセンティブ導入も検討課題の一つです。
1. フィルムコミッションの現状と役割
日本各地には、映画や映像制作のロケーション誘致・支援を目的としたフィルムコミッションが設立されており、2000年以降増加を続け、現在では全国で約300のフィルムコミッションが活動しています。2009年には、NPO法人ジャパン・フィルムコミッションが設立され、海外対応強化なども行われています。フィルムコミッションは、撮影場所の提供や許認可手続きの支援、地域住民との調整など、多岐にわたる支援を行っています。 邦画の興行収入ベスト32作品のうち、実写作品22本のうち21本でフィルムコミッションの支援があったというデータからも、その活動の広がりと重要性が示されています。しかしながら、国内の撮影環境は諸外国と比べて必ずしも充実しているとは言えず、日本を舞台にした海外作品が、諸外国で撮影されるケースが多いことも指摘されています。これは、日本のロケ環境の課題を示唆するものです。
2. ロケーション支援における課題と改善策
日本のロケーション支援は、政府レベルではロケ情報の提供や地域振興のための支援策などが行われています。地方自治体レベルでは、ロケ誘致のための助成金などが提供されている地域もあります。しかし、諸外国では、製作費の15~20%を助成または税額控除するインセンティブ制度が導入されており、この制度の有無がロケ地の選定に影響を与えていると指摘されています。 検討会議では、日本のロケ環境整備に向けて、①許認可手続きの円滑化、②海外作品の誘致強化、③映像コンテンツを活用した地域振興促進の3つの観点から議論が行われました。具体的な課題としては、許認可手続きの複雑さや、住民からのクレームによるロケ時間の短縮、インセンティブ制度の不足などが挙げられています。 改善策として、許認可手続きの円滑化、オープンセットの整備、国民の理解促進のための啓発活動、そして海外作品誘致のためのインセンティブ導入などが提案されています。ニュージーランドの『ロード・オブ・ザ・リング』の成功事例を参考に、ポストプロダクション用のスタジオ整備も検討課題となっています。
3. 撮影環境改善と地域経済への波及効果
より良い撮影環境の整備は、映画産業の発展に大きく貢献します。 具体的には、許認可手続きの簡素化、予見可能性の向上、オープンセットの整備といった行政側の取り組みが不可欠です。また、住民の理解と協力も必要不可欠です。 海外作品誘致の強化は、国内での撮影機会を増やすだけでなく、経済的な効果も期待できます。ロケによる宿泊費、飲食費、雇用創出といった直接的な経済効果に加え、継続的なロケ誘致による周辺産業の育成、そして日本の地域や都市の魅力を発信することで国内外の観光客誘致につながるといった間接的な効果も期待できます。 これらの効果は、地域経済の活性化に大きく貢献するでしょう。 しかし、現状の道路使用許可の運用では、ロケ撮影が難しいケースも多く、許認可取得のプロセスにおける予見可能性を高めるためのマニュアル作成なども必要です。
V.人材育成 持続可能な映画産業への投資
映画産業の持続的な発展には、優れたクリエーターとスタッフの育成が不可欠です。 人材育成は、個社レベルでは限界があるため、政府による長期的な支援が求められます。 文化庁や経済産業省による既存の人材育成事業の継続・改善に加え、現場で求められる人材像を明確化し、教育機関との連携強化を図る必要があります。特に、監督、プロデューサー、撮影スタッフなど、多様な分野における人材育成が重要です。
1. 人材育成の重要性と現状
日本の映画産業の持続的な発展のためには、人材育成が不可欠です。優れた監督、プロデューサー、撮影スタッフなど、多様な分野で活躍できる人材の育成なくして、魅力的な作品を生み出し続けることは困難です。 しかしながら、現状では、特に中小制作会社においては、人材育成に十分な投資を行うことが難しい状況です。個々の企業レベルでは中長期的な視点に立った人材育成は限界があり、政府による支援が求められています。 文化庁や経済産業省では、人材育成のための事業を実施していますが、成果が現れるまでには数年から10年程度の時間を要する長期的な取り組みであるため、継続的な支援と評価・改善が重要となります。 これらの事業は開始から5~10年を経てようやく成果が出始めつつある段階であり、政府は継続的な支援と、常に評価・改善を加えながら、息長く事業を継続していく必要があります。
2. 政府による人材育成支援策と課題
政府による人材育成支援策としては、文化庁の「日本映画製作支援事業」や経済産業省による「国際コンテンツビジネスプロデューサー」育成事業などが挙げられます。 しかし、これらの支援策だけでは十分ではなく、より体系的な人材育成システムの構築が求められています。 具体的には、業界全体で必要とされる人材像を明確化し、教育機関との連携を強化することで、教育内容やカリキュラムの改善を図る必要があります。 また、諸外国では映画に関する高等教育機関が業界内で高い評価を得ているケースもあり、日本においても映画分野の専門課程を持つ教育機関との連携強化が重要です。 さらに、新人発掘を目的とする助成制度と、実績のある監督・プロデューサー等に対する助成制度を組み合わせることで、育成の段階に応じた効果的な支援体制の構築が必要とされています。 一定の実績のある者に対しては、リスクマネーの供給といった仕組みも有効と考えられます。
3. 中長期的な視点に立った人材育成への投資
人材育成は、すぐに成果が出るものではなく、中長期的な視点に立った投資が必要です。中小制作会社は、規模が小さく、中長期的な人材育成への投資には限界があるため、政府による継続的な支援が不可欠です。 政府は、人材育成事業の継続的な実施に加え、常に評価と改善を行いながら、より効果的な支援策を検討していく必要があります。 映画産業全体の活性化、ひいては日本の文化芸術の発展のためにも、人材育成は重要な投資であり、政府、業界関係者双方による継続的な取り組みが求められています。 映画業界自身も、日々の事業活動の中で、次世代を担う人材育成に真剣に取り組み、持続可能な発展のための基盤を築いていく必要があります。
