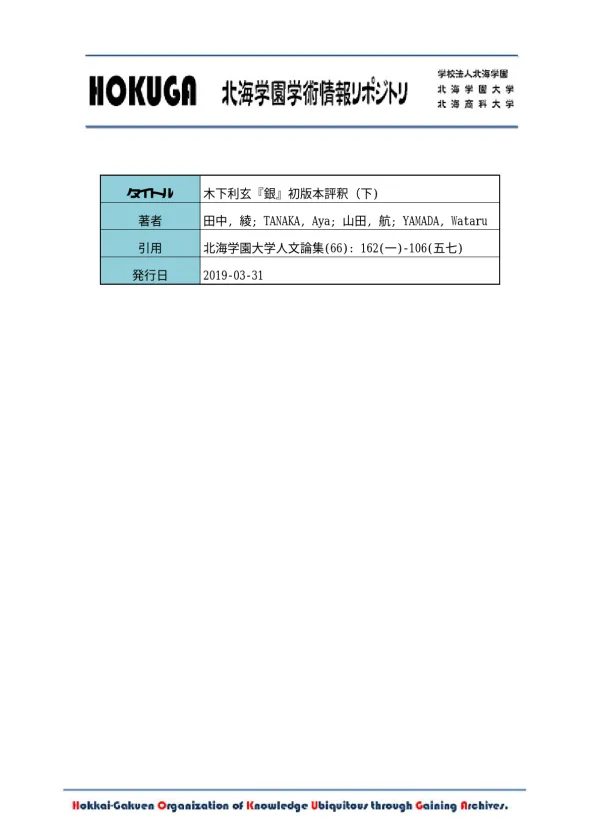
木下利玄「白樺」歌集研究
文書情報
| 著者 | 田中 綾 |
| 学校 | 北海学園大学 |
| 専攻 | 人文科学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.19 MB |
概要
I.木下利玄歌集 銀鑞 初版本評釈 主要作品と分析
本稿は、木下利玄の第一歌集『銀鑞』初版本を詳細に評釈した研究論文の要約です。初版本は逆年順に編纂されており、その編集意図を検証しています。分析対象は主に明治・大正時代に白樺や心の花といった雑誌に掲載された短歌です。 重要なキーワードとして、木下利玄、銀鑞、白樺、心の花、短歌が挙げられます。 分析では、各歌の初出情報(白樺、心の花、学習院輔仁会雑誌など)と、現代の定本との比較、また、歌に込められた作者の心情や当時の社会情勢との関連性が考察されています。 取り上げられている歌の題材は多岐にわたり、自然風景(夏草、樫の木、月見草、野茨、桐など)、都市風景(停車場、山の手、築地など)、人物描写(茶屋女、舞姫など)、そして作者自身の心情などを反映しています。 特に注目すべき点は、歌集の構成における作者の意図、すなわち逆年順による精神的な遡航の試みです。 本稿は、各歌の簡潔な解説と、初出情報に関する訂正も提示しています。
1. 初夏 自然の描写
このセクションでは、木下利玄の初期の短歌、特に初夏の自然を鮮やかに描写した作品群が分析されています。歌番号205「初夏の真昼の野辺の青草にそのかげおとし立てる樫の木」は、白樺誌三巻七号に掲載された作品で、初夏の日差し、野辺の青草、そして遠くに見える樫の木という構図が、丁寧な写生に基づいた表現によって描かれています。 田中綾と山田航は、時間(真昼)、近景(青草)、遠景(樫の木)という視覚的な構成を指摘し、初夏の生命力あふれる情景を的確に捉えていると評価しています。一方、歌番号211「夏草のにおひの中にたゞずみ物思ひ居れば日のかげろへる」は、夏草の香りの中で物思いにふける様子を描写。初出は白樺誌三巻七号で、この歌の背景には、同年秋に誕生予定だった子のことを思案していた心情が読み取れます。 これらの作品は、自然描写における木下利玄の繊細な観察眼と、自然と自身の内面を結びつける表現力の高さを示しています。 特に、初夏の爽やかさと生命力、そして静寂な時間の中で芽生える内省的な感情が、具体的な情景描写と相まって効果的に表現されている点は注目に値します。また、歌集未収録の作品も分析されており、歌集編集における作者の意図を探る上で重要な手がかりとなっています。
2. 都市風景と人間模様
本セクションでは、都市における生活や人々の様子を描写した短歌が取り上げられています。歌番号209「汽車とまり汽車の出で行く停車場のダリアの花の昼のくたびれ」は、白樺誌三巻八号に掲載。忙しい停車場の昼間の情景と、くたびれたダリアの花を対比させることで、近代都市の喧騒と自然の静けさとの対比が表現されています。 駒込駅開業の時期を考慮すると、利玄にとって新しい停車場であったことが分かります。 また、歌番号217「茶屋女団扇持つ手の汗ばみの昼のけだるさきりぎりすなく」は、心の花誌に掲載され、茶屋女の汗ばむ手で団扇を持つけだるい昼間の情景と、初秋の季語であるきりぎりすの鳴き声を組み合わせることで、典型的な東京の夏の昼間の風情が描写されています。 これらの作品は、近代都市における人間模様や、都市生活に潜む様々な感情を、繊細な視点で切り取っている点が特徴です。 山の手という、当時の東京における特定の地域性も意識されており、その地域独特の雰囲気や人々の生活が歌に反映されていると考えられます。 また、歌集の編集において、これらの都市風景を描いた作品がどのように配置されているかについても考察されています。
3. 花の描写と象徴性
木下利玄の作品における花の描写は、単なる自然描写にとどまらず、象徴的な意味合いを持つことが本セクションで示されています。 歌番号207「菊に似し白き小花を多くつけ夏草しげる汽車みちの堤をばなどて」では、汽車道の堤に咲く菊に似た白い小花が描写され、大正時代の鉄道の普及という近代的な風景と、名も知られぬ小花の美しさとの対比が示唆されています。 一方、歌番号246「花びらの真紅の光沢に強き日を照り返し居る雛芥子の花」では、雛芥子の鮮やかな真紅と強い日差しを照り返す様子が、生命の力強さを象徴的に表現しています。 さらに、歌番号248「しほらしき野薔薇の花を雨はうつ たたかれで散るほの白き花」では、雨に打たれて散る野薔薇の儚げな美しさが、人間の生と死、あるいは過ぎ去る時間の流れといったテーマと関連付けられています。 これらの作品を通して、木下利玄が花を単なる被写体としてではなく、様々な感情や象徴性を託す媒体として巧みに用いていることが分かります。 また、歌集における花の配置や、同一の花を異なる歌でどのように表現しているかなど、細やかな分析を通して、木下利玄の創作上のこだわりや意識が明らかになります。
4. その他の主題と象徴的表現
このセクションでは、自然や都市風景、人物描写といった主要な主題に加え、より個人的な心情や、象徴的な表現を用いた作品群が分析されています。例えば、歌番号224「風触れず指尖暑き繃帯を君苦にしつヽ寝寝がてにするい」では、指を負傷した恋人を案じる心情が表現され、具体的な情景描写を通して、作者の深い愛情が伝わってきます。 また、歌番号252「愛に酔ふ雌蕊雄蕊を取り囲むうばらの花をつつむ昼の日」では、野茨の花の中心にある雌蕊と雄蕊を「愛に酔う」と擬人化し、小さな花の中心から昼間の太陽へと視点を広げることで、自然の生命力と生々しいエネルギーが表現されています。さらに、歌番号273「おんな坂袖もつれあふまひ姫がかすみになるヽ朝詣かな」では、築地西本願寺の女坂を朝霞に濡れながら歩く舞姫の美しい姿が描写され、独特の情景描写を通して、伝統的な祭りの雰囲気と、近代都市の空気感が交錯する独特の空間が表現されています。 これらの多様な主題と、比喩や擬人化といった高度な表現技法を用いた作品群を通して、木下利玄の表現力の豊かさや、多様な視点が示されています。 歌集におけるこれらの作品の配置や、初出情報の検証についても、重要な分析対象となっています。
II.主な掲載誌と関連人物
『銀鑞』に収録された短歌の多くは、白樺と心の花という二つの重要な文学雑誌に掲載されていました。 白樺派との関連も深く、その影響が歌風にも見られます。 また、心の花は曙会という歌会と関係しており、佐々木信綱など著名な歌人が関わっていたことがわかります。 これらの雑誌や歌会における掲載情報、およびその時期は、本研究における重要な情報源となっています。
1. 白樺誌と心の花誌 主要な掲載誌
木下利玄の短歌は、主に『白樺』誌と『心の花』誌に掲載されていました。 これらの雑誌は、木下利玄の作品発表において極めて重要な役割を果たしており、多くの作品が両誌に掲載されていることが、本稿の分析から明らかになっています。 『白樺』誌は、その名の通り白樺派の同人誌として知られており、木下利玄の作品が白樺派の文芸運動にどのように関わっていたのか、その位置づけを検討する上で、『白樺』誌への掲載状況は重要な情報となります。 掲載時期や掲載された巻数、号数などは、作品分析、および木下利玄の創作活動の変遷を辿る上で不可欠な要素です。 一方、『心の花』誌は、『白樺』誌とは異なる文脈、特に曙会という歌会との関連において、木下利玄の作品がどのように位置づけられていたのか、その背景を探る上で重要な資料となります。 同じ歌が『白樺』誌と『心の花』誌の両方に掲載されているケースもあり、同人誌と所属歌会の雑誌の両方に投稿する行為が、現代の歌壇ではあまり認められない慣習である点も、興味深い点として指摘されています。
2. 曙会と佐々木信綱 歌会との関わりと評価
『心の花』誌との関連において、曙会という歌会が重要な役割を果たしていたことが本稿で示されています。 曙会は、佐々木信綱など当時著名な歌人が参加していた歌会であり、木下利玄の作品も曙会で詠まれていたことが確認できます。 曙会での作品発表は、木下利玄の作品が、当時の歌壇においてどのように評価され、どのような影響を受けていたのかを解明する上で重要な手がかりとなります。 本稿では、曙会の歌会で詠まれた作品と、『白樺』誌や『心の花』誌に掲載された作品との比較検討が行われ、作品における表現方法や主題の変化、そして歌集編集における作者の意図など、多角的な分析が行われています。 佐々木信綱による木下利玄の作品評も引用されており、彼の評価が、木下利玄の作品理解にどのような影響を与えているかについても検討されています。 特に、佐々木信綱が木下利玄の作品に対して行った評価やコメントは、当時の歌壇における木下利玄の作品の位置付けや、彼の作風の特徴を理解する上で貴重な情報源となっています。 これらの情報から、木下利玄の創作活動と、当時の歌壇における文芸状況との関連性をより深く理解することができます。
3. 学習院輔仁会雑誌 その他の掲載誌
『白樺』誌や『心の花』誌に加え、『学習院輔仁会雑誌』にも木下利玄の作品が掲載されていたことが、本稿の分析から明らかになっています。 これは、木下利玄の創作活動の幅広さを示す重要な情報であり、彼の作品が、どのような多様な媒体を通じて発表されていたのかを理解する上で重要な要素となります。 『学習院輔仁会雑誌』への掲載は、他の雑誌への掲載と比較することで、木下利玄の作風や主題に変化が見られるか、あるいは、異なる読者層を意識した表現の変化が見られるかどうかといった点を分析する上で、重要な比較対象となります。 本稿では、『学習院輔仁会雑誌』に掲載された作品についても、初出情報や、作品の内容、そして歌集編集におけるその位置付けなどが詳細に検討されています。 これらの分析を通して、木下利玄が様々な雑誌に作品を発表することで、自らの作風や表現をどのように模索し、展開させていったのか、その創作活動の多様性と奥深さが明らかになってきます。 また、各雑誌の特性や読者層を考慮することで、木下利玄の作品が、それぞれの媒体においてどのように受け止められ、評価されていたのかについても推測することができます。
III.歌集 銀鑞 の構成と編集意図
『銀鑞』は299首の短歌を収録し、逆年順に編纂されている点が特徴です。この編集方法には、木下利玄自身の精神的な回顧、過去の自分への遡航という意図が読み取れます。 最後の1首は常に「現在の自分」によって補完されるものとして意識されていた可能性があり、利玄独自の構成意識と編集意図が強く反映されています。 この逆年順の構成は、現代の木下利玄全集のような編年体とは大きく異なり、初版本独自の価値を示しています。
1. 逆年順の構成と編集意図
『銀鑞』歌集の最も顕著な特徴は、歌の掲載順が逆年順である点です。現代に流通する編年体で構成された定本とは大きく異なり、この逆年順の構成は、単なる偶然ではなく、木下利玄自身の明確な編集意図に基づいていると推測されます。 論文では、この逆年順の構成が、木下利玄の精神的な遡行、つまり、最新の作から過去の作品へと精神的に時間を遡る試みを示している可能性を指摘しています。 岩手の一関の旅情から始まり、学習院高等科卒業年である明治39年の作品へと至る構成は、この仮説を支持する根拠となります。 また、歌集の収録歌数が299首という一見中途半端な数字も、残りの一首は常に「現在の自分」によって補完されるものとして意識されていた可能性を示唆しており、この点も利玄独自の構成意識と編集意図を反映していると解釈できます。 この逆年順という独自の構成法は、単なる作品集ではなく、木下利玄自身の内面世界を反映した、一種の自伝的な作品集としての側面を強く示唆しています。 従来の編年体とは異なるアプローチによって、読者は作品群を通して、木下利玄の精神的・時間的変遷を深く理解できる構成となっていると言えます。
2. 歌集構成における細部への配慮
歌集の構成は、逆年順という大枠に加え、細部においても木下利玄の意図が見て取れる点が指摘されています。 例えば、同じ時期に異なる雑誌に掲載された歌の配置や、特定のテーマに関連する歌の集中的な配置など、歌集全体の構成には、単なる時系列順ではなく、ある種の意図的な配置が見られます。 これは、単に過去作品を洗い出しただけでなく、木下利玄が徹底的に構成を練り上げ、全体として意味のある構成を意識していたことを示唆しています。 また、歌集に未収録の作品が存在する点も、編集意図を考察する上で重要な要素となります。 未収録作品の存在は、木下利玄が歌集に収録する作品を厳選する際、どのような基準を用いたのか、そして、歌集全体としてどのようなメッセージを伝えたいと考えていたのかを考察する上で、重要な情報となります。 これらの細部への配慮は、歌集『銀鑞』が、単なる作品集ではなく、木下利玄の思想や感情を深く反映した、意図的な構成を持つ作品集であることを示しています。 これらの分析によって、一見、単純な逆年順に思える歌集構成の裏に隠された、木下利玄の深い創作意識と、作品への強いこだわりが浮かび上がってきます。
3. 初版本と定本との比較
本稿では、現在流通している『定本木下利玄全集』などの編年体で構成された歌集との比較を通して、初版本『銀鑞』の構成上の独自性を強調しています。 編者によって歌順が編年体へと変更された定本とは異なり、初版本は逆年順に編纂されている点が大きく異なっています。 この違いは、歌の理解や解釈に影響を与えうる重要な点であり、初版本に込められた木下利玄の意図を理解する上で欠かせない要素となります。 初版本と定本を比較検討することで、歌の配置順序の違いが、作品全体の印象や、個々の歌の持つ意味合い、そして作者の意図の解釈にどのように影響を与えるかを分析することができます。 この比較を通して、木下利玄が意図的に逆年順を選んだ理由、そしてその構成法が、読者へのメッセージとして、どのように機能しているのかを解明する試みがなされています。 初版本『銀鑞』の独自性をより明確に理解し、木下利玄の創作活動や思想を深く理解するための、重要な比較分析となっています。
IV.初出情報の検証と訂正
本研究では、各歌の初出情報を徹底的に調査し、既存の資料(例えば『木下利玄集』日本近代文学大系)に誤りがある箇所を指摘し、正確な初出情報を提示しています。 具体的には、掲載誌名、掲載号、掲載年、歌題などを検証し、必要に応じて訂正を行っています。これは、木下利玄研究において重要な基礎資料となります。
1. 各歌の初出情報の精査
本稿の重要な目的の一つは、木下利玄の短歌の初出情報を正確に特定することです。『銀鑞』歌集に収録されている各歌について、初出誌名、巻数、号数、発行年などを詳細に調査し、その結果を提示しています。 この作業は、一見単純な作業のようですが、既存の研究資料に誤記が存在するケースも多く、正確な情報の検証が極めて重要になります。 実際、本稿では既存の研究資料である『木下利玄集』(日本近代文学大系)などに記載されている初出情報に誤りが見つかり、それらを訂正する形で正確な初出情報を提示しています。 例えば、特定の歌が複数の雑誌に掲載されている場合、その掲載順序や時期の違いなども詳細に検討され、初出情報の正確性を高めるための綿密な調査が行われています。 これらの精査された初出情報は、木下利玄の創作活動の解明や、作品間の関連性の分析に不可欠な基礎資料となります。 正確な初出情報を基に、作品間の繋がりや、創作活動における変化などをより詳細に考察できるようになっています。
2. 既存資料との比較と訂正の必要性
本研究では、既存の研究資料、特に『木下利玄集』(日本近代文学大系)などの初出情報と比較検討を行い、その結果に基づいて訂正を行う作業も行われています。 既存の資料は、研究の進展や情報の更新によって、必ずしも常に正確であるとは限りません。 本稿では、そのような既存資料に含まれる誤りを指摘し、より正確な初出情報を提示することで、今後の木下利玄研究の基礎資料として役立つことを目指しています。 この作業を通して、初出情報の精査の重要性、そして既存資料を批判的に吟味する必要性が改めて強調されています。 単に既存資料をそのまま受け入れるのではなく、複数の資料を比較検討し、矛盾点を洗い出すことで、より信頼性の高い情報を提示することが、学問研究においては不可欠であることが示されています。 『白樺』誌、『心の花』誌、『学習院輔仁会雑誌』など、複数の雑誌に掲載された作品について、それぞれの初出情報を詳細に検証し、必要に応じて訂正を加えることで、より正確な木下利玄の作品史を構築するための基礎が築かれています。
3. 初出情報に基づく作品理解の深化
初出情報の検証と訂正は、単なる事実確認にとどまらず、作品理解を深める上でも重要な役割を果たしています。 正確な初出情報に基づいて作品を分析することで、その作品が書かれた背景、そして木下利玄の創作活動における位置付けなどをより深く理解することが可能になります。 例えば、同じ歌が複数の雑誌に掲載されている場合、その掲載時期や雑誌の特性などを考慮することで、木下利玄がそれぞれの雑誌の読者層を意識して、作品の内容や表現方法を変えていた可能性などが推測できます。 また、初出情報と作品の内容を詳細に比較することで、作品に込められた作者の心情や、当時の社会状況との関連性などをより深く考察することができます。 本稿では、これらの分析を通して、木下利玄の作品世界を多角的に理解し、より深い考察を行うための基礎を築いています。 初出情報という一見地味な情報にも、作品理解を深める上で重要な手がかりが隠されていることを示す、重要な研究となっています。
