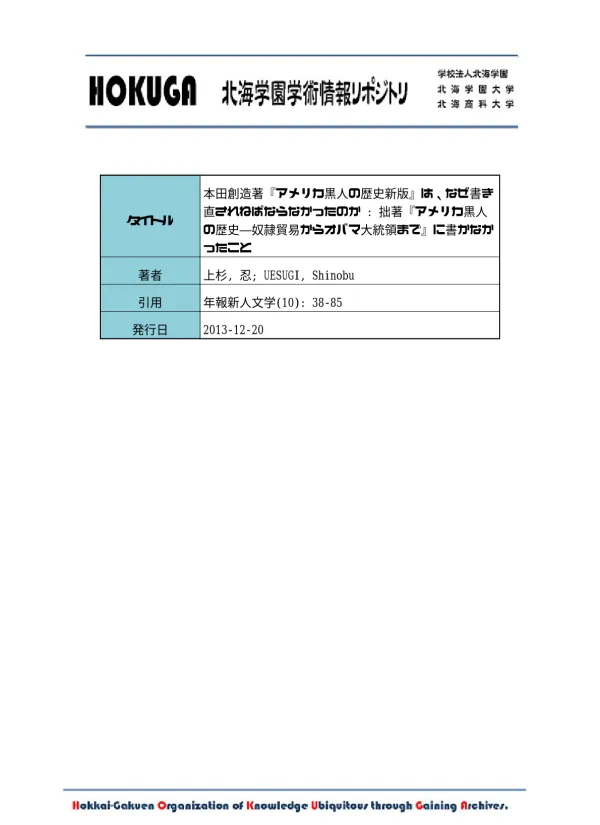
本田『アメリカ黒人史』改訂の必然性
文書情報
| 著者 | 上杉忍 |
| 学校 | 不明 |
| 専攻 | 歴史学 |
| 場所 | 不明 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 588.16 KB |
概要
I.アメリカ黒人史における抵抗と抑圧 本田氏の解釈への批判的考察
本書は、本田氏のアメリカ史に関する著作を批判的に分析したものである。特に、アメリカ黒人の奴隷制と公民権運動に関する記述に焦点を当て、その歴史認識の妥当性を検証している。本田氏は、黒人を単なる抑圧された存在としてではなく、アメリカ社会の矛盾をいち早く示す「カナリア」として捉えているが、その分析にはマルクス主義的歴史観の影響が強く、南北戦争、再建期、プランテーション制度といったキーワードにおける解釈に問題点があることが指摘されている。例えば、プランテーション奴隷制を「前近代的」と断定する点や、黒人の抵抗運動の規模や影響力を過小評価している点が批判されている。また、独立革命、合衆国憲法、ジェファーソンの奴隷問題に関する記述の正確性も疑問視されている。
1. 本田氏のアメリカ黒人史観 カナリアのメタファーと問題点
本田氏は新著において、アメリカ黒人をアメリカ社会の矛盾をいち早く示す「カナリア」として位置づけ、単なる抑圧された存在としてではなく、社会変革の最前線に立ってきた主体として捉えています。南北戦争、再建期、公民権運動においても、黒人の行動はアメリカ社会全体の変革を促す力として描写されています。しかし、この「カナリア」のメタファーは、潜在的に危険な歴史観を孕んでいる可能性が指摘されています。それは、あたかも歴史に予め定められた発展法則があり、黒人の経験はその法則を反映するものとして解釈されている点です。これは、マルクス主義的歴史学における「世界史の発展法則」への信仰と類似しており、価値判断に影響を与えかねない危険性を抱えていると批判されています。さらに、アフリカ人奴隷貿易についても、単なる暴力的な略奪行為としてではなく、商品交換という経済メカニズムの中で捉えることの重要性が強調されています。
2. プランテーション奴隷制と 前近代的 という規定 資本主義との関係性
本田氏は、奴隷制プランテーションを「前近代的な搾取制度」と規定し、近代的資本主義とは異なる性格を持つものとしています。奴隷労働は不自由労働であり、労働力の商品化は行われていないと主張しています。この見解は、本田氏が「労働力の商品化」を近代の第一の指標として位置付けていることに基づいています。しかし、この「前近代的」という規定は、南北戦争・再建期の革命を「第三のブルジョア民主主義革命」として位置づける論理と深く結びついており、近代資本主義の成立過程におけるプランテーション奴隷制の役割を十分に考慮していないとの批判がなされています。また、1830年代以降、奴隷価格の高騰に伴い、奴隷の生活水準が改善されたという事実も考慮されていない点が指摘されており、本田氏の段階区分が乱暴であると批判されています。 さらに、この「前近代的」な生産関係の克服が近代化の鍵となるという本田氏の論理は、内在的発展を重視する特殊日本的マルクス主義の目的意識に縛られている可能性も示唆されています。
3. 独立革命期における黒人の役割 誤ったジェファーソンの記述と憲法の解釈
本田氏は、独立革命期において自由黒人が植民地議会に請願を行った事実を指摘しますが、独立宣言起草者であるジェファーソンが自身の奴隷をほとんど解放したという記述は事実誤認だと批判されています。実際には、ジェファーソンは治安維持のため奴隷の解放を規制すべきだと主張しており、一部の奴隷の解放はあったものの、大部分の奴隷は解放されていませんでした。また、合衆国憲法の解釈においても、本田氏は憲法によって北部と南部で異なる社会・政治制度が生まれたと述べていますが、憲法が奴隷制を容認した事実を南部プランターの勝利として片付けている点が問題視されています。この憲法の解釈をめぐっては、奴隷制廃止主義者ウィリアム・ロイド・ギャリソンと黒人指導者フレデリック・ダグラスの対立も重要な視点となります。
II.南北戦争と再建期の黒人 自由と抑圧の狭間
南北戦争と再建期における黒人の役割と経験について、本田氏の記述における偏りや誤りが指摘されている。特に、黒人と貧しい白人の同盟による民主的改革が着実に進展したという記述には疑問が呈され、実際には元奴隷所有者の圧倒的な力関係、共和党の対応、そして黒人に対する暴力や抑圧がより重視されるべきだと主張されている。また、ユニオンリーグの役割や影響力に関する記述についても、より詳細な分析が必要であるとされている。重要な人物として、エイブラハム・リンカーン、そして再建期における黒人指導者たちが挙げられる。
1. 再建期の黒人と貧しい白人の同盟 理想と現実の乖離
本田氏は、再建期において黒人と貧しい白人が同盟を結び、民主的な改革を進めたと主張しています。1865年夏から秋にかけて、南部各地で大規模な大衆集会が開催され、貧しい白人も積極的に参加したと記述されています。さらに、この民主的改革の進展が、戦時ブームで成長した産業資本家を脅かし、再建運動の妨げになったと述べられています。しかし、この記述は再建期における実際の力関係を正しく反映していないと批判されています。経済的にも軍事的に、情報面においても、元奴隷所有者が圧倒的に優位に立っており、連邦軍の力は限定的でした。共和党州政府も財政難に苦しみ、独自の政策を展開する力は弱かったと指摘されています。黒人にとって重要なのは身の安全の確保であり、そのためには司法制度の民主化が不可欠でしたが、南部白人武装集団による暴力と共和党への攻撃によって、民主的改革は思うように進展しなかったと反論されています。
2. ユニオンリーグと黒人の政治参加 効果と限界
本田氏は、南北戦争中から共和党急進派によって設立されたユニオンリーグが南部に深く根を下ろし、最盛期には50万人の会員数を誇り、その多くが黒人だったと述べています。ユニオンリーグは黒人が政治に参加し、立法活動で成果を上げることを支援する役割を果たしました。しかし、この記述だけでは再建期南部の複雑な力関係が十分に理解できないと批判されています。経済的、軍事的に元奴隷所有者が圧倒的な力を持っていた現実、そして連邦政府の支援が限定的であった点を考慮すると、ユニオンリーグの活動は、黒人大衆の安全保障という最も重要な課題に対し、十分な効果を発揮できなかった可能性が高いと指摘されています。また、黒人代表が政治活動を展開したことは評価すべきですが、白人武装集団による暴力や共和党勢力への攻撃によって、自由な政治活動は阻害され、民主的な司法制度の確立は遅滞したと反論されています。
3. 北部共和党の対応と黒人見捨て 1874年の中間選挙とその後
北部共和党が南部黒人を事実上見捨てた原因として、1874年の中間選挙で下院の過半数を民主党が獲得したことが挙げられています。この結果、共和党は南部の黒人保護政策を縮小せざるを得なくなり、黒人に対する暴力や抑圧がさらに増大したとされます。しかし、この記述だけでは、北部共和党の対応の複雑さを十分に説明しきれていないと指摘されています。また、黒人農民同盟のような組織に関する記述についても、その規模や影響力に関する主張の根拠が不十分であると批判されています。オーガスト・マイヤーやウィリアム・ホルムズといった研究者の指摘を踏まえると、黒人農村住民の抵抗運動は、本田氏の主張よりもはるかに小規模で、その存在を示す証拠も少ないとされています。さらに、人種差別撤廃に向けた活動において、1930年代の左派労働運動の貢献も軽視されていると指摘されています。
III.世紀の黒人運動 公民権運動とその後
20世紀におけるアメリカ黒人の公民権運動に関する記述についても、本田氏の分析が不十分であると批判されている。大恐慌、ニューディール政策、第二次世界大戦といった重要な歴史的文脈が軽視され、1950年代以降の運動に焦点が当てられていることが問題視されている。また、1963年のワシントン大行進に関する記述においても、事実誤認や偏った描写が指摘されている。重要な人物として、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア、メドガー・エヴァース、そして黒人女性指導者たちが挙げられる。さらに、全国黒人向上協会 (NAACP)、人種平等会議 (CORE)、**南部キリスト教指導者会議 (SCLC)**といった組織の活動についても詳細な分析が求められている。
1. 1950年代以降の公民権運動 限定的な視点と歴史的文脈の欠如
本田氏の著作は、1950年代以降の公民権運動に焦点を当てていますが、それ以前の歴史的文脈、特に大恐慌、ニューディール政策、そして第二次世界大戦期の黒人の動向が十分に考慮されていないと批判されています。この欠落は、単なる時代の一部分の欠如ではなく、公民権運動の理解を歪める可能性があると指摘されています。近年では、公民権運動を1954年のブラウン判決以降の運動として捉える見方が批判されており、「長い公民権運動」論、すなわち1930年代の労働運動、特に共産党などの左派運動が黒人差別撤廃の活動に取り組み、戦後の公民権運動の基礎を築いたという視点が重視されるようになっています。本田氏の記述は、この「長い公民権運動」論を無視し、第二次世界大戦後の出来事のみを強調しているため、不十分であると指摘されています。大統領行政命令8802号や白人予備選挙憲法違反判決などにも触れられていますが、それらと戦後の教育の人種隔離撤廃裁判との関連性が不十分にしか示されていない点が批判されています。
2. 1963年ワシントン大行進 事実誤認と偏った描写
本田氏は、1963年のワシントン大行進を戦後黒人解放運動の頂点として熱っぽく描写していますが、その記述には事実誤認や偏った描写が含まれていると批判されています。例えば、マハリア・ジャクソンがゴスペルソングを歌い、エヴァース未亡人が演説し、参加者たちが感動のあまり涙を流したという記述は、実際にはエヴァース未亡人は演説しておらず、ジャクソンの歌唱も記述とは異なる時間に行われたという事実と矛盾しています。また、主要な黒人団体4団体のうち3団体(NAACP、CORE、SCLC)の代表の演説を紹介しながら、最もラディカルな学生非暴力調整委員会のジョン・ルイスの演説には触れていない点が指摘されています。ルイスは、連邦政府の対応を批判する発言をしていたにも関わらず、本田氏の記述ではそれが省かれており、この行進が当時のジェンダーロールに制約されていたという問題意識も欠如していると批判されています。さらに、行進の目的が、冷戦下のケネディー政権の許容範囲内で「国民の祭典」として開催され、経済的平等要求が抑制されたという重要な文脈も無視されている点が問題視されています。
3. 公民権運動後の黒人の動向 限定的な成功事例と問題点の無視
本田氏は、ローレンス・ダグラス・ワイルダーのヴァージニア州知事当選を、かつての奴隷制権力の象徴の地で黒人が成功した事例として取り上げていますが、これは公民権運動後の黒人の社会的地位の向上を限定的にしか示していないと批判されています。公民権運動の成果や、その後の黒人の社会進出についてより広い視点からの記述が求められています。また、公民権運動全体の成功を強調する一方で、運動が抱える問題点や限界についてはほとんど触れられていない点も指摘されています。全体として、本田氏の記述は、公民権運動を単なる成功物語として捉え、その複雑さや矛盾、限界を十分に反映していないと結論づけられています。
IV.ハイチ革命とラテンアメリカの独立運動 比較歴史的視点からの検証
本田氏の著作におけるハイチ革命とラテンアメリカの独立運動に関する記述についても、歴史的事実に反する点や不正確な解釈が指摘されている。ハイチ革命の成功がラテンアメリカの植民地解放運動に与えた影響を過大評価しているだけでなく、ラテンアメリカの支配層がハイチ革命に敵対的な立場をとっていた事実を無視している点が批判されている。重要な人物として、フランシスコ・デ・ミランダ、シモン・ボリーバルなどが挙げられる。
1. ハイチ革命の成功とラテンアメリカ独立運動 因果関係の誤謬
本田氏の記述においては、ハイチ革命の成功がその後ラテンアメリカ諸国を席巻した植民地解放闘争の突破口となったという主張がなされています。しかし、この主張は事実に反しており、無理のある解釈だと批判されています。実際には、ハイチ革命はラテンアメリカの支配階級に強い危機感を抱かせ、カウンターレヴォリューションを引き起こしました。『サン=ドマングの二の舞』を避けるため、現地支配層は先住民や黒人の抵抗を抑えるべく、むしろ「独立」運動を展開したとされています。浜忠雄氏の指摘を引用し、ハイチ革命に呼応するかたちで展開された解放運動はことごとく鎮圧され失敗に終わったとされています。その要因として、ハイチ革命に対する警戒心と、ハイチ型国家形成への忌避感が挙げられています。 このことから、ハイチ革命がラテンアメリカ独立運動の直接的な突破口になったという本田氏の主張は、歴史的事実と矛盾するとして否定されています。
2. ラテンアメリカ独立運動指導者たちのハイチ革命への敵対的姿勢
ラテンアメリカ独立運動の指導者たちが、ハイチ革命に対して敵対的な姿勢をとっていたという事実が、本田氏の記述では無視されていると批判されています。フランシスコ・デ・ミランダはハイチ革命を「流血と犯罪の舞台」と批判し、シモン・ボリーバルも「黒人の蜂起はスペインの侵略より千倍も有害だ」と述べていたことが例として挙げられています。これらの発言は、ラテンアメリカ独立運動が、ハイチ革命とは対照的に、支配階級による先住民や黒人の抵抗の抑制を目的として展開されたことを示唆しています。従って、ハイチ革命の成功をラテンアメリカ独立運動の直接的な要因とする本田氏の解釈は、ラテンアメリカにおける独立運動の実態を正確に反映していないと指摘されています。 これらの歴史的事実に基づけば、ハイチ革命とラテンアメリカ独立運動の関係性については、より複雑な分析が必要であることが示唆されます。
