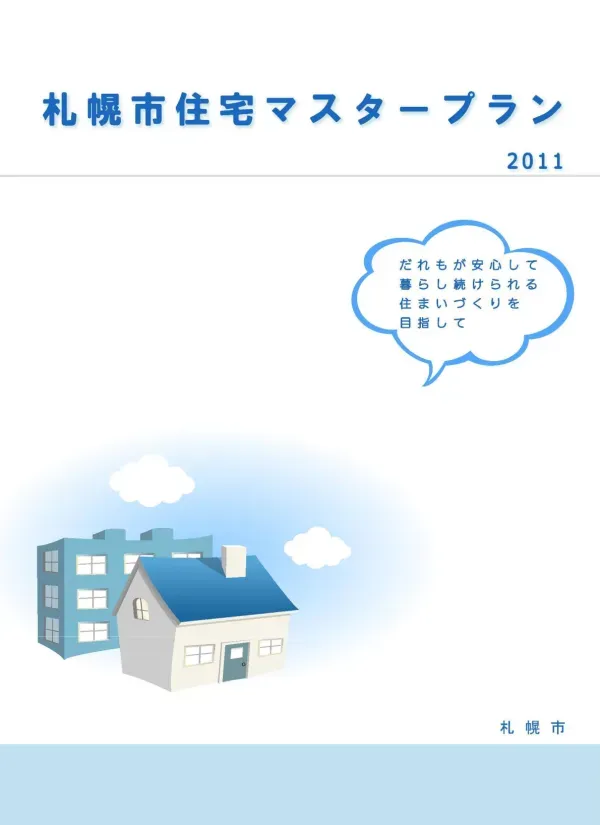
札幌市住宅マスタープラン
文書情報
| 著者 | 札幌市長 |
| 場所 | 札幌市 |
| 文書タイプ | マスタープラン |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.17 MB |
概要
I.札幌市住宅マスタープラン 現状と課題
本計画は、少子高齢化の急速な進展、人口減少、経済状況悪化といった社会情勢の変化を踏まえ、札幌市住宅政策を見直すため策定されました。特に、高齢者住宅、子育て世帯住宅、障がい者住宅の確保、空き家対策、市営住宅の適切な管理・更新、民間賃貸住宅への入居支援が重要な課題として挙げられています。札幌市の人口は191万人(平成22年推計)で、高齢化率は20%を超えています。市営住宅の管理戸数は27,518戸(平成22年度末)ですが、老朽化が進んでおり、耐震化やバリアフリー化が急務です。住宅ストックの有効活用と質の向上が求められており、特に昭和55年以前に建築された住宅の耐震性能の向上が重要です。また、民間賃貸住宅においては、高齢者や子育て世帯が、身元保証人や広さの問題で入居を断られるケースが多く、入居支援の強化が必要とされています。
1. 人口減少と高齢化の進展
札幌市は、戦後急激な人口増加を経て、平成2年以降は増加率が鈍化し、平成22年には191万人(推計)となっています。しかし、少子高齢化の急速な進展と人口減少社会の到来が予測され、住宅政策の見直しが必要となっています。高齢化率は平成22年4月1日時点で20%を超え、介護保険による要介護・要支援認定者数は約6万7千人に達し、今後も増加傾向が見込まれます。この高齢化は、高齢者住宅の需要増加や、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域コミュニティによる支援の必要性を浮き彫りにしています。また、家族形態の変化や住宅確保を配慮すべき世帯のニーズの多様化も、住宅を取り巻く社会情勢の変化として挙げられます。
2. 市営住宅の現状と課題
平成22年度末時点で、札幌市の市営住宅の管理戸数は2万7518戸です。昭和40年代の人口急増期に建設された住宅の更新時期が到来しており、維持修繕や更新には莫大な費用が必要となります。しかし、低廉で良質な市営住宅の需要は依然として高く、新築住宅の応募倍率は40倍程度、既存住宅の空き家でも30倍程度と、高い競争率が続いています。既存の市営住宅では、バリアフリー対応住戸は全管理戸数の25.4%にとどまり、浴室未整備の住戸も1500戸以上残るなど、現在の居住ニーズに合致していない部分も多く、改善が必要です。省エネルギー化も課題で、二重サッシや複層ガラス窓は普及していますが、太陽光発電機器の普及は今後の課題となっています。
3. 民間賃貸住宅の現状と課題
札幌市では、昭和48年以降、住宅数が世帯数を上回り、空き家が増加し続け、平成20年には13万6千戸に達しています。特に築後10年以上経過した民間賃貸住宅の空きが目立ちます。これらの空き家の有効活用が今後の課題となります。一方、民間賃貸住宅市場では、高齢者や子育て世帯が、身元保証人や緊急連絡先がないこと、あるいは適切な広さの住宅が不足しているなどの理由で入居を拒否されるケースが多く、住宅確保要配慮者のニーズに対応できていない状況が指摘されています。アンケート調査では、札幌市内の住宅オーナーや不動産仲介業者の約6割が入居を断った経験があると回答しており、高齢者や外国人などが入居制限を受けている現状が明らかになっています。
4. 既存住宅ストックの課題と対策
平成20年時点で、札幌市には居住世帯のある住宅が約84万戸あり、そのうち持ち家が約41万6千戸、民営借家が約34万3千戸です。全体の約20%が昭和55年以前に建築された住宅で、耐震性能の向上が求められています。しかし、中古住宅市場では、住宅の品質や性能に関する情報不足、取得後の瑕疵や不具合に関する保証の不安などが課題となっており、市場の拡大にはこれらの課題の解消が必要です。また、昭和40年代から供給が始まった分譲マンションは平成19年に15万戸を超えましたが、古いマンションや小規模マンションを中心に長期修繕計画が整備されていないケースが多く、適正な維持管理と将来的な建替えへの備えが重要となっています。既存住宅の省エネルギー化、バリアフリー化、耐震化などによる住宅性能向上と、良質な住宅ストックの形成が求められています。
II.基本目標と基本方針 安心 快適な住環境の形成
本計画の基本目標は、①安心安全な住まいの確保、②良質な住宅ストックの形成、③安心・快適な住環境の形成です。基本方針として、市営住宅の適切な建替え・改修と既存民間賃貸住宅の有効活用、高齢者・子育て世帯・障がい者への居住支援、適切な住み替えの仕組みづくり、災害時の居住の安定確保などが掲げられています。特に、高齢者向けには、介護・医療と連携したサービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅の普及促進が重要視されています。また、省エネルギー住宅の普及に向け、「札幌版次世代住宅基準」を策定し、断熱・気密性能の高い住宅づくりを支援します。さらに、地域コミュニティの維持・活性化も重要課題として位置づけられています。
1. 三つの基本目標 安心 快適な住環境の実現
本計画の基本目標は、大きく分けて三つあります。一つ目は、高齢化社会や人口減少社会における不安を解消し、誰もが安心して暮らせる住まいを確保することです。二つ目は、既存の住宅を有効活用し、耐震性やバリアフリー化などの性能を向上させることで、良質な住宅ストックを形成することです。そして三つ目は、地域コミュニティの活性化を促進し、住み慣れた地域で安心して生活できる快適な住環境を形成することです。これらの目標達成に向け、高齢者、子育て世帯、障がい者など、様々な世帯のニーズに応じた具体的施策が計画されています。
2. 基本方針 多様なニーズへの対応と連携
計画では、上記の三つの基本目標を達成するための七つの基本方針が示されています。具体的には、市営住宅の適切な建替え・改修と既存民間賃貸住宅の有効活用、市営住宅の入居管理の適正化、高齢者に優しい住環境の形成、子育て世帯や障がい者への居住支援、民間賃貸住宅への入居支援、適切な住み替えの仕組みづくり、そして災害時の居住の安定確保です。これらの基本方針は、単に住宅供給を増やすだけでなく、高齢者や子育て世帯、障がい者など、住宅確保に配慮が必要な世帯への支援、既存住宅の有効活用、地域コミュニティとの連携強化など、多様なニーズに対応した内容となっています。特に、高齢者については、介護・医療と連携したサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の普及促進が目指されています。
3. 高齢者 子育て世帯 障がい者への支援策
少子高齢化の進展により高齢者世帯が増加している中で、高齢者、子育て世帯、障がい者など、住宅確保に配慮が必要な世帯に対する支援策が重要視されています。具体的には、民間賃貸住宅への入居支援、高齢者にとって使いやすい住環境の整備、子育て世帯や障がい者にとって住みやすい住宅の確保などが挙げられます。民間賃貸住宅への入居支援では、身元保証人や緊急連絡先がないことなどが理由で入居を断られるケースへの対応策が検討されています。また、高齢者の居住の安定確保のため、介護・医療と連携したサービス提供の推進も重要な施策の一つとして位置付けられています。これらの施策を通じて、様々な世帯が安心して住み続けられる環境づくりを目指しています。
4. 既存住宅ストックの有効活用と質の向上
人口減少社会においては、既存住宅ストックの有効活用が重要な課題となっています。本計画では、既存住宅の耐震化、バリアフリー化、省エネルギー化などの性能向上を図り、良質な住宅ストックの形成を目指しています。老朽化した市営住宅の建替えや耐震改修、エレベーター設置などの計画的な実施も推進されます。また、分譲マンションの維持管理・更新に関する情報提供の充実なども重要な施策の一つです。さらに、新築住宅だけでなく既存住宅についても、客観的に評価するための制度普及を進めることで、既存住宅の流通促進を図り、良質な住宅ストックの形成を目指しています。 積雪寒冷地の特性を考慮した省エネルギー性能の高い住宅の普及促進にも力を入れています。
5. 地域コミュニティの活性化
少子高齢化の進展に伴い、地域コミュニティの維持・活性化が課題となっています。計画では、市営住宅や地域におけるコミュニティ活動を維持・活性化するための施策を検討するとされています。高齢者世帯が増加する中で、地域コミュニティによる安全性の確保や支えあいの機能が重要となっており、こうした機能を強化することで、安心して暮らせる地域社会の形成を目指します。良好な住環境の形成を支える制度として、地区計画や建築協定、景観協定なども活用を検討し、地域の実情に合った制度の選択・活用が促されます。
III.施策の推進 多様な連携と具体的な取り組み
計画の実施にあたっては、民間事業者、NPO、建築関係団体などとの連携を強化し、多様な住宅確保要配慮者への支援を推進します。具体的には、市営住宅の住み替え制度の見直し、安全・安心な市営住宅への再生、既存住宅のバリアフリー化・耐震化支援、分譲マンションの維持管理支援などが挙げられます。また、空き家の有効活用についても検討を進め、住宅ストックの質向上に繋げます。住宅金融市場の整備による無理のない住宅取得支援についても国との連携を強化します。市民からの意見を踏まえ、計画内容の修正も行われました。
1. 市営住宅の再生と民間賃貸住宅の有効活用
老朽化した市営住宅の建替えや改修を計画的に進め、エレベーター設置や車いす対応住戸の整備を進めることで、安全で安心な住環境を提供します。市営住宅ストック総合活用計画に基づき、老朽度や立地条件などを考慮した計画的な実施を図ります。また、増加する民間賃貸住宅の空き家を有効活用し、住宅確保に課題を抱える世帯への支援に繋げます。 特に、子育て世帯や高齢者世帯など、住宅ニーズが多様化する中で、適切な住み替えを促進するための制度見直しも検討されます。狭い住宅に住む子育て世帯と広い住宅に住む高齢世帯の住み替えを促進し、家族構成の変化に対応した適切な住宅への転居を支援します。
2. 民間賃貸住宅への入居支援の強化
高齢者や障がい者、子育て世帯など、身元保証人や緊急連絡先がないなどの理由で民間賃貸住宅への入居が困難な世帯に対して、北海道や民間事業者と連携した入居支援を強化します。入居審査における柔軟な対応や、適切な住宅情報の提供を通じて、これらの世帯が安心して民間賃貸住宅に入居できる環境づくりを目指します。 例えば、一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借上げ制度」のような、既存の制度や民間サービスとの連携も検討されます。これにより、高齢者が自宅を売却することなく住み替えを行い、老後の資金確保にも繋がる可能性を検討します。
3. 既存住宅の耐震化 バリアフリー化支援
バリアフリー化が進んでいない既存住宅や、耐震化が必要な昭和55年以前に建築された住宅が多く存在する現状を踏まえ、既存住宅の耐震化やバリアフリー化を促進するための支援策を展開します。具体的には、耐震化やバリアフリー化改修に対する助成金制度の拡充や、改修に関する情報の提供、専門業者との連携強化などが考えられます。 また、新築住宅だけでなく既存住宅についても、環境負荷の低減に配慮した住宅が長く住み継がれていくことを目指し、良質なストックとして客観的に評価するための各種制度の普及を促進します。これにより、既存住宅の流通促進と、より良い住環境の整備を目指します。
4. 分譲マンションの維持管理 更新支援
老朽化が進む分譲マンションの維持管理・更新は、今後大きな課題となります。そのため、マンションの管理組合などに対して、維持管理や更新に関する情報を広く提供するための施策を検討します。 具体的には、適切な情報提供のためのセミナー開催や、専門家による相談窓口の設置などが考えられます。また、長期修繕計画の策定支援や、修繕費用の確保に関するアドバイスなども検討事項です。これにより、分譲マンションの適切な維持管理を促進し、居住者の安全・安心を確保することを目指します。
5. 多様な関係者との連携強化と情報提供の充実
住宅に関する様々な支援や相談窓口は、民間事業者、NPO、建築関係団体などによって独自に運営されている現状があります。より効果的な施策推進のため、これらの団体との連携を強化します。 また、住まいに関する情報の提供方法の充実も重要です。インターネットを活用した情報提供に加え、インターネット環境のない市民にも配慮し、広報紙やパンフレットなど多様な媒体を活用した情報提供を推進します。 さらに、国が推進する住宅金融市場の整備、既存住宅の適正評価・円滑な流通促進のための施策にも積極的に協力し、普及に努めます。
