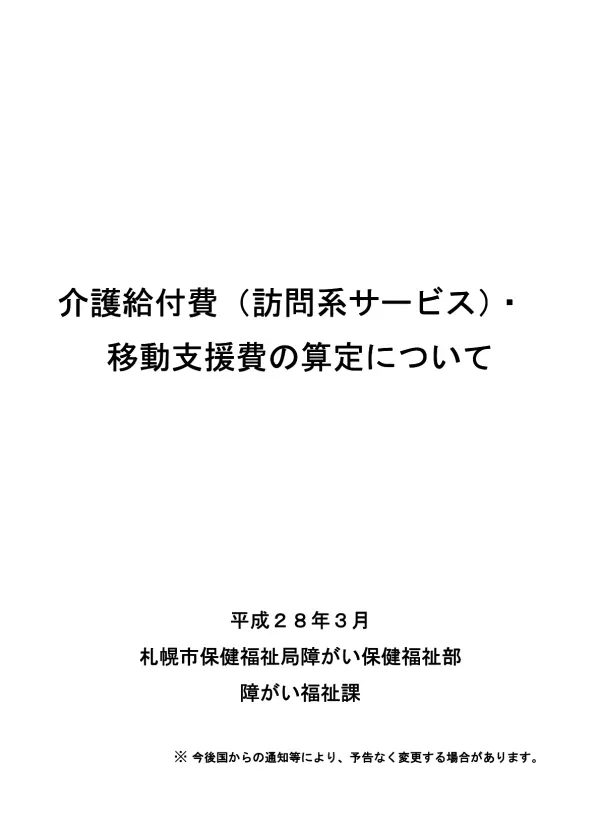
札幌市移動支援費算定マニュアル
文書情報
| 著者 | 札幌市保健福祉局 障がい保健福祉部 障がい福祉課 |
| 場所 | 札幌市 |
| 文書タイプ | マニュアル |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.58 MB |
概要
I.居宅介護等計画の作成と算定時間
本資料は、日本の介護保険制度における居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、移動支援(以下「居宅介護等」)の計画作成と算定時間に関する重要な情報を提供します。居宅介護等計画は、利用者の日常生活全般の状況や希望を踏まえ、具体的なサービス内容を記載する必要があります。算定時間は、実際に要した時間ではなく、居宅介護等計画に記載された計画時間(標準的な時間)に基づきます。計画時間と実際のサービス提供時間に差異がある場合は、計画の見直し・変更が必要です。身体介護は1回3時間まで、家事援助は1.5時間までが標準利用可能時間数です。これを超える場合は、アセスメント結果を記録する必要があります。ヘルパー2人派遣は、利用者の同意とアセスメントに基づき行われ、その必要性を計画に記録します。サービス提供時間の間隔は概ね2時間以上ですが、例外規定も存在します。
1. 居宅介護等計画について
居宅介護等計画の作成は、利用者の日常生活全般の状況や希望を詳細に把握・分析した上で、具体的なサービス内容を記載することが必須です。 サービス提供実績記録票の計画時間欄には、この居宅介護等計画に基づいて記載されます。利用者の状況に応じた適切な計画策定が、サービスの質と利用者の満足度に直結するため、アセスメントに基づいた目標設定と援助の方向性の明確化が重要です。指定特定相談支援事業者等が作成したサービス等利用計画を参考に、保健医療サービスや他の福祉サービスとの連携も考慮して作成する必要があります。 計画作成にあたっては、利用者の状況を正確に把握し、居宅介護等によって解決すべき課題を明確にするアセスメントが不可欠です。 このアセスメント結果に基づき、援助の方向性や具体的な目標を明確にすることで、効果的なサービス提供が可能になります。
2. 居宅介護等計画と算定時間数について
居宅介護等の算定は、実際に要した時間ではなく、居宅介護等計画に記載された計画時間(サービス提供に要する標準的な時間)に基づいて行われます。 計画時間通りにサービスが提供されない場合は、速やかに居宅介護等計画の見直しと変更が必要となります。 これは、利用者への適切なサービス提供を確保し、計画と実績のずれによる不備を防止するためです。例えば、当初計画時間が1時間の身体介護において、ヘルパーの経験不足や利用者の心身状態の悪化により1時間30分要した場合でも、算定時間は1時間となります。 この計画時間と実際の提供時間の乖離は、サービス提供の精度やヘルパーのスキル、利用者の状態変化などを反映している可能性があり、計画の見直しを通じて、より適切なサービス提供体制を構築することが重要になります。
3. 居宅介護等計画の所要時間について
居宅介護等計画の作成において、所要時間30分未満で算定を行う場合は、所要時間は20分程度以上必要です(通院等乗降介助を除く)。サービスの種類や時間によって所要時間は異なり、注意が必要です。 具体的には、サービスの種類や時間に応じて適切な時間を確保し、計画に反映させる必要があります。 例えば、身体介護と家事援助を組み合わせた場合、それぞれのサービスに必要な時間を考慮し、全体としての所要時間を算出する必要があります。 また、居宅介護の提供を重度訪問介護研修終了者が行う場合も考慮しなければなりません。 このことは、計画作成における正確性と、サービス提供の効率性、そして利用者への適切なサービス提供という観点から非常に重要です。
4. 標準利用可能時間数について
居宅介護における1回あたりの標準利用可能時間数は、身体介護が3時間まで、家事援助が1.5時間までと定められています。 この時間数を目安に居宅介護等計画を作成する必要があります。ただし、利用者の身体状況やサービスの必要性について十分なアセスメントを行い、標準利用可能時間数を超えるサービス提供が必要な場合は、その理由とアセスメント結果を居宅介護等計画に記録する必要があります。計画提出を求められる場合もあります。 この標準利用可能時間数は、サービスの質と効率性を確保するための目安であり、利用者の状況によってはこれを超えるサービス提供が必要となる場合もあります。 重要なのは、利用者への適切なサービス提供を確保しながら、標準時間数の遵守と、超過する場合の明確な根拠を示すことです。
5. ヘルパーの2人派遣について
ヘルパーの2人派遣は、利用者の同意を得ており、かつ特定の要件に該当する場合にのみ実施できます。 利用者の身体状況やサービスの必要性について十分なアセスメントを行い、2人派遣が必要な場合は、そのアセスメント結果と必要性を居宅介護等計画に記録する必要があります。 計画の提出を求められる可能性があります。 2人体制が必要となるケースは、利用者の身体状況が複雑であったり、安全確保のために複数人での支援が必要な場合などが考えられます。 この場合、アセスメント結果を丁寧に記録し、2人派遣の必要性を明確に示すことで、適切なサービス提供と保険請求を行うことが重要となります。
6. 提供時間の間隔について
居宅介護(通院等乗降介助を除く)、同行援護、移動支援を1日に複数回算定する場合は、提供時間の間隔は概ね2時間以上必要です。2時間未満の場合は、前後のサービス提供時間を通算して1回のサービスとして算定します。ただし、別のサービス類型を使用する場合(例:身体介護に連続して家事援助を提供する場合)、緊急時対応加算の要件に該当する場合、利用者の身体状況や生活パターンにより短時間の間隔で複数回訪問が必要な場合は例外となります。 これらの例外規定は、利用者の状況や緊急性を考慮した柔軟な対応を可能にするものです。ただし、単に1回の居宅介護を複数回に分割する場合などは除外されます。 それぞれのケースにおいて、利用者の状況を十分にアセスメントし、その必要性を居宅介護等計画に記録することが求められます。
7. 減算対象ヘルパーについて
居宅介護等計画上、減算対象ヘルパーを派遣する予定が、事業所の都合により減算対象ヘルパー以外になった場合、またはその逆の場合、減算対象ヘルパーが派遣される場合の単位数を算定します。 これは、減算対象ヘルパーの派遣予定が変更になった場合でも、算定基準を維持することで、サービス提供の公平性を保つための規定です。 事業所の都合によるヘルパー変更は、利用者へのサービス提供に影響を与えないよう、適切な対応と計画変更が必要となる点を示しています。 この規定は、サービス提供の質の維持と、保険請求における正確性を確保するために重要です。
II.時間帯加算とサービス提供時間の間隔
居宅介護等(行動援護を除く)の算定には、時間帯(早朝、夜間、深夜)に応じた加算があります。時間帯をまたぐ場合は、開始時刻が属する時間帯の基準で算定しますが、提供時間がごくわずかな場合は終了時刻の基準を使用します。居宅介護、重度訪問介護、同行援護、移動支援において、同じサービス類型を複数回利用する場合、間隔が2時間未満であれば、1回のサービスとして合計時間を算定します。ただし、利用者の身体状況や生活パターンにより短時間の間隔で複数回訪問が必要な場合は除外されます。重度訪問介護研修終了者による居宅介護サービス提供は、一時的な人材確保が必要な場合に限定されます。
1. 時間帯加算
居宅介護等(行動援護を除く)の算定には、早朝、夜間、深夜の時間帯に応じた加算が設けられています。サービスの最小単位(30分など)が時間帯をまたぐ場合は、開始時刻が属する時間帯の算定基準に従って算定します。ただし、開始時刻が属する時間帯での提供時間がごくわずかな場合は、終了時刻が属する時間帯の算定基準が適用されます。これは、サービス提供時間における時間帯の区分を明確にすることで、適切な加算を算出するための規定です。時間帯加算は、早朝や深夜などの時間帯にサービスを提供する際の業務負担を考慮したものです。 具体的には、サービス提供開始時刻がどの時間帯に属するかによって算定方法が変わり、ごく短い時間でも、開始時刻や終了時刻の属する時間帯によって加算が適用されるかどうかが決定されます。このため、正確な時間管理と記録が重要になります。
2. サービス提供時間の間隔
居宅介護(通院等乗降介助を除く)、同行援護、移動支援を1日に複数回算定する場合は、提供時間の間隔は概ね2時間以上必要です。2時間未満の場合は、前後のサービス提供時間を合計した1回のサービスとして算定されます。ただし、例外として、別のサービス類型を使用する場合(例えば、身体介護に続けて家事援助を提供する場合)、緊急時対応加算の要件に該当する場合、利用者の身体状況や生活パターンにより短時間の間隔で複数回の訪問が必要な場合は、この2時間以上の間隔の制限が適用されません。 この規定は、サービス提供の効率性と利用者のニーズへの対応を両立させるためのものです。 ただし、単に1回のサービスを複数回に分割するような場合は、この例外規定は適用されません。 それぞれの状況において、利用者の状態やニーズを十分に考慮し、適切なサービス提供を行う必要があります。
3. 重度訪問介護研修終了者による居宅介護サービス
重度訪問介護研修終了者による居宅介護サービスの提供は、早朝・深夜帯や年末年始など、一時的に人材確保を行う必要がある場合に限定されます。 この規定は、専門的な知識とスキルを持つ研修修了者を、特に需要の高い時間帯に効率的に配置するための措置と考えられます。 研修終了者によるサービス提供は、利用者にとってより質の高いケアを提供できる可能性がある一方、その配置には一定の条件が課せられていることを示しています。 このため、サービス提供計画においては、研修終了者の配置の必要性を明確に示すことが重要です。特に時間帯加算との関連において、時間帯と研修終了者の配置状況を明確に示す必要があります。
4. 複数時間帯にまたがるサービス提供の算定
居宅介護、重度訪問介護などのサービス提供時間が複数の時間帯にまたがる場合、日単位で分けて単位数を算出します。最小単位(30分など)が24時(0時)をまたぐ場合は、ごくわずかな時間は考慮せず、開始日として算定します。 これは、時間帯加算の算定において、正確な時間帯を特定し、適切な加算を行うための規定です。 サービス提供時間が深夜帯に僅かしか及ばない場合でも、開始時刻が深夜帯に属する場合は深夜帯の算定基準が適用されます。 複数日間にまたがるサービス提供の場合、日毎に時間帯を区別して算定し、適切な加算を行う必要があります。特に重度訪問介護では、日またぎのサービスコードが存在しないため、翌日は通常のサービスコードで算定されます。
III.サービス提供実績記録票への記載事項
サービス提供実績記録票の算定時間欄には、実際に要した時間ではなく、計画時間数を記載します。 移動支援計画には、サービス提供予定日と曜日、30分単位の計画時間を記載し、サービス提供終了時に双方が押印します。記載内容の訂正は、二重線を引いて、サービス提供者と利用者の双方が押印する必要があります。ヘルパー2人派遣の場合、提供時間がずれる場合は、2行に分けて記載し、備考欄に空き時間を記載します。
1. 算定時間欄への記載
サービス提供実績記録票の算定時間欄には、実際に要した時間ではなく、居宅介護等計画に記載されている計画時間数を記載します。サービス提供が全くなかった場合は除きます。これは、サービスの算定基準を明確にするためであり、計画に基づいた時間管理の重要性を示しています。 計画時間数は、サービス提供計画において事前に決定された時間であり、実際のサービス提供時間とは異なる場合があります。 そのため、記録にあたっては、計画時間数と実際のサービス提供時間の差異を把握し、必要に応じて計画の見直しを行うことが重要となります。 計画時間数は、サービス提供内容や利用者の状況に合わせて適切に設定する必要があるため、計画策定段階での綿密なアセスメントが重要になります。
2. 計画時間数の有効活用と見直し
決定された計画時間数を有効に活用するため、利用者の要望を踏まえることが重要です。 実際のサービス提供が当初の計画と合致しない場合は、速やかに計画の見直しと変更を行う必要があります。 これは、利用者への適切なサービス提供を確保し、計画と実績のずれによる不備を防止するためです。 例えば、利用者の状態変化や予期せぬ事態が発生した場合、計画時間数を調整する必要があるかもしれません。 その際には、変更の理由を明確に記録し、関係者間で共有することで、適切なサービス提供と記録管理を行うことが重要です。 計画の見直しは、継続的なサービス改善にもつながります。
3. 移動支援計画への記載事項
移動支援計画には、当該サービス提供月におけるサービス提供予定日とその曜日を記載する必要があります。計画時間は必ず30分単位で作成し、サービス提供終了の都度、サービス提供者と利用者の双方が押印することが求められます。これは、サービス提供の実績を正確に記録し、利用者とサービス提供者間の合意を確認するためです。 移動支援計画は、サービス提供計画全体の中で重要な役割を果たし、サービスの計画性と透明性を高めることに貢献します。 記載事項の正確性は、サービスの質の維持と、保険請求における正確性を確保するために非常に重要です。 そのため、記録にあたっては、細心の注意を払う必要があります。
4. 記載内容の訂正
記載内容を訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引いて、サービス提供者と利用者の双方が押印する必要があります。移動支援計画の訂正は、サービス提供責任者と利用者の双方の押印が必要です。 これは、記録の改ざんを防止し、記録の信頼性を確保するための重要な手順です。 訂正を行う際には、訂正内容を明確に示し、変更の理由を記録しておくことで、記録の透明性を高めることができます。 正確な記録管理は、サービス提供の実績を正確に把握し、保険請求を行う上で不可欠です。 そのため、記録作成と訂正手続きにおいては、細心の注意を払うことが重要です。
5. 2人派遣の場合の記載方法
ヘルパーを2人派遣する場合で、提供時間がずれるときは、2行に分けて記載します。1行目には全体の通算時間を、2行目にはヘルパーが重複する時間を記載します。ヘルパーごとに番号(丸囲み)を記載し、派遣人数は行ごとに「1」と記載します。サービス提供者印は、最後の提供者のみで構いません。備考欄に空き時間を記載します。 これは、複数ヘルパーによるサービス提供における時間管理を明確にするためです。 ヘルパー間の連携状況や、サービス提供における時間配分を正確に記録することで、サービスの質の維持と効率的な運営に貢献します。 特に、サービス提供時間の重複部分や空き時間を明確に記載することで、算定時間における正確性を確保することが重要になります。
