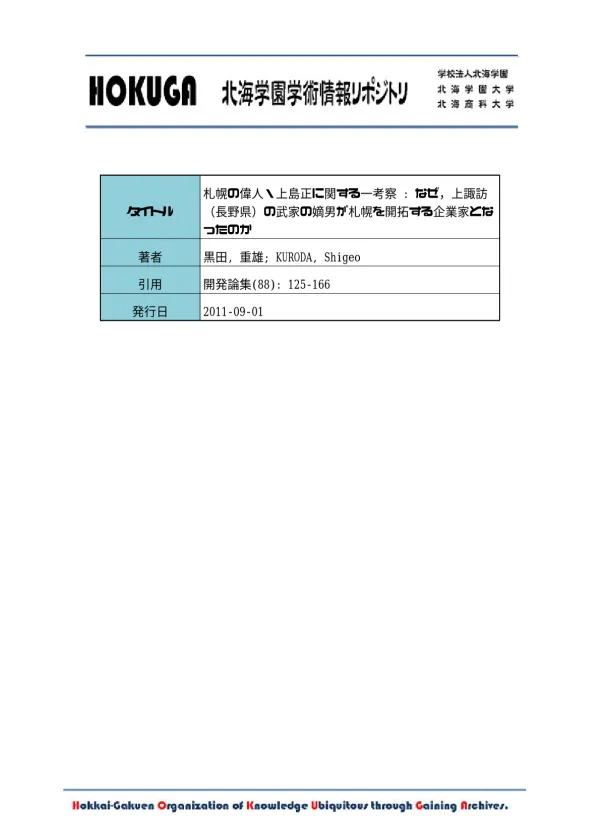
札幌開拓の偉人 上島正の生涯
文書情報
| 著者 | 黒田重雄 |
| 学校 | 北海学園大学開発研究所 |
| 専攻 | 北海道開拓史、企業史(推定) |
| 場所 | 札幌(推定) |
| 文書タイプ | 論考 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.06 MB |
概要
I.上島正と札幌開拓 信濃からの移住と東皐園
長野県諏訪郡湖南村出身の【上島正】は、明治10年、札幌に移住し開拓に携わった人物です。その功績は、札幌歴史資料館の「札幌の歴史を築いた先人達」にも記されています。【上島正】は、自ら経営した【東皐園】という著名な花園で知られ、牡丹、花菖蒲など数多くの和洋花卉を栽培・販売しました。東皐園は、当時の札幌市民の憩いの場として重要な役割を果たしました。さらに、札幌諏訪神社の創建にも尽力しました。彼の南画作品は、北海道開拓の様子を伝える貴重な資料として高く評価されています。
1. 上島正の札幌移住と開拓への貢献
上島正は長野県諏訪郡湖南村出身で、明治10年に札幌に移住し開拓事業に着手しました。札幌歴史資料館の「札幌の歴史を築いた先人達」にも名を連ねているように、札幌の発展に大きく貢献した人物の一人です。 文書では、彼が札幌諏訪神社の創建に関わったこと、そして何よりも彼の尽力で完成した「東皐園」が強調されています。東皐園は、牡丹、薬草、花菖蒲、ベコニア、萩など、和洋様々な花卉を栽培する大規模な花園であり、札幌市民の憩いの場として重要な役割を果たしました。この花園は、単なる花畑ではなく、句会や碁会、謡曲などの催しが開かれるイベント会場としても活用されていたと記されています。 上島正の活動は、札幌における農業開発、園芸事業の振興、そして地域文化の醸成に多大な影響を与えたと考えられます。彼の功績は、札幌の歴史に深く刻まれていると言えるでしょう。さらに、上島は南画の腕前にも優れ、北海道開拓の様子を描いた多くの作品を残しており、それらは北海道開拓記念館に所蔵されています。これらの絵画は、当時の開拓の様子を知る上で貴重な資料となっています。
2. 東皐園 規模と特徴 札幌における役割
上島正が経営していた「東皐園」は、札幌区で著名な花園として知られていました。 その規模は大きく、牡丹、薬草、花菖蒲、ベコニア、萩など、和洋数十種の花卉が栽培され、種苗の販売も行われていたと記述されています。花菖蒲の変種が多く栽培されていたことが特に有名で、上島自身もこれを誇りとしていたとあります。この東皐園の成功は、上島正の優れた園芸技術と努力の賜物です。 文書には、札幌の東西南北に大規模な公園を建設するという開拓使の構想が紹介されており、東皐園はその構想における東側の公園として位置づけられていたことがわかります。円山公園や中島公園のように現在も残る公園とは異なり、東皐園は現存していませんが、もし計画通りに建設されていたら、札幌の街並みは全く異なる趣になっていた可能性があると述べられています。 東皐園は、単なる花園にとどまらず、当時の札幌市民にとって憩いの場、そして文化的交流の場としての役割を果たしていたことが、文書から読み取れます。
3. 上島正の南画と北海道開拓の描写
上島正は南画の才能にも恵まれており、札幌に移住後も数多くの作品を残しています。彼の描いた絵画は、北海道開拓の様子を伝える重要な資料として、しばしば引用されています。文書には、開拓時代の開墾の様子を描いた2枚の絵画(北海道開拓記念館蔵)が具体的な例として挙げられています。これらの絵画は、上島正が単なる園芸家や開拓者ではなく、優れた芸術家としての側面も持っていたことを示しています。 上島正の絵画は、当時の北海道の自然環境や開拓の様子をリアルに表現していると考えられ、歴史的価値は極めて高いものと言えるでしょう。これらの作品は、北海道開拓の歴史を研究する上で重要な視覚資料を提供しています。 また、彼が政治権力者や著名な文化人の庇護を受けることなく、武家の出身でありながら市井の人として生きながら、札幌の開拓に深く関わったという事実も、彼の絵画を通してより深く理解できる側面となっています。
II.上島正の経歴と北海道移住の動機
上島正の祖先は信濃国上伊那を領する上島城主でしたが、落城後、諏訪家に仕え、代々普請奉行を務めました。上島自身は、高島藩の重臣の嫡男として、漢文や俳句などの教養を受けました。しかし、幕末の動乱と、武士の没落を目の当たりにした上島は、明治時代に測量官として東京近郊を測量中に、北海道の開拓の可能性に着目します。自身の経験と成功を基に、明治15年には故郷の信濃の人々に北海道移住を勧奨し、数十名を引き連れて札幌へ移住しました。これは、彼自身の【北海道開拓】への貢献として重要な転換点となりました。
1. 上島家の家系と上島正の生い立ち
上島正は長野県諏訪郡湖南村の出身です。彼の家系は古く、信濃国上伊那を領する上島城主であったと日記に記されています。落城後、諏訪家に仕え、家老職に就き、子孫は代々普請奉行を務めたとのことです。上島正の父、幸右衛門も奉行の要職にあったと推測されます。上島正は幼名を源吉と言い、家督相続の際に名を正と改めたとあります。この家系図から、上島正が武士階級の出身であり、伝統的な家柄に育ったことがわかります。また、高島藩の重臣の嫡男であったこと、歴代藩主が文芸を奨励していたことから、上島正は藩校で儒学や武士道を学び、漢文や俳句などの教養を身につけた可能性が高いです。さらに、彼は南画を好み、師事して絵の腕を磨いたことも記述されています。これらの背景から、上島正は高い教養と幅広い素養を備えた人物であったことが伺えます。彼の後々の行動や成功を理解する上で、この家系と生い立ちが重要な要素となります。
2. 幕末の動乱と上島正の決断
上島正が生きていた時代は、幕末から明治維新へと続く激動の時代でした。天保12年の幕政改革(天保の改革)では、武士の借金が帳消しになる一方、札差といった金融業者は壊滅的な打撃を受けました。この混乱の中で、上島正は江戸で佐幕派と倒幕派の抗争を目の当たりにします。武士の権威が失墜し、武家政治への幻滅を感じた可能性が高いです。高島藩の重職である奉行の嫡男である彼は、江戸で身分を明かすことが危険であると判断し、逗留先の屋敷にも迷惑を掛けないよう行動していたと考えられます。 このような状況下で、上島正は権威を失った武士の身分を捨て、新たな道を模索する決意をしたと考えられます。この決断は、彼の人生における大きな転換点となり、後に北海道への移住へと繋がっていく重要な要素となっています。
3. 北海道移住の契機と経緯
上島正が北海道へ移住した直接のきっかけは、明治7年の地租改正時の測量官としての活動です。東京近郊の測量中に、札幌にいた門弟から北海道の状況を聞き、開拓の可能性に魅力を感じたことが記述されています。その後、明治10年1月に一旦帰郷し、測量官の職を辞して札幌へ向かいます。 移住の決定には、彼が測量官として得た北海道に関する知識や情報が大きく影響していることは明らかです。 さらに、札幌へ移住してから5年後の明治15年、上島正は故郷の上諏訪を訪れ、自身の成功体験を基に、郷里の人々に北海道への移住を勧奨しています。 しかし、当初は牛山民吉の開成会社と協力関係を結んでいましたが、約束と異なる状況であったため、破約して、独自で札幌に新たな集落を作る計画を立て、20名余りを引き連れて札幌へ移住したとあります。これは上島正の強い意志と、北海道開拓への強い決意を示すエピソードとなっています。
III.東皐園と上島正の園芸技術
【東皐園】は、上島正の【園芸技術】の粋を集めた花園でした。特に、花菖蒲の変種育成においては高い評価を得ており、その技術は札幌農学校の外国人教師から学んだ応用植物学に基づいていました。上島は、植物の交配方法に関する知識を応用し、多くの新しい品種を生み出しました。彼の技術は、当時の人々から驚きをもって受け止められ、日本園芸会からも認められるほどでした。これは、彼が単なる開拓者ではなく、高度な専門知識を持つ【企業家】であったことを示しています。
1. 東皐園の概要と札幌における位置付け
上島正が札幌で経営した東皐園は、牡丹、薬草、花菖蒲、ベコニア、萩など、和洋様々な花卉を栽培する大規模な花園でした。種苗の販売も行われていたことから、商業的な成功も収めていたと考えられます。 東皐園は、当時の札幌市民にとって重要な憩いの場であったと記述されています。句会、碁会、謡曲など、様々な催しが開催されるイベント会場としての役割も果たしていました。 興味深いのは、札幌の東西南北に大規模な公園を作るという開拓使の構想において、東皐園が東側の公園として計画されていた点です。西の円山公園、南の中島公園は現在も残っていますが、東皐園と北の偕楽園は現存しません。もし、これらの公園計画が実現していたら、札幌の街並みは現在とは大きく異なっていたでしょう。東皐園は、札幌の都市開発や市民生活、そして文化活動において、重要な役割を果たしたと考えられます。
2. 上島正の園芸技術と花菖蒲の変種育成
東皐園の成功は、上島正の優れた園芸技術によるところが大きいです。特に、花菖蒲の変種育成においては高い評価を得ており、その技術は彼独自の技能として秘されていたと記されています。 その技術の源泉は、札幌農学校の外国人教師から学んだ応用植物学にあったと推測されます。 具体的に、彼は雌雄芯の所在と交配の方法を学び、それを応用して多くの新しい品種を生み出したとあります。 彼の交配技術は、当時の人々から驚きをもって受け止められ、「人間の子を生む秘伝を知っている」という噂が立つほどでした。 この高い技術力は、単なる経験則ではなく、科学的な知識に基づいていたことを示しており、上島正が近代的な園芸技術を積極的に取り入れていたことを物語っています。この技術は、明治26年に日本園芸会から学芸委員を嘱託されるという栄誉にも繋がりました。
3. 上島正の切花に関する技術革新
文書には、上島正が切花の水揚げに関する技術革新にも取り組んでいたことが記されています。特に、萩や天竺牡丹(ダリア)の水揚げに苦労した経験から、独自の工夫を凝らしたとあります。 萩は、切花として瓶の中で長く保たないことで知られていますが、上島正は長期間鮮度を保つ方法を工夫したのです。 また、天竺牡丹(ダリア)についても、切り取った花がすぐに萎れるという課題を解決するために、熱湯に浸してから花箱に入れるという方法を発見しました。この方法は偶然の発見であったとされていますが、彼の植物に対する深い知識と観察眼がなければ、このような発見はありえなかったでしょう。これらのエピソードは、上島正が単なる園芸家ではなく、植物に関する深い知識と実践的な技術を駆使した、いわば園芸における「発明家」としての側面を持っていたことを示唆しています。
IV.上島正の晩年と人生観
明治33年、63歳で生涯を閉じた上島正は、日記の中で自身の人生を振り返っています。彼は、誰にも仕えない自由な生き方を貫き、王侯貴族のような名誉や地位よりも、気楽な生活を好んだ【楽天主義者】でした。晩年の彼の言葉は、彼の【人生観】と【北海道開拓】における功績を理解する上で重要な手がかりとなります。
1. 晩年の生活と日記における自己回顧
明治33年10月27日、63歳で生涯を終えた上島正は、自身の『想い出の記』という日記の中で、人生を振り返っています。日記の最後の日付には、63年間の人生を総括する記述があり、その要約は「誰にも仕えない楽しみ」という言葉に集約されます。 上島は、王侯貴族や名誉の奴隷になるような生活ではなく、気ままに、誰にも束縛されない自由な生き方を好んだようです。「気楽で世を通て行く塩梅はマア佛家でいう極楽世界とでも申しましょうか」という記述は、彼の楽天的な性格と、世俗的な成功や地位よりも、自由な精神を重視する人生観を鮮やかに表しています。 日記からは、彼自身の生き方への自信と満足感が感じ取れます。それは、彼が権力者や著名人に頼ることなく、独自の力で成功を収め、自由な人生を全うしたという自負に基づいていると言えるでしょう。彼の晩年の言葉は、彼の人生の軌跡と価値観を理解する上で重要な手がかりとなります。
2. 若き日の夢と現在の境遇への満足感
60歳を超えて過去を振り返る中で、上島は「宿昔青雲志」という詩を引用し、若かりし頃に抱いていた大きな志や野心、そして未達成の夢に触れています。 しかし同時に、彼は現在の境遇への満足感を示しています。「今の境界(報いとしての境遇)が勝し(他に勝っていた)てあったのだと考えなほすような次第で」という記述は、過去の野心や未達成の夢を否定するものではなく、現在の自由で気楽な生活の方が、彼にとってより大きな価値を持っていたことを示唆しています。 この記述からは、若き日の夢を追い求めた経験と、晩年の穏やかな生活との間で葛藤があった可能性が読み取れますが、最終的には、現在の境遇に満足し、楽天的な人生観を貫き通したことがわかります。 彼の言葉は、人生における成功や幸福の定義が多様であり、個々人の価値観によって異なることを示唆しています。
3. 上島正の人生観 楽天主義と自由への希求
上島正の日記や、小池睦郎氏の『川下百年誌』における記述から、彼の明確な人生観が浮かび上がります。彼は、誰にも仕えることなく自由に生きることを喜びとし、世間の評価や地位に囚われない生き方を貫きました。 「気楽で年を経て行く塩梅はマア佛家でいう極楽世界とでも申しましょうような私は全く楽天主義でござりました」という日記の記述は、彼の楽天的な性格と、自由を強く求める人生観を端的に表しています。 これは、彼が幕末の動乱期を経験し、権威を失った武士社会に幻滅を感じ、自ら新たな道を切り開こうとした行動と深く関わっていると言えるでしょう。 上島正の人生観は、現代社会においても、個人の自由や幸福を追求する上で重要な示唆を与えてくれるでしょう。彼の生き方は、成功の定義を再考するきっかけを与え、より充実した人生を送るためのヒントになるかもしれません。
V.関連人物と団体
この文書には、上島正と共に北海道開拓に貢献した人物や団体が複数登場します。例えば、牛山民吉(開成会社)、河西由造(厚別への入植者)、藤森銀蔵(円山村で農業・園芸)、そして、札幌農学校の外国人教師などです。これらの関連人物や団体に関する情報も、上島正の生涯を理解するために重要です。また、高島藩、諏訪氏、そして、明治政府による【屯田兵】政策なども、背景として理解する必要があります。
1. 北海道移住における関連人物 牛山民吉と河西由造
上島正の北海道移住と開拓において重要な役割を果たした人物として、牛山民吉と河西由造が挙げられます。上島は、札幌へ移住後5年目の明治15年、牛山民吉の開成会社の人員募集に応募する形で、上諏訪へ赴き、郷里の人々に北海道移住を勧奨しました。しかし、東京で牛山と会って約束と大きく異なる点があったため、破約しています。 その後、上島は独自で札幌に新たな村を作る計画を立て、東京から同行した河西由造ら20名余りと共に札幌へ移住しました。河西由造は、移住当初は資金が乏しかったものの、白石村字厚別で開墾に従事し、成功を収めて村内屈指の資産家となった人物として、上島正の業績とともに紹介されています。 若林功の『故河西由造小傳』には、上島正と河西由造の北海道での活動が記述されており、彼らの成功は、北海道開拓における個人の努力と決断の重要性を示す事例となっています。これらの関連人物は、上島正の北海道での活動を理解する上で欠かせない存在です。
2. 札幌開拓における他の関連人物と団体
上島正以外にも、北海道開拓に貢献した人物が文書中に登場します。札幌歴史資料館の「札幌の歴史を築いた先人達」に名を連ねるエドウィン・ダンはその一例です。彼はアメリカ出身で、明治6年に札幌に来ていました。 また、文書では、札幌近郊への諏訪郡民の移住についても触れられています。明治10年に上島正が移住したのを皮切りに、その後数年間で数十戸が移住しましたが、リーダーの不正によって団結が解け、各自が札幌周辺で土地を購入して定着したとあります。その中には、白石村字厚別で未開地を開墾し、新部落を形成した人々も含まれており、藤森銀蔵や河西由造などがその代表格として挙げられています。 これらの移住者たちは、農業や園芸、畜産業などを営み、成功を収めています。このことは、上島正の北海道移住勧奨活動が、多くの信濃の人々に成功をもたらしたことを示しています。 さらに、明治政府の「屯田兵」政策も北海道開拓の背景として重要な要素でした。
3. 上島正の園芸技術と日本園芸会
上島正の園芸技術は、日本園芸会からも認められていました。文書には、彼が花菖蒲の交配技術で高い評価を得ていたことが記されています。 移住の際に持ち込んだ70種類の菖蒲を、人為的な交配によって500~600種類にまで増やし、西洋花菖蒲の増殖にも成功しました。 これらの業績が日本園芸会の知るところとなり、明治26年には日本園芸会々長の花房義質氏から「本会学芸委員を嘱託す」という辞令が送られています。 これは、上島正の園芸技術が、当時の日本における園芸界で高いレベルに達していたことを示す証拠です。 彼の技術は、単に東皐園の成功に留まらず、日本の園芸の発展にも貢献したと考えられます。 札幌農学校の外国人教師からの技術指導も、彼の成功に繋がった重要な要素の一つです。
