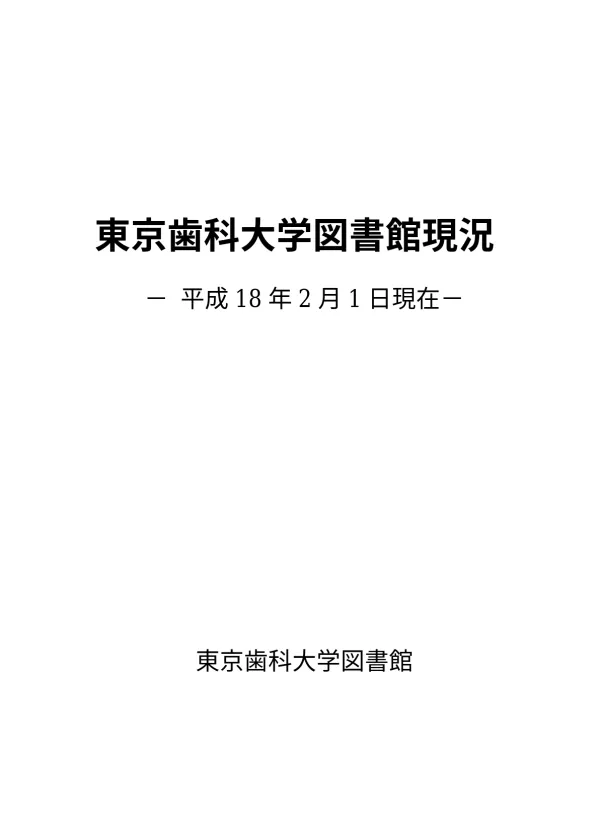
東京歯科大学図書館:現状と課題
文書情報
| 学校 | 東京歯科大学 |
| 専攻 | 図書館学 |
| 場所 | 東京 |
| 文書タイプ | 図書館報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 122.88 KB |
概要
I.資料収集と選定方針
東京歯科大学図書館は、歯科医学関連資料を国内有数の規模で所蔵しており、教育・研究に関連する専門図書(洋書を含む)を優先的に収集しています。特に歯科医学関連の逐次刊行物(洋雑誌、医学辞典等)は、英語版を優先し、必要なものは複数冊揃えています。予算の制約から、電子ジャーナルへの移行や、コンソーシアムへの加入を検討しており、為替レート変動も考慮する必要があります。新刊の選定は図書委員会が行い、副冊購入は館長が決済します。教員との連携を強化し、授業要覧等を参考に資料収集を進めています。著作権法遵守のため、複写に関するオリエンテーションやポスター掲示を実施しています。
1. 資料収集の現状と重点分野
東京歯科大学図書館は、歯科医学関連資料の収集に重点を置いており、国内有数の所蔵数を誇っています。教育・研究に直結する専門図書、特に洋書を優先的に収集しています。 これは、学生や研究者のニーズを満たすためだけでなく、歯科大学としての専門性を維持・発展させる上で不可欠な取り組みです。 収集対象は、歯科医学関連の雑誌、医学辞典、ハンドブック、データブックなど多岐に渡り、特に医学の主要抄録や索引誌に掲載されている歯科医学関連の洋雑誌は可能な限り収集し、関連分野の資料も収集対象としています。複数言語で出版されている場合は、英語版を優先的に収集することで、情報アクセスの効率化を図っています。ハンドブックやデータブックなどの歯科医学関連資料は、新規の内容のものについても可能な限り収集する方針です。医学辞典・辞書類、歯科医学・医学分野の便覧、住所録・名簿などもできる限り収集することで、研究活動の幅広いニーズに対応できるよう努めています。さらに、医学関連分野や一般語学関係の辞典、事典類についても、定評のあるものを収集することで、幅広い知識の習得を支援しています。これらの資料収集は、大学における教育・研究活動を支える重要な基盤となっています。
2. 予算と資源配分の課題
図書館の予算は横ばいであるため、継続購読の打ち切りなどの対応を余儀なくされており、その限界も見えてきています。コスト削減策として、電子ジャーナルへの移行が検討されています。電子ジャーナルへの切り替えは、導入時点では約10%のコスト削減が見込めますが、翌年から再び価格が上昇する可能性があるため、長期的な視点での検討が不可欠です。また、利用可能なタイトル数を増加させるために、コンソーシアムへの加入も検討されていますが、加入費用も毎年上昇しているため、費用対効果の面から慎重な検討が必要です。為替レートの変動も、特に洋書などの購入費用に影響を与えるため、レートの良い時期にまとめて購入するなどの対策が必要となっています。これらの予算と資源に関する課題は、図書館運営における重要な課題であり、全学的な検討が必要であると認識されています。医科系図書館のような億単位の予算は確保できないため、現実的な範囲内で効率的な資源配分を行うことが求められています。設備関係支出として毎年2800万円が計上されていますが、事務方との更なる折衝が必要となります。
3. 資料選定と委員会の役割
図書館では、歯科関係の新刊はほぼ「見計い」で現物が到着しますが、その他の資料は各種資料から選定されています。この選定は図書委員会が行っており、副冊の購入は館長の決済が必要となります。特に雑誌の購読更新に関しては、委員会での十分な検討が求められています。これは、雑誌購読が図書館の経費に大きな負担をかけているため、継続購読の可否を慎重に判断する必要があるためです。委員会は、教員の専門知識を活かしつつ、必要性の高い資料を選定することで、図書館資料の質の維持・向上に貢献しています。 授業要覧や研究年報に掲載された図書、本学関係資料も収集対象としており、教員や教務課との緊密な連携が不可欠です。特に洋書については、委員の専門知識が選定に大きく影響するため、図書館員による選定も検討すべきです。 しかしながら、購入希望が出ない資料も多く存在し、資料のアピール方法についても改善が必要であることが指摘されています。これらの選定プロセスは、図書館資料の質と利用効率を左右する重要な要素となっています。
4. 著作権法遵守への取り組み
図書館では、著作権法違反による複写が問題となっています。特に、一人につき一部という規定が守られていない状況が指摘されており、著作権法の遵守を徹底する必要があります。図書館としては、オリエンテーションでの説明や、コピー機付近へのポスター掲示などを通じて、利用者への啓発活動を行っています。著作権法第31条(図書館等における複製)に基づき、調査研究のための複製は認められていますが、その範囲を超える複写は厳に慎むよう、利用者に呼びかけています。 この著作権問題への対応は、図書館の社会的責任を果たす上で重要な課題であり、継続的な啓発活動と、法令遵守を促すための制度整備が必要不可欠です。 効果的な啓発活動を行うためには、利用者のニーズを踏まえた内容にする必要があると共に、定期的な講習会の開催や、オリエンテーションの内容を見直すことも検討すべきです。
II.図書館サービスと利用状況
図書館では、レファレンスサービス、文献複写サービス、相互貸借等のサービスを提供しています。自動貸出機は好評ですが、返却ボックスの設置が検討されています。学生を中心に利用者は増加しており、貸出冊数も伸びています。「books pick up」「新着図書案内」等の問い合わせも増加しており、図書館の積極的な資料案内が必要となっています。市川、水道橋の分館では、サービス向上のため、レファレンスコーナーの設置や出張講習会の実施が検討されています。水道橋分館は利用促進のため見直しが必要です。地域連携として、千葉市歯科医師会会員への貸出も行っています。同窓生の利用も増加しており、特に文献複写の利用が伸びています。
1. 提供サービスと利用状況の現状
東京歯科大学図書館では、レファレンスサービス(文献所在・所蔵調査、書誌事項調査、利用方法指導など)、貸出・返却業務(延長、予約、督促、自動貸出機の管理)、相互貸借業務、複写業務といった様々なサービスを提供しています。その他、個室や第二書庫の利用受付、学外利用者への対応、館内環境保全なども重要な業務です。情報検索支援として、ナビゲーションやマニュアル作成、講習会なども実施しています。近年、図書館離れが懸念される中、本学図書館では学生を中心に利用者数、貸出冊数共に増加傾向にあります。試験期間や授業期間の利用は増加しますが、最近ではカウンターにて「books pick up」「新着図書案内」といった問い合わせが増加しており、掲示物による利用促進効果も見られます。これらの状況を踏まえ、図書館資料の積極的な案内が重要であり、閲覧係だけでなく整理係、さらには授業との連携も視野に入れた展開が必要だと考えられています。自動貸出装置は利用者に好評ですが、閉館後の返却方法や長期延滞者への対応、卒業・退職時の未返却対策など、今後の課題も残されています。文献複写業務の増加に伴い、業務量の増加と他の業務とのバランス調整、さらにはアウトソーシング化の可能性なども検討する必要があります。
2. 市川 水道橋分館の現状と課題
市川総合病院図書分館は館員1名体制で、資料の貸借、文献複写サービスなどをスムーズに提供できています。一方、水道橋病院図書分館は館員がおらず、月2回の本館館員による開館を行っていますが、現状では十分に活用されていません。水道橋分館の利用促進のためには、抜本的な見直しが必要です。また、千葉校舎だけでなく、市川・水道橋の分館においても、同じレベルのサービス提供を行うために、出張講習会の実施など、図書館からの積極的な情報提供と各施設との連携強化が求められています。 市川・水道橋の分館においては、図書館が提供する各種データベースの利用方法などを利用者に案内することが重要であり、情報の格差が生じないよう、定期的な講習会やパンフレットの作成なども有効な手段と考えられます。 特に、水道橋病院図書分館については、現状の活用状況を踏まえ、より効果的な運営方法を検討する必要があります。
3. 相互貸借システムと今後の展望
図書館では、他の図書館との相互貸借業務を日常的に行っています。しかし、現在のシステムでは申し込み依頼、支払いが複雑なため、業務効率化のために国立情報学研究所のNACSIS-ILLシステムへの加入と料金相殺制度への参加が検討されています。NACSIS-ILLシステムへの移行によって、他図書館からの複写申し込みの増加が見込まれる一方で、業務の効率化が期待されます。 また、千葉市歯科医師会会員への図書貸出など、地域連携も積極的に行われています。同窓生の利用も年々増加しており、特に文献複写の利用増加は顕著ですが、館員の負担増加という課題も抱えています。無人開館も検討課題の一つではありますが、図書館の管理や利用者の安全面などを考慮すると、慎重な対応が必要となります。開館時間延長についても、学生中心の利用状況を踏まえ、学内全体で検討する必要があるでしょう。
III.図書館運営と課題
開館時間は平日8時45分~20時、土曜8時45分~13時(試験期間は延長)ですが、利用状況を鑑みて検討が必要です。カウンター業務は現状一人体制で、利用者サービス向上のため業務内容の整理が必要となっています。データベースの利用案内を強化し、情報格差解消のための情報発信も重要です。問題利用者への対応マニュアル作成も今後の課題です。災害対策として、火災、地震対策のマニュアル作成や訓練実施が重要です。特に貴重図書の保護、非常時の連絡体制、避難経路の確保、資料の安全な搬出方法を検討する必要があります。
1. カウンター業務の現状と課題
現在、カウンター業務は館員全員が交互に一人で担当しており、貸出からレファレンスサービスまで全てを一人で対応しています。しかし、利用者からの問い合わせが多いと、十分なサービスを提供することが困難な状況です。そのため、今後、利用者サービスの質向上を図るためには、カウンター業務の見直しが必要不可欠です。具体的には、レファレンスコーナーを設置し、担当者を一定時間配置することで、カウンター業務の効率化と専門性の向上を目指すべきです。また、図書館が提供する各種データベースの利用方法などを利用者に案内することも重要であり、千葉校舎だけでなく、市川・水道橋の分館においても同様のサービスを提供できるよう、情報格差の解消に努める必要があります。そのためには、定期的な講習会の実施やパンフレットの作成などによる積極的な情報発信が有効です。 これらの課題解決には、人員配置の見直しや、業務プロセスの改善といった具体的な対策が求められます。
2. 分館の運営状況とサービス向上策
市川総合病院図書分館は館員1名体制で資料の貸借や文献複写サービスなどを円滑に提供できていますが、水道橋病院図書分館は館員が不在で、月2回の本館職員による開館しか行われておらず、十分な活用ができていません。水道橋病院図書分館の利用促進のためには、現状の運営方法の見直しが必要であり、大学各施設へのサービス向上のためには、市川・水道橋両分館において、出張講習会の実施など、図書館からの積極的な情報提供と各施設との連携強化が必要不可欠です。 各分館において、同じレベルのサービス提供を行うためには、情報共有システムの構築や、職員間の情報交換の機会を増やす必要があるでしょう。また、分館の利用状況を定期的に調査し、ニーズに合わせたサービス提供を行うことも重要です。
3. 開館時間とサービス量の増加による課題
図書館の開館時間は、平日8時45分から20時、土曜日は8時45分から13時となっており、試験期間中は土曜日の開館時間を午後5時まで延長しています。しかし、現状の開館時間が利用者のニーズに合致しているかどうかの検討が必要です。時間延長の可能性も検討する必要がありますが、時間延長には人的資源の確保が必要となります。また、全体としてサービス量は増加しており、他の業務とのバランスが崩れ始めています。文献複写業務のアウトソーシング化など、人的配置やサービス提供方法の見直しも必要です。 図書館の開館時間やサービス内容については、利用者のニーズを常に把握し、柔軟に対応していくことが求められます。 そのためには、利用状況の分析やアンケート調査などを活用し、最適な運営体制を構築することが重要です。また、効率的な業務遂行のため、業務の標準化や効率化のためのツール導入なども検討する必要があります。
4. 災害対策と問題利用者への対応
これまでの災害対策は主に火災を想定して行われてきましたが、地震への対策も急務となっています。全館禁煙で火災リスクは低いものの、火災発生時はもちろん、地震による被害(資料の落下・散乱、漏水、天井・照明器具の落下、ガラス破損など)への対策として、貴重図書の安全な保管場所の確保、非常時の連絡体制の整備、避難経路の確保、資料の搬出方法の検討、耐火金庫の購入などが挙げられます。さらに、電話回線が不通になった場合を想定した代替連絡手段(携帯電話、無線機、インターネット、メール)の検討も必要です。近年、問題利用者への対応も課題となっています。現状ではマニュアルがなくケースバイケースでの対応ですが、予防策として館内に防犯カメラを設置しています。問題利用者への効果的な対応策を検討し、マニュアルを作成する必要があるでしょう。
IV.電子化と学術情報発信
雑誌価格の高騰に対応するため、電子ジャーナルへの移行を進めています。Blackwell Synergy、Wiley InterScience等のコンソーシアムに参加し、電子ジャーナルの閲覧可能タイトル数を増加させています。機関リポジトリ構築・運用も比較的容易であり、大学の知的成果を保存し社会へ発信することで、大学評価の向上に繋げることが期待されます。ホームページの改訂により学術情報のポータル化を目指していますが、学内情報発信の強化が必要です。The Bulletin of TOKYO DENTAL COLLEGEの電子化も進めています。
1. 雑誌価格高騰への対応と電子ジャーナルの活用
学術雑誌の価格高騰は深刻な問題であり、国内で収集される海外学術雑誌のタイトル数は減少傾向にあります。本学図書館においても購読雑誌のタイトル数は減少していますが、日本医学図書館協会・日本薬学図書館協議会のコンソーシアムを積極的に活用することで、電子ジャーナルへのアクセスを拡大しています。具体的には、平成17年からBlackwell Synergy、平成18年からWiley InterScienceのコンソーシアムに参加し、平成18年1月現在、購読洋雑誌415タイトルに対して、閲覧可能な電子ジャーナルは680タイトルに達しています。 また、電子ジャーナルの安定した利用を確保するため、Elsevier社のバックファイル(歯科分野)を購入するなど、供給の安定化にも取り組んでいます。 これらの取り組みは、雑誌価格の高騰という厳しい状況下においても、質の高い学術情報を確保するための重要な戦略となっています。 今後も、コンソーシアムへの参加や電子ジャーナルの購入を継続することで、情報アクセスを維持・向上させていく必要があります。
2. オープンアクセス誌への取り組みと学術情報発信
商業出版社が主導権を握る学術コミュニケーションを変革する動きとして、学術界ではオープンアクセス誌が活発化しています。本学図書館では、『The Bulletin of TOKYO DENTAL COLLEGE』の電子化に取り組んでおり、学内情報の発信だけでなく、研究者自身による学術コミュニケーションの構築にも貢献しています。これは、研究成果の迅速な公開と情報共有を促進し、学術の発展に寄与することを目的としています。 さらに、大学からの情報発信機能の整備として、2005年にはホームページの大幅な改訂を行い、学術情報のポータル化を目指しました。しかし、学内で生産される学術情報の積極的な発信という意味では、まだ不十分であり、今後の更なる改善が必要です。 機関リポジトリの構築・運用は比較的容易であると考えられ、大学の知的成果を保存・発信することで、大学評価の向上や大学の説明責任を果たす上で重要です。そのためには、全学的な合意形成と財政基盤の強化が必要です。
3. 機関リポジトリ構築の重要性と今後の展望
『学術情報基盤としての大学図書館等の今後の整備の在り方について(中間報告)』では、大学等で電子的に生産される研究成果や電子化された資料などを図書館が中心となって蓄積・保存し、インターネットを通じて広く利用者に提供する「機関リポジトリ」への取り組みが重要視されています。本学は、『東京歯科大学研究年報』の電子化実績があり、機関リポジトリの構築・運用は比較的容易だと考えられます。 質の高い情報(データベース)構築には図書館員の専門知識が不可欠であり、機関リポジトリは図書館が担うべき事業です。大学の知的成果を社会へ発信することは、大学評価の向上だけでなく、大学の説明責任を果たす上でも重要です。 機関リポジトリ構築に向けては、全学的な合意形成、財政基盤の強化など、様々な課題への取り組みが求められます。 本学図書館は、これらの課題を踏まえ、機関リポジトリ構築に向けた準備を進めるべきです。
V.図書館団体への加入状況
東京歯科大学図書館は、日本図書館協会、私立大学図書館協会、千葉県大学図書館協議会、千葉市図書館情報ネットワーク協議会、日本医学図書館協会・日本薬学図書館協議会等のコンソーシアムに加入し、相互協力体制を構築しています。これらの団体からの情報や、相互貸借、重複雑誌交換事業などを通して、図書館サービスの向上、予算面でのメリット、館員のスキルアップを図っています。
1. 大学図書館関連団体への加入と連携
東京歯科大学図書館は、日本図書館協会大学図書館部会、私立大学図書館協会東地区部会に加入しており、日本の図書館界をリードする団体との連携を強化しています。これらの団体を通じて、著作権法改正問題やRFID標準化問題といった、図書館運営に関連する重要な情報を入手し、大学図書館の改善・発展に役立てています。 日本図書館協会大学図書館部会は、図書館の理念・思想をリードする存在であり、専門家集団として諸団体を代表する立場にあります。同部会からの情報は、著作権問題や技術標準化など、本学図書館にとっても非常に有用です。私立大学図書館協会東地区部会は、私立大学の9割以上の図書館が加盟する団体で、大学図書館の改善・発展のための調査研究、研究会・講演会開催、機関誌の刊行といった事業を行っています。これらの団体への加入は、情報収集や他大学との連携強化、図書館運営の改善に大きく貢献しています。
2. 保健医療関連団体と地域連携団体への加入
本学図書館は、昭和36年に加盟した日本医歯薬図書館協議会に所属しており、国公私立の保健・医療系大学図書館、病院図書館、研究機関の図書館など110館以上が加盟する、医療関連領域における重要なネットワークの一員です。 この協議会は、保健・医療関連領域の図書館事業の振興、情報の流通に関する調査・研究・開発を推進しており、高度な知識習得のための環境整備、ひいては保健・医療関連領域の進歩発展に貢献することを目的としています。本学図書館は、昭和36年加盟という歴史を持ち、歯科系図書館としては草分け的存在です。 資料の貸借や文献複写などの相互利用、重複雑誌交換事業、電子ジャーナル・コンソーシアムへの参加などを通じて、予算面でのメリットも享受しています。平成13年には、館員のスキルアップのため「ヘルスサイエンス情報専門員認定資格制度」を創設するなど、医学図書館員の育成にも貢献しています。平成18年には、開催当番館として、協議会への積極的な参加を行っています。
3. 地域連携団体と大学図書館協議会の役割
本学図書館は、千葉市図書館情報ネットワーク協議会にも加盟しており、市内大学図書館や公共図書館、各種法人の図書館など27館が加盟する地域ネットワークの一員として、地域への図書館サービス向上に貢献しています。この協議会は、平成6年に設立され、全国的な趨勢の先駆け的存在となっています。 また、千葉県大学図書館協議会にも参加し、県内大学図書館との連携を図り、互いの発展に寄与しています。年1回の会議で、加盟50館以上の図書館から近況や課題が報告され、大変参考になっています。 さらに、電子ジャーナル・コンソーシアム(PULC:Private University Library Consortium)や「Lラーニング研究部会」にも参加し、情報資源の共有や研究活動の促進にも積極的に取り組んでいます。これらの団体への加入は、図書館の運営のみならず、地域社会への貢献にも繋がる重要な活動です。
