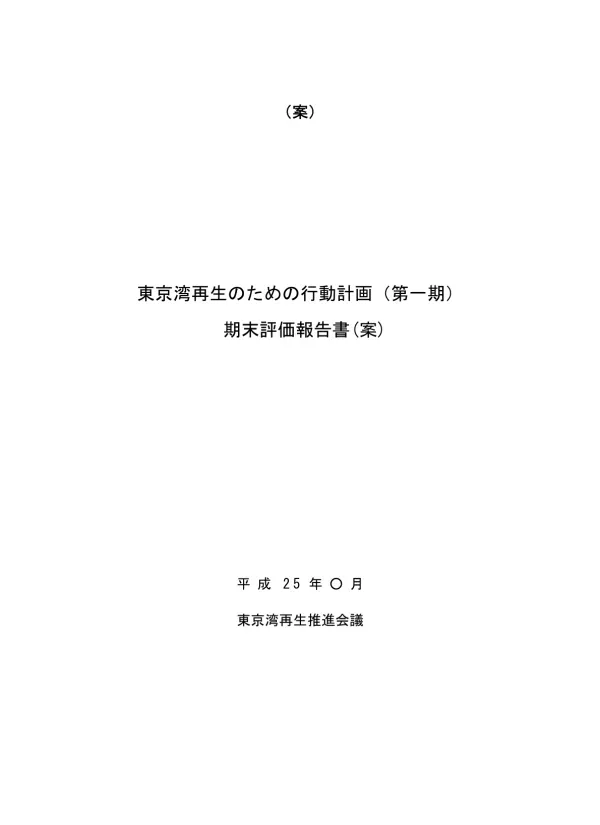
東京湾再生行動計画:最終評価
文書情報
| 著者 | 東京湾再生推進会議 |
| 文書タイプ | 期末評価報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 5.41 MB |
概要
I.東京湾の現状と課題 水質改善に向けた取り組み
東京湾は閉鎖性海域のため、窒素・リンによる富栄養化が進み、赤潮・青潮が発生、生態系に悪影響を与えています。CODなどの水質指標は改善傾向が見られず、底層DOも低いままで、底生生物の生息に影響を及ぼしています。汚濁負荷量の約7割は生活系であり、下水道整備、農業集落排水施設、浄化槽などの汚濁負荷削減対策が喫緊の課題です。 七都県市首脳会議を中心に、国土交通省、環境省などの関係省庁と連携し、東京湾再生のための行動計画に基づき、陸域・海域両面からの対策を実施しています。具体的な取り組みとしては、下水処理の高度化、干潟・藻場の再生、合流式下水道の改善などが挙げられます。しかしながら、底層DOの改善には至っておらず、長期的な視点での継続的な取り組みが必要です。
1. 東京湾の水環境の現状 閉鎖性海域の課題
東京湾は後背地に人口密集地を抱える閉鎖性海域であるため、窒素やリンによる富栄養化が進行し、赤潮や青潮の発生、生物への悪影響といった深刻な問題を抱えています。汚濁負荷量の約7割は生活系が占め、COD(化学的酸素要求量)の環境基準達成率は昭和61年度から横ばい状態が続いています。干潟や浅場の埋め立てによる自然浄化機能の低下、漂着ゴミによる沿岸域の環境悪化も大きな課題となっています。これらの現状を踏まえ、水質改善に向けた具体的な対策が急務となっています。特に、底層の溶存酸素量(DO)の低さが、多くの生物の生息を脅かしており、この改善が重要な目標となっています。COD、全窒素(T-N)、全リン(T-P)といった水質指標の改善も、生態系の回復には不可欠です。現状分析から、持続可能な東京湾の再生のためには、多角的なアプローチによる長期的な取り組みが必要であることが示唆されています。
2. 陸域からの汚濁負荷削減対策 多様な施策の展開
陸域からの汚濁負荷削減に向け、様々な対策が講じられています。具体的には、第7次水質総量削減計画に基づく取り組み、下水道・農業集落排水施設・浄化槽などの汚水処理施設の整備・普及と高度処理の促進、河川浄化対策、森林の整備・保全、貯留浸透施設の設置、浮遊ゴミの回収などが挙げられます。これらの対策は、栄養塩類などの流入負荷を削減し、赤潮の発生抑制、生態系の回復を目指しています。さらに、市民参加型の取り組みも推進されており、埼玉県では河川美化活動団体への登録制度、横浜市では水辺愛護会への支援、川崎市では多摩川美化活動への支援など、地域住民との協働による環境保全活動が活発に行われています。これらの取り組みを通じて、陸域からの汚濁負荷を一定程度削減することに成功していますが、更なる削減目標の達成には、継続的な努力と新たな対策の導入が不可欠です。
3. 海域における環境改善対策 底質改善と生物生息環境の回復
海域における環境改善対策としては、行動計画に位置づけられた汚泥浚渫・覆砂、浅場・海浜の造成、生物に配慮した港湾構造物の整備、深掘跡の埋め戻しなどが実施されています。これらの施策によって、周辺環境においては水質・底質の改善や生物相・生物量の増加が確認され、一定の効果が認められています。しかしながら、底質の改善や湾全体の底層DOへの顕著な変化は認められず、現状では明らかな改善傾向は見られていません。特に、底層DOの改善は、年間を通して底生生物が生息できる環境を実現するために不可欠な要素であり、更なる対策の強化が求められています。アマモ場再生といった取り組みも実施されていますが、海水浴やマリンスポーツとの両立など、課題も存在します。
4. 東京湾再生に向けたモニタリングと今後の展望
東京湾の水質環境を把握し、施策の効果を評価するため、「東京湾の環境モニタリング」が実施されています。平成20年度から実施されている東京湾水質一斉調査は、参加団体数が増加し、調査項目に生物調査が追加されるなど、内容が充実しています。 データは東京湾環境情報センターで公開され、シミュレーションモデルの構築にも活用されています。海洋短波レーダーによるモニタリングシステムも開発・運用され、生態系のネットワーク解明に貢献しています。 今後の課題としては、水質・底質中心のモニタリングから、生物の生息状況を含むより包括的な生態系モニタリングへの進化が挙げられます。 これは、東京湾の「水環境再生」にとどまらず、「豊かな生態系の再生」を目指す上で不可欠なステップです。 更なる定点観測点の増設や、関係機関との連携強化による効率的なモニタリング体制の構築が求められます。
II.陸域からの汚濁負荷削減 具体的な対策と成果
陸域からの汚濁負荷削減のため、下水道整備の促進、農業集落排水施設や浄化槽の整備・高度化、河川浄化、森林整備・保全など多様な対策を実施。エコファーマーの推進も含まれています。埼玉県では「川の国応援団美化活動団体」を支援、横浜市では水辺愛護会への補助金交付、川崎市では多摩川美化活動への支援など、市民参加型の取り組みも推進されています。これらの施策により一定の成果は認められましたが、栄養塩類の流入削減、雨天時流出負荷の抑制など、更なる対策強化が必要です。特に、合流式下水道の改善は、平成15年度の下水道法改正を受け、平成25年度(処理区域面積が大きい場合は平成35年度)までに完了することが義務付けられています。
1. 下水道整備と汚水処理施設の高度化
陸域からの汚濁負荷削減において、下水道整備の充実と汚水処理施設の高度化は重要な柱となっています。具体的には、下水道対策の推進、農業集落排水施設や浄化槽などの生活排水処理施設の整備・普及、そして高度処理の促進が挙げられます。これらの施策は、生活排水から排出される窒素やリンなどの栄養塩類の削減に大きく貢献し、富栄養化による赤潮・青潮の発生抑制に繋がる効果が期待されます。特に、合流式下水道については、平成15年度の下水道法施行令改正により、雨天時の未処理放流水の削減が義務付けられており、ろ過スクリンの設置、貯留施設、消毒施設の整備などが重点的に実施されています。効率的な合流式下水道緊急改善計画策定の手引きも策定され、計画的な改善が進められています。これらの取り組みを通じて、最終的には東京湾への栄養塩類の流入量を削減し、水質の改善を図ることが目指されています。
2. 河川浄化対策と森林整備 保全
河川の水質改善と森林の保全も、陸域からの汚濁負荷削減に重要な役割を果たしています。河川浄化事業は、河川に流入する汚染物質を削減し、東京湾への汚濁負荷を減らす効果があります。一方、森林の整備・保全は、土壌浸透能力の向上による雨水中の栄養塩類の流出抑制、水源涵養、土砂流出・崩壊防止といった多様な効果をもたらします。特に、公益的機能の高い森林である保安林の指定、荒廃地の復旧、間伐などの森林整備は、面源汚濁負荷の削減に貢献しています。これらの対策は、点的な汚濁源対策だけでなく、広範囲にわたる面的な対策を組み合わせることで、より効果的な汚濁負荷削減を目指しています。 これらの取り組みを通じて、陸域からの汚染物質の流入抑制と東京湾の水質保全に貢献しています。
3. 市民参加型環境保全活動の推進
東京湾再生に向けた取り組みにおいて、市民参加型の環境保全活動の推進も重要な要素となっています。埼玉県では河川愛護意識の高揚と良好な河川環境の維持・保全を目的として、「川の国応援団美化活動団体」への登録制度を設け、ボランティア活動への支援を行っています。平成24年3月末時点で283団体が登録しており、活発な活動が行われています。横浜市では水辺愛護会による河川や緑道の美化活動に補助金を交付するなど、地域住民による自主的な環境保全活動を支援しています。川崎市では、多摩川美化活動に多くの市民が参加し、毎年大量のごみが回収されています。これらの取り組みは、市民の環境保全意識の向上、自主的な活動の促進、そして地域社会全体の環境意識の醸成に繋がっています。国土交通省や港湾管理者による清掃船を用いた海面清掃活動も、市民参加型の活動と併せて、東京湾の環境改善に貢献しています。平成21~23年度には0.8トンのゴミが回収されています。
III.海域における環境改善対策 底質改善と生物多様性
海域対策として、汚泥浚渫、覆砂、浅場・海浜の造成、生物に配慮した港湾構造物の整備などが実施され、一部地域では水質・底質の改善、生物相の増加が確認されました。しかし、湾全体の底層DOの改善には至っていません。アマモ場の再生なども行われていますが、レクリエーション利用との調整が必要となっています。底生生物調査を強化し、生態系モニタリングをより包括的なものにすることで、水質・底質だけでなく生物多様性を考慮した東京湾再生を目指しています。具体的には、高濃度酸素水の海底への曝露による夏季における底質悪化抑制効果の確認や、海草等を用いたエタノール再生技術の可能性検討などが挙げられます。
1. 汚泥浚渫 覆砂 浅場 海浜造成等の底質改善対策
東京湾の海域における環境改善対策として、汚泥の浚渫や覆砂、浅場や海浜の造成、生物に配慮した港湾構造物の整備などが実施されています。これらの対策は、海底の底質を改善し、海水の浄化能力を高めることを目的としています。具体的には、汚泥浚渫によって海底に堆積した汚泥を除去し、水質を改善します。覆砂は、汚染された底質を砂で覆い、汚染物質の拡散を防ぎ、生物の生息環境を向上させる効果があります。浅場や海浜の造成は、生物の生息場所を創出するとともに、自然の浄化機能を回復させる効果が期待されます。また、港湾構造物の整備においても、生物への影響を考慮した設計・施工を行うことで、生態系の保全に配慮しています。これらの対策は、東京湾の底質環境の改善と生物多様性の向上に貢献するものと期待されていますが、湾全体の底層DOに顕著な変化は見られない現状です。これらの対策の効果をさらに高めるためには、継続的なモニタリングと評価、そして必要に応じた対策の修正・追加が不可欠です。
2. アマモ場再生等による生物生息環境の改善
海域の環境改善策として、アマモ場などの海草藻場の再生・育成も重要な取り組みとなっています。横浜港金沢地区のベイサイドマリーナ前面水域では、アマモ場の再生とモニタリングが平成15年から19年度にかけて実施され、アマモ場の再生・拡大が確認されています。しかし、海水浴やウィンドサーフィンなどのレクリエーション利用との兼ね合い、アマモ場の管理方法について調整が必要な状況です。 海草藻場は、水質浄化作用や生物の生息場所を提供するなど、生態系の維持・回復に重要な役割を果たすことから、これらの再生・拡大は東京湾の生物多様性の向上に大きく寄与すると考えられています。 今後、アマモ場再生等の取り組みを拡大していくためには、効果的な育成方法の確立や、レクリエーション利用との調和を図るための計画的な管理体制の構築が重要となります。
3. 高濃度酸素水発生装置の導入と効果
夏季の底質悪化抑制策として、高濃度酸素水発生装置の導入とその効果検証が実施されています。 これは、装置近傍においては夏季の底質悪化を抑制できることが確認されています。ただし、効果範囲は限定的であるため、より広範囲に効果を発揮できる技術開発や、複数箇所への導入による効果の検証が必要となります。高濃度酸素水発生装置は、貧酸素水塊の解消に寄与する可能性があり、底層DOの改善に繋がる効果が期待できます。 今後の取り組みとしては、装置の性能向上や導入方法の最適化、効果的な配置計画などの検討が必要となるでしょう。より効果的な底質改善に向けた技術革新と、その効果の更なる検証が求められます。
IV.モニタリングと情報発信 データに基づく効果的な対策
東京湾水質一斉調査は、参加団体数が増加し、調査項目に生物調査が追加されるなど、内容が充実しています。得られたデータは東京湾環境情報センターで公開され、シミュレーションシステムの構築にも活用されています。海洋短波レーダーによるモニタリングシステムも開発・運用され、生態系ネットワークの解明に貢献しています。 今後、更なる定点観測点の増設や、水環境モニタリングから生態系モニタリングへの進化を目指し、より包括的なモニタリング体制を構築することが重要です。 これにより、東京湾再生の施策効果の評価をより正確に行い、順応的な管理体制を構築することが求められています。
1. 東京湾水質一斉調査とその成果
東京湾の水質環境を把握し、水質改善施策の効果を評価するために、東京湾水質一斉調査が実施されています。平成20年度の初回調査では約50団体が参加しましたが、平成21年度以降は毎年約140団体が参加するなど、調査への参加が拡大しています。調査地点数も約600から約800に増加しており、調査の広がりを見せています。平成22年度からは調査結果を共有し、改善策を議論するワークショップを開催し、さらに平成23年度からは生物調査も追加するなど、調査内容も充実させています。これらの取り組みは、東京湾再生への関心の醸成、汚濁メカニズムの解明に貢献しています。国土交通省関東地方整備局の東京湾環境情報センターでは、収集されたデータが統一フォーマットで公開・提供されており、関係機関による情報共有やシミュレーションモデルの構築にも活用されています。平成24年度調査では、生物調査データの収集は試験的な段階であり、共通ルールの設定が検討されている段階です。
2. 海洋短波レーダー等によるモニタリングシステム
東京湾の環境モニタリングにおいては、海洋短波レーダーによるモニタリングシステムが重要な役割を果たしています。このシステムはインターネット上で公開されており、海洋短波レーダーによる流況観測結果と人工衛星データの重ね合わせ解析も行われています。これにより、アサリ浮遊幼生を指標とした湾内の生態系ネットワークの存在が示され、東京湾の環境メカニズムの解明に役立つデータが得られています。さらに、システムの高度化に向けて、海洋短波レーダーによる流況観測結果の高次的な利用、自動昇降ブイによる湾口モニタリング、長期連続観測ブイによる湾内浅海域水質リアルタイムモニタリングなどを組み合わせたシステム構築が検討されています。これらの取り組みは、東京湾の生態系ネットワークの解明、環境メカニズムの理解を深める上で重要な役割を果たしており、今後の水質改善や生態系保全のための施策に役立てられます。
3. モニタリングの進化 水環境から生態系モニタリングへ
東京湾モニタリングの将来に向けた課題として、水質・底質中心のモニタリングから、生物の生息状況なども含めたより包括的な生態系モニタリングへの進化が挙げられています。これは、東京湾の「水環境再生」にとどまらず、生物多様性などの視点からも健全な「豊かな生態系の再生」を目指す上で不可欠です。そのためには、底質や底生生物の実態把握を強化する必要があります。七都県市首脳会議環境問題対策委員会水質改善専門部会で策定された「東京湾における底生生物調査指針及び底生生物等による底質評価方法」を活用し、七都県市が連携して底生生物のモニタリングを行うことで、より詳細な生態系の状況を把握し、効果的な対策を講じることが可能になります。 この包括的なモニタリング体制の確立によって、東京湾再生のための戦略的な意思決定を行うことができます。
V.今後の展望 持続可能な東京湾再生に向けて
東京湾再生には、長期的な視点と粘り強い取り組みが必要です。底層DOの改善といった最終目標だけでなく、過程における効果も評価できる指標の開発が重要です。市民参加型の活動や、企業のCSR活動への連携強化も不可欠です。 「食」と東京湾再生を繋げる取り組みも重要であり、江戸前のブランド復活を目指した取り組みも必要です。 情報発信の強化、環境教育の推進、関係機関との連携強化により、次世代に繋がる持続可能な東京湾再生を実現していく必要があります。
1. 東京湾再生の長期的な取り組みと指標の重要性
東京湾の再生は、短期的な取り組みでは達成できない長期的な課題です。そのため、継続的な取り組みと、その効果を適切に評価できる指標の設定が不可欠です。これまでの行動計画では、底層のDO(溶存酸素量)のみを指標としていましたが、これは最終的な目標であり、その過程における様々な施策の効果を十分に評価できていませんでした。今後は、より多様な主体による活動を促進するため、分かりやすく、よりきめ細かい指標と評価手法の開発が必要です。例えば、NPOによる海岸清掃活動のように、底層DOに直接影響しない活動も、東京湾再生に貢献する重要な活動として適切に評価する必要があります。 また、部分的で小規模な対策であっても、継続的に多数の場所で実施することで、積み重ねて効果を発揮する可能性があるため、地道な努力が重要です。
2. 順応的管理と情報共有の重要性
東京湾再生の取り組みにおいては、モニタリング結果を迅速かつ適切に環境改善施策にフィードバックできる順応的な管理体制の構築が重要です。モニタリングデータに基づいて柔軟に施策を運用することで、より効率的かつ効果的な対策を実現できます。また、関係機関や市民など、様々な主体が東京湾再生に参画するためには、情報共有の促進が不可欠です。東京湾の環境に関する正しい知識の普及・啓発、再生の取り組み状況に関する情報共有、今後の対策に関する意見交換などを積極的に行うことで、より多くの主体が理解と協力を得ることが期待できます。 さらに、必ずしも環境改善を直接の目的とした活動でなくても、様々な主体が楽しみながら実施する活動が、結果的に環境改善や環境教育に繋がる可能性があるため、連携・協働が重要です。
3. 企業のCSR活動の促進と人材育成
東京湾の環境保全においては、企業の社会的責任(CSR)を果たす活動の促進が重要です。陸域における森林保全などは進んできていますが、海域における環境保全活動は依然として不足しています。特に、東京湾沿岸の護岸の約1/5は民間所有であり、これらの所有者による老朽化対策や耐震化と合わせて、環境保全への配慮が求められます。 また、東京湾に関する情報を集約・蓄積し、シンクタンクとしての機能を強化することで、研究体制の充実・深化、情報の一元把握が可能になります。さらに、子どもの頃から海での体験や環境教育の機会を推進し、海への理解や関心を育むことで、将来、東京湾再生を担う人材を育成することが重要です。 これらを通じて、社会全体で東京湾の環境保全に取り組む意識を高めることが必要です。
4. 食 との連携による東京湾再生の促進
東京湾再生を推進する上で、「食」との連携が重要だと指摘されています。かつて東京湾は豊かな漁場であり、「江戸前」として知られるブランドを形成していました。この豊かな食文化を取り戻すことを目指すことで、多くの人々の関心を東京湾再生に向けることができます。そのためには、東京湾の環境に関する正しい知識の普及啓発、再生の取り組み状況に関する情報共有、今後の対策・行動に関する意見交換が不可欠です。 様々な主体が楽しみながら参加できる活動も、環境改善や環境教育に繋がるため、積極的な連携・協働が求められます。 東京湾の豊かな生態系と食文化の復活は、持続可能な東京湾再生への強力な推進力となるでしょう。
