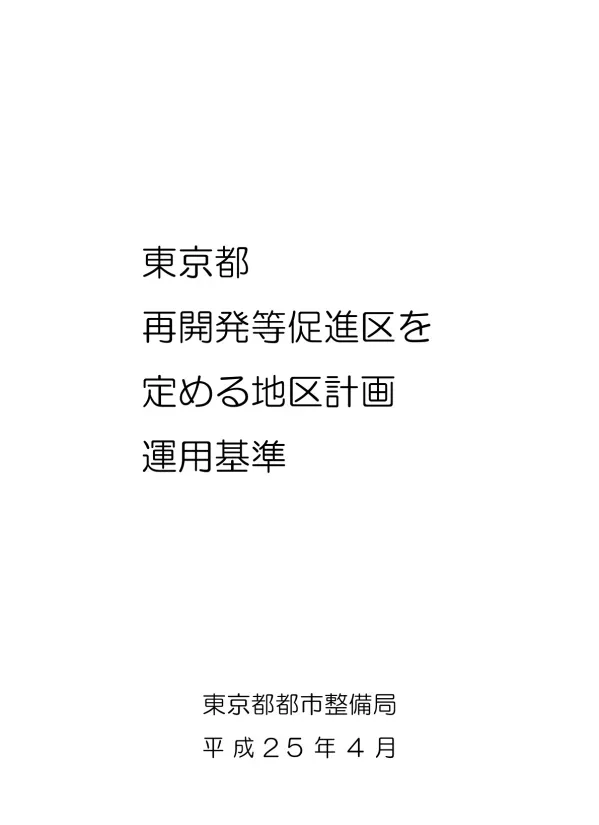
東京都再開発促進地区計画運用基準
文書情報
| 学校 | 東京都 (Tokyo Metropolitan Government) |
| 専攻 | 都市計画 (Urban Planning) |
| 場所 | 東京都 (Tokyo) |
| 文書タイプ | 運用基準 (Operational Guidelines) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.29 MB |
概要
I.評価容積率の設定基準 Assessment Floor Area Ratio Setting Standards
本資料は、東京都区部の面積3.0haを超える「再開発等促進区を定める地区計画」の運用基準を示しています。評価容積率は、有効空地、緑化率、都市基盤施設整備状況などを考慮して算定されます。計画容積率は、見直し相当容積率に評価容積率を加えた範囲内で、計画内容の優良性、周辺市街地への貢献度などを総合的に判断して設定されます。 東京の街並み景観の形成や都心居住の推進にも配慮した計画となっています。
1. 評価容積率の算定 Assessment Floor Area Ratio Calculation
評価容積率の算定は、地区計画における土地利用転換の円滑化、土地の高度利用、都市機能の増進を目的として行われます。 具体的な算定方法は、有効空地、緑化率、都市基盤施設の整備状況など、複数の要素を総合的に勘案して決定されます。 例えば、緑化率が高い区域では、緑化係数を用いて評価容積率にプラスアルファが加算される仕組みとなっています。 また、見直し相当容積率という基準があり、これは当該区域の都市構造上の位置付け、土地の高度利用や都市機能の増進への貢献度、都心居住の推進や業務商業機能の開発・整備・育成への寄与度などを勘案して決定されます。 最終的な計画容積率は、この見直し相当容積率に評価容積率を加えた範囲内で、計画内容の優良性、周辺市街地への貢献度、計画規模と都市基盤施設とのバランス、地域環境の育成・整備への貢献度、景観への配慮、周辺市街地との調和などを総合的に判断して決定されます。 これらの要素は、東京の街並み景観の形成や都心居住の推進といった都市政策目標とも密接に関連しています。
2. 評価容積率の最高限度と用途制限 Maximum Assessment Floor Area Ratio and Usage Restrictions
評価容積率には最高限度が設定されており、その上限は用途によって異なります。 例えば、事務所用途や住居系用途地域では、それぞれに制限が設けられています。 具体的な制限内容は、基本計画等で都市計画上の位置付けがある地域か、周辺市街地との土地利用上の一体性を確保できる地域かなどによって変化します。 住宅用途については、基本計画等で都市計画上の位置付けがある地域、または周辺市街地との土地利用上の一体性を確保できる地域において、評価容積率に算入できる可能性があります。 育成用途の設定割合が一定の条件を満たす場合にも、住宅用途として評価容積率に算入できる場合があります。 これらの制限は、計画区域全体のバランスや、周辺環境への影響を考慮して定められています。 東京都の景観計画や、東京のしゃれた街並みづくり推進条例なども、これらの制限に影響を与えます。
3. 計画容積率の設定と周辺環境への配慮 Planned Floor Area Ratio Setting and Consideration for the Surrounding Environment
計画容積率は、評価容積率と見直し相当容積率を基に、計画の優良性や周辺市街地への貢献度などを総合的に判断して決定されます。 計画区域内の交通量増加などの影響も考慮され、必要に応じて対策が講じられます。 大規模災害時の建築物の自立性確保や帰宅困難者対策なども重要な検討事項となります。 具体的には、防災備蓄倉庫や自家発電設備の設置、東京都帰宅困難者対策条例の趣旨を踏まえた対策などが求められます。 周辺環境との調和も重視され、緑化率の向上、ヒートアイランド対策、風環境への配慮などが求められます。 特に、街並み景観重点地区などでは、条例やガイドラインに則った計画が必須となります。 周辺市街地との調和を図るため、隣接する土地の利用状況などを考慮した計画とする必要があります。これは、住宅の配置や高さなどにも反映されます。 建ぺい率や絶対高さ制限の緩和を行う場合も、周辺環境との調和を優先し、適切な範囲内で緩和が認められます。
II.有効空地算定基準 Effective Open Space Calculation Standards
有効空地は、評価容積率算定において重要な要素です。算定基準は、有効空地面積、有効係数などを含み、集合住宅の共用庭などが一定条件下で有効空地に算入できる特例も規定されています。緑化空間の確保や景観形成への貢献度も考慮されます。
1. 有効空地による評価容積率の設定 Setting Assessment Floor Area Ratio using Effective Open Space
このセクションでは、有効空地が評価容積率の算定にどのように影響するかを説明しています。有効空地は、都市計画において重要な要素であり、その面積や質によって評価容積率が変動します。 具体的には、有効空地の面積が大きければ大きいほど、評価容積率が高くなる傾向があります。 この基準は、良好な都市環境の形成、特に緑地やオープンスペースの確保を促進することを目的としています。 また、有効空地として認められる範囲についても明確な基準が示されており、単なる空地だけでなく、景観形成や地域活性化に貢献するような空間が考慮されています。 例えば、住居系用途地域における集合住宅の居住者用共用庭などは、一定の条件を満たせば有効空地として認められ、評価容積率の算定に反映されます。これは、緑化空間の確保や良好な居住環境の形成を促進するための重要な要素となっています。 この基準によって、開発事業者は、有効空地の確保に積極的に取り組むインセンティブを得ることになり、結果として、より魅力的で住みやすい都市環境の創造に繋がるものと考えられています。
2. 有効空地面積の算定 Calculation of Effective Open Space Area
有効空地面積の算定方法については、文書では具体的な数値や計算式は示されていませんが、敷地の形状や利用状況に応じて柔軟に判断されることが示唆されています。 重要なのは、単なる面積だけでなく、その空間が都市環境に与える質的な影響も考慮される点です。 例えば、まとまった緑化空間が確保されているか、景観上または修景上、当該地域の環境形成に寄与するような形態や機能を有しているかなどが、評価の対象となります。 そのため、有効空地面積の算定は、単なる測量の結果ではなく、計画全体の意図や周辺環境との調和などを考慮した上で総合的に判断される必要があると解釈できます。 この算定基準は、単に数値的な目標を達成することだけでなく、質の高い都市空間を創造することを重視していると言えるでしょう。 具体的な算定方法は、後続の技術基準などで詳細に規定されていると考えられます。
3. 有効係数の適用 Application of Effective Coefficient
有効係数は、有効空地の質や役割を数値化する指標として用いられます。 文書では、有効係数の具体的な算出方法や数値は表を参照することとして詳細な説明は省略されていますが、有効空地の機能や配置によって係数が変化することが示唆されています。 例えば、区域内のネットワークを形成する歩行者専用通路などは、通常の有効係数よりも高い係数が適用される可能性があります。 これは、歩行者にとって快適で安全な空間を確保することにより、都市環境の質を高めることを目的としています。 同様に、貫通通路のように、公共施設相互間を有効に連絡する歩行者専用通路も高い係数が適用される可能性があります。 これらの特例規定は、単に空地の面積を増やすだけでなく、都市空間における機能性や利便性を向上させるような空間の創出を促すためのものです。 有効係数の適用によって、質の高い有効空地を確保した計画がより高く評価される仕組みとなっています。
III.容積の適正配分 Appropriate Volume Allocation
容積の適正配分は、隣接地区間の調整を考慮し、周辺環境への配慮や主要な公共施設の整備状況を勘案して行われます。計画容積率に基づき、地区ごとに算定された数値の範囲内で容積を配分します。ただし、周辺市街地環境への貢献や公共施設の有効性向上などが認められる場合は、特例が適用される場合があります。
1. 容積の適正配分の原則 Principles of Appropriate Volume Allocation
このセクションでは、地区整備計画における容積の適正配分の基本原則が示されています。原則として、地区整備計画の区域内の区分された地区ごとに算定した計画容積率の数値に、当該数値の定められた区域内の敷地面積を乗じたものの合計の範囲内で、建築物の容積を適正配分するとされています。これは、計画容積率を各地区に均等に割り当てることで、計画全体のバランスを保ち、過度な高層建築物の建設などを抑制することを目的としていると考えられます。 各地区の特性や周辺環境を考慮した柔軟な対応も可能であり、単なる数値的な配分にとどまらず、都市計画全体の目標達成に資するよう配慮されている点が重要です。 この原則は、計画区域全体の調和と、各地区の特性を尊重した開発を両立させるための基盤となっています。 具体的な配分方法は、計画容積率や各地区の面積、そして周辺環境との関係性などを総合的に判断して決定されることになります。
2. 容積の適正配分の特例 Exceptional Cases of Appropriate Volume Allocation
容積の適正配分においては、いくつかの特例が認められています。 隣接する地区間において、周辺市街地環境への配慮や区域内環境の向上に貢献する計画、主要な公共施設等に位置付けられた広場などの有効性の確保と向上が認められる計画、そして容積の配分による交通負荷などの交通上の支障がない計画といった条件を満たす場合、標準的な基準よりも柔軟な容積配分が認められる可能性があります。 これは、特定の地区に集中させることで相乗効果が期待できる場合や、公共性の高い施設の整備を促進する場合などに有効です。 ただし、特例適用にあたっては、周辺環境への影響や交通への影響などの詳細な検討が必要となり、より厳格な審査が行われることが想定されます。 これらの特例は、画一的な容積配分では対応できない特殊な状況に対応するための柔軟な制度として位置づけられています。 都市計画全体の目標達成と個々の計画の特性をバランス良く考慮することで、より最適な都市空間の形成を目指しています。
3. 用途の適正配置 Appropriate Allocation of Land Use
複数の街区または地区を一体的に整備する計画において、用途の適正配置に関する規定があります。 これは、特定の用途を集約することで、より良好な環境の形成や区域の活性化に繋がる場合に、育成用途などの建築物の用途を相互に適正に配置することを認めるものです。 例えば、商業施設をまとめて配置することで、賑わいのある街区を形成したり、住宅地と商業地を明確に分けることで、静穏な居住環境を確保したりするといった計画が考えられます。 この規定は、計画全体のバランスや、周辺環境への影響などを考慮して、柔軟な用途配置を可能にすることで、より質の高い都市空間を形成することを目指しています。 ただし、用途の配置は、周辺市街地への影響や、計画区域全体の調和なども考慮し、計画的に行われる必要があります。 具体的には、近隣住民との協議や関係機関との調整などを通して、最適な配置が決定されることになります。
IV.建築制限と都市景観 Building Restrictions and Urban Landscape
建築物の高さ、壁面の位置、色彩などは、東京のしゃれた街並みづくり推進条例などに基づき、街並み景観との調和を図りながら制限されます。特に「街並み景観重点地区」では、ガイドラインに沿った計画が求められます。周辺市街地への影響にも十分配慮し、住宅の配置や高さなどを調整する必要があります。都市計画における建築基準法の規定も遵守する必要があります。
1. 建築物の高さ制限 Building Height Restrictions
このセクションでは、建築物の高さに関する制限について解説しています。 まず、「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」で指定された「街並み景観重点地区」など、条例や基本計画等で建築物の高さについて具体的な数値や考え方が示されている区域では、それらの規定に適合する必要があります。これは、地域の景観を保全し、調和のとれた街並みを形成することを目的としています。 一方、それ以外の区域については、表に示された数値以上の高さを確保する必要があります。ただし、近隣の土地利用状況や都市計画上の合理的理由があれば、この制限が適用されない場合があります。 また、道路に沿った歩行者交通の円滑化を図る必要性がある場合、壁面後退区域における工作物の設置制限を行うことで、結果的に建築物の高さが制限されるケースも想定されます。 高層建築物の計画においては、風環境への配慮も重要視され、風洞実験などのシミュレーションによる影響予測と、予防・改善のための適切な措置が求められます。 これらの高さ制限は、周辺市街地への影響や、安全性の確保といった多角的な視点から総合的に判断され、決定されます。
2. 壁面の位置制限と都市景観への配慮 Wall Position Restrictions and Consideration for Urban Landscape
建築物の壁面の位置に関しても、制限が設けられています。「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」で指定された「街並み景観重点地区」などでは、条例や基本計画等で示されたガイドラインに沿う必要があります。これは、歴史的建造物や伝統的な街並みの保全、あるいは新たな景観形成の指針となるものです。 それ以外の区域では、表に示された数値以上の壁面後退を確保する必要があります。ただし、近隣の土地利用状況などを考慮し、支障がないと判断される場合は、この制限の適用除外が認められます。 壁面後退は、歩行者空間の確保や、建築物と道路・空地との調和を図る上で重要な要素であり、快適な都市空間の創出に貢献します。 また、建築物の形態、色彩などが周辺地域に与える影響についても考慮が必要であり、個々の建築物のデザインだけでなく、建築物相互の調和に配慮し、計画区域全体で質の高い都市景観を創出する計画が求められます。 東京都及び区市町村の景観条例に基づき、景観関係部局との十分な調整も不可欠です。
3. 建築制限条例による担保と街並み再生地区の特例 Guarantee by Building Restriction Ordinance and Special Cases in Townscape Regeneration Districts
地区整備計画で定められた建築物の敷地、構造、建築設備、用途、形態に関する事項は、原則として建築基準法第68条の2に基づく条例で制限事項として定められます。これは、計画内容を法的根拠に基づいて確実に実現するための重要な措置です。 この条例によって、計画に沿った開発・整備が行われ、計画された都市景観が保全されます。 一方で、「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」に基づき指定された街並み再生地区内においては、特例が適用される可能性があります。「街並み再生方針」で示された考え方に基づき、地域の特性に応じた柔軟な対応が認められるケースも存在します。 これは、歴史的、文化的価値の高い街並みを再生する際に、画一的な基準では対応できない特殊な状況を考慮したものです。 これらの建築制限と都市景観に関する規定は、都市計画における重要な要素であり、良好な都市環境の形成と維持に貢献するものです。 建ぺい率の緩和なども、周辺市街地との調和を図る上で重要な要素となります。
V.開発者負担と協議 Developer Burden and Consultation
公共施設等の整備は、関係地権者、住民、開発事業者間での協議に基づき、都市計画決定前に協定を締結する必要があります。周辺市街地への影響が大きい場合は、開発事業者による区域外の公共施設整備が開発条件となる場合もあります。公共施設の整備状況は、容積率の算定や建築基準法の認定に影響します。
1. 主要な公共施設 地区施設の整備に関する協議 Consultation on the Development of Major Public and District Facilities
地区計画の区域内における主要な公共施設や地区施設の整備については、企画提案段階から区市町村、関係地権者、住民、開発事業者間で綿密な協議を行う必要があります。 協議事項には、施設の整備主体、規模、時期、将来の所有、維持、管理などが含まれ、原則として都市計画決定前に協定を締結し、その写しを東京都へ提出する必要があります。 これは、関係者間の合意形成を図り、計画の円滑な推進を確保するための重要なプロセスです。 協定の内容は、関係者間の合意に基づき決定されますが、特に地区計画と再開発等促進区のみを定める場合には、開発動向などを勘案して、関係者による確実な施設整備を内容とする場合があります。 この段階での協議は、後々のトラブル防止や、計画の円滑な実行に大きく貢献します。
2. 開発者負担と区域外公共施設整備 Developer Burden and Development of Public Facilities Outside the Designated Area
計画の内容、開発容量、発生交通量などが周辺市街地の環境に著しく影響を与える可能性がある場合には、開発事業者による区域外の公共施設等の整備が開発条件となる場合があります。 これは、開発行為による周辺環境への影響を最小限に抑え、地域全体への貢献を確保するための措置です。開発事業者には、区域外公共施設の整備費用など、応分の負担が求められます。 具体的にどのような公共施設の整備が必要となるかは、個々の計画によって異なりますが、周辺道路の拡幅や交通渋滞対策のための施設などが考えられます。 この負担は、開発事業者にとって追加的なコストとなりますが、同時に、開発計画の承認を得るための重要な条件となります。 この規定は、開発事業者と地域社会との相互理解に基づいた、持続可能な都市開発を目指しています。
3. 施設整備の時期と標示板設置 防災計画への記載 Timing of Facility Development Signboard Installation and Inclusion in Disaster Prevention Plans
容積率の算定対象となる公共施設、有効空地、住宅などの整備は、関連する建築物や施設の供用開始時期に合わせて行われるべきです。 これは、施設の利用開始と同時に必要なインフラが整備されている状態を確保するためです。 また、評価容積率の設定対象とした部分を示す位置、内容、管理責任者などを記載した標示板を、一般の公衆や居住者が認知できるように設置する必要があります。 これは、透明性を確保し、利用者への情報提供を徹底するための措置です。 さらに、大規模災害時における建築物の自立性確保や一時滞在施設の確保に係る部分は、東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画に記載し、東京消防庁へ届け出る必要があります。 これらの規定は、安全で安心な都市空間の形成に資するものであり、開発事業者にはこれらの規定を遵守することが求められます。
