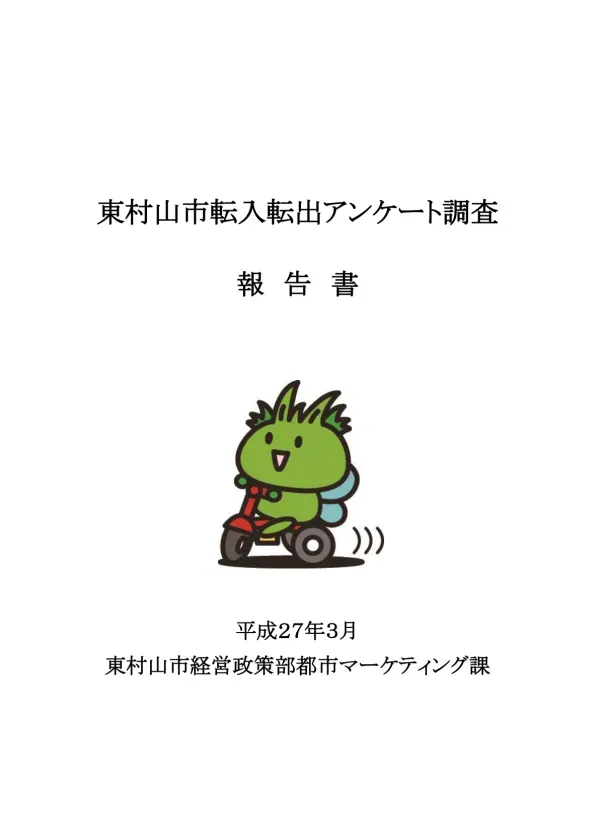
東村山市民転入実態調査報告書
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 4.24 MB |
| 文書タイプ | 調査報告書 |
概要
I.東村山市への転入理由 主要な動機と検討地域
東村山市への転入理由は、約7割が自身の意思によるもので、「他の市区町村も探したが、東村山市に決めた」(51.3%)が最も多く、「最初から東村山市に決めていた」(20.0%)が続きました。検討地域は、近隣の小平市、清瀬市、西東京市、所沢市が上位でした。子育て環境や自然環境への関心の高さがうかがえます。住宅価格や通勤時間も転入の決め手として重要視されています。
1. 東村山市への転入 主要な動機
東村山市への転入理由に関する調査では、回答者の約7割が自身の意思で転入を決めたと回答しています。その中で最も多かった理由は「他の市区町村も探したが、東村山市に決めた」で51.3%を占め、次いで「東村山市に住むしかなかった(社宅が東村山市にある、同居する家族が住んでいる等)」が28.1%、「最初から東村山市に決めていたので、他は検討しなかった」が20.0%となっています。これは、東村山市が居住地として魅力的な選択肢であったことを示唆しており、多くの転入者が他の地域を検討した上で東村山市を選択しているという点が注目に値します。 特に、「他の市区町村も探したが、東村山市に決めた」と回答した人たちの選択基準を知ることは、東村山市の魅力を理解する上で重要です。 この結果から、東村山市は単なる選択肢ではなく、積極的に選ばれる街であることが分かります。 今後、東村山市の魅力をさらに高めるためには、この高い割合を維持・向上させるための施策が必要となるでしょう。 具体的には、どのような点が東村山市を選んだ理由になったのか、詳細な分析を行うことで、更なる魅力向上のための施策を検討できる可能性があります。
2. 東村山市以外の検討地域
「他の市区町村も探したが、東村山市に決めた」と回答した人たちが、東村山市以外に検討した市区町村について分析すると、小平市、清瀬市、西東京市、所沢市といった東村山市に隣接または近接する市町村が上位にランクインしています。この結果は、転入者にとって地理的な近さが重要な要素であることを示唆しています。通勤・通学の利便性や、既存の生活圏からの距離の近さなどが、市町村選択における大きな要因となっていると考えられます。 これらの近隣市町村との比較において、東村山市が選ばれたということは、価格、自然環境、教育環境、生活利便性などの面で、競争力があることを意味します。 しかし、これらの近隣都市との比較において東村山市の強み・弱みを分析し、競争優位性を明確にする必要があります。 また、より遠隔地からの転入者を増やすためには、東村山市の認知度向上や、交通アクセス改善などの対策が必要となる可能性があります。
II.東村山市の認知度と印象 魅力と課題
東村山市の認知経路は、「以前市内または近隣に住んでいた」(44.2%)、「友人・知人を通じて知った」(28.5%)が上位です。「東村山音頭」(66.3%)、「八国山緑地などの自然環境」(30.1%)、「志村けん」(25.3%、その他回答に多く含まれる)が印象として強く残っています。一方で、「東村山という名前だけしか知らなかった」という声も多く、知名度向上と魅力発信が課題です。
1. 東村山市の認知経路 居住経験や口コミの影響
東村山市の認知経路に関する調査では、「以前市内または近隣市などに住んでいた」が44.2%と最も高い割合を占めています。これは、東村山市に既に親しみのある人が、再度転入を検討するケースが多いことを示唆しています。次いで、「友人・知人・親族などを通じて知った」が28.5%、「鉄道や道路で通った」が25.7%、「テレビやラジオで見聞きした」が18.1%と続いており、口コミや日常的な接触を通じて認知されているケースが多いことが分かります。 特に、近隣地域からの転入が多いという点は、東村山市の地理的な利便性や、地域コミュニティの強さを示唆するものであり、今後の広報活動においても重要な要素となるでしょう。 また、友人や知人からの口コミは、非常に信頼性の高い情報源であるため、住民の満足度を高める施策が、新たな転入者の獲得に繋がる可能性があります。 さらに、鉄道や道路を利用した際に東村山市を知ったという回答も一定数あり、可視的な情報発信の重要性が示唆されています。
2. 東村山市の印象 東村山音頭と自然環境が中心
東村山市の認知内容・印象に関する調査では、「東村山音頭」が66.3%と圧倒的に高い割合を占めています。これは、東村山音頭が市の象徴的な存在であり、広く認知されていることを示しています。次いで、「八国山緑地などの自然環境」が30.1%、「うどん、梨、黒焼きそばなどの物産品」が28.9%、「菖蒲まつり」が26.9%と続き、自然環境や地元の特産品、イベントなども一定の認知度があることが分かります。 しかし、最も多く回答に散見された「志村けん」は、著名人の出身地としての認知が強く、街としての具体的なイメージが不足している可能性を示唆しています。 東村山音頭や自然環境といったポジティブな印象と、志村けんといった著名人への依存をバランス良く活用することが、市のイメージ戦略において重要となります。 具体的なイメージの醸成には、地域資源の活用、広報活動の強化、そして、新たな魅力の発掘と発信が不可欠です。
3. 東村山市の認知度向上 課題と対策
調査結果からは、特に20代において「東村山という名前だけしか知らなかった」という回答が29.3%と目立ちます。これは、若い世代への認知度が低いことを示しており、東村山市の魅力を効果的に発信するための新たな戦略が求められます。 具体的には、SNSなど若い世代が利用する媒体を活用した広報活動や、市独自のイベント、魅力的なコンテンツの開発、そして、若者向けの居住支援策などが考えられます。 また、東村山市の認知度向上を図るためには、具体的な施策と、それらによる効果測定が不可欠です。 例えば、広報活動の効果を数値で示すことや、アンケート調査などを活用することで、より効果的な広報戦略を立てることができるでしょう。 さらに、多様な世代に合わせた情報発信を行うことで、東村山市の認知度向上と、魅力的なイメージの定着を図ることが重要です。
III.東村山市居住の満足度 良かった点と悪かった点
転入出時に子どもがいた人を対象とした調査では、「公園・自然環境」、「買い物の利便性」、「子育て環境」などが良かった点として高く評価されています。一方、悪かった点としては「その他」「住宅の都合」「仕事上の都合」などが挙げられています。待機児童問題への懸念も示されており、子育て支援の充実が求められています。
1. 東村山市居住 良かった点
転入出時に子どもがいた世帯を対象とした調査において、悪かった点よりも良かった点の比率が10ポイント以上上回った項目は7つありました。これらは、東村山市の生活環境における大きな強みを示しています。具体的には、「公園・自然環境」、「買い物の利便性」、「自然災害の少なさ」、「子育て環境」、「公共施設(公民館、図書館、スポーツ施設等)」、「最寄駅へのアクセス」、「地域コミュニティ」です。これらの項目は、家族にとって非常に重要な要素であり、東村山市がこれらの点で高い評価を得ていることは、今後の市政運営においても重要な指針となるでしょう。特に、「公園・自然環境」と「子育て環境」の高評価は、子育て世帯にとって魅力的な居住地であることを示しています。これらの満足度の高い要素を維持・向上させるための施策を継続的に実施していく必要があります。また、これらの項目に関する具体的なデータ分析を行うことで、更なる改善点の発見や、新たな施策の検討も可能になります。
2. 東村山市居住 悪かった点
一方、良かった点よりも悪かった点の比率が10ポイント以上上回った項目も存在します。これらの項目は、東村山市の課題を示しており、改善を必要とする点です。具体的には、「その他」、「結婚(事実婚を含む)」、「住宅の都合(住宅の購入・借家の借り換えなど)」、「仕事上の都合(就職・転勤・転職・退職など)」、「生活環境(交通や買い物の利便性、治安など)をよくすること(子育て環境をよくすることを除く)」、「親や子と同居、または近くに住む必要があったこと」です。これらの項目は、個々の事情やライフステージに密着した課題であり、単純な解決策が見つからない場合もあります。しかし、これらの課題を洗い出すことで、具体的な改善策を検討することができます。例えば、「住宅の都合」に関しては、住宅政策の見直し、「仕事上の都合」に関しては、雇用創出の促進などが考えられます。 特に、「その他」の項目については、より詳細な分析が必要であり、市民の声を丁寧に聞き取ることで、具体的な課題を把握し、解決策を探る必要があります。
3. 転入 転出者の満足度比較 異なるニーズ
転入出時に子どもがいた世帯を対象とした、転入者と転出者のポイント差を比較した結果も示されています。転入者にとって重要な項目は「家賃・住宅価格」、「住宅の条件(広さ、日当たり、静かさ)」、「自然災害の少なさ」である一方、転出者にとって重要な項目は「街並みや街の雰囲気」、「都心へのアクセス」、「小中高校などの教育環境」、「治安」でした。この結果から、転入者と転出者では、重視する点が大きく異なることが分かります。転入者は、住居の物理的な条件を重視する傾向があるのに対し、転出者は、生活の質や利便性を重視する傾向があると言えるでしょう。この違いを踏まえることで、より効果的な市政運営を行うことができます。例えば、転入者を増やすためには、住宅政策の充実、そして、自然災害への対策強化が重要となります。一方、転出を抑制するためには、街全体の雰囲気向上、都心へのアクセス改善、教育環境の充実、治安対策の強化などが求められます。
IV.東村山市転入のきっかけ 年代別 地域別 住居形態別
転入のきっかけは年代によって大きく異なります。20代は「仕事上の都合」と「結婚」、50代は「仕事上の都合」、60代は「親と同居」、70代以上は「住宅の都合」と「健康上の理由」がそれぞれ高い割合を占めています。地域別では、久米川町で「子育て環境」、富士見町で「仕事上の都合」が高い傾向が見られました。住居形態別では、持ち家では「住宅の都合」、賃貸住宅では「結婚」や「仕事上の都合」が主な理由となっています。
1. 年代別転入のきっかけ ライフステージの変化が反映
東村山市への転入のきっかけを年代別に分析すると、それぞれの年代で異なる理由が上位を占めていることが分かります。20代では「仕事上の都合(就職・転勤・転職・退職など)」(40.7%)と「結婚(事実婚を含む)」(32.1%)が他の年代に比べて高く、仕事や結婚を機に転入する若年層が多いことがわかります。50代では「仕事上の都合」(43.8%)が最も高く、キャリア上の転機が転入の大きな要因となっている可能性があります。60代では「親や子と同居、または近くに住む必要があったこと」(25.9%)、「生活環境の改善」(22.2%)、「家族の人数の変化」(14.8%)が上位で、家族構成の変化や生活環境の向上が転入理由として重要視されていると考えられます。70代以上では「住宅の都合(住宅の購入・借家の借り換えなど)」(40.0%)と「健康上の理由」(20.0%)が他の年代に比べて高く、高齢者の転入理由には住宅事情や健康面が大きく影響していることが分かります。このように、年代別に転入の動機が大きく異なることから、年代別に特化した施策が必要であることが示唆されます。
2. 地域別転入のきっかけ 地域特性とニーズの多様性
居住町名別に転入のきっかけをみると、町ごとに異なる傾向が見られます。久米川町では「子どもが生まれた、または生まれる予定があったこと」(13.3%)と「子育て環境をよくすること」(10.0%)の割合が高く、子育て世代のニーズが強い地域であることが分かります。富士見町では「仕事上の都合」(50.0%)が圧倒的に多く、仕事が転入の主要な理由となっていると考えられます。美住町では「生活環境の改善」(21.4%)、野口町では「結婚」(38.1%)の割合が高いなど、地域によって転入の動機が異なることが明らかになっています。この結果は、東村山市内においても地域ごとに異なる特性があり、それぞれの地域に合わせた施策が必要であることを示しています。例えば、子育て世帯が多い地域には、保育園の整備や子育て支援サービスの充実、若年層が多い地域には、雇用創出や住宅政策の強化などが考えられます。地域特性を踏まえたきめ細やかな施策によって、より多くの住民を惹きつけ、地域活性化を図ることが可能となるでしょう。
3. 住居形態別転入のきっかけ 住宅事情とライフスタイル
転入後の住居形態別に転入のきっかけを分析すると、持ち家(新築一戸建て、中古マンション)では「住宅の都合(住宅の購入・借家の借り換えなど)」の割合がそれぞれ54.8%、51.9%と非常に高く、住宅事情が転入の大きな要因となっていることがわかります。民営の借家・アパート・マンションでは「結婚(事実婚を含む)」(34.3%)が、UR・公社賃貸住宅や社宅・寮・宿舎では「仕事上の都合」(58.3%、71.4%)がそれぞれ高い割合を占めています。この結果は、住居形態によって転入の動機が大きく異なることを示しており、住宅政策や雇用対策を検討する上で重要な示唆を与えています。持ち家希望者への対応としては、住宅供給の増加や住宅ローンの金利優遇策などが考えられます。一方、賃貸住宅に住む層への対策としては、子育て世帯向けの賃貸住宅の供給拡大や、家賃補助制度の導入などが効果的かもしれません。 このように、住居形態別のニーズを的確に捉え、多様な住宅政策を展開することで、より多くの転入者を呼び込むことができるでしょう。
V.東村山市転出の理由 主要な要因と転出先
転出理由は、20代では「結婚」と「仕事上の都合」、40代では「住宅の都合」、70代以上では「健康上の理由」と「親と同居」が多いです。転出後の居住地域は、東京23区では「結婚」と「仕事上の都合」、多摩地域では「住宅の都合」が主な理由となっています。生活環境の改善を目的とした転出も目立ちます。
1. 年代別転出のきっかけ ライフステージと転出理由
東村山市からの転出理由を年代別に分析すると、20代では「結婚」(43.9%)と「仕事上の都合」(28.8%)が大きく、結婚や就職を機に転出する若年層が多いことがわかります。30代では「結婚」(34.7%)、40代では「住宅の都合」(41.7%)がそれぞれ高い割合を占めており、ライフステージの変化が転出理由に大きく影響していると考えられます。50代と60代では「家族の人数の変化」(それぞれ18.2%、20.0%)が顕著で、家族構成の変化が転出の要因となっている可能性を示唆しています。70代以上では「健康上の理由」(41.9%)と「親や子と同居、または近くに住む必要があったこと」(41.9%)が最も多く、高齢者の転出理由には健康面や家族との同居が大きく関わっていることがわかります。このように、年代別に転出理由が異なるため、年代別に合わせた対策が必要となります。例えば、若年層には雇用機会の創出や子育て支援策、高齢者には健康増進策や高齢者向け住宅の整備などが考えられます。
2. 転出後の居住地域別 東京23区と多摩地域への移動
転出後の居住地域別に見ると、東京23区への転出者では「結婚」(35.4%)、「仕事上の都合」(29.3%)、「生活環境の改善」(26.8%)が主な理由となっており、仕事や生活環境の向上を求めて23区へ転出する人が多いことが分かります。一方、東村山市以外の多摩地域への転出者では「住宅の都合」(35.5%)が最も多く、より広い住宅を求めて多摩地域へ移住する傾向があることがわかります。この結果は、東京23区と多摩地域では転出の動機が異なることを示しています。東京23区への転出を防ぐためには、雇用機会の創出や生活環境の整備、そして、子育て支援策の充実が重要となります。多摩地域への転出については、住宅政策の見直しや、より魅力的な住宅環境の整備が必要となるでしょう。 転出理由を詳細に分析することで、東村山市に残留してもらうための具体的な対策を検討することが可能になります。
3. その他の転出理由 住宅事情とライフスタイルの変化
その他の転出理由としては、「住宅の都合」と「子どもが生まれた、または生まれる予定があったこと」が挙げられています。特に、「住宅の都合」は、転出の大きな要因となっており、より広い住宅や住環境を求めて転出する人が多いと考えられます。「子どもが生まれた、または生まれる予定があったこと」も転出理由として挙げられており、より充実した子育て環境を求めて転出する人がいることが示唆されています。さらに、二世代世帯から単身世帯になった層では、「仕事上の都合」、「生活環境の改善」、「親からの独立」が主な理由となっており、ライフスタイルの変化が転出理由に繋がっている可能性があります。これらの理由を分析することで、東村山市の課題が見えてきます。例えば、住宅政策の改善、子育て環境の充実、そして、単身者向けの住居や生活サービスの提供などが考えられます。 これらの転出理由への対策を効果的に講じることで、人口減少に歯止めをかけることが期待されます。
VI.市民からの提案 意見 要望 改善点と魅力向上策
市民からは、子育て支援の充実(保育園の待機児童問題解消、保育料の軽減など)、交通アクセスの改善(道路整備、バス路線の拡充など)、商業施設の充実、駅前環境の改善、治安の向上など、多岐にわたる意見・要望が寄せられました。自然環境の保全と活用、東村山の魅力を効果的に発信する方策も求められています。特に子育て世代からの要望が多く、東村山を魅力的な子育てしやすい街にするための施策が重要となります。
1. 子育て環境の充実 待機児童問題への対応と保育サービスの向上
市民からの提案・意見・要望の中で、最も多く寄せられたのは子育て環境の充実に関するものでした。特に、保育園の待機児童問題の解消や、保育サービスの向上を求める声が多数ありました。待機児童問題については、東京都内でも深刻な課題となっており、東村山市においても例外ではありません。働く女性の増加に伴い、保育所の需要はますます高まっており、その需要に応えるための抜本的な対策が求められています。具体的には、保育園の増設、保育士の確保、保育料の軽減などが挙げられます。また、子育て支援サービスの充実も重要な課題であり、子育て支援センターの機能強化、子育てに関する相談窓口の拡充、そして、子育て世帯向けの各種補助金制度の拡充などが検討されています。これらの課題への対応は、東村山市の魅力を高め、子育て世帯の定着率を向上させる上で不可欠です。
2. 交通 生活環境の整備 道路 公共交通機関 商業施設の充実
交通環境や生活環境の改善に関する要望も数多く寄せられました。具体的には、道路の整備(歩道拡幅、道路補修など)、公共交通機関の充実(バス路線の拡充、駅周辺の利便性向上など)、そして、商業施設の充実(大型スーパーマーケットの誘致、商店街の活性化など)に関する意見が多く見られました。道路の狭さや交通渋滞は、特に子育て世帯にとって大きな負担となっており、安全で快適な歩行者空間の確保が求められています。公共交通機関の充実も重要な課題であり、利便性の向上は、市民生活の質を高める上で不可欠です。また、商業施設の充実も、生活利便性の向上に繋がる重要な要素です。駅前環境の改善や、地域住民の交流促進のためのイベント開催なども、生活環境の向上に貢献する可能性があります。これらの施策を総合的に推進することで、より住みやすい街づくりを進めることが可能となります。
3. その他の要望 魅力発信 情報提供 地域資源の活用
その他、東村山市の魅力を発信するための施策、市民への情報提供の改善、そして、地域資源の活用に関する意見なども寄せられました。東村山市の魅力を効果的に発信するためには、広報誌やウェブサイトの活用、SNSなどの新たなメディアの活用、そして、地域イベントの開催などが考えられます。また、市民への情報提供の改善としては、行政手続きの簡素化、そして、必要な情報を分かりやすく提供するための体制整備などが挙げられます。さらに、八国山緑地などの自然環境や、地元の特産品などを活用した観光客誘致策も検討されています。これらの施策によって、東村山市の魅力を内外に効果的に発信し、多くの住民を惹きつけることが期待されます。市民の意見を反映した、魅力的な街づくりを進めることが重要です。
