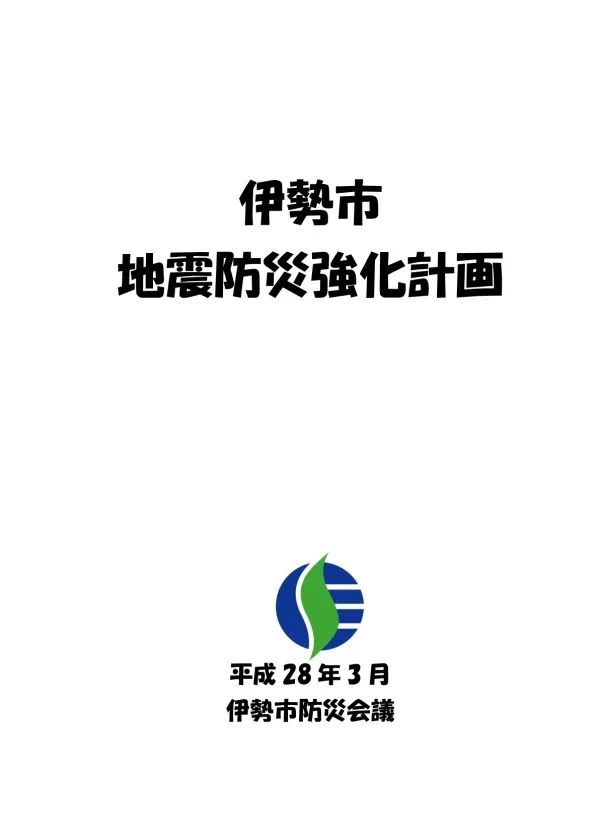
東海地震防災強化計画
文書情報
| 著者 | 伊勢市防災対策本部 |
| 専攻 | 防災計画 |
| 場所 | 伊勢市 |
| 文書タイプ | 防災計画 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.37 MB |
概要
I.東海地震警戒宣言発令時の地震防災応急対策
本計画は、大震法に基づき、東海地震を想定した地震防災対策強化地域(三重県では10市町)における警戒宣言発令時の応急対策を定めています。警戒宣言発令前に政府が準備行動を行う意思決定をした場合、必要な準備行動を実施します。計画では、被害軽減のための事前措置、情報伝達、避難誘導、緊急輸送、医療救護、公共施設対策、生活必需品確保、広域的な応援・受援体制の整備など、多岐にわたる対策が盛り込まれています。特に、津波や土砂災害の危険性の高い地域住民への迅速な避難勧告と誘導が重要視されています。伊勢市を含む関係市町村、中部地方整備局三重河川国道事務所、日本郵便株式会社など、多くの機関が連携して対策を実施します。
1. 計画の目的と概要
この計画は、大震法に基づき、東海地震の地震防災対策強化地域において、警戒宣言発令時に実施すべき地震防災応急対策を定めることを目的としています。三重県では伊勢市(旧伊勢市、旧二見町、旧御薗村を含む)など10市町が強化地域に指定され、津波被害などが懸念されています。警戒宣言発令時には社会的混乱も予想されるため、迅速かつ的確な対策が求められます。計画では、警戒宣言発令時における応急対策、大規模地震に備えた施設整備、被害軽減のための事前措置などが規定されています。東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う旨の意思決定が行われた場合、必要な準備行動も実施されます。労働災害防止や緊急避難の徹底も強く求められています。
2. 事前措置と準備行動
東海地震の被害を防止・軽減するため、市と防災関係機関は、事前に必要な措置を講じます。具体的な内容は計画に明記されます。警戒宣言発令前に、東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う意思決定をした場合は、計画に基づいた準備行動が実施されます。これは、地震発生への備えを強化し、被害を最小限に抑えるための重要なステップです。この準備行動には、情報伝達体制の確認、避難経路の確保、緊急物資の点検、関係機関との連携強化などが含まれる可能性があります。関係機関としては、中部地方整備局三重河川国道事務所や日本郵便株式会社などが挙げられ、情報伝達、警戒体制整備、人員・資機材の配備、利用者への警戒宣言伝達、安全確保などが具体的な対応として期待されます。
3. 市警戒本部の活動体制と情報伝達
警戒宣言発令時には、大震法に基づき市警戒本部を設置し、地震防災応急対策活動を行います。本部の組織・運営は関連法規に基づき行われ、本部員への連絡は勤務時間中は庁内放送、時間外は連絡網で行われます。地震防災応急対策の迅速かつ円滑な実施のため、情報収集・伝達体制の構築が重要です。消防団員や自主防災組織の隊員から地域の情報収集責任者をあらかじめ指定し、同報系防災行政無線、ケーブルテレビ、ホームページ、広報車、有線放送、地震防災信号など多様な手段を用いて住民・観光客への広報を行います。政府が準備行動を行う意思決定をした場合は、関連情報への問い合わせに対応する窓口も設置されます。地震防災応急計画を作成すべき事業所への計画実施の呼びかけ、計画を作成しない事業所や住民への措置、金融機関の対応情報なども重要な情報となります。
4. 広報計画と自主防災活動
東海地震予知情報等の周知徹底と、突然の発表による混乱防止のため、市と防災関係機関は効果的な広報活動を実施します。警戒宣言発令から地震発生または警戒解除までの間、市警戒本部と自主防災組織は連携して地震防災応急対策を実施します。自主防災組織は、避難誘導、避難地での生活支援、災害時要配慮者への支援、帰宅困難者への対応など、多様な役割を担います。避難地での生活では、役割分担、資機材の準備、生活必需品の確保、災害時要配慮者への配慮、関係事業者との協力などが重要になります。縁故避難についても、自主防災組織は避難者の情報把握、安全確認、活動への支障がない体制づくりに努めます。
5. 警戒区域の設定と避難に関する周知事項
警戒宣言発令時には、市長は速やかに警戒区域を設定し、退去または立入禁止措置をとります。警察官、海上保安官の協力を得て、住民の退去確認やパトロールを行います。避難対象地区はあらかじめ選定され、周知徹底されます。避難に関する事項(避難すべき地区、避難時期等)は、市、消防本部、消防団、警察が自主防災組織や住民に常日頃から周知します。避難地は原則として公園や学校のグラウンド等の屋外に設置しますが、災害時要配慮者への配慮がなされた建物内も可能です。避難地の運営にあたっては、災害時要配慮者への配慮、自主防災組織と市の連携、関係事業者との協力などが重要となります。避難行動における携帯品、服装等の注意事項も周知されます。
II.避難対策
警戒宣言発令時には、津波浸水や土砂災害危険地域住民は速やかに指定避難所へ避難します。それ以外の住民は耐震性の高い自宅待機を基本とします。避難対象地区住民への避難勧告は、防災行政無線、広報車等で行います。避難所運営は自主防災組織が中心となり、災害時要配慮者への配慮も重要です。公園や学校グラウンド等に避難所を設置します。避難誘導にあたっては、警察、消防、海上保安庁と連携します。
1. 避難対象地域と避難勧告 指示
津波浸水や山崩れの危険性が高い沿岸部、土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域とその周辺地域住民は、警戒宣言発令と同時にあらかじめ指定された避難場所へ迅速に避難します。それ以外の地域住民は、耐震性の確保された自宅待機または安全な場所での行動を基本とします。市長は警戒宣言発令後、避難対象地区の住民に対し、同報系防災行政無線や広報車などを用いて速やかに避難勧告および指示を行います。警察官や海上保安官にも避難勧告の伝達、避難誘導、避難路の交通規制への協力を要請します。必要に応じて、市は避難勧告や指示に関する広報を県に依頼します。この迅速かつ的確な情報伝達と避難誘導が、被害軽減に大きく貢献します。避難対象地域の詳細な範囲や避難場所の指定は、事前に周知徹底される必要があります。
2. 避難場所と運営
避難場所は原則として公園や学校のグラウンドなどの屋外に設置しますが、災害時要配慮者への配慮がなされた建物内も利用可能です。避難地の設置期間は、警戒宣言発令から警戒宣言解除まで、または地震発生し避難生活施設が設置されるまでとなります。避難地での生活においては、自主防災組織が中心となり、役割分担、必要な資機材の準備、秩序ある避難生活施設の運営に努めます。生活必需品が不足した場合には、市警戒本部等と連絡を取り、確保に努めます。高齢者、子ども、障害者、外国人など災害時要配慮者への配慮は特に重要視され、自主防災組織を中心とした地域一体となった協力・支援体制の構築が求められます。また、多数の観光客の収容が見込まれる避難地については、関連事業者と協力して運営します。
3. 避難誘導と帰宅困難者への対応
避難誘導にあたっては、災害時要配慮者への配慮が不可欠です。交通規制により発生する帰宅困難者や滞留旅客に対しても、交通事業者と連携し、避難誘導や保護活動を行います。耐震性の低い建物に住む住民は、建物の状況に応じて付近の安全な空地などに避難します。自宅の耐震点検を事前に実施することも推奨されます。避難に関する事項については、市(消防本部、消防団を含む)と警察が自主防災組織や避難対象地区住民に常日頃から周知を図り、警戒宣言発令時には、警戒宣言の発令、避難すべき地区名、避難する時期などを明確に伝達する必要があります。避難行動における携帯品や服装などの注意事項も事前に周知することで、円滑な避難行動を促します。
4. 警戒区域の設定とその他
市長は警戒宣言発令時に速やかに警戒区域を設定し、退去または立入禁止措置を取ります。警察官、海上保安官の協力を得て住民の退去確認を行い、防犯・防火のためのパトロールを実施します。警戒区域設定対象地域は、大震法と災害対策基本法に基づきあらかじめ選定され、周知されます。避難対象地区のうち、災害対策基本法第63条に基づく警戒区域として設定すべき地域が事前に選定され、周知が図られます。警戒区域の設定と避難誘導に関する具体的な内容、実施方法、注意事項などは、関係機関との綿密な連携の下で決定・実行されます。海上における避難対策は第四管区海上保安部が担当し、津波による危険が予想される港や沿岸付近の船舶への対応を行います。
III.交通対策
警戒宣言発令時には交通混雑が予想されるため、緊急物資輸送や救助活動の円滑化のため、交通規制や公共交通機関の運行確保が重要です。三重交通株式会社伊勢営業所、三交伊勢志摩交通株式会社伊勢営業所等のバス会社は、危険箇所や避難場所の情報を従業員に周知し、運行中止等の対応を取ります。列車運行についても、情報伝達、避難誘導、帰宅支援などの対策が実施されます。
1. 警戒宣言発令時の交通対策の基本方針
警戒宣言発令時には、車両滞留による一般道路の交通渋滞が予想されるため、交通混乱の防止、緊急物資の輸送、警察・消防活動の円滑な実施を確保するための交通・公共輸送の運行確保が最重要課題となります。この計画では、警戒宣言発令時に発生する可能性のある交通渋滞を未然に防ぎ、緊急車両の通行を確保し、住民の避難を円滑に進めるための対策が盛り込まれています。具体的には、道路交通の規制、公共交通機関の運行調整、緊急車両の優先通行措置などが含まれるでしょう。また、この計画は、関係機関との連携を密にすることで、迅速かつ効果的な交通対策の実施を目指しています。
2. 情報収集 伝達と運行中止手順
東海地震注意情報や警戒宣言発令時の情報収集・伝達経路はあらかじめ定められています。特に、運行車両の乗務員はラジオ、サイレン、標識などを用いて情報を収集し、警戒宣言発令の情報を入手した場合は、速やかに車両の運行を中止します。運行中止にあたっては、車両の安全確保を最優先し、安全な場所に停車させ、旅客に対して避難場所を指示します。避難地での帰宅支援が行われている場合は、その旨も旅客に伝えなければなりません。運行中止後も、旅客の避難状況を営業所などに報告する必要があります。滞留旅客に対しては、警戒宣言の内容、最寄りの避難地、運行中止の措置などを掲示物や放送などで広報します。これらの手順を事前に周知徹底することで、混乱を最小限に抑えることができます。
3. バス事業者への対策要請
バス事業者(三重交通株式会社伊勢営業所、三交伊勢志摩交通株式会社伊勢営業所など)に対しては、運行路線における津波被害、山崩れ、崖崩れなどの危険箇所と避難場所を事前に調査し、従業員への周知徹底が求められます。これは、地震発生時に迅速かつ的確な対応を可能にするために不可欠です。従業員は、危険箇所や避難場所に関する知識を習得し、警戒宣言発令時には、安全確保を最優先し、旅客の避難誘導や安全確保に努めなければなりません。また、運行計画の変更や、バスの安全な停車場所の確保なども重要な課題となります。バス事業者には、事前にこれらの対策を十分に準備し、従業員への教育・訓練を行うことが求められます。
4. その他の交通機関への対応
鉄道などその他の交通機関に対しても、警戒宣言発令時の情報伝達、列車運行状況の案内、旅客の待機・救護、帰宅支援などの対策が計画に盛り込まれていると考えられます。具体的には、運行車両の乗務員はラジオやサイレンなどを用いて情報収集に努め、警戒宣言発令時には運行を中止し、安全な場所に停車、旅客への避難誘導、帰宅支援の案内などを行います。また、強化地域外においては、折り返し設備などを勘案し、区間を定め、必要に応じて速度制限を行いながら運行を継続するなどの対策も検討されるでしょう。これらの対策は、緊急物資の輸送や被災者の避難を円滑に進めるために重要であり、関係機関との連携が不可欠です。
IV.生活必需品確保対策
政府が準備行動を行う旨の意思決定を行った場合または警戒宣言発令時には、食料、飲料水、日用品等の生活必需品の確保が重要です。住民の自助努力を基本としつつ、市による供給で補完します。緊急物資の備蓄と、小売・卸売業者からの調達も検討されます。飲料水確保のため、貯水励行の呼びかけや応急給水計画の策定も行います。
1. 生活必需品の確保に関する基本方針
東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う旨の意思決定を行った場合、または警戒宣言が発令された場合、食料、飲料水、日用品などの生活必需品の確保が喫緊の課題となります。この計画では、住民の自助努力による確保を基本としつつ、市による供給体制を整備することで、民生の安定を図ることを目指しています。警戒宣言発令時に必要な生活必需品は、できる限り住民自身で確保することを基本とし、市からの供給はそれを補完する役割を担います。そのため、平時からの備蓄の推奨や、情報提供による適切な行動喚起などが重要となります。また、不足が生じた場合の迅速な対応策として、市は緊急物資の備蓄、生活必需品を取り扱う小売・卸売業者等からの調達・配分なども検討します。
2. 食料の確保と緊急物資の配分
警戒宣言発令時には、食料、飲料水、日用品などの生活必需品の確保が不可欠です。計画では、住民の自助努力による確保を基本としつつ、市による供給体制でそれを補完する方針を示しています。政府が準備行動を行う旨の意思決定を行った場合は、食料や生活必需品の調達可能数量の点検を行います。津波や土砂災害の危険が予想される地域で、非常時持ち出しが困難だった住民や旅行者などに対しては、備蓄した緊急物資の配分、または生活必需品を取り扱う業者からの調達・配分を実施します。この緊急物資の配分体制は、迅速かつ効率的な支援を可能にするため、事前に計画・準備しておくことが重要です。 具体的な供給ルートや、配分方法、対象者の選定基準などは、事前に明確にしておく必要があります。
3. 飲料水の確保と給水計画
飲料水の確保は、地震発生後の生存に不可欠な要素です。この計画では、住民への貯水励行の呼びかけを最重要事項としています。さらに、東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う旨の意思決定を行った場合、または警戒宣言が発令された場合には、給水計画に基づき、他の地方公共団体からの応援給水を含む応急給水活動の準備を行います。この計画は、平時からの備蓄や、非常時の給水ルートの確保、関係機関との連携などを含む包括的な対策を必要とします。住民への啓発活動を通じて、平時からの備蓄の重要性を周知徹底し、非常時の対応についても明確な手順を確立する必要があります。また、給水計画には、給水場所、給水量、給水方法、担当者などを明確に示す必要があります。
V.医療対策
警戒宣言発令時には、医療機関は医療救護活動の準備を行い、救護所や仮設救護病院の設置を検討します。緊急を要する患者への診察体制を維持します。要救護者の搬送準備も重要な対策です。
1. 医療機関の事前準備と医療救護活動
東海地震注意情報発表時または警戒宣言発令時には、医療機関は関係機関に医療救護活動の準備を要請します。これは、地震発生による負傷者への迅速な対応を確保するためです。医療救護施設の設備・資機材の配置や点検を行い、必要に応じて救護所や仮設救護病院などの設置も検討します。医療機関は、平時から災害時の医療体制について計画を立て、必要な物資や人員を確保しておく必要があります。また、地震発生前に、医療機関の職員は、災害時における役割分担や連絡体制を明確にしておく必要があります。さらに、近隣の医療機関との連携を強化し、情報共有や相互支援体制を構築することで、より効率的な医療提供が可能になります。市長が事前に協議して定めた医療機関は、警戒宣言時においても緊急を要する患者への診察を継続することを住民に周知します。
2. 要救護者搬送と救護所の周知
東海地震注意情報発表時または警戒宣言発令時には、要救護者の搬送準備を行います。これは、負傷者や高齢者など、自力での避難が困難な人々を安全な場所に避難させるための重要な措置です。搬送手段の確保、搬送ルートの確保、搬送人員の確保など、様々な準備が必要です。計画では、搬送手段として、救急車、消防車、その他車両などを活用することを検討するでしょう。また、搬送ルートの確保には、道路状況の把握、交通規制への対応などが含まれます。搬送人員の確保には、ボランティアの募集なども考えられます。さらに、住民に対して、救護所や仮設救護病院などの場所を事前に周知しておくことで、混乱を最小限に抑え、迅速な対応を可能にします。これらの準備は、地震発生前に綿密に行う必要があります。
VI.公共施設等対策
警戒宣言発令時には、公共施設の点検整備を行い、地震防災応急対策の円滑な実施を確保します。学校、社会教育施設、社会福祉施設等の安全確保、避難誘導対策が重要です。工事中の公共施設については、工事を中断し、安全確保のための措置をとります。東海地震注意情報や警戒宣言の発令情報は来訪者にも伝達します。
1. 東海地震注意情報 警戒宣言発令時の対応
東海地震注意情報または警戒宣言が発令された場合、市が管理または運営する公共施設および不特定多数の人が利用する施設において、地震発生に備えた点検整備が実施されます。これは、地震防災応急対策の円滑な実施を確保するためです。具体的な対応としては、施設の緊急点検、設備の安全確認、必要に応じた補強などが挙げられます。特に、充電式携帯無線機については完全充電を行うことが指示されています。道路などの公共インフラについても緊急点検と巡視を行い、状況把握の上、工事中断や震災対策といった適切な措置が講じられます。これらの対策は、地震発生前に実施されることで、地震発生時の被害を最小限に抑えることにつながります。また、不特定多数の人が利用する施設では、来訪者への警戒宣言等の情報伝達と安全確保のための避難誘導などの措置が講じられます。
2. 工事中の公共施設 建築物への対応
東海地震注意情報または警戒宣言が発令された場合、工事中の公共施設や建築物については、工事を中断し、必要な安全対策が講じられます。これは、地震による倒壊や落下事故を防ぐためです。具体的な措置としては、立入禁止措置、落下物防止対策、構造物の補強などが含まれます。工事現場の状況に応じて適切な対策を選択し、作業員の安全確保を最優先事項として対応することが重要です。工事中断による遅延などを考慮し、工事の進捗状況や安全対策の状況について、関係各所への報告を徹底する必要があります。地震発生時の被害拡大防止に資するよう、事前に工事現場の防災計画を策定し、訓練を行うことが重要です。
3. 砂防 地すべり 急傾斜地等の対策
東海地震注意情報または警戒宣言が発令された場合、砂防、地すべり、急傾斜地などの指定地で危険の恐れがある地域に対して、あらかじめ定められた情報連絡を行い、必要に応じて警戒体制を整えます。これは、地震による土砂災害の発生リスクを軽減するためです。危険箇所の特定、住民への避難勧告、関係機関への通報などが迅速に行われるよう、事前に連絡体制を整備しておくことが重要となります。具体的な情報連絡手段や、警戒体制の構築手順などは、事前に関係機関と協議し、決定しておく必要があります。また、危険箇所周辺の住民に対して、避難場所や避難経路を明確に周知しておくことで、地震発生時の迅速な避難を促すことができます。
VII.民間施設対策
市は、消防計画作成義務のある施設・事業所に対し、警戒宣言発令時における対策を指導・要請します。不特定多数の人の出入りする施設は営業自粛を要請し、生活必需品等を取り扱う事業所は安全確保を図りつつ営業継続を要請します。家庭では、正確な情報収集、非常持出品の準備、安全な服装への着替えなどが推奨されます。
1. 警戒宣言発令時における事業所の対応
警戒宣言発令時における事業所の営業継続または自粛に関する事項が規定されています。具体的には、地震発生時にパニック発生の恐れがある映画館やイベントホールなどは営業自粛を、生活必需品を取り扱う事業所は安全確保を図りつつ営業継続に努めることが求められています。これは、地震発生時の混乱を防止し、住民生活への影響を最小限に抑えるための重要な対策です。市は、消防法等により消防計画作成義務のある施設・事業所に対し、警戒宣言発令時における安全確保、混乱防止のための措置を盛り込んだ計画の作成を指導・要請します。事業者自身による防災計画の策定と、その計画に基づいた訓練の実施が、適切な対応に繋がります。事業継続計画(BCP)の策定と、その訓練が重要になります。
2. 市による指導 要請事項
市は、消防法等により消防計画作成義務のある施設・事業所に対し、警戒宣言発令時にとるべき措置について指導・要請します。具体的には、安全確保、混乱防止のための措置、危険物の安全措置、消火用具の準備確認、安全な服装への着替え、非常持出品の用意確認などが含まれます。これは、地震発生時の被害を最小限に抑え、迅速な復旧活動に繋げるためです。市は、事業者に対して、地震発生時の具体的な行動手順を事前に周知徹底し、訓練を行うよう指導します。また、地震発生時の連絡体制の整備、従業員の安全確保、従業員の早期帰宅なども指導事項に含まれます。これにより、民間施設における地震への備えが強化され、災害時の混乱防止に役立ちます。
3. 家庭における地震対策
家庭における地震対策として、東海地震関連情報の入手、市や消防署、警察署からの情報への注意が促されています。これは、正確な情報に基づいた適切な行動をとるために重要です。また、外出中の従業員との連絡体制を確保し、安全確保を指示することが求められています。これは、従業員の安全を確保し、事業所の被害を最小限に抑えるための重要な対策です。さらに、家庭内では、灯油などの危険物の安全措置、消火器などの消火用具の準備確認、身軽で安全な服装への着替え、生活用水、食料、携帯ラジオ、懐中電灯、医薬品などの非常持出品および救助用具の準備確認などが推奨されています。これらの準備は、地震発生前に済ませておくことで、地震発生時の対応を円滑に進めることができます。
4. 運転者への注意喚起
警戒宣言発令中に車を運転している場合、地震発生に備え、慌てずに低速で走行し、カーラジオなどで地震情報や交通情報を継続して聞くことが推奨されています。これは、安全な場所への避難や、交通規制への対応を迅速に行うために重要です。車を置いて避難する際は、道路外に移動することが推奨され、やむを得ず道路上に駐車する場合は、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーをつけたまま、窓を閉め、ドアをロックしないように指示されています。これは、緊急車両の通行や避難者の通行の妨げにならないよう配慮するためです。運転者は、常に周囲の状況に注意し、安全な行動をとるように心がける必要があります。
VIII.広域的な応援 受援体制
警戒宣言発令時には、必要に応じて県に対し自衛隊の派遣要請を行います。自衛隊、海上保安庁、警察、消防機関との連携、広域応援部隊や救援物資の受入れ体制の整備が重要です。消防機関の調整は三重県消防応援活動調整本部が行います。
1. 自衛隊派遣要請と広域応援体制
警戒宣言発令時、市は地震防災応急対策を迅速かつ的確に実施するために必要と判断した場合、県に対して自衛隊の地震防災派遣を要請します。これは、市単独では対応困難な大規模災害への備えとして重要です。 派遣要請にあたっては、被害状況の的確な把握と、必要な人員・資機材の規模を県に正確に伝える必要があります。 また、広域応援部隊、救援物資、DMAT、ボランティア等の受入れを迅速に行うための体制も整備します。これは、他地域からの支援を円滑に受け入れるための準備であり、効率的な災害対応に不可欠です。受入れ体制には、受け入れ場所の確保、人員の配置、情報伝達システムの確立などが含まれます。消防機関の具体的な調整は三重県消防応援活動調整本部が行います。
2. 関係機関との連携と資源の有効活用
市は、県、自衛隊、海上保安庁、警察、消防機関など関係機関との連携を強化し、災害対応にあたります。 これは、人的資源、物的資源を効率的に活用し、災害対応能力を高めるためです。特に、自衛隊、海上保安庁、警察、消防機関が保有するヘリコプターや船舶などの有効活用を図るための調整を行います。これは、広範囲にわたる捜索救助活動や物資輸送を円滑に進めるために必要です。また、警戒宣言発令時には、火災の発生防止と初期消火について、報道機関の協力を得て広報活動を行います。これは、住民への迅速な情報伝達と、火災発生時の初期対応の迅速化に貢献します。緊急消防援助隊や県内消防相互応援隊の応受援体制の整備も重要です。
3. 県による支援と連携
県は、市の消防活動が迅速かつ円滑に行われるよう支援します。警戒宣言発令時には、自衛隊、海上保安庁、警察、消防機関など救助機関との事前活動調整を行います。これは、各機関の役割分担を明確にし、連携を強化することで、災害対応の効率性を高めるためです。さらに、地域復旧体制への協力、情報収集、緊急車両の通行確保、船舶・ヘリコプターなどの運用のため、地方自治体、県警察、公共機関などとの連携を保ちます。これは、災害後の復旧・復興活動を円滑に進めるために不可欠です。必要に応じて、県警戒本部に連絡要員を派遣します。これは、市と県との間の情報伝達を迅速かつ確実に確保するための措置です。
