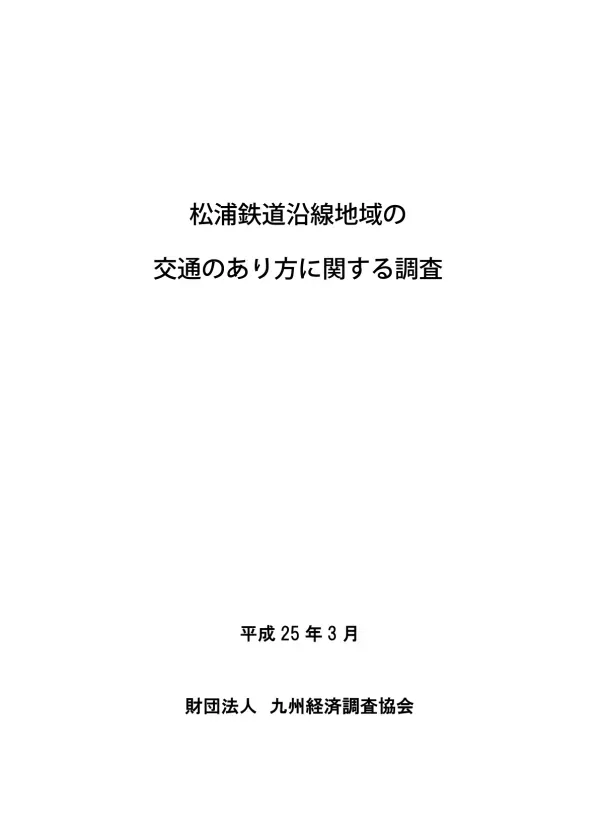
松浦鉄道沿線交通実態調査:利用実態と課題
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 7.51 MB |
| 文書タイプ | 調査報告書 |
概要
I.住民アンケート結果概要 松浦鉄道と路線バスの現状と課題
このアンケートは、長崎県北部の松浦鉄道と路線バスの利用実態、特に高齢化と人口減少が進む地域における公共交通の課題を明らかにすることを目的として実施されました。主な内容は、利用頻度、利用目的、満足度、利用しない理由、そして仮定シナリオ(災害時など)における利用意向の把握です。運賃水準や運行頻度に関するニーズ、自治体の公共交通維持への税金投入に対する評価なども調査項目に含まれています。特に、高齢者の無料バス利用の是非や、学生向けの割引制度の導入についても多くの意見が寄せられました。
1. アンケート調査の目的と内容
この住民アンケートは、長崎県北部の松浦鉄道と路線バスの利用実態を多角的に把握することを目的としています。具体的には、利用頻度、利用目的・理由、サービスに対する満足度などを調査し、公共交通サービスの現状を詳細に分析することを目指しています。 利用しない人の理由についても深く掘り下げ、仮定の状況(例えば、災害による松浦鉄道の運行停止)下での利用意向も調査項目に含めています。 運賃水準や運行頻度に対するニーズ、さらには自治体の公共交通維持への税金投入に対する住民の評価も重要な調査内容となっています。これらの情報を総合的に分析することで、地域の実情に即した公共交通政策の策定に資するデータを得ることが期待されています。アンケートは、利用実態の把握にとどまらず、将来的な人口減少や高齢化といった社会情勢の変化を踏まえた上で、持続可能な公共交通システムの在り方を模索するための重要な基礎データとなることを目的としています。特に、高齢者の無料バス利用の是非や、学生に対する割引制度の導入といった具体的な政策についても、住民からの意見を収集することで、より現実的な解決策の検討に繋げようとしています。
2. 人口減少と高齢化が進む地域における公共交通の課題
アンケートでは、人口減少と高齢化が進む地方部における公共交通の維持運営の困難さが繰り返し指摘されています。回答者からは、高齢者の多い地域では無料バスの必要性について議論が交わされています。無料バスは高齢者にとって大きな助けとなる一方、他の地域では低料金制度を採用している例もあり、財政面や公平性の観点から、無料化の是非が問われています。100円程度の利用料を設定することで、運営に充当できる収入が増加する可能性が示唆されています。また、高齢者だけでなく、学生(特に高校生)への割引制度導入についても、多くの支持が得られています。さらに、乗降時のステップの高さが高齢者や車椅子利用者にとって大きな障壁となっていること、改善の必要性が指摘されています。これらの課題は、単に交通手段の確保というだけでなく、地域住民の生活の質、そして地域全体の活性化という視点からも捉える必要があることを示しています。人口減少が進む中で、公共交通の維持は容易ではありませんが、高齢者や学生、そして地域社会全体にとって必要不可欠な存在であることが、多くの回答から読み取れます。
3. 松浦鉄道と路線バスの現状と利用者ニーズ
松浦鉄道と路線バスの利用状況は、回答者によって様々な意見が示されています。長年利用してきた回答者からは、松浦鉄道への深い思い入れが語られています。また、これらの交通手段は地域活性化や観光客誘致に不可欠であり、県北地域のみならず、長崎全体の活性化に貢献すると考えられています。一方、利用頻度が低い回答者からは、不便さや利便性の低さが指摘されています。具体的には、運行本数の少なさ、時間帯の制限、接続の悪さなどが挙げられており、特に高齢者や運転免許を持たない人にとって、公共交通機関の不足は深刻な問題となっています。 また、自家用車の普及により、公共交通機関の利用者が減少している現状が浮き彫りになっています。利用者の減少は、さらなる運行本数の削減や、ひいては事業者撤退につながる可能性も示唆されています。このため、現状維持、ひいてはサービス向上のためには、利用者のニーズを的確に捉え、運行計画や料金体系の見直しなど、抜本的な改善策の検討が必要であることが示されています。特に、高齢者や学生など、特定の層への配慮が求められていることが分かります。
4. 自治体への期待と具体的な改善提案
アンケート回答からは、自治体に対して、現状の課題を住民に周知徹底するための広報活動の強化や、より明確な公共交通政策を示すことが強く求められています。 具体的な改善策としては、コミュニティバスの積極的な活用、時刻表の各戸配布、広告収入の確保、大学との連携による活性化プロジェクト、バリアフリー化の推進などが提案されています。 また、高齢者や障害者への配慮として、タクシー利用補助制度の導入、車椅子対応バスの導入、駅やバス停からのアクセス向上なども求められています。 更に、運賃体系の見直し、特に現在の料金設定が高すぎるという意見が多く、長崎市の路面電車の料金体系を参考に、利用しやすい料金設定にするべきだという意見も目立ちます。 これらの提案は、単なる公共交通機関の維持にとどまらず、高齢者の移動支援、学生の通学支援、そして地域全体の活性化を図るための総合的な対策が必要であることを示唆しています。 自治体には、住民の意見を真摯に受け止め、地域の実情に合った持続可能な公共交通システムの構築に向けて、積極的な取り組みが期待されています。
II.利用者の声 不便さ 必要性 そして改善策
アンケート回答からは、公共交通機関の不便さに関する多くの声が上がっています。特に、運行本数の少なさ、時間帯の制限、アクセス性の悪さ(駅やバス停からの距離、バリアフリーの不足など)が課題として挙げられています。一方、高齢者や運転できない人にとって、松浦鉄道と路線バスは生活の必需品であるという意見も多く、その存続を強く望む声が多数を占めています。改善策としては、運行頻度の向上、時刻表の分かりやすい配布、運賃の値下げ、小型バスの導入、駅周辺の整備などが提案されています。また、地域活性化を目的としたイベント開催や、企業との連携による広告収入の確保なども提言されています。
1. 公共交通機関の不便さに関する意見
多くの回答者から、松浦鉄道と路線バスの利用における不便さが指摘されています。具体的な問題点としては、運行本数の少なさ、特に時間帯によっては利用できないほどの本数の少なさが挙げられています。 また、運行時間帯の制限も大きな課題となっており、特に学生の帰宅時間帯や高齢者の通院時間帯など、ニーズの高い時間帯において運行が不足しているという意見が目立ちます。さらに、駅やバス停までのアクセス、特に高齢者や車椅子利用者にとっての物理的なバリアー(高いステップなど)が不便さを助長しているという指摘も多く見られます。 不便なアクセス環境は、公共交通機関の利用を阻害し、結果的に利用者数の減少に繋がっているという指摘もあります。 これらの不便さは、高齢者や車椅子利用者、そして通学・通院を必要とする人々にとって、生活の質を大きく左右する深刻な問題となっています。改善に向けた具体的な方策が求められています。
2. 公共交通機関の必要性と存続への要望
一方で、公共交通機関の必要性を訴える声も多数寄せられています。特に、高齢者や運転免許を持たない人々にとっては、松浦鉄道と路線バスは生活の必需品であり、その存続を強く望む声が多数を占めています。 高齢者は買い物や通院、病院への送迎に公共交通機関を必要としており、若者が送迎できない現状を鑑みると、公共交通の維持は不可欠です。 また、自家用車を持たない人、あるいは家族と共用しているため自由に利用できない人にとっても、公共交通機関は重要な移動手段となっています。 さらに、災害時における交通手段の確保という観点からも、公共交通機関の重要性が指摘されています。 これらの意見は、公共交通機関が単なる移動手段にとどまらず、地域住民の生活基盤を支える重要なインフラであることを示しています。そのため、その維持・存続のためには、利用者の減少という課題への積極的な対策が不可欠であることが改めて認識されます。
3. 利用者からの具体的な改善策提案
アンケートでは、公共交通機関の利便性向上のための具体的な改善策も数多く提案されています。 運行頻度の向上、特に時間帯別の運行本数の見直し、そして時刻表の分かりやすいデザインと各戸への配布が強く求められています。 高齢者や車椅子利用者への配慮として、バスのステップの低床化、停留所のバリアフリー化、駅周辺の整備なども重要な改善策として挙げられています。 料金体系の見直し、特に運賃の値下げや割引制度の導入も、利用促進のための有効な手段として提案されています。 さらに、地域の活性化を促進するためのイベント企画、企業との連携による広告収入の確保、そして大学との連携によるプロジェクトなども、新たな視点からの改善策として提案されています。 これらの提案は、利用者目線に立ったきめ細かい改善策であり、地域住民の生活実態を反映した具体的かつ実現可能な提案であると言えるでしょう。実現に向けた自治体や事業者の積極的な取り組みが期待されています。
III.公共交通ネットワークの将来 費用便益分析と可能性
松浦鉄道の存続または廃止、そして代行バス導入による代替案について、費用便益分析(50年間) を行う必要性が指摘されています。この分析では、鉄道維持に伴う費用と便益、バス代替案による費用と便益を比較検討し、社会的便益の高い方を選択する必要があります。分析には、道路交通量のデータ、時間価値原単位、自動車への転換率などが用いられます。しかしながら、観光客減少や商店街衰退といった定量化できない負の影響も考慮する必要があるとされています。西肥バスなど他事業者との連携による効率化、例えば熊本市のように共同出資会社設立による統合なども、検討すべき可能性として挙げられています。平成23年度の路線バス補助金は2億3600万円に上りますが、利用者減少傾向は続いており、事業者撤退のリスクも懸念されています。
1. 運行本数と時間帯の不足
アンケート回答からは、松浦鉄道と路線バスの運行本数が少ないこと、そして運行時間帯が限定されていることが大きな問題として浮き彫りになっています。特に、通勤・通学時間帯や通院時間帯など、需要の多い時間帯において運行本数が不足しているという指摘が多数寄せられています。 これにより、利用者は長時間待つ必要に迫られたり、目的の場所に時間通りに到着できないといった不便さを強いられています。 特に、平戸地区や松浦地区では、午後8時以降や午前6時以前のバスが運行されていないため、学生や高齢者にとって大きな負担となっています。 また、運行間隔の広さによって、利用機会そのものが減少しているという指摘も複数見られます。 これらの問題は、利用者の減少という悪循環を引き起こし、公共交通ネットワークの維持をさらに困難にしている可能性があります。運行本数と時間帯の改善が喫緊の課題となっています。
2. アクセス性とバリアフリーの問題
公共交通機関の利用を妨げている要因として、アクセス性の悪さとバリアフリー化の遅れが挙げられています。 多くの回答者から、駅やバス停までの距離が遠く、高齢者や身体の不自由な人にとってアクセスが困難であるという意見が出ています。 特に、駅からのアクセスやバス停までの道のりが不便なため、自家用車に頼らざるを得ないという意見も散見されます。 また、バスや鉄道の乗降口におけるステップの高さが、高齢者や車椅子利用者にとって大きな障壁になっているという指摘も複数あります。 バリアフリー化の遅れは、利用者の減少を招き、公共交通機関の持続可能性を脅かす要因の一つとなっています。 これらの問題を解決するためには、駅やバス停周辺の整備、バリアフリー対応の向上、そして利用者にとって分かりやすい案内表示の設置などが不可欠です。 より多くの住民が利用しやすい環境づくりが求められています。
3. サービスレベルと改善に向けた提案
利用者からは、公共交通機関のサービスレベルの向上を求める声が多数上がっています。 具体的には、従業員の対応の改善、運転マナーの向上、そして時刻表の分かりやすさなどが指摘されています。 松浦鉄道の電話対応や車内での対応に不満を持つ意見、路線バスの運転手の運転マナーに問題があるという意見など、サービス面での改善を求める声が複数寄せられています。 また、時刻表の分かりにくさから、目的地にたどり着けなかったという具体的な事例も報告されており、時刻表の改善、特に各家庭への配布や分かりやすい地図形式の導入が強く求められています。 さらに、利用状況に合わせた車両のサイズ変更(小型バスの導入など)、料金体系の見直し、そして地域活性化のためのイベント開催といった、多様な改善策が提案されています。 これらの提案は、利用者にとってより快適で利用しやすい公共交通機関を実現するための具体的な取り組みであり、自治体や事業者による積極的な対応が求められています。サービス向上は、利用者増加に繋がるだけでなく、地域全体の活性化にも貢献するでしょう。
IV.具体的な改善提案 多様なニーズへの対応
具体的な改善策としては、大学への通学時間帯の延長、伊万里~有田間の終電時刻繰り下げといった時間帯調整、駅舎の活用による高齢者施設や商店の誘致、バリアフリー化の推進(低いステップの設置など)、そして時刻表の改善(分かりやすさ、家庭への配布、地図形式の導入など)が挙げられています。さらに、松浦鉄道の活性化策として、イベントの開催(ビール列車以外の企画)、広告収入の獲得、学校との連携による利用促進などが提案されています。 高齢者に対するタクシー利用補助や、一日乗車券の導入も検討課題として提示されています。
1. 運行頻度 時間帯の改善と料金体系の見直し
アンケートでは、公共交通機関の利用促進のための具体的な改善策として、運行頻度と時間帯の改善、そして料金体系の見直しに関する提案が多数寄せられています。 運行頻度については、特に通勤・通学時間帯や通院時間帯など、需要の高い時間帯に運行本数を増やすことが強く求められています。 また、終電時刻の繰り下げ、特に大学のある佐世保や伊万里から有田への路線の終電時刻繰り下げに関する要望が目立っています。 料金体系については、現在の運賃が高すぎるという意見が多く、利用しやすい料金設定にするべきという提案が多数寄せられています。 具体的には、学生向けの割引制度の導入や、高齢者向けの低料金制度の導入、あるいは長崎市の路面電車料金を参考に運賃体系を見直すことが提案されています。 さらに、一日乗車券の導入によって、複数の路線を乗り継ぐ際の料金負担を軽減することも提案されています。これらの提案は、公共交通機関の利用を促進し、より多くの住民が利用しやすい環境を整備するための具体的な方策を示しています。
2. アクセス性向上とバリアフリー化の推進
公共交通機関の利用促進には、アクセス性向上とバリアフリー化の推進が不可欠であるとの意見が多数寄せられています。 駅やバス停までの距離が遠いため、利用しにくいという意見が多く、特に高齢者や身体の不自由な人にとって、駅から自宅までの距離が課題となっています。 そのため、最寄りの駅までアクセスしやすいシャトルバスの導入や、バス停の数を増やし、住宅地に近い場所にバス停を設置するなどが提案されています。 また、高齢者や車椅子利用者にとって大きな障壁となっている、バスや鉄道の乗降口のステップの高さを低くするなど、バリアフリー化の推進も強く求められています。 さらに、松浦鉄道の駅舎を活用し、高齢者向け施設や商店などを誘致することで、駅周辺の利便性を高める提案や、駅舎のバリアフリー化も提案されています。 これらの提案は、公共交通機関を利用するすべての人が、快適に安全に利用できる環境を整備するための具体的な方策を示しています。
3. サービス向上と地域活性化のための提案
利用者からは、公共交通機関のサービス向上と地域活性化のための様々な提案がなされています。 具体的には、松浦鉄道や路線バスの利用促進を目的としたイベントの企画・開催が提案されています。 既存のビール列車のようなイベントだけでなく、合コンや趣味の集まりなどを開催できる車両の導入などが提案されています。 また、時刻表の見やすさや分かりやすさを改善するための提案もなされており、各家庭への配布、地図形式による分かりやすい表示、そして経由地の明確化などが求められています。 さらに、企業との連携による広告収入の確保や、学校との連携による利用促進のための取り組みも提案されています。 これらの提案は、単なる交通手段の確保にとどまらず、地域住民の生活の質を向上させ、地域経済を活性化するための積極的な取り組みが求められていることを示しています。 地域住民の意見を反映した、より魅力的で利用しやすい公共交通機関の実現に向けて、自治体や事業者の積極的な取り組みが期待されています。
