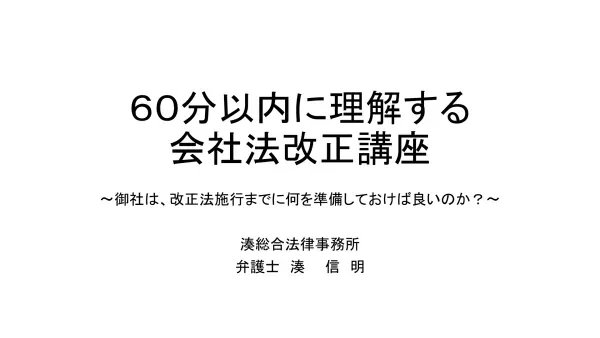
株式会社制度:歴史と課題
文書情報
| 学校 | 〇〇大学 (例: 東京大学) |
| 専攻 | 法学 |
| 出版年 | 2024 (例: 授業が行われた年) |
| 場所 | 〇〇市 (例: 東京) |
| 文書タイプ | 講義資料 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 468.12 KB |
概要
I.株式会社制度の現状と改正点 会社法改正 のポイント
本資料は、日本の会社法改正に関する重要な変更点を解説しています。特に、社外取締役、社外監査役、監査役会、委員会設置会社、監査等委員会設置会社といった企業統治に関する制度改革に焦点を当てています。公開会社や大会社におけるこれらの制度の適用条件、責任限定契約の範囲変更、会計監査人の選解任手続きの見直しなどが主な内容です。改正により、社外取締役・社外監査役の要件が厳格化され、監査等委員会の権限強化、多重代表訴訟制度の導入など、企業のガバナンス強化とM&A関連規制の整備が図られています。これらの変更は、企業のコーポレートガバナンスに大きな影響を与え、対応が求められます。
1. 株式会社制度の成立と問題点
このセクションでは、株式会社制度の成立過程と、その歴史的背景が簡潔に述べられています。コロンブスのアメリカ大陸発見の頃を例に、大規模経営がごく一部の王侯貴族に限られていた時代から、株式会社制度の成立によって小資本を糾合し大規模経営が可能になった点が、制度の大きなメリットとして挙げられています。所有と経営の分離、株主有限責任といった株式会社制度の基盤となる要素も説明されています。これらの記述は、現代の株式会社制度の理解を深めるための歴史的コンテキストを提供しています。特に、小資本による大規模経営の促進という点は、現代の経済活動においても重要な意味を持つ株式会社制度の根幹をなす要素と言えるでしょう。このセクションは、歴史的な視点から株式会社制度の意義と発展を簡潔に示すことで、後のセクションで詳述される改正点への理解を促進する導入部としての役割を果たしています。
2. 公開会社と大会社の定義
本セクションでは、会社法改正において重要な役割を果たす「公開会社」と「大会社」の定義が明確に示されています。「公開会社」は、株式の譲渡に際して株式会社の承認を要しない株式を発行している会社と定義され、「大会社」は、最終事業年度の貸借対照表において資本金5億円以上または負債合計額200億円以上の要件を満たす会社と定義されています。これらの定義は、後のセクションで解説される、社外取締役設置義務や監査役会設置義務などの適用範囲を決定する上で重要な役割を担います。特に、資本金や負債額といった財務状況が、企業の規模とリスクレベルを反映する重要な指標として用いられている点が注目に値します。これらの定義を明確にすることで、改正法の適用範囲を明確化し、企業の対応を容易にしていると言えるでしょう。 この定義に基づいて、後のセクションでは、公開会社や大会社に対する具体的な規制変更が説明されます。
3. 監査役会と委員会設置会社 そして執行役員制度
このセクションは、日本の会社における監査体制と経営構造について、監査役会設置会社と委員会設置会社の2つの主要な形態を比較しながら解説しています。原則として監査役会設置は義務ではないものの、大会社かつ公開会社は、監査役会設置会社または委員会設置会社のいずれかを選択する必要があると説明されています。監査役会設置会社では経営者を選解任する権限がなく、適法性監査のみに限定される一方、委員会設置会社はほとんど採用されていない現状が指摘されています。さらに、執行役員制度は会社法に規定された制度ではなく、委員会設置会社とは異なる構造であることに注意が必要であると述べられています。このセクションは、改正法による監査体制の変化を理解する上で不可欠な基礎知識を提供しています。監査役会設置会社と委員会設置会社のそれぞれの特性を比較することで、改正法による新たな監査等委員会設置会社制度の位置づけを理解するための重要な前提が示されています。特に、執行役員制度に関する注意喚起は、誤解を防ぐ上で重要です。
4. 会計監査人の選解任に関する権限委譲
このセクションは、会計監査人の選解任に関する手続きにおける改正点を解説しています。改正前は、監査役設置会社または監査役会設置会社において、取締役は会計監査人の選解任について監査役または監査役会の同意を得る必要がありました。改正法では、監査役会または監査役への同意権から、監査役会への決定権委譲へと権限が拡大されました。この変更の趣旨は、業務執行取締役と会計監査人との意見対立による会計監査人の恣意的交替を防止することです。このセクションでは、改正前後の手続きの違いを明確に示すことで、会計監査人選解任におけるガバナンス強化の狙いが明確に示されています。特に、業務執行取締役と会計監査人の意見対立という具体的な問題点を提示することで、改正の必要性が説得的に説明されています。この変更は、企業会計の透明性と独立性を確保するための重要なステップと言えるでしょう。
II.社外取締役 監査役制度の強化
改正会社法では、社外取締役及び社外監査役の設置要件と役割が大きく見直されました。特に公開会社、大会社においては、社外取締役の選任に関する説明義務が創設され、社外取締役及び社外監査役の選任基準が厳格化されました。監査役会設置会社と委員会設置会社のどちらを選択するかも重要な検討事項です。監査等委員会設置会社は、従来の監査役会設置会社や委員会設置会社とは異なる特徴を持ちます。監査等委員会は、適法性監査だけでなく妥当性監査も行う権限を持ちます。 これらの変更は、企業の透明性と説明責任を高めることを目的としています。
1. 社外取締役の設置義務と説明責任
このセクションでは、改正会社法における社外取締役の設置に関する規定が中心的に扱われています。まず、公開会社においては、監査役会設置会社または委員会設置会社のいずれかを選択する必要があり、金融商品取引法に基づき有価証券報告書を提出する義務のある会社が社外取締役を置いていない場合、その理由について説明する義務が新たに創設されたことが解説されています。これは、企業の透明性を高め、ガバナンスの強化を図るための重要な改正点です。特に、金融商品取引法との関連性が示されている点が重要で、公開市場における情報開示の重要性を強調していると言えるでしょう。説明義務の対象となるのは、監査役会設置会社と、公開会社かつ大会社であることが明確にされています。この説明責任の強化は、企業の意思決定過程における透明性を高め、株主や投資家の保護に繋がるものと期待されています。
2. 社外取締役 社外監査役の要件見直し
改正法では、社外取締役および社外監査役の要件についても変更が加えられています。改正前は、業務執行取締役等でないこと、一定の資格要件を満たすこと、過去10年間業務執行取締役等にならなかったこと、などが要件として挙げられていましたが、改正後には、さらに詳細な要件が追加されています。具体的には、過去10年間の業務執行取締役等への就任状況に関する規定が厳格化されており、非業務執行取締役、監査役、会計参与といった役職に就任していた場合も考慮されるようになりました。これにより、社外取締役・社外監査役の独立性をより一層高め、企業ガバナンスの強化を目指していることが読み取れます。この変更は、社外取締役・社外監査役の選任において、より厳格な審査が必要となることを意味し、企業は人選において慎重な対応が求められます。既存の社外取締役・社外監査役についても、改正後の要件を満たさない場合は、交代が必要となる可能性があります。
3. 社外監査役の人選と監査役会設置の義務
監査役会設置会社における社外監査役の人選については、親会社の現職全員や兄弟会社の現職の業務執行者を除外することが推奨されています。これは、独立性を確保し、客観的な監査を行うためです。また、監査役会の設置が義務付けられるのは大会社かつ公開会社のみであることが強調されており、それ以外の会社は、任意に監査役会を設置するか、設置しないかを決定できます。子会社が大会社かつ公開会社の場合は、株式に譲渡制限を設けることで非公開会社とし、監査役設置会社とすることも一つの方法として示されています。これらの記述から、企業規模や形態に応じて柔軟な対応が可能である一方で、独立性と透明性を確保するための配慮が求められていることが分かります。特に、子会社に対する対応策は、企業グループ全体のガバナンスを考慮した上で戦略的に選択する必要性を示唆しています。社外取締役・社外監査役の範囲変更により、責任限定契約ができなくなるケースも想定され、企業は適切な対応を検討する必要があります。
III.責任限定契約の範囲拡大と監査等委員会
改正により、責任限定契約を締結できる者の範囲が拡大され、社内取締役でも非業務執行取締役、社内監査役も締結可能となりました。また、新たな制度として監査等委員会設置会社が創設されました。これは、監査役会設置会社と委員会設置会社の中間的な位置づけにあり、社外取締役の関与が強まる仕組みです。監査等委員会は、取締役の職務執行監査、会計監査人の選任・解任など重要な役割を担います。監査役会との違いは、監査等委員は独任制ではない点と、妥当性監査を行う権限を持つ点です。
1. 責任限定契約の範囲拡大
このセクションでは、改正会社法による責任限定契約の範囲拡大について解説しています。改正前は、責任限定契約を締結できるのは限定的な役員に限られていましたが、改正法では、社内取締役であっても非業務執行取締役は責任限定契約を締結できるようになりました。さらに、社内監査役も責任限定契約の締結が可能となりました。この変更は、企業におけるリスク管理の観点から、より多くの役員が責任限定契約を活用できるようになり、企業活動における柔軟性と効率性を高める効果が期待されます。従来、責任限定契約は、特定の役員に限定される傾向があり、企業活動における制約となっていた側面がありました。改正により、責任限定契約の適用範囲が拡大されたことで、より多くの役員が自身の責任範囲を明確化し、業務遂行におけるリスクを軽減できるようになります。特に、社内監査役への適用拡大は、監査業務の独立性と客観性を維持しつつ、監査役個人のリスク軽減にも貢献すると考えられます。ただし、責任限定契約の濫用を防ぐための適切な管理体制の構築も重要になります。
2. 監査等委員会設置会社制度の創設
このセクションの焦点は、新たに創設された監査等委員会設置会社制度です。監査等委員会の職務として、取締役の職務執行の監査、監査報告の作成、会計監査人の選任・解任に関する議案の作成などが挙げられています。監査等委員会は、監査報告の作成において、報告徴収権や調査権を有する監査等委員の決議に従う必要があります。監査役会と比較すると、監査役会は監査役が独任制の機関であるのに対し、監査等委員会は独任制ではなく、複数の監査等委員で構成されます。委員会設置会社との比較では、指名委員会や報酬委員会の設置義務がないこと、執行役が設置されないこと、「監査等委員である取締役」が株主総会で他の取締役と区別して選任されることなどが挙げられています。監査等委員会設置会社は、委員会設置会社の変種と捉えることも、監査役会設置会社の発展形と捉えることもでき、それぞれ異なる評価が可能です。前者では経営者人事への社外取締役の関与が不十分とされ、後者では複数の社外取締役の設置と経営者人事への関与が可能となります。
3. 監査等委員会と監査役会 委員会設置会社との比較
このセクションでは、監査等委員会設置会社を、委員会設置会社および監査役会設置会社と比較することで、その特徴と位置づけを明確にしています。監査等委員会設置会社は、指名委員会や報酬委員会の設置義務がなく、執行役も設置されません。監査等委員である取締役は、他の取締役と区別して株主総会で選任されます。これは、委員会設置会社とは異なる点です。監査権限においては、監査等委員会は適法性監査に加え、妥当性監査も行うことができますが、監査役会は適法性監査のみに限定されます。また、一定の要件を満たせば、取締役会決議事項の一部を個別の取締役に委任することも可能です。監査等委員会設置会社を委員会設置会社の変種と見ると、経営者人事への社外取締役の関与が不十分という弱点がありますが、監査役会設置会社の発展形と見ると、複数の社外取締役の設置と経営者人事への関与が可能となり、ガバナンス強化に繋がるという評価が可能です。これらの比較分析を通じて、監査等委員会設置会社が、企業ガバナンスの多様なニーズに対応できる柔軟な制度であることが示唆されています。
IV.M Aに関する規制強化と多重代表訴訟
M&A関連では、支配株主の異動を伴う募集株式発行や、一定規模以上の子会社株式譲渡に関する規制が強化されました。特に、キャッシュアウト(圧迫買収)対策も強化されています。さらに、多重代表訴訟制度の導入により、親会社株主が、一定要件を満たす子会社の取締役等に対し責任追及を行うことが可能となりました。これは、親会社株主の保護を強化することを目的としています。重要な子会社の定義は、その株式価値が最終完全親会社の資産の5分の1を超える場合とされています。
1. M A関連規制の強化 支配株主の異動と子会社株式譲渡
このセクションでは、M&Aに関する規制強化について、支配株主の異動を伴う募集株式の発行と、一定の要件を満たす子会社株式等の譲渡の2つの側面から解説しています。支配株主の異動を伴う募集株式の発行に関しては、改正法において、公開会社が特定の引受人に募集株式を割り当てることで、その引受人が総株主の議決権の過半数を有することとなる場合の手続きが規定されています。現行法では、公開会社における募集株式の発行は、払込金額が引受人に特に有利な金額でない限り、株主総会の決議を必要としませんでしたが、改正法では、支配株主の異動を伴うケースでは新たな手続きが必要となります。また、子会社株式の譲渡については、子会社株式の帳簿価額が総資産の5分の1を超える場合に、新たな規制が適用されます。これらの規制強化は、M&Aにおける透明性と公正性を高め、株主保護を強化するためのものです。特に、支配株主の変更という重要な事項について、より厳格な手続きを導入することで、不透明な取引や、少数株主の権利侵害を防ぐ効果が期待されます。
2. キャッシュアウト法制の整備と組織再編に関する規制
このセクションでは、キャッシュアウト(squeeze-out)法制の整備と、組織再編に関する規制について説明しています。キャッシュアウト法制とは、総株主の議決権の90%以上を有する株主(特別支配株主)が対象会社の承認(取締役会決議)を得た場合に、残りの株主から強制的に株式を取得できる制度です。この制度の整備は、M&Aにおける効率性を高める一方で、少数株主の保護にも配慮する必要があります。また、組織再編(吸収分割、新設分割など)に関しても、改正法では、全部取得条項付種類株式の取得や株式の併合といったケースに対する差し止め制度の整備が触れられています。さらに、詐害的な会社分割等における債権者保護の強化についても言及されており、吸収分割会社(新設分割会社)が債権者を害することを知って吸収分割(新設分割)を行った場合の対応が規定されています。これらの規定は、M&Aや組織再編における様々なリスクを考慮し、関係者の権利保護を図ることを目的としています。特に、債権者保護の強化は、企業の再編に伴う債務不履行のリスクを軽減する上で重要な役割を果たします。
3. 多重代表訴訟制度の導入
このセクションでは、改正法で導入された多重代表訴訟制度について解説しています。多重代表訴訟とは、子会社の取締役等の会社に対する責任が発生した場合に、親会社の株主が子会社の株主として、その責任を追及できる制度です。従来の株主代表訴訟制度では、株主は自らが株式を保有している会社の取締役等の責任のみを追及可能でしたが、多重代表訴訟制度の導入により、親会社株主が子会社の取締役等の責任を追及できるようになりました。これは、親会社と子会社間の人的関係等により、子会社役員等への責任追及が滞る現状への対応策として位置付けられています。原告になれるのは最終完全親会社等の株主であり、追及されるのは、その株式価値が最終完全親会社の資産の5分の1を超える重要な子会社の役員等となります。この制度は、企業グループ全体のガバナンス強化に貢献するとともに、親会社株主の保護を強化することを目的としています。特に、企業グループにおける複雑な関係性の中で、少数株主の権利保護をより確実なものにするための重要な制度と言えるでしょう。
V.施行直後の対応と今後の展望
改正法は、施行直後から社外取締役の設置に関する説明義務など、即時対応が必要な事項を含みます。株主総会招集手続きや、支配株主変更を伴う募集株式発行などについても、改正法の施行日以降に適用されます。これらの改正は、日本の企業ガバナンスの抜本的な改革を目指しており、企業は迅速な対応と体制整備が求められます。特に、公開会社及び大会社は、これらの改正内容を十分に理解し、適切な対応を行う必要があります。
1. 施行直後の対応 説明義務と経過措置の欠如
このセクションでは、改正会社法施行直後から対応が必要となる事項について解説しています。特に、経過措置がない点が強調されており、施行直後の定時株主総会において、「社外取締役を置くことが相当でない理由」の説明義務が課されることが指摘されています。この説明義務は、適用時期についての経過措置がないため、施行直後の株主総会から適用されます。これは、企業にとって、迅速な対応が求められることを意味しています。改正法の施行により、企業は直ちに新たな規定に適合する必要があるため、準備期間が限られていることが、企業にとって大きな課題となります。特に、社外取締役の選任や、その理由の説明準備は、施行直前の時期に集中して行われる必要があり、企業の人的・時間的リソースに大きな負担がかかる可能性があります。この説明義務の履行状況は、企業のガバナンス体制の透明性を評価する上で重要な要素となるため、企業は綿密な準備と対応が不可欠です。
2. 株主総会決議事項と改正法の適用時期
このセクションでは、改正法の適用時期に関する重要な注意点が述べられています。株主総会決議が必要となる事項、例えば会計監査人の選解任などは、株主総会の招集手続きの開始時期を基準として改正法が適用されます。一方、支配株主に変更を来す募集株式の発行については、改正法の施行日以降に募集事項の決定があった募集株式・募集新株予約権の割り当てから適用されるとされています。このことは、改正法の適用時期が、対象となる行為の決定時期や株主総会の招集時期によって異なることを示しています。企業は、それぞれの状況に応じて、改正法の適用時期を正確に把握し、適切な対応を行う必要があります。特に、M&Aなど、重要な経営判断を伴う事項については、改正法の施行時期との関係を慎重に検討する必要があるでしょう。このセクションは、改正法の適用に関する細かな点にまで触れることで、企業がスムーズに改正法に対応できるよう支援する役割を果たしています。
