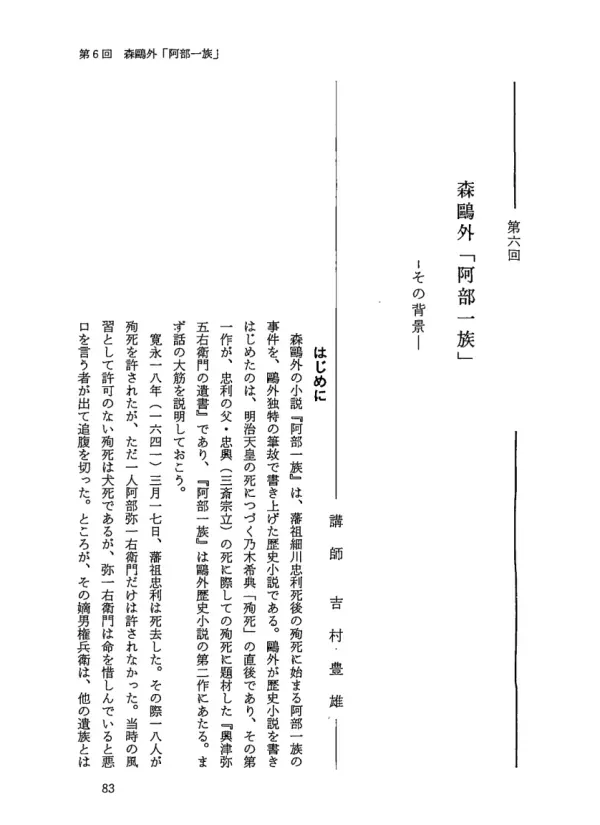
森鴎外『阿部一族』:殉死の背景と史実
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.12 MB |
| 著者 | 吉村豊雄 |
| 文書タイプ | 講義録 |
概要
I.熊本藩における 阿部一族事件 細川忠利 の死と家臣たちの選択
この文書は、熊本藩主細川忠利の死後発生した阿部一族事件の真相解明を試みるものである。特に、家臣阿部弥市右衛門の殉死とその背景、そして息子の阿部権兵衞による落髪事件とその後の一族郎党の悲劇に焦点を当てる。阿部弥市右衛門は、高い地位と知行高(1000石以上)を得ていたにも関わらず、許しを得ないまま切腹した。その理由、そして同等の地位にあった寺本八左衛門との対比を通して、阿部弥市右衛門の行動の解釈を探る。寛永年間の熊本藩の政治状況も重要な要素となる。
1. 細川忠利の死と19名の殉死者
熊本藩主細川忠利の死後、19名の家臣が殉死した。その内訳は知行取9名、切米・扶持取10名とされ、禄高の低い下級家臣が多いことが特徴として挙げられる。 鷗外の小説『阿部一族』では、忠利から普段から疎まれていたとされる阿部弥市右衛門が、許しを得ずに追腹したことから阿部家悲劇が始まるとして描かれている。 この殉死者の構成や阿部弥市右衛門の行動を理解するには、忠利から光尚への藩政の転換期という時代背景を考慮する必要があるとされている。 特に、阿部弥市右衛門とほぼ同格の知行高を持っていた寺本八左衛門とを比較することで、阿部弥市右衛門の殉死の特異性が強調されている。 様々な家臣の殉死の状況や、禄高、年齢、役職などが簡潔に記述されており、当時の家臣団の構造や忠利の統治様式の一端を垣間見ることができる。
2. 阿部弥市右衛門の経歴と殉死の動機
阿部弥市右衛門は、細川氏の豊前時代末期には山村姓の豊前国宇佐郡の惣庄屋であったとされる。細川氏の肥後移封に伴い、家臣に召抱えられ、阿部姓を名乗るようになった。 奉書に記録された忠利の命令では、塩年貢の取立てに関して献策した弥市右衛門の知行を50石加増し100石としたとあり、その内30石を嫡男に与え惣庄屋職を譲らせたことが記されている。 一方、寺本八左衛門の先祖は今川家に属し、父は秀吉の朝鮮出兵に加わった後、牢人となった経歴を持つ。大坂の陣では豊臣方に属し、その後、細川家に召抱えられた経歴を持つ。 阿部弥市右衛門と寺本八左衛門は、知行高は同程度であったが、出自や経歴が大きく異なっていた。 阿部弥市右衛門は農民出身からの出世であり、一貫して非軍事の役方(行政組織)の道を歩み、短期間で加増を重ねたという異例の経歴を持つ。この点が、彼の殉死の背景に深く関わっている可能性を示唆している。
3. 寺本八左衛門の殉死と殉死志願者
寺本八左衛門は、追腹する前々日に新藩主光尚の側近に宛て、忠利に殉じたい旨の書状を出している。この書状の内容から、寺本八左衛門が新参者として忠利からの恩義を強く感じ、報いるために殉死を決意したことがわかる。 書状には、鉄砲衆の出入りへの配慮や、光尚への取り次ぎ依頼などが記されている。 忠利の死後、多くの殉死志願者が出た中で、寺本八左衛門は殉死志願者の「目安」のような存在であった可能性が示唆されている。 阿部弥市右衛門が殉死を願っていた可能性は少ないとされている。 また、国元の老臣たちが寺本八左衛門の追腹とその家臣への影響を強く警戒していたことも指摘されている。
4. 阿部権兵衞の落髪と阿部一族の最期
阿部一族事件の直接のきっかけは、忠利の三回忌法要における阿部権兵衞(阿部弥市右衛門の嫡男)の落髪であった。 権兵衞は、父が家中の嘲笑の中で忠利の許しを得ずに切腹したため、跡目相続で差別を受け、落髪して位牌に供えた。 残された兄弟たちは、山崎の本家に籠城し、藩側の討手と戦い、全員討死した。 この落髪は、藩当局や新藩主光尚への直接的な非難・抗議というよりも、武士としての行為として解釈できるのではないかとされている。 光尚は、権兵衞の所業に激怒し、一族郎党を討伐した。 この事件は、阿部家の知行高の相続問題や光尚の藩政改革と深く関わっており、複雑な背景を持つ事件であることが示唆されている。
II. 阿部弥市右衛門 の 殉死 忠義か 政治的圧力か
阿部弥市右衛門の殉死は、単なる忠義によるものなのか、それとも藩政の転換期における政治的圧力や細川光尚の政策との関連性があるのかが問われる。阿部弥市右衛門は、惣庄屋から家臣に抜擢された異例の経歴を持ち、その出世の経緯や細川忠利との関係、そして殉死を決意した背景について、文書は多角的な考察を試みている。殉死しなかった家臣、奥田権左衛門の存在も対照的に示されている。
1. 阿部弥市右衛門の殉死 経緯と解釈の多様性
阿部弥市右衛門の殉死は、この事件の中心であり、その動機や意味について様々な解釈が提示されている。文書では、彼が細川忠利の許しを得ずに追腹した事実が強調されている。 これは、単なる忠義による行動なのか、それとも他に隠された事情があるのかが議論の中心となる。 彼は、惣庄屋から家臣に抜擢された異例の経歴を持ち、忠利からの信頼が厚かったと同時に、家臣たちから疎まれていたという側面も指摘されている。 また、ほぼ同等の知行高を持っていた寺本八左衛門との比較を通して、阿部弥市右衛門の殉死の特異性が浮き彫りにされている。 彼の人物像は、有能だが人付き合いが苦手な武士として描かれており、この点が彼の行動を理解する上で重要な要素となる。
2. 出自と経歴 惣庄屋から家臣への異例の出世
阿部弥市右衛門の出自は、惣庄屋という農民に近い身分から家臣に登用されたという異例性を持つ。 この経歴は、彼の人物像や殉死の動機を考える上で重要な要素となる。 文書では、彼の出世は忠利の強力な引き立てによるものであったことが強調されている。 奉書に記された忠利の命令から、阿部弥市右衛門が塩年貢の取立てに関して献策し、その功績により知行が加増されたことがわかる。 しかし、この出世の経緯は、家臣団内部での反発や嫉妬を招いた可能性も示唆している。 従来の武士階級出身者とは異なる経歴が、彼の殉死の背景に複雑な要素を加えていると推測できる。
3. 殉死しなかった奥田権左衛門との対比
阿部弥市右衛門の殉死と対照的に、殉死しなかった奥田権左衛門の存在が注目されている。奥田権左衛門は、殉死しなかったことで家中で強く非難されたとされている。しかし、彼は明確な奉公観念に基づき、殉死せず次の藩主に仕えたと記述されている。 奥田権左衛門の行動は、殉死が必ずしも忠義の唯一の表現ではないことを示唆している。 彼の発言からは、主君に召抱えられた者だけが殉死すべきという考え方を批判するニュアンスが読み取れる。 この対比を通して、阿部弥市右衛門の殉死が、単なる忠義だけでなく、複雑な政治的・社会的な背景を持つ可能性が示唆される。
III. 阿部権兵衞 の 落髪 抗議か それとも
阿部弥市右衛門の死後、息子の阿部権兵衞は、細川忠利の三回忌法要において落髪という行動に出る。この行為が、藩当局や細川光尚への直接的な抗議であったのか、それとも武士道に基づく別の解釈ができるのかが議論されている。阿部権兵衞の行動と、その後の一族郎党による籠城、そして討死という悲劇的な結末に至る過程について、文書は様々な史料を基に分析している。阿部家の知行高(2000石)の分割相続問題もこの事件に絡んでいる。
1. 阿部権兵衞の落髪 事件の直接的引き金
阿部権兵衞の落髪は、阿部一族事件の直接的な引き金となった行為である。 鷗外の小説では、父・阿部弥市右衛門の無許可の切腹と、それに伴う跡目相続における差別への反発として描かれている。 法要の場で落髪し、位牌に供えたという行為は、単なる抗議行動というだけでなく、武士としての強い決意表明とも解釈できる。 文書では、この行為が藩当局や新藩主・細川光尚への直接的な非難であったか、あるいは別の解釈が可能なのかが議論されている。 権兵衞の落髪は、その後の一族郎党の籠城と討死という悲劇的な展開へと繋がる重要な出来事であった。
2. 落髪の解釈 抗議か それとも忠義の別の表現か
阿部権兵衞の落髪は、藩当局への抗議行動と解釈することもできるが、文書では、武士としての行為、あるいは先君への哀惜・追慕の表現と捉えることも可能だと示唆している。 彼の落髪は、単なる反逆ではなく、武士としての倫理観や、父への深い思い、そしてもはや武家奉公を続ける意思がないという表明であった可能性がある。 光尚の意向を無視して切腹した19名の殉死者の相続問題、特に阿部家の知行高の相続に関する光尚の対応も、権兵衞の行動に影響を与えた可能性がある。 当時の記録資料が詳細ではないため、落髪の真意は断定できないものの、様々な解釈の余地を残す行為であったと言えるだろう。
3. 光尚の対応と阿部一族の籠城 討死
阿部権兵衞の落髪に対し、光尚は激怒し、阿部一族を討伐するに至る。 これは、光尚が家督相続時に深刻化していた財政窮乏を克服するための政策と、家臣団の門閥的秩序を強化しようとした動きと関連している可能性がある。 阿部権兵衞は捕縛され、残された兄弟たちは籠城し、討手と戦って全員討死した。 この籠城と討死は、阿部一族の結束と、権兵衞の行動に対する責任の共有を示すものと見なせる。 一族郎党が文字通り「徒党」とみなされ、討伐されたという事実は、当時の藩政における厳格な秩序と、光尚の断固とした対応を浮き彫りにしている。
4. 阿部家の知行相続と光尚の政策との関連性
阿部家の知行相続は、この事件の重要な側面である。 阿部弥市右衛門の死後、阿部家の知行高は当初2000石であったが、その後大幅に削減された可能性が示唆されている。 この削減が、光尚の財政政策と関連しているか、あるいは権兵衞の落髪に対する罰則として行われた可能性がある。 光尚は、当初は殉死者の跡式相続を認めていたが、後にそれを取り消し、阿部家の知行高を没収した可能性がある。 この相続問題をめぐる藩当局と阿部家側のやり取りの詳細については、史料が乏しいため不明な点が多い。 しかし、この相続問題が、権兵衞の落髪や阿部一族の行動の背景に影響を与えたことは否定できない。
IV. 細川光尚 の対応と 阿部一族 の運命
新たな藩主細川光尚は、阿部一族に対する対応において、当初は譲歩的な姿勢を見せたものの、最終的には厳しい措置に出る。阿部家の知行高の大幅な削減や阿部権兵衞の処刑、そして一族郎党の討伐は、細川光尚の藩政改革と、阿部一族の行動に対する厳格な対応を示している。文書は、細川光尚の政治的判断と阿部一族の悲劇的な最期を詳細に記述し、阿部一族事件の全体像を明らかにしようとしている。
1. 細川光尚の初期対応 譲歩と相続問題
細川光尚は入国当初、殉死者の跡式相続を認め、ある程度の譲歩的な姿勢を見せていた。 これは、19名もの殉死者を出し、藩政が停滞していた状況を鑑みた対応とも考えられる。 しかし、この跡式相続は、阿部弥市右衛門の嫡男である阿部権兵衞の落髪事件によって状況が一変する。 光尚は、阿部弥市右衛門の跡式相続を認めつつも、権兵衞の行為には厳しく対処する。 阿部家に対する相続の決定は、知行高の分割や、扶持取の五男への相続など、複雑な要素を含んでおり、その決定過程の詳細や阿部家側の反応は文書からは不明である。
2. 阿部家知行高の削減と光尚の政策
阿部権兵衞の落髪事件の後、阿部家の知行高は大幅に削減された。 文書では、この削減が光尚による意図的なものだった可能性が示唆されている。 当初2000石あった阿部家の知行高は、兄弟で分割相続された後、900石にまで減らされた。これは、光尚が入国当初に見せた譲歩的な姿勢とは対照的な、非常に厳しい措置と言える。 この知行高の削減は、光尚が家臣の禄高削減を通して藩の財政再建を目指していたという、当時の藩政の状況と関連している可能性が高い。 この厳しい措置は、権兵衞の落髪という行動に対する罰則的な意味合いも持っていたと考えられる。
3. 阿部一族の籠城と討伐 光尚の断固たる対応
阿部権兵衞の落髪事件と、それに続く阿部家の知行高削減に対し、阿部一族は山崎の本家に籠城する。 この籠城は、光尚への抗議や、一族の結束を示す行為と解釈できる。 しかし、光尚は阿部一族の籠城を「徒党」とみなして討伐命令を出し、一族郎党は全員討死した。 この討伐は、光尚が藩政の安定と秩序維持を最優先し、権兵衞の行為を許容しなかったことを示している。 光尚は入国早々に追腹を禁止しており、この事件における光尚の断固とした対応は、彼の藩政改革における強硬な姿勢を示すものと言えるだろう。 この事件は、光尚による藩政改革の過程における、厳しい現実と力関係を浮き彫りにしている。
4. 光尚の御意と家臣団の秩序 事件の背景
光尚は入国直後、殉死を禁じる「御意」を示していた。 しかし、阿部弥市右衛門の殉死後、光尚は当初は跡式相続を認めた。 しかし、権兵衞の落髪事件後、その決定を撤回し、阿部家の知行高を削減した。 これは、光尚が家臣団の秩序維持を重視し、権兵衞の行為を許容できなかったためと考えられる。 また、忠利の死後、殉死を押しとどめた譜代門閥家臣も、権兵衞の行為を快く思わなかった可能性が高い。 この事件は、光尚の藩政運営、家臣団の内部構造、そして武士の忠義と秩序といった多様な要素が複雑に絡み合った結果であると言える。
