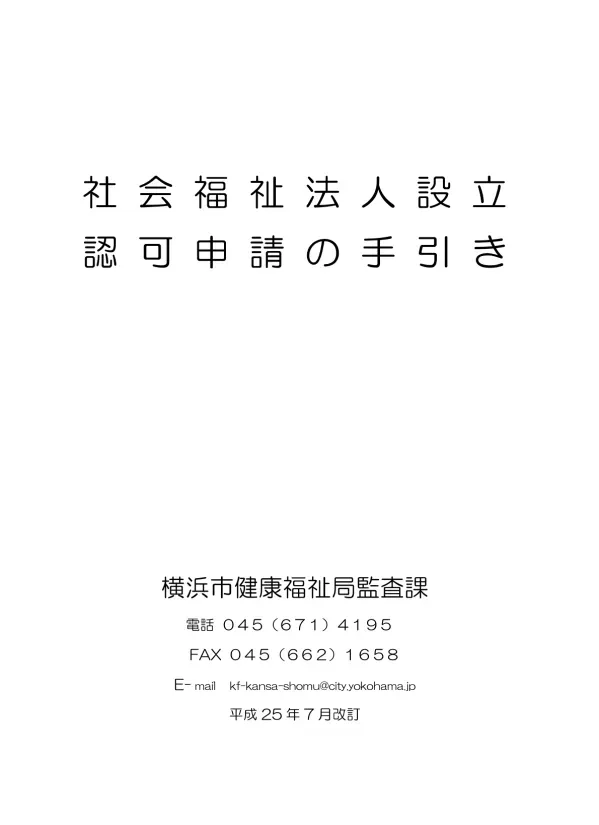
横浜市社会福祉法人設立認可申請ガイド
文書情報
| 著者 | 横浜市健康福祉局監査課 |
| 会社 | 横浜市健康福祉局監査課 |
| 場所 | 横浜市 |
| 文書タイプ | ガイドライン、手続き説明書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.39 MB |
概要
I.社会福祉法人設立認可申請に必要な書類と手順
横浜市における**社会福祉法人設立(Shakai Fukushi Houjin Setsuriku)**の認可申請には、多くの書類の準備が必要です。**認可申請(Ninka Shinsei)**には、定款(Teikan)、事業計画書、財産目録(Zaisan Mokuroku)、役員(Ri-ji)・監事(Kanji)に関する書類、設立代表者(Setsuriku Daihyousha)に関する書類、そして財産の帰属を証明する書類などが必要となります。特に重要なのは、財産目録には、運転資金として年間事業費の12分の1以上(指定介護老人福祉施設等の場合、12分の2以上)の現金、普通預金等を記載する必要があります。また、**贈与契約書(Zouyo Keiyaku)や不動産(Fudousan)**に関する書類(登記簿謄本、公図など)も必須です。 申請書類は全てA4サイズに統一し、提出期限を守ることが重要です。 不明な点は横浜市の監査課に確認してください。
1. 申請書類の提出方法と注意点
申請書はA4ファイルに綴じて1部提出します。準備会としての控えは別途用意してください。提出書類は、提出書類1~14ごとにインデックス等で表示しましょう。印鑑証明書、登記簿謄本などサイズの小さいものは、A4用紙に貼り付けて、なるべくA4サイズに統一してください。役員等の住所、氏名は、印鑑登録証明書の記載通りに一字一句正確に記入する必要があります。特に「沢」と「澤」、「斉」と「齋」のような表記の違いに注意が必要です。土地、建物の表示は、1筆、1棟ごとに登記事項証明書等の記載通りに記入してください。各様式例に記載されている(注)や様式は、提出する際に必ず削除してください。各証明書(身分証明書、印鑑登録証明書等)は申請受理日の直近のものでなければなりません。申請書の提出から、修正等が必要となり受理までに日数を要する場合があるので、取得時期については監査課に確認してください。
2. 社会福祉法人設立計画概要書
社会福祉法人設立等計画概要書(様式1)は、申請書類の総括表として作成してください。メールでの提出も可能です。理事の要件に関する部分(職歴、社会福祉活動歴等)については、現職(現職に就かれていない場合は「元」として元の職業)を具体的に記載する必要があります。 当該法人に係る社会福祉施設の整備、運営と密接に関連する業務を行う者は、理事総数の3分の1を超えてはなりません。理事同士に親族等の特殊な関係がある場合は、関係の有無とその内容(夫、妻、同一法人の役員等)を記載してください。横浜市暴力団排除条例第2条に定める者は、役員に就任できません。
3. 定款の作成と注意点
定款(様式3)は、メールでの提出も可能です。モデル定款は、厚生労働省通知(平成12年12月1日(最近改定平成24年3月30日)「社会福祉法人の認可について」)で示された社会福祉法人定款準則を基に作成してください。評議員会を置く場合、公益事業を行う場合などには、それぞれ章を加えてください。公益事業を行う場合は、資産の区分にも注意してください。建物を新設する場合は、基本財産(定款準則13条2項)には土地のみを1筆ごとに記載し、市有地貸与等の場合は空欄のままにしてください。建物は完成後、定款変更の届出(基本財産の追加)をしてください。施設を経営する法人は、1人以上の施設長等を理事として加えてください。ただし、評議員会を設置していない法人については、施設長等施設の職員である理事が理事総数の3分の1を超えてはなりません。
4. 設立当初の財産目録と関連書類
設立当初の財産目録(様式4)は、必要に応じて適宜修正して作成してください。運転資金として、法人の年間事業費の12分の1以上に相当する現金、普通預金等を有していることが必要です。ただし、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等の介護保険法上の事業にも該当する社会福祉事業及び障害者自立支援法等の支援費対象の社会福祉事業を主として行う法人は、12分の2以上に相当する現金、普通預金等が必要です。印鑑は、下記(4)の印鑑登録証明書で確認できる実印を使用してください。法人の設立代表者個人が贈与契約により当該法人に対して寄附する場合は利益相反事項となるため、設立代表者の代理者を設立準備委員会等で選任し、設立代表者の法人への贈与契約に係る権限を委任してください。未建設の建物は記載しないでください。福祉医療機構からの借入金は負債として計上しないでください。不動産目録(様式5)は様式5を参照し作成してください。贈与契約書は、寄附者ごとに作成してください。枚数が多い場合は、総括表を作成し、添付してください。法人事務所及び施設所在地を選挙区とする議員からの寄附は、公職選挙法に抵触するので認められません。現金の贈与を受ける場合、贈与者の残高証明書(原本)を添付してください。証明日はすべて同一の日付で取得してください。
5. 財産の帰属を証明する書類
設立当初の財産が法人に帰属することを証明する書類として、贈与契約書(様式6)、地上権、土地賃借権等の契約書及び登記誓約書、契約の相手方の印鑑登録証明書が必要です。国、地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受ける場合は、事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、様式7~10を参照に作成して添付してください。また、契約の相手方それぞれについて、印鑑登録証明書の原本を添付してください。不動産に抵当権、根抵当権、地上権等が設定されていないことが原則ですが、やむを得ない理由で未解除の場合は、権利者の解除承諾書等を添付してください。承諾書には、解除に必要な条件をできるだけ具体的に記載してください。不動産の賃借によって既に事業を実施している場合は、社会福祉法人設立後も現在の契約内容を承継する確認書を様式11を参照に作成してください。貸与を受ける不動産のすべてについて、全部事項証明書(原本)を添付してください。公図は、貸与地を縁取りして示してください。国有財産の建設等予定地については、旧道、水路等が含まれる場合は、それぞれ色分けして示してください。また、貸与地及びその隣接地には、その地権者名を記入してください。賃借料の水準は無償又は極力低額であることが望ましく、当該法人の理事長又は当該法人から報酬を受けている役員等から賃借により貸与を受けることは望ましくありません。
6. 設立代表者に関する書類
設立代表者の身分証明書及び印鑑登録証明書の原本を添付してください。ただし、設立代表者が財産の贈与者と同一であり、上記の身分証明書や印鑑登録証明書と重複する場合は、再度添付する必要はありません。設立代表者との贈与契約がない場合は、様式14を参考に、設立代表者からの贈与契約等がある場合は、様式15を参考に作成してください。設立代表者からの贈与契約等がある場合は、様式16を参考に、その部分について設立代表者とは別の発起人に権限を委任する旨の委任状を添付してください。権限を委任される発起人以外の設立発起人(理事、監事)全員の委任状としますが、連名のものも、個別に作成したものも構いません。印鑑は、印鑑登録証明書で確認できるものを使用してください。設立代表者を除く設立発起人(理事、監事)全員による委任状としますが、連名のものも、個別に作成したものも構いません。印鑑は、印鑑登録証明書で確認できるものを使用してください。
II.役員 監事に関する要件
**社会福祉法人設立(Shakai Fukushi Houjin Setsuriku)**における理事、監事の選任には、いくつかの要件があります。監事は2名以上とし、1名は財務諸表を監査できる者、もう1名は社会福祉事業に精通した者でなければなりません。また、理事・監事間には親族関係などの特別な関係がないこと、暴力団排除条例に抵触する者が役員になることはできません。理事の選任においては、社会福祉法人の運営に密接に関わる者は理事総数の3分の1を超えてはなりません。 これらの要件は、事前に配布された「社会福祉法人設立の手引き」で再確認してください。
1. 理事に関する要件と注意点
理事の選任にあたっては、いくつかの重要な点に注意が必要です。まず、当該法人に係る社会福祉施設の整備、運営と密接に関連する業務を行う者は、理事総数の3分の1を超えてはなりません。これは、特定の分野の専門家ばかりが理事にならないよう、バランスを保つための規定です。また、理事同士に親族等の特殊な関係がある場合は、その関係の有無とその内容(夫、妻、同一法人の役員等)を明確に記載する必要があります。これは、透明性を確保し、不正を防止するための措置です。さらに、横浜市暴力団排除条例第2条に定める者は、役員に就任できません。これは、社会福祉法人の健全な運営を維持するために不可欠な条件です。理事の職歴や社会福祉活動歴なども詳細に記載する必要があり、現職か元職かを明確に示す必要があります。これらの要件は、事前に配布された「社会福祉法人設立の手引き」の「第3 法人役員(理事・監事)、評議員の要件」で改めて確認してください。
2. 監事に関する要件と注意点
監事の選任においても、重要な要件が定められています。監事は2名以上選任する必要があり、そのうち1名は財務諸表等を監査できる者、もう1名は社会福祉事業について学識経験を有する者、または地域の福祉関係者(自治会、町内会、婦人会及び町内会等の役員を除く)を選任する必要があります。これは、法人の財務状況と事業運営の両面から監査を行うことを目的としています。監事は、他の役員と親族等の特殊な関係にあってはなりません。これは、監査の独立性と客観性を確保するために不可欠です。また、当該法人に係る社会福祉施設の整備、運営と密接に関連する業務を行う者も監事になることはできません。例えば、監事が所属する事務所が法人の決算業務等を受託することはできません。これらの要件は、監査の公正性を確保し、法人の健全な運営を支えるために重要です。
III.設立初期の財産と財産移転
**社会福祉法人設立(Shakai Fukushi Houjin Setsuriku)**の際には、設立初期の財産を明確にする必要があります。**財産目録(Zaisan Mokuroku)**には、土地、建物、運転資金などを記載し、その財産が法人へ適切に移転されたことを証明する書類(贈与契約書など)を提出する必要があります。 **贈与(Zouyo)**を受ける際には、贈与者からの残高証明書(原本)の提出が求められ、特に法人経費として既に支出済みの部分と、残りの贈与額を明確にする必要があります。 また、国や市からの補助金についても、その金額と積算内訳を明記した書類を提出する必要があります。財産移転完了後1ヶ月以内に、市長へ報告を行うことも必要です。
1. 設立当初の財産目録の作成
設立当初の財産目録は、様式4を参考に、必要に応じて適宜修正して作成する必要があります。特に重要なのは運転資金の確保です。法人の年間事業費の12分の1以上に相当する現金や普通預金などを有していることが必要とされます。ただし、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホームなど)を運営する法人や、介護保険法上の事業、障害者自立支援法等の支援費対象事業を主に行う法人の場合は、年間事業費の12分の2以上に相当する運転資金が必要になります。未建設の建物は記載せず、福祉医療機構からの借入金も負債として計上しない点に注意が必要です。印鑑は、印鑑登録証明書で確認できる実印を使用してください。設立代表者個人が法人へ寄付する場合、利益相反事項となるため、設立代表者の代理人を設立準備委員会等で選任し、委任状を提出する必要があります。不動産に関する記述も重要で、土地は1筆ごとに登記簿謄本記載の通りに記入する必要があります。
2. 不動産に関する書類の提出
不動産に関する書類としては、不動産目録(様式5)を作成する必要があります。施設整備関係で同様の書類を作成する場合は、それを流用しても差し支えありません。贈与契約書は寄附者ごとに作成し、枚数が多い場合は総括表を作成して添付します。法人事務所及び施設所在地を選挙区とする議員からの寄附は、公職選挙法に抵触するため認められません。現金の贈与を受ける場合は、贈与者の残高証明書(原本)を添付し、証明日はすべて同一の日付で取得する必要があります。残高証明書の枚数が多い場合は、総括表を作成して添付してください。施設用地の貸与を受ける場合、事業継続に必要な期間の地上権または賃借権を設定し、様式7~10を参考に作成、添付します。契約相手方全員の印鑑登録証明書原本も必要です。不動産に抵当権等がある場合は、権利者の解除承諾書を添付し、解除条件を具体的に記載する必要があります。既に事業を実施している場合は、契約内容承継の確認書(様式11)も作成・提出する必要があります。貸与を受ける不動産全てについて、全部事項証明書(原本)と、貸与地を縁取った公図を提出する必要があります。公図には地権者名も記入し、贈与地と貸与地は別色で示してください。
3. 財産移転報告
申請時に財産目録に記載した財産(土地、建物、運転資金、建設自己資金等)の移転完了後1ヶ月以内に、市長あてに報告を行う必要があります。この報告には、財産が法人に適切に移転されたことを証明する書類を添付する必要があります。土地や建物の贈与を受けて登記する場合、横浜市が発行する証明書により、登記時の登録免許税が免除されます。申請時の提出書類については、P13を確認してください。寄附予定額のうち、既に支出済みの法人経費(施設整備費等)を除いた残額の贈与を受けた後、法人としての領収書(寄附目的に応じて)を発行する必要があります。既に支出した経費分の支出経過表と領収書も提出が必要です。贈与契約書に定めた期間内に財産移転手続きを行い、寄附の受領については寄附金台帳(参考:別冊様式4)を作成する必要があります。
IV.その他重要な事項
申請書類作成にあたっては、様式例に記載されている注記は必ず削除してください。 申請書類は、A4ファイルに綴じて1部提出します。 印鑑証明書など小さい書類はA4用紙に貼り付けてください。 住所氏名は印鑑登録証明書に記載されている通りに記入してください。 **社会福祉法人(Shakai Fukushi Houjin)**の会計処理は、法律で定められた会計基準に準拠して行う必要があります。 **評議員会(Hyougi-inkai)**を設置する場合は、その旨を定款に記載する必要があります。施設を運営する法人は、1人以上の施設長を理事として加える必要があります。
1. 申請書類の一般的な注意点
申請書類を作成する際には、いくつかの一般的な注意点を守ることが重要です。まず、各様式例に記載されている(注)や、様式自体に含まれる不要な注釈などは、提出する際には必ず削除しなければなりません。これは、申請書類の簡潔さと正確性を保つためです。次に、申請に必要な証明書(身分証明書、印鑑登録証明書など)は、申請受理日の直近のものでなければなりません。申請書の提出から受理までには、修正が必要になるなど、日数を要する場合があります。そのため、証明書の取得時期については、念のため監査課に確認しておくことが重要です。書類のサイズは、可能な限りA4サイズに統一してください。小さい書類はA4用紙に貼り付けて提出しましょう。住所や氏名などの個人情報は、印鑑登録証明書に記載されている通りに正確に記入する必要があります。特に、似たような漢字(例:「沢」と「澤」、「斉」と「齋」)には十分注意しましょう。
2. 会計処理に関する事項
社会福祉法人を設立すると、法律で定められた会計ルールに基づき、法人独自の会計経理の決まり(経理規程)を定め、日々の会計処理、予算、決算を行う必要があります。 各法人で「経理規程」を作成し、理事会に諮る必要があります。その経理規程に基づき、実際の会計処理が行われます。資産の総額は、毎会計年度終了後には必ず変更登記を行う必要があります。法人の登記が完了したら、すぐに理事会を開催し、議事録を作成する必要があります。評議員会を設置する場合は、評議員会と理事会の承認を得て、基本規程(法人の運営に関する基本的な規程類)、設立年度の事業計画と予算、寄附財産の基本財産相当分の編入手続きなどを承認してもらう必要があります。認可書を受領したら、贈与契約書に定めた期間内に手続きを行い、寄附金の受領については寄附金台帳を作成する必要があります。
3. その他の留意事項
申請書類を提出する際には、申請書類全体をA4ファイルに綴じて提出する必要がある点に注意が必要です。また、提出書類の各項目(提出書類1~14)について、インデックスなどを用いて整理し、内容が分かりやすくする工夫も必要です。施設基準等により施設長資格が不要な場合は、就任承諾書のみ作成すれば済みます。 施設長予定者の履歴書は、上記10で添付している場合は、再度添付する必要はありません。基本財産編入誓約書(建物)(様式20)を作成し、施設長資格を取得している場合は資格取得状況がわかる関連書類の写しを添付します。未取得の場合は、施設長研修の受講に関する確約書(様式21)が必要です。施設長資格及び施設長研修については、事業所管課に確認してください。補助金積算表は任意の様式で構いませんが、施設建設計画書の根拠となるものでなければならず、項目、金額の整合性を確認する必要があります。評議員の定数は、理事定数の2倍を超える人数(理事の定数×2+1以上)としてください。
