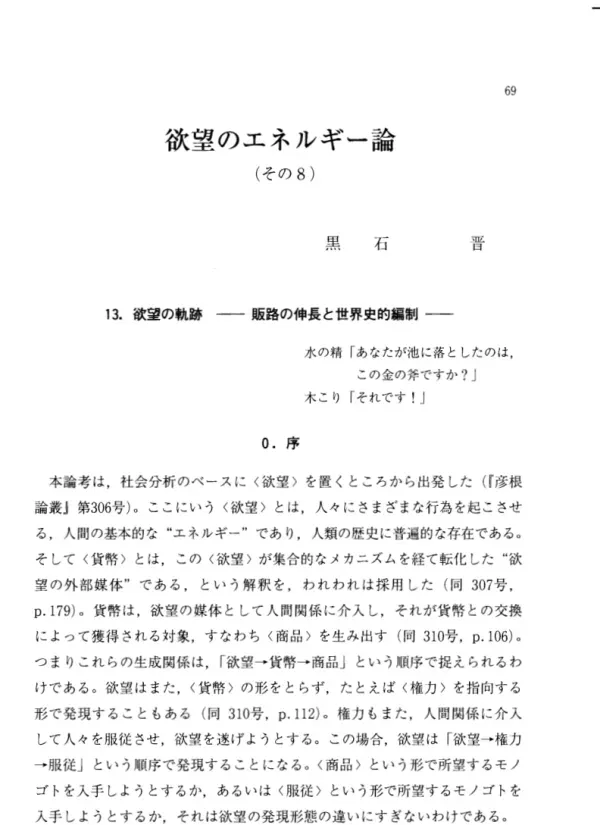
欲望エネルギー論:金銀比価と世界史
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 766.36 KB |
概要
I.古代の貨幣と金銀比価 リュディアからローマ帝国へ
本論文は、貨幣の歴史、特に金銀比価の変遷と経済発展の関係を分析しています。古代リュディアにおける貨幣の「発明」から始まり、ダレイオス比(クロイソス=ダレイオス比とも)がオリエント全域に広まった過程、そしてギリシャ諸邦やローマ帝国における貨幣制度の展開、デナリュス銀貨の登場とスタテル金貨との関係などを概観します。古代エジプトにおける金の利用や、秤量貨幣から計数貨幣への移行についても言及しています。 重要な人物としては、クロイソス王、ダレイオス1世、アレクサンドロス3世などが挙げられます。
1. リュディアにおける貨幣の発明とエレクトラム貨
本文書は、リュディアにおける貨幣の起源を考察するところから始まります。エレクトラム貨幣は、しばしば天然に産する金銀合金として理解されてきましたが、地質・鉱物学の観点から、リュディアで豊富だった砂金に意図的に銀を混ぜて鋳造された可能性が高いと指摘されています。これは、金銀比価の発生を意図的に回避し、貨幣基準の金銀分裂を防ごうとした為政者の策略であった可能性が示唆されています。ヘロドトスの記録が、リュディアの砂金の存在を裏付けている点も重要です。 このエレクトラム貨の分析を通じて、初期の貨幣制度における金銀比価の管理と政治的意図が読み取れる点が注目されます。貨幣が単なる交換手段を超え、政治・経済システムを支える基盤であったことが示唆されています。
2. ダレイオス比と金銀比価の安定性
リュディアの貨幣制度を受け継いだダレイオス1世は、グレイコス金貨とシグロス銀貨を鋳造し、商業振興と税制整備を進めました。この際に確立された金銀比価(ダレイオス比、またはクロイソス=ダレイオス比)は、その後2000年以上にわたって、ヨーロッパからオリエントにかけて理念上の基準として維持されました。これは、金銀比価における驚くべき安定性(固定相場制)を示す歴史的事実として重要視されています。 アレクサンドロス3世の治世におけるギリシャ・ヘレニズム時代(スタテル金貨とドラクマ銀貨)、そしてローマ共和国・帝国(アウレウス金貨とデナリュス銀貨)でも、このダレイオス比が継承され、その影響力の大きさが強調されています。新大陸からの大量の銀流入による価格革命まで、この比価が維持されたという事実が、金銀比価の安定性と歴史的意義を浮き彫りにしています。
3. ローマ共和国の貨幣制度とギリシャの影響
ローマ共和国の貨幣制度は、先住民エトルリア人の銅の秤量貨幣(アス)に起源を持ちますが、広く通用するにはギリシャのドラクマ銀貨を模倣する必要がありました。 紀元前269年、ローマ最初のオリジナル銀貨であるデナリュスが鋳造され、アスはデナリュスの下位単位となりました。アテネの良質な銀山(ラウレイオン)と、その銀貨の信用力は、地中海世界のみならずヨーロッパ内陸部にも影響を及ぼし、ケルト人がギリシャ貨幣を模倣した模造貨を大量に鋳造した事実からも、ギリシャ貨幣制度の広範な影響力が確認できます。 ローマの貨幣制度は、その信用を確立するために、既存の有力な貨幣制度を模倣したという点が興味深い考察の対象です。この模倣という行為が、ローマの経済・政治的発展にどう貢献したのかという視点が重要となります。
4. ギリシャ諸邦とローマ帝国における貨幣経済と政治
リュディアの影響を受けたギリシャ諸邦は、共通の重量基準(スタテル金貨とドラクマ銀貨)に基づく貨幣制度を持ち、高度な貨幣経済を発展させました。しかし、権力者による悪鋳は、ローマ帝国の貨幣制度を徐々に疲弊させました。ネロ帝やカラカラ帝による悪鋳、そして3世紀のディオクレティアヌス帝時代の銀貨の劣化などは、その例として挙げられています。 この悪鋳と、グレシャムの法則による幣制の混乱は、ローマ帝国の政治的・経済的疲弊と軌を一にしています。 ギリシャ諸邦における共通通貨の不在と、ローマにおける悪鋳の問題は、貨幣制度の安定性と政治的権力の関係を示す重要なケーススタディとなります。 権力者の恣意的な政策と、その経済への影響を分析する上で重要なセクションとなっています。
II.中世ヨーロッパにおける貨幣経済の変容と東方との交易
古代都市の衰退に伴い縮小したヨーロッパの貨幣経済は、東方との交易、特にアラビア商人やビザンツ帝国との関係を通して徐々に回復していきます。ビザンツ帝国のソリドゥス金貨や、フィレンツェのフローリン金貨、ベネチアのダカッット金貨といった金貨の復活が、商業の復興と結びついています。この時代、西欧における貨幣は品質が低く、領主や修道院による恣意的鋳造が横行していました。 アンリ・ピレンヌの商業史研究も重要な文脈として取り上げられています。
1. 西欧中世における貨幣経済の衰退とアンリ ピレンヌ
西欧の中世においては、古代都市の衰退と商業の縮小に伴い、貨幣経済も縮小傾向を示しました。アンリ・ピレンヌの指摘するように、メロヴィング期以降は金の不足傾向が顕著になり、カロリング期には長期にわたって金貨が消滅、低品質の小額銀貨が細々と流通する状況が続きました。この時代の西欧は、アラビア商人やビザンツ帝国との交易を除けば、世界商業史の縁辺に置かれていたと言えるでしょう。信頼できる取引を行うためには、ビザンツ金貨(ソリドゥス)の信用に頼るしかありませんでした。アヴァール族、ブルガール族、ノルマン人などの活動も、ビザンツやアラビアとの接触による経済的繁栄がもたらしたものであり、当時の西欧とオリエントの経済力の違いを如実に反映しています。 この記述から、西欧における貨幣経済の停滞と、ビザンツ帝国を中心とする東方経済圏との依存関係が読み取れます。
2. 東方交易と金貨の復活 フローリンとダカット
13世紀を過ぎた頃、十字軍遠征などを契機に東方との接触機会が増えた西欧諸都市では、商業の復活(ピレンヌ)とともに金貨が復活しました。フィレンツェで1252年に初鋳されたフィオリーノ金貨(フローリン、のちグルデンないしギルダーとも呼ばれる)と、ベネチアで1280年頃に初鋳されたツェッキーノ金貨(のちダカット)が代表的です。初期においては、両者とも理論上7リブラ(£=リラ=ポンド)に相当する高額金貨であり、プロの商人が使用するものでした。これらの金貨の出現は、大規模商業の再来を象徴し、社会的「欲望」の拡大期が到来したことを示しています。これらの金貨は、イタリア諸都市がビザンツやアラビアなどとの東方交易からもたらしたものであり、ビザンチン帝国経由でローマ末期からのソリドゥス金貨の系統を引くものでした。 フローリンとダカットは、後の西洋貨幣の原型となり、現代の貨幣制度にまで繋がっていることが示唆されています。
III.新大陸からの銀流入と価格革命 金銀比価の地理的濃度勾配
新大陸からの大量の銀流入は、ヨーロッパで価格革命を引き起こし、金銀比価に大きな影響を与えました。増井経夫の研究を引用し、中国における銀への強い欲望と、その結果として生じた金銀比価の地理的濃度勾配について説明します。 スペインにおける銀山の発見と精錬技術の進歩、フッガー家のような豪商への影響なども重要なポイントです。 金銀比価の地域差は、ヨーロッパ商人によるアジアへの交易を促進する要因となりました。
1. 新大陸からの銀流入と価格革命
新大陸における銀山の発見と精錬技術の進歩により、大量の銀がスペインに輸入され、スペインの繁栄を支えました。しかし、この大量の銀流入はヨーロッパにおいて急激な物価上昇、いわゆる価格革命を引き起こしました。この価格革命は、金銀比価の変動という歴史的事例として重要視されており、特に金銀比価を欲望の基準としていた人々にとって死活問題となりました。 この銀の大量流入は、南ドイツのフライブルク銀山などに依存していたフッガー家のような豪商にも影響を与え、衰退を招いたという事実も指摘されています。新大陸からの銀流入が世界史に与えた初期の影響として、この豪商の衰退が挙げられています。 このセクションでは、新大陸からの銀流入がもたらした経済的・社会的な激変と、その世界史的な影響が論じられています。
2. 金銀比価の地理的濃度勾配と東西交易
新大陸からの銀流入は、世界規模で金銀比価の濃度勾配を形成しました。増井経夫の研究を引用しながら、ヨーロッパからアジアにかけての金銀比価の地理的分布と歴史的推移が説明されています。 ヨーロッパでは、ダレイオス比やスペイン人の活動とは無縁の地域も存在し、それゆえに世界的な金銀比価の濃度勾配が形成されたと分析されています。 メキシコやペルーが銀本位制からなかなか離脱できなかったのも、この濃度勾配が背景にあったとされています。 17世紀のイギリスの記録には、銀が西から東へ流れ、中国で最も高価になっている様子が記されており、この地理的濃度勾配が、ヨーロッパの商人によるアジアへの交易を推進する力になったことが示唆されています。
3. 中国における銀への欲望とヨーロッパの戦略
中国において金がリカード的な意味で比較優位にあったわけではなく、単に金の相対的比価が安かっただけです。これは、中国人が西欧人以上に銀を歴史的に「欲望した」という事実に起因するとされています。 これは「国民性」という集合的メンタリティの問題であり、本来経済とは関係がないとされています。しかし、西欧人はこの偶然を「合理的に」利用し、経済現象へと転化させました。 この中国人の銀に対する強い欲望を、ヨーロッパ人が逆手に取ったことが、後の世界史に大きな影響を与えたとされています。 江戸時代の日本における金1銀4の比価も、この金銀比価の地理的濃度勾配と関連づけて論じられています。 このセクションでは、金銀比価の地域差と、それを利用したヨーロッパの戦略が分析されています。
IV.重商主義と産業革命 欲望と経済行動の連鎖
ヨーロッパ諸国は、アジア諸国(特に中国)との交易において重商主義的な政策を展開しました。 アヘン貿易や列強による中国の半植民地化は、この欲望と金銀比価の変動に関連づけられます。 一方、銀の大量流入によるインフレや、金銀比価の変動は、ヨーロッパにおける産業化を促す要因となりました。アダム・スミスらの古典派経済学の台頭も、この時代の経済的・社会的な変化と深く関連しています。 欲望の高揚と解放のサイクル、そして技術革新が、歴史の転換点として強調されます。
1. 重商主義的行動と 囚人のジレンマ
銀本位制のアジア・アフリカ諸国(特に中国)への銀流入は、リカード機構に従い、国内で貨幣として機能しインフレを招きました。これは遅れてきた価格革命と言えるでしょう。銀建て資産が目減りし、人々の生活は疲弊しました。ヨーロッパ諸国は、新大陸からの銀流入で国内の銀が余剰となった場合、それを国外へ、できれば銀を高く評価し金を安く入手できる国へ送る必要がありました。ヨーロッパ国内では銀が高く金が安い方が有利だったからです。この状況は、囚人のジレンマのような状況を生み出し、ヨーロッパ諸国は、重商主義的な政策を維持することの困難さを認識していました。 このセクションは、重商主義政策下におけるヨーロッパ諸国のジレンマと、その解決策を探るための論理的な枠組みを提示しています。
2. 重商主義の打開策としての産業化
ヨーロッパ諸国間の国際決済手段は伝統的に金(デュカット金貨など)であり、商人たちは金銀比価に敏感に反応していました。新大陸からの銀流入は、この状況に変化をもたらしました。 ヨーロッパ、特にイギリスにおける産業革命は、高揚した欲望が自由に発現できる媒体としての貨幣を得ながらも、一時的に重商主義的閉塞状況に陥った結果、その閉塞状況を打開するために新たな発明を行い、それが欲望を再び解放するという「自己増幅のサイクル」を生み出したからだと解釈できます。 このサイクルには貨幣需要の増大が伴っていました。 一方、中国では欲望が専制君主への指向性を持っていたため、そのような欲望の高揚と解放のサイクル、そして産業化は起こらなかったとされています。
3. アヘン戦争と列強の中国進出 重商主義の継続
19世紀初頭のイギリスにおける銀高を契機としたアヘン貿易、そして19世紀末の銀安を契機とした列強の中国進出は、重商主義が行動として継続していたことを示しています。 ヨーロッパ人の欲望は、銀高であれば中国から銀を奪い、銀安であれば銀を押し付けて代わりに金やモノを奪うという形をとっていました。 イギリスは、アフリカの黄金海岸から大量の金を得てギニー金貨を発行しましたが、中国茶への欲望から銀本位制の中国への銀の支払いに苦慮し、アヘン貿易に手を染めました。 1752~1816年のイギリスにおける大型銀貨「クラウン」の発行停止は、銀の流出傾向と金本位制への移行を促進する要因となりました。 このセクションでは、重商主義的な行動がアヘン戦争や列強による中国進出という歴史的事件にどのように結びついているかを論じています。
4. 産業化と重商主義 そして古典派経済学
金本位制への移行によって不要になった銀の大量発生は、ヨーロッパにおける銀の暴落を招きました。特に19世紀後半の銀価暴落は甚大でした。 ドイツ、日本、アメリカなどの金本位制への移行、そしてシャーマン法の廃止などは、この銀価下落の要因として分析されています。 この銀価下落は、列強による中国の利権分割と半植民地化と時期が一致しており、国際政治経済に大きな影響を与えました。 重商主義は古典派経済学によって取って代わられたのではなく、重商主義の論理が経済行動のベースに貫徹しており、その上に産業主義が乗る形で古典派経済学が形成されたと解釈されています。 このセクションでは、重商主義と産業革命、そして古典派経済学の相互関係を歴史的視点から考察しています。
