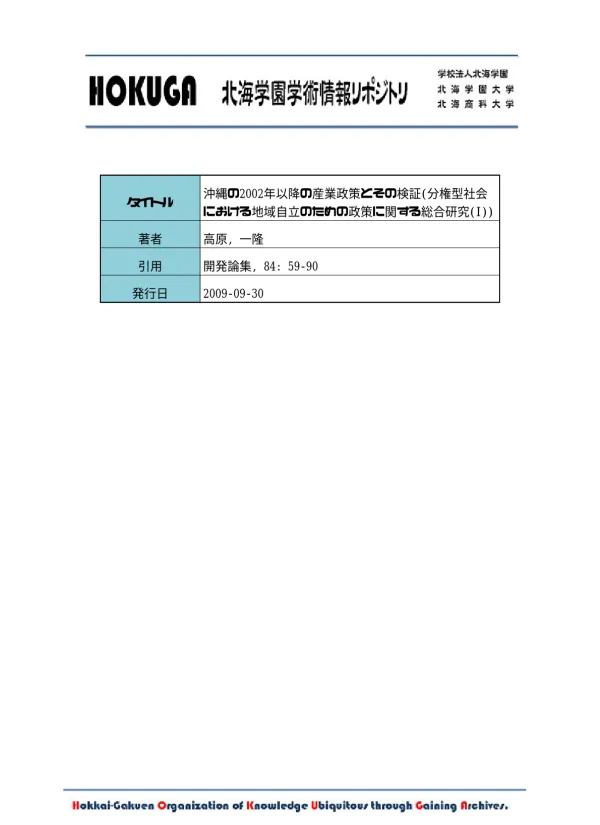
沖縄産業政策:検証と発展
文書情報
| 著者 | 高原 一隆 |
| 専攻 | 地域政策 |
| 文書タイプ | 研究論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 712.96 KB |
概要
I.沖縄の基地経済と経済構造
戦後沖縄経済は、米軍基地の存在(基地経済)に大きく依存してきた。特殊な為替レートや軍用地料による「不労所得」が、輸出産業の発展を阻害。1995年の米兵少女暴行事件は、その後の産業政策に影響を与えた。沖縄経済は、一次産業比率1.8%、二次産業比率12.1%、三次産業比率70.3%と、三次産業、特に観光産業と公共事業への依存度が高い。基地経済の割合は減少傾向にあるものの、依然として重要な要素である。
1. 基地経済の構造と沖縄経済への影響
沖縄経済は、米軍基地の存在(基地経済)によって大きく影響を受けてきた。この基地経済は、米軍基地という「ムチ」と、それに対応する政府の財政支出という「アメ」という構造で特徴づけられる。戦後、特殊な為替レート設定により、米軍は沖縄統治と基地建設の両方を効率的に進めることができた一方、沖縄経済は輸出産業を育成しにくい構造に陥った。軍用地料という特殊な不労所得が基地経済の構成要素となり、一方では基地の存在による物理的・精神的被害も無視できない。特に、1995年9月の米兵による少女暴行事件は、その後の沖縄の産業政策に大きな影響を与えた象徴的な出来事と言える。基地経済は、軍人・軍属の消費支出、軍雇用者所得、軍用地料から構成され、1972年の返還直後は県外受取の19.4%、県民総所得の15.5%を占めていたが、2005年にはそれぞれ9.2%、5.5%に減少した。しかし、軍用地料は現在でも基地関連収入の最大項目であり、多くの高齢者が主要な収入源としている現状も認識する必要がある。
2. 沖縄のマクロ経済概況と産業構造
2005年度の沖縄県内総生産は約3兆6千億円であり、全国最下位クラスではないものの、産業構造に大きな特徴が見られる。第1次産業比率は1.8%と低く、第2次産業比率は12.1%、第3次産業比率は70.3%と極めて高い。第2次産業の中でも、製造業は4.3%に対し建設業は7.6%と、建設業の割合が大きい。政府サービス生産者の割合は17.3%と、全国平均9.4%を大きく上回っており、これは就業者数にも反映されている。就業者59万人余りのうち、第1次産業就業者は5.1%、製造業は5.4%、建設業は11.5%、第3次産業は77.0%であり、建設業の就業者数の多さが際立つ。サービス業の中でも、観光産業と関連の深い飲食店・宿泊業の就業者は8.1%と全国平均を上回る。製造業よりも売上高、従業者数ともに多い建設業は、沖縄経済の成長を阻害する要因の一つであり、平成に入って建設投資額は減少傾向にある。公共投資が6割を占める建設業は公共事業削減の影響を大きく受けているにもかかわらず、建設業者の数は減少していないという現状も課題となっている。
3. 基地経済と3K産業への依存 現状と課題
沖縄経済は、政府からの財政移転と「3K産業」(危険、汚い、きつい)に大きく依存してきた。2005年の県外受取総額は2兆3,930億円余りで、そのうち国庫からの財政移転が約4割を占めていた。経常取引に限定すると、国庫からの財政移転は約4,000億円、財政から県外への資本移転は約1,000億円であり、これらを差し引くと約6,700億円の県外受取超過となる。公共事業も3K産業の一つであり、2007年の沖縄県の建設工事受注高2,139億円のうち、公共機関からの受注は1,401億円と約3分の2を占めている。しかし、公共事業は減少傾向にあり、基地関連経済もその比率を大きく下げてきた。基地返還と経済活性化の両立というジレンマの中で、将来的な経済発展のビジョンを描くことが重要な課題となっている。軍用地料は事実上の年金・小遣いとなっている高齢者も多く、産業創造を考える上で大きなポイントとなる。
II.沖縄の産業政策 現状と課題
沖縄の産業政策は、基地経済からの脱却と自立的発展を目指してきた。沖縄振興開発特別措置法に基づく計画では、観光・リゾート産業、情報通信産業、農業関連産業が戦略的産業として位置づけられている。しかし、経済特区(自由貿易地域、金融特区)の効果は限定的で、企業誘致は思うように進んでいない。情報通信産業は、IT津梁パークやGI X構築などのプロジェクトが進められているものの、高度人材の確保が課題。観光産業は成長しているものの、大型ホテルへの依存、環境問題、雇用リスクなど課題も多い。
1. 沖縄振興開発計画と産業政策の変遷
沖縄の産業政策は、米軍基地への経済依存からの脱却と自立的発展を目指して、幾つかの沖縄振興開発計画を経て変遷してきた。第一次(1972~1981年)と第二次(1982~1991年)沖縄振興開発計画では、基地依存経済からの脱却と自立的発展のための基礎条件整備が目標とされた。第二次計画では、糸満工業団地への工場誘致や中城湾新港地区整備、海洋博覧会を踏まえた観光・レクリエーション振興などが盛り込まれた。第三次計画(1992~2001年)では、自立経済の基礎条件整備に加え、国の発展に貢献する特色ある地域の整備が目標となった。しかし、これらの計画は、道路などのインフラ整備が中心で、具体的な産業振興策は限定的だった。観光振興基本計画(1976~2001年)が唯一の具体的な産業政策と言えるものであった。1996年には『国際都市形成計画』、翌年には『国際都市形成基本計画』が策定され、沖縄をアジア太平洋地域の流通中継基地と位置づけ、自由貿易地域の設定、情報通信関連産業振興、国際観光・保養基地形成などが戦略産業として挙げられた。
2. 経済特区制度の現状と課題 自由貿易地域 金融特区
沖縄振興特別措置法(沖振法)に基づき、3つの経済特区制度が導入された。まず、中城湾特別自由貿易地域(89.6ha)では、3,000㎡以上の用地を購入する製造業を対象に、法人税の35%所得控除、不動産取得税免除などの税優遇措置が講じられている。しかし、2008年時点でも誘致企業は限定的で、進捗度は低い。次に、金融業務特別地区(名護市全域)は、沖振法によって日本で初めて創設された制度であり、金融業および関連業務を行う者を対象に税優遇措置や雇用助成金などが提供されている。しかし、世界のタックスヘイブンと比較して課税率が高く、規制緩和も弱い点が課題である。知名度も低く、金融の中核機能を果たす企業の誘致は進んでいない。これらの経済特区制度は、新産業創設と地域経済活性化を目指した長期プロジェクトの一部であるが、期待されたほどの成果は上がっていない。
3. 情報通信産業と観光産業振興 現状と将来展望
沖縄の産業政策では、情報通信産業と観光産業が重要な戦略産業と位置付けられている。情報通信産業については、「沖縄マルチメディアアイランド構想」や「IT津梁パーク」などのプロジェクトが推進されている。IT津梁パークは、うるま市の中城湾新港地区に10万㎡の県有地を用いて、インキュベーション施設などを整備する大規模プロジェクトであるが、2011年度までに8,000人の雇用を目標としている。GI X(グローバルインターネットエクスチェンジ)構築事業も、沖縄経済を流通中継基地として発展させる戦略の一環であり、沖縄と香港を直接高速回線で結ぶ事業である。観光産業は、沖縄国際海洋博覧会以降、継続的に成長を続けているものの、近年はアメリカ発金融危機の影響を受けてホテル建設の中止・中断が相次いでおり、雇用リスクも発生している。将来の観光客1,000万人計画に向けては、質の高い観光、環境保全、地域経済への波及効果などを考慮した政策が必要とされている。
4. 産業クラスター政策と中小企業支援
1999年の新事業創出促進法と連動して『新事業創出促進法沖縄県基本構想』が策定され、沖縄では初めて起業・創業が産業政策の構成要素となった。これは、全国的な中小企業政策の大転換の流れを受けてのものであり、新規創業やベンチャー企業の創設が期待された。中小企業政策は、従来の社会政策的な対応から競争・選別政策へと変化し、創業支援、経営革新、新連携が柱となった。特に新連携は、中小企業が経営資源を補完し、高い付加価値を実現するための連携を支援する政策であり、2002年から始まった産業クラスター政策の根拠となっている。しかし、沖縄では産業展開が未成熟なまま新産業創出の政策体系に組み込まれた側面があり、創業後の事業継続支援や異業種ネットワーク形成などの総合的な支援は不足している。行政による継続的な情報提供や、専門家との協働による柔軟な支援体制の構築が求められる。
III.主要産業の現状と将来展望 観光と情報通信
観光産業は、2008年には観光客604万人、観光収入4,339億円を記録するなど成長を続けている。しかし、ホテル建設ラッシュと金融危機の影響で、ホテル事業の撤退や延期も発生している。将来の1,000万人計画に向けては、質の高い観光の推進と、環境保全との両立が求められる。情報通信産業では、コールセンターからソフトウェア開発へのシフトが進み、高度な人材需要が高まっている。IT津梁パークは、ソフトウェア開発の戦略拠点として期待されているが、人材育成とアジアとの連携強化が不可欠である。 (株)沖縄ソフトウェアセンター(OSC)は、中小企業のネットワークによる大型開発受注モデルとして注目される。
1. 観光産業の現状と課題 成長とリスクの両面
沖縄の観光産業は、沖縄国際海洋博覧会以降、右肩上がりの成長を続け、2008年には観光客数604万人、観光収入4,339億円を記録した。離島ブームなども追い風となり、多くの地域で観光客数が増加している。しかし、この成長は、格安パックツアーに依存する側面が強く、大手ホテル資本による大型ホテルへの依存度が高い。そのため、質の高い観光の追求や環境保全との両立が課題となっている。2006年頃から再びホテル建設ラッシュが始まったものの、2008年秋の金融危機により多くのホテル計画が中止・延期となり、雇用リスクも発生している。沖縄振興開発金融公庫の報告によると、2008~2012年のホテル投資額は計画・構想を含めると4,500億円に上ると予測されていたが、金融危機によりこの計画は大きく狂った。 ホテル建設による緑地減少や埋め立てによる生態系の混乱も、持続可能な観光・リゾート産業にとってのリスクとして指摘されている。将来の観光客1,000万人計画は、現状の大量消費型観光に依存しており、沖縄独自の付加価値を創出する戦略が必要とされている。
2. 情報通信産業の現状と課題 高度化と人材育成
沖縄の情報通信産業は、コールセンターなどを中心に成長してきたが、近年はソフトウェア開発が急増し、高度な人材需要が高まっている。地震が少ないという地理的優位性を活かし、BPOセンターとしても発展している。しかし、2000年頃までは労働コストの安価さを活かした単純作業の委託が多くを占めていたのに対し、2007年頃から付加価値の高い分野へのシフトが進んでいる。この高度化に伴い、高度な開発技術者やアーティストの人材不足が課題となっており、労働需要が供給を上回る状態となっている。IT津梁パークは、情報通信産業の戦略拠点として期待されており、ソフトウェア開発やコンテンツ制作分野への人材集積が重要となる。また、優秀な人材の確保とBPOセンター化を結びつけることで、企業の本社機能の一部を沖縄に移転させることも可能となるだろう。IT津梁パークの計画では、2011年度までに8,000人の雇用を目標としている。GI X(グローバルインターネットエクスチェンジ)構築事業も情報通信産業振興の重要な取り組みであり、沖縄と香港を直接高速回線で結ぶことで、海外との通信における東京経由の必要性を解消しようとしている。
3. 沖縄ソフトウェアセンター OSC の事例 協同戦略モデル
(株)沖縄ソフトウェアセンター(OSC)は、複数のソフトウェア開発会社のネットワークを背景に、大企業からの大型開発案件を受注する協同戦略モデルとして注目される。2002年設立の「フロンティアオキナワ21」を母体とし、IT関連企業21社、金融機関10社、県外関連企業14社が出資し、資本金2億5,350万円で設立された。県内企業は個々の規模が小さく、県外からの大型開発案件の受注が困難であったため、OSCは東京に営業拠点を設け、案件の受注から工程管理までを一括して行い、開発作業は各専門企業が分担するという仕組みをとっている。このモデルは、個々の企業の独立性を維持しながら、コア技術をネットワーク化することで、大型開発案件の受注を可能にし、企業の技術向上と雇用創出に貢献している。このOSCの取り組みは、21世紀型のグローバル競争に対応する、組織間ネットワークモデルの一つの成功例と言える。
IV.沖縄の産業政策におけるその他重要な取り組み
環境産業は、沖縄の地域資源を活用した持続可能な産業として期待されている。宮古島のバイオエタノール実験や、廃ガラス再資源化事業((株)トリム)などがその一例。しかし、資源量の制限やブランド維持の課題がある。健康バイオ産業も注目されており、モズク由来の成分の医薬品への応用研究などが進められている。沖縄科学技術大学院大学の設立は、世界最高水準の研究拠点を目指すが、財政支出や人材確保などの課題を抱えている。
1. 沖縄科学技術大学院大学 OIST の設立と課題
沖縄振興特別措置法(沖振法)に基づき、国際的に卓越した教育研究を行う大学院として設立された沖縄科学技術大学院大学(OIST)。ノーベル賞受賞者を理事長に迎え、世界最高水準の研究施設を目指している。当初は2005年開学を目指していたが、法案成立の遅れ、予算執行への批判、人材確保の難航、研究者報酬に関する問題など、様々な課題を抱え、2012年開学も不透明な状況にあった。2005年9月に(独)沖縄科学技術研究基盤整備機構が設立されたものの、野党からの予算執行への追及や人材確保の困難さ、トップ研究者の報酬問題などが指摘されており(朝日夕刊2007/10)、2008年11月28日付の沖縄タイムス記事にも無駄な財政支出ではないかという懸念が掲載されている。 OISTの設立は、沖縄の産業活性化に大きく貢献する可能性を秘めている一方で、その実現には、政治的な障壁や人材確保、財政問題など、多くの課題を乗り越える必要があることを示している。
2. 環境産業の取り組み 宮古島のバイオエタノールと廃ガラス再資源化
沖縄の環境産業は、地域資源や持ち込まれた資源を活用したサステイナブルな産業として注目されている。宮古島では、環境省の「宮古島バイオエタノール・アイランド構想」に基づき、石油販売会社が中心となり、島内で消費されるガソリンをバイオエタノールを3%混合したE3燃料に置き換える実験が行われている。年間24,000キロリットルの消費ガソリンのうち、島内のサトウキビで約700キロリットルのバイオエタノールを生産し、CO2削減とサトウキビ需要の増加を目指す。これは、地域産業再生のモデルケースとなりうる。一方、廃ガラス再資源化事業では、(株)トリムが廃ガラスを原料とした多孔質軽量発泡資材「スーパーソル」を製造・販売し、2004年に特許を取得、2006年には県産リサイクル製品として認定された。スーパーソルは、土木・建築、農漁業など様々な用途に利用可能である。同社は、スーパーソルの製造プラントの開発・販売も行なっており、全国11拠点に導入実績があり、水平的な連携によるビジネスモデルを構築している。しかし、島野菜やモズクなどの地域資源は量産が難しく、沖縄ブランド維持の課題も存在する。
3. 中小企業支援と産業クラスター政策 新事業創出促進法と連携
1999年の新事業創出促進法と連動した『新事業創出促進法沖縄県基本構想』により、沖縄では初めて起業・創業が産業政策の重要な要素となった。これは、全国的な中小企業政策の大転換を受けてのものであり、創業支援、経営革新、新連携が政策の柱となった。2005年4月には、中小企業新事業活動促進法が成立し、創業、経営革新、新連携を3本柱とする中小企業政策が明確化された。新連携は、中小企業が経営資源を補完し、高い付加価値を実現するための連携を支援する政策であり、2002年から始まった産業クラスター政策を支える重要な要素となっている。(財)沖縄県産業振興公社は、1971年の設立以来、中小企業への設備貸与や創業支援を行っており、1998年には企業化支援オフィス(インキュベーション施設)を開設し、IT関連企業の支援も実施している。しかし、創業後の事業継続支援や異業種ネットワーク形成支援などは、行政だけでは完結せず、行政と民間企業との連携強化が課題となっている。
V.まとめ 沖縄経済の自立的発展に向けて
沖縄経済は、基地経済からの脱却、観光産業と情報通信産業の持続的発展、そして環境産業や健康バイオ産業など新産業の育成が課題。経済特区などの政策効果を高め、高度人材育成、地域資源の有効活用、そして科学的な検証体制の構築が不可欠。官民連携による柔軟な支援体制の構築も重要である。
1. 環境産業の現状と課題 資源量とブランド維持のバランス
沖縄の環境産業は、サステイナブルな発展を支える重要な産業として位置づけられている。宮古島でのバイオエタノール・アイランド構想の実験は、地域資源であるサトウキビを活用し、ガソリンの地産地消を目指す試みとして注目される。年間24,000キロリットルのガソリン消費量に対し、島内のサトウキビから約700キロリットルのバイオエタノール生産を目指しており、CO2削減と地域産業の活性化に貢献する可能性を秘めている。一方、廃ガラス再資源化事業では、(株)トリムが廃ガラスを原料としたスーパーソルを製造・販売、再資源化プラントの開発・販売も展開している。スーパーソルは多様な用途を持つが、原料である廃ガラスは観光客による人工的な資源である点に特徴がある。しかし、島野菜、モズク、海ブドウなど、沖縄の地域資源は資源量が限られており、大量生産が困難である点が課題である。大量生産を可能にすると、沖縄ブランドの維持が難しくなるというジレンマを抱えている。そのため、地域商標制度の活用などによる少量生産・高価格維持の仕組みづくりが重要となる。
2. 健康バイオ産業の現状と課題 資源量と価格形成
沖縄の亜熱帯性気候を活かしたバイオ産業も、将来的な発展が期待される分野である。ウコンや薬草などの自生植物、モズクから抽出されたフコイダンやフコキサンチンなどの成分の医薬品への応用研究が進められている。県内企業や沖縄科学技術振興センター(旧亜熱帯総合研究所)などが中心となり、商品化に向けた連携研究が行われている。しかし、島野菜、モズク、海ブドウ、薬草など、資源量が限られているため、商品としての大量生産が困難である点が課題である。大量生産を可能にすると、沖縄ブランドが失われるというジレンマも存在する。もう一つの課題は販売における価格形成であり、地域商標制度の活用など知的所有権を駆使して、少量生産・高価格を維持する仕組みづくりや情報提供が重要となる。
3. 中小企業支援の現状と課題 事業継続とネットワーク形成
(財)沖縄県産業振興公社は、復帰直前から中小企業への設備貸与や創業支援を行ってきた。1990年代半ばからは企業化支援事業を本格化し、インキュベーション施設の開設やデジタルメディアセンターの設立など、積極的な取り組みを行っている。しかし、創業後の事業継続支援や異業種ネットワーク形成などの総合的な支援は十分とは言えない。特に、沖縄では事業開始後、技術面だけでなく経理や労務管理などの経営力を発揮できる環境が不足しているため、これらの支援が重要となる。行政は、支援可能な個人や団体、組織と企業を結びつける情報提供を継続的に行う役割を担うべきだが、計画策定や財政支出だけで役割を終えるのではなく、事業が持続可能なよう柔軟な支援体制を構築していく必要がある。これは、行政だけでなく、様々な専門分野のプロフェッショナルとの協働が必要となる。
