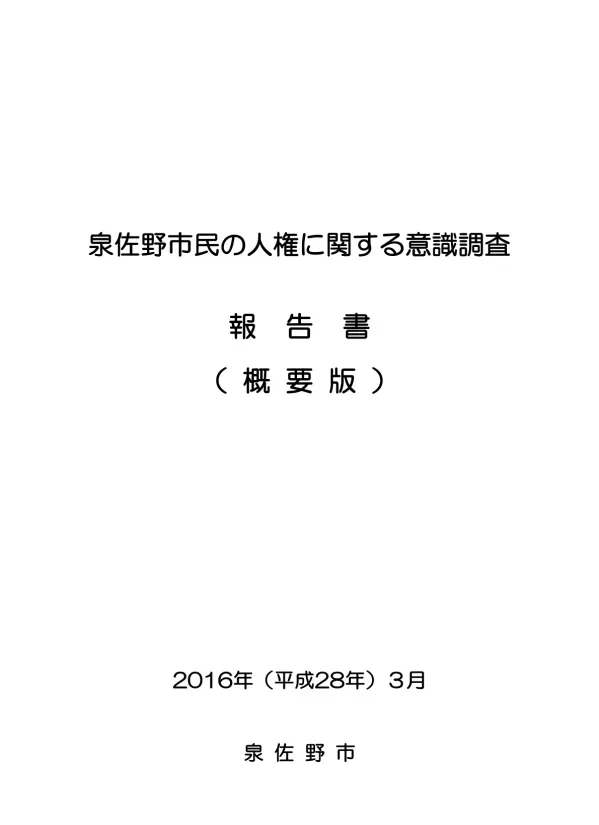
泉佐野市人権意識調査:市民の声と課題
文書情報
| 学校 | 泉佐野市 (Izumisano City) |
| 専攻 | 社会学, 人権学 (Sociology, Human Rights Studies) |
| 場所 | 泉佐野市 (Izumisano City) |
| 文書タイプ | 調査報告書 (Research Report) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.22 MB |
概要
I.泉佐野市における人権問題に関する市民意識調査 概要
本調査は、泉佐野市市民(母集団101,182人)の人権問題に関する意識を把握するため、アンケート調査を実施しました。調査対象は高齢者、女性、子ども、障害者、外国人、同和地区住民など多岐に渡り、それぞれの人権課題に関する認識や対応について分析しています。特に、同和問題、インターネット上の人権侵害、障害者差別解消法への認知度など、泉佐野市特有の課題についても調査しました。
1. 調査目的
本調査は、泉佐野市市民の様々な人権問題に関する意識の現状と傾向を把握することを主な目的として実施されました。その目的は、人権課題の解決に向けた施策の基本方針や実施計画の策定、そして市民への人権に関する教育・啓発のための基礎資料を提供することにあります。調査対象は、高齢者の人権問題、子どもの人権問題、女性の人権問題、インターネット上の人権侵害問題、同和問題、犯罪被害者の人権問題、戦争による人権侵害、エイズ患者等・ハンセン病(元)患者や難病患者の 人権問題、ヘイトスピーチ、刑を終えて出所した人およびその家族の人権問題、外国人住民の人権問題、性同一性障害の人権問題、性的指向の異なる人の人権問題、ホームレスの人権問題、アイヌ民族の人権問題など、幅広い人権問題を網羅しています。これらの多様な人権課題に対する市民意識を詳細に分析することで、より効果的な施策の立案と、市民参加型の啓発活動の実施を目指すことを目指しています。平成27年9月末現在の泉佐野市の住民数は101,182人であり、この母集団を対象に調査が行われたことが報告書から読み取れます。標本誤差を±5%以内に抑えるために、400名程度の回収サンプルが必要とされており、実際の回収数はこの基準を満たしているものと推察されます。
2. 調査方法と標本誤差
調査はアンケート調査を用いて実施され、回答者数から標本誤差が算出されています。報告書には、標本誤差の計算式と、信頼度95%における±5%以内という一般的な社会調査における許容範囲が記載されています。母集団である泉佐野市の人口(平成27年9月末現在:101,182人)と比較して、実際のアンケート回収数がどの程度であったかは明示されていませんが、標本誤差の算出結果が示されていることから、統計的に有意な結果を得るために必要なサンプルサイズが確保されていたと推測されます。図表のn(number of case)は設問に対する回答者数を、回答比率(%)は回答者数を100%として算出した数値であり、四捨五入の結果、内訳の合計と計が一致しない場合がある旨の記述があります。これらの説明から、調査結果の信頼性確保に配慮された調査設計であったことが分かります。 この記述は、調査結果の精度と信頼性を担保するための統計的な根拠を示しており、調査の客観性と科学的なアプローチを強調しています。
II.男女間の役割分担と人権問題
男女間の役割分担については、「状況に応じた分担」が最も支持されました。しかしながら、職場における男女差別(昇進・採用)、家事・育児の不平等な分担、女性の政治参加の遅れなど、多くの市民が人権問題を認識していました。セクシュアルハラスメントやマタニティハラスメントなども大きな課題として挙げられています。
1. 男女の役割分担に関する意識
仕事と家庭における男女の役割分担に関する質問では、「男性、女性で役割を決めずに、その状況に応じて分担する方が良い」という意見が36.1%と最も多く、次いで「男性、女性ともに働き、家事・育児も分担する方が良い」が27.0%、「保育所や介護サービス等を利用し、男女が協力する方が良い」が17.7%という結果でした。このことから、従来の固定的な役割分担からの脱却を目指す意識が一定程度存在する一方、現実的な課題への対応策も必要とされていることが示唆されます。 さらに、男性優遇と女性優遇の現状についての質問では、「男性が優遇されている」と回答した割合が高い項目として、「しきたりや慣習」「政治の場」「社会全体」「職場」が挙げられました。特に「しきたりや慣習」では70.7%と非常に高い割合を示しており、伝統的な価値観が男女間の不平等に影響を与えている可能性が示唆されます。一方で、女性優遇と回答した割合はいずれの項目でも1割未満と低く、女性が優遇されている状況はほとんどないと考えられます。これらの結果は、男女間の不平等な現状と、その改善に向けた意識の多様性を示しています。
2. 男女間で起きている人権問題
男女間で起きている人権問題に関する質問では、「職場において、採用あるいは昇進等で男女の扱いに違いがある」が52.9%と最も多く、次いで「家事・育児や介護など男女共同の社会の仕組みが整えられていない」が52.3%、「男は仕事、女は家事・育児など男女の固定的な役割分担意識がある」が44.4%、「議員や会社役員、管理職などに女性が十分に参画していない」が38.4%という結果でした。これらの回答は、職場における差別、家事・育児の負担の不平等、女性の社会進出の遅れといった、日本社会における男女間の深刻な不平等問題を反映しています。また、セクシュアルハラスメントやマタニティハラスメント、DV、ストーカー行為なども問題として認識されており、これらの問題に対する対策の必要性が強く示唆されています。回答結果からは、男女平等の実現に向けて、職場環境の改善、家事・育児支援制度の充実、女性の社会進出促進など、多角的な取り組みが求められていることが明らかになっています。
III.子どもの人権問題
子どもの人権問題として、いじめ(75.6%)、親による虐待(60.2%)、インターネット上のいじめ(49.7%)が深刻な問題として認識されています。虐待への対応としては、行政機関への通報が最も多く、市民の関心の高さがうかがえます。
1. 子どもに対する人権侵害の実態
調査では、子どもに起きている人権問題として、「いじめ」(仲間はずれ、身体的暴力、嫌がらせなど)が75.6%と最も高い割合を占めていました。これは、子どもを取り巻く環境における深刻な問題であることを示しています。 さらに、「親(保護者)による暴力、育児放棄、心理的虐待」が60.2%、「インターネット上の書き込みなどによる特定の子どもへの攻撃」が49.7%と、高い割合を示しています。これらの結果は、家庭内やインターネット上での人権侵害が、子どもたちの権利を大きく脅かしていることを示唆しています。その他の項目としては、体罰、子どもの意見を無視した大人の意見押し付け、児童福祉施設における不適切な処遇、登下校時の安全確保不足、買春・援助交際、教師による体罰、プライバシー侵害などが挙げられており、多様な角度から子どもの人権問題が認識されていることがわかります。これらの問題の背景には、親の育児能力不足、社会全体の意識の低さ、インターネットの悪用などが考えられます。
2. 子どもへの虐待への対応
身近な子どもが虐待を受けていることを知った場合の対応について尋ねた設問では、「市役所や児童相談所などの行政機関に連絡する」が65.8%と最も多く、次いで「子どもの様子を見る」が33.2%、「警察に通報する」が32.6%という結果となりました。この結果から、虐待に対する市民の関心の高さと、行政機関への通報を第一の対応とする傾向が見て取れます。しかし、一方で「子どもの様子を見る」という消極的な対応も一定数存在しており、虐待の早期発見・通報の促進に向けた啓発活動の必要性が示唆されます。 通報先として、行政機関に加え、警察、近所の人、自治会長・民生委員、児童相談所全国共通ダイヤル「189」、保育所・幼稚園・学校、祖父母・親族などが挙げられており、情報伝達ルートの多様性と、地域全体で子どもを守る意識の醸成が重要であることが分かります。虐待への対応は、迅速かつ適切な行動が求められるため、通報システムの充実や、市民への啓発活動の強化が課題として挙げられます。
IV.高齢者の人権問題
高齢者は、オレオレ詐欺などの経済的な権利侵害(56.2%)、施設における虐待(38.9%)、介護サービスの不足(37.1%)などの人権問題に直面していることが明らかになりました。バリアフリー化の遅れなども課題となっています。
1. 高齢者に対する人権侵害の実態
高齢者に起きている人権問題に関する質問では、「オレオレ詐欺や振り込み詐欺に狙われる」が56.2%と最も高い割合を占めていました。これは高齢者の経済的な脆弱性を突いた犯罪が深刻な問題となっていることを示しています。 次いで、「病院や施設、家庭等において拘束や虐待などがある」が38.9%、「特別養護老人ホームなどの介護や福祉サービスが十分ではない」が37.1%と、高い割合を示しています。これらの回答は、高齢者の尊厳を脅かす様々な問題が存在し、社会全体で対応していく必要があることを示唆しています。 さらに、バリアフリー化の遅れによる外出の困難さ、高齢者の能力発揮機会の不足、高齢者への軽視や意見の尊重不足、判断能力が低下した高齢者に対する経済的権利侵害、高齢者向け施設や製品の不足、スポーツ・文化活動への参加機会の不足なども問題として挙げられており、高齢者の生活全般にわたる課題が浮き彫りになっています。これらの問題の解決には、詐欺被害防止対策の強化、高齢者虐待防止対策の推進、介護サービスの充実、バリアフリー化の推進、高齢者の社会参加促進などが不可欠です。
V.障害者の人権問題
障害者に関する人権問題として、就労機会の不足(53.9%)、社会の理解不足(52.3%)、バリアフリー化の遅れ(37.8%)が大きな課題となっています。障害者差別解消法の認知度は低く(知らない76.9%)、啓発活動の必要性が示唆されました。
1. 障害者の人権問題に関する認識
障害者(児)に関する人権問題について、回答者の多くが課題を感じていることが示されました。特に、「就労機会が少なく、障害者(児)が働く職場環境整備が十分ではない」という意見が53.9%と最も多く、障害者雇用における社会全体の意識や制度の不足が浮き彫りになっています。 また、「障害者(児)の人権に関する人々の認識や理解が十分ではない」という意見も52.3%と高い割合を示しており、社会全体における障害者への理解促進の必要性を示唆しています。「道路や駅などのバリアフリー化が進んでいないため、外出しづらい」という意見も37.8%あり、物理的なバリアフリー化の遅れが、障害者の社会参加を阻害している現状が明らかになっています。これらの結果から、障害者の社会参加を促進するためには、雇用環境の整備、社会全体の意識改革、そしてバリアフリー化の推進が不可欠であることが示されています。 さらに、学校や地域における受け入れ体制の不足、精神科医療機関への偏見、結婚差別、差別的な言動、社会復帰の困難さ、医療環境の不足、学校・職場での不当な扱い、資格取得制限、詐欺被害、文化活動参加機会の不足なども問題として挙げられています。
2. 障害者差別解消法の認知度
平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の認知度については、「知らない」が76.9%を占め、「内容を知っている」はわずか3.7%という結果でした。この低い認知度は、法律の周知が不十分であることを示しており、障害者差別解消法の啓発活動の必要性を強く示唆しています。 法律の認知度が低いということは、障害者差別解消法の目的や内容が、社会に十分に浸透していないことを意味します。そのため、法律の周知徹底を図るための効果的な啓発方法を検討し、実施していく必要があります。 この調査結果から、障害者差別解消法の認知度向上に向けた具体的な対策、例えば、広報誌やウェブサイトなどを活用した情報発信、啓発イベントの実施、教育機関での啓発活動などが必要であることが示唆されます。また、法律の内容を分かりやすく簡潔に説明することで、より多くの市民に理解を促すことが重要です。
VI.同和問題に関する意識
同和問題に関する差別意識は弱まっているものの、依然として残っているという認識が多数を占めました。同和地区への居住を避ける割合は高く(56.9%)、その理由は生活環境の違いやトラブルへの不安などが挙げられています。同和問題の解決策としては、人権教育の充実が効果的とされています。
1. 同和問題に対する差別意識の現状
同和地区や同和地区の人々に対する差別意識の現状について尋ねた質問では、「差別意識は弱まっている」が48.9%と最も多く、次いで「差別意識は変わっていない」が23.4%、「差別意識はない」が20.3%という結果でした。この結果から、同和問題に関する差別意識は減少傾向にあるものの、依然として相当数の市民が差別意識の存在を認識していることが分かります。 同和地区出身者との結婚に関する質問では、「当然、子どもの意思を尊重する」が44.3%と最も多く、次いで「反対だが、子どもの意思であれば、仕方がない」が24.8%、「わからない」が20.3%という結果でした。「結婚に反対する」と回答した割合は7.2%でしたが、「反対だが、子どもの意思であれば、仕方がない」も含めると32.0%となり、依然として結婚への反対意見も存在していることが示唆されます。これらの回答から、同和問題に対する社会全体の意識は変化しつつあるものの、根強く残る偏見や差別意識への対応が、依然として重要な課題であることが示されています。
2. 住居選択における同和地区への忌避感
住居を選ぶ際に、人権的な問題を理由に物件を避けることがあるかという質問では、「同和地区の地域内にある」物件を避けるという回答が「避けると思う」26.2%、「どちらかといえば避けると思う」30.7%と高く、合計で56.9%に達しました。これは他の項目に比べて高い割合であり、同和地区への居住に対する忌避感が強いことを示しています。 住居の購入や入居を避ける理由としては、「生活環境や文化の違い、言葉の問題等でトラブルが多いと思うから」が48.7%と最も多く、次いで「治安の問題などで不安があると思うから」、「売却の際に不利になると思うから」、「自分も同じだと思われるのがいやだから」、「子どもの教育上、問題があると思うから」といった理由が挙げられました。これらの回答から、同和地区に対するネガティブなイメージや誤解が、忌避感の大きな要因となっていることが推察されます。 これらの結果は、同和問題が住宅問題にも深く関わっており、地域社会における共存・共生に向けた取り組みの必要性を示唆しています。
3. 同和問題解決のための効果的な施策
同和問題解決のための効果的な施策について尋ねた質問では、「学校教育・社会教育や企業内研修を通じて、広く人権を大切にする教育・啓発活動を行う」が「非常に効果的」と「やや効果的」を合わせた割合で50.3%と最も高く、次いで「同和地区と周辺地域の人々が交流を深め、協働してまちづくりを進める」が48.4%、「同和地区の人々がかたまって住まないで、分散して住むようにする」が43.9%という結果でした。 一方、「あまり効果的ではない」と「効果的ではない」を合わせた割合が最も高かったのは「差別を法律で禁止する」(47.0%)であり、「同和問題に悩んでいる人たちが、差別の現実や不当性をもっと強く社会に訴える」も高い割合を示しました。これらの結果から、教育・啓発活動による意識改革の重要性と、地域住民間の交流促進による共生社会構築への期待が示唆されています。同時に、法律による差別禁止だけでは不十分であり、より積極的な社会運動や地域レベルでの取り組みが効果的であるという認識も存在することがわかります。
VII.外国人住民の人権問題
外国人住民の人権問題としては、文化・宗教への理解不足(54.1%)、言語によるサービスアクセスの困難(37.5%)、就職差別(32.4%)、住宅差別(31.4%)などが挙げられています。
1. 外国人住民が直面する人権問題
外国人住民が直面する人権問題に関する質問では、「外国人の生活習慣や宗教・文化への理解や認識が十分ではない」が54.1%と最も高い割合を占めました。これは、文化的な違いに対する理解不足が、外国人住民の生活に困難をもたらしていることを示しています。 次いで、「日常生活で外国語の情報が少ないため十分なサービスを受けられない」が37.5%、「就職や仕事の内容、待遇などで、不利な条件におかれている」が32.4%、「外国人への偏見などで住宅を容易に借りることができないこともある」が31.4%という結果でした。これらの回答は、言語バリア、雇用差別、住居差別など、外国人住民が日常生活において様々な困難に直面していることを示しています。 さらに、日本語や日本文化に関する教育機会の不足、選挙権などの権利制限、結婚問題における周囲からの反対、入店拒否なども問題として挙げられており、外国人住民の社会参加を阻害する様々な要因が存在することがわかります。これらの問題への対策として、文化交流促進、多言語対応の充実、差別解消に向けた啓発活動、そして外国人住民への支援体制の強化などが不可欠です。
VIII.インターネット上の人権侵害
インターネット上での人権侵害として、誹謗中傷・差別表現(63.1%)、ネットいじめ(58.7%)、犯罪誘発(53.5%)などが深刻な問題として認識されています。
1. インターネット上の人権侵害の実態
インターネット上における人権侵害に関する質問では、「他人への誹謗中傷や差別を助長する表現を用いた情報を掲載する」が63.1%と最も高い割合を占めました。これは、インターネットが匿名性を利用した誹謗中傷や差別発言の温床となっていることを示しています。 次いで、「子どもたちの間で、インターネットを利用したいじめ問題が発生している」が58.7%、「犯罪を誘発する場となっている」が53.5%という結果でした。これらの回答は、インターネットが、いじめや犯罪といった深刻な人権侵害に利用されている現状を反映しています。 さらに、個人情報の不正な調査・取扱い・流出、わいせつ画像や残虐な画像などの有害情報掲載、個人情報流出による迷惑メールの増加、未成年者や家族の実名・顔写真の掲載、悪質商法の取引場としての利用なども問題として挙げられており、インターネットの利用に伴う様々なリスクが明らかになっています。これらの問題への対策として、インターネットリテラシー教育の推進、誹謗中傷や差別発言への厳格な対応、個人情報保護対策の強化、有害情報へのアクセス制限などが求められます。
IX.人権教育 啓発の必要性
市民の人権意識を高めるため、学校・家庭における人権教育の充実、相談窓口の周知、企業における人権尊重の推進など、多様な啓発活動の必要性が示されました。特に、分かりやすく親しみやすい啓発活動が求められています。
1. 人権教育 啓発施策に関する市民意識
人権尊重社会の実現に向けて、推進すべき人権教育や啓発施策に関する質問では、「学校・家庭等における人権教育を充実させる」が55.2%と最も高い支持を得ました。これは、人権教育の重要性を市民が広く認識していることを示しています。 次いで、「人権侵害を受けた人に対する相談窓口の広報・周知をはかる」が28.9%、「企業、事業所における人権尊重に向けた取り組みを支援する」が27.5%と、高い割合を示しています。これらの結果から、人権教育は学校だけでなく、家庭や職場にも広げる必要があり、相談体制の整備も重要であるという認識が市民の間で共有されていることがわかります。 その他、教員や行政職員の人権意識向上のための研修、公共施設等での人権教育・啓発の充実、行政による啓発活動の推進、人権に関する情報収集・提供体制の充実、住民や各種団体による人権尊重に向けた取り組みの支援なども支持を集めており、多様な主体による協働的な取り組みの必要性が示唆されています。これらの結果は、人権教育・啓発活動の更なる充実と多角的な展開が求められていることを明確に示しています。
2. 効果的な人権教育 啓発の方法
人権問題への理解を深めるための効果的な方法に関する質問では、「難しいテーマは参加しにくいので、親しみやすく分かりやすくする」が39.1%と最も高い支持を得ました。これは、人権教育・啓発において、内容の分かりやすさと親しみやすさが重要であることを示しています。 次いで、「市で行われる講演会、人権研修会や市のホームページ等を充実する」が22.4%、「形式にこだわらず、マンネリ化しないように内容を充実させる」が22.0%と、高い割合を示しています。これらの結果から、多様な学習機会の提供や、内容の工夫が重要であるという認識が市民の間にあることがわかります。 その他、テレビ・ラジオ・インターネット・新聞広告による啓発、職場での研修会・講演会・社内報の充実、同和問題を含む様々な人権をテーマにした学習機会の増設、若年層も参加しやすい工夫、体験活動を取り入れた人権教育、フィールドワークや当事者の話を聞く機会の増設、市民交流センターの地域交流事業の推進なども支持を集めており、多様な手法を組み合わせた啓発活動の必要性が示唆されています。これらの回答は、市民のニーズに合わせた柔軟な啓発活動の重要性を改めて示しています。
