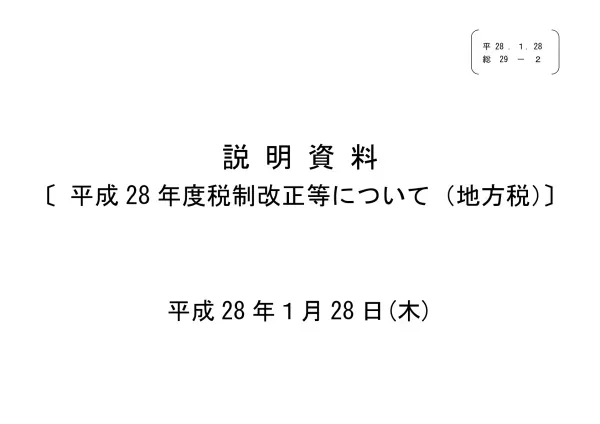
法人事業税軽減:外形標準課税拡大と税率改定
文書情報
| 学校 | 大学名(不明) |
| 専攻 | 税法、財政学など |
| 場所 | (不明) |
| 文書タイプ | 税制調査会資料 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 6.24 MB |
概要
I.外形標準課税の拡大と法人への影響軽減措置
本資料は、外形標準課税の拡大(2016年度:8分の5へ)に伴う法人への負担増問題への対応策を説明しています。特に、欠損法人や事業規模に比して所得が小さい法人の負担増加を軽減するため、3年間の負担軽減措置が講じられます。これは、法人税制改革の一環として、「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」という成長志向の政策に基づいています。法人事業税や法人住民税の税率見直し、所得割と資本割の課税標準のあり方など、地方税全般への影響も考慮されています。具体的な軽減策としては、外形標準課税の適用範囲や税率の調整、法人税実効税率の引き下げなどが挙げられます。
1. 外形標準課税拡大による法人負担増と軽減措置の概要
外形標準課税の拡大(2016年度: 8分の5)により、特に事業規模に比して所得が小さい法人や欠損法人が大きな負担増に見舞われることが懸念されています。この問題に対処するため、一定規模以下の法人に対して、3年間の負担軽減措置が講じられることになりました。この措置は、平成27年度税制改正で導入された負担変動軽減措置の拡充であり、成長志向の法人税改革の一環として位置づけられています。具体的には、課税ベースの拡大と税率の引き下げを同時に行い、法人税負担の公平性を図りつつ、企業の投資意欲を高め、賃上げを促進することを目的としています。平成27年度の税制改正では、欠損金繰越控除の見直し、受取配当等益金不算入の見直し、法人事業税の外形標準課税の段階的拡大などが行われ、その財源を確保しつつ、法人実効税率が34.62%から32.11%に引き下げられました。この軽減措置は、外形標準課税の拡大による急激な負担増を緩和し、企業の成長と雇用創出を支援することを目指しています。特に、地域経済を支える中小企業への影響を考慮し、慎重な対応がなされています。
2. 軽減措置の具体的な内容と法人税制改革の理念
軽減措置の具体的な内容は、事業規模が一定以下の法人に対して、外形標準課税による負担増を3年間軽減するというものです。軽減の割合や具体的な基準は、文書からは明確に読み取れませんが、企業の規模や収益状況などを考慮した上で、段階的な軽減措置が適用されるものと推測されます。この軽減措置は、単なる税負担の軽減だけでなく、企業の収益力拡大に向けた前向きな投資や継続的・積極的な賃上げを促すことを目的としています。これは、「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」という成長志向の法人税改革の理念に基づいており、法人課税の構造改革を通して、より広く負担を分かち合い、企業の競争力強化を支援するという政策目標を反映しています。 そのため、軽減措置は一時的なものではなく、長期的な視点に立った法人税制改革の一環として位置づけられています。 この改革によって、企業はより積極的な経営戦略を展開することが可能となり、ひいては経済全体の活性化に繋がることを期待しています。
3. 地方法人課税との関連と今後の課題
外形標準課税の拡大は地方法人課税にも影響を与えます。特に、大法人向けの法人事業税の外形標準課税は、平成27年度税制改正で平成28年度に8分の4とすることとされましたが、中堅企業への影響を考慮し、8分の5へと拡大されました。同時に、所得割の標準税率も引き下げられています。これらの措置は、地域経済への影響を十分に考慮した上で決定されていることが強調されています。しかしながら、文書からは具体的な数値や軽減措置の対象となる企業規模の定義までは明示されていません。 今後の課題としては、分割基準や資本割の課税標準のあり方、外形標準課税の適用対象法人のあり方について、地域経済・企業経営への影響を踏まえながら慎重に検討を進めていく必要があると述べられています。 これは、外形標準課税の拡大が、企業活動や地域経済に及ぼす影響を継続的にモニタリングし、必要に応じて制度設計を見直していく必要性を示唆しています。
II.地方法人課税の見直しと偏在是正
地方法人課税については、大法人向けの法人事業税の外形標準課税拡大の影響を踏まえ、分割基準や資本割の課税標準の見直し、外形標準課税の適用対象法人のあり方が検討されています。地域経済や企業経営への影響を考慮した慎重な検討が強調されています。また、地方法人特別税の廃止と法人事業税への復元、法人住民税法人税割の地方交付税原資化などが、地域間の税源の偏在是正と財政力格差縮小のための重要な施策として挙げられています。消費税率の10%への引上げも、これらの施策と密接に関連しています。
1. 法人事業税の外形標準課税の拡大と所得割の税率引下げ
地方法人課税においては、大法人向けの法人事業税の外形標準課税の拡大が主要な論点となっています。平成27年度税制改正では、平成28年度に外形標準課税の割合を8分の4とすることとされましたが、中堅企業への影響を考慮し、最終的には8分の5へと拡大されました。これは、法人事業税における課税ベースの拡大を意味し、企業の規模に比例した負担を求める政策です。同時に、所得割(地方法人特別税を含む)の標準税率が平成27年度の6.0%から平成28年度には3.6%に引き下げられました。この税率引下げは、外形標準課税の拡大による負担増をある程度相殺する役割を担っており、企業への影響を和らげるための措置と考えられます。 この課税標準の見直しは、地域経済への影響を考慮しつつ、公平かつ効率的な地方税体系の構築を目指したものです。特に、地域経済を支える中堅企業への影響を最小限に抑えるよう、慎重な検討が重ねられたことが文書から読み取れます。 しかしながら、この拡大と税率引下げのバランスが、全ての規模の企業にとって最適かどうかは、更なる検証が必要でしょう。
2. 地方法人特別税の廃止と法人事業税への復元
地方法人特別税は、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系が構築されるまでの暫定的な措置として導入されました。しかし、平成28年度改正では、地方法人特別税は廃止され、法人事業税に復元されることになりました。これは、税制の簡素化と効率化を目的としており、地方税体系の抜本的な改革に向けた重要なステップです。廃止に伴い、市町村の税収に影響が生じるため、経過措置として3年間の措置が設けられる予定です。具体的には、年度間の税収変動や偏在性の大きい市町村分の法人住民税法人税割の一部を、税収の安定化が図られてきた法人事業税の交付金に置き換えることで、市町村の税源の偏在是正と財政運営の安定化に寄与することを目指しています。消費税率10%段階においても、同様の偏在是正措置が講じられ、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小が図られる予定です。 この廃止と復元は、地方税体系の効率化と公平性の向上を目指す改革の一環として位置付けられます。
3. 今後の検討課題 分割基準 資本割 外形標準課税の適用対象法人
地方法人課税については、大法人向けの法人事業税の外形標準課税の拡大を踏まえ、分割基準や資本割の課税標準のあり方、外形標準課税の適用対象法人のあり方について、更なる検討が必要とされています。これらの検討においては、地域経済や企業経営への影響を十分に考慮することが重要視されており、慎重なアプローチが求められます。 具体的には、課税の公平性と効率性を両立させるためには、どのような分割基準や資本割の課税標準が適切なのか、また、外形標準課税を適用する法人の範囲をどのように設定すべきなのかといった点について、多角的な視点からの検討が必要です。 これらの検討結果に基づいて、より公平で効率的な地方税体系が構築されることが期待されます。 特に、地域経済への影響を最小限に抑えながら、地方公共団体の財政基盤を強化するための制度設計が求められます。
III.自動車関連税制の改革
消費税率10%への引上げに伴い、自動車取得税は廃止され、環境性能に配慮した環境性能割が自動車税及び軽自動車税に導入されます。これは、環境保護と税負担軽減の両立を目指した改革です。環境性能割の税率は燃費基準達成度に応じて決定され、税収の一部は市町村に交付されます。 グリーン化特例の延長や見直しも議論されています。
1. 自動車取得税の廃止と環境性能割の導入
消費税率10%への引上げ(平成29年4月1日)を機に、自動車取得税が廃止され、環境性能割が自動車税および軽自動車税に導入されることが決定されました。これは、自動車取得税のグリーン化機能を維持・強化し、環境性能に優れた自動車の普及を促進するための措置です。環境性能割は、燃費基準値達成度に応じて税率が決定され、新車・中古車ともに課税対象となります。税率は、非課税、1%、2%、3%の4段階を基本とし、営業車や軽自動車の税率については、当分の間、2%を上限とする予定です。免税点は50万円とされ、これは現行の自動車取得税と同様です。 環境性能割の導入により、自動車ユーザーは環境性能に配慮した車両を選択することで税負担を軽減できるインセンティブが与えられることになります。また、環境性能割の税収の一部は市町村に交付される制度が設けられる予定で、地方財政への影響も考慮されています。税率決定に用いる燃費基準値達成度などは、技術開発の動向や地方財政への影響などを踏まえ、2年ごとに 見直される予定です。
2. グリーン化特例の見直しと延長
自動車税および軽自動車税におけるグリーン化特例(軽課)は、平成27年度末で期限切れを迎えます。この特例は、環境性能に優れた自動車の普及を促進することを目的としていましたが、環境性能割の導入に伴い、その役割の見直しが行われています。具体的には、基準の切り替えと重点化を行った上で、1年間延長されることになっています。これは、環境性能割が導入されるまでの期間、環境性能に優れた自動車への優遇措置を継続することで、円滑な移行を支援することを目的としています。 また、自動車重量税に係るエコカー減税の見直しについても検討が行われており、燃費性能がより優れた自動車の普及を継続的に促す構造を確立することが目標です。燃費水準の年々の上昇を踏まえ、更なるグリーン化に向けた制度設計が求められています。この検討においては、原因者負担・受益者負担としての性格なども考慮されます。
3. 消費税率10 引上げ前後における駆け込み需要 反動減への対応と今後の検討
消費税率10%への引上げの前後には、駆け込み需要や反動減といった経済的な影響が懸念されます。自動車関連税制の改革においても、これらの影響を考慮した対応策が検討されています。具体的には、消費税率の引上げ前後における需要動向、自動車をめぐるグローバルな環境、登録車と軽自動車との課税のバランス、自動車に係る行政サービスなどを総合的に勘案し、自動車ユーザーの負担軽減、グリーン化、税制の簡素化などを図ることが目標です。 平成29年度税制改正においては、安定的な財源を確保し、地方財政に影響を与えないよう配慮しつつ、自動車の保有に係る税負担の軽減に関する総合的な検討が行われ、必要な措置が講じられる予定です。この検討は、環境性能割の導入による税制変更が、自動車市場やユーザーに与える影響を最小限に抑え、公平かつ円滑な移行を促すための重要なプロセスとなります。
IV.地方創生のための税制支援
地方創生を推進するため、企業版ふるさと納税(地方公共団体への寄附に対する税額控除)等の地方創生応援税制が導入されています。これは、地方公共団体への財源確保と地域経済活性化を目的としています。中小企業の設備投資促進のための固定資産税の特例措置も検討されています。
1. 地方創生応援税制 企業版ふるさと納税 の創設
地方創生を推進するため、地方公共団体が行う地方創生事業への法人寄附に対して、税制上の優遇措置が設けられています。これは「地方創生応援税制」あるいは「企業版ふるさと納税」と呼ばれ、地方公共団体が地方創生を推進する上で効果の高い事業に法人が寄附した場合、現行の寄附金の損金算入措置に加え、法人事業税、法人住民税、法人税から税額控除を受けることができます。寄附の下限額は10万円とされています。この制度は、企業による地方への貢献を促進し、地方公共団体の財政基盤強化と地域経済活性化を目的としています。地方版総合戦略に位置づけられた事業が対象となり、地方交付税の不交付団体かつ三大都市圏に所在する団体、企業の本社が立地する都道府県・市町村の事業に対する寄附は対象外となります。 この制度により、企業は社会貢献活動と税負担軽減を同時に実現できるため、地方創生への積極的な参加が期待されます。
2. 地域中小企業の設備投資支援のための固定資産税特例
地域の中小企業の設備投資促進を図るため、中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の制定を前提に、固定資産税の特例措置が設けられる予定です。中小企業者等が平成31年3月31日までに取得した、認定生産性向上計画に記載された一定の機械及び装置について、固定資産税の課税標準額を最初の3年間、価格の1/2とします。これは、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進し、地域経済の活性化に貢献することを目的としています。 この特例措置は、中小企業の負担軽減と同時に、生産性向上による経済効果の創出を期待した政策です。 ただし、中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の制定が前提条件となっているため、この法律の成立が特例措置の実施に不可欠となります。
V.その他重要な税制措置
その他、不申告等に対する加算金制度の強化、農地保有に関する課税の強化・軽減策などが盛り込まれています。 これらは、税制の公平性と効率性を高めるための施策です。
1. 不申告等に対する加算金の強化
税の不申告や仮装・隠蔽といった不正行為に対する罰則強化策が盛り込まれています。現状では、不申告等の回数に関わらず加算金の割合が一律であるため、意図的な繰り返し行為に対する抑止効果が限定的でした。そこで、悪質な行為を防止する観点から、過去5年以内に不申告加算金または重加算金を賦課された者が、再び同様の不正行為を行った場合、加算金の割合に10%を加重する措置が導入されました(平成29年1月1日施行)。これは、不正行為の再発防止を図り、税制の公平性を確保するための重要な措置です。 この措置は、独占禁止法や金融商品取引法における課徴金制度と同様の考え方を取り入れており、再犯に対する厳格な対応を示しています。仮装・隠蔽の場合の重加算金は45%と、高率なペナルティが課せられる仕組みとなっています。対象となる税目は、個人住民税(利子割、配当割、株式等譲渡所得割、分離課税に係る所得割)、法人事業税、たばこ税、ゴルフ場利用税など、申告納付方式の地方税(国税に連動するものを除く)です。
2. 農地保有に関する課税の強化 軽減
農地保有に関する税制では、課税の強化と軽減の両面からの対策が提示されています。まず、強化策として、農地法に基づく農業委員会の協議勧告を受けた遊休農地について、固定資産税の評価方法が変更されます。具体的には、平成27年度評価替えにおいて0.55とされていた正常売買価格に乗じられている割合を乗じないことで、課税が強化されます(平成29年度から実施)。これは、遊休農地の有効活用を促進し、農業生産性の向上に繋げることを目的としています。一方、軽減策として、所有する全農地に農地中間管理事業のための賃借権等(設定期間10年以上)を新たに設定した農地に対して、固定資産税の課税標準の特例措置が創設されます。最初の3年間は価格の1/2、賃借権等の設定期間が15年以上であれば最初の5年間は価格の1/2となります。これは、農地中間管理事業の促進を図り、農地の有効活用を支援することを目的としています。
