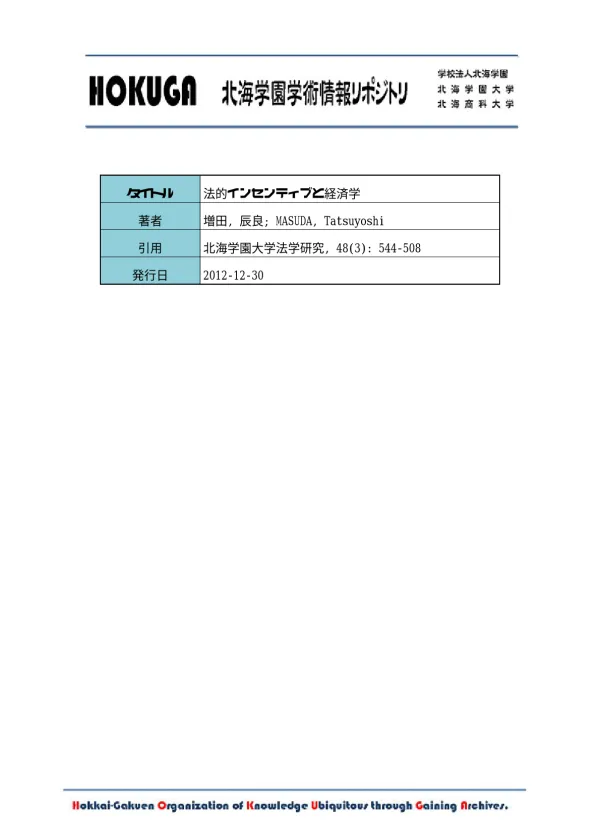
法的インセンティブと経済学:効率的資源配分へのアプローチ
文書情報
| 著者 | 増田辰良 |
| 学校 | 北研 |
| 専攻 | 法と経済学 |
| 文書タイプ | 研究ノート |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 599.68 KB |
概要
I.法の経済分析 資源配分とインセンティブ効果
本稿は、法と経済学(Law and Economics)の視点から、法が経済主体の行動に与える【インセンティブ効果】を分析する。特に、【資源配分】の効率性という観点から、様々な法制度の機能を考察する。市場経済では、競争がうまく機能すれば限界効用=市場価格=限界費用となり、資源は効率的に配分されるが、市場メカニズムの失敗を補正する役割を法が担っている。 【損害賠償制度】は、契約不履行時の損失を減らし、効率的な契約を促進する【インセンティブ装置】の一例として挙げられる。また、刑事罰や税制も、犯罪や経済活動への【インセンティブ】として機能し、【資源配分】に影響を与える。
1. 法改正と資源配分の関連性
市場経済における法の改正は、人、物、金、時間の資源配分に影響を与える。市場経済の根幹をなす法改正は、資源配分そのものを変更するのと同様の効果を持つため、法改正が人間や組織に与える効果を検証することが重要となる。この検証を通して、より望ましい立法や法改正の方法を理解できる。本稿では、法や制度が人間の意思決定に与える効果を検証した先行研究を紹介し、法的インセンティブと経済学の関係を考察する。法学と経済学は、事前・事後の人間行動を分析対象とする点で共通性を持つ一方、関心の置き所に違いがある。しかし、法をインセンティブ装置と捉えることで両者の共通点が見出せる。
2. 法のインセンティブ機能とゲーム理論
法は効率的な資源配分を達成する機能を備えている。簡単なゲーム理論を用いることで、法によるインセンティブ効果が説明できる。例えば、処罰や褒美という法の導入は、人間の利己的行動を抑制し、社会的効率性を高める。農民の行動を例に、法が経済主体の行動に影響を与え、社会的効率性を高める役割を担うことを示す。これは、インセンティブとして機能する法が、経済主体の行動を変え、社会全体の利益を増大させることを意味する。 この観点から、法の役割をインセンティブ装置として捉えることで、経済学を用いた法現象の分析が可能になる。
3. 経済学における価値判断と資源配分
経済学、特に厚生経済学は価値判断を重視する分野である。厚生経済学は、経済目的を達成するための手段の組み合わせを研究する学問であり、手段の選択には価値判断が伴う。 厚生経済学の目的の一つは、分配的正義(distributive justice)、つまり各人が能力に応じて報酬を受け取るような分配の公平性や資源の効率的な配分を実現することである。市場がうまく機能すれば、この状態が実現すると考えられる。 裁判における損害賠償は、被告から原告への所得移転、つまり資源配分の改善と捉えることができる。 これは、対価のない受動喫煙といった外部不経済を市場取引可能な財として内部化し、その対価を金銭で交換することで、矯正的正義を実現することと等価である。
4. 法の事前的 事後的資源配分機能
法の役割は、紛争発生後の事後的な資源配分の改善という理解が一般的だが、経済学の視点からは、訴訟費用のような事前設定によって経済取引を円滑化し、事前的な資源配分を改善する機能も有する。 経済取引において、債務不履行時の訴訟費用を事前に設定することで、債務者の返済を促すインセンティブ効果が生まれる。 弁護士費用などの取引費用を考慮すると、債務履行は経済学的に合理的な選択となる。 しかし、現実には不確実性があるため、利得や費用を確率計算して判断する必要がある。
II.損害賠償制度と効率的な資源配分
【損害賠償制度】は、不法行為による【外部不経済】を市場メカニズム内部に【内部化(internalize)】する機能を持つ。 ラムザイヤー(1990)の研究では、日本の交通事故訴訟における裁判利用率の低さを分析し、事前の情報入手可能性と和解の促進効果を指摘している。 訴訟費用を考慮した【経済的取引】の観点からも、損害賠償制度は事前的な【資源配分】機能を有し、経済取引を円滑化させることが示される。 契約における【完備契約】と【不完備契約】の比較を通して、損害賠償の取り決めが、不確実性下での効率的な契約履行を促す【インセンティブ】となることが説明されている。
1. 損害賠償制度の目的と機能
損害賠償制度は、単なる債務者の不利益救済手段ではなく、資源配分を効率化する重要な機能を持つ。不法行為に基づく損害賠償請求権を被害者に認め、負の外部不経済を市場メカニズム内部に内部化(internalize)することで、社会的に効率的な資源配分を達成する。これは、二者間の問題だけでなく、公害問題のように第三者へ影響を与える経済活動における不経済の解消にも有効である。 裁判過程は、市場におけるセリ人の役割を裁判官が担うと捉えることができ、資源配分メカニズムとして機能する。ただし、裁判官の客観性には限界があるため、市場メカニズムとの完全な一致は保証されない。
2. 訴訟費用と経済的取引
法の役割は、紛争発生後の事後的な資源配分の改善という見方だけでなく、訴訟費用といった費用負担を事前に設定することで、経済取引を円滑化し、事前的な資源配分を改善する機能も有する。 債務不履行時の訴訟費用を事前に設定することで、債務者(企業)に返済を促すインセンティブを与えることができる。 弁護士費用が15万円の場合、銀行は110万円を取り戻しても、融資しない場合の0より少ない利益(-5万円)となるため、融資しない選択をする。 完全情報下では、訴訟費用(罰)を操作することで経済主体の行動を変えるインセンティブを与えられるが、現実には不確実性を考慮する必要がある。
3. 損害賠償制度と効率的契約の促進
損害賠償制度は、契約不履行者への罰ではなく、契約を履行させるためのインセンティブ装置であり、モラルハザードを抑止する機能も持つ。 部品メーカーと親企業の委託生産契約を例に、不完備契約下での損害賠償の役割を分析。 不完備契約では、生産費用が親企業の留保価格を超えた場合でも契約を履行することで、非効率性が発生する。 損害賠償の取り決めは、契約時のモニタリングコストを削減し、不完備契約であっても効率性を高めるインセンティブを与える。期待損害賠償額は、契約履行時の親企業の利益額に等しく設定するのが合理的である。
4. 完備契約と不完備契約における損害賠償の効果
部品メーカーと親企業の委託生産契約において、生産費用に不確実性がある場合、完備契約と不完備契約を比較することで、損害賠償制度の効率性向上効果が示される。 損害賠償金を支払う場合と支払わない場合の取引価格と利益を比較すると、損害賠償金を支払う方が社会全体の利益が増加する。 これは、損害賠償制度が資源配分を効率的にする機能を果たしていることを示す。 取引価格は交渉ゲームを通じて決定されるため、最終的な価格水準は当事者間の交渉力に依存する。損害賠償金は、契約不履行によって発生する逸失利益や機会費用を補償する役割を果たす。
III.税制と経済主体の行動選択
【税制】は、地域間移動や就業形態選択といった経済主体の行動に影響を与える重要な【インセンティブ】要因である。Long(1982)とGoode(1949)の研究は、アメリカにおける税負担の地域間格差や、所得税率が就業形態選択に与える影響を示している。 高税率地域から低税率地域への【労働移動】、そして自営業と給与所得者の選択は、税制による【インセンティブ】によって左右される。 日本の場合も、新規開業白書(日本政策金融公庫総合研究所編, 2011)等のデータを参照しつつ、税制が事業形態選択に与える影響が分析されている。限界税率(MTR)や税負担額(RTAX)は、自営業を選択する【インセンティブ】としてプラスに作用することが示唆されている。また、解雇規制についても、裁判所の判決が企業の雇用姿勢に【インセンティブ】を与えていることが指摘されている。大竹(2004)らの研究は、解雇規制の強さと雇用率の負の相関関係を示唆している。
1. 税制と地域間移動
税制は、労働者の地域間移動に影響を与える重要な要因である。Long(1982)のアメリカにおける研究によると、地域や州によって税額(税率)が異なり、南部より北部、地方より都市部で税負担が高い傾向がある。この税負担の差は、労働者の地域間移動を促すインセンティブとして機能する。分析結果では、限界所得税率(MTR)の上昇や税負担額(RTAX)の増加は、純移動率を低下させる負の相関関係が確認された。特に近年、この負の相関関係は強まっている。例えば、限界所得税率が1%上昇すると、1970~77年には純移動率が約0.87%減少し、1960~70年の減少率(約0.78%)よりも大きかった。これは、税負担の高い地域から低い地域への移動が促されることを示している。
2. 税制と就業形態選択
理論的には、比例所得税は自営業者と給与所得者への影響が同じはずだが、現実には税制度が自営業を有利にする側面がある。Goode(1949)は、自営業者の税負担感が給与所得者より小さいことを指摘している。 アメリカでは、税制の変化が事業形態選択(個人経営か法人形態か)に影響を与えている。二重課税の問題や所得税と法人税の限界税率差の変化が、法人設立意欲や所得の移動に影響を与えたことが検証されている(田近・八塩、2005)。 日本の場合、限界税率(MTR)や税負担額(RTAX)の上昇は、自営業を選択するインセンティブとしてプラスに作用する。 一方、実質中位収入(WAGE)の上昇や製造業(MFG)、政府部門(GOVT)での雇用量の増加は、自営業を選択するインセンティブを減らす。これは、雇用環境が良い状況では、給与所得者になる傾向が強まることを示唆している。
3. 日本の税制と事業形態選択に関する研究
日本では、事業を興す個人の属性に関する研究は多い(忽那・安田編、2005;樋口・村上・鈴木他、2007;橘木・安田編、2006;日本政策金融公庫総合研究所編、2011)が、税制が就業地や就業形態の選択に与える効果を検証する研究は少ない。 アメリカにおける研究(Long 1982, Goode 1949)では、税額や税率の違いが労働者の地域間移動や就業形態選択に影響を与えていることが示されている。 例えば、アメリカの給与所得控除は、多くの個人事業主を法人成りさせるインセンティブとして機能していたと推定されている(田近・八塩、2005)。これは、税制が個人事業主の事業形態選択に影響を与えることを示す好例である。 また、公正取引委員会による団体規制強化は、事業者団体の生成数に影響を与えるインセンティブとして機能する。
IV.法の設計と運用 効率性を目指して
法は【矯正的正義】の実現という目的を持つが、その実現には【効率性】が重要である。Tullock(1980)の指摘を踏まえ、【インセンティブ装置】としての法を計量分析し、その知見を立法・法改正・法運用に反映させるべきである。 本稿で提示された様々な事例研究は、法の経済分析を通じて、より望ましい【資源配分】と【社会的効率性】を実現するための【インセンティブ設計】の重要性を示している。
