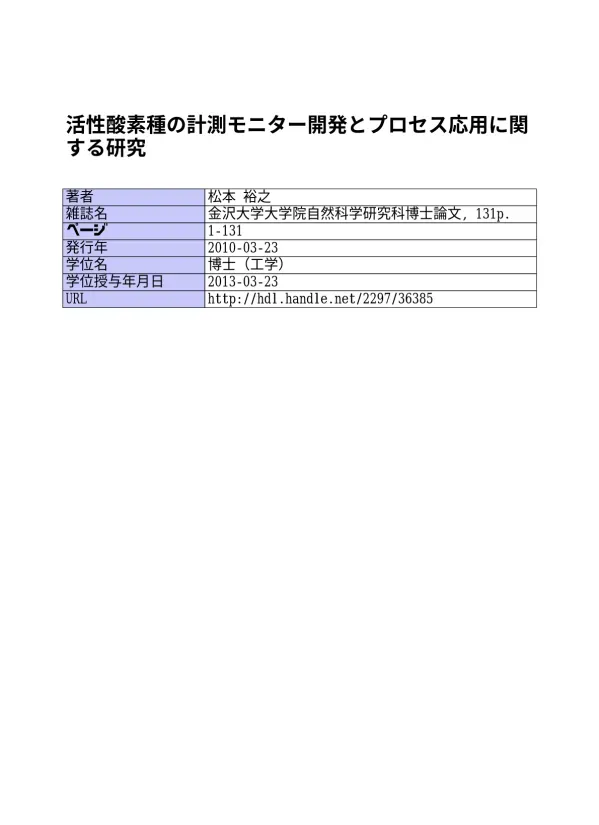
活性酸素種計測モニター開発
文書情報
| 著者 | 松本 裕之 |
| 学校 | 金沢大学大学院自然科学研究科 |
| 専攻 | システム創成科学専攻 知的システム開発講座 |
| 文書タイプ | 博士論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 5.63 MB |
概要
I.活性酸素種を用いた殺菌 滅菌および表面処理技術の研究
本研究は、医療機器の滅菌、半導体製造工程における表面処理、食品の殺菌・脱臭など幅広い分野で注目されている活性酸素種の生成、計測、応用に関する研究です。特に、プラズマ滅菌、UV殺菌、オゾン殺菌といった技術に焦点を当て、QCM(水晶振動子)を用いたリアルタイムモニタリングによる活性酸素種の定量化と作用メカニズムの解明に取り組んでいます。 既存の滅菌法である高圧蒸気滅菌法やエチレンオキサイド滅菌法の課題を克服する新たな技術として、過酸化水素低温プラズマ滅菌法の可能性を探っています。
1. 既存の殺菌 滅菌方法の課題と活性酸素利用の必要性
近年、世界的な感染症拡大を背景に、医療品、食品、空気、飲料水の殺菌・滅菌プロセスへの活性酸素利用が注目されています。従来の高圧蒸気滅菌法は、1880年代から主流ですが、熱に弱いプラスチック製品の処理が困難です。また、1950年代から使用されているエチレンオキサイド滅菌法は、発がん性ガスの安全性と除害処理が課題となっています。これらの問題点を解決するために、相良らによる過酸化水素低温プラズマ滅菌法が提案されています。この方法は、減圧チャンバー内でプラズマ化した過酸化水素を用いることで、高活性なヒドロキシラジカルを生成し、効果的な殺菌・滅菌を実現する可能性があります。さらに、半導体製造工程では、シリコン基板の洗浄や表面酸化、レジストアッシング、薄膜成膜といった様々なプロセスにおいて、活性酸素種が重要な役割を果たしており、その高い酸化力から、有機・無機系の基材表面洗浄や改質など、幅広い工業用途への応用が期待されています。食品や原材料の殺菌・脱臭においては、オゾンが古くから利用されており、オゾンガスやオゾン水が食品製造工程や貯蔵工程、包装材の殺菌に使用されています。近年では、紫外線による上水や下水の浄化も進んでおり、光化学反応で生成されたヒドロキシラジカルによる水中有機物質の分解処理や微生物の不活化などの研究開発が進められています。これらの背景から、本研究では、様々な分野で有効な活性酸素種を用いた新たな殺菌・滅菌、表面処理技術の開発を目指します。
2. 活性酸素種の計測 定量化に関する現状と課題
工業用途において、活性酸素の生成量とその作用量をリアルタイムでモニタリングする技術は未だ確立されていません。気相中の活性酸素のリアルタイム検出技術としては、レーザー誘起蛍光(LIF)法が挙げられます。小野らは、このLIF法を用いて、基底状態原子状酸素の数密度を計測する手法を確立しています。また、堀・後藤らは、真空紫外分光法を開発し、原子状酸素の数密度を求める方法を提案していますが、高価な装置が必要であり、大気中でのプロセスモニタリングには適用できません。田川らは、スペースチャンバーを用いて、レーザーデトネーションで生成した原子状酸素ビームを材料に照射し、劣化現象を評価する手法を開発しています。この手法は高感度で活性酸素の作用をモニタリングできる利点がありますが、実際のプロセス装置への応用は進んでいません。これらの既存手法の限界を踏まえ、本研究では、簡便で高精度な活性酸素種の計測・定量化技術の開発が重要な課題となります。特に、工業プロセスへの適用を考慮した、リアルタイムモニタリング技術の開発が求められます。
3. 低圧水銀UVランプを用いた活性酸素生成と表面処理
低圧水銀UVランプは、184.9nmと253.7nmのUV光を放射し、大気中の酸素分子と反応してオゾンや励起状態の原子状酸素(O(¹D))を生成します。このO(¹D)は高い反応性を持つため、基材表面の有機物を除去する表面処理に有効です。本研究では、市販のUVランプ(岩崎電気製 QGL90U-31)を用いて、銀薄膜付きQCM(Silver-QCM)の表面酸化反応を調べました。実験では、UVランプ照射時間による銀の酸化層の厚さ変化をX線回折(Rigaku製 Miniflex, Ultima-IV)、光電子分光(XPS)、走査透過型電子顕微鏡(STEM)を用いて評価しました。その結果、UV照射により銀表面に酸化銀層(Ag₂O)が形成されることが確認され、その厚さは照射時間に依存することがわかりました。また、オゾン濃度とUV照度の相関についても検討し、ランプ直下では原子状酸素による酸化が支配的である一方、離れた位置ではオゾンによる酸化が主であることを明らかにしました。これらの結果から、UVランプを用いた表面処理における活性酸素種の役割と、その生成メカニズムについて重要な知見を得ることができました。Inficon製XTCセンサヘッド、Sigma製Q-pod発振回路、東芝製CXW/47HWパソコンを用いて測定を行いました。
II.QCMを用いた活性酸素種検出技術の開発と評価
QCMを用いた活性酸素種の検出技術を開発し、その特性を評価しました。質量加算型と質量減算型のQCMセンサを開発、プラズマプロセス下での検出特性を調査し、励起一重項原子状酸素(O(¹D))などの高活性種の検出に成功しました。特に、銀電極QCMを用いた実験では、UVランプ照射による銀の酸化過程をX線回折、光電子分光(XPS)、**走査透過型電子顕微鏡(STEM)**を用いて詳細に分析しました。AFMを用いた表面形状解析も実施し、検出特性への影響を評価しました。また、周辺湿度環境の影響も考慮し、安定した測定を実現するための条件検討を行いました。
1. QCMを用いた活性酸素種検出の原理と既存技術の課題
本研究では、水晶振動子(QCM)を用いた活性酸素種の検出技術の開発と評価を行っています。QCMは、ナノグラムオーダーの質量変化を高感度に検出できることから、活性酸素種と反応による質量変化を計測することで、活性酸素種の定量化を目指します。しかしながら、従来の質量増加型QCMを用いた活性酸素検出では、検出飽和という問題がありました。そのため、本研究では、この問題点を解決するために、新たなQCMセンサの開発に取り組みました。具体的には、質量減算型および質量増加型検出層を積層したCarbon/Silver-QCMを新たに開発し、プラズマプロセス下での検出特性を詳細に調査しました。また、QCMを用いた測定においては、周辺湿度環境による素子表面への水分子吸着・脱離が測定値に影響を与える可能性があるため、その影響についても検討を行いました。At-cut水晶振動子を使用し、リードピン付きタイプとプラナータイプの2種類を用いて実験を行いました。セイコーインスツル製SPA300原子間力顕微鏡(AFM)を用いて、電極材料および表面状態が検出特性に及ぼす影響についても解析しました。北海道東科製の周波数カウンタを用いて、大気圧、25℃の条件下で相対湿度(R.H.)を変化させ、周波数変化を測定しました。
2. 新規QCMセンサの開発とプラズマプロセス下での特性評価
従来の質量増加型QCMの検出飽和問題を克服するため、質量減算型および質量増加型検出層を積層したCarbon/Silver-QCMを開発しました。この新規センサを用いて、プラズマプロセス下での活性酸素検出特性を評価しました。具体的には、プラズマ処理によるQCMの周波数変化をリアルタイムでモニタリングし、活性酸素種の検出感度や応答速度を評価しました。また、異なる種類の検出層(Silver層、有機系薄膜(ポリイミド)層)を用いたQCMセンサの比較検討を行い、それぞれ検出メカニズムの違いをXPS(光電子分光)やAFM(原子間力顕微鏡)等の分析手法を併用して明らかにしました。特に、Silver-QCMを用いた実験では、UVランプ照射による銀電極の酸化過程について、光学顕微鏡、X線回折、XPS、STEM(走査透過型電子顕微鏡)を用いた詳細な分析を行い、酸化銀層の構造や形成メカニズムを解明しました。Maxtek製SC-101水晶振動子、新島真空工業研究所製真空蒸着装置、田中貴金属製銀ワイヤ、高純度化学製W製ボートKA-5、SHIMAZU製CC-50カーボンコーター、東海カーボン製カーボンロッドを用いました。 JEOL製JPS-9010TR XPS装置、Cratos製AXIS-Ultra XPS装置を用いてXPS測定を行いました。また、Inficon製水冷式センサヘッド、Sigma製Q-pod発振回路、東芝製CXW/47HWパソコンを用いて測定を行いました。
3. 有機系薄膜付きQCMによる活性酸素検出メカニズムの解明
ポリイミド薄膜を成膜したQCM(PI-QCM)を用いて、誘導結合プラズマ下での原子状酸素検出特性と検出メカニズムの解明を行いました。高周波スパッタリング法により、6MHzの水晶振動子上にポリイミド薄膜を約75nmの膜厚で成膜しました。プラズマ処理後のPI-QCMの周波数変化と、XPS、AFMによる表面分析結果を総合的に解析することで、原子状酸素とポリイミド薄膜との反応機構を推定しました。その結果、原子状酸素はポリイミドのイミド基やベンゼン環に吸着し、シクロ付加反応を経て環が開裂し、最終的にCOやCO2といった揮発性有機物として脱離していくというメカニズムが示唆されました。この結果、PI-QCMは、原子状酸素によるポリイミド膜の分解を検出する質量減少型センサとして有効であることが示されました。Cratos製AXIS-Ultra XPS装置を用いてXPS測定を行いました。また、AFM測定を行い、表面状態の変化を評価しました。
III.プラズマプロセスにおける活性酸素種の生成と挙動のシミュレーション
誘導結合プラズマ(ICP)を用いたリモートプラズマ発生装置を試作し、モンテカルロシミュレーションによってプラズマ中の活性酸素種の空間分布と挙動を解析しました。特に、励起一重項原子状酸素(O(¹D))の生成密度と寿命を評価し、UV光照射条件下での表面反応への寄与を明らかにしました。OES(発光分光分析)によるプラズマ状態の計測を行い、シミュレーション結果との整合性を確認しました。 シミュレーションの結果、原子状酸素が支配的な活性酸素種であり、そのフラックスは約10¹⁸ /m²/secであることがわかりました。
1. プラズマシミュレーション手法とモデル
プラズマ状態の解析には、ラングミュアプローブ法や発光分光分析法が一般的に用いられますが、それぞれに限界があります。ラングミュアプローブ法はプラズマを擾乱し、広範囲な空間での計測が困難です。発光分光分析法は簡便ですが、測定精度が分光器の分解能に依存し、非発光励起種の同定ができません。そのため、本研究では、これらの限界を克服するために、モンテカルロシミュレーションを用いてプラズマ状態を解析しました。具体的には、市販のプラズマ気相反応解析ソフトPEGASUS®を用い、誘導結合プラズマ(ICP)における電子の衝突反応と中性粒子間の反応を考慮したシミュレーションを行いました。このシミュレーションでは、多数の粒子の位置、速度、内部状態を計算し、衝突や境界の影響を考慮することで、プラズマ中の各粒子種(電子、イオン、中性粒子)の生成密度分布とそのエネルギー状態を同時に得ることができます。シミュレーションは、流れ場をセルに分割し、同一セル内の粒子間の衝突を確率的に計算するDirect Simulation Monte Carlo (DSMC)法に基づいて行われました。セルの大きさは平均自由行程程度に設定され、セル内での物理量はほぼ一様であると仮定しました。得られたデータから、各粒子種の空間分布、反応速度、エネルギー状態などを解析しました。
2. 誘導結合プラズマ ICP を用いたリモートプラズマ生成と活性酸素種の同定
本研究では、活性酸素生成源として誘導結合方式によるリモートプラズマに焦点を当てました。試作した装置は、内径66mm、肉厚2mmの石英管周囲に4ターン水冷アンテナを巻いたICP源を上部に備えた金属製真空チャンバーで構成されています。ICP源と処理室は、開口径1mmのエキスパンドメタルメッシュで電気的に隔離されており、荷電粒子の処理基材への拡散を抑制する構造になっています。放電管には、原子状酸素の再結合率が低いパイレックス管を使用しました。この装置を用いて、高周波(RF:13.56MHz)励起によるリモートプラズマを生成し、OES(発光分光分析)によりプラズマ状態を計測しました。その結果、生成されたプラズマ中では、放電によって生成した原子状酸素が排気方向へと拡散し、支配的な活性酸素種となっていることが明らかになりました。ULVAC製PVD-360ロータリーポンプを用いた真空排気系を使用しました。Maxtek製SC-101(6MHz)水晶振動子を活性酸素検出用のQCMセンサとして使用し、試料台に固定配置しました。実験条件は、酸素導入圧力10Pa、RF電力200W、照射距離30mm、処理時間15分です。IWATSU製SC-7205周波数カウンタでQCMの周波数変化を測定しました。
3. モンテカルロシミュレーションによる活性酸素種の生成 挙動解析と考察
モンテカルロシミュレーションを用いて、誘導結合酸素プラズマ中の活性酸素、特に励起一重項原子状酸素(O(¹D))の生成分布と挙動を解析しました。シミュレーションでは、光化学反応も考慮し、電子の衝突反応や中性粒子間の反応を詳細にモデル化しました。その結果、O(¹D)は10⁻⁸秒以下の非常に短い時定数で密度が大幅に低下することが明らかとなりました。これは、O(¹D)が他の分子とクエンチ反応を起こし、短時間で消滅するためです。この結果は、戸坂らの実験結果と概ね一致しています。ただし、彼らの実験では高光強度のエキシマレーザーを使用しており、本研究とは条件が異なるため、密度減衰の時定数に違いが見られました。本研究のシミュレーション結果から、基材表面でO(¹D)が反応するためには、オゾンが表面に吸着した直後に253.7nmのUV光を照射してO(¹D)を生成させる必要があることが示唆されました。シミュレーションでは、253.7nm光子のフラックスは約2×10¹⁶/cm²/secで、10cmの距離を通過する際に約55%がガス分子に吸収され、残りは透過することが示されました。これらの結果から、リモートプラズマを用いた活性酸素処理において、活性酸素種の生成・輸送・反応を制御するための重要な知見が得られました。
IV.活性酸素種とUV光による表面処理および殺菌効果の検証
ポリイミド薄膜を成膜したQCMを用いて、UVランプとリモートプラズマによる表面処理効果をリアルタイムでモニタリングしました。UV光の波長と活性酸素種の作用による殺菌効果の違いを、枯草菌(Bacillus atrophaeus (NBRC1683))を用いた実験で検証しました。UVランプとリモートプラズマ装置を用いた殺菌実験を行い、それぞれの殺菌効果を比較することで、活性酸素種とUV光の殺菌への寄与を明らかにしました。リモートプラズマにおける原子状酸素のフラックスは約1.2 × 10¹⁵ atom・cm⁻²・sec⁻¹ でした。
1. UVランプを用いた表面処理における活性酸素とUV光の寄与の検証
本研究では、低圧水銀UVランプを用いた表面処理における活性酸素とUV光の寄与について検証しました。ポリイミド薄膜を成膜したQCM(PI-QCM)を用いて、UVランプからの距離を変えながら(20mm, 40mm, 60mm)、リアルタイムで共振周波数の変化をモニタリングしました。UV光の作用を評価するために、(a)185/254nmのUV光と200nm以下のUV光をカットするガラスフィルターを挿入した条件と、(b)254nm光のみを照射する条件の2つの実験を行いました。20mmの位置における185nmと254nmのUV照度は、条件(a)でそれぞれ2.9mW/cm²と16.2mW/cm²、条件(b)で0.9mW/cm²と15.4mW/cm²でした。これらの実験結果から、UV光と活性酸素種の両方が表面処理に寄与していることが示唆されました。特に、185nmの真空紫外線による原子状酸素の生成と、254nmのUV光によるオゾンの光解離と励起状態原子状酸素(O(¹D))の生成が重要な役割を果たしていると考えられます。岩崎電気製QGL90U-31UVランプ、Maxtek製SC-101水晶振動子を使用しました。
2. UVランプ殺菌ボックスと低圧リモートプラズマ装置による殺菌効果の比較
活性酸素とUV光の殺菌効果の差異を明らかにするために、UVランプ殺菌ボックスと低圧リモートプラズマ装置を用いて、枯草菌(Bacillus atrophaeus (NBRC1683))の殺菌実験を行いました。枯草菌芽胞は、Soybean-Casein Digest寒天培地上で培養後、滅菌水で回収、洗浄し、80℃で15分間の熱処理によって調製しました。芽胞濃度は十倍希釈法により測定しました。UVランプ殺菌ボックスでは、様々なQCM測定によって活性酸素生成量が明らかとされている装置を用いました。一方、低圧リモートプラズマ装置では、UVランプが介在せず、原子状酸素のみが殺菌に寄与する条件を設定しました。この装置では、真空排気系によりプラズマ中の原子状酸素が試料に照射されます。C/Ag-QCM測定により、原子状酸素のフラックスは約1.2×10¹⁵atom・cm⁻²・sec⁻¹と算出されており、酸素イオン等の荷電粒子は照射されません。シミュレーションの結果、原子状酸素の密度は3.5×10²¹m⁻³であることが確認されました。ICP源と試料間の距離は25mmに設定しました。NRBC((独)製品評価技術基盤機構生物遺伝資源部門)から枯草菌を購入し、実験に用いました。これらの実験結果から、活性酸素種とUV光による殺菌効果の相違を明らかにし、本測定手法の工業的な応用可能性を探りました。
