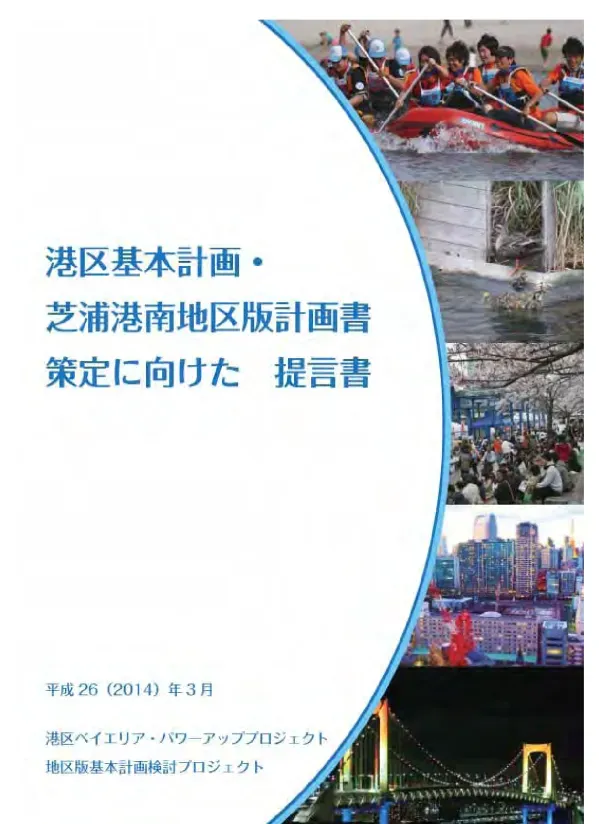
港区芝浦港南地区版基本計画:提言書
文書情報
| 著者 | 港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト「地区版基本計画検討プロジェクト」 |
| city | 東京都港区 |
| 文書タイプ | 提言書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 3.00 MB |
概要
I.みなとパーク芝浦を活用したコミュニティ活性化提案
港区【芝浦】・【港南】地区の活性化を目指し、田町駅近隣に位置する【みなとパーク芝浦】を核とした複数の事業提案がなされています。主な提案としては、【コミュニティカフェ】の開催、【芝浦・海岸・港南クリーンアップ大作戦】による環境美化、地域住民参加型の【ワークショップ】、地域の歴史・文化を学ぶ【地域学講座】、そして水辺の自然環境を活用した【ビオトープのある公園づくりプロジェクト】などが挙げられます。これらの事業は、地域住民の【地域交流】促進、【まちづくり】への参加、そして【水辺】の魅力向上に貢献することを目的としています。特に、みなとパーク芝浦は、地域住民だけでなく、区民全体の交流拠点としての活用が期待されています。
1. みなとパーク芝浦の活用目的と事業主体
港区芝浦・港南地区において、田町駅東口北地区公共公益施設であるみなとパーク芝浦の開設を機に、地域活性化のための事業提案がなされています。港南、台場地区は地理的に孤立しており、中心となる施設が不足していましたが、みなとパーク芝浦は田町駅、レインボーバス、ちぃばす停留所にも近く、テラス、広場、アトリウムなどを備えているため、地区住民だけでなく、区民全体の交流拠点として有効活用できると期待されています。事業主体は芝浦港南地区総合支所と港区ベイエリア・パワーアッププロジェクトです。事業内容は、みなとパーク芝浦内にコミュニティ意識を醸成する広場を整備し、やすらげる空間を創出すること、そして定期的なイベントを区と区民参画組織が協働して実施することを目指しています。しかし、週1~2回の定期開催を目指すため、シンプルな運営方法の検討や、港区ベイエリア・パワーアッププロジェクトメンバーの企画・運営能力を最大限に発揮できる仕組み作りが課題となります。
2. コミュニティカフェ開催事業提案
事業提案の一つとして、みなとパーク芝浦においてコミュニティカフェの開催が挙げられています。これは、地域住民間の交流を促進し、コミュニティ意識の醸成を目的としています。具体的な運営方法や頻度については、シンプルで持続可能な運営体制の構築が重要となります。 カフェの運営を通して、地域住民の交流を深め、地域社会の活性化に貢献することが期待されています。 また、この事業は、みなとパーク芝浦の利用促進にもつながる可能性があります。 しかし、運営の簡素化と同時に、集客方法や収益性の確保についても考慮する必要があります。
3. 芝浦 海岸 港南クリーンアップ大作戦
地域環境の改善を目的とした「芝浦・海岸・港南クリーンアップ大作戦」も提案されています。この事業は、ごみゼロのまちを目指し、地域住民の環境意識を高めることを目的としています。 清掃活動を通じて、地域住民の参加意識を高め、地域社会への愛着を育む効果が期待されます。 また、清掃活動は、地域住民の健康増進にも貢献する可能性があります。 しかし、継続的な活動のための体制整備や、参加者の確保が課題となります。 定期的な活動計画や、参加者への広報活動が重要です。
4. 水辺のまちワークショップとビオトープのある公園づくり
地域住民参加型のワークショップの開催と、ビオトープを活用した公園づくりも提案されています。ワークショップは、運河を中心としたまちづくりをテーマに、各世代が参加できる内容を企画し、横断的な交流を図ります。 ビオトープは、芝浦水再生センターの処理水を活用し、地域住民が水辺の動植物に親しみ、学ぶ場を提供します。 これにより、芝浦水再生センターのイメージ向上や、地域全体のイメージアップを目指しています。 ワークショップの成果発表会や、ビオトープの観察会・調査会などを定期的に開催することで、地域住民の環境意識を高め、持続可能な地域社会の構築に貢献することが期待されています。東京都下水道局との継続的な調整も必要となります。
5. 地域学講座と夏みかんコーナー設置事業
地域の歴史や文化を学ぶ「地域学講座」の開催と、地域資源である夏みかんを活用した加工品の販売コーナーの設置も提案されています。地域学講座は、地域住民の地域への理解を深め、地域への愛着を高めることを目的としています。講座修了後には、学んだ人々が地域課題の解決活動に自主的に参加できるシステム構築を目指しています。 夏みかんコーナーは、既存の夏みかんマーマレード作りを発展させ、焼き菓子やアイスクリームなどの加工品を販売することで、地域経済の活性化にも貢献することを目指しています。みなとパーク芝浦の売店での販売も検討されています。 これらの事業は、地域資源の活用と地域住民の意識向上を同時に目指しています。
II.運河と水辺資源を活用した地域活性化
【芝浦】・【港南】地区は運河沿いの立地を活かしたまちづくりが重要視されています。提案されている事業には、運河周辺の環境整備、運河をテーマとしたワークショップの実施、そして【ビオトープ】の活用による水辺環境の保全と啓発活動などが含まれます。 これらの取り組みを通じて、水辺空間の利活用促進、地域住民の環境意識向上、そして【芝浦水再生センター】のイメージアップを目指しています。 東京海洋大学との連携による環境学習プログラムなども検討されています。
1. 運河を活用したワークショップと発表会
この提案では、運河を中心としたまちづくりをテーマに、地域住民を対象としたワークショップと発表会が計画されています。対象年齢は幼稚園児から大人まで幅広く、絵や模型など、参加者それぞれの表現方法で成果を発表する機会が設けられています。ワークショップは、地域住民の創造性を刺激し、地域への愛着を育むことを目的としています。運営体制は、当面の間は区と協働で行い、将来的には自立した運営を目指しています。修了後は、参加者同士のネットワーク形成を支援し、地域課題解決のための活動に繋げるシステム作りを目指しています。上級者は講師として指導に当たることで、講座の自立的な運営を促進します。この事業は、多世代の交流促進と地域課題解決への住民参加を促進することを目指しています。
2. 芝浦水再生センターとビオトープの活用
芝浦水再生センターの処理水を活用したビオトープの整備と活用が提案されています。このビオトープは、地域住民が水辺の動植物に親しみ、学ぶ場として機能し、ひいては芝浦水再生センターのイメージ向上に繋がることを目指しています。 具体的には、定期的な観察会や専門家による解説、研究機関との協働による動植物調査会などが計画されています。 これにより、地域住民は身近な自然に触れる機会を得るとともに、水辺環境への理解を深めることが期待されます。 また、ビオトープは、芝浦港南地区全体を淡水・汽水・海水域の動植物と共生する「やさしいまち」へと変えていくための重要な要素として位置付けられています。 ただし、東京都下水道局との継続的な調整が必要となる点が課題として挙げられています。
3. 運河周辺環境の整備と利活用
地域住民からの意見として、運河の美化や利活用に関する要望が多数寄せられています。具体的には、運河の清掃活動、運河を利用したカフェの開設、海外の運河活用事例の調査・紹介などが提案されています。現状では運河沿いの空間が十分に活用されていないという指摘があり、より魅力的な水辺空間を創出することで、地域住民の生活の質向上を目指します。 これらの取り組みは、運河周辺の活性化に繋がるだけでなく、地域住民の交流促進にも効果があると期待されています。 しかし、実現のためには、東京都との連携や、効果的な広報活動が重要となります。 また、住民向けの店舗の増加も、水辺の魅力を高める上で重要だと考えられています。
III.台場地域の史跡と魅力の再発見
【台場】地域の歴史的資源に着目した【台場フォーラム】の開催が提案されています。このフォーラムでは、台場の歴史、地域資源の活用事例、そして地域住民参加型のイベントなどを企画することで、台場の歴史的魅力を再認識し、地域活性化につなげることが目指されています。 【第三台場】、【第六台場】といった史跡の活用、そして近隣自治体との連携も検討事項です。
1. 台場フォーラムの目的と内容
台場地域の活性化を目的とした「台場フォーラム」の開催が提案されています。このフォーラムは、台場が持つ歴史的資源と現代的魅力を再認識し、地域住民の交流を促進することを目指しています。 フォーラムの内容は、アンケート調査によるニーズの把握に基づいて決定されますが、例として「台場築造から今日までの台場地域発展ギャラリー」「台場まちづくりフォーラム」「台場子どもオリンピック」「台場地域見学会」などが挙げられています。「台場まちづくりフォーラム」では、全国各地の台場の地域資源活用事例を紹介する他地域団体からの発表も予定されています。 事業主体は港区となり、区民がプロジェクトチームを組んで企画・運営に参画します。1年目はアンケート調査と参加団体への呼びかけ、2年目はフォーラム開催の準備と資料作成、3年目はフォーラムの開催を予定しています。伊豆の国市など、歴史的海洋構造物を地域資源として活用する取り組みを行っている地域団体との連携も計画されています。
2. 台場の歴史的資源と現状
台場は、1853年(嘉永6年)のペリー来航以降、幕府が黒船の襲来に備えて築造されたものです。当初11か所の建設が予定されていましたが、日米和親条約締結後、5か所(第一、第二、第三、第五、第六台場)の完成で中止となりました。現在では、多くの台場は取り壊されましたが、第三台場と第六台場のみが国史跡として残されています。第三台場は台場海浜公園に接続する史跡公園として公開され、第六台場は原状保存のため海上に残されています(非公開)。 また、第三台場から南西に伸びる防波堤(延長2.4km、幅36m、高さ4.5m)も東京港築港の一環として昭和6年に竣工しており、土提構造の防波堤という珍しい特徴を持っています。 これらの史跡は、台場地域の貴重な歴史的資源であり、フォーラムを通じてその魅力を再発見し、地域住民に広く知らしめることが重要となります。 さらに、東京都埋蔵文化財センターによる発掘調査で、品川台場の遺構が良好な状態で残されていることが確認されていることも重要な情報です。
IV.地域住民の意見と課題
地域住民からは、子育て支援の充実、高齢者を含む多世代の交流機会の創出、そして買い物環境の改善といった要望が多く寄せられています。また、事業の運営面では、簡素な運営方法の検討、港区ベイエリア・パワーアッププロジェクトメンバーの能力を最大限に活かす仕組みづくりなどが課題として挙げられています。 さらに、既存の事業計画の見直し、収益性のある事業への転換、そして地域住民の【地域愛】を育む取り組みの必要性が指摘されています。
V.その他の地域資源と取り組み
この資料では、【芝浦港南地区安全・美化協議会】や【青少年対策地区委員会】などの地域団体による活動、そしてカルガモの保護活動なども紹介されています。 さらに、プラタナス公園、港南緑水公園などの公園整備、過去の地域イベントや施設(芝浦球場、芝浦グラウンドなど)に関する記述もあり、これらの資源を活用したまちづくりが期待されています。 【お台場ふるさとの海づくり事業】なども地域の自然環境保全と活用に貢献しています。
