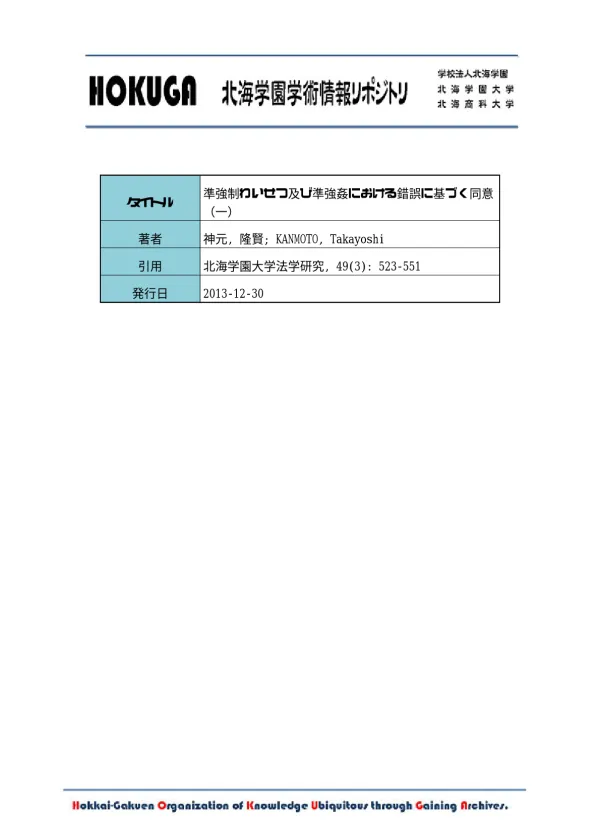
準強制わいせつ・準強姦の錯誤に基づく同意
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 0.96 MB |
| 著者 | 神元 隆賢 |
概要
I.心理的抗拒不能状態における準強姦罪 準強制わいせつ罪の成立要件
本判決は、**準強姦罪(jun kyōkan-zai)及び準強制わいせつ罪(jun kyōsei waisetsu-zai)における抗拒不能(kōkyo funō)状態、特に心理的抗拒不能(shinriteki kōkyo funō)**に焦点を当てた複数の事案を分析しています。被害者が詐欺や脅迫によって錯誤に陥り、正常な判断能力を欠いた状態での性行為を巡る争点が中心です。**刑法第178条(Keihō Dai-178-jō)の解釈が問題となり、被害者の自由意思の有無、客観的・主観的基準の適用などが詳細に検討されています。具体的には、偽医者による治療を装った行為、地位を利用した脅迫、宗教的な教義による洗脳など、様々な手口による欺罔(gimō)**が、抗拒不能状態を作り出していたと判断されています。
1. 欺罔による心理的抗拒不能と準強姦罪 準強制わいせつ罪の成立
この節では、被害者が加害者の欺罔行為によって心理的に抗拒不能の状態に陥り、準強姦罪または準強制わいせつ罪が成立するか否かが論じられています。特に、法益関係的錯誤説に基づき、極度の眠気や人間違いといった例外を除き、心理的抗拒不能による準強制わいせつ罪の成立が認められるものの、それが自由意思を欠いた状態であったかどうかの検討が必要であると指摘されています。具体的な事例として、医師を装った被告人が、治療行為を装いながら性行為を行い、被害者がその行為を抗拒できなかった事例が挙げられています。この事例においては、遮断幕のない診察台や、被害者の羞恥心から目を閉じていた状況などが、抗拒不能状態を裏付ける証拠として提示されています。また、性行為の意味を理解できない少女を騙して性行為を行った事例についても言及され、刑法178条の強姦罪に該当する可能性が指摘されています。さらに、必要な施術を行うものと誤信させたケース、権威ある医師を装って性病治療の名目で脅迫的な言動を行い、性行為を強要したケースなども分析されています。これらの事例を通して、欺罔行為による心理的抗拒不能と、準強姦罪・準強制わいせつ罪の成立要件との関係が詳細に検討されています。特に、被害者の年齢、精神状態、加害者の言動、状況証拠などが総合的に判断材料として用いられています。
2. 錯誤に基づく同意と抗拒不能の区別
この節では、被害者が加害者の行為に同意したように見えるケースにおいて、その同意が自由意思に基づくものなのか、それとも加害者の欺罔や脅迫による錯誤に基づくものなのかを区別する問題が取り上げられています。例えば、被害者が加害者を夫と間違えて性行為に応じたケースでは、性行為自体には同意があったものの、それが自由意思に基づくものではないと判断された事例が紹介されています。この判決では、強姦罪の構成要件が「婦人をその意思に反して姦淫した者」と限定的に規定されていないこと、被害者の意思のみを判断基準とすることは問題があるという批判的な意見も紹介されています。また、身体障害者と誤信させた上で性行為を行ったケースや、娘の夫を装って性行為を行い、拒否すれば家族に危険が及ぶと誤信させたケースなども分析され、これらのケースにおいて、被害者が抗拒不能の状態にあったと判断される根拠が示されています。さらに、モデル撮影を装って性行為に及んだケースでは、被害者の性的無知や驚愕を利用した巧妙な手口が指摘され、抗拒不能状態が認められています。これらの事例を通して、錯誤に基づく同意と抗拒不能状態を峻別する難しさ、そしてその判断における客観的・主観的基準の使い分けが論じられています。
3. 抗拒不能状態の客観的 主観的判断基準
本節では、準強姦罪・準強制わいせつ罪における抗拒不能状態の判断基準、特に客観的基準と主観的基準の適用について詳細に検討されています。 判決においては、被害者の心理状態や状況証拠に基づく主観的な判断と、客観的に見て抗拒が不可能または著しく困難であったかどうかの判断が併用されています。例えば、A女のケースでは、指の挿入による驚愕から自由意思を失ったと解釈され、主観的基準が採用されたと分析されています。一方で、就職希望企業の人事担当者を装い、就職を条件に性行為を要求されたケースでは、被害者が拒否することが著しく困難であったと客観的に判断され、客観的基準が重視されています。テレビ局の採用面接で人事担当者のわいせつ行為を黙認せざるを得なかったと誤認したケースも、客観的基準に基づき抗拒不能と判断されたと述べられています。これらの事例を通じて、抗拒不能の判断においては、被害者の具体的な状況、加害者の行為、社会的な文脈など、様々な要素を総合的に考慮する必要性が強調されています。単純に被害者の意思の有無のみで判断するのではなく、客観的な状況証拠も重要な判断材料となることが示唆されています。
II.医師による信頼関係の悪用と抗拒不能
医師という権威ある立場を悪用し、患者の信頼関係を利用して性行為に及んだ事案が複数含まれています。被害者は、医師の専門知識や治療効果への期待から、**抗拒不能(kōkyo funō)**状態に陥っていたと判断されています。特に、**信 頼関係(shinrai kankei)**の構築と、それによる被害者の判断力の低下が、準強姦罪(jun kyōkan-zai)・**準強制わいせつ罪(jun kyōsei waisetsu-zai)**の成立に大きく影響している点が強調されています。これらの事案では、被害者の年齢や精神状態、加害者の言動などが詳細に分析され、**心理的抗拒不能(shinriteki kōkyo funō)**の有無が慎重に検討されています。
1. 医師の権威を利用した欺瞞と抗拒不能
この部分では、医師という立場を利用した欺瞞行為によって被害者が抗拒不能状態に陥った事例が分析されています。被告人は医師を装い、治療行為と偽って性行為を行い、被害者はその専門性への信頼から抵抗できなかったとされています。具体例として、遮断幕のない診察台で治療中、羞恥心から目を閉じていた被害者が、被告人の行為に抗拒できなかった事例が挙げられています。この事例では、被告人の行為が正当な医療行為であると被害者が誤信していた点、そして診察台の特殊な構造や被害者の心理状態が、抗拒不能状態に陥った要因として重要視されています。つまり、医師という立場から生まれる信頼関係と、その信頼関係を悪用した被告人の欺瞞行為が、被害者の抗拒不能状態を招いたという論点が強調されています。 判決では、この信頼関係が被害者の自由意思を奪い、心理的抗拒不能状態を作り出したと結論づけられています。この事例は、専門職の地位や権威が、性犯罪においてどのように利用されるかを示す重要なケーススタディとなっています。
2. 信頼関係と心理的抗拒不能の関連性
この節では、医師と患者間の信頼関係が、心理的抗拒不能状態の成立にどのように影響するかを分析しています。 一般的に、医師は患者から高い信頼を得ており、その信頼関係は患者の判断力に影響を与えうる可能性があります。本判決では、この信頼関係が、被告人の行為への抵抗を困難にさせる要因として明確に示されています。 特に、被害者が抱える不安や疾患(例えば、悪性腫瘍や癌への不安)が、被告人への依存を高め、抗拒不能状態を助長した可能性が指摘されています。 被告人が医療行為を装っていたことは、被害者の信頼を裏切るものであり、その信頼関係の悪用が、準強姦罪・準強制わいせつ罪の成立に大きく関与していると判断されています。判決は、医師と患者の信頼関係を前提とした上で、その信頼関係がどのように歪められ、悪用されたか、そしてその結果として被害者が抗拒不能な状態に置かれたかを詳細に検討しています。この信頼関係の悪用は、被害者の心理状態に大きく影響し、自由意思に基づく同意を不可能にしたと結論づけています。
3. 他の専門職における信頼関係の悪用との比較検討
この節は、必ずしも明示的には記述されていませんが、医師以外の専門職における信頼関係の悪用と、抗拒不能状態の関連性について、間接的に示唆されています。 例えば、他の事例で言及されている宗教指導者や企業人事担当者といった権威ある立場の人物による欺瞞や脅迫は、医師の事例と同様に、被害者の信頼関係を悪用したものであると解釈できます。 これらの事例と医師の事例を比較することで、専門職特有の信頼関係が、性犯罪における抗拒不能状態の成立に共通して影響を与えている可能性が示唆されます。 すなわち、権威や専門知識を背景とした信頼関係は、加害者にとって、被害者の抵抗を弱める有効な手段となりうるという点が、複数の事例を通して示されていると言えます。 今後、様々な専門職における同様の事案を分析することで、より包括的な理解が得られる可能性があり、この判決は、そのための重要な基礎資料となっています。
III.脅迫や錯誤に基づく性行為と抗拒不能
就職活動中の若者への脅迫、家族への危害を仄めかす言動、宗教的教義による洗脳など、様々な脅迫的手法や欺瞞によって被害者を**抗拒不能(kōkyo funō)**の状態に陥れ、性行為に及んだ事案が分析されています。これらの事案では、被害者の置かれた状況、加害者の言動、被害者の心理状態などが詳細に検討され、抗拒不能状態の客観的・主観的判断基準が議論されています。脅迫(kyōhaku)、**詐欺(sagishi)**といった行為が、準強姦罪(jun kyōkan-zai)・**準強制わいせつ罪(jun kyōsei waisetsu-zai)**の構成要件にどのように影響するかを明らかにしようとしています。
1. 脅迫による抗拒不能状態の成立
この節では、加害者による脅迫行為が被害者の抗拒不能状態を招き、準強姦罪・準強制わいせつ罪の成立要件を満たすか否かが論じられています。具体的には、戸籍に赤字で記載されるなどの脅迫的な言動により、結婚を妨げる、家族の生活をめちゃくちゃにするなどの脅迫を伴う事例が分析されています。 また、性病治療を名目に、治療には被告人との性行為が必要だと誤信させ、性行為を強要した事例も含まれています。さらに、宗教的な教義を用いて、被告人に従わなければ地獄に落ちるなど、強い恐怖心を植え付け、長年に渡り性行為を繰り返した事例も分析対象となっています。これらの事例においては、被害者の年齢、精神状態、加害者の言動、状況証拠などが総合的に検討され、客観的に見て抗拒が不可能または著しく困難であったかどうかの判断が行われています。脅迫による心理的支配が、被害者の意思決定能力を著しく阻害し、抗拒不能状態を作り出したと結論づけられています。 特に、未成年者に対する性的虐待事例では、加害者の年齢や知識を考慮した上で、抗拒不能状態の成立要件が厳格に検討されています。
2. 錯誤に基づく同意と抗拒不能の区別
この節では、加害者の欺瞞や錯誤誘導によって被害者が性行為に同意したように見えるケースについて、その同意が真に自由意思に基づくものなのか、それとも錯誤に基づくものなのかを区別する問題が論じられています。 例えば、妊娠を偽って不安に陥れたり、特殊な治療だと誤信させたりするなど、様々な欺瞞的手法が用いられています。 これらのケースにおいて、被害者が性行為の意味を理解していたとしても、加害者の欺瞞によって錯誤に陥り、正常な判断能力を欠いていたと判断された事例が複数紹介されています。 判決では、被害者の年齢や精神状態、加害者の巧妙な手口、そして被害者が置かれていた状況などが、抗拒不能状態の判断において重要な要素として考慮されています。単なる同意の有無ではなく、その同意に至るまでの過程における被害者の心理状態や、加害者の行為の違法性が詳細に検討され、抗拒不能状態の成立要件が厳格に判断されています。 錯誤に基づく同意は、自由意思に基づく同意とは異なり、抗拒不能状態を構成する重要な要素となると結論付けられています。
3. 様々な脅迫 欺瞞手法と抗拒不能状態
この節では、就職希望の企業の人事担当者を装って性行為を強要した事例や、写真撮影を装ってわいせつ行為を行った事例など、様々な脅迫や欺瞞手法を用いたケースが分析されています。 これらの事例では、被害者が将来の進路や生活に大きな影響を与える状況に置かれており、その状況が抗拒不能状態に陥る要因として考慮されています。 加害者は、被害者の不安や希望を利用し、巧妙に心理的に追い詰めることで、抗拒不能状態を作り出しているとされています。判決では、これらの事例における加害者の行為の違法性、被害者の置かれた状況、そして被害者の心理状態が詳細に検討され、抗拒不能状態の成立要件が厳格に判断されています。 特に、被害者の年齢、社会経験、精神状態などが、抗拒不能状態の判断において重要な要素として考慮されています。 これらのケースは、脅迫や欺瞞行為が、いかに被害者の抗拒能力を奪い、性犯罪を成立させるかを示す重要な事例となっています。
IV.錯誤に基づく同意と抗拒不能の判別
被害者が加害者を夫と誤認した状態での性行為など、錯誤に基づく「同意」と**抗拒不能(kōkyo funō)の境界線が曖昧な事案も分析されています。被害者が性行為に「同意」したとしても、それが真に自由な意思に基づくものか、それとも欺罔(gimō)や脅迫(kyōhaku)による錯誤(sakkō)**に基づくものかといった点が、判決において重要な論点となっています。これらの事案では、被害者の年齢、知能、状況判断能力などが考慮され、**心理的抗拒不能(shinriteki kōkyo funō)**の有無が個別に判断されています。
1. 夫と間違えたケースにおける同意と抗拒不能
本判決では、被害者が加害者を自分の夫と誤認した状態での性行為について、同意と抗拒不能の区別が重要な論点となっています。 被害者が性行為に同意したように見える場合でも、その同意が自由な意思に基づいているかどうかが厳しく問われます。 具体的には、A女が夢うつつの中で被告人を情夫と間違えて性行為に応じた事例が挙げられています。 このケースでは、性行為自体はA女が同意したものの、その同意が錯誤に基づくものであり、自由な意思によるものではないと判断されています。 判決は、強姦罪の構成要件が「婦人をその意思に反して姦淫した者」と限定的に規定されていないことを指摘し、被害者の意思のみを判断基準とすることの限界を述べています。 夫と間違えたという状況、そしてA女の意識が徐々に明確になり、被告人に気づいた後に抵抗したという事実も考慮されています。 これらのことから、判決は、錯誤に基づく同意は、真の自由意思に基づく同意とは異なるものであり、抗拒不能状態を構成する重要な要素となると結論付けています。
2. 錯誤に基づく同意の成立要件
この節では、錯誤に基づく同意が成立するための要件、およびそれが抗拒不能状態とどのように関連するかについて論じられています。 被害者が加害者の行為に同意したとしても、それが加害者の欺瞞や脅迫によって誘導された錯誤に基づくものであれば、真の自由意思に基づく同意とはみなされません。 判決では、被害者の年齢、精神状態、加害者の言動、そして状況証拠などが総合的に検討され、錯誤の程度やそれが抗拒不能状態に与える影響が詳細に分析されています。 例えば、受験勉強に疲弊した生徒が、成績向上のための特殊な治療だと誤信して性行為を受け入れたケースや、病気の治療を名目に性行為を強要されたケースなどが挙げられています。 これらのケースにおいては、被害者の年齢や精神状態、加害者の言動、そして被害者が置かれていた状況などが、抗拒不能状態の判断において重要な要素となります。 判決は、これらの要因を総合的に考慮することで、錯誤に基づく同意と抗拒不能状態の明確な区別、そして準強姦罪・準強制わいせつ罪の成立要件への影響を丁寧に検討しています。
3. 客観的状況と主観的状況の総合的判断
この節では、錯誤に基づく同意と抗拒不能状態の判別において、客観的状況と主観的状況を総合的に判断する必要性が強調されています。 単に被害者の主観的な意思表示のみならず、客観的な状況証拠も考慮されるべきであるという点が強調されています。 例えば、被害者の年齢や精神状態、加害者の行為、そして社会的な文脈などが、抗拒不能状態の有無を判断する上で重要な要素として挙げられています。 判決では、被害者の心理状態だけでなく、加害者の行為が客観的に見て脅迫的であったか、または被害者が置かれていた状況が客観的に見て抗拒不能状態を作り出すものであったかといった点が、重要な判断基準となっています。 また、極めて短期間の非正規雇用の面接で性行為を要求されたケースなど、人生や生活に重大な影響を与える状況かどうかという点も考慮されるべきであると述べられています。 これらのことから、抗拒不能状態の判断は、主観的な要素と客観的な要素を総合的に考慮した上で、個々の事案の具体的な状況に応じて行われるべきであるという結論が導かれています。
