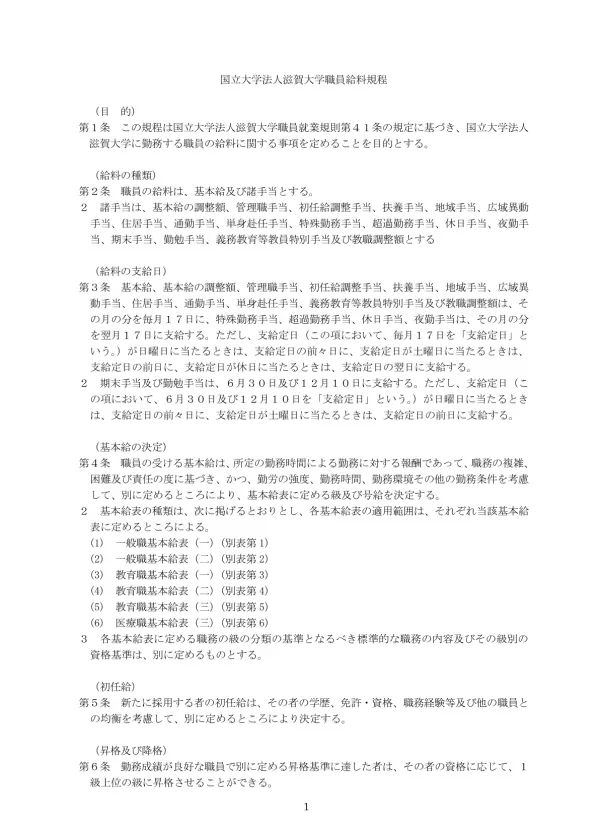
滋賀大学職員給与規程:給料体系と支給日
文書情報
| 学校 | 国立大学法人滋賀大学 |
| 専攻 | 人事・給与 |
| 場所 | 滋賀県 |
| 文書タイプ | 規程 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 10.07 MB |
概要
I.給与の支給日と各種手当
本規程は、大学職員の給与に関する重要な情報を網羅しています。基本給、管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当などの各種手当の支給日や計算方法を規定しています。特に、基本給、調整額、管理職手当などは毎月17日、特殊勤務手当、超過勤務手当などは翌月17日に支給されます。支給日は土日祝日の場合は変更となります。彦根市、大津市勤務の職員の地域手当はそれぞれ給与の3/100、5/100が支給されます(人事交流職員は除外あり)。通勤手当は通勤手段や距離によって金額が異なり、上限額が設定されています。単身赴任手当は、配偶者と別居し、通勤が困難な職員に支給されます。
1. 給与支給日
本規程第3条では、大学職員への給与支給日を定めています。基本給、基本給調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当など多くの手当は、当該月の分を毎月17日に支給されます。しかし、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当は、当該月の分を翌月17日に支給されます。重要なのは、支給日が土日祝日に当たる場合の取り扱いについてです。日曜日の場合は支給定日の前々日、土曜日の場合は支給定日の前日に支給日が繰り下げられます。この規程において毎月17日を「支給定日」と定義している点にも注意が必要です。給与の支給日は、職員にとって非常に重要な情報であり、正確な理解が求められます。
2. 地域手当
地域手当は、勤務地の地理的条件を考慮した手当です。本規程では、彦根市と大津市の事業所に勤務する職員への地域手当の支給率を明確に示しています。彦根市所在の事業所に勤務する職員には基本給の3/100、大津市所在の事業所に勤務する職員には基本給の5/100の手当が支給されます。ただし、人事交流等により採用された教育職(二)、教育職(三)適用職員で学長が認めた者については、大津市勤務の場合も5/100の手当が支給されます。この地域手当の支給率は、勤務地の選定や職員の待遇に影響を与える重要な要素であり、地域格差の是正にも配慮した規定であると考えられます。具体的な支給額は、個々の職員の基本給によって変動するため、個々の職員への通知が必要です。
3. 通勤手当
通勤手当は、職員の通勤費用を補助するための手当です。本規程では、通勤手段や距離によって支給額が異なる複雑な計算方法が規定されています。具体的には、公共交通機関を利用する職員と自家用車を利用する職員で計算方法が異なります。公共交通機関利用者の場合、算出された運賃等相当額が上限55,000円に制限されます。自家用車利用者の場合、片道5km未満で2,000円、それ以上は別途規定に基づいて計算されます。また、新幹線等の特別急行列車を利用する場合の特別料金等についても、半額を支給するという規定があります。通勤手当の支給額は、通勤距離、交通機関の利用状況、そして職員の生活実態を考慮して決定されるため、個々の職員への正確な支給には細やかな配慮が必要です。さらに、給与法適用職員等からの継続採用職員についても、通勤事情を考慮した規定が設けられています。
4. 単身赴任手当
単身赴任手当は、事業所の異動や移転に伴い、配偶者と別居して単身で生活する職員に支給される手当です。支給要件としては、事業所の異動や移転に伴い住居を移転し、配偶者と別居することとなり、かつ、配偶者の住居から勤務先への通勤が困難であることが必要です。通勤の困難さは、通勤距離等を考慮した別に定める基準に基づいて判断されます。単身赴任手当の支給額は、本規程では詳細な計算方法が明記されていませんが、別途定められるとされています。給与法適用職員等からの継続採用職員についても、同様の要件を満たせば、単身赴任手当の支給対象となる可能性があります。この手当は、職員の生活負担を軽減し、業務への専念を支援するための重要な制度です。
5. その他の手当
本規程では、上記以外にも様々な手当が規定されています。管理職手当は、別表第8に掲げる職員に支給され、その金額も別表第8に規定されています。ただし、全日数勤務しなかった場合は支給されません。扶養手当は、配偶者、父母、子などの扶養親族がいる職員に支給され、一人当たりの支給額は扶養親族の種類によって異なります。初任給調整手当、広域異動手当、住居手当、義務教育等教員特別手当、教職調整額なども、それぞれ規定に基づいて支給されます。これらの手当は、職員の生活状況や勤務条件などを考慮して支給されるものであり、職員の生活安定と業務遂行の支援に大きく貢献しています。各手当の支給要件や計算方法は、本規程全体を通して詳細に規定されています。
II.昇給と基本給の調整
職員の昇給は、勤務成績に基づき学長が決定します。昇給の号給数は、勤務成績が良好な職員を基準に決定されます。また、職務の複雑さや困難さなどを考慮し、基本給の調整額が設定される場合があります。基本給表(教育職基本給表(一)~(三)、指定職基本給表など)に基づき、職務の級に応じて給与が決定されます。
1. 昇給
本規程第7条は、職員の昇給に関する規定を定めています。昇給は、学長が別に定める日に、前1年間の勤務成績を基に行われます。昇給の有無や号給数は、前1年間を良好な成績で勤務した職員の昇給号給数を基準として決定されます。具体的には、基準となる昇給号給数は4号給とされ(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各基本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして学長が定める職員にあっては、3号給)、学長が定める基準に従って決定されます。つまり、昇給は個々の職員の勤務成績に大きく依存し、その成績が優秀であれば、基準以上の昇給が期待できる反面、成績が不十分であれば昇給が見送られる可能性も示唆されています。この昇給制度は、職員の能力向上とモチベーション維持に重要な役割を果たすと考えられます。
2. 基本給の調整
第9条では、基本給の調整について規定されています。学長は、基本給月額が、職務の複雑さ、困難さ、責任の度合い、労働強度、勤務時間、労働環境などの勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比べて著しく特殊な職に対して適切でないと認めた場合、その特殊性に基づき、基本給月額について調整額表を定めることができます。この調整は、職務の特殊性による不公平を是正するための重要な措置であり、個々の職務の特性を正確に評価することが求められます。調整額の支給に関する具体的な事項は、別に定められるとされています。基本給表、職務の級、そして個々の職員の職務内容を正確に把握することが、基本給の適切な調整に不可欠であると言えます。また、この調整は、常に公平性を保つよう、柔軟な運用が期待されます。
III.扶養手当
扶養手当は、配偶者、父母、子などの扶養親族がいる職員に支給されます。支給額は扶養親族の種類と職員の職務級によって異なり、配偶者1人につき6500円(教(一)5級職員等は3500円)、子1人につき10000円です。扶養親族の状況に変更があった場合は、速やかに学長に届け出ることが必要です。平成29年度~30年度、30年度~33年度は扶養手当の支給基準が変更されています。
1. 扶養手当の支給額
本規程では、扶養手当の支給額を明確に規定しています。扶養親族が配偶者、父母等である場合、1人につき6,500円が支給されます。ただし、教育職基本給表(一)の適用を受ける職員で職務の級が5級であるもの、及び国立大学法人滋賀大学年俸制適用職員給料規程別表第3(第4条関係)基本年俸号給表(承継職員)の適用を受ける職員で職名が教授であるもの(以下「教(一)5級職員等」という。)の場合は、3,500円となります。一方、子が扶養親族である場合は、1人につき10,000円が支給されます。この支給額は、扶養親族の数や職員の職務級によって変動するため、個々の職員への正確な支給には細やかな配慮が必要です。また、扶養親族たる要件を欠くに至った場合は、手当の支給は終了します。扶養手当は、職員の生活を支える上で重要な要素であり、その支給基準の明確化は、職員の生活安定に貢献すると考えられます。
2. 扶養手当の支給期間
扶養手当の支給期間は、扶養親族の状況変化によって変動します。新たに職員となった場合、または新たに扶養親族ができた場合、または扶養親族の要件を欠くに至った場合などは、それぞれ異なる支給開始日と終了日が規定されています。具体的には、新たに職員となった場合、または新たに扶養親族ができた場合は、その事実が生じた日の属する月の翌月から支給開始となります。一方、扶養親族の要件を欠くに至った場合は、その事実が生じた日の属する月をもって支給が終了します。ただし、届出が事実発生から15日後になった場合は、届出受理日の属する月の翌月から支給開始となります。これらの規定は、扶養手当の支給の正確性と迅速性を確保するために、厳格な届出制度と明確な支給期間の定義を設けているものと推測されます。この正確な手続きの遵守は、職員自身の権利を保護する上でも不可欠です。
3. 扶養手当の届出義務
職員は、扶養手当の支給を受けるために、または扶養手当の支給に影響を与える事由が発生した場合には、速やかに学長に届け出ることが義務付けられています。具体的には、新たに職員となった者に扶養親族がいる場合、または新たに扶養親族ができた場合、または扶養親族の要件を欠くに至った場合(扶養親族たる子や特定の扶養親族が22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く)などに該当します。この届出義務は、正確な扶養手当の支給を行う上で非常に重要であり、職員は、自身の扶養状況に変更があった場合は、速やかに届け出を行う必要があります。また、平成29年度から30年度、30年度から33年度にかけて扶養手当の支給基準が見直されており、その変更点についても十分な理解が必要です。届出の遅れは、手当の支給に支障をきたす可能性があるため、迅速な対応が求められます。
IV.超過勤務手当と期末 勤勉手当
超過勤務手当は、所定労働時間を超えて勤務した場合に支給され、時間外勤務時間に応じて計算されます。期末手当と勤勉手当は、基本給、調整額、扶養手当などを基礎として算出されます。支給額は基準日現在の給与額、在職期間、職員の区分などを考慮して計算されます。期末手当、勤勉手当の支給は、職員の行為に係る刑事事件の状況によっては一時差し止められる場合があります。特定職員(55歳以上)については、給与の減額措置が適用されます。
1. 超過勤務手当
超過勤務手当は、所定労働時間を超えて勤務した場合に支給される手当です。規程では、1ヶ月における超過勤務時間が60時間を超えた場合の支給基準が定められています。60時間を超えた時間については、勤務1時間あたり、第21条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の150(午後10時から翌朝5時までは100分の175)を乗じて算出されます。ただし、超勤代替休暇が指定され、職員がその休暇日に勤務しなかった場合は、代替された超過勤務時間については、上記割合から一定の割合を減じた額が支給されます。この規定は、超過勤務の発生状況、そして超勤代替休暇の利用状況によって、支給額が変動することを示しています。超過勤務手当の正確な計算には、勤務時間管理の正確さと、規程の細則への精通が不可欠です。
2. 期末手当
期末手当は、基準日現在(退職者・解雇者については退職日・解雇日現在)における職員の基本給月額、基本給調整額、教職調整額、扶養手当月額、地域手当月額、広域異動手当月額の合計額を基礎として算出されます。6月期は、この合計額に100分の122.5(特定管理職員は100分の102.5)を乗じ、12月期は100分の137.5(特定管理職員は100分の117.5)を乗じます。さらに、基準日以前6ヶ月以内の在職期間に応じて、別表に定める割合を乗じて最終的な支給額が決定されます。特定管理職員とは、教育職基本給表(一)5級で学部長の職にある職員を指します。期末手当の支給は、職員の在職期間中の行為に係る刑事事件の状況によっては一時差し止められる可能性があり、国民の信頼の確保と制度の円滑な実施が優先されます。
3. 勤勉手当
勤勉手当は、期末手当と同様に、基準日現在の給与額を基礎に算出されます。基準日現在の基本給月額、基本給調整額、教職調整額、地域手当月額、広域異動手当月額の合計額(特定職員は加算率を考慮)を基礎額とし、学長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて算出されます。ただし、勤勉手当の総額は、勤勉手当基礎額に扶養手当などを加算した額に100分の85(特定管理職員は100分の105)を乗じた額の範囲内に制限されます。この規定では、勤勉手当の算出に、複数の要素が複雑に絡んでいることが分かります。公平な支給のためには、それぞれの要素を正確に把握し、規程に沿った計算を行うことが不可欠です。また、期末手当と同様に、刑事事件の状況によっては、支給が一時差し止められる可能性があります。
V.休職中の給与
傷病による休職の場合、休職期間と傷病の種類によって給与の支給額が異なります。長期休養を要する傷病の場合は給与の全額または一部が支給されます。ただし、休業補償給付や傷病補償年金がある場合は、控除後の金額が支給されます。基本給等の80%が支給される場合があります。
1. 長期休養を要する傷病の場合の休職
休職規程第2条第1項第1号に該当する長期休養を要する場合の休職については、休職期間中、給料の全額が支給されます。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い、休業補償給付または傷病補償年金がある場合は、給料からその補償額を控除した残額が支給されます。この規定は、附属学校に勤務する職員が結核性疾患により同様の休職を命ぜられた場合にも適用されます。長期休養を要する傷病の場合、職員の生活を支えるために、給与の全額または一部が支給される制度が設けられていることが分かります。しかし、他の社会保障制度との関係も考慮されているため、実際に支給される金額は、個々の職員の状況によって大きく異なると考えられます。
2. その他の傷病の場合の休職
長期休養を要する傷病以外の傷病の場合、休職期間が1年(結核性疾病の場合は2年)に達するまでは、基本給、基本給調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、教職調整額、期末手当(以下「基本給等」という。)の100分の80が支給される可能性があります。しかし、この期間経過後は無給となります。この規定は、傷病の種類と休職期間の長さによって、給与支給額が異なることを示しています。1年もしくは2年という期間制限、そして給与の80%という割合は、職員の生活と健康状態を考慮した上で設定されていると考えられます。ただし、休職期間が長引く可能性があることを踏まえ、職員は自身の経済状況についても十分に考慮する必要があるでしょう。
3. 基本給の半減
第33条では、特定の条件下において、基本給及び基本給調整額の半額が減額されることが規定されています。具体的には、一の負傷または疾病が治癒し、他の負傷または疾病による特定病気休暇(勤務時間等規程第20条に規定する特定病気休暇)が続いている場合に、最初の特定病気休暇開始日から90日の勤務しない期間経過後、継続して勤務しない特定病気休暇の日数について、基本給と基本給調整額の半額が減額されます。この規定は、病気による休職の場合でも、一定の条件下では給与が減額される可能性があることを示しています。この減額規定は、休職期間全体の給与を考慮し、長期にわたる休職による過剰な給与支給を抑制する目的で設けられているものと考えられます。
VI.その他経過措置
本規程には、様々な経過措置に関する規定が含まれています。これには、平成18年4月1日改正給料規程、平成21年12月1日改正給料規程、平成23年4月1日、平成24年4月1日、平成25年4月1日、平成26年4月1日における号給調整、そして平成25年、26年度の附属学校における特例期間中の措置などが含まれます。これらの経過措置は、職員の基本給、手当、昇給などに影響を与えます。
1. 平成18年4月1日改正給料規程附則第6項適用職員への経過措置
平成18年4月1日改正給料規程附則第6項の適用を受ける職員で、改正後の基本給月額が同日において受けていた基本給月額に100分の99.76(指定職職員は100分の99.68)を乗じて得た額に達しない場合、その差額相当額が基本給として追加支給されます。この措置は、給料規程改正による基本給の変更に伴い、職員の給与が不当に減額されないよう配慮した経過措置です。この規定は、改正前の給与水準をある程度維持することを目的としており、改正による影響を最小限に抑えるための措置であると言えます。ただし、学長が定める職員はこの限りではありません。
2. 平成21年12月1日改正給料規程施行に伴う経過措置
平成21年12月1日改正給料規程施行時、平成18年4月1日改正給料規程附則第6項の適用を受けていた職員に対する経過措置が定められています。この経過措置では、同日において受けていた基本給月額を、一定の割合を乗じて算出された額と定義し、その額に1円未満の端数がある場合は切り捨てられます。さらに、差額相当額についても、附則第3項の規定により給料が減額されている職員に対しては、その額に100分の98.5を乗じて算出されます。この経過措置は、給与規程の複数回の改正による影響を明確に示し、職員への給与計算の正確性を担保するためのものです。改正による給与への影響を最小限にするための細やかな配慮が見て取れます。
3. 平成19年4月1日改正による管理職手当の経過措置
平成19年4月1日改正後の管理職手当額が、改正前(平成19年3月31日)の支給額(経過措置基準額)に達しない職員に対しては、改正後の手当額に加え、改正前後の差額に一定の割合を乗じた額が追加支給されます。この割合は、経過期間によって異なり、この経過措置は、給与規程改正による管理職手当の減額を緩和するための措置です。この規定は、改正による管理職への影響を段階的に軽減し、円滑な移行を図ることを目的としています。1円未満の端数は切り捨てられます。
4. 調整手当の異動保障
施行日の前日において給与法第11条の7の適用を受けていた承継職員に対しては、施行日における調整手当の支給について、給与法第11条の7の適用を受けた日から3年を経過する日、または平成18年3月31日のいずれか早い日まで、基本給、基本給調整額、扶養手当、管理職手当、教職調整額の月額合計額に一定の割合を乗じた額が調整手当として支給されます。この規定は、給与法改正に伴う調整手当の変更による不利益を軽減するための経過措置です。この措置は、制度変更による職員への影響を最小限に抑え、安定した生活を確保するための配慮を示しています。
5. 昇給停止に関する経過措置
施行日の前日において、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年法律第120号)附則第11項から第13項までの適用を受けていた承継職員については、昇給停止年齢に達した後も、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができます。この規定は、過去の法律に基づく昇給規定からの移行を円滑に行うための経過措置です。この措置は、制度変更によって不利になる可能性のある職員への配慮を示しています。
6. 平成23年4月1日 平成24年4月1日 平成25年4月1日 平成26年4月1日における号給の調整
これらの規定では、それぞれの時期において、年齢や昇給状況などを考慮して、職員の号給を調整する経過措置が定められています。具体的には、特定の年齢に満たない職員、特定の条件を満たす職員などが対象となり、号給が繰り上げられるなどの措置がとられます。これらの措置は、給与制度の変更や人事上の都合などによる不利益を軽減するための措置と捉えることができます。これらの調整は、職員の待遇を維持し、モチベーションを確保するための重要な配慮を示しています。また、平成25年3月31日までは地域手当の支給率が変更され、平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間は附属学校に勤務する職員の基本給について特例が適用されます。そして、平成29年4月1日から平成30年3月31日、平成30年4月1日から平成33年3月31日にかけて扶養手当の支給基準が変更されています。
