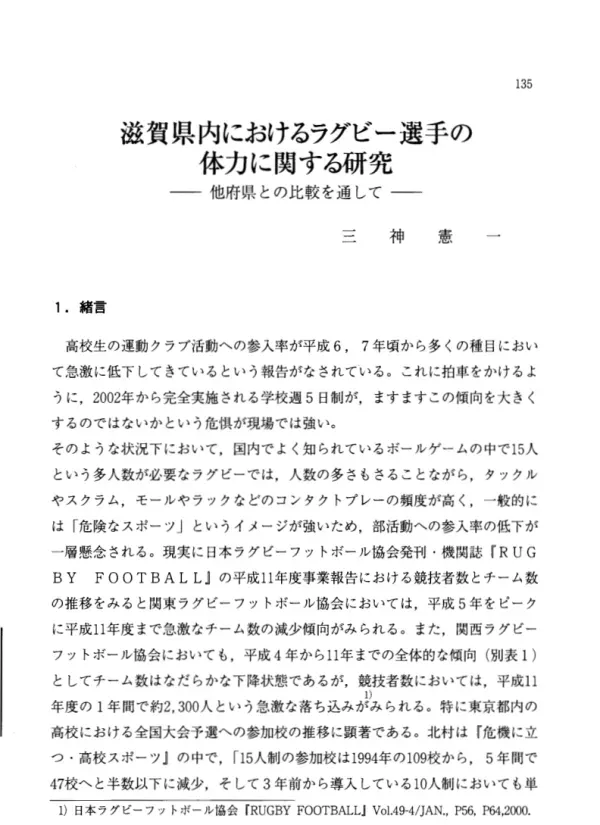
滋賀県ラグビー選手体力研究:他府県比較
文書情報
| 学校 | 不明 |
| 専攻 | 体育学、スポーツ科学関連 |
| 場所 | 不明 |
| 文書タイプ | 研究論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 0.90 MB |
概要
I.滋賀県高校ラグビー選手の体力実態と他府県との比較
本研究は、滋賀県内高校ラグビー部員の体力(特に筋力、持久力、瞬発力、柔軟性)を、インターハイ常連校を含む他府県5校と比較分析したものです。調査対象は、滋賀県内5校(八幡工業高校、膳所高校、近江高校、瀬田工業高校、東大津高校)と他府県5校(大東文化第一高校、長崎北陽台高校、鹿児島工業高校、同志社香里高校、新田高校)のレギュラー候補選手15名ずつ、計150名です。分析の結果、他府県選手に比べ、滋賀県選手は体力、特に全身筋力(背筋力)と持久力(1500m走)に明らかな差が見られました。破壊力(背筋力×体重)や相対筋力においても同様の傾向が見られ、特に八幡工業高校を除く県内高校の選手は、他府県選手に大きく劣ることが判明しました。競技力向上のためには、筋力トレーニングと持久力トレーニングの強化が喫緊の課題です。
1. 調査概要と目的
本研究は、滋賀県下高校ラグビー部員の体力実態を他府県と比較し、競技力向上と普及指導のための基礎データを得ることを目的として実施されました。滋賀県内5校(八幡工業高校、膳所高校、近江高校、瀬田工業高校、東大津高校)とインターハイ常連校を含む他府県5校(大東文化第一高校、長崎北陽台高校、鹿児島工業高校、同志社香里高校、新田高校)のレギュラー候補選手15名ずつ、計150名を対象に独自作成の調査表を用いた調査が行われました。 調査結果から、今後の高校運動部活動のあり方や地域スポーツとの連携を考える上で役立つデータを提供することを目指しています。 特に、全国大会で上位常連校でありながら、県内では部員不足により大会開催が危ぶまれる現状など、強化施策における問題点も提起されています。この調査は、そうした課題解決に向けて、現場指導者との連携をどのように進めていくべきかを探るための基礎資料を得ることを目的としています。
2. 体力測定項目と方法
体力の測定は、身体の形態面(身長、体重、胸囲)と機能面(筋力、持久力、敏捷性、瞬発力、柔軟性)で行われました。機能面の測定には体力診断テストと運動能力テストが用いられ、ラグビー競技に必要な項目がピックアップされました。 特に、ラグビー競技の特性であるコンタクトプレーを考慮し、全身的な筋力と体重の重要性に着目。日本ラグビーフットボール協会のラグビー体力科学研究班による「破壊力の指標」(体重×背筋力)を用いた分析も行われました。 具体的には、反復横とび(Side step)、垂直とび、背筋力、握力(左右平均)、立位体前屈などのテスト項目を用いて、滋賀県内高校と他府県高校の選手を比較しています。これらの測定データは、競技力向上、そして選手の安全確保に欠かせない身体的条件を客観的に評価するための重要な指標となります。
3. 滋賀県と他府県高校の体力比較結果
調査の結果、他府県高校と比較して、滋賀県内高校の選手は身長、体重、胸囲、背筋力、握力、1500m走、柔軟性など多くの項目で有意な差が見られました。特に、全身的な筋力を示す背筋力と、呼吸循環機能の持久力を示す1500m走では、他府県高校の選手に大きく劣ることが明らかになりました。 一方、反復横とびにおいては、滋賀県高校の平均値が他府県を上回っていました。 また、破壊力(背筋力×体重)についても、他府県高校の選手が滋賀県高校の選手を大きく上回っており、特に八幡工業高校を除く県内高校の選手は、他府県選手に比べて数値が低い傾向が見られました。 この結果から、滋賀県内高校ラグビー選手の体力向上のためには、筋力、特に背筋力と持久力の強化が重要な課題であることが示唆されました。八幡工業高校は県内では例外的に他府県と遜色のない数値を示していました。
4. 各体力要素の詳細分析と考察
各体力要素について詳細な分析を行い、その結果を考察しています。例えば、瞬発力を測る20m走では、八幡工業高校が他校を大きくリードしていましたが、他の県内高校は他府県校に劣っていました。全身的持久力を測る1500m走においても、他府県校が滋賀県内高校を大きく上回っており、60分間の試合を戦い抜くための持久力強化の必要性が示唆されました。 筋持久力に関しても、他府県高校が優れており、県内高校における筋力トレーニングの必要性が改めて示されました。 さらに、握力についても他府県高校の方が平均値が高く、ボールハンドリング技術向上のためにも握力の強化が必要であることがわかります。柔軟性に関しても、他府県高校と比べて低い数値を示しており、練習前後のウォーミングアップやクーリングダウンの重要性が強調されました。
II.ラグビー競技特性と体力トレーニング
ラグビーは80分間の激しいコンタクトプレーを伴うスポーツであり、筋力、瞬発力、持久力のバランスが不可欠です。コンタクトプレー(タックル、スクラム、モールなど)の頻度が高いため、身体的危害防止の観点からも、適切な体力トレーニングが重要です。世界のラグビー先進国では、体力(fitness)の研究が盛んであり、持久力、ダッシュ力、筋力などをバランスよく向上させるトレーニング方法が用いられています。本研究でも、ゲームに要求される体力に着目し、トレーニング方法の改善について考察しています。
1. ラグビー競技の特性と体力要件
ラグビーは、15人という多人数が激しくぶつかり合うコンタクトスポーツです。タックル、スクラム、モールなど、激しい身体接触を伴うプレーが頻繁に発生するため、一般的に危険なスポーツというイメージが強く、部活動への参加率低下が懸念されています。 競技時間中は、ボールを持って走る(running)、ボールをキャッチ・パスする(handling)、ボールを蹴る(kicking)といった基本的なプレーに加え、これらのコンタクトプレーが繰り返し行われます。 そのため、激しい衝撃や心理的なプレッシャーに耐え抜き、レフリーの笛が吹かれるまでプレーを継続するための体力、そして身体的危害の防止のための体力、両面を兼ね備えた、精神面を含む総合的な体力トレーニングが不可欠です。 このため、持久力、瞬発力、筋力、そして柔軟性など、多様な体力要素のバランスが求められます。
2. 世界と日本のラグビーにおける体力トレーニング
1970年代頃から、世界各国ではラグビーにおける「fitness(体力)」の重要性が認識され、継続的な研究が行われています。 例えば、Rugby UnionのBetter Rugbyでは、ゲーム中のボール継続性のために走力(持久性、ダッシュ力)を養うことの重要性が指摘され、技術練習にfitnessを組み込む方法が提案されています。 南アフリカのLzakvan Heerdenは、「Tactical and Attacking Rugby」において、従来単なる身体接触という意味で使われてきた「physical contact」という言葉が、現代ラグビーではタックル、スクラム、ラック・モールなど接触プレー全般を指すようになり、相手を倒してボールを奪い、前進して得点する技能とさえ言われるようになったと述べています。 ウェールズの代表選手でもあったBrian OnesとIan Bennettは「Rugby Under Pressure」において、従来日本ではシーズン中の体力トレーニングの重要性が軽視されていたのに対し、シーズンとプレシーズンに分けたトレーニング計画を提唱し、シーズン中も体力トレーニングの必要性を強調しています。この方法は現在広く用いられています。
3. 日本のラグビーにおける体力トレーニングの現状と課題
日本においても、1966年以来、日本協会の代表チーム強化委員会とスポーツ科学研究班が連携し、体力測定やトレーニング処方の研究が継続的に行われています。 トレーニング処方においては、「ラグビーゲームに要求される体力とは何か」を主眼に、医学、運動生理学、心理学、測定評価などの分野からの科学的なアプローチがなされ、成果が出始めています。 しかし、ワールドカップなどの国際レベルの試合を見ると、さらに多角的な視点からの構築が必要であると指摘されています。 具体的なトレーニング方法として、ゲーム中のスクラム、ラインアウト、ラック・モール、ペナルティなどの回数を分析し、strength(筋力)、speed(速度)、stamina(持久力)の3Sを強調するトレーニング方法や、ボールを持たずにゲームを行うトレーニングなどが提案されています。 これらのトレーニング方法を参考に、個々の選手に合わせたトレーニング処方の工夫が必要になります。
III.心理的競技能力とメンタルトレーニング
本研究では、心理的競技能力(競技意欲、精神の安定、集中力など)についても調査を実施しました。その結果、他府県選手と比較して滋賀県選手は、自己コントロール能力や集中力に差が見られました。ラグビー経験年数との関係についても分析し、経験年数5年以上の選手の方が、多くの項目で高い数値を示す一方で、協調性では5年未満の選手の方が高い数値を示すという興味深い結果が得られました。今後、メンタルトレーニングの重要性が増すことが予想されます。
1. 心理的競技能力の定義と測定
本研究では、ラグビー選手のパフォーマンスに影響を与える心理的側面を明らかにするため、徳永らの研究に基づき「心理的競技能力」を調査しました。 徳永らは「精神力」を競技意欲、精神の安定・集中、自信、作戦能力、協調性の5因子に分類し、さらに忍耐力、闘争心、自己実現意欲、リラックス能力、集中力、自信、決断力、予測力、判断力、協調性の12尺度で構成される尺度を用いて分析を行っています。本研究では、この尺度に加え「自己コントロール能力」を含め、計10項目を2倍に換算した10点満点で、滋賀県内3校と他府県5校の計8校を対象に調査を行いました。 欧米では、このような能力は「心理的スキル(技術)」と呼ばれ、トレーニングによって向上させる能力であると捉えられています。 この調査により、選手たちの競技意欲、精神的安定性、集中力、作戦遂行能力、そしてチームワークといった要素を多角的に評価し、メンタルトレーニングの必要性を検証することを目的としています。
2. 滋賀県と他府県高校の心理的競技能力比較
調査結果によると、競技意欲(忍耐力、闘争心、自己実現意欲、勝利意欲)は、滋賀県と他府県ともに高い数値を示しました。しかし、精神の安定・集中に関する項目、特に自己コントロール能力と集中度においては、他府県高校の選手の方が高い数値を示す傾向が見られました。 作戦思考度に関しても、滋賀県と他府県ともに低い数値となっており、高校生の心理状態においては状況判断能力が低い可能性が示唆されています。 この結果は、滋賀県内高校ラグビー選手のメンタルトレーニングの必要性を強く示唆するものです。 単純な体力だけでなく、心理的な側面も競技力向上に大きく影響していることがわかります。 これらの分析結果は、今後のメンタルトレーニングプログラム開発や指導法改善に役立つ重要な知見となります。
3. ラグビー経験年数と心理的競技能力の関係
ラグビー経験年数(5年以上と5年未満)による心理的競技能力の比較も行われました。 競技意欲に関する質問(忍耐力、闘争心、自己実現意欲)では、経験年数による差はほとんど見られませんでした。しかし、勝利意欲においては、5年未満の選手よりも5年以上の選手の方が有意に高い数値を示しました。 精神の安定・集中に関する項目では、大きな差は見られませんでしたが、集中度においては5年以上の選手の方がわずかに高い数値を示しました。 全体的には、ラグビー経験5年以上の選手の方が高い心理的競技能力を示す傾向が見られましたが、意外にも協調性においては5年未満の選手の方が高い得点を得ており、チームワークの重要性を考慮すると興味深い結果と言えます。 この結果は、経験年数に応じたメンタルトレーニングプログラムの必要性、そしてチームワークの育成の重要性を示唆しています。
IV.高校ラグビー部活動の現状と課題
高校ラグビー部活動を取り巻く現状として、部員獲得の困難さ、特にFWの選手不足が大きな課題となっています。また、練習環境(グランドの芝化など)や予算不足、指導者不足なども問題視されています。普及のためには、小中学校でのタグラグビーの導入や、マスコミを通じたラグビーの広報活動が有効と考えられます。将来的には、欧州型クラブ制への移行や地域スポーツとの連携強化も検討されるべきでしょう。八幡工業高校は県内トップレベルのチームですが、他校の競技力向上と底辺拡大のためには、更なる努力が必要です。
1. 部員獲得の困難さ
高校ラグビー部活動における最大の課題は部員獲得の困難さです。 特にFW(フォワード)の選手不足は深刻であり、指導者たちは体格や体力のありそうな生徒を中心に、様々な方法で勧誘活動を行っているのが現状です。 多くの学校が部員確保に苦労しており、ある県では春季新人戦において、1校を除き15人以上の部員数を満たす学校がなく、大会自体が開催されない事態も発生しています。 これは、ラグビーが一般的に危険なスポーツというイメージが強く、参加率の低下につながっていることを反映していると考えられます。 部員数の減少は、チーム編成や練習の質にも影響を与え、競技力向上への大きな障壁となっています。 小中学校レベルではスポーツ少年団やスクール、クラブ活動への参加が多いことから、学校と地域社会の連携によるスポーツクラブのあり方、方向性について議論する必要性も示唆されています。
2. 体力トレーニングの現状と課題
60分間のラグビーゲームを戦い抜くための体力作りとして、インターバルやサーキットトレーニングなどの有酸素トレーニングと、筋力・パワーを養成するための無酸素トレーニングを重点的に行っている学校が多いことが報告されています。 しかし、具体的なトレーニング内容については、さらなる調査が必要とされています。 調査協力校の多くは、怪我防止の観点から、練習前後のウォーミングアップとクーリングダウンを徹底している他、特にFWは頚部周辺の筋力トレーニングを実施するなど、安全面にも配慮した指導が行われていると報告されています。 しかし、県内高校と他府県高校との体力比較結果から明らかなように、現状のトレーニング方法では、他府県校のレベルに到達するには不十分であることが示唆されています。 より計画的で効果的なトレーニングプログラムの開発と実践が求められています。
3. 高校ラグビーの未来に向けた提言と課題
高校ラグビーの将来的な発展のためには、いくつかの重要な課題と提言が挙げられています。 まず、競技の特性上、怪我防止の観点からグランドの芝化が強く望まれています。 また、底辺拡大と普及のためには、テレビやマスコミを活用したラグビーの広報活動や、小中学校におけるタグラグビーの導入が提言されています。 さらに、施設面では、グランドの利用状況や将来的な整備(各市町村への多面的なグランド・体育館の増設)が課題となっています。 予算面では、スポーツ関係予算の増額や、県体協、高体連、県ラグビー協会など関係方面からの強化費の増額が望まれています。 その他、教員の部活動への関与が困難になっている現状を鑑み、高校のクラブを学校組織から切り離す、欧州型クラブ制への移行といった意見も出ています。地域と学校の連携についても、より具体的な議論が必要であると指摘されています。
