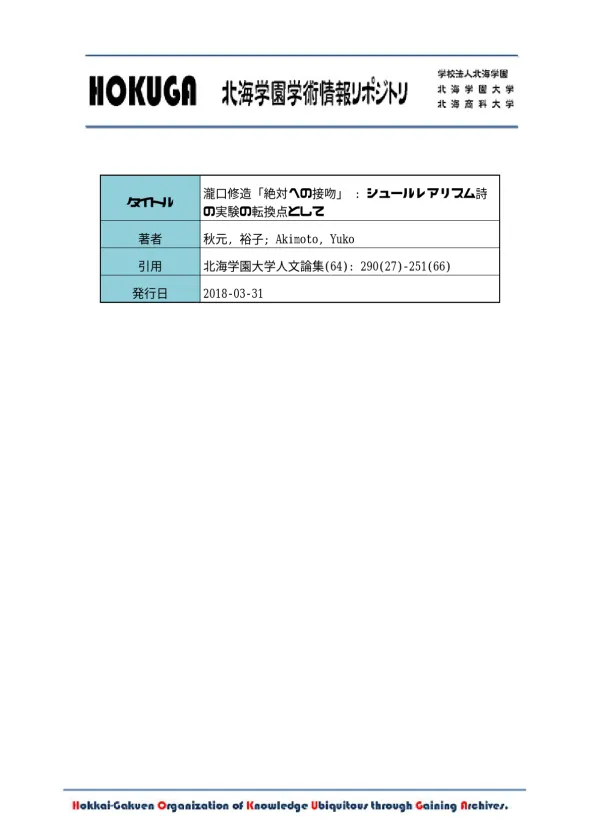
瀧口修造「絶対への接吻」:シュールレアリスム詩の転換点
文書情報
| 著者 | 秋元 裕子 |
| 学校 | 北海学園大学 |
| 専攻 | 人文科学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.76 MB |
概要
I.瀧口修造のシュールレアリスム受容と 絶対への接吻
本論文は、詩人瀧口修造のシュールレアリスムへの関わり、特に代表作『絶対への接吻』(1931年)における詩的実験の転換点を分析する。瀧口修造は1920年代後半からフランスのシュールレアリスム運動に深く関与し、自動記述などの技法を用いた詩作を行った。論文では、瀧口修造が『絶対への接吻』発表前後でシュールレアリスムへの熱狂がピークに達し、その後、シュールレアリスム運動の変遷や思想的転換、自身の内的葛藤などを背景に、詩作スタイルを変化させた過程を考察する。重要な人物として、西脇順三郎(瀧口のシュールレアリスム紹介者)、ブルトン(シュールレアリスム運動の中心人物)、そして『衣装の太陽』(瀧口が参加したシュールレアリスム同人誌)のメンバーらが挙げられる。
1. 瀧口修造とシュールレアリスムとの出会い
瀧口修造は1923年、慶應義塾大学在学中に一度は退学するものの、1925年に復学し、翌年から文学部で学ぶ。帰朝したばかりの西脇順三郎氏を通じてフランスのシュールレアリスムの詩に触れ、1927年にはブルトンとスーポーの『磁場』、ブルトンの『シュールレアリスム宣言』、『失われた足跡』、エルュアールの作品を入手し、徐々に影響を受けるようになる。西脇順三郎の講義を通してシュールレアリスムと本格的に出会ったのはこの頃である。 1920年代後半から、瀧口はフランスを中心とするシュールレアリスム運動の理念と作品を積極的に受け入れ、その詩作に反映させていく。 この頃の瀧口は、シュールレアリスムの自動記述の方法、つまり理性による制御を振り払い、思考よりも速くイメージを表現し書き留める手法に傾倒していた。疾走する白雲、突然飛び立つ鳥、絶え間なく揺れる葦など、次々と湧き出てくるイメージが詩の特徴として挙げられる。
2. 衣装の太陽 とシュールレアリスム運動への参加
1928年11月から1929年7月にかけて、富士原清一が発起人となり、瀧口修造が編集者として参加した同人誌『衣装の太陽』(のちに『L’Evolution surréaliste』と改題)が刊行された。この雑誌は、フランスのシュールレアリスム機関誌『La Révolution surréaliste』の影響を受けており、表紙には『L’Evolution surréaliste』と記され、超現実主義を標榜していた。 参加メンバーには、瀧口修造、西脇順三郎、上田保、山田一彦、中村喜久夫、三浦孝之助、北園克衛、上田敏雄、佐藤直彦、友谷静栄らがおり、それぞれがシュールレアリスム的な作品を発表していた。 しかし、1929年にはシュールレアリスムの観念的規定と芸術との奇妙な混合、あるいは現実と超現実の関係の認識の困難さなどを巡って、同人誌のメンバー間で対立が生じ、グループは分裂に向かう。1929年から1930年頃には、瀧口のシュールレアリスムへの心酔は最高潮に達していたと言えるが、同時に、運動内部での摩擦や対立も深刻化していたことがわかる。
3. シュールレアリスム運動の変遷と瀧口の葛藤
1930年前後、フランスのシュールレアリスム運動は思想的な激変を経験し、第二期的な活動に入っていた。日本ではプロレタリア芸術が台頭し、シュールレアリスムへのリアリズム的重圧が極点に達していた。 1930年11月の第二回国際革命作家会議では、ブルトンによる第二宣言(至上点の提唱)を巡って、共産党指導の芸術を支持する者と、芸術の自由を訴える者との間で激しい対立が生じた。 この様な国内外のシュールレアリスム運動を取り巻く状況、芸術理念と思想上の変化、そしてマルクス主義への傾斜などを受け、瀧口は1930年頃を「身ぶるいを覚えるほどの孤独の時代」と振り返っている。 シュールレアリスム運動への心酔はピークを過ぎ、1932年には経済的困窮から脱するため、映画製作の機構(PCL)に入社する。シュールレアリスムの芸術運動とは直接関係のない仕事に就き、映画製作に没頭するようになる。
4. 絶対への接吻 発表と詩的実験の終焉
1931年1月、瀧口は『絶対への接吻』を発表する。これは、彼にとってシュールレアリスム詩における実験の転換点と捉えられている。 それまで瀧口は、シュールレアリスム詩法である自動記述を用いて、自身の内的世界からイメージを引き出し、言葉として定着させる方法を追求していたが、『絶対への接吻』ではその手法を放棄している。 安藤元雄は、『絶対への接吻』において瀧口の詩的実験は終わったと主張している。論文では、この詩作スタイルの変化の背景として、瀧口自身のシュールレアリスムへの心酔のピークを越え、運動のマルクス主義への傾斜への戸惑い、そしてシュールレアリスム詩・詩法に対する疑問を抱いたことなどを考察する。 しかしながら、シュールレアリスムの写真、絵画、オブジェなどへの関心は依然として高く維持されていたことも事実である。
II. 絶対への接吻 における錬金術的イメージ
『絶対への接吻』は、シュールレアリスム的な自動記述とは異なる新たな詩的表現を示す転換点の作品である。論文では、この詩作に顕著な錬金術的イメージに着目し分析する。特に、「彼女」という人物像が、水、土、火、気といった四大元素や、錬金術における「エーテル」といった概念と結びつき、物質の変成、死と再生といった象徴的なイメージを想起させることを論じる。 錬金術における色の変化(黒→白→黄→紫紅色)が、「彼女」の変容に重ね合わされ、絶対への到達過程が表現されていると解釈される。重要なキーワードとしては、錬金術、四大元素、エーテル、哲学者の卵などが挙げられる。
1. 絶対への接吻 における 彼女 のイメージと四大元素
『絶対への接吻』の冒頭には、「滝の飛沫に濡れた客間に襲来する一人の純粋直観の女性」という記述があり、この「彼女」のイメージが作品の中心となっている。 この「彼女」は、ダイヤモンドを光らせ、時間を燃やし、暴風を象徴するなど、水(滝の飛沫)、土(ダイヤモンド)、火(燃焼)、気(暴風)の四大元素と密接に結びついていると解釈できる。岡田隆彦は、この「彼女」を「いまひとつ元素的な、人間的要素としての性愛が対象化される現場」と表現し、詩の核心に迫っている。 「彼女」は単なる女性像ではなく、四大元素を媒介とした、より根源的な存在、あるいは「絶対」への到達過程を象徴する存在として捉えることができる。この詩において「彼女」は、瀧口の内的世界、あるいは「絶対」を表現する重要な象徴として機能している。
2. 錬金術的世界観と 彼女 の変容
「彼女」は、賽の目のように、白や紫に変化するなど、その姿形が流動的である。これは錬金術における物質の変成過程を想起させる。 錬金術では、色の変化は実験の進展を表わし、物質の変成を映し出すものとされている。黒色化、白色化、黄色化を経て、最終的に紫紅色化に至る過程は、金属の完全な状態への変成を意味する。 「彼女」の白や紫への変化は、錬金術におけるこの変成過程に照らし合わせることができる。また、「彼女の胴は、相違の原野で、水銀の墓標が妊娠する」という表現は、死と再生、あるいは錬金術における「哲学者の卵」を想起させ、完全な物質への変化を暗示していると考えられる。 「彼女」の妊娠は、単なる生殖の意味にとどまらず、錬金術における物質の変成、創造の過程を象徴的に表現している可能性がある。
3. 錬金術における エーテル と 彼女 の性質
「彼の女は硝子体の中の稲妻」という表現は、ガラス容器に封じ込められたエーテルが発光しているような錬金術的なイメージを喚起させる。 錬金術においてエーテルは第五元素とされ、アリストテレスは、四大元素(火、空気、水、土)では世界の全てを説明できないと考え、それらを超えた基本的な物質としてエーテルを導入した。 澤井繁男は、四大元素は第一質料と知覚世界の事物の中間的存在であると説明し、アリストテレスがエーテルを第五元素として位置付けた背景を解説している。 「彼女」は、硝子体の中の稲妻という表現からも分かるように、ガラスの容器に封じ込められたエーテルのような、捉えがたい、先験的な性質を持つ存在として描写されていると考えられる。
4. 錬金術的イメージと瀧口の詩的表現
「絶対への接吻」における錬金術的イメージは、瀧口が単に錬金術の知識を引用しただけでなく、その世界観を基に、捉えがたい「絶対」という概念を表現しようとしたことを示唆している。 「第一質料プリマ・マテリア」は、錬金術師によって様々な名前が与えられたように、瀧口にとっての「絶対」も、言葉やイメージを媒介することでしか捉えられない、流動的な存在だったと言える。 瀧口自身は、錬金術的思想が次第に先験的思惟の範疇から離れていったことを認め、象徴の罪悪や反応の観念的倒錯といった弊害を批判している。 しかし、それは同時に、瀧口が言葉とイメージの限界、そして「絶対」を表現することの困難さを自覚していたことを示していると言える。
III.瀧口修造の詩的実験 自動記述からの脱却
論文は、瀧口修造が『絶対への接吻』において、それまでのシュールレアリスム的な自動記述、つまり思考よりも速くイメージを書き留める手法を放棄した理由を考察する。これは、シュールレアリスム運動におけるマルクス主義への傾斜や、運動内部の分裂、そして瀧口修造自身のシュールレアリスムに対する心酔のピークを越えたことなどに起因すると分析する。 『絶対への接吻』以降、瀧口修造は、より洗練され、錬金術的な世界観に基づいた、新たな詩的表現へと移行したと結論付けている。
1. 自動記述を中心とした初期の詩的実験
瀧口修造は1920年代後半からシュールレアリスム運動に深く関わり、その詩作において自動記述を積極的に取り入れていた。自動記述とは、理性的な制御を排し、思考よりも速くイメージを言葉として書き留める技法である。 この手法を用いた瀧口の詩は、疾走する白雲や突然飛び立つ鳥といった、鮮烈で非日常的なイメージが特徴的であった。 『衣装の太陽』などの同人誌を通して発表された作品群は、シュールレアリスム的な自動記述を基盤とした実験的な詩作と言える。この時代、瀧口はシュールレアリスムに深く傾倒しており、その詩的実験は、到達できない「白熱の一点」を目指す「白熱への詩法」として捉えることができる。
2. シュールレアリスム運動の変遷と詩法への影響
しかし、1930年前後、フランスのシュールレアリスム運動は思想的な激変を経験し、マルクス主義への傾斜が強まっていった。日本でもプロレタリア芸術の隆盛など、社会情勢の変化がシュールレアリスム運動に影響を与えた。 『衣装の太陽』の活動停止も、この時代のシュールレアリスム運動の衰退を反映している。 運動内部における様々な摩擦や対立、そして共産党からの圧力なども、瀧口の詩作に影響を与えたと考えられる。 瀧口自身も、この時代のシュールレアリスム運動を巡る状況、そして自身のシュールレアリスムへの「心酔」のピークが過ぎたことなどを、後年、孤独な時代として回顧している。
3. 絶対への接吻 における詩的実験の転換点
1931年1月発表の『絶対への接吻』は、瀧口の詩的実験における重要な転換点であるとされる。 この作品では、それまでの自動記述によるイメージの連鎖的な表現ではなく、新たな詩的表現が試みられている。 安藤元雄は、『絶対への接吻』をもって瀧口の詩的実験は終わったと主張している。 この変化の背景には、シュールレアリスム詩法への疑問、運動の変遷、そして瀧口自身の内面的な変化などが考えられる。 論文では、『絶対への接吻』の分析を通して、瀧口がなぜ自動記述という手法を放棄したのか、そしてその後の詩作スタイルにどのような変化が生じたのかを明らかにしようとしている。
4. 自動記述からの脱却と新たな詩的表現
『絶対への接吻』以降、瀧口の詩作スタイルは、それまでのシュールレアリスム的自動記述とは異なるものとなる。 岩崎弥子は、瀧口がイメージの世界への耽溺から脱却し、詩の文体を変えたと指摘している。 具体的には、従来のタイトルで言葉を連綿と並べてイメージを描く手法から離れ、より簡潔で、錬金術的世界観に基づいた表現へと変化していったと言える。 しかしながら、瀧口のイマジネーションへの探求は生涯にわたって続けられ、その探求の方法が変化しただけで、イマジネーションへの憧憬が失われたわけではない。 『絶対への接吻』は、瀧口の詩的実験の到達点であり、同時に新たな出発点であったと言えるだろう。
