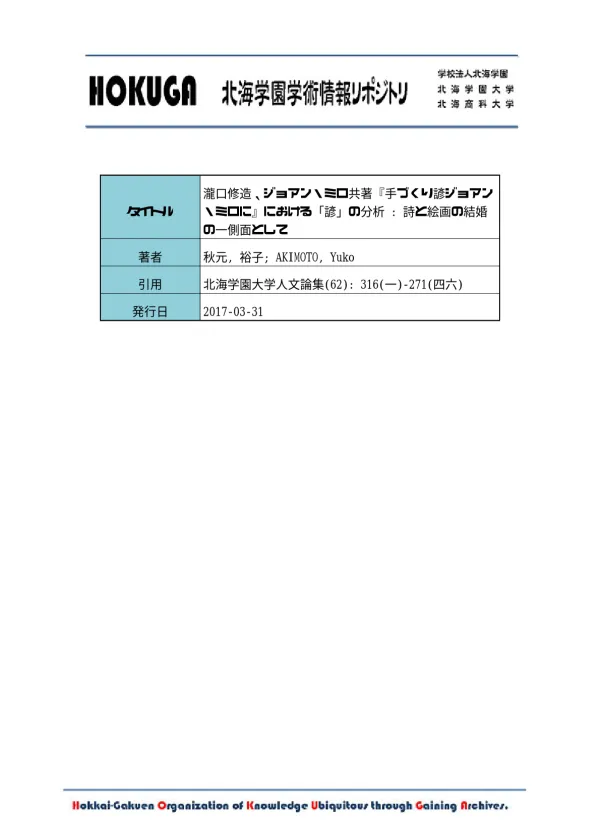
瀧口修造とミロの「諺」:詩画集の深層分析
文書情報
| 著者 | 瀧口修造 |
| 専攻 | 美術史、比較文学、または関連分野 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.20 MB |
概要
I.瀧口修造とジョアン ミロの共著 手づくり諺ジョアン ミロに における 諺 の分析
本論文は、詩人瀧口修造と画家ジョアン・ミロの共著『手づくり諺ジョアン・ミロに』を分析対象とし、作品の中核をなす「諺」に焦点を当てています。特に、シュールレアリスムの影響下にある両者の芸術的表現、そして詩と絵画の融合という観点から、「諺」の持つ意味や機能を考察しています。瀧口修造の病中における創作という文脈も考慮され、その独特の表現形式と、ミロのリトグラフとの関係性も分析されています。
1. 諺の生成背景と制作過程
この節では、瀧口修造とジョアン・ミロの共著『手づくり諺ジョアン・ミロに』に収録されている「諺」の創作背景と制作過程が詳細に分析されています。1969年の脳卒中以降、瀧口修造は「曖昧な諺」というラベルを貼ったノートに日々の言葉を書き留めていました。このノートの中から、ミロの要望である短い句に合致するものが選ばれ、選定された諺を受け取ったミロは、手づくり諺に掲載するリトグラフを制作したことが記されています。 スペインの独裁政権への抵抗を示していたミロに関する本の出版という政治的背景、そして、それぞれの芸術的行程に対する感慨やブルトンへの追憶が、この「諺」の創作に影響を与えていると示唆されています。 つまり、本書における「諺」は、単なる言葉の集積ではなく、両者の複雑な人生経験と芸術的信念が凝縮された、深い意味を持つ表現形式であると言えるでしょう。 ミロの依頼と、瀧口の病中における創作という特殊な状況も考慮に入れながら、この「諺」の特異な性質が丁寧に解説されています。
2. 諺の性質と詩画の融合
この節では、「諺」の形式、特に詩と絵画の融合という点に着目し、その性質を多角的に分析しています。 岡田による解釈では、諺は単なる記号を超えた、通貨のような普遍的なものと説明されており、瀧口とミロ両者にとっての詩画集は、揺るぎない芸術的立脚点を示すものと位置付けられています。1936年の瀧口の詩と絵画に関するエッセイでは、詩と絵画の交流の必要性と想像力の重要性が強調されており、これは「諺」の創作にも通じる思想と言えるでしょう。 また、1929年に瀧口が初めてミロについて言及した際の、ダダイズムを揺籃として生まれたシュールレアリスムの歴史的経緯と、その芸術運動の組織化・発展への貢献も考察されています。両者の内省的な性格や精神の自由を尊ぶ純粋さといった人柄の共通点も指摘され、これらの要素が「諺」という表現形式に反映されていることが示されています。
3. 瀧口修造とジョアン ミロの芸術的特徴と 諺 への反映
この節では、瀧口修造とジョアン・ミロそれぞれの芸術的特徴が分析され、それらが「諺」にどのように反映されているかが考察されています。 瀧口修造の芸術的特徴として、「すべての無用のものを剥ぎ取る除去作用」という表現が挙げられています。これはノアの大洪水以前の状態への憧憬、善悪を知る以前の人間性、あるいは洪水後に不純なものが一掃された澄明な世界への憧れを表していると考えられています。 一方、ミロの芸術的特徴として、「大洪水前期を夢見るような澄明なグラフィズム」が指摘されています。これは、ジョルジュ・ユリエによる比喩表現を明記した上で解説されています。 また、瀧口が描いたオートマティスムによるデッサンの意義や、天地創造の瞬間への希求、ミロにおける人間が善悪を知る以前の世界(大洪水の後)といったイメージが、両者の「諺」における共通のテーマとして扱われています。これらの芸術的特性が、「諺」という表現形式を通してどのように融合し、独特の世界観を構築しているのかが分析の焦点となっています。
II. 諺 の性質と詩画両者の芸術的視座
分析では、「諺」が単なる言葉の羅列ではなく、詩と絵画を繋ぐ象徴的な存在であることが示唆されています。瀧口修造の表現は、簡潔ながらも奥深い比喩を用い、ミロの絵画との共鳴関係を形成しています。両者の共通点は内省的な性格や精神の自由への希求であり、それらが「諺」という形式を通して具現化されていると論じています。シュールレアリスムやダダイズムといった前衛芸術運動との関連性も分析の重要な要素となっています。
1. 諺の形式と詩画融合の表現
この小節では、『手づくり諺ジョアン・ミロに』における「諺」の形式と、詩と絵画の融合という観点からの分析が行われています。 「諺」は単なる言葉の羅列ではなく、詩と絵画を繋ぐ象徴的な存在として捉えられています。 岡田の同エッセイにおける解釈では、「諺」は「通貨のような通り一遍の記号を超えたもの」と説明されており、記号以上の意味、すなわち詩と絵画の融合による新たな表現の可能性が示唆されています。 瀧口とミロ両者にとって、この詩画集はそれぞれの揺るぎない芸術的立脚点を示すものであり、両者の芸術的視座が「諺」という表現形式を通して具現化されている点が強調されています。 簡潔な言葉の中に込められた奥深い比喩表現と、ミロのリトグラフとの相関関係が、詩と絵画の融合という観点から分析されています。
2. 瀧口修造とジョアン ミロの芸術的共通点と相違点
この小節では、瀧口とミロ両者の芸術的共通点と相違点が、「諺」という作品を通して分析されています。 両者には、内省的な性格や精神の自由を尊ぶ純粋さといった共通点が見られます。 しかし、ミロが必ずしもシュールレアリスムの芸術理念を重視していたわけではない点、そして瀧口の「すべての無用のものを剥ぎ取る除去作用」という表現方法などは、両者の相違点として挙げられています。 瀧口の「除去作用」は、ノアの大洪水以前の状態への憧憬や、善悪を知る以前の人間性、あるいは洪水後に不純なものが一掃された澄明な世界への憧憬と解釈されています。 これらの共通点と相違点が、どのように「諺」という表現形式に反映され、独特の詩画集を形成しているのかが考察されています。 両者の芸術的個性が尊重されつつ、共通のテーマによって結び付けられた作品としての「諺」の特異性が示されています。
3. シュールレアリスムとの関連性と芸術的文脈
この小節では、「諺」の芸術的文脈、特にシュールレアリスムとの関連性が分析されています。 1936年の瀧口のエッセイ「詩と絵画」において、詩と絵画の交流の必要性と想像力の重要性が強調されており、シュールレアリスムの理念と深く関わっていると考えられます。 また、1929年に瀧口が初めてミロについて言及した際には、ダダイズムを起源とするシュールレアリスムの歴史的経緯と、その芸術運動におけるミロの役割が示されています。 シュールレアリスムの理念において重要な要素である「理性に制御されている狂気」の存在も言及され、ミロが必ずしもシュールレアリスムの理念に固執していたわけではない点が指摘されています。 これらの考察を通して、「諺」という作品が、シュールレアリスムという芸術的文脈の中でどのように位置づけられるのか、そしてその独自の表現方法がどのように成立しているのかが分析されています。シュールレアリスムの枠組みを超えた独自の表現方法と、その芸術的意義が示されています。
III.瀧口修造とミロの芸術的共通点と相違点
瀧口修造とジョアン・ミロは、それぞれの芸術的立場を固めながらも、詩と絵画の融合という点で共通の志向を持っていました。しかしながら、ミロが必ずしもシュールレアリスムの理念に固執していたわけではない点、瀧口修造の「すべての無用のものを剥ぎ取る除去作用」という表現方法などが、両者の芸術的相違点として挙げられています。大洪水以前の理想郷への憧憬といった共通のテーマも分析されています。
1. 共通の芸術的志向 詩と絵画の融合
瀧口修造とジョアン・ミロは、それぞれ異なる表現方法を持ちながらも、詩と絵画の融合という共通の芸術的志向を持っていたことが指摘されています。 瀧口は1936年のエッセイにおいて、詩と絵画の交流の必要性、そして想像力の重要性を強調しており、これはミロとの共著『手づくり諺ジョアン・ミロに』における「諺」の創作にも通じる思想と言えるでしょう。 両者にとって、この詩画集は、それぞれの揺るぎない芸術的立脚点を固めていることを示すものであり、詩と絵画という異なる表現方法を融合させることで、新たな表現の可能性を探求する姿勢が共通していました。 内省的な性格や精神の自由を尊ぶ純粋さといった、人となりにおける共通点も指摘されており、これらの共通した精神性が、両者の作品世界、そして「諺」という独特の表現形式に反映されていると推察できます。
2. 芸術的相違点 表現方法とシュールレアリスムへの関わり
一方、両者の間には、表現方法やシュールレアリスムへの関わり方といった点で、いくつかの相違点も見られます。 瀧口修造の芸術的特徴として、「すべての無用のものを剥ぎ取る除去作用」という表現方法が挙げられています。これは、ノアの大洪水以前の状態への憧憬、善悪を知る以前の人間性、あるいは洪水後に不純なものが一掃された澄明な世界への憧れといった、ある種の理想郷への志向を表していると考えられます。 対して、ミロの芸術的特徴は「大洪水前期を夢見るような澄明なグラフィズム」と表現され、ジョルジュ・ユリエの比喩表現を用いて解説されています。 重要な点として、ミロは必ずしもシュールレアリスムの芸術理念を重視していたわけではなく、両者のシュールレアリスムへの関わり方にも違いがあったと考えられます。 これらの相違点は、それぞれの芸術家としての個性を際立たせる要素であり、同時に「諺」という作品において、多様な表現方法の融合と共存が実現していることを示しています。
3. 大洪水という共通の象徴と異なる解釈
「大洪水」という象徴は、瀧口とミロ両者の作品世界において重要な役割を果たしており、共通のテーマとして挙げられます。しかし、その解釈には違いが見られます。 瀧口の「すべての無用のものを剥ぎ取る除去作用」は、ノアの大洪水以前の純粋な状態への憧憬と結びついており、善悪を知る以前の人間性や、洪水後の澄明な世界への憧憬を表すものとして解釈されています。 一方、ミロの「大洪水前期を夢見るような澄明なグラフィズム」は、より視覚的なイメージに重点を置いた表現であると考えられます。 このように、共通のテーマを用いながらも、それぞれ独自の視点と解釈に基づいて表現されている点が、両者の芸術的個性と、詩と絵画の融合による表現方法の豊かさを見事に示していると言えるでしょう。 大洪水という共通の象徴を通して、両者の芸術的共通点と相違点がより明確に浮き彫りになり、それらが「諺」という作品にどのように反映されているかが分析されています。
IV. 諺 における象徴とイメージ
「諺」に用いられている象徴やイメージは、大洪水前後の世界観、善悪を知る以前の人間性、あるいはオートマティスムによる無意識からの湧出といったテーマと深く結びついています。ノアの大洪水や楽園といった聖書的なモチーフ、そしてミロの絵画にみられる独特のグラフィズムも重要な解釈材料となっています。これらの象徴表現を通して、両者はそれぞれの芸術世界を展開し、詩と絵画の結婚という独特な表現形態を確立しています。
1. 大洪水前後の世界観と人間の心性
この小節では、「諺」に用いられている象徴やイメージが、大洪水前後の世界観や人間性の考察と深く関わっていることが分析されています。 瀧口修造の「すべての無用のものを剥ぎ取る除去作用」という表現は、ノアの大洪水以前の状態、すなわち善悪を知る以前の人間性への憧憬、もしくは洪水後に不純なものが一掃された澄明な世界への憧れを表していると解釈されています。 この「除去作用」は、理想的な状態、あるいは原初的な状態への回帰願望を象徴的に表現していると言えるでしょう。 ミロの絵画における「大洪水前期を夢見るような澄明なグラフィズム」も、同様の世界観を共有しており、詩と絵画が互いに補完しあい、より複雑で多層的な意味を生成していることが示唆されています。 聖書的なモチーフであるノアの大洪水や楽園のイメージが、両者の作品世界において、共通の象徴として機能している点も注目すべきでしょう。
2. オートマティスムと内的世界の開闢
「諺」における象徴とイメージの分析において、オートマティスム(自動記述)という芸術手法も重要な要素となっています。 瀧口が描いたオートマティスムによるデッサンは、「瀧口の内的な世界を開闢させる太初のことば」として、その重要性が示唆されています。 1963年5月に東京画廊で開催された前田常作個展への寄稿文において、瀧口は虹色に輝く真夜中を「影像の母胎であって、存在に満ち溢れたユニークな無」と表現しています。 この表現は、天地創造の瞬間、あるいは無意識からの湧出といった、原初的な創造の過程を想起させます。 ミロの作品においても、いわば人間が善悪を知る以前の世界、もしくは洪水後の澄明な世界が表現されており、これらのイメージは、瀧口のオートマティスムによるデッサンと共鳴し、独特の世界観を構築しています。 これらの象徴的なイメージを通して、両者はそれぞれの芸術世界を展開し、詩と絵画の結婚という独自の表現形式を確立していると言えるでしょう。
3. 象徴表現の多様性と詩画の相互作用
この小節では、「諺」における象徴表現の多様性と、詩と絵画の相互作用が分析されています。 例えば、ヤギを生んでいる女性の性器からの血、足が地面に釘付けにされた状態、必死に前方へ伸ばされた腕といったイメージは、地獄とが一つになり合う世界を想起させます。 これは、最初の女性エバとの間の性的関係性ゆえの罪、楽園の門番であるグリフォンのイメージと関連付けられ、象徴的な解釈が試みられています。 また、小鳥が自身の影像に引き寄せられて鏡にぶつかり命を落とすというイメージや、共棲の星が落ちるというイメージなども、新たな影像の世界を生み出し、詩と絵画の相互作用を通して、無数の「結婚」を生み出している様子が示されています。 これらの多様な象徴表現は、単独では理解できない意味を持つものが、詩と絵画の相互作用によって、新たな意味を生成し、深みのある世界観を構築していることを示しています。 マルセル・デュシャンや杉山悦子などの作品との関連性も示唆されています。
V.関連文献と作品情報
論文では、瀧口修造とジョアン・ミロの関連作品や、シュールレアリスムに関する複数の文献が参照されています。これらを通して、両者の芸術活動の軌跡や、当時の美術界の動向が詳細に示されています。具体的には、瀧口修造の詩集やエッセイ、ミロの絵画、そして両者の共著『手づくり諺ジョアン・ミロに』などが重要な情報源となっています。また、パリや東京での展覧会情報も含まれています。
1. 瀧口修造とジョアン ミロの関連作品
この小節では、瀧口修造とジョアン・ミロの両者の作品が、分析の根拠として示されています。 論文の中心となるのは、もちろん両者の共著『手づくり諺ジョアン・ミロに』です。この作品における「諺」の形式や内容が、綿密に分析されています。 加えて、瀧口修造の詩集やエッセイ、例えば1936年の「詩と絵画」といった作品が、両者の芸術的思想や表現方法を理解する上で重要な資料として参照されています。 これらの作品から、瀧口の詩と絵画に関する考え、想像力の重要性、そしてシュールレアリスムへの関わりなどが読み取れると示唆されています。 また、ミロの絵画についても言及があり、特に「大洪水前期を夢見るような澄明なグラフィズム」という表現が用いられ、ミロの芸術的特徴が解説されています。 これらの関連作品を分析することで、共著『手づくり諺ジョアン・ミロに』における「諺」の意味や、両者の芸術的交流がより深く理解できるとされています。
2. シュールレアリスム関連文献と美術界の動向
この小節では、シュールレアリスムに関する文献や、当時の美術界の動向が、分析の文脈として提示されています。 瀧口修造が1929年にミロについて初めて言及した際の記述が、ダダイズムを揺籃として生まれたシュールレアリスムの歴史的経緯を理解する上で重要だとされています。 また、シュールレアリスム美術の新たな動向を示すエッセイなども参照されており、当時の美術界におけるシュールレアリスムの影響力や、その芸術運動の多様な側面が示唆されています。 さらに、日仏両国のシュールレアリスム文化交流に関する記述があり、その発展に貢献した動きなども紹介されています。 具体的には、1936年9月のパリ・東京新興美術展覧会や、1938年4月に開催されたサルバドール・ダリの個展などが言及されています。 これらの文献や美術界の動向を背景として、瀧口修造とジョアン・ミロの共著『手づくり諺ジョアン・ミロに』における「諺」の意義や、両者の芸術的創造の背景がより深く理解できるとされています。 特に、シュールレアリスムという芸術運動が、両者の作品にどのような影響を与えたのかが分析の重要なポイントとなっています。
3. その他の関連資料と作品情報
この小節では、本文で触れられたその他の資料や作品情報について簡単に触れられています。 具体的には、瀧口修造の『アララットの船 あるいは 空の蜜へ 小さな透視の日々』といった作品集や、西脇順三郎著『超現実主義詩論』といった関連書籍などが挙げられています。 これらは、瀧口修造の詩作や思想、そしてシュールレアリスムに関する更なる知見を得るために有用な資料であると示唆されています。 また、瀧口修造がグッゲンハイム美術館などで壁画制作をしていたことにも触れられています。これらの情報から、瀧口修造の活動範囲の広さと、国際的な美術界との繋がりを推察することができます。 さらに、本文では、瀧口修造の家族に関する記述も含まれています。姉の嫁入りに関する記述は、瀧口修造の私生活の一端を示すものであり、彼の作品世界を理解する上で、間接的に役立つ可能性があると推測できます。 これらの情報は、論文全体の理解を深める補足的な役割を果たしています。
