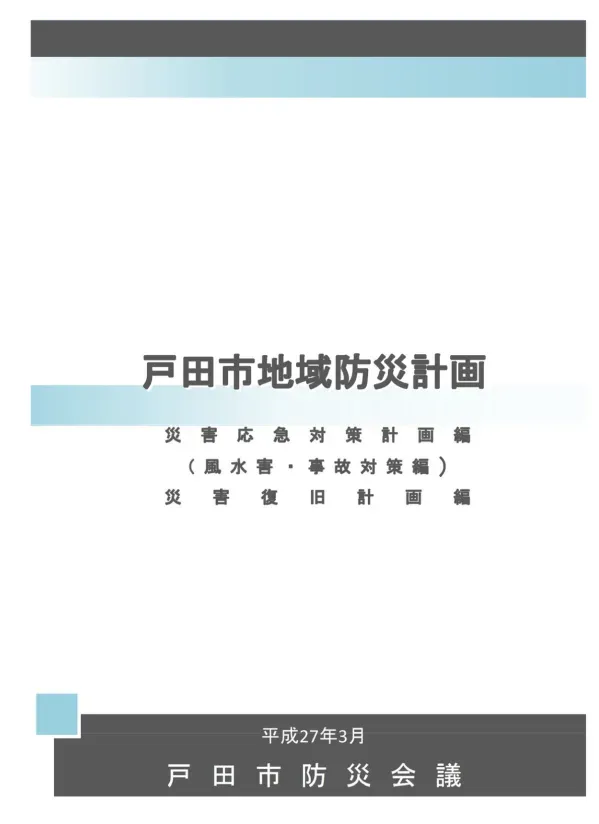
災害対策計画:応急・復旧
文書情報
| 学校 | 大学名(不明) |
| 専攻 | 防災工学、土木工学、環境学など関連分野 |
| 出版年 | 不明 |
| 場所 | 不明 |
| 文書タイプ | 災害対策計画書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.48 MB |
概要
I.風水害対策計画
戸田市地域防災計画では、台風や前線による大雨を想定し、市内各地での【浸水被害】(床下・床上)や中小河川の【溢水・越水】、それに伴う住民避難(避難所の開設・運営)と【帰宅困難者】への対応を計画しています。特に、被害地域が孤立し生活必需品の補給が困難な場合や、多数の生命・身体に被害を及ぼす災害による社会的混乱への対応を重視。災害救助法の適用手続きや緊急消防援助隊への要請手順も明確に示されています。【災害時要配慮者】(高齢者、障害者、乳幼児など)への配慮も重要事項として挙げられています。
1. 風水害による被害想定と対策期間
この計画は、台風や前線等による長期の大雨により、戸田市内で発生する可能性のある大規模な風水害への対策を定めています。市内各地での浸水被害(床下浸水、床上浸水)や中小河川の溢水・越水を想定し、被害規模が大きく、対策期間も長期に及ぶことを前提としています。計画では、広範囲にわたる浸水被害や河川の氾濫による家屋の損壊、それに伴う住民の避難、そして交通機関の混乱による帰宅困難者への対応について、具体的な対策を検討しています。特に、被害を受けた地域が孤立し、生活物資の供給が困難になるケースも想定し、被災者への迅速な救助と物資供給のための特殊な方法についても言及しています。災害の規模と影響範囲を正確に捉え、長期的な視点に立った対策を講じる重要性が強調されています。これは、単なる一時的な対応ではなく、住民生活の早期回復と社会秩序の維持を目的とした包括的な対策を必要とすることを意味します。また、住宅被害の程度に関わらず、多数の人的被害が生じる可能性がある場合、迅速な救助活動が人心の安定と社会秩序の維持に不可欠であると位置付けています。
2. 災害救助法の適用と緊急消防援助隊要請
市域で災害が発生し、災害救助法の適用基準に該当する、または該当する見込みがある場合、市長は埼玉県知事に直ちに報告し、口頭または電話で要請、後日文書で改めて要請を行います。これは、国や県の支援を迅速に得るための重要な手順です。また、災害が市域を広く覆い、近隣の自治体からの消防支援が困難な場合は、埼玉県に緊急消防援助隊の派遣を要請する手順も定められています。この要請は、県との連絡が取れない場合は、直接消防庁長官に要請し、その後埼玉県知事に連絡するなど、迅速な対応を確保するためのバックアップ体制も整備されています。さらに、災害情報伝達に関して、特に緊急を要する場合には、警察専用電話や警察無線設備の使用についても警察本部と協定を結ぶことで、迅速な情報伝達体制を構築することを目指しています。これらの手順は、災害発生時の迅速な対応と効果的な連携を確保するために不可欠な要素として位置づけられています。災害規模や状況に応じて柔軟に対応できるよう、複数ルートの連絡体制を確立することで、迅速な情報共有と的確な判断を下すための基盤が作られています。
3. 非常通信の利用と被害状況調査
地震、台風、洪水など非常事態発生時、有線通信が困難な場合、電波法第52条に基づく非常通信の利用が認められています。この計画では、その利用方法を規定し、人命救助や災害救援、交通通信確保といった緊急時における通信手段を確保することを目的としています。具体的には、鉄道、道路、電力、電気通信設備の被害状況把握や復旧のための資材調達、人員確保、緊急措置などに関する通信が想定されています。さらに、中央防災会議や非常災害対策本部間の情報伝達にも非常通信が活用されます。被害状況の調査については、市内の連携強化を図り、調査漏れや重複を避けるよう努め、相違点があれば報告前に調整するよう定められています。水害による浸水状況の調査は、時刻や現場状況の関係から困難な場合が多いことから、当該地域に詳しい関係者の判定による概況把握と、平均世帯人員による罹災人員の速報が規定されています。道路の被害状況と交通確保の緊急性を考慮した応急復旧順位の設定も重要な要素です。放置車両等の移動に関しても、緊急通行車両の通行空間確保の観点から、市が管理する道路について区間を指定し、車両等の移動を命じる手続きが明確に示されています。
4. 避難所開設 運営と帰宅困難者対策
避難所の開設が決定された場合、避難所指定職員は戸田市役所に参集し、本部長の指示に従って避難所を開設します。指定避難所が被災した場合には、近隣の避難所や公共施設を臨時避難所として確保します。避難所の運営は、内閣府の指針に基づいたマニュアルに従って行われ、高齢者や障害者への配慮、女性へのセクシャルハラスメント対策、相談窓口の設置などが盛り込まれています。避難所開設の報告は、市長から埼玉県知事に行われます。避難所開設状況は住民に広報され、指定避難所以外への避難者集結への対応策も検討されています。さらに、帰宅困難者への情報提供については、県、東日本旅客鉄道株式会社などの関係機関から情報を収集し、防災行政無線やホームページ、メール、SNS等を通じて、鉄道運行状況や市内の被害状況、一時滞在施設の情報などを提供する体制を整えています。鉄道運行停止が長期化する場合は、駅周辺の施設や公共施設を一時滞在施設として開放し、水や食料などの配布、情報提供を行う体制も整備されています。
5. 救出活動と情報伝達体制
住民からの通報や救出要請に基づき、消防署班は消防団と連携して救出チームを編成し、警察や自衛隊と協力して救出活動を行います。大規模水害時の孤立者の把握のため、避難者名簿作成時に安否不明者の情報を早期に把握し、救出活動の準備を行います。要救出者を発見した者は、災害対策本部または蕨警察署に通報します。予防班と消防署班は、通報された情報を収集・管理します。 情報伝達手段としては、防災行政無線、ホームページ、防災情報メール、緊急速報メール、SNSなどを活用し、迅速かつ多角的な情報発信を行い、住民が状況を把握し適切な行動をとれるよう支援します。 特に、傷病者の効率的な救護のため、市、医療機関、警察などの関係機関との連絡体制を密にすることを重視しており、同時に小規模な救助救急事象が発生した場合には、人命の危険度の高い事象を優先的に対応する体制を整備しています。
II.災害時要配慮者の安全確保対策計画
高齢者、障害者、乳幼児など【災害時要配慮者】の避難誘導と支援を重点に置いた計画です。避難行動要支援者の個別計画に基づく避難支援、未作成者への救助体制、福祉避難所への移送、生活救援物資の供給、そして介護やメンタルケア等の巡回サービス実施体制が示されています。【戸田市】では、自主防災会や民生委員などの地域関係者との連携を強化し、迅速かつ適切な支援体制の構築を目指しています。
1. 災害時要配慮者の定義と計画の方針
この計画は、災害発生時に避難や避難生活において支障をきたす可能性のある高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、そして言葉や文化の違いから特別な配慮を要する外国人(これらを総称して「災害時要配慮者」と定義)の安全確保対策を示しています。災害時要配慮者は、災害対応能力が弱く、避難行動や避難生活において困難を経験する可能性が高いと認識されています。そのため、本計画では、これらの要配慮者の安全確保を最優先事項とし、具体的な支援策を提示することで、災害時の混乱の中でも、彼らが安全に避難し、生活を維持できるよう支援することを目的としています。計画は、それぞれの要配慮者の特性を理解した上で、的確な支援を提供するための具体的な方策を提示することを目指しています。これは、単なる避難誘導だけでなく、避難生活におけるケアや、災害後の生活再建への支援を含めた包括的な支援体制の構築を必要とすることを示唆しています。
2. 救助活動の実施と福祉避難所への移送
災害発生時には、自主防災会や民生委員などの避難支援関係者が、個別計画に基づき、避難行動要支援者の避難所への避難誘導と支援を行います。個別計画が未作成の避難行動要支援者については、避難行動要支援者名簿などを活用し、援護班や応急・救出班が消防署班や住民の協力を得ながら在宅救助を実施します。これは、要配慮者一人ひとりの状況を把握し、適切な支援を提供するための重要な取り組みです。また、適切な輸送手段を確保し、自主防災会やボランティア団体の協力を得て、福祉避難所などの受入施設への移送も行われます。これは、避難所における生活環境の確保だけでなく、要配慮者の身体的・精神的な負担を軽減するための配慮であり、安全で快適な避難生活を確保する上で不可欠な要素となります。これらの救助活動は、個々の要配慮者の状況に合わせたきめ細やかな対応が求められ、関係機関との連携強化が成功の鍵となります。迅速かつ効率的な救助活動を行うために、事前に避難行動要支援者名簿の作成や関係機関との連携体制の構築が重要になります。
3. 生活救援物資の供給と相談窓口の設置
援護班は避難行動要支援者の被災状況を把握し、食料、飲料水、生活必需品などを備蓄・調達して供給します。配布場所や時間は一般被災者と区別することで、要配慮者への配慮を示しています。これは、災害時における生活必需品の確保が、特に要配慮者にとって非常に重要であることを示しています。また、福祉保健センターに相談窓口を開設し、職員、福祉関係者、医師、ソーシャルワーカーなどを配置することで、総合的な相談に対応します。この相談窓口は、避難行動要支援者にとって、様々な問題や不安を相談できる場所を提供することで、精神的な支えとなり、安心して避難生活を送る上で重要な役割を果たします。相談内容に応じて、適切な支援や情報提供を行うことで、避難生活の質を向上させ、心のケアにも重点を置いた支援体制を構築することを目指しています。これらの取り組みは、災害時要配慮者の生活の安定と安心を確保するために不可欠な要素です。
4. 巡回サービスの実施
援護班は職員、民生委員、ホームヘルパー、保健師、地域包括支援センターなどからなるチームを編成し、在宅、避難所、応急仮設住宅などで生活する避難行動要支援者のニーズを把握します。そして、事業者と協力し、介護やメンタルケアなどの巡回サービスを実施します。これは、避難生活における継続的な支援の必要性を示しています。特に、要配慮者の中には、高齢者や障害者など、日常生活に支援が必要な人が多くいるため、継続的なケアを提供することは、彼らの健康と安全を守る上で極めて重要です。巡回サービスでは、個々のニーズに合わせた支援を行うため、関係機関との連携が不可欠であり、地域住民との協力体制の構築も重要な要素となります。このサービスによって、避難行動要支援者の生活の質を向上させ、安心して生活できる環境を整備することを目指しています。継続的なモニタリングと柔軟な対応によって、より効果的な支援体制の構築を目指しています。
III.帰宅困難者対策計画
大規模災害発生時の【帰宅困難者】対策として、情報提供(防災行政無線、ホームページ、メール等)、一時滞在施設の確保(駅周辺施設、公共施設など)、代替交通手段の確保などが計画されています。特に、鉄道運行停止が長期化する際の駅前滞留者への対応について、具体的な施設と連携体制を提示。【戸田市】は東日本旅客鉄道株式会社など関係機関と連携し、迅速な情報伝達と支援体制の構築を目指します。
1. 帰宅困難者対策計画の方針
大規模災害発生時には、多くの通勤・通学者などが帰宅困難となることが予想されます。この計画では、事業所における社員の待機呼びかけ、帰宅困難者への適切な情報提供、避難所への一時収容、代替交通手段の確保など、帰宅活動への支援対策を実施することを方針としています。特に、首都圏からの徒歩帰宅者に対する支援として、県と協定を結んでいるガソリンスタンド、コンビニエンスストア、ファミリーレストランなどを災害時帰宅支援ステーションとして活用し、一時滞在施設に加え、幹線道路付近の公共施設を一時休憩所として開放することで、水や食料の提供、情報提供を行います。この計画は、帰宅困難者に対し、安全で迅速な帰宅を支援するとともに、災害時の混乱の中で不安を抱える人々に対して、安心できる環境を提供することを目的としています。そのため、関係機関との連携を密にし、情報伝達手段の多様化、避難場所の確保、生活支援の提供など、多角的なアプローチによる支援体制の構築が求められます。計画の根幹には、帰宅困難者の安全と安心を最優先に考え、そのための様々な対策を講じるという強い意志が示されています。
2. 帰宅困難者への情報提供
帰宅困難者対応班は、県、東日本旅客鉄道株式会社などの関係機関から情報を収集し、防災行政無線、ホームページ、防災情報メール、緊急速報メール、SNSなどを通じて、鉄道運行状況、市内の被害状況、一時滞在施設などの情報を帰宅困難者へ提供します。これは、帰宅困難者が自身の状況を正確に把握し、安全な行動をとるために不可欠な情報提供です。情報伝達の迅速性と正確性は、帰宅困難者対策の成否を大きく左右する重要な要素であり、多様な情報伝達手段を活用することで、より多くの人に情報を届けることを目指しています。情報の内容も、単なる状況報告にとどまらず、帰宅方法のアドバイスや避難場所の情報、生活支援の情報など、帰宅困難者にとって実質的に役立つ情報を提供することで、より効果的な支援を目指しています。これらの情報提供は、帰宅困難者にとっての不安軽減だけでなく、自主的な行動を促し、災害対応の効率化にも貢献すると考えられます。
3. 一時滞在施設の設置
鉄道の運行停止が長期化し、代替交通手段も確保できない場合、鉄道運行再開までの間、駅前に滞留する帰宅困難者を一時的に収容する施設の確保が重要となります。この計画では、駅周辺の協定を結んでいる民間事業者などに、帰宅困難者の一時滞在施設として開設を要請することを定めています。これは、帰宅困難者が安全に過ごせる場所を提供し、疲労や不安を軽減するために不可欠な措置です。一時滞在施設では、休息場所の提供に加え、食料や飲料水などの生活物資の供給、そして最新の情報提供なども行われることが想定されています。これらの対策は、単に一時的な避難場所を提供するだけでなく、帰宅困難者に対して、心理的な支えや生活上の支援を行うことを目的としています。駅周辺施設の活用に加え、必要に応じて公共施設の一時休憩所としての開放も検討されており、柔軟な対応によって、より多くの帰宅困難者に対応できる体制の構築が目指されています。
IV.遺体の捜索 処理及び埋 火葬計画
災害による生死不明者の捜索・救出、死亡者の検視・検案、身元不明者の埋葬・火葬に関する計画です。警察、医師との連携体制、そして必要に応じた【救援物資】の調達・供給体制(県、近隣市町村への要請を含む)についても記載されています。
1. 計画の方針と捜索 救出活動
この計画は、生命に危険のある者や生死不明者の捜索・救出、災害により死亡していると推定される者の収容、そして死亡者に対する警察官による検視と医師による検案、さらに身元不明者の適切な埋葬・火葬を目的としています。災害による人的被害は、その規模に関わらず、大きな社会的影響をもたらすため、迅速かつ適切な対応が求められます。捜索・救出活動においては、生命の危険度が高い者から優先的に対応を行い、迅速な救助体制の構築が不可欠です。また、検視・検案のプロセスは、死因究明だけでなく、遺族への対応や社会的な責任を果たす上でも重要な役割を担います。身元不明者の埋葬・火葬手続きについても、法に基づいた適切な手順に従い、故人の尊厳を保つことが重要な課題となります。これらの活動は、警察、消防、医療機関など関係機関との連携によって円滑に進められるよう、計画において明確な役割分担と連携体制が示されています。
2. 食料供給体制と物資管理
計画では、協定業者だけでは遺体処理に必要な食料供給が不足する場合に備え、県や県内市町村、協定市町村への食料供給要請手順が定められています。これは、災害規模が大きく、広範囲にわたる被害が発生した場合でも、必要な物資を迅速に確保できる体制を構築することを目指しています。また、応急用米穀の確保が困難な場合、県への調達要請、さらには関東農政局や政府食料保管倉庫への緊急引渡し要請を行う手順も明記されています。これは、災害発生時に迅速な食料供給を確保するための多重的なバックアップシステムを構築することを示しています。大規模災害時には、救援物資が大量に搬送されることが予想されるため、戸田市スポーツセンターを物資管理センターとして指定し、物資班がボランティアなどの協力を得て、救援物資の受入れ、品目ごとの整理、在庫管理を行います。これは、救援物資の効率的な管理と迅速な配布を可能にするための重要な拠点です。物資管理センターの役割は、被災者への物資供給を円滑に進めるために不可欠な要素であり、計画におけるその位置づけは、災害対策の重要な一環として認識されています。
V.事故災害対策計画 大規模火災 危険物等災害 放射性物質及び原子力発電所事故等災害 道路災害 航空機事故
様々な事故災害への対策が網羅されています。大規模火災では消火活動と【交通規制】、危険物災害では危険物保管事業所との連携、放射性物質災害では【屋内退避】・避難、空間放射線量モニタリング、住民への情報提供、そして道路災害と航空機事故では迅速な救急・救助活動と関係機関との連携が強調されています。【戸田市】は、国・県・関係機関との連携を重視し、迅速かつ的確な対応を目指しています。
1. 大規模火災対策計画
この計画では、大規模火災発生時の迅速かつ的確な対応を目的としています。市消防本部を主体とし、関係機関との連携を強化することで、人命救助と消火活動の効率化を目指しています。市街地における大規模火災は、延焼の危険性が高く、多数の死傷者が出る可能性があるため、人命の安全確保を最優先とした対応が求められます。そのため、消防署班は人命救助を最優先事項とし、消火活動を実施します。さらに、防犯くらし交通課と道路課は、蕨警察署や国・県などの道路管理者と連携し、通行可能な道路や交通状況を迅速に把握することで、緊急輸送を確保し、必要に応じて通行禁止などの交通規制を行います。これは、消防隊や救急隊の迅速な現場到着を確保し、災害対応を円滑に進める上で極めて重要な役割を果たします。大規模火災への対応は、関係機関間の連携と、迅速な情報伝達、そして状況に応じた柔軟な対応が不可欠です。
2. 危険物等災害対策計画
危険物、高圧ガス等の漏洩・流出、火災、爆発、毒物・劇物の飛散・漏洩・流出、原子力施設以外からの放射性物質による放射線障害などを想定し、迅速かつ的確な応急対策を実施するための計画です。市と市消防署は、危険物等保管事業所と連携し、災害発生時の情報収集、被害状況把握、そして消火活動や漏洩・流出防止などの対策を行います。高圧ガス充てん容器が損傷した場合の安全な廃棄手順も定められています。埼玉県知事は、災害の防止や公共の安全維持のために高圧ガス保安法に基づく緊急措置命令を発することができ、液化石油ガスについては市長が基準適合命令を発します。この計画は、危険物等災害の多様なリスクを想定し、関係機関との連携を基盤とした迅速な対応体制を構築することで、市民の生命と財産を守ることを目的としています。危険物災害への備えは、災害発生時の被害を最小限に抑える上で極めて重要であり、日頃から関係機関との連携強化と、災害への備えを万全にする必要があります。
3. 放射性物質及び原子力発電所事故等災害対策計画
原子力事故等による放射性物質の放出を想定し、警戒区域の設定、住民の屋内退避・避難、緊急輸送活動、飲料水の供給、住民の健康調査などを計画しています。市長は、事業者からの情報、モニタリング結果、専門家の助言等に基づき、警戒区域を指定し、近隣自治体へ通知、住民へ屋内退避・避難を指示します。放射線の影響を受けやすい乳幼児、児童、妊産婦などを優先し、高齢者、障害者にも配慮した避難誘導を行います。国が示す放射性物質の摂取基準値を超えた場合は、水道水の飲用自粛と応急給水の措置が取られます。東京電力株式会社との連携による情報提供体制も整備されています。この計画は、原子力災害という特殊な災害への対応を明確に示しており、迅速な情報伝達と、住民の安全確保を最優先とした対応体制の構築が重要になります。関係機関との情報共有と連携体制の構築、そして住民への正確な情報伝達によって、パニックを防ぎ、住民の安全を守ることが求められます。
4. 道路災害対策計画と航空機事故対策計画
道路災害対策計画では、道路上の事故による多数の死傷者を想定し、道路管理者、国、県などの関係機関と連携した迅速かつ的確な救急・救助活動、医療活動、消火活動などの応急対策を実施することを目的としています。東日本旅客鉄道株式会社との連携による鉄道災害への対応も含まれており、消防機関を主体とした救出・救助活動、必要に応じた応援要請などが規定されています。航空機事故対策計画では、大規模な航空事故を想定し、国、県などの関係機関と連携した捜索活動、救助・救急活動、消火活動などの応急対策を実施します。これらの計画は、多様な事故災害を想定し、関係機関との連携と迅速な対応体制の構築によって、被害を最小限に抑え、住民の安全と安心を確保することを目指しています。 迅速な情報収集と共有、そして連携した対応が、これらの事故災害対策の成否を左右する重要な要素です。
VI.その他重要事項
計画全体を通して、住民への情報伝達手段(防災行政無線、ホームページ、メール、SNS等)の多様化と迅速化が重視されています。また、地域住民、自主防災会、関係機関との連携強化により、災害への備えと効果的な【応急対策】の実施が図られています。特に、竜巻発生時の対処行動についても具体的に記述されている点が特徴です。
1. 情報伝達手段の多様化と迅速化
戸田市の地域防災計画では、住民への情報伝達において、防災行政無線(固定系)、ホームページ、防災情報メール、緊急速報メール、そしてソーシャルネットワーキングサービス(SNS)など、多様な手段を組み合わせた迅速な情報伝達体制の構築が重要視されています。これは、災害発生時の情報伝達の遅れが、被害拡大や住民の混乱を招く可能性があるためです。多様な手段を用いることで、情報が届きにくい住民層への情報伝達を確保し、情報弱者への配慮も示しています。さらに、情報の内容についても、住民が適切な行動をとりやすいよう、可能な範囲で付加情報を提供するなど、住民目線の情報発信に努めることが重要とされています。情報伝達手段の多様化と迅速化は、災害への備えと効果的な対応を可能にする上で、極めて重要な要素となっています。これらの多様な手段を効果的に活用することで、迅速かつ的確な情報伝達を行い、住民の安全確保に貢献することを目指しています。
2. 地域連携の強化と応急対策
計画全体を通して、地域住民、自主防災会、そして市役所、警察、消防、県などの関係機関との連携強化が繰り返し強調されています。これは、災害対応において、関係機関間の連携がスムーズに行われることが、迅速かつ効果的な対策実施に不可欠であることを示しています。特に、災害時要配慮者への支援や、帰宅困難者への支援においては、地域住民やボランティアの協力を得ながら、きめ細やかな対応を行うことが重要です。また、応急対策においても、道路の被害状況や交通確保の緊急性を考慮した応急復旧順位の設定、放置車両の迅速な移動などが計画に含まれており、迅速かつ効率的な災害対応を可能にするための様々な工夫が凝らされています。これらの連携強化と具体的な対策は、災害発生時の混乱を最小限に抑え、住民の安全と安心を守るために不可欠な要素です。計画のあらゆる場面において、関係機関や地域住民との連携が、災害への効果的な対応に繋がるという強いメッセージが込められています。
3. 竜巻対策と文化財保護
竜巻注意情報発表時や、竜巻発生確度ナウキャストで発生確度2の範囲に入った場合、防災行政無線や防災メールで住民への注意喚起と対処行動を促す情報伝達を行います。これは、竜巻という突発的な災害への迅速な対応が求められることを示しています。具体的な情報伝達例文も示されており、住民が状況を的確に理解し、安全確保のための行動をとれるよう配慮されています。さらに、文化財災害応急対策として、県指定文化財などの被害状況を県教育委員会に報告し、可能な限り保護・救出活動を行うとともに、関係機関との連絡調整、所有者への指導・助言を行う体制も整備されています。これは、歴史的・文化的資産の保護も重要な防災対策であるという認識を示しています。これらの対策は、自然災害の多様なリスクへの対応と、地域社会全体の安全と安心の確保を目的としています。
