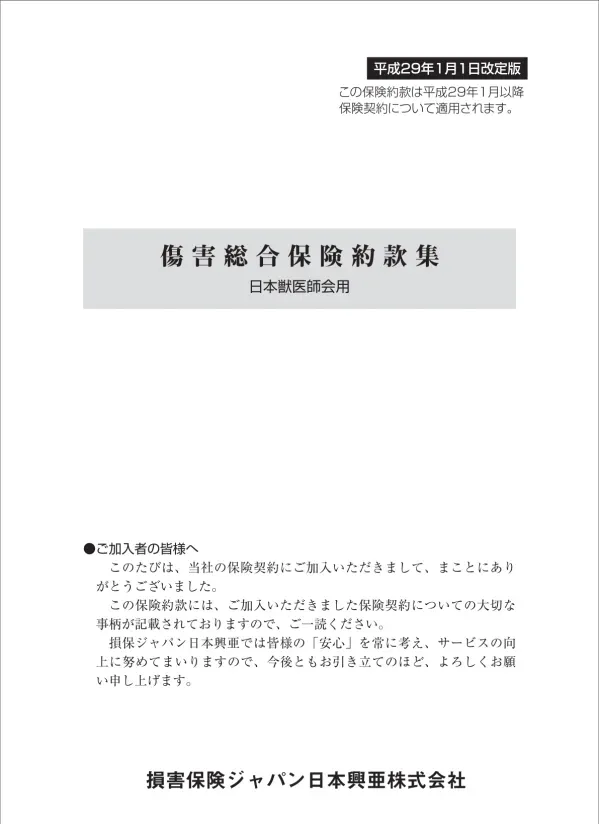
獣医師向け傷害総合保険約款
文書情報
| 著者 | 損保ジャパン日本興亜 |
| 会社 | 損保ジャパン日本興亜 |
| 文書タイプ | 保険約款 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.50 MB |
概要
I.損害保険契約者保護機構と保険金支払
本契約は、個人、小規模法人(従業員20名以下)、またはマンション管理組合を対象に、損害保険契約者保護機構の補償を受けられます。損保ジャパン日本興亜が経営破綻した場合、保険金・返戻金等の8割(破綻後3ヶ月以内の事故は全額)が補償されます。保険金支払に関する詳細や個人情報の取り扱いについては、損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト(http://www.sjnk.co.jp/)、取扱代理店、または営業店にお問合せください。これは、損害保険契約者にとって重要な保護制度です。
1. 損害保険契約者保護機構の補償対象
この保険は、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。ただし、その対象は限定されており、契約者が個人、または従業員数が20名以下の小規模法人、もしくはマンション管理組合の場合に限られます。 これは、中小規模の事業者や個人にとって重要な保護となります。もしも保険会社(引受保険会社)が経営破綻した場合、この機構が保険金の支払を支援します。具体的には、保険金や返戻金等の8割までが補償されます。ただし、重要な例外として、保険会社が経営破綻した日から3ヶ月以内に発生した事故による保険金については、全額が補償されます。この機構による補償は、契約者にとって大きな安心材料となり、経営破綻リスクを軽減する効果があります。 損害保険契約者保護機構の詳細については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。この機構は、保険契約者の経済的な損失を最小限に抑えるために存在する重要な機関です。 この補償制度の利用条件や具体的な補償内容については、契約内容をよく確認し、不明な点は速やかに代理店または損保ジャパン日本興亜に問い合わせることが重要です。これは、万が一の事態に備えるための、きわめて重要な手続きとなります。
2. 個人情報の取扱いについて
損保ジャパン日本興亜は、保険契約の履行、各種サービスの案内提供などを目的として、保険契約に関する個人情報を取得・利用します。 取得された個人情報は、業務委託先や再保険会社などにも提供されます。これは、保険サービスを提供するために必要な情報共有です。ただし、保健医療情報などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則に従い、限定された目的以外には利用しません。 個人情報保護の徹底は、損保ジャパン日本興亜にとって重要な課題です。 個人情報の取扱いに関する詳細は、損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト(http://www.sjnk.co.jp/)に掲載されている個人情報保護宣言をご確認ください。 また、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜営業店へお問い合わせいただくことも可能です。 個人情報の保護は、契約者にとって非常に重要な事項であり、情報の適切な管理と利用が求められます。 この情報の透明性とアクセス可能性を確保することで、契約者自身の権利保護にも繋がります。 損保ジャパン日本興亜は、個人情報の適切な管理と保護に努め、契約者からの信頼に応えるべく、継続的な改善に努めています。
3. 保険金支払に関する問い合わせ先
損害保険契約者保護機構の詳細、および保険金支払に関するご不明な点、個人情報の取扱いに関するご質問などは、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。 損保ジャパン日本興亜の公式ウェブサイト(http://www.sjnk.co.jp/)にも、関連情報が掲載されています。 ウェブサイトでは、個人情報保護宣言をはじめ、保険契約に関する様々な情報が提供されています。これらの情報を確認することで、契約内容に関する理解を深めることができます。 不明な点や疑問点が生じた場合は、速やかに問い合わせることが重要です。迅速な対応と的確な情報提供によって、契約者にとってよりスムーズな手続きが可能となります。 問い合わせ窓口は、契約者にとって重要な情報源となります。 不明点を解消し、安心して保険サービスを利用できるよう、損保ジャパン日本興亜はサポート体制を整えています。 問い合わせ先を把握しておくことは、万が一の際に迅速な対応をとる上で不可欠です。
II.保険金支払条件と手続き
保険金は、被保険者が特定の傷害を負い、別表2に記載の後遺障害(後遺障害)が生じた場合、または死亡した場合に支払われます。保険金の支払額は別表5の算定基準に基づき算出され、賠償義務者がいる場合は自賠責保険等の支払額を下回らない範囲となります。事故発生後30日以内に損保ジャパン日本興亜へ事故の通知が必要です。必要な書類の提出や調査への協力も求められます。保険金請求手続きに関する詳細は、契約内容をご確認ください。
1. 保険金支払の対象となる事故
保険金が支払われるのは、保険期間中に発生した特定の事故が原因で被保険者が死亡した場合、または別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障害を負った場合です。事故の例としては、人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為による事故、もしくは運行中の自動車等との衝突・接触などによる交通事故が挙げられます。後者の交通事故については、加害者らが救護や警察への通報等の必要な措置を取らずに現場を去った場合に限られます。 これらの事故によって被保険者またはその父母、配偶者、もしくは子が被る損害に対して、本章および第4章基本条項の規定に従って保険金が支払われます。 保険金支払の可否は、事故の内容と被保険者の状態によって厳格に判断されます。契約者は、保険契約締結前に告知事項を正確に申告し、万が一の際にスムーズな保険金支払を受けられるように準備しておくことが重要です。 また、事故発生後は速やかな連絡と必要な情報の提供が求められます。 契約内容をよく理解し、不明な点は保険会社に問い合わせることで、トラブルを回避し、迅速な対応を実現できます。
2. 保険金の金額算定
保険金の支払額は、被保険者が負った後遺障害の等級(別表2)や死亡の有無に基づき、別表5に定められた算定基準に従って計算されます。 それぞれの等級や状況に応じて、算出された金額の合計額が保険金の支払額となります。ただし、賠償義務者が存在し、その賠償義務者から支払われる自賠責保険等の金額が、算出された保険金支払額を下回る場合は、自賠責保険等によって支払われる金額が保険金支払額となります。 この算定基準は、公平かつ透明性を確保するために、明確な基準に基づいて設定されています。契約者は、この算定基準を理解することで、保険金請求の手続きや、支払われる金額の予測をすることができます。 また、賠償義務者からの賠償金との関係についても明確に規定されているため、二重払いなどを防ぐことができます。契約者は、これらの規定を理解することで、保険金請求手続きを円滑に進めることができます。
3. 事故の通知と必要な協力
保険契約者、被保険者、保険金受取人、または保険金請求権者は、事故発生後30日以内に保険会社へ事故の発生を通知する義務があります。通知には、事故の原因となった内容に関する詳細な情報が必要です。 保険会社が必要と判断した場合、書面による通知や説明、被保険者の診断書や死体検案書の提出を求めることがあります。これらの要請には速やかに対応しなければなりません。 さらに、保険会社が特に必要とする書類や証拠の提出、損害調査への協力も求められる場合があります。これらの要請には遅滞なく対応することが重要です。正当な理由なくこれらの規定に違反した場合、保険会社は被った損害額を保険金から差し引いて支払います。 事故の通知と協力は、保険金請求手続きにおいて非常に重要なステップです。契約者は、これらの規定を遵守し、保険会社との円滑なコミュニケーションを図ることで、迅速かつ適切な保険金支払を実現できます。
4. 賠償義務者との関係と保険金支払
損害賠償責任の割合や賠償義務者との合意などについては、あらかじめ保険会社の承認を得る必要があります。 保険契約者または保険金請求権者が、この規定に違反した場合、保険会社は、賠償義務者から請求できたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 賠償義務者との交渉や合意は、保険金請求手続きに影響を与える可能性があります。 保険会社への事前相談は、スムーズな手続きを進める上で重要です。 契約者は、保険会社との連携を密にすることで、より有利な条件での保険金支払を実現できる可能性があります。 この規定は、保険金支払の公平性と効率性を確保するための重要な要素となっています。
III.保険金の支払時期と確認事項
保険金の支払時期は、請求完了日から原則180日以内ですが、必要な事項の確認に特別な照会や調査が必要な場合は、日数が延長される場合があります。確認事項には、事故内容、傷害の程度、損害額、他の保険契約の有無などが含まれます。損保ジャパン日本興亜は、必要に応じて、保険契約者、被保険者、保険金受取人に対して、書類提出や調査への協力を求めることがあります。これは、保険金支払をスムーズに進めるための重要な手続きです。
1. 保険金の支払時期 基本的な流れ
保険金の請求手続きが完了した日から、原則として180日以内に保険金が支払われます。これは、保険会社が請求内容を確認し、必要な手続きを行うための標準的な期間です。しかし、この期間は、状況によって変動する可能性があります。 例えば、保険会社が請求内容の確認に必要な情報が不足している場合や、特別な照会や調査が必要な場合などです。 これらの追加的な調査や確認作業が必要となるケースでは、保険金支払が遅れる可能性があります。 保険会社は、確認が必要な事項と確認完了予定時期を被保険者または保険金受取人に通知します。 迅速な保険金支払のためには、契約者は、必要な書類を正確かつ速やかに提出することが重要です。 また、保険会社からの問い合わせに対して、迅速かつ誠実に対応することで、手続きの遅延を最小限に抑えることができます。 契約者は、保険金支払に関する手続きの詳細を事前に理解しておくことで、スムーズな手続きを進めることができます。
2. 保険金の支払時期 特別な照会 調査の場合
保険金の支払に必要な事項の確認に、特別な照会や調査が不可欠な場合は、請求完了日から180日の期間にかかわらず、個別の期間が適用されます。 これらの特別な照会・調査には、例えば、日本国外での調査(国内に代替手段がない場合)や、損害賠償請求権の有無や内容の確認、他の保険契約の有無や内容の確認などがあります。 具体的な日数は、調査の内容や複雑さによって異なり、保険会社が個別に通知します。 この場合、保険会社は確認が必要な事項と確認を終えるべき時期を被保険者などに通知しますので、契約者はその指示に従う必要があります。 これらの調査に協力しない場合、確認が遅延し、保険金の支払時期がさらに遅れる可能性があります。 契約者は、保険会社からの問い合わせや調査への協力をスムーズに行うことで、保険金の支払を迅速化することができます。 特別な調査が必要となるケースを事前に理解しておくことは、保険金請求をスムーズに進める上で重要です。
3. 必要な書類 証拠の提出と調査への協力
保険会社は、事故の内容、傷害の程度、損害の額などを考慮し、保険契約者、被保険者、保険金受取人、または保険金請求権者に対して、追加の書類や証拠の提出、または調査への協力を求めることがあります。 これは、保険金の支払額を正確に決定するために必要な情報収集のためです。 要求された書類や証拠は速やかに提出し、必要な協力をする必要があります。 正当な理由なく協力に応じない場合、保険金の支払が遅れる可能性があります。 契約者は、必要な書類を準備し、保険会社からの問い合わせに迅速に対応することで、保険金支払の遅延を防ぐことができます。 保険会社による調査への協力を拒否したり、必要な書類を提出しないことは、保険金支払の遅延や支給額の減少につながる可能性があります。 スムーズな保険金請求のためには、保険会社との協力体制が不可欠です。
IV.賠償責任と法律相談費用保険金
本契約には、賠償事故に関する法律上の損害賠償責任について、損保ジャパン日本興亜が協力または援助を行う特約が含まれます。また、紛争発生時に法律相談を受けた場合、法律相談費用保険金が支払われる場合があります。法律相談は弁護士法に基づくもので、口頭鑑定や電話相談なども含まれます。弁護士委任費用も保険金の対象となる場合があります。ただし、保険金支払には、特定の条件と手続きが必要となります。
1. 賠償責任に関する保険会社の協力 援助
この特約では、被保険者が日本国内で賠償事故に巻き込まれ、損害賠償請求を受けた場合、保険会社が被保険者の法律上の賠償責任の内容を確定するために協力・援助を行います。この協力・援助は、保険会社が被保険者に対して支払責任を負う範囲内で提供されます。具体的には、被保険者が行う折衝、示談、調停、訴訟の手続きについて、保険会社が協力または援助するというものです。 保険会社は、被保険者の負担を軽減し、円滑な解決を支援することで、被保険者の権利を保護することを目的としています。 この特約は、賠償事故が発生した際に、被保険者が単独で対応する負担を軽減し、専門的な知識や経験を必要とする手続きを支援することで、より公平な解決を促す役割を果たしています。 被保険者は、この特約を利用することで、賠償責任に関する手続きにおいて、保険会社からの適切なサポートを受けることができます。 このサポートは、専門的な知識や経験が不足している場合でも、安心して手続きを進めることができる大きな助けとなります。
2. 保険金請求権の発生時期
この特約に基づく保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)に規定されている事故が発生し、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停、もしくは書面による合意が成立した時から発生します。 これは、損害賠償責任の額が確定した時点をもって、保険金請求権が発生することを意味しています。 この明確な発生時期の規定は、保険金請求手続きの開始時期を明確にし、契約者にとって不確実性を減らす役割を果たしています。 被保険者は、この規定を理解することで、保険金請求のタイミングを的確に把握することができます。 また、この規定は、保険金請求手続きの円滑な進行に寄与し、迅速な保険金支払を実現するために不可欠な要素となります。
3. 法律相談費用保険金
原因事故によって発生した紛争について、保険金請求権者が法律相談を行った場合、事前に保険会社の同意を得た上で、法律相談費用を負担することにより被った損害に対して、法律相談費用保険金が支払われます。 この法律相談は、弁護士法第3条(弁護士の職務)に規定される「その他一般の法律事務」に基づくもので、口頭による鑑定、電話相談、それに付随する書面の作成や連絡なども含まれます。 保険金が支払われるのは、紛争に関する法律上の損害賠償請求について、法律相談費用または弁護士委任費用を負担した場合に限られます。 初年度契約の保険期間開始前に同一または密接に関連する原因事故に関する法律相談や弁護士委任を行っていた場合、またはこれらを予定していた場合は、保険金は支払われません。 また、他の保険契約の有無や内容なども確認事項となります。 法律相談費用保険金は、紛争解決に際して生じる経済的な負担を軽減するための制度であり、被保険者にとって重要なサポートとなります。契約者は、この制度の利用条件を理解し、必要に応じて積極的に利用することで、紛争解決を円滑に進めることができます。
V.その他重要な条項
残存物や盗難品の帰属、保険契約の失効後の保険金支払、手術保険金倍率変更特約などが記載されています。保険金支払に関する詳細は、契約書全文をご確認ください。これらの条項は、損害保険契約全体の理解に不可欠です。
1. 保険金の支払と残存物 盗難品の帰属
保険金が支払われた場合、保険対象物の残存物は、保険会社が取得する旨の意思表示がない限り、被保険者の所有物となります。これは、保険金支払後も、被保険者が残存物に対する所有権を保持することを意味します。 一方、盗難された保険対象物が、保険金支払前に回収された場合は、特定の費用を除き、盗難による損害はなかったものとみなされます。 盗難された保険対象物について、保険会社が保険金を支払った場合は、その保険対象物の所有権その他の物権は、保険金の保険価額に対する割合によって保険会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額を保険会社に支払うことで、所有権その他の物権を取得できます。 これらの規定は、保険金支払後の財産権の帰属について明確に定めており、契約者と保険会社間のトラブルを防止する役割を果たします。 契約者は、これらの規定を理解することで、保険金支払後の手続きを円滑に進めることができます。 また、盗難された物件の回収状況によっても、保険金の支払や所有権の移転の扱い方が変わることに注意が必要です。
2. 債権の移転と協力義務
保険会社が保険金支払に伴い取得する債権について、被保険者が引き続き保有する債権は、保険会社に移転した債権よりも優先して弁済されます。これは、被保険者の権利を保護するための規定です。 保険契約者および被保険者は、保険会社が取得する債権の保全および行使、それに必要な書類や証拠の提出、損害調査への協力を求められた場合は、遅滞なく対応しなければなりません。 保険会社に協力するために必要な費用は、保険会社の負担となります。 これらの規定は、保険会社が取得する債権の管理と活用について、被保険者の権利を保護しつつ、効率的な手続きを進めるためのルールを定めています。 被保険者は、これらの規定を理解し、必要に応じて適切な対応をすることで、自らの権利を保護し、手続きを円滑に進めることができます。 また、保険会社との協力体制を構築することで、迅速かつ公正な処理を実現することができます。
3. 保険契約の失効後の保険金支払と手術保険金
被害事故や人格権侵害に関する紛争で、原因事故により被保険者が死亡した場合、保険契約が失効した後であっても、特約の規定に従って保険金が支払われる場合があります。これは、保険契約の失効後も、特定の状況下では保険金の支払が保証されることを意味しています。 この特約が付帯された保険契約に手術保険金倍率変更特約が付帯されている場合、普通保険約款の規定にかかわらず、より高い額の手術保険金が支払われる場合があります。ただし、1事故に基づく傷害については、1回の手術に限られます。 これらの規定は、保険契約の失効や特約の適用など、保険金支払に関する複雑な状況に対処するためのルールを定めています。 契約者は、これらの規定を理解することで、保険契約の条件や、保険金支払に関する様々なケースへの対応を把握し、適切な手続きをとることができます。 不明な点は、保険会社に問い合わせることで、より正確な情報を取得することができます。
