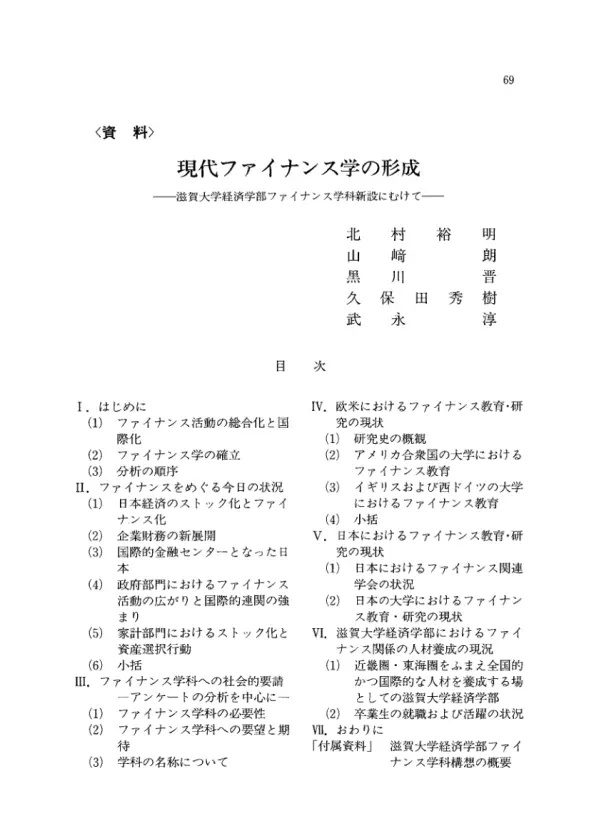
現代ファイナンス学:学科新設の必要性
文書情報
| 著者 | 田村崎川 永保 |
| 学校 | 滋賀大学経済学部 |
| 専攻 | ファイナンス |
| 場所 | 彦根 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.18 MB |
概要
I.現代ファイナンス学の形成と滋賀大学経済学部におけるファイナンス学科設立の必要性
本論文は、急速に進む経済のグローバル化と金融市場の自由化に対応し、日本の大学におけるファイナンス教育とファイナンス研究の現状を分析した上で、滋賀大学経済学部にファイナンス学科を新設する必要性を論じています。国際金融、企業財務、金融政策、財政政策など、現代社会におけるファイナンスの重要性を強調し、既存の金融論、財政学、財務論といった個別科目では対応しきれない、総合的で体系的なファイナンス教育の必要性を訴えています。特に、欧米の大学におけるファイナンス学科の成功事例を紹介し、日本においても同様の学科設立が急務であると主張しています。設立による社会貢献度についても、アンケート調査結果を基に高いニーズがあることを示しています。具体的なニーズとしては、企業の国際化、金融の自由化、高度情報技術の進展への対応が挙げられます。東京市場の成長(1987年にはニューヨーク市場を抜き世界一の株式市場に)や、日本における金融自由化の進展(国債市場の成長など)といった事実も、ファイナンス学科設立の根拠として提示されています。
1. ファイナンス活動の総合化と国際化の進展
現代社会において、ファイナンスは資金調達や運用という総合的な意味を持つ重要な概念となっています。経済のソフト化・情報化の急速な進展により、企業、金融機関、政府、個人のレベルにおいて、ファイナンスに関する知識の総合的・国際的な理解がこれまで以上に求められています。企業では、かつては狭い意味での資金管理に留まっていたファイナンス活動が、国際的な資金調達や資金運用へと拡大しています。日本が国際的な金融センターとなるにつれて、金融機関の多国籍化、金融業務の自由化、金融のグローバル化が加速しています。政府部門でも、公共投資政策や租税政策が国際的な連関を持つようになり、ファイナンス政策は企業や個人の投資行動に大きな影響を与えるようになっています。個人レベルでも、消費者信用の拡大、金融資産の多様化、保険・年金の選択、住宅金融など、ファイナンスに関わる側面が増大しています。こうした状況を踏まえ、科学的なファイナンス知識を体系的に修得し、健全なファイナンシャル・システムを構築していくための「ファイナンス学」の確立が急務となっています。このため、ファイナンス活動の総合化・国際化、そしてファイナンス教育・研究の自立化・専門化に対応した独自のカリキュラムを持つファイナンス学科の新設が、社会的要請に応えるだけでなく、教育・研究上も大きな意義を持つとされています。現状、日本にはそのような組織が存在しないため、ファイナンス学科の新設は急務と言えるでしょう。
2. ファイナンスをめぐる今日の状況 金融市場の構造変化
ファイナンス化の進展は、単なる金融機関の増大や財テクの活発化だけを意味するものではありません。金融市場の国際化・自由化、金融商品の多様化、金融行動の複雑化、ストックとフローの連関性の増大といった、ファイナンス活動の構造変化全体を指します。これは、業界再編を柱とした経済社会システムの転換を伴う現象です。ファイナンス研究の体系化・総合化の必要性には、産業構造における金融部門の比重増大、財テクやエクイティ・ファイナンスの活発化に代表されるファイナンス活動の量的拡大、金融市場の自由化・国際化といった問題が背景にあります。さらに、世界経済の相互依存性の高まり、東欧諸国の制度改革、発展途上国の経済発展、地球環境問題への対応など、国際的な資金移動の重要性はますます高まっています。国内においても、生活関連社会資本の整備、土地資産格差の是正、高齢化社会への対応といった課題があります。日本のストック・フロー比率は他の先進国と比べて高く、地価や株式市場の調整が進むと考えられます。企業財務ニーズの高まりも、新金融商品の開発や金融証券化といったイノベーションを促進しており、金融自由化や変動相場制への移行に伴い、リスクヘッジの必要性も増しています。為替・金利・株価に関する金融先物やオプションの導入はその好例です。欧米企業では、低成長・高インフレ下で低収益に苦しむ中、ファイナンス活動を積極的に収益の柱にする動きが始まっています。
3. 国際的金融センターとなった日本と今後の課題
1980年代後半から日本において金利自由化が本格化し、金融市場のグローバル化が金利や業務の自由化を推進しています。東京国際金融センター研究会は、21世紀末までに東京の金融取引従事者が現在の3倍の7万5千人に達すると予測し、霞ヶ関ビルの8倍に相当する110万㎡のオフィスが必要になると推定しています。東京臨海部副都心計画(4兆1400億円規模)はこの予測に対応するものです。東京市場の時価総額は1980年代に急成長し、1987年にはニューヨーク市場を上回り世界一となりました。しかし、国際性、自由度、効率性、安定性という点では、ニューヨークやロンドン市場にはまだ劣るとされています。日本の国際的な金融的地位は近年著しく向上し、円はドルに次ぐ取引通貨となっています。輸出入においても円建て化が進み、準備通貨としての地位も高まっています。一方で、低利資金調達を可能とする日本の金融制度は、国際競争力の源泉であるとされ、アメリカなどから金利自由化への圧力があります。1992年度以降、自己資本比率を8%以上にするというBIS(国際決済銀行)の目標もあります。日本の国債市場は急速に発展し、1988年末には残高が330兆円に達しています。これは金融自由化の原動力となり、公債管理政策は金融市場と密接な関係を持つようになりました。日本の政府規模は小さいですが、一般政府総資本形成の対GNP比は高く、公共投資が民間投資と密接に関連していることを示しています。これは、日米構造協議におけるアメリカの対日公共投資増額要求にも表れています。
4. 家計部門におけるファイナンス ストック化と資産選択行動の変化
1987年末の家計部門の総資産残高は2046兆円で、国民総資産の約4割を占めていました。一世帯当たりでは5100万円です。内訳は土地52.7%、金融資産36.2%、純固定資産9.1%です。負債額は237兆円で、正味資産は1809兆円です。戦後、高い貯蓄率を背景に資産蓄積が進んできましたが、金融自由化による金融商品の多様化や地価高騰などにより、金融資産選択行動に変化が生じています。金融資産構成比は1980年代に大きく変化し、現金通貨や定期預金の割合が減少し、株式や保険の割合が増えています。これは家計部門が資産の収益性を高めるためポートフォリオを積極的に組み替えていることを示しています。しかし、近年の株式急落や一時払い養老保険の有利性低下などにより、この構成比は再び変化しています。家計部門の資金調達面、負債面にも大きな変化が見られます。家計負債の約7割が住宅ローンで、残りは割賦販売、クレジット、消費者ローンなどです。住宅ローン以外の消費者信用の利用が増大しており、資産と負債の両建て化が進んでいます。総合口座やクレジットカードの普及などが、家計部門の金融行動の変化を促進しています。都市銀行では自由金利調達比率が70%を超え、第二地銀や信用金庫でも50%を超えています。1991年4月には小口MMCの最低預入額が50万円に引き下げられる予定で、自由金利調達比率は今後零細金融機関で急上昇するでしょう。
5. ファイナンス学科設立の意義と社会的なニーズ
滋賀大学経済学部にファイナンス学科を設ける意義について、アンケート調査の結果を基に分析しています。企業、地方公共団体、卒業生の多くが、ファイナンス学科の設立に高い意義を感じていることが示されています。また、ファイナンスの知識を体系的に身につけた学生は、産業界で必要とされるとの回答も高い割合を占めています。アンケートでは、金融業界全体のニーズに応えるもの、国際取引の拡大に対応できる人材育成に貢献するものといった肯定的な意見が多く見られました。一方で、商業・産業の発展過程における歴史的変遷や国際比較研究の必要性、基礎理論研究の重視、法制度に関する知識の充実、コンピュータや数学に関する知識の必要性なども指摘されています。これらの意見は、ファイナンスをめぐる教育・研究が本格的に必要とされていることを示しています。従来の金融論、財務論、財政学といった個別科目では、現代のファイナンスを取り巻く現象を説明できないという認識が社会的に広がりつつあることが、ファイナンス学科という名称への賛同からもわかります。 このことは、従来の枠組みを超えた横断的かつ総合的な教育・研究が必要であることを示唆しています。
II.欧米におけるファイナンス教育 研究の現状と日本の現状との比較
アメリカ(ペンシルバニア大学ウォートン・スクール、ミシガン州立大学など)、イギリス、西ドイツの大学におけるファイナンス教育の現状を分析し、日本の現状との比較を行っています。欧米では、1950年代以降、ファイナンス学科やコースが多くの大学に設置され、ファイナンス研究が自立化・専門化しているのに対し、日本は金融論、財政学、財務論といった個別科目の教育が中心であり、それらを統合する体系的な教育が不足している点を指摘しています。特に、ウォートン・スクールやミシガン州立大学のカリキュラムにおける企業財務、国際金融、金融市場、財政学関連科目の充実度が強調されています。また、イギリスでは会計士養成に重点が置かれ、西ドイツでは財政学の伝統を反映した財政学科が独立して存在していることが述べられています。日本の大学では、ファイナンス関連の科目は特殊講義として存在するものの、体系的な取り組みが不足している点が課題として挙げられています。
1. 欧米におけるファイナンス教育 研究の現状 アメリカ合衆国
アメリカ合衆国では、1950年代以降、多くの大学でファイナンスに関する専門の学科やコースが設置され、ファイナンス教育・研究の自立化・専門化が進んでいます。論文では、ペンシルバニア大学ウォートン・スクールとミシガン州立大学を例に挙げて、その現状が説明されています。ウォートン・スクールは、アメリカの中でも特に充実したファイナンス学科を持ち、学部レベルでは貨幣経済論、企業財務論、銀行論、投資管理論、国際財務管理、不動産投資と不動産金融、住宅金融と公共政策、アメリカ金融史など、多岐にわたる科目が開講されています。ミシガン州立大学では、ファイナンス・保険学科が設置され、会計学、投資計画、金融市場、金融制度管理、企業財務論、国際金融論などの科目が提供されています。両大学とも、経済学の基礎理論を踏まえた上で、企業財務を起点に金融論、財政学関連の科目を配置するカリキュラム構成が特徴的です。また、土地や住宅に関する科目が設置されている点も注目に値します。これらの大学では、学部レベル(undergraduate)と大学院レベル(graduate)の両レベルでファイナンス教育が行われています。これらの事例は、欧米におけるファイナンス教育の高度化と専門化を示すものです。
2. 欧米におけるファイナンス教育 研究の現状 イギリスと西ドイツ
イギリスの大学におけるファイナンス関連教育は、会計士という専門職の養成という観点から特徴付けられます。会計学を中心として、金融論、財政学(特に租税論)、財務論といった科目が配置されるのが一般的です。グラスゴー大学のファイナンス学科(School of Financial Studies)を例に、会計学、経済学、租税論、企業財務論、情報システム論、国際会計、金融論、投資分析といった科目が紹介されています。西ドイツでは、財政学の伝統を反映して、財政学科が独立して設置されていることが特徴です。ケルン大学の財政学科では、経費論、歳入論、財政政策、公債論、地方財政論といった科目が開講されています。金融論関連科目は経済学科、財務論関連科目は経営学科に配置される傾向があります。このように、イギリスと西ドイツでは、それぞれ国の社会状況や学問的伝統を反映したファイナンス関連教育が行われています。これらの国々の事例は、ファイナンス教育における多様なアプローチを示しています。
3. 日本のファイナンス教育 研究の現状と課題
日本におけるファイナンスに関する教育は、金融論、財政学、財務論といった個別科目が中心であり、それらを統合する場が不足していることが指摘されています。欧米のようにファイナンスを専門的に扱う学科は存在せず、体系的な教育・研究体制が整っていない点が課題です。一部の大学では、「金融構造の変化と中央銀行」、「ファイナンス」、「信託経済論」といったファイナンス領域の新しい動きに対応した科目が設定されていますが、これらの多くは特殊講義という形式で、体系的な取り組みには至っていません。会計関係科目については、会計学科という独立した学科で教育が行われており、充実した科目配列がなされています。しかし、ファイナンスと会計は密接に関連しているため、両者の連携を強化することで、より効果的な教育が実現できる可能性があります。東京大学や京都大学などの例からも、ファイナンスに関する教育・研究は、個別の科目に分散しており、総合的なアプローチが不足している現状がわかります。この現状を改善するために、ファイナンス学科の新設が強く求められています。
III.滋賀大学経済学部ファイナンス学科構想の概要
滋賀大学経済学部が目指すファイナンス学科の構想が提示されています。ファイナンス理論の充実と現実のファイナンス活動との連携を重視したカリキュラム、少人数ゼミ、ファイナンス関連法制度・情報処理・外国語教育、専門資格取得支援などが計画されています。学科は、ファイナンス計画、ファイナンス市場、ファイナンスシステムという3つの大講座から構成され、金融市場論(株式市場論、外国為替市場論、保険・年金市場論、不動産市場論など)、金融システム論(金融システム、金融ネットワーク、比較金融システムなど)といった科目が予定されています。近畿圏・東海圏を基盤とした全国規模、そして国際的な人材育成を目指していることが強調されています。卒業生の就職状況に関するデータも提示され、近畿圏・東海圏への就職が多いこと、全国38都道府県からの学生が集まっていることが示されています。
1. 滋賀大学経済学部におけるファイナンス学科設立の背景
滋賀大学経済学部は、経済学科、経営学科、会計学科、情報管理学科を擁し、教育研究体制の整備・充実を図ってきましたが、日本のファイナンス活動の総合化・国際化の急速な進展と、欧米におけるファイナンス教育・研究の自立化・専門化を踏まえ、新たな取り組みとしてファイナンス学科の設立を構想しています。既存の4学科の協力を得ながら、ファイナンスに関する総合的で系統的な教育・研究の場を設けることで、社会のニーズに応え、日本の「ファイナンス学」の発展に貢献することを目指しています。欧米諸国では、1950年代以降、ファイナンス研究の進展に伴い、多くの大学でファイナンスに関する専門学科やコースが設置されていますが、日本においては、金融論、財政学、財務論といった個別科目の教育・研究が中心であり、それらを統合する場はこれまで存在しませんでした。そのため、日本の経済社会状況と大学における教育・研究の伝統を考慮し、ファイナンスに関する学科を新設することは喫緊の課題となっています。
2. 滋賀大学経済学部ファイナンス学科の教育 研究内容
本構想では、ファイナンス理論の充実とともに、現実のファイナンス活動との関連性を重視したカリキュラムを編成することを目指しています。少人数制のゼミナー教育を必修とし、ファイナンスに関わる法制度、情報処理、外国語能力の教育にも力を入れます。さらに、証券アナリスト、不動産鑑定士、税理士などの専門的資格取得のための基礎学力の修得にも対応できるようカリキュラムを設計しています。学科は「ファイナンス計画」、「ファイナンス市場」、「ファイナンス・システム」の3つの大講座から構成されます。ファイナンス計画大講座では、ファイナンスに関する意思決定を行うための計画策定に関する教育・研究を行います。ファイナンス市場大講座では、株式市場、外国為替市場、保険・年金市場、不動産市場など、様々な金融市場の理論と実態を学びます。ファイナンス・システム大講座では、ファイナンスにかかわる計画や市場の枠組みを形作る制度についての理論と現状を教育・研究します。これらの講座を通して、ファイナンスに関する総合的な知識とスキルを習得できる教育体制を構築します。
3. 滋賀大学経済学部ファイナンス学科の教育目標と目指す人材像
滋賀大学経済学部は、近畿圏・東海圏を基盤としながらも、全国的かつ国際的な人材育成を目指しています。1987年度および1988年度の就職状況調査によると、卒業生の8割が近畿圏・東海圏出身であり、就職地域も近畿・東海圏と関東圏に集中していることから、この地域を拠点とした人材育成が有効であると考えられます。しかしながら、38都道府県から学生が集まっているという事実からも、本学部の教育が全国的な広がりを持っていることがわかります。この全国的なネットワークと、近畿・東海圏という地理的な利点を活かし、国際的な視点を持ったファイナンス分野の専門家を育成する場として、ファイナンス学科を設立することで、日本のファイナンス学の発展に貢献したいと考えています。 本学科のカリキュラムは、経済学、経営学、会計学、情報管理学などの基礎知識をベースに、ファイナンスに関する専門知識を体系的に学ぶことができるよう設計されます。少人数ゼミや専門資格取得支援を通して、実践的な能力を備えた人材育成を目指します。
