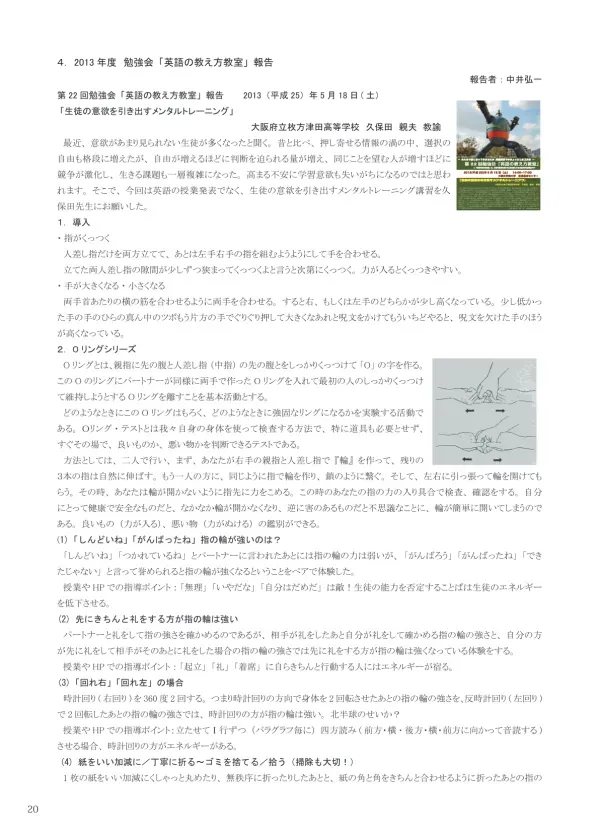
生徒の意欲UP!メンタルトレーニング
文書情報
| 著者 | 中井弘一 |
| 学校 | 大阪女学院大学 |
| 専攻 | 英語教育 |
| 場所 | 大阪 |
| 文書タイプ | 活動報告 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 3.35 MB |
概要
I.生徒の学習意欲向上のためのメンタルトレーニング
近年の生徒は情報過多と激化する競争により、学習意欲の低下が見られる。そのため、メンタルトレーニングの導入が提案された。久保田先生(大阪府立枚方津田高等学校教諭)による講習では、ポジティブ思考を促し、集中力を高めるトレーニングと不安解消のテクニックが紹介される。具体的な方法として、「私は意欲的に取り組む」といった肯定的な自己暗示や、教具(中古の黄色い硬式テニスボール)の使用などが挙げられる。参考書籍として、「なぜ若者は優先順位を決められないのか」(長谷川一彌著)が紹介されている。
1. 学習意欲低下の背景とメンタルトレーニング導入の必要性
現代の生徒を取り巻く環境は、情報過多、選択の自由増加、競争激化、複雑化する生き方の課題など、かつてないほど複雑化している。これらの要因から、多くの生徒で学習意欲の低下が見られるという現状が指摘されている。この問題に対処するため、本資料では、英語の授業発表ではなく、生徒の意欲を引き出すメンタルトレーニング講習の導入が提案されている。メンタルトレーニングは、意志、意欲、決断力といった精神力を強化するトレーニングであり、生徒の抱える不安を解消し、学習意欲を高めることを目的としている。具体的には、ネガティブな思考(「笑われるかもしれない」「怒られるかもしれない」など)をポジティブな思考(「私は意欲的に取り組む」など)へと転換させるトレーニングや、集中力を高めるための実践的な方法が紹介されている。
2. メンタルトレーニングの内容と具体的な実践方法
久保田先生(大阪府立枚方津田高等学校教諭)が担当するメンタルトレーニング講習では、先生自身が実践し、阪大生にも講義を行っている「実力発揮の公式」に基づいたトレーニングが提供される。心と体の抵抗を減らし、集中力を高めるための具体的な方法が指導される。講習には、中古の黄色の硬式テニスボールを2~3個用意するよう指示されており、これはトレーニングに用いる教具として活用されることが示唆されている。さらに、昨年度の「英語Ⅰ」、今年度の「英語速読」「英文法Ⅱ」でのメンタルトレーニングや教具についても紹介される予定であり、実践的な指導内容が期待される。参加者には、講習で学んだトレーニング法を実際の授業で実践し、生徒の不安解消に新たなアプローチを試みるよう促している。
3. 参考書籍の紹介とメンタルトレーニングの効果
講習内容を補完する書籍として、「なぜ若者は優先順位を決められないのか」(長谷川一彌著、学研新書)が推奨されている。この本は、優先順位の設定や意思決定に悩む若者の実態を詳細に解説しており、講習内容をより深く理解する上で役立つとされている。また、「一流になる」(小浦武志著)も紹介されており、集中力に関する内容が記載されていると述べられている。これらの書籍を読むことで、メンタルトレーニングの効果をより深く理解し、実践的な指導に繋げることが期待される。特に、「なぜ若者は優先順位を決められないのか」は、講演内容よりも詳細な情報が網羅されていると強調されており、メンタルトレーニングにおける課題解決のヒントが得られる可能性が高いと言える。
II.活用型英語授業の実践と語彙指導の工夫
二森先生(兵庫県立尼崎小田高等学校教諭)は、思考力・判断力・表現力を育む活用型授業の実践を紹介。リスニング・リーディング・スピーキング・ライティングの4技能を総合的に鍛え、タスクやプロジェクトを通して生徒の自主的な学習を促進する。語彙指導においては、単語を羅列するのではなく、語彙力の向上を目指し、単語の使われ方や文脈を重視した指導が重要だと強調。具体的には、英英辞典を用いた学習や、学習した単語を使ったストーリー作成などが提案されている。
1. 活用型英語授業の目的と実践例
二森先生(兵庫県立尼崎小田高等学校教諭)は、従来の英語授業における4技能(リスニング、リーディング、スピーキング、ライティング)習得に加え、思考力、判断力、表現力の育成を重視した活用型授業を実践している。これは、学習指導要領が求める英語力の育成の方向性にも合致する。実践では、タスクやプロジェクト活動を通して、生徒が自ら課題を発見し、解決していく過程を重視する。生徒は、与えられた課題の本質を見抜き、重要点を整理・判断し、工夫を凝らした表現活動を行う。この授業を通して、生徒は自ら理解し、発信していく力を身につけることを目指している。 具体的な実践例として、生徒が自ら課題を発見したり、与えられた課題から重要点を抽出し、自ら工夫した表現活動を行う授業が紹介されている。 ペアワークも積極的に取り入れ、協力して学ぶことを通じて、個々の生徒の自立的な学習を促す指導方法も示されている。
2. 効果的な語彙指導のための工夫
語彙指導においては、単なる単語の羅列ではなく、語彙力の真の向上を目指した工夫が紹介されている。単なる単語リストではなく、語彙をカテゴリーや使用場面で分類し、単語同士の繋がりをネットワークとして理解させることが重要だとされている。品詞の知識も大切だが、それ以上に重要なのは、単語の使われ方、使用場面、使用方法、そしてその単語を使う理由を理解させること。単語の概念やイメージを伝える指導が不可欠だとされている。逐語訳的な単語リストは、真の理解に繋がらず、日本語的な固定概念に陥る危険性があると指摘されている。 生徒に新出単語を分類させ、修得させること、学習した単語を使って短いストーリーを書かせる活動なども提案されている。文章作成後の教員のフィードバックが、生徒個人の学習意欲を高める効果も期待できるとしている。
3. 活用型授業における課題と改善策
多様な活動を行う活用型授業には、教員の相当な準備が必要であるという指摘がある。事前に配布する資料による予習の促進も考えられるが、生徒が与えられた課題をこなすことに慣れてしまい、自ら考える力が不足する可能性も懸念されている。この点を踏まえ、生徒が主体的に学習に取り組むための工夫が求められる。 尼崎小田高等学校では、国際探求学科、サイエンスリサーチ科、普通科の3学科があり、地域英語教育拠点校を目指して、ALTを含む14名の英語科教員が日々の授業研究に励んでいる。具体的には、ディベートやポスターセッション、スピーチ指導など、多様な取り組みが行われていることが示されている。 授業における課題解決のための具体的な方法や工夫が、参加者同士で議論されている様子も伺える。
III.創造的な英語学習活動の提案
山口先生(滋賀県湖南市立石部中学校教諭)は、ペアやグループ学習を中心とした共同学習、既習表現を使った創造的な英文作成、身の回りの話題を使ったスピーキング活動などを紹介。協働学習の重要性を強調し、生徒同士の協力と相互作用を通して学習効果を高める方法を提示。さらに、生徒の発表や質疑応答をビデオ撮影し、観点別評価に活用するなど、きめ細やかな指導と評価方法が紹介されている。先生は「いっぷくカフェ」という英語教員有志の集いを企画・運営し、中学校・高校の英語教育発展に貢献している。
1. 協働学習と創造的な英語学習活動
山口先生(滋賀県湖南市立石部中学校教諭)は、生徒の創造性を育む英語授業として、ペアやグループ学習を中心とした共同学習、既習表現を用いた創造的なプラス1センテンスの英文作成、そして身の回りの話題を用いたスピーキング活動などを紹介している。共同学習(group learning)は、協働学習(collaborative learning)や協調学習(cooperative learning)とも呼ばれ、スモールグループで協力しながら共通の目標達成を目指す学習方法であり、互恵的な相互依存関係が重要となる。プラス1センテンス活動では、既存例文をベースに生徒が独自の例文を作成することで創造性を刺激する。身の回りの話題を英語で表現する活動は、生きた英語に触れ、英語表現を楽しむ機会を提供する。これらの活動を通して、生徒の創造的なスキル育成と英語学習への意欲向上を目指している。
2. 効果的な音読指導とリプロダクション活動
山口先生は、音読指導においても工夫を凝らしている。単純な暗唱ではなく、本文のキーワードや強調すべき語句のみを提示したシートを用い、生徒に30秒で内容を再現させる活動を紹介している。これは、本文の暗唱からリプロダクションへと段階的に学習を進める方法であり、生徒が文や句のまとまりを意識し、内容理解を深める効果が期待できる。また、生徒間のインタヴュー活動では、同性への質問は1点、異性への質問は3点、先生への質問は4点という独自の評価基準を設けている。これは、中学生に多い同性間コミュニケーションの偏りを解消し、先生への質問を促す意図がある。この活動は3段階のステップで構成され、最後に印象に残ったことを数行の文章でまとめさせることで、時制の活用能力も同時に育成する。
3. 表現定着のための工夫と生徒への配慮
山口先生は、話す活動において「話したい内容であるべき」「印象に残ったことを話させること」を重視している。既習表現を整理した「お助けボード・表現定着ボード」を作成し、生徒がいつでも参照できるように工夫している。しかし、全てのクラスで掲示すると不公平になるため、全てのクラス分を作成して持ち運んでいるという苦労も紹介されている。また、授業では生徒が英語を使用することに抵抗感を持たないように配慮している。英語に自信のない生徒が質問に来やすいよう、周囲の生徒が練習している状況を作り、質問しやすい環境を構築している。全ての活動はビデオに記録され、後から生徒一人ひとりの努力を丁寧に評価する観点別評価に活用している。この丁寧な評価方法は時間と労力を要するため、クラスサイズの縮小などの支援策が必要だと感じていると述べられている。
IV.新学習指導要領と高校英語授業実践
新学習指導要領における「英語の授業は英語で行う」という指針に対し、吉野先生(滋賀県立水口高等学校教諭)は、生徒の英語力向上を目指した実践を紹介。語彙力、発音、反復練習を重視し、生徒が英語を使用することに抵抗感を持たないように配慮している。具体的な取り組みとして、「キクタン」を用いた小テストや、授業導入における「つかみ」活動の重要性を指摘。「TED Talk」のプレゼン術にならい、生徒に興味を持たせる導入を心がけている。
1. 新学習指導要領と 英語で授業 への課題
高等学校では、新学習指導要領により「英語の授業は英語で行う」ことが原則となった。吉野先生(滋賀県立水口高等学校教諭)は、この指針に対し、生徒の英語学習への消極的な姿勢を踏まえ、具体的な授業実践と課題について発表している。水口高校は部活動や生徒会活動が盛んで生徒の意欲は高いものの、英語学習に自信を持つ生徒は少ないという現状が示されている。 吉野先生は、この現状を踏まえ、新学習指導要領の指針にどのように対応していくべきか、日々の授業でどのような点に留意すべきかを探っている。 発表では、現状の課題と、新指導要領への対応策、そして生徒への効果的な指導方法について具体的な事例を交えながら議論が展開されていることが予想される。
2. 英語で授業を行うための工夫と具体的な実践例
吉野先生は、生徒の英語力、特に語彙力、発音力、反復練習の重要性を指摘し、授業実践の根幹に据えている。生徒が英語を使用することに抵抗感を持たないように、「情意フィルター」を低く保つことを意識している。生徒に解答を黒板に書かせる際、間違えることを恐れる生徒が多いことから、間違えることを成長の過程として捉える雰囲気づくりを心がけている。また、授業導入の5~10分を「つかみ」の時間に活用し、生徒の関心を惹きつける工夫を重要視している。 具体的には、「キクタン」を用いた小テストで成功体験を与えたり、日常会話や英語トリビアなどを用いて、英語学習の楽しさを伝える試みなどが行われている。TED Talkの「Start with why」の考え方を授業に取り入れ、学習活動の目的とプロセスを明確にすることで、生徒の納得感と期待感を高める方法も提案されている。
3. 授業における課題と今後の展望
「英語の授業を英語で行う」という新学習指導要領の指針は、生徒の英語力や学習意欲、教員の指導力など、様々な要因を考慮する必要があることを示唆している。特に、英語学習に消極的な生徒が多い現状では、より効果的な指導方法の工夫が不可欠である。吉野先生は、生徒の英語力向上のため、語彙力、発音、反復練習を重視した指導を行っているものの、生徒の英語力や学習意欲の向上、そして授業の質を高めるための更なる工夫が必要だと認識している。 発表を通して、新学習指導要領の指針をどのように実践し、生徒の学習意欲を高め、英語力を向上させるかについての課題と、それに対する具体的な解決策が提示されるだろう。また、slow learnerへの配慮や、生徒が英語を使用することに抵抗感を持たないよう、授業の雰囲気づくりも重要な要素として議論されると思われる。
V.新科目 英語表現Ⅰ の授業デザイン
加藤先生は、新科目「英語表現Ⅰ」における授業デザインの工夫について議論。従来の文法中心の授業ではなく、コミュニケーション重視の授業展開を模索。自由英作文を中心としたライティング課題(辞書使用不可)を取り入れ、生徒の表現力を育成する試みが紹介されている。
1. 新科目 英語表現Ⅰ の目的と課題
高等学校で今年度から導入された新科目「英語表現Ⅰ」は、従来の文法中心の授業から脱却し、コミュニケーション能力の育成を目指している。 しかし、英語科教員の間には、文法の体系的な指導が不可欠であり、大学入試にも対応できる力を養わなければならないという考えが根強く残っている。そのため、教科書の範囲、文法書や問題集の活用、授業における表現活動の量、そして考査方法など、新しい科目の指導方法について、教員間での認識のすり合わせが必要となっている。新学習指導要領の意図を踏まえつつ、生徒の英語運用能力を効果的に育成するための授業デザインが求められている。この科目では、コミュニケーションの場面設定を通して、多様な英語表現の習得を目指すことが意図されている点が重要である。
2. 授業デザインにおける工夫と実践例
加藤先生は、「英語表現Ⅰ」において、従来のOC(Oral Communication)を看板にした文法授業とは異なるアプローチを試みている。具体的には、コミュニケーションの場面設定を重視し、多くの英語表現を行うことで英語運用能力の向上を目指している。 授業実践の一例として、生徒が作成した自由英作文の提出物や、考査問題(自由英作文、辞書使用不可)が紹介される予定である。 考査問題の30%を占めるライティング(自由英作文)は、当日の問題用紙に提示され、事前のテーマ告知は行われない。これは、生徒の即興的な英語表現能力を測ることを意図していると考えられる。 これらの実践例を通して、新科目の授業デザインにおける工夫や課題が議論され、参加者からの意見交換を通してより効果的な指導方法を探っていくことが期待される。
3. 教員間の認識のすり合わせと今後の展望
新科目「英語表現Ⅰ」の指導にあたっては、英語科教員一人ひとりの授業デザインに対するイメージの共有が重要となる。 教員間で「教科書をどこまで使うか」「文法書と文法問題集は使うのか使わないのか」「表現活動を授業の中でどれだけできるか」「考査はどのようなものになるか」といった点について、新年度開始以降、擦り合わせが行われてきた。 この擦り合わせの経緯と、加藤先生の授業実践、そして考査問題例の紹介を通して、新科目の授業デザインにおける課題や工夫が議論される。参加者からの意見も踏まえ、より効果的な授業デザインの構築を目指している。 自由英作文を中心としたライティング課題の評価方法や、生徒の英語表現力の育成に繋がる指導法について、具体的な議論が展開されることが予想される。
VI.効果的な言語活動と創造的実行力
松川先生(奈良県立高取国際高校)は、生徒の創造性を刺激する実践的な英語授業を紹介。具体的な教材や歌などを用いたデモンストレーションを通して、創造的実行力の育成を重視。中井先生は、言語活動を効果的に行うための指導法(direct methods、audio-lingual methodなど)や、思考力を鍛えるための指導の重要性を強調。ワークシート作成においては、生徒が自由に考え、書き込むためのスペースを確保することの必要性を指摘している。
1. 松川先生の授業実践と創造的実行力
松川先生(奈良県立高取国際高等学校教諭)は、「こんな授業は面白い!」と題し、具体的な教材を用いた実践発表を行った。英語の歌のデモンストレーションなども行われ、生徒の創造的実行力に繋がる示唆に富んだ内容であった。 発表では、入試英語の長文読解と、言語活動の充実を両立させるための解決策として、wpm(Words Per Minute)を意識した速読、推論を促す質問、そしてretelling(要約・復唱)の3点が提示されている。 中学校と高等学校の両方の経験を持つ松川先生の実践は、具体的な教材提示とデモンストレーションを通して、非常に分かりやすく、生徒と教師の双方にとって創造的実行力を高める上で役立つ示唆に富んだ内容であったことが伺える。
2. 効果的な言語活動と教員間の連携
参加者間では、効果的な言語活動の実施方法と教員間の連携強化について議論が行われた。 具体的な意見としては、基礎を復習しながら英語の使用を促すこと、スピーキングだけでなく、リスニング、リーディング、ライティングを含む4技能を総合的に育成する活動設計の重要性が挙げられている。 教員間の連携強化については、教材の共有化などが提案されている。 高校3年生の授業において、問題演習だけでなく言語活動を充実させる方法についても議論されている。入試対策と英語力向上とのバランス、具体的な活動例などが検討されたと推測される。
3. 中井先生の基調講演と英語授業の哲学
中井先生による基調講演「明日からの授業実践―英語授業の哲学―」では、英語授業における「ものの見方の拡げ方」「教材の読み込み」「生徒の達成感の共有」の3点が特に印象的であったとされている。 「ものの見方の拡げ方」では、多様な視点を持つことの重要性が強調され、合宿参加者による意見交換がその効果を上げたことが示唆されている。「教材の読み込み」では、テキストを表面的に解釈するのではなく、言葉や状況をイメージ化し、教材に込められた思いを生徒に伝えることの大切さが説かれている。「生徒の達成感の共有」では、教師が生徒の英語学習における達成感や、その先に広がる可能性を共有することの重要性が説かれている。
4. 言語活動における指導法とワークシート作成のポイント
中井先生は、言語活動を英語で行う指導法として、direct methods、audio-lingual method、oral methodなどを挙げ、それらが話し言葉を重視した反復練習による習慣化を目指していることを指摘している。 書き言葉の理解と話し言葉への変換、図解や英問英答などの工夫、発音やシャドウイングといった基礎的な音声訓練の重要性も強調されている。 また、ワークシート作成においては、生徒が自由に考え、メモを取ったり、考えたり、質問をしたりするための空所を設けることが不可欠だと指摘している。英語教育を「線→平面→立体」と捉え、生徒間のインタラクションを通して言語習得を促すことが重要視されている。
VII.英語教育における時間と質の重要性
小財先生(滋賀県立虎姫高等学校教諭)は、グローバル化社会における教育のあり方について、効率性だけでなく、時間をかけて質の高い教育を行うことの大切さを訴える。効率性を重視するだけでなく、生徒一人ひとりに寄り添った丁寧な指導を行うことの重要性を強調した。これは、教育を「手軽でコストパフォーマンスの良いスープ」ではなく、「シェフが時間をかけてじっくりと作り上げたスープ」に例えて説明されている。
1. グローバル化社会における教育のあり方
小財先生(滋賀県立虎姫高等学校教諭)は、グローバル化が加速する社会において、教育現場にもスピード、効率、コストパフォーマンスが重視される傾向があると指摘する。しかし、先生は、教育のあり方について、効率性だけで測れるものではないという疑問を呈している。 先生は、教育の質を「スープ」に例え、手軽で効率的に作られたスープと、時間と手間をかけて作られたスープを比較することで、教育における時間と質の重要性を訴えている。 手軽なスープは、すぐに食べられる利便性がある一方、時間をかけて作られたスープは、深い味わいと満足感がある。教育も同様に、すぐに結果を求めるのではなく、時間をかけてじっくりと生徒を育むことが重要だと主張している。教育は国家100年の計であり、短期的な成果だけでなく、長期的な視点が必要であると結論付けている。
2. 小財先生の授業実践と今後の課題
小財先生は、滋賀県立虎姫高等学校(SSH指定校、現役進学率91%)で教鞭をとっており、穏やかな生徒が多い反面、発表などが苦手な生徒も多いことを指摘している。 先生自身も、教員1年目であり、日々試行錯誤を繰り返している中で、「正解」を探すよりも「信念を持つことが大事」という結論に至っている。 先生は、言語活動を取り入れることをテーマに、具体的な授業実践を紹介している。 具体的な活動内容や、その効果、課題などは本文からは読み取れないが、参加者からのアドバイスを得ながら、効果的な言語活動について話し合う場が設けられている。 今後の課題として、グローバル化社会の中で、教育のスピード、効率、コストパフォーマンスばかりが重視される現状への疑問が投げかけられている。
3. 教育における時間と質の重要性の再確認
小財先生の発表で最も印象的だったのは、教育のあり方に関する考察である。グローバル化社会において、教育もスピード、効率、コストパフォーマンスを重視する傾向があるが、先生は、教育は時間のかかるものであり、効率性だけで評価できるものではないと主張する。 「手軽でコストパフォーマンスの良い食材で、マニュアルどおり短時間で手際よく作られたスープがいいですか。それともシェフが食材探しからはじめて、日にちをかけてじっくり作り上げたスープとあなたはどちらを飲みたいと思うか。」という問いかけで、教育における時間と質の重要性を改めて問いかけている。 教育は国家100年の計であり、じっくりと時間をかけて、生徒にとって本当に「美味しい」教育を提供することが大切だと締めくくっている。
