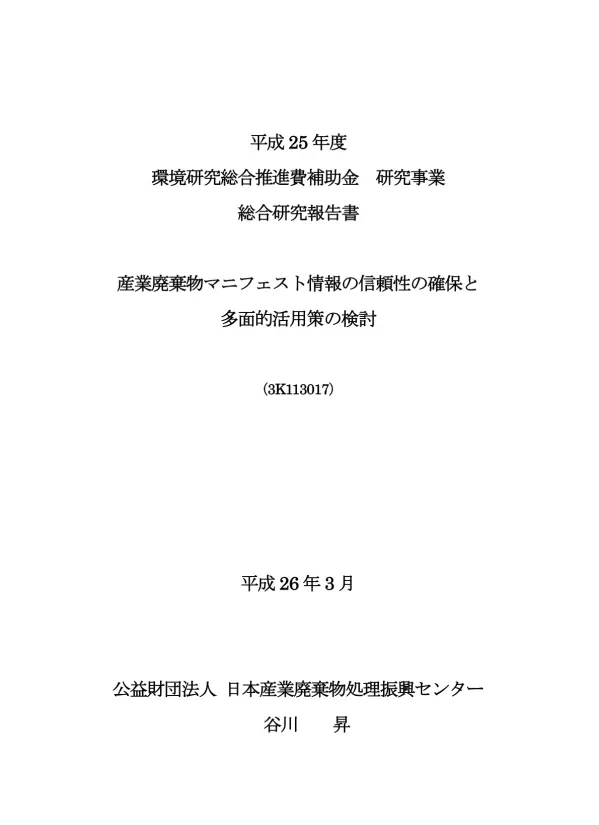
産業廃棄物マニフェスト情報活用策
文書情報
| 著者 | 谷川 昇 |
| 学校 | 該当情報なし |
| 専攻 | 環境学関連 |
| 出版年 | 平成26年(2014年) |
| 会社 | 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター 等 |
| 場所 | 該当情報なし |
| 文書タイプ | 総合研究報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 5.72 MB |
概要
I.マニフェストを用いた産業廃棄物3R推進と適正処理に関する研究
本研究は、持続可能な社会の実現に向け、産業廃棄物の3R推進と適正処理を目的とする。産業廃棄物管理票(マニフェスト)の記載情報(廃棄物の種類、名称、数量等)に着目し、その運用実態と活用状況を分析。電子マニフェストと紙マニフェストの効率的な利用可能性、量・質の流れ解析への活用可能性を明らかにする。特に、マニフェスト記載情報の信頼性向上、熱灼減量や**エネルギー分散型蛍光X線分析(EDXRF)**などの分析手法を用いた廃棄物質の迅速な把握方法、および災害廃棄物へのマニフェスト活用方法を検討した。海外(韓国、台湾、オーストリア、ドイツ、アメリカ)の電子マニフェストシステムの事例も分析し、日本のシステム改善に繋げる方策を提案する。
1. 研究目的 産業廃棄物3R推進と適正処理のためのマニフェスト活用
本研究は、持続可能な社会の実現に向け、産業廃棄物の3R推進と適正処理を促進するための基盤として、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の有効活用を検討する。マニフェスト記載情報(廃棄物の種類、名称、数量など)の分析を通して、マニフェストの運用実態と活用状況を詳細に調査する。具体的には、最終処分場や中間処理施設におけるマニフェスト記載情報の信頼性検証、産業廃棄物の質的特性の現状把握と効率的な分析手法の確立、電子マニフェストと紙マニフェストの効率的な利用可能性の検討を行う。さらに、国・都道府県、排出事業者、処理業者といった関係者がマニフェスト情報を多面的に活用し、3R推進と適正処理を促進するための具体的な方策を提案する。特に、産業廃棄物の量と質の流れを正確に把握するための分析手法の開発と、災害廃棄物の適正処理・リサイクルにおけるマニフェストの活用方法についても検討する。
2. マニフェスト記載情報の分析手法 迅速かつ低コストな質情報取得
本研究では、産業廃棄物の質を迅速かつ低コストに把握するための分析手法の開発に重点を置く。具体的には、熱灼減量測定値と安価なエネルギー分散型蛍光X線分析装置(EDXRF)を用いた元素含有量測定値を組み合わせることで、化学元素組成を短時間で取得する可能性を検証する。特に、目視では質の把握が困難な汚泥を対象に、EDXRFによる化学組成の短時間把握法を提案する。さらに、溶出成分の迅速な分析手法についても検討し、簡易な測定キットや既存メーター類の活用可能性を検証する。これらの結果から、マニフェストに記載する化学元素の質情報を、低コストかつ短時間で提供できることを実証する。 この分析手法の開発は、マニフェスト記載情報の信頼性向上に大きく貢献し、より正確な産業廃棄物の量・質の流れの把握を可能にする。
3. マニフェスト交付等状況報告の活用と課題 データの正確性と効率的な活用
マニフェスト交付等状況報告書の情報に基づき、廃棄物の排出、移動、処理の実態を分析する。自治体の産業廃棄物実態調査よりも詳細な排出・移動量の解析、長距離移動廃棄物の種類・移動先の特定、委託処理原単位の推定、事業所の分別状況、移動時の温室効果ガス排出量の算出など、多角的な分析を行う。 しかし、報告書の有効活用のためには、マニフェスト記載内容の正確性向上、電子化の推進による集計作業の効率化、報告義務者の全数把握が不可欠である。都道府県・政令市は、中間処理業者・最終処分業者に対して、実績報告の数量根拠の確認や重量測定の指導を行う必要性を指摘する。 本研究では、マニフェスト交付等状況報告のデータ活用による、より詳細かつ正確な産業廃棄物管理のあり方を提示する。
4. マニフェストシステムの現状と課題 信頼性向上のための提案
日本のマニフェスト制度の導入経緯と現状、マニフェスト記載情報の信頼性、重量換算係数の妥当性について検討する。最終処分場や中間処理施設へのアンケート調査、現場調査等を実施し、マニフェスト記載情報と搬入廃棄物の一致度、重量測定頻度、重量換算係数への信頼性などを分析する。 その結果、マニフェスト記載情報の信頼性が必ずしも高くなく、特に重量換算係数については、見かけ比重とのずれが大きいケースも見られることが判明した。マニフェスト記載情報の信頼性向上のためには、重量換算係数の見直しが必要であると結論付ける。 さらに、現在のマニフェスト分類が中間処理や最終処分後の管理性に考慮されていない点を指摘し、より効率的な産業廃棄物の管理のための新たな分類基準の必要性を示唆する。
5. 産業廃棄物の質情報に基づいたマニフェスト改善提案 質情報による効率的な管理
産業廃棄物の質に関する情報収集と解析を行い、簡便な質の把握方法を検討する。焼却灰、鉱さい、汚泥、廃プラスチック類、建設混合廃棄物などを対象に、組成分析、金属組成分析、有機成分分析、溶出成分分析などを行い、質情報に基づいたマニフェストのあり方を提案する。 分析結果から、燃えがら、ばいじんでは塩類含有量が高い傾向がある一方、一部には塩類濃度の低い廃棄物もあり、排出元による細分類が重要であると結論付ける。鉱さいでは有用金属を高濃度で含有するものが多く、含有量情報の付加による有効利用の可能性を示唆する。 さらに、質情報と管理の目安、生じうる問題点をリンクさせた整理方法を提案し、リサイクルを含めた維持管理の容易化、受け入れコスト基準の設定への活用可能性を示す。 質情報に基づいた新たな分類基準の開発、産業廃棄物の組み合わせ処分による安定化促進などの研究の必要性も示唆する。
6. 国際比較 海外電子マニフェストシステムの事例分析と日本の課題
韓国、台湾、オーストリア、ドイツの電子マニフェストシステムを比較分析する。韓国では電子マニフェストの義務化による業務効率化、リアルタイム監視による不法投棄防止、信頼性の高い廃棄物統計データの取得といった効果が認められる。台湾ではGPS追跡システムと連携した厳格な監視体制が構築されている。オーストリアでは排出事業者の責任範囲の柔軟性、ドイツでは州レベルでの連携による効率的なシステム運営が特徴的である。 アメリカにおける電子マニフェストシステム導入に向けた取り組みについても調査する。これらの事例分析から、日本のマニフェストシステムの課題を抽出し、改善に向けた具体的な提案を行う。特に、電子マニフェストの普及促進、データの信頼性向上、効率的なデータ活用のための施策を検討する。
7. マニフェスト情報の多面的活用と今後の展望 データ見える化による効果的な施策立案
マニフェスト交付等状況報告書の多面的活用策の実行可能性を検証するため、都道府県・政令市、排出事業者、収集・運搬事業者、処理処分事業者へのアンケート調査を実施する。マニフェスト記載情報の信頼性向上、報告書作成・集計の効率化のための提案に対し、関係者から概ね実現可能との回答を得る。 マニフェスト交付等状況報告書のデータを用いて、産業廃棄物の排出・移動・処理状況を可視化し、排出量、移動量、処理量の分析、長距離移動廃棄物の特定、委託処理原単位の推定、事業所の分別状況、温室効果ガス排出量の算定を行う。静岡県内を事例として、排出場所と移動先の可視化による効果的な施策立案の可能性を示す。 神奈川県、鳥取県などの自治体の取り組み事例を紹介し、より詳細な情報を収集するための報告様式の改善策を提案する。
II.マニフェスト記載情報の信頼性と活用実態
全国の産業廃棄物最終処分場・中間処理施設を対象としたアンケート調査等により、マニフェスト記載情報の信頼性と、マニフェスト交付等状況報告の活用実態を分析。重量換算係数の精度、見かけ比重のばらつき、排出事業者における分別状況など、マニフェスト情報の正確性向上のための課題を明らかにした。特に、紙マニフェストの利用率が高い現状と、その報告における課題を指摘。電子マニフェストの普及促進によるデータの信頼性向上と、効率的な廃棄物統計データ収集の可能性を示唆した。
1. マニフェスト記載情報の信頼性に関する調査 現場調査とアンケート調査
本節では、産業廃棄物最終処分場および中間処理施設におけるマニフェスト記載情報の信頼性に関する調査結果をまとめる。全国212カ所の産業廃棄物最終処分場(安定型と管理型)を対象にアンケート調査を実施した。調査項目は、施設情報、パソコン等の有無とマニフェスト管理への利用状況、トラックスケールの有無と廃棄物重量測定頻度、マニフェスト記載情報と搬入産業廃棄物の一致度など多岐に渡る。特に、北海道、静岡県、富山県、愛知県、三重県、広島県、福岡県等の産業廃棄物協会の協力を得て、調査対象施設の選定とアンケート配布、回収を実施した。 北海道については、許可数と稼働率の高さを考慮し、1協会あたり10施設を目標としたが、全国の約17%をカバーする規模とした。 この調査を通して、マニフェスト記載情報の現状と課題を明らかにし、信頼性向上のための具体的な方策を検討する。
2. マニフェストの運用状況と記載情報活用の実態解析 アンケート調査と現場調査
平成23年度と24年度に、産業廃棄物協会等の協力を得て、最終処分場と中間処理施設におけるマニフェストの運用状況に関するアンケート調査を実施した。対象は、排出事業者、収集・運搬事業者、中間処理事業者、最終処分場事業者など。 また、都道府県・政令市への許可更新申請を行う事業者を対象とした講習会において、中間処理・最終処分事業者のマニフェスト記載情報への認識と活用実態に関するアンケート調査も実施した(平成23年度)。 これらの調査を通して、マニフェスト記載情報の信頼性、運用上の課題、データの活用状況などを多角的に分析し、より効果的なマニフェスト活用のための改善策を提案する。 調査地域は、北海道、首都圏、神奈川県、静岡県、富山県、愛知県、三重県、広島県、福岡県など広範囲に及ぶ。
3. マニフェスト記載情報の信頼性検証 重量換算係数と見かけ比重の比較分析
マニフェスト記載情報の信頼性を検証するため、重量換算係数と見かけ比重の比較分析を行った。最終処分場と中間処理施設に搬入される産業廃棄物について、見かけ比重の測定を行い、そのばらつきと平均値を定量的に明らかにした。 平成25年度までの調査結果と環境省通知の重量換算係数を比較した結果、産業廃棄物の種類によっては、大きな違いが見られた。アンケート調査の結果からも、処理・処分事業者における重量換算係数への信頼性が低いことが確認された。 この結果から、マニフェスト記載情報の信頼性向上のためには、重量換算係数の迅速な見直しが必要であると結論づけた。 分析対象には、汚泥、鉱さい、シュレッダーダスト、焼却灰など、量が多く化学組成の判別が困難な廃棄物が含まれる。
4. マニフェスト交付等状況報告の有効活用 データ解析による産業廃棄物管理の高度化
マニフェスト交付等状況報告書を活用し、産業廃棄物の排出、移動、処理実態の解析を行った。その結果、排出・移動量のより詳細な解析、長距離移動廃棄物の種類や移動先の特定、委託処理原単位の推定、事業所の分別状況、移動時の温室効果ガス排出量の算出などが可能であることを示した。 しかし、この報告書の有効活用のためには、マニフェスト記載内容の正確性向上、電子化による集計作業の効率化、報告義務者の全数把握を可能にする制度構築が必要であると結論づけた。 特に、紙マニフェスト利用者からの報告において、都道府県・政令市が報告者の総数を把握できていない現状を指摘し、報告データの代表性に関する信頼性確保の必要性を強調した。 本研究では、マニフェスト交付等状況報告のデータ活用による、より詳細かつ正確な産業廃棄物管理のあり方を提案する。
III.産業廃棄物の質情報に関する分析と簡便な把握方法
最終処分場に搬入される汚泥、鉱さい、シュレッダーダスト、焼却灰等を対象に、EDXRFと波長分散型蛍光X線分析(WDXRF)を用いた化学元素組成分析、溶出試験、粒径組成分析を実施。熱しゃく減量測定値との比較検討から、低コスト・短時間での質情報取得の可能性を示した。さらに、簡便な測定キットを用いた溶出成分の迅速分析手法を検討し、鉛、六価クロム、ヒ素、カルシウムなどの特定成分の簡易分析法を提案した。これらの結果に基づき、質情報を含むマニフェストのあり方を提案。
1. 産業廃棄物の質情報収集と分析 最終処分場搬入廃棄物の特性把握
本節では、最終処分場に搬入される産業廃棄物の質に関する情報を収集・分析し、その特性を明らかにする。特に、量が多く、化学組成の判別が困難で、有害物質の溶出量基準が設定されている汚泥、鉱さい、シュレッダーダスト、焼却灰の4グループを重点的に分析する。これらの廃棄物について、粒径組成分析、エネルギー分散型蛍光X線分析(EDXRF)、各種イオン類・有機物の溶出試験などを実施し、主要構成成分、有害金属、希少金属の含有量などの質的情報を整理する。 分析結果から、各廃棄物グループの特性を明らかにするとともに、マニフェストに記載すべき質情報項目の選定、およびそれらの情報を効率的に管理する方法を検討する。 既存文献情報も参考に、より精緻な質情報に基づいた産業廃棄物管理のあり方を提案する。
2. 簡便な質情報把握方法の検討 EDXRF分析と簡易測定キットの活用
産業廃棄物の質情報を簡便かつ低コストで把握するための分析手法を開発する。高額な波長分散型蛍光X線装置(WDXRF)と安価なエネルギー分散型蛍光X線装置(EDXRF)を用いた金属類分析値を比較検討し、EDXRFを用いた簡易分析手法の開発を行う。 汚泥については、有機物マトリックスを除去するために焼却残渣を分析し、検出元素を100%として金属類の含有率を算出する。熱しゃく減量による補正を行い、EDXRFを用いた簡易分析手法の精度を評価する。 溶出成分については、迅速な試料調製方法と簡易な測定キットの可能性を検討する。鉛、六価クロム、ヒ素、カルシウムなどの特定成分について、パックテストなどの簡易分析キットの適用可能性を評価する。 これらの検討を通して、マニフェストに記載する質情報を低コスト・短時間で提供可能な手法を提案する。
3. 汚泥の詳細検討 各種分析手法の比較と簡易分析手法の開発
本節では、特に質的多様性が高い汚泥について、詳細な分析を行う。EDXRFとWDXRFによる分析結果を比較し、有機物マトリックスの影響を考慮した分析手法を検討する。汚泥の焼却残渣についてバルクFP法を用いた測定を行い、熱しゃく減量による分析結果の補正を行う。 処理・処分・再利用の観点から考慮すべき元素群に分類し、簡易分析手法で得られたデータと化学含有量分析のデータとの比較を行う。これにより、簡易分析手法の精度を評価する。 溶出量試験の迅速化についても検討する。汚泥、鉱さい、廃プラスチック処理残渣、燃えがらを対象に、溶出量の時間変化を調べ、公定法値との関係を分析する。鉛、六価クロム、ヒ素などの特定成分の簡易分析法についても検討する。
4. 埋立物管理による溶出制御の可能性 混合廃棄物における溶出特性の検討
最終処分量が多く、質が大きく異なる複数の産業廃棄物について、単独および2種混合での溶出試験を行い、溶出成分への影響を検討する。塩類を多く溶出する燃えがらと、異なる組成を持つ4種類の汚泥を供試サンプルとする。 溶解度積の影響、含有成分間の相互作用による溶出量の変化を確認する。着色状況やろ過抵抗から有機物や鉄の溶出濃度への影響も評価する。 これらの分析結果から、埋立処分場における溶出制御の可能性、および廃棄物の混合による影響を評価し、より安全で効率的な埋立処分管理のための知見を得る。 分析対象には、カルシウム、塩化物イオン、硫酸イオンなどを多く含む燃えがら、および土壌様試料、高鉄含有・低塩類溶出試料、高Ca・低pH試料、高Si・低塩類溶出試料の4種類の汚泥が含まれる。
5. 質情報に基づいたマニフェストのあり方提案 新たな分類基準と管理方法
本節では、これまで得られた分析結果と文献調査に基づき、産業廃棄物の質を考慮したマニフェストのあり方を提案する。 従来のマニフェスト分類に加え、管理上重要な項目(含有成分、溶出成分、熱しゃく減量、粒径分布など)をチェックできるマニフェストの例を示す。排出事業者と処理事業者が自ら分析した情報をマニフェストに記載、もしくはWDSとして添付する仕組みを提案する。 質情報とその管理の目安、生じうる問題点をリンクさせた整理方法を提案する。これにより、リサイクルを含む維持管理の容易化、受け入れコスト基準の設定への活用可能性を示す。 さらに、質情報が集積・整理されることで、新たな分類基準が生じたり、産業廃棄物間の効率的な管理(組み合わせ処分による安定化促進など)が進む可能性を示唆する。
IV.海外の電子マニフェストシステムの事例研究
韓国、台湾、オーストリア、ドイツの電子マニフェストシステムを調査。韓国ではリアルタイム監視、データの信頼性、効率的な統計データ収集といった利点を明らかにした。台湾ではGPS追跡システムと組み合わせた厳格な監視体制、オーストリアでは排出事業者の責任範囲に関する柔軟なシステム設計、ドイツでは州レベルの連携による効率的なシステム運営を確認。アメリカにおける電子マニフェスト導入に向けた取り組みについても文献調査を実施。これらの事例から、日本のシステム改善に向けた示唆を得た。
1. 韓国の電子マニフェストシステム リアルタイム監視とデータ利活用
韓国の電子マニフェストシステムは、対象範囲が広く、政府・自治体関係者、排出事業者、収集運搬事業者、中間処理事業者、最終処分事業者など、幅広い関係者が利用している。システムの特徴は、リアルタイムに近い状況での廃棄物流れの監視による不法投棄・不適正処理の防止、データの信頼性に基づく廃棄物統計の構築、電子化によるデータ集計・統計の容易化による廃棄物管理計画への活用にある。 電子マニフェストの義務化により、事業者と行政双方の業務効率化とコスト削減が実現している。 ヒアリング調査を通して、システム構築の経緯、システム内容、バーゼル条約に係る越境移動への利用状況、電子マニフェスト情報の具体的な活用方法などを詳細に調査した。 韓国の事例は、日本の電子マニフェストシステム改善のための重要な示唆を与えてくれる。
2. 台湾の電子マニフェストシステム GPS追跡システムと広範な報告義務
台湾の電子マニフェストシステムは、韓国と同様にリアルタイム監視機能、電子マニフェスト統計システム、オンライン報告制度を備えているが、運営主体は国(環境保護署)である点が異なる。 特徴的なのは、有害廃棄物の収集運搬車両をGPS端末でリアルタイム追跡監視するシステム(2002年運用開始、2012年時点で6,880台)の積極的な活用である。 排出事業者は、毎月の廃棄物排出量に加え、生産能力、原料投入量、廃棄物保管量、リサイクル量、輸出入量などの情報を報告する必要がある。約20%の排出者(全体の排出量の80%)が全ての情報をオンライン管理しており、行政によるマニフェストの点検はほとんど行われていない。有害物質については環境保護署が管理している。 日本への廃棄物輸出における課題として、日本側の審査期間の長さを指摘。台湾では電子マニフェストシステムにより1ヶ月程度で済む手続きが、日本では約1年かかっている点を問題視した。
3. オーストリアの電子マニフェストシステム 柔軟な責任分担と情報伝達システム
オーストリアの電子マニフェストシステムは、排出者が廃棄物の最終処分まで確認する「Cradle to Grave」システムではない点が特徴である。排出事業者は収集運搬業者とのみ契約することも可能で、収集運搬業者が市場原理に基づき処理業者を選択する。 電子マニフェスト情報は、各州のインターネットポータル、プロバイダー、EDIの3ルートを介してインターネットで伝送される。公共部門はウェブポータルで情報照会を行い、関係者間の交信はバーチャル郵便箱で行われる。 行政による監視は、マニフェスト情報に基づく廃棄物監視システム(ASYS)で行われる。電子署名の信頼性確保のため、トラストセンターが設置されている。 オーストリアとベルギーでのパイロット試験(2013年)成功後、他の加盟国への拡大を予定している(オランダ、ドイツ、スイス、ルクセンブルク)。
4. ドイツの電子マニフェストシステム 州レベルの連携による効率的な運営
ドイツの電子マニフェストシステムは、韓国や台湾と同様に6枚組みのマニフェストを使用し、基本的な流れは同じである。これは、韓国と台湾がドイツのシステムを参考に構築したためである。 ZKS-Abfall(中央調整室‐廃棄物)が、マニフェスト関係者(事業者、運搬業者、処分業者、州当局)の総合交信プラットホームとして機能し、電子マニフェスト情報の集約・変換を行う。運営主体は、16の州の共同プロジェクト組織であり、連邦政府は助言・支援を行う。 関係者の署名と主管当局によるマニフェスト内容確認により、記載情報の信頼性が確保されていると推察される。 ドイツのシステムは、州レベルでの連携による効率的な運営が成功要因の一つとして考えられる。
5. アメリカの電子マニフェストシステム 導入に向けた取り組みと現状
アメリカにおける電子マニフェストシステム構築への取り組みは、2001年のEPAの提案から始まり、10年以上にわたる利害関係者との意見収集、パイロット試験、データ収集などを経て進められている。 2012年10月には、「有害廃棄物電子マニフェスト設立法(Hazardous Waste Electronic Manifest Establishment Act)」が制定された。 本研究では、アメリカの取り組みについて文献調査を行い、日本のシステム構築・改善に役立つ情報を収集した。 アメリカでの取り組みは、長期的な視点と関係者間の合意形成の重要性を示唆している。
V.マニフェスト交付等状況報告の多面的活用策
マニフェスト交付等状況報告のデータを活用し、産業廃棄物の排出・移動・処理の実態を詳細に分析。排出量、移動量、処理量の解析、長距離移動廃棄物の特定、委託処理原単位の推定、事業所の分別状況把握、温室効果ガス排出量の算定が可能であることを示した。特に、静岡県内の事例を用いて、見える化による排出・移動状況の把握方法を提案。また、神奈川県、鳥取県等の自治体の取り組み事例を紹介し、より詳細な情報を収集するための報告様式の改善策を提案した。
1. マニフェスト交付等状況報告のデータ分析 排出 移動 処理実態の把握
マニフェスト交付等状況報告書に含まれるデータを活用し、産業廃棄物の排出、移動、処理の実態を詳細に分析する。従来の自治体による実績報告書等を用いた産業廃棄物実態調査よりも詳細な分析が可能となる。具体的には、排出量と移動量の解析、長距離移動する産業廃棄物の種類と移動先の特定、委託処理原単位の推定、事業所における産業廃棄物の分別状況の把握、そして移動に伴う温室効果ガス排出量の算出などが実現する。これにより、産業廃棄物行政におけるより効果的な施策立案や事業者への適切な指導が可能となる。分析の結果、地域ごとの排出・処理状況の差異や、特定地域への大量移動といった傾向が明らかになり、不適正処理の有無の確認にも繋がる。
2. マニフェスト交付等状況報告の更なる活用に向けた課題 データの正確性と効率化
マニフェスト交付等状況報告書を効果的に活用するためには、いくつかの課題を克服する必要がある。まず、マニフェスト記載内容の正確性を向上させる必要がある。次に、電子化の推進による集計作業の効率化が求められる。紙マニフェストが依然として多く利用されている現状では、データ入力の手間と人為的ミスの可能性が高いため、電子化による効率化は不可欠である。さらに、マニフェスト交付等状況報告書を提出すべき事業者の全数把握を可能にする制度設計が必要となる。特に、紙マニフェストを使用する事業者については、その総数把握が困難なため、報告データの代表性に疑問が残る。これらの課題を解決することで、より信頼性の高いデータに基づいた産業廃棄物管理が可能となる。
3. マニフェスト交付等状況報告の見える化 排出 移動状況の可視化と効率的管理
マニフェスト交付等状況報告書のデータを可視化することで、委託産業廃棄物の排出場所と移動先を明確に把握することができる。これにより、多くの廃棄物が発生している地域や、処理施設が集中している地域を容易に特定できる。 静岡県を例に、排出場所と移動先を地図上に表示することで、地域ごとの排出量や移動量の偏り、遠方への大量移動などの特徴を明確に示す。 静岡市と浜松市では、マニフェスト記載情報に発生場所の詳細な住所が記載されていなかったため、市役所の住所が排出場所として扱われたことが分析結果に影響を与えた。 東京都八丈島への産業廃棄物の特異的に高い移動量なども、可視化によって容易に把握できる。この見える化は、不適正処理の監視や、効果的な廃棄物処理計画の立案に役立つ。
4. 委託処理原単位の推定と事業所別分析 事業規模と廃棄物排出量の関連性
マニフェスト交付等状況報告書と、事業規模を示す従業員数や売上高などの公開情報(エコアクション21認証事業所の環境活動レポート、多量排出事業者による産業廃棄物処理計画実施状況報告書)を組み合わせることで、産業廃棄物の委託処理原単位を推定する。 静岡県内の建設業3社を例に、売上高と処理委託産業廃棄物量の関係を示し、業種、事業規模、廃棄物分別状況などとの関連性を分析する。 分析の結果、同じ建設業でも事業内容によって排出される廃棄物の種類と割合が大きく異なることが明らかになった。 また、廃棄物分別が進んでいない事業所では建設混合廃棄物の比率が高くなる傾向が見られた。 これらの分析は、事業者ごとの廃棄物排出特性を把握し、より効果的な指導を行う上で重要な情報を提供する。
5. 自治体事例 神奈川県と鳥取県の取り組みと報告様式の改善提案
神奈川県と鳥取県におけるマニフェスト交付等状況報告書の活用事例を紹介する。 神奈川県では、多量排出事業者に対し、報告様式に項目を追加し、発生量、有償物量以外の数値の記載を求めている。これにより、自己処理される産業廃棄物の詳細なフローを把握できるようになる。 鳥取県では、県独自のアンケート欄を設け、発生量、中間処理方法、最終処分方法、事業概要(従業員数、売上高など)の記載を求めている。これにより、自己処理量、委託処理量、最終処分量などを詳細に把握し、県全体の排出量推計が可能となる。 これらの事例から、マニフェスト交付等状況報告書の様式を改善し、より詳細な情報を収集するための提案を行う。多量排出事業者だけでなく、全事業者からの報告を促進するための制度設計も重要となる。
