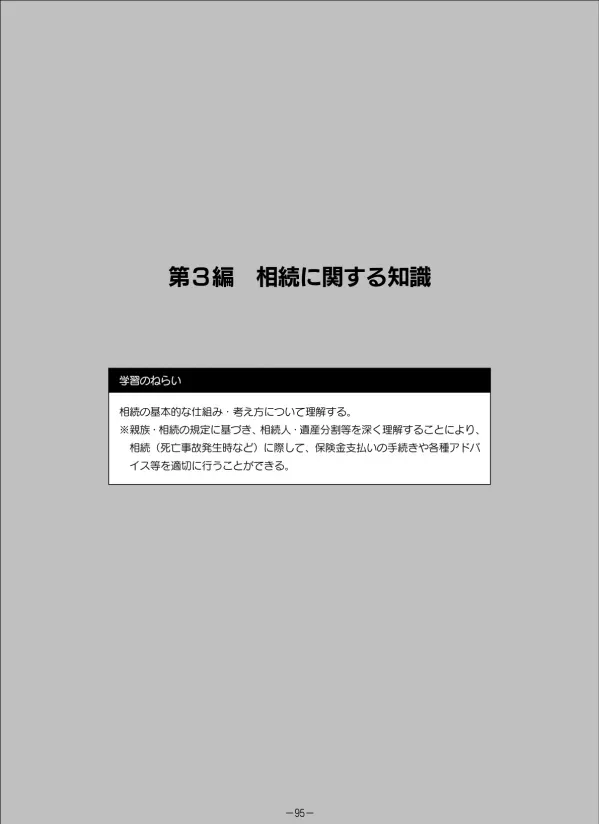
相続の基本知識:親族・夫婦関係
文書情報
| 学校 | 大学名(不明) |
| 専攻 | 民法、相続法、損害保険法等 |
| 出版年 | 不明 |
| city | 不明 |
| 文書タイプ | 講義資料、テキスト |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 886.10 KB |
概要
I.第1章 家族関係 婚姻と離婚 親子関係の基礎
本章では、日本の民法に基づく家族関係の基礎を解説します。婚姻に関する法律上の定義と、事実婚である内縁との違い、婚姻費用分担、夫婦財産契約の重要性を説明します。また、離婚の種類(協議離婚、裁判離婚)と手続きについても触れます。さらに、親子関係、特に認知や養子縁組の手続きと法的効力について解説します。未成年者の婚姻や養子縁組における法定代理人の役割も重要なポイントです。
1. 婚姻と内縁の違い
この節では、法律上の婚姻と事実婚である内縁の区別について説明しています。婚姻届の提出有無が、法律上の夫婦関係の成立を決定づける重要な要素であると強調されています。婚姻届を提出していない場合、たとえ結婚の意思があり共同生活を送っていても、法律上は内縁関係とみなされ、婚姻関係とは異なる法的扱いを受けることを明確に示しています。婚姻と内縁では、法律上の規定に様々な違いがあることも指摘されています。また、夫婦間で締結された契約は、婚姻中はいつでも一方の意思で取り消すことができる一方、民法第754条に基づき、第三者の権利を害することはできないと規定されています。2022年4月1日以降は民法改正により未成年者の婚姻が認められなくなるため、関連規定は削除されるとの注記もあります。
2. 夫婦の財産と婚姻費用
婚姻前の財産と婚姻中に取得した財産は、それぞれの特有財産となります。所有者が不明な財産は、民法第762条に基づき夫婦の共有財産と推定されます。婚姻費用については、民法第760条に基づき、夫婦は資産、収入などを考慮して分担する義務があると規定されています。しかし、夫婦財産契約は婚姻届出前に締結し、婚姻届出までに登記しなければ第三者に対抗できない(民法第755条、第756条)ため、実際にはあまり利用されておらず、法定財産制が用いられるのが一般的であると説明されています。また、一方の配偶者が死亡した場合、生存配偶者の姻族関係は、その意思表示によって初めて終了するとされています(民法第728条第2項)。
3. 離婚の種類と手続き
離婚の種類として、協議離婚(民法第763条)と裁判離婚(民法第770条第1項)が紹介されています。協議離婚は、夫婦間の合意と届出によって成立しますが、裁判離婚は協議が成立しない場合に、不貞行為や悪意の遺棄などの理由で裁判所が離婚を認める手続きとなります。成年の子の認知には、その子の承諾が必要であること(民法第782条)、そして嫡出でない子の母子関係については、最高裁判例では分娩の事実によって確定するため認知は不要とする見解が示されていること(最判昭37.4.27)などが説明されています。
4. 養子縁組と親子関係
養子縁組について、15歳未満の子の養子縁組には法定代理人の代諾が必要であること(民法第797条)が述べられています。養子縁組によって養親子間の権利義務が生じるものの、実親との法的親子関係に変更はないと明確にされています。親権者の代理権限は、原則として財産上の行為に限定され、身分上の行為は相続の承認・放棄などに限られるとされています(民法第824条)。親子間の利益が相反する行為の場合は、親権者は家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければならないとされ(民法第826条第1項)、裁判所は調停に付さなければならない(家事事件手続法第257条第1項、第2項)と規定されています。また、審判離縁についても家庭裁判所の権限として簡潔に説明されています。
II.第2章 相続 相続開始から遺産分割まで
この章では、相続に関する重要な事項を網羅的に説明します。被相続人の死亡による相続の開始、相続人の範囲、相続財産の範囲(積極財産、債務を含む)を解説します。代襲相続、相続欠格、推定相続人の廃除といった、相続における特殊な状況についても触れます。遺留分の概念と遺留分減殺請求権についても詳述し、単純承認、限定承認、相続放棄といった相続人の権利行使についても解説します。遺産分割の方法(協議による分割)と共同相続人間の責任、そして特別受益(生前贈与、遺贈)の取り扱いについて解説し、最新の民法改正(2018年改正)による配偶者の相続強化についても言及します。戸籍法に基づく死亡届出義務なども重要な要素です。
1. 相続の開始と相続人の要件
この節では、相続の開始と相続人の要件について説明しています。相続開始は被相続人の死亡によって発生し、相続人は被相続人の死亡時に生存している必要があります。被相続人と相続人が同時に死亡した場合、民法第32条の2に基づき、誰が先に死亡したかが不明な場合は同時に死亡したものと推定され、相続は開始しないとされています。相続開始の事実を戸籍法に基づき、死亡届を7日以内に届け出る必要があることも重要です。この届出義務者は、親族などが担います。相続人の範囲、特に代襲相続(被相続人の死亡前に相続人が死亡した場合、その相続分をその子の直系卑属などが相続する制度)についても解説されています。代襲相続の原因となる事由には、相続人の死亡、相続欠格、推定相続人の廃除などが挙げられています。相続欠格とは、被相続人を殺害したり、詐欺や強迫で遺言作成を妨害した場合など、被相続人との関係を破壊した相続人は相続資格を失うことを指し、民法第891条で規定されています。また、推定相続人の廃除は、遺留分を有する相続人が被相続人を虐待した場合などに、家庭裁判所が相続権を剥奪する制度で、民法第892条で規定されています。
2. 相続財産と債務の承継
相続財産には、預貯金、有価証券、不動産、動産、権利など様々なものが含まれ、被相続人の不法行為や債務不履行による損害賠償請求権や慰謝料請求権も含まれると説明されています(最判昭42.11.1)。相続できる財産の範囲は、民法第896条で規定されており、単なる具体的な権利義務だけでなく、将来発生する可能性のある権利義務も含みます。ただし、すでに具体化しているもの(過去の扶養料、内縁の不当破棄に基づく慰謝料など)は相続の対象となります。相続財産には債務も多い場合があり、相続人が知らない債務まで承継するのは不公平であるため、民法では相続人に債務を承継するか、責任を免れるかの選択権(単純承認、限定承認)を与えて相続人の利益を保護しています。単純承認は、被相続人の権利義務を無条件で承継することを意味し、相続財産が債務超過の場合、相続人の固有財産も弁済に充てられます(民法第920条)。一方、限定承認は、相続財産を限度として債務を弁済するもので、相続財産と相続人の固有財産は別個に清算されます(民法第922条、第926条)。限定承認の手続きには、3ヶ月の熟慮期間内の財産目録の作成と家庭裁判所への申述が必要です(民法第924条)。
3. 遺産分割と特別受益
この節では、遺産分割と特別受益について解説されています。遺産分割は、遺産の種類、相続人の状況などを考慮して行われ(民法第906条)、遺言で禁止されていない限り、共同相続人は協議によって分割できます(民法第907条第1項)。遺産分割は相続開始時に遡及して効力を生じますが、第三者の権利を害することはできません(民法第909条)。共同相続人が取得した財産に欠陥があった場合、各相続人はその相続分に応じて担保責任を負います(民法第911条)。特別受益とは、被相続人から生前に贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合、相続分の算定において不公平が生じるため、民法では、公平を確保するために、これらの贈与を加えた上で相続分を算出する「特別受益の持戻し」(民法第903条第1項)や、被相続人の事業に貢献した相続人には、その寄与分を加算して相続分を算出する規定(民法第904条の2第1項)があります。また、相続手続きの負担軽減のため、法務局が「法定相続情報証明書」を発行する新制度にも言及されています。
III.第2章 相続 遺言と遺言執行
遺言の法的性質、遺言の方式(自筆証書、公正証書、秘密証書など)、受遺者、遺贈義務者について説明します。遺言執行者の役割と遺言書の検認手続きについても解説します。相続人が遺言の内容を実行できない場合の遺言執行者の重要性も強調します。 特に、民法第896条、民法第903条、民法第904条の2、民法第960条、民法第1004条といった条文に関連する内容に焦点を当てます。
1. 遺言の法的性質と方式
この節では、遺言の法的性質と方式について解説しています。遺言は、被相続人が死後に効力を発生させる目的で行う要式行為であり(民法第960条)、遺言者の生前の最終意思が尊重されます。ただし、遺言事項は、遺産相続、財産処分、および一定の身分行為に限られます。遺言の方式として、自筆証書、公正証書、秘密証書の普通方式と、特別方式が存在します(民法第967条)。このテキストでは、普通方式について説明されており、特別方式は死亡の危急に迫られた者などに対する特別な方式であるとされています。受遺者には、法人・自然人の区別なく、胎児も含まれるとされ(民法第965条、第886条)、相続人と同様に欠格事由も存在すると説明されています。遺贈義務者は、遺贈による財産の引渡しや登記手続きなどを履行する者であり、原則的には相続人が担うことになります。遺言の加除訂正を行う際には、変更箇所を指定し、変更した旨を付記して署名・押印する必要があること、証人と立会人の役割についても触れられています。
2. 遺言の執行と検認
この節では、遺言の執行と遺言書の検認について説明しています。遺言の執行とは、遺言の効力発生後、その内容を実現するための事務を行うことであり、遺言書の保管者は、相続開始後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を受けなければなりません(公正証書による遺言を除く)(民法第1004条第1項)。封印のある遺言書の開封は、検認前に家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いの下で行われなければなりません(民法第1004条第3項)。検認は、遺言書の現状を確認し、偽造・変造を防ぐための証拠保全手段です。遺言執行者については、嫡出でない子の認知、相続人の廃除とその取消し、相続人の利益に反する遺贈や寄附行為など、相続人に執行させることが公正を期すことができない場合に、別途選任される必要があると説明されています。
