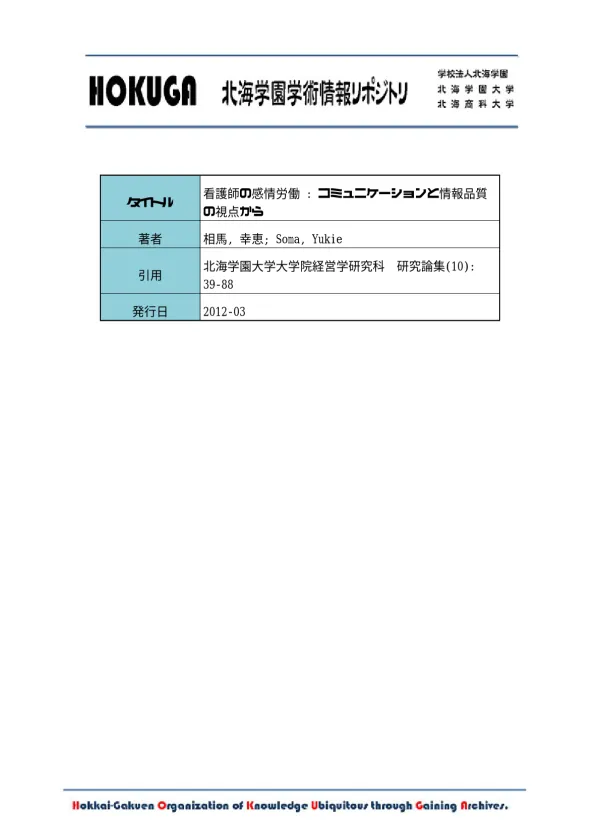
看護師の感情労働:コミュニケーションと情報品質
文書情報
| 著者 | 相馬幸恵 |
| 学校 | 北海学園大学大学院経営学研究科 |
| 専攻 | 経営学 |
| 文書タイプ | 研究論集論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 4.87 MB |
概要
I.看護師の専門性と基礎教育制度
本論文は、日本の医療現場における看護師 (kango-shi) の役割と課題に焦点を当てています。特に感情労働 (kanjou roudou) の視点から、看護師の専門性、基礎教育制度、人材育成プログラムを分析し、病院経営 (byouin keiei) における顧客満足度 (kokyaku manzoku-do) 向上への貢献を考察します。看護師の定義と法的規制、准看護師 (jun kango-shi) 問題、4年制大学化の進展(1991年9校→2010年188校)、新人看護職員研修事業などの現状を整理します。チーム医療 (chiimu iryou) 推進のためには、看護師の専門性の向上と役割拡大が不可欠であり、特定看護師養成調査試行事業(平成22年度開始)なども紹介しています。
1. 看護師の定義と役割
本論文では、まず看護師の定義を保健師助産師看護師法第5条に基づき明確化します。2007年時点で88万人が従事する看護師は、厚生労働大臣の免許を受けて傷病者または産婦に対する療養上の世話や診療補助を行うことを業とする者と規定されています。同法第37条では、医師の指示の下で職務を遂行することが義務付けられており、これは他の専門職とは異なる点です。看護師の日常業務は採血・点滴などの治療行為から、ベッドメイキング、食事介助、排泄の世話といった日常生活の援助、さらにはクレーム対応まで多岐に渡り、時に患者のプライベートな相談にも応じることを求められるため、多大な負担となっています。こうした負担は、新人看護師の早期離職の一因とも指摘されています。
2. 看護師教育制度の現状と課題
質の高い看護師を育成するため、基礎教育の充実と制度改革が求められています。具体的には、看護師教育の4年制大学化の促進が挙げられ、文部科学省の統計によると、1991年には9校だった看護系大学は2010年には188校に増加しています。さらに、看護の質向上、医療安全確保、新卒看護師の早期離職防止を目的として、厚生労働省は平成22年度から新人看護職員研修事業を開始し、卒後臨床研修が努力義務として実施されています。しかし、養成機関の多様性、特に2年課程の准看護師養成機関の多様性により、看護師養成制度は非常に複雑なものとなっています。日本看護協会は准看護師の廃止と資格統一を目指していますが、日本医師会は看護師、准看護師、看護補助者の三層構造を維持すべきという立場を取っており、准看護師問題は依然として解決に至っていません。
3. 専門看護師と認定看護師
高度な専門性を有する看護師として、専門看護師と認定看護師が挙げられます。専門看護師は、日本看護系大学協議会が教育課程を認定し、実践、相談、調整、倫理調整、教育、研究の6つの役割を担います。一方、認定看護師(CEN)は日本看護協会が認定し、特定分野において熟練した技術と知識を持つ者として、実践、指導、相談の3つの役割を担います。これらの専門看護師や認定看護師の育成は、チーム医療推進における医療スタッフの専門性向上、役割拡大、連携強化に大きく貢献すると期待されています。専門看護師、認定看護師の育成開始年や認定者数については、本文中の表2、表3、図3を参照のこと。
4. チーム医療における看護師の役割と将来展望
チーム医療において、看護師はクライアントや医師などから大きな期待を寄せられるキーパーソンです。診察・治療関連業務から療養生活支援まで幅広い業務を担うことから、厚生労働省は看護師の専門性を活かし、医療サービスの質向上とクライアントのQOL向上を目指しています。そのため、看護師が実施可能な行為の拡大と、特定の医行為を医師の指示下で実施できる新たな枠組みの構築(特定看護師養成調査試行事業、平成22年度開始)が検討されています。大分県立看護科学大学大学院では2008年4月から老年及び小児のナース・プラクティショナー養成教育が始まるなど、高度な実践家の育成も進められています。 厚生労働省のチーム医療推進に関する検討会報告書(2010年3月)も参照。
5. ジェネラリストとスペシャリスト エキスパートの役割分担
看護職における専門分化は、ジェネラリストの存在があって初めて可能となります。スペシャリストやエキスパートは、それぞれの専門領域で高度な知識・技術を持つ一方で、ジェネラリストは幅広い知識と技術を備え、あらゆるクライアントに対応できる存在として重要です。看護管理者は、これらの多様な職域の看護師がそれぞれの能力を最大限に発揮できるよう、システム構築、人員配置、マネジメント、人材育成を行う必要があります。変化する社会ニーズに対応するため、看護職における役割分担の明確化がますます重要になっています。
II.医療現場におけるコミュニケーションと情報伝達
医療現場は、看護師、医師、患者間における効果的なコミュニケーション (komyunikeshon) が不可欠です。医療現場 (iryou genba) の特殊性として、複数の医療従事者が同時並行的にタスクを処理し、患者の状態が絶えず変化することを踏まえ、情報伝達の質と感情労働の関連性を分析します。カルテなどの紙媒体と対面コミュニケーションの両方を検討し、情報伝達における問題点、特に患者の主観的情報の取り扱いにおける課題を明らかにします。近年、在院日数短縮に伴い、入院前からの明確な診療計画と患者の意思尊重が重要となり、そのためにもコミュニケーションの活性化が求められています。
1. 医療現場のコミュニケーション特性
医療現場は、複数の個人とシステムが共同で目標達成を目指す複雑な場です。個々の医療・看護行為は比較的単純ですが、時間的に分散して発生し、一人の看護師が複数のタスクを同時並行的にこなすことが一般的です(松本斉子他、2009)。さらに、患者の状態は刻々と変化し、その対応が患者の生死に関わるため、多様で臨機応変な対応が求められます。特に病棟では、医師と看護師間の円滑なコミュニケーションが不可欠です。コミュニケーション手段としては、カルテや処方箋などの紙媒体による一方向型と、対面や電話による双方向型があります。近年の病院経営では、在院日数の短縮が課題となっており、入院当初から退院までの明確な診療計画を提示し、医療者と患者の合意に基づいた治療を進めることが重要になっています。そのため、医療スタッフはクライアントの情報の意味解釈について合意形成し、組織内コミュニケーションを活性化させる必要があります(井戸田博樹、2008)。治療計画の遂行において、コミュニケーションは相互理解のための情報共有プロセスです(Everett M. Rogers, 1986)。
2. クライアントと看護師のコミュニケーション事例
患者の痛みへの対応を例に、クライアントと看護師間のコミュニケーションの重要性を示します。看護師は、患者の表情や行動、バイタルサイン、検査データなどから情報を収集し、過去の患者との関係性から得た知識も加味して痛みの原因を予測し、対処します。例えば、腹痛に発熱や白血球増加などが伴う場合は、緊急手術などの対応が必要な生命に関わる事態の可能性を医師に報告します。また、血圧管理においては、生活習慣の改善指導を行う際、患者の年齢、性別、職業、家族構成などを考慮した、実現可能な生活改善策を提案します。食事療法においても、クライアントの状況に合わせた適切な指導が必要です。食事は治療の一環であると同時に、日常生活の一部であり、クライアントの心理的、社会的な側面も考慮する必要があります。患者の食事に関するニーズは、単なる栄養摂取だけでなく、心理的安心感や喜び、社会的な交流の手段としての側面も持ちます。
3. 看護師の情報伝達における問題点と感情労働
医療現場では、臨機応変な対応と高い責任感が求められるため、医療スタッフの心理的負荷は高くなっています。特に看護師は患者と直接コミュニケーションする機会が多く、患者の安心感を高めるための共感や気遣いが求められます(武井麻子、2003;Pam Smith、1992)。そのため、看護師は医療・看護の知識に加え、自身の感情を適切にコントロールする能力も必要とします。一人の患者に複数の医療従事者が関わるため、看護師は患者だけでなく、同僚や他職種との関係においても感情のコントロールが求められます。医療現場における情報伝達は、製造業とは異なり、クライアントの主観的情報を正確に把握し、客観化することが困難です。そのため、看護師が提供する情報の品質も安定しにくいという課題があります。石川弘道(2008)は、B to Cビジネスでは情報提供の表現や解釈が多様化すると指摘しており、医療現場における情報伝達の複雑さを示しています。
4. 円滑な情報伝達のための感情労働と課題
看護師は、医療現場におけるコミュニケーションネットワークの中心的役割を担い、収集した情報を医師など他の医療従事者に伝達しています。円滑なコミュニケーションを図るために、看護師は感情労働を行います。しかし、感情のコントロールは大きなエネルギーを必要とし、職務上のストレスやバーンアウトの一因にもなりかねません。患者や医師との信頼関係構築、患者満足度向上、医療サービスの評価向上には、看護師による適切な感情労働が不可欠です。しかし、現状では、職務上の感情コントロールは当然のこととされ、感情労働の重要性が十分に理解されていない点が課題です。これは看護管理者や病院管理者についても同様であり、感情管理スキルを教育に取り入れる必要性、そして感情労働を職務として評価する医療システムの構築が求められています。
III.看護師の感情労働と職務上のストレス
看護師 (kango-shi) は、患者とのコミュニケーション (komyunikeshon) を通じて多くの感情労働 (kanjou roudou) を行っています。表層演技 (surface acting) と深層演技 (deep acting) の違いを踏まえ、感情労働が職務上のストレスの一因となり、バーンアウトにつながる可能性を考察します。患者の前で冷静さを保つ必要性、感情コントロールスキルと経験年数の関係、そして感情労働の適切な評価と報酬システムの必要性を指摘します。感情労働に関する研究動向(例:Steinbergの職務評価システム、関連文献:崎山治男、石倉義博、菅由希子、三橋弘次、他)も参照します。米兵のメンタルヘルス対策(鈴木滋、2009)なども参考に、日本の看護師の現状と課題を分析します。
1. 看護師における感情労働の実態
看護師の仕事は、患者のケアを通じて多くの感情労働を伴います。これは、肉体労働や頭脳労働とは異なり、しばしば「ちょっとした気配り」程度にしか認識されず、その労苦に見合う評価や報酬が与えられていないのが現状です。患者の前で常に冷静沈着を装う必要があり、感情をコントロールすることが求められます。例えば、患者の痛みや不安を軽減するため、何度も病室を訪問し、コミュニケーションを取らなければなりません。しかし、感情をコントロールし続けることは大きなエネルギーを消費し、職務上のストレスやバーンアウトにつながる可能性があります。経験年数別に感情のコントロールの有無を調べた結果、新人看護師は100%、中堅看護師は96%、ベテラン看護師は89%が感情をコントロールしていると回答しており、経験を積むことで感情のコントロールスキルが向上する一方、新人看護師は心理的な負担が大きいことがわかります。この感情コントロールのスキルは、臨床経験を通して育成・獲得されると考えられます。
2. 表層演技と深層演技
感情を管理する方法は、表層演技(surface acting)と深層演技(deep acting)の2種類に分類できます。表層演技は、Goffman(1959)の指摘するように、本当の感情とは異なる感情を装うことであり、ボディランゲージや作り笑いなどで外観を変える方法です。一方、深層演技は、Stanislavsky流の演技法のように、心からそう思うように感情に働きかけ、適切な感情を作り出す方法です。例えば、お葬式で過去の悲しい出来事を思い出して悲しむなどです。看護師は、クライアントに安心感を与えるため、表層演技や深層演技の両方を用いて感情をコントロールし、職務を遂行しています。しかし、これらの演技は、心身に大きな負担をかける可能性があります。感情労働は、肉体労働や頭脳労働と同様に労働であるにもかかわらず、労働として認識されていない、いわゆるシャドウワークの側面も持ち合わせています。
3. 感情労働の評価と報酬システムの課題
看護師の職務を中立的に評価するために、感情労働を正確に評価することが重要です。Steinbergは、感情労働の要素を取り入れた新しい職務評価システムを作成しました。このシステムは、対人関係技能、コミュニケーション技能、感情的努力、顧客への責任などを評価要素としており、カナダのオンタリオ州の自治体で看護師の差別的賃金を解消するための戦略として用いられました。しかし、完全な実施には至らず、不十分なまま終わったと報告されています。Steinbergは、論文「Emotional Labor in Job Evaluation Redesigning Compensation Practices」(1999)において、従来の職務評価システムが製造業中心に設計されているため、サービス業における感情労働のスキルが正当に評価されていないことを指摘しています。ジェンダーに中立な職務評価システムの構築に向けた取り組みが求められています。感情労働は、生産性に影響を与える目に見えない重要な要素であり、採用、訓練、指導を通して経営者が管理・活用できるものです。
4. 軍隊と看護師における感情労働の比較
感情労働の構造は職業によって異なります。軍隊では、指揮官の指示に従い、組織目標達成のために個々の責任において行動します。指揮官の判断が部下の生死に関わるため、高い感情労働が求められます。一方、看護師は医師の指示や看護管理者の指揮の下で働くものの、個々の看護師の判断が患者の生死に関わる場面が多くあります。しかし、看護師自身が職務上生命の危機に晒されることは稀です。従って、軍隊の指揮官の方が、感情労働の程度が高いと言えるでしょう。 軍隊と看護師はどちらも危機対応が重要な職業ですが、感情労働の構造は異なる点に注意が必要です。近年の在院日数短縮に伴い、外来での治療・看護の拡大、入院前の計画立案・調整など、看護師とクライアント間の意思疎通の重要性は増しています。看護師は「病院の顔」として、感情をコントロールしながら、期待されるサービスを提供することが求められます。
5. 新卒看護師の現状と感情労働への対応
近年の新卒看護師は、自己の課題や困難に直面すると容易に諦めてしまう傾向があり、上司からの指導も「いじめ」と解釈するケースも少なくありません。仕事中に泣いている看護師も増加しています。クライアントが安心して医療サービスを受けられるよう、看護師はクライアントの前では冷静沈着に振る舞うことが求められます。患者の前で涙を見せることは好ましくないと考えられますが、患者の最期を看取った後、家族と悲しみを分かち合うことは許容されるでしょう。現代医療は、クライアントの選択権と自由意志を尊重する方向に変化しており、インフォームド・コンセント(IC)に基づいた医療提供が求められています。医療者とクライアント間の意思疎通が、質の高い医療サービス提供に不可欠です。そして、感情管理を看護師に求められるスキルとして捉え、看護学生や看護師の教育・訓練の中に感情管理のスキルを学ぶ機会を取り入れる必要があるでしょう。感情労働を職務として評価する病院および医療システムの構築も必要です。
IV.感情労働と病院経営への提言
本論文は、看護師 (kango-shi) の感情労働 (kanjou roudou) が、顧客満足度 (kokyaku manzoku-do) 向上と病院経営 (byouin keiei) に必須であることを示唆します。情報通信技術 (ICT) の発展により、情報処理能力が向上した現代においても、ヒトを対象とするサービス業である医療現場では、情報伝達の質の確保が困難です。そのため、感情労働を適切に評価し、看護師の人材育成 (jinzai ikusei) 、感情管理スキルの教育・訓練の重要性を強調し、早期離職 (souki rishoku) 防止にも繋がるシステム構築を提案します。 看護管理者や病院管理者にも感情労働への理解と組織的取り組みを促します。
1. 感情労働の重要性と現状認識の不足
本論文では、これまで負の側面ばかりが強調されてきた看護師の感情労働が、今後の病院経営において顧客満足度向上に必須であることを示唆しています。情報通信技術(ICT)の発展により、企業は高品質な情報を活用して製品・サービスの質向上と顧客満足を実現していますが、医療現場では、ヒトを対象とするサービスの特性上、患者の主観的情報を客観化することが難しく、情報の品質も安定しません。看護師は、コミュニケーションネットワークの中核を担い、多様なニーズを持つクライアントに対し、感情をコントロールしながらサービスを提供する必要があります。しかし、現状では、看護師自身や管理者において、看護師の仕事が感情労働であること、そしてそれがクライアントの危機対応に大きな役割を果たすという特殊性が十分に理解されていません。そのため、感情労働に見合う評価や報酬がなされていないという課題があります。
2. 感情管理スキルの育成と組織的取り組みの必要性
多様化するクライアントのニーズに対応し、期待される医療・看護サービスを提供するためには、感情管理を看護師に求められる重要なスキルとして捉える必要があります。軍人、自衛隊員、消防・レスキュー隊員などが緊急事態下での感情管理の教育・訓練を受けているように、看護においても、看護学生の基礎教育や看護師の臨床研修に感情管理のスキルを学ぶ機会を取り入れるべきです。そして、感情労働を職務として評価する病院および医療システムの構築が不可欠です。これにより、看護師の職務満足度向上、早期離職防止にも繋がるでしょう。 看護師が文脈に合わせて感情労働を行うことは、今後の医療サービスや病院経営において不可欠であり、その質を左右するといっても過言ではありません。しかし、現状では、感情労働の重要性が十分に理解されておらず、組織的な取り組みが不足している点が課題です。
3. 情報伝達における質の確保と感情労働の関連性
医療現場における誤った情報伝達は、患者の生命やQOLに深刻な影響を与えます。製造業のように数値化でフィードバックできるシステムとは異なり、一度生じた事態の回復は困難です。石川弘道(2008)の指摘するように、情報提供者と利用者が個人の場合(B to C)は、企業間(B to B)よりも情報提供の表現や解釈が多様化するため、クライアントの主観的情報に配慮した情報伝達が重要になります。看護師は、入院患者から医師への情報伝達に介入する機会が多く、コミュニケーションネットワークのハブとしての役割を担っています。そのため、円滑なコミュニケーションを図るための感情労働が求められますが、感情のコントロールには大きなエネルギーが必要であり、それが職務上のストレスの一因となり、バーンアウトに繋がる可能性も高いです。患者の生命と安全の確保、そしてクライアントの期待に応える医療サービス提供のため、看護師は感情労働を適切に行わなければなりません。
4. 病院経営における感情労働への組織的対応
情報伝達と感情労働の質は、クライアントと医療者の信頼関係構築、患者満足度向上、医療・看護サービスの評価向上に大きく影響します。したがって、看護師の感情労働は、今後の医療サービスや病院経営において不可欠であり、その質を左右するといっても過言ではありません。しかし、現状では、看護師が職務上の感情をコントロールするのは当然のことと捉えられており、感情労働そのものの重要性が十分に理解されていません。これは、看護管理者や病院管理者についても同様です。多様化するクライアントのニーズに対応するためには、感情管理を看護師のスキルとして捉え、教育・訓練の機会を設けることが重要です。そして、感情労働を職務として評価するシステムを構築することで、看護師のモチベーション向上、そしてひいては顧客満足度向上に繋がるでしょう。楠本万里子(2009)や鈴木滋(2009)の研究も参考になります。
文書参照
- 新人看護職員研修ガイドライン (厚生労働省)
