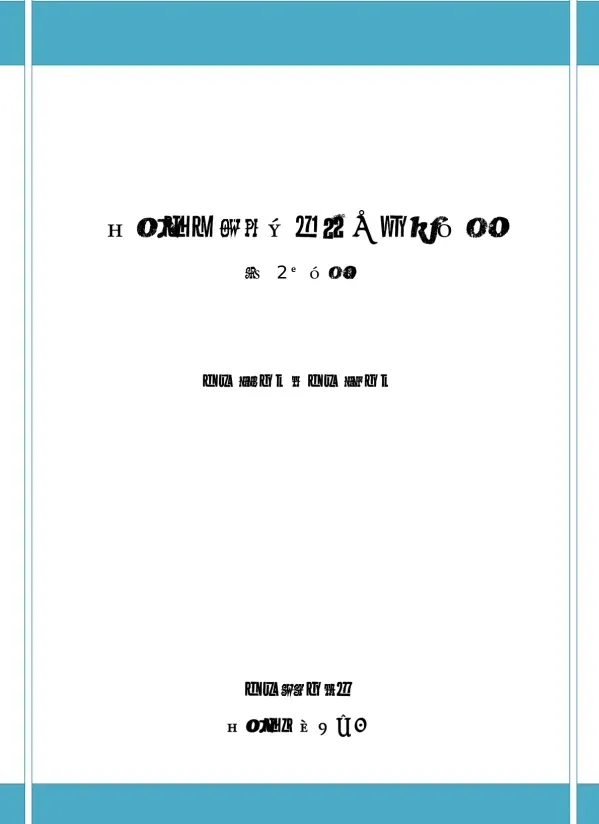
磐田市子ども読書推進計画(第2次)
文書情報
| 著者 | 磐田市教育委員会 |
| 場所 | 磐田市 |
| 文書タイプ | 計画書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 628.26 KB |
概要
I.磐田市 子ども読書活動推進計画 第2次計画 の概要
本計画は、子どもの読書活動の推進に関する法律に基づき、磐田市における子どもの読書離れ、活字離れ対策として策定されました。読書習慣の定着を目指し、家庭、地域、学校、市立図書館の連携強化を図ります。特に、親子読書の推進、読み聞かせの普及、魅力的な読書環境整備に重点を置きます。学校図書館の機能向上、市立図書館との連携強化、障がい児への対応なども重要な柱です。具体的な取り組みとして、おはなし会、ブックスタート事業、団体貸出の充実、多言語対応図書の整備などが挙げられます。 平成18年2月に策定された第1次計画の成果と課題を踏まえ、より効果的な読書活動推進を目指します。
1. 計画の背景と目的
近年、情報メディアの発達により子どもの読書離れ、活字離れが深刻化している状況を踏まえ、本計画は策定されました。平成13年には「子ども読書活動の推進に関する法律」が公布され、平成17年には「文字・活字文化振興法」が成立するなど、読書環境の整備に向けた法整備が進められてきました。磐田市においても、平成18年2月に第1次「磐田市子ども読書活動推進計画」を策定し、乳幼児期からの読書機会の確保、読書環境の整備に努めてきました。しかし、情報化社会の進展や生活環境の変化などにより、新たな課題も発生しています。この計画は、第1次計画の成果と課題を踏まえ、家庭、地域、学校、図書館などが連携し、子どもたちの読書活動を効果的に推進していくためのものです。 計画の目的は、読書離れ、活字離れを克服し、子どもたちが読書に親しみ、豊かな心を育み、生きる力を培うことができるよう、読書環境の整備と読書活動の促進を図ることです。具体的には、家庭での読み聞かせの推奨、学校図書館の機能向上、地域図書館との連携強化などを通して、子どもを取り巻くすべての環境において読書を促進することを目指しています。
2. 計画の法的根拠と位置づけ
本計画は、「子ども読書活動の推進に関する法律」第9条の規定に基づき策定されています。国の「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(第2次)」、静岡県「静岡県子ども読書活動推進計画(第2次計画)」を参考に、磐田市における現状や課題を踏まえて策定されました。 計画は、国の基本計画や県計画を参考にしながらも、磐田市の地域特性や子どもの読書活動の現状を詳細に分析し、具体的な施策を盛り込むことで、地域に密着した計画となっています。 具体的には、親子のふれあいを重視した取り組みへの支援・啓発、身近な地域の読書環境整備、大人自身の読書活動の推進などが挙げられ、これらの施策を通じて、磐田市の子どもたちが読書に親しみ、活字文化を享受できる社会の実現を目指しています。 計画の策定にあたっては、関係機関との綿密な連携と情報共有が行われ、それぞれの立場からの意見を反映させることで、より実効性のある計画となっています。
3. 計画の主要な取り組みと課題
本計画では、家庭、地域、学校、図書館それぞれの役割を明確化し、連携協力体制の構築を図ります。家庭においては、保護者による読み聞かせや親子での読書、読書を通じたコミュニケーションの促進を推奨します。地域では、図書館、公民館、児童館などの地域施設における読書関連事業の充実、読書環境の整備、ボランティア活動の支援などが計画されています。学校においては、学校図書館の機能向上、学校司書の配置促進、教職員やボランティアによる読書活動の支援などが重要視されます。図書館では、団体貸出の充実、障がい児へのサービス提供、情報提供の充実などが挙げられます。 しかしながら、計画の実施にあたっては、いくつかの課題も指摘されています。家庭では、保護者の就業形態の変化や塾・習い事の増加による親子で読書を楽しむ時間の減少、大人の読書離れなどが課題として挙げられています。地域では、公共施設の図書コーナーの充実、図書館との連携強化が課題です。学校では、学校図書館の機能や現状の市立図書館への周知不足、蔵書数の不足、特に学習指導に必要な資料の充実、障がい児への対応不足、読書に集中できる環境整備が課題です。これらの課題を解決するために、計画では具体的な施策が提示されています。
II.家庭における 子どもの読書活動 の推進
家庭での読み聞かせや親子での読書を通して読書習慣を育むことの重要性を強調しています。親子読書の機会の確保、保護者への読書活動の啓発が課題です。市立図書館、公民館、子育て支援センターなどでの親子参加型イベントの開催、広報活動の強化が計画されています。 ブックスタート事業の継続や、乳幼児期の育児教室への絵本読み聞かせの導入なども行われています。
1. 家庭における読書習慣の形成
子どもの読書習慣は日常生活の中で形成されるため、保護者の積極的な関与が重要です。保護者は、読み聞かせや一緒に読書をすることで読書習慣を身につけさせ、読書を通して子どもと語り合うことで、読書への興味関心を高めるよう促すべきです。具体的には、絵本の読み聞かせ、年齢に合わせた本の選択、読書後の感想を共有するなど、親子で読書を楽しむ時間を作ることを推奨しています。 保護者の役割は、単に本を読ませることだけでなく、読書体験を共有し、子どもの思考や感情を育む場を提供することです。 そのためには、保護者自身も読書に親しむことが重要であり、保護者向けの読書啓発活動も必要不可欠です。子どもだけでなく、保護者自身の読書離れも問題視されており、家庭での読書環境の改善、親子で共に時間を共有できるような工夫が求められています。
2. 家庭における読書活動推進の課題と対策
家庭における読書活動推進の課題として、保護者の就業形態の多様化や塾・習い事の増加による時間不足、親子で読書を楽しむ機会の減少、そして大人自身の読書離れなどが挙げられています。 これらの課題に対して、計画では、市立図書館や公民館、子育て支援センターなどで開催される親子向けおはなし会などの継続的な運営、職員の育成、参加促進のための広報活動の強化を提案しています。 また、乳幼児期の育児教室(離乳食教室)や2歳8ヶ月児対象の育児相談において、ブックスタート事業や図書館職員による絵本の読み聞かせなどを通して、早期からの読書体験の機会を積極的に提供していく取り組みも紹介されています。 さらに、読み聞かせは母親だけでなく、家族全員で参加することが重要であることを強調し、家族ぐるみで読書に親しむための環境づくりを促進していく必要があると述べられています。
III.地域における 子どもの読書活動 の推進
地域図書館、文庫、読書グループ、幼稚園、保育園などの役割を重視し、読書環境の充実を図ります。 市立図書館による団体貸出の充実、障がい児向け図書資料の充実、遠隔地への巡回サービスなどを計画。地域施設の図書コーナー整備、図書館との連携強化が課題として挙げられています。特に、児童図書の充実、中学生の図書館利用促進が重要視されています。
1. 地域における読書環境の整備と充実
地域全体で子どもたちが読書に親しめる環境を整備・充実させることが重要です。そのため、地域図書館、文庫、読書グループ、幼稚園、保育園、公民館、児童館など、様々な地域機関が連携して、子どもたちが読書に親しむ機会を提供する必要があります。 具体的には、これらの機関が連携して、子ども向けの読書イベントやワークショップなどを企画・実施したり、図書館の団体貸出制度を積極的に活用したりすることで、子どもたちがより多くの良書と出会える機会を増やすことが重要です。また、図書館では、市内の全ての子どもたちが良書と出会い、読書を楽しむことができるよう、児童図書の充実や教育施設・地域施設への団体貸出の拡大を図る必要があります。特に、中学生の図書館利用増加のためのサービス拡充や、質の高い図書資料の充実が求められます。 さらに、図書館に通うことが困難な地域の子どもたちのために、司書が地域の公共施設や教育施設に出向き、読み聞かせやブックトークを行うアウトリーチ活動も重要となります。
2. 地域連携の課題と今後の施策
地域における読書活動推進の課題として、公民館や児童館などの図書コーナーの充実度合いがまちまちであること、地域公共施設と図書館との連携が不十分であることが挙げられています。 これらの課題に対し、計画では、地域の公共施設(公民館、児童館、放課後児童クラブ、子育て支援センターなど)における図書コーナーの整備と、おはなし会や保護者向けの読書啓発事業などの継続的な実施を提案しています。 また、県立図書館との連携を強化することで、地域における読書環境の充実に努めるとしています。 具体的には、関係団体・機関における子どもの読書関連事業の充実を図るための働きかけや、障がいのある子どもたちへの点訳本、布絵本、拡大写本などの提供、特別支援学級や特別支援学校への団体貸出の促進などが計画されています。 さらに、遠隔地に住む子どもたちへの巡回サービスの実施など、地域全体で子どもたちの読書活動支援体制を強化する必要性が示唆されています。
IV.学校における 子どもの読書活動 の推進
学校図書館の機能強化、学校図書館と市立図書館の連携強化を目指します。学校独自の読書週間、読書会、読み聞かせ活動の推進、魅力的な図書資料の整備・充実が重要です。 学校図書館の現状としては、蔵書数の不足、資料の老朽化、障がい児への対応不足が課題として挙げられています。 学校司書の配置促進、市立図書館からの団体貸出の活用、外国語対応図書の充実なども計画されています。教職員やボランティアとの連携も強化します。
1. 学校図書館の機能強化と読書環境整備
学校図書館は、子どもの自発的、主体的な学習活動を支援する学習情報センター、そして豊かな心を育む読書センターとしての機能強化が求められています。そのため、学校図書館の整備・充実、魅力的な図書資料の計画的な整備・充実が不可欠です。 具体的には、子どもの知的活動の増進や多様な興味関心に応える資料の整備、各教科の学習活動を支える資料の充実が図られます。時代遅れの図書の廃棄・更新、計画的な図書購入による図書標準の達成にも努力が払われます。 また、学校独自の読書週間の設定、読書会、紙芝居、ブックトーク、アニマシオンなど多様な読書活動の実施、必読図書・推薦図書の選定(小学校83%、中学校60%)、教室内読書コーナーの設置、読み聞かせ活動の充実など、学校レベルでの取り組みも重要です。特に、特別支援学級の児童生徒への配慮として、適切な図書資料の整備も課題となっています(小学校43%、中学校10%)。
2. 学校と市立図書館の連携強化
学校図書館と市立図書館の連携強化は、子どもの読書活動推進に不可欠です。 現状では、市立図書館は学校からの要請に応じて、団体貸出や読み聞かせ、図書館利用ガイダンスなどを実施し、支援を行っています。豊岡地区では移動図書館も実施されています。「茶の間ひととき読書運動」では、小学校3年生とその家族を対象に家庭での読書推進を図っています。 しかし、学校図書館の機能や現状が市立図書館に十分に周知されていないため、連携の在り方について明確化していく必要があります。 今後の施策として、市立図書館からの外国語版図書の団体貸出の活用、調べ学習への協力(年間計画、利用指導計画に基づく資料提供)、子どもの成長段階に合わせたブックリストの作成・配布などが挙げられています。 さらに、学校司書の全校配置促進、学校司書や司書教諭の研修機会の充実、県立図書館や他市町立図書館との相互貸借ネットワーク化の推進などが課題として挙げられています。
3. 学校における読書活動推進の課題と対策
学校における読書活動推進の課題として、学校図書館の蔵書数の不足、特に学習指導に必要な資料の充実、時代遅れの資料の廃棄の遅れ、障がいのある児童生徒や発達段階に応じた図書資料の不足、読書に集中できる図書館環境の整備の不足などが挙げられています。 また、学校図書館と市立図書館間の連携不足も課題として認識されており、情報共有の徹底が必要とされています。 ブラジル人の児童生徒が多い地域では、ポルトガル語版の教科書や図書資料の提供、それらを読み聞かせる人材の育成も課題となっています。 これらの課題に対し、計画では、魅力的な図書資料の計画的な整備・充実、市立図書館との連携強化、学校司書の全校配置促進、司書教諭の業務負担軽減のための働きかけ、中遠・東遠地域(磐田市、御前崎市、掛川市、菊川市、袋井市、森町)との図書館業務提携による資料の相互利用などを具体的な対策として提示しています。
V. 市立図書館 の役割と連携
市立図書館は、団体貸出、読み聞かせ、ガイダンス、調べ学習への協力などを通して、学校や地域における読書活動を積極的に支援します。ホームページ等での情報発信、ブックリストの作成、ボランティア養成講座の実施なども行っています。 課題として、地域・学校との連携強化、情報提供の充実が挙げられ、市記者クラブへの情報提供を通じて市民への広報活動を強化する計画です。 中遠・東遠地域(磐田市、御前崎市、掛川市、菊川市、袋井市、森町)との図書館業務提携により、より広範な資料提供を目指します。
1. 市立図書館の役割と学校 地域への支援
市立図書館は、学校や地域における子どもの読書活動推進において中心的な役割を担っています。具体的には、学校での調べ学習や読書推進活動への支援として、団体貸出を実施しています。また、学校からの要請があれば、図書館職員が学校に出向き、読み聞かせや図書館の利用方法などのガイダンスを行っています。豊岡地区では、定期的に地域学校を訪問する移動図書館も実施しています。 さらに、市内全小学校3年生と家族を対象とした「茶の間ひととき読書運動」を通じて、子どもたちに読書の楽しさを伝え、保護者には読書の大切さを再認識させる取り組みも行っています。 市立図書館は、読み聞かせボランティア養成講座の実施など、地域や学校のボランティアを育成・支援する活動にも積極的に関わっています。インターネットの活用、広報紙の発行、ブックリストの作成なども行い、読書活動に関する情報の収集・提供にも力を入れています。市立図書館のホームページへのアクセス数も年々増加しており、情報提供の有効性が示されています。
2. 市立図書館と学校 地域機関との連携強化
市立図書館は、学校や地域機関との連携強化によって、より効果的な読書活動推進を目指しています。学校との連携としては、年度当初に学校から「図書館資料を使った教科学習年間計画」や「図書館利用指導計画」を受け、時期に応じた資料提供を実施する体制が整えられています。 また、子どもの成長段階や状況に合わせたブックリストを作成し、配布することで、読書活動の支援を図ります。 地域との連携強化に向けては、読み聞かせボランティアの養成・支援、地域団体への図書館サービスの積極的なPR、読み聞かせに適した絵本の紹介など、地域団体との連携を強化することで読書活動の裾野を広げようとしています。 しかしながら、地域や学校と図書館との相互理解・協力の促進、学校司書の配置促進、司書教諭、ボランティア、図書館による情報交換の場や研修機会の創設などが今後の課題として挙げられています。 市記者クラブへの情報提供を通じて、市民への広報活動も強化していく方針です。中遠・東遠地域との図書館業務提携(住民の相互利用)も進められています。
