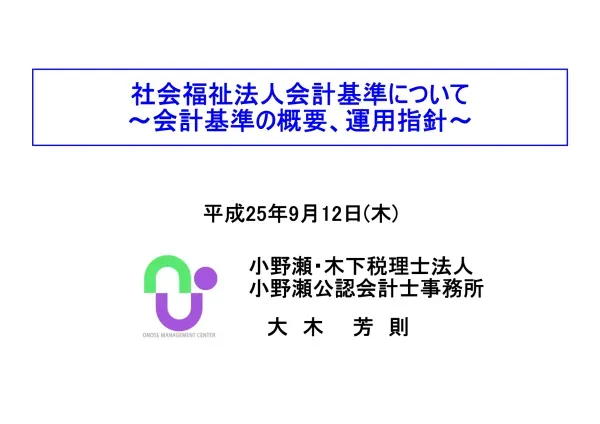
社会福祉法人会計基準解説
文書情報
| 著者 | 小野瀬公認会計士事務所 |
| 専攻 | 社会福祉法人会計 |
| 会社 | 小野瀬・木下税理士法人 |
| 文書タイプ | 研修資料 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 849.82 KB |
概要
I.新基準導入に伴う課題と対応
本資料は、社会福祉法人会計基準(社会福祉法人会計基準)の改正、特に平成23年7月27日通知による新基準導入に伴う課題と、その対応について解説しています。主な課題として、通知の遅延、会計ソフトの不備、会計制度の抜本改定(新たな会計手法の導入)などが挙げられています。リース会計、退職給付会計等の複雑な会計処理への対応についても重要です。
1. 新基準導入の遅延と対応
社会福祉法人会計基準の改定に関する通知は、素案(平成21年)から案(平成22年)、正式通知(平成23年7月27日)と段階的に進められました。この遅延は、関係者にとって準備期間の短縮を意味し、円滑な新基準導入における大きな課題となりました。特に、会計処理システムへの影響が懸念され、多くの社会福祉法人が対応に苦慮したことが予想されます。迅速な情報伝達と十分な準備期間の確保が、今後の基準改定においては不可欠です。既存の会計システムの更新や、新基準に沿った会計処理の研修、職員への周知徹底など、迅速かつ適切な対応策が必要不可欠となります。会計ソフトの不備も問題視されており、前もって準備されていたにもかかわらず、新基準に対応しきれなかったケースもあったと考えられます。この点を踏まえると、将来的な基準改定に備え、柔軟性と対応力を持つ会計システムの導入や、継続的なシステム更新の重要性が改めて認識されます。スムーズな移行のためには、関係機関やソフトウェア開発会社との連携強化が求められます。
2. 会計制度の変更と範囲
新基準の導入は、会計処理の範囲を単なる会計処理から、措置制度や介護保険制度といった、より広範な社会福祉制度にまで拡大しました。しかし、この変更は制度そのものの改正を伴うものではなく、既存制度の範囲内で会計処理の見直しを行うことが求められています。そのため、社会福祉法人は、介護保険制度や措置制度に関する知識や理解を深め、会計処理への反映を図る必要に迫られました。既存の会計処理システムが、これら制度の多様性に対応できるよう柔軟性を持つことが重要になります。また、それぞれの制度に精通した専門家による適切な助言やサポート体制の構築も、円滑な移行を支援する上で不可欠な要素となります。新基準導入による業務増加への対策として、業務効率化のためのシステム導入や、人的資源の最適配置なども重要な課題となります。
3. 会計制度の抜本的改定と新たな会計手法
新基準導入の大きな特徴として、会計制度の抜本的な改定と新たな会計手法の導入が挙げられます。これは、社会福祉法人の会計処理に大きな変化をもたらし、関係者にとって新たな学習と適応が求められることを意味します。特に、リース会計や退職給付会計といった複雑な会計処理については、専門的な知識と理解が必要不可欠となります。新基準の理解を促進するために、政府機関や専門機関による研修プログラムや情報提供の充実が不可欠です。また、社会福祉法人同士の情報共有や、成功事例の共有による横断的な連携も、課題解決に有効な手段となるでしょう。会計処理の正確性と効率性を高めるため、専門家によるコンサルティングや、会計システムの高度化も検討すべきでしょう。新会計基準への対応をスムーズに進めるためには、関係者間の情報共有、十分な研修、そして必要なシステムへの投資が重要です。
II.年基準とリース会計
資産・負債の流動/固定の区分は、貸借対照表日(3月31日)から1年以内の支払期限のものを流動負債、それ以降を固定負債と定義されています。リース会計では、ファイナンス・リース取引は通常の売買取引と同様に、オペレーティング・リース取引は通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うこととされています。リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下、またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、例外的に賃貸借取引に準じた処理が可能です。また、有形・無形固定資産の時価が帳簿価額から50%を超えて下落している場合の使用価値による評価についても規定されています。
1. 資産と負債の流動 固定区分に関する1年基準
本資料では、貸借対照表日(3月31日)を基準として、1年以内に支払期限が到来する債務を流動負債、1年を超えるものを固定負債として分類する「1年基準」について解説しています。これは、借入金等の経常的な取引以外の取引によって生じた債務にも適用される重要な基準です。この基準に従うことで、企業の短期的な支払い能力と長期的な財務状況をより明確に把握することが可能になります。 会計処理においては、支払期限を正確に把握し、適切な分類を行うことが重要です。 支払期限の判断が難しいケースや、例外的な状況への対応についても、明確な基準が示されている必要があります。この1年基準は、社会福祉法人の財務状況を正確に反映するため、正確な会計処理と、財務諸表の信頼性を高める上で不可欠な要素となります。将来的な財務計画や資金調達計画策定においても、この基準に基づいた正確なデータが求められます。
2. リース会計 ファイナンス リース取引とオペレーティング リース取引
リース会計に関する記述では、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引の会計処理方法が明確に区別されています。ファイナンス・リース取引とは、リース期間中に契約を解除できず、借手が経済的利益を実質的に享受し、コストを実質的に負担するリース取引を指します。この取引は、通常の売買取引と同様の会計処理が行われます。一方、オペレーティング・リース取引は、ファイナンス・リース取引以外のリース取引であり、通常の賃貸借取引に準じた会計処理が行われます。 リース料総額が300万円以下、またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、例外的に賃貸借取引に準じた会計処理を行うことが認められています。この例外規定は、小規模なリース取引における会計処理の簡素化を目的としています。 会計処理においては、リース取引の性質を正確に判断し、適切な会計処理を行うことが重要です。 ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引の区別を明確にすることで、財務諸表の透明性と信頼性を確保することができます。
3. 使用価値による評価とリース資産の重要性
有形・無形固定資産の時価が帳簿価額から50%を超えて下落した場合、使用価値が時価を超えるならば、帳簿価額を超えない範囲で、その使用価値をもって評価することができる、と規定されています。ここでいう使用価値は、将来キャッシュ・フローの現在価値であり、当該資産または資産グループを単位として計算されます。この規定は、資産の減損リスクに対応し、より現実的な評価を行うためのものです。 一方で、リース資産総額が重要性に乏しいと認められる場合は、リース料総額から利息相当額の見積額を控除しない方法によることもできます。この規定は、会計処理の簡素化を図り、実務上の負担軽減を目的としています。 これらの規定は、社会福祉法人の会計処理において、資産の評価方法に関する柔軟性と実務的な配慮を示しています。正確な評価を行うためには、将来キャッシュフローの予測や、重要性の判断について、適切な基準と手続きが求められます。
III.退職給付会計とその他の会計処理
退職給付会計においては、福祉医療機構の実施する退職手当共済制度など、拠出後に追加負担がない外部拠出型制度については、掛金額をもって費用処理されるとされています。その他、国庫補助金等特別積立金の取崩し処理、設備資金借入金償還補助金に関する会計処理、減価償却費の計算方法なども規定されています。勘定科目の説明として、介護用品費、診療・療養等材料費、職員給与、退職給付費用、有形リース資産、無形リース資産、退職給付引当金などが挙げられています。
1. 退職給付会計 福祉医療機構の退職手当共済制度
退職給付会計に関する記述では、独立法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を例に、外部拠出型の制度の会計処理方法が説明されています。拠出後に追加的な負担が生じない外部拠出型の制度の場合、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理することとされています。これは、退職給付債務の確定時期と費用計上時期の一致を図るための会計処理であり、財務諸表における透明性と正確性を高める上で重要です。この会計処理方法は、確定拠出年金制度など、同様の仕組みを持つ制度にも適用されます。社会福祉法人は、自らが加入している退職給付制度のタイプを正確に把握し、適切な会計処理を行う必要があります。この処理方法の理解を深めるためには、制度設計に関する知識や、会計基準に関する専門的な知識の習得が不可欠となります。 また、会計システムにおいても、この処理に対応できる機能が求められます。
2. その他の会計処理 勘定科目と説明
資料には、様々な勘定科目とその説明が記載されています。具体的には、介護用品費、診療・療養等材料費、職員給与、職員賞与、業務委託費、退職給付費用、土地・建物賃借料、保守料、諸会費など、社会福祉法人の事業運営に関連する多様な項目が含まれています。 さらに、国庫補助金等特別積立金取崩額の計算方法、徴収不能引当金の計上方法なども記載されており、これらの会計処理は、社会福祉法人の財務状況を正確に把握し、適切な経営判断を行うために必要不可欠な情報です。 これらの勘定科目の説明は、社会福祉法人の会計処理の透明性を高め、関係者間の理解を促進する上で非常に役立ちます。 会計処理の正確性と効率性を確保するために、これらの勘定科目の定義と処理方法に関する理解を深めることが重要です。また、会計システムの機能についても、これらの勘定科目を適切に処理できるものが求められます。
3. 国庫補助金等特別積立金と設備資金借入金償還補助金
国庫補助金等特別積立金については、その取崩し処理に関する規定が示されています。指導指針の方法で取崩しを行っていた場合は調整不要ですが、会計基準の方法で計算している場合は調整が必要になります。原則として、当初から国庫補助金等特別積立金として処理していたものとして調整を行うことになります。 また、設備資金借入金償還補助金についても、指導指針の方法で処理していた場合は調整不要とされています。しかし、介護保険事業などについては、別途検討が必要な場合があります。これらの規定は、国庫補助金等の会計処理における適切な対応と、既存の会計処理からの円滑な移行を支援するものです。 社会福祉法人は、それぞれの補助金の種類や会計処理方法を正確に理解し、適切な会計処理を行う必要があります。 このためには、会計基準や関連する通達などの理解、そして会計処理に関する専門的な知識が求められます。
IV.拠点区分とサービス区分に関する会計処理
会計処理における拠点区分とサービス区分の設定方法が規定されています。拠点区分は予算管理の単位であり、法人本部と一体的に運営される施設・事業所を一つの拠点区分とします。各拠点区分においては、事業活動の内容を明らかにするため、サービス区分を設けて収支計算を行う必要があります。介護保険サービスや障害福祉サービス、保育所運営費、措置費などの事業については、サービス区分の具体的な設定方法と、別紙資料(別紙3、別紙4)の作成要否についても言及されています。複数の事業所や施設が会計を一元的に管理されている場合は、同一拠点区分とすることが可能です。ただし、拠点区分が1つの法人、または事業区分に1つの拠点区分しかない場合は、一部書類の作成を省略できます。
1. 拠点区分の定義と設定
会計処理における拠点区分の設定は、予算管理の単位として重要視されています。法人本部、および一体的に運営される施設・事業所・事務所を1つの拠点区分とします。公益事業(社会福祉事業と一体的に実施されているものを除く)や収益事業は、別の拠点区分として扱うことになります。新たな施設建設時には、拠点区分の設定が可能とされています。複数の事業所や施設が会計を一元的に管理されている場合も、同一拠点区分として扱うことができます。これは、障害者自立支援法や介護保険法に基づく指定施設など、複数の事業所や施設が連携して運営される場合に特に有効です。拠点区分が1つだけの法人の場合は、特定の書類作成を省略できる場合があります。この拠点区分の設定は、社会福祉法人の財務状況を正確に把握し、各事業所の経営状況を明確に分析するために不可欠です。予算配分や経営分析、そして適切な経営判断を行う上で、適切な拠点区分の設定と管理が求められます。
2. サービス区分の設定と収支計算
事業活動の内容を明確化するために、各拠点区分においてサービス区分を設け、収支計算を行う必要があります。サービス区分の設定は、事業活動の多様性を反映し、それぞれの事業の収益性や費用構造を詳細に把握するために重要です。介護保険サービスと障害福祉サービスを実施する拠点は、特定の別紙資料(例:別紙4)を作成し、別の資料(例:別紙3)の作成を省略できます。逆に、保育所運営費や措置費による事業を実施する拠点は、別の別紙資料(例:別紙3)を作成し、別の資料(例:別紙4)の作成を省略できます。 介護サービスと一体的に行われる介護予防サービスなど、コストの区別が困難な場合、介護予防サービスの収入額のみを把握できれば、同一のサービス区分として会計処理を行うことができます。しかし、一度選択した基準は原則として継続的に使用することになります。サービス区分の設定は、補助金等の適正な執行を確保する上でも重要な役割を果たします。所轄庁や補助を行う自治体の求めに応じて、サービス区分ごとの事業費の算出基準や内訳を提出できるよう、書類を整理しておく必要があります。
3. 会計責任者と出納職員の役割
各拠点区分または各サービス区分には、会計責任者と出納職員を置くことになっています。会計責任者は、その拠点区分またはサービス区分の経理事務全般を監督する役割を担います。出納職員は会計責任者に代わり、経理事務を行います。業務に支障がない限り、1人の会計責任者または出納職員が複数の拠点区分またはサービス区分の業務を兼務することも可能です。この規定は、社会福祉法人の会計処理における責任体制を明確化し、会計処理の正確性と効率性を確保するためのものです。 会計責任者と出納職員は、会計基準や関連規則を十分に理解し、適切な職務遂行能力を持つことが求められます。 また、法人の規模や業務量に応じて、適切な人員配置と業務分担を行うことが重要です。
V.社会福祉法人モデル経理規程の改訂
全国社会福祉施設経営者協議会は、社会福祉法人会計基準の改正を受けて「社会福祉法人モデル経理規程」を全面的に見直しました。この規程は、各法人がそれぞれの事情に応じた独自の経理規程を策定するための参考資料として位置付けられています。原則的な会計処理方法に加え、省略可能な方法や簡便的な方法についても示されており、**社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)**に基づいて、適正な会計処理を行うための指針となっています。
1. 社会福祉法人モデル経理規程の改訂の背景
平成23年7月27日付けの厚生労働省通知による「社会福祉法人会計基準」の改正を受け、全国社会福祉施設経営者協議会は「社会福祉法人モデル経理規程」の全面的な見直しを行いました。 これは、平成12年2月17日付けの社援第310号通知で策定された既存のモデル経理規程(平成12年3月31日厚生省社会・援護局施設人材課施設係長事務連絡)を、最新の会計基準に適合させるための改訂です。 新基準導入による会計処理の変化に対応するため、各社会福祉法人が自らの事情に合わせた独自の経理規程を策定できるよう、本モデル経理規程は参考資料として提供されています。画一的な規程の作成を強いるものではなく、柔軟な対応を可能にしています。この改訂は、社会福祉法人の会計処理の適正化と、透明性の向上に大きく貢献するものと期待されています。 全国社会福祉施設経営者協議会は、社会福祉法人の会計処理に関する支援機関として、今後も継続的な情報提供とサポートを行う姿勢を示しています。
2. 改訂における基本方針と注記の3項目
改訂されたモデル経理規程は、下記の3つの基本方針に基づいて策定されています。まず、基準、注解、運用指針で原則的な方法と省略できる方法、または原則的な方法と簡便的な方法が定められている場合は、原則的な方法をモデル経理規程の原文とし、省略できる旨または簡便的な方法を注書きとして記載しています。これは、社会福祉法人が会計処理方法を選択できる柔軟性を確保しつつ、原則的な処理方法を明確にするための工夫です。 次に、重要性の適用により会計処理方法を選択できる項目については、原則法と簡便法、原則法と省略できる方法を組み合わせた内容を原文として記載しています。これは、実務の効率化と柔軟な対応を両立するための配慮です。最後に、解説や補足事項は注書きとして記載されています。これは、会計処理に関する理解を深めるための支援となります。 第42条と第45条の勘定科目については網羅的に記載されていますが、各法人は独自の経理規程を策定する際に、該当するもののみを記載し、必要のない科目は削除することができます。これは、各法人の事情に合わせた柔軟な対応を可能にするための配慮です。
