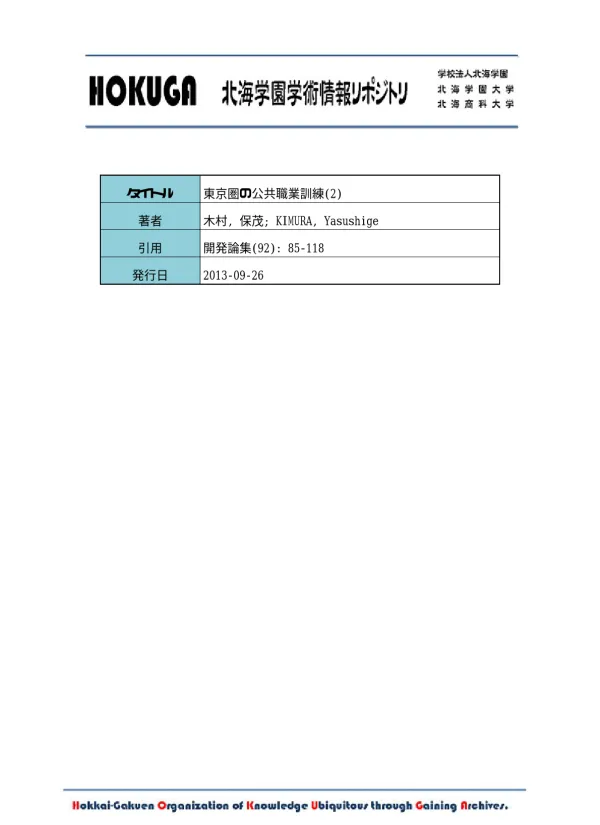
神奈川県公共職業訓練:いちょう計画と職業能力開発
文書情報
| 著者 | 木村 保茂 |
| 専攻 | 開発論 |
| 会社 | 開発研究所 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 704.38 KB |
概要
I.神奈川県の公共職業訓練 いちょう計画と高等職業技術校の変遷
本資料は、神奈川県の公共職業訓練、特に**「いちょう計画」による職業能力開発の変遷と、高等職業技術校の再編整備について詳述しています。戦後から始まった神奈川県の職業訓練は、70年代前半には13校体制にまで拡大しましたが、その後は減少傾向にあり、「いちょう計画」(1986~1990年度)により、職群制と単位制訓練を導入することで、訓練内容の専門化と効率化を目指しました。この計画では、7つの職群**(高度技術群、工業技術群、建設技術群・建設サービス群、社会サービス群、情報技術群、保守技術群)が設定され、高等職業技術校は各職群に特化した専門校として再配置されました。モジュール訓練の理論に基づく単位制訓練も導入され、訓練の柔軟性と個別対応性を高めました。
1. 神奈川県の多様な職業能力開発施設
神奈川県は、全国でも類を見ないほど多様な公共職業能力開発施設を擁しています。国立の高齢・障害・求職者支援機構(新機構)傘下には、職業能力開発総合大学校(全国に1校のみ、2012年度末まで)、港湾職業能力開発短期大学校(全国に2校のみ、神奈川県に1校)、関東職業能力開発促進センター(全国61校のうち1校)などがあります。これらの施設の存在は、神奈川県の職業訓練の充実度を示しています。 日本の職業訓練法の改正(1969年、1978年)を受け、神奈川県でも向上訓練や能力再開発訓練の強化、中卒から高卒訓練への移行などが行われました。しかし、神奈川県は更なる発展を目指し、東京工業大学斎藤学長の提言を踏まえ、1981年に労働部局内に職業訓練行政研究会を設置。職業変化の実態調査や指導員からの意見聴取を経て、新しい職業訓練についての研究報告書を作成し、1984年には具体的な事業計画案「新職業訓練体系整備事業」、通称「いちょう計画」を策定し、長洲知事に提出。1985年の試行期間を経て、1986~1990年度に本格的に実施されました。
2. いちょう計画 の誕生と高等職業技術校の初期体制
戦後、神奈川県の職業補導は1946年に紅葉ヶ丘校から始まり、1970年代前半には13校体制となり、北海道、東京に次ぐ規模を誇りました。これらの学校は、紅葉ヶ丘校、藤沢校、京浜校、小田原婦人校、相模原校、横須賀校、衣笠校、鶴見校、秦野校、横浜校、川崎校、平塚校に加え、横浜校の分校として技能訓練センターが設置されていました。しかし、この13校体制はその後減少。いちょう計画完了時には12校、高等職業技術校再編整備計画前年(2004年)には11校体制へと縮小しました。これは、技能訓練センターの横浜校への吸収合併などが影響しています。北海道(20校→8校)や東京都(18校→)と比較しても、神奈川県の職業訓練校の再編は大きな変化を示しています。いちょう計画では、高等職業技術校の専門校化と配置転換が重要な目標でした。具体的には、7つの職群が設定され、各校はその職群に特化した訓練を提供する体制が構築されました。この職群制導入は、訓練内容の多様化、合同授業による効率化、設備の共同利用によるコスト削減などを目指したものでした。
3. いちょう計画における職群制と高等職業技術校の専門校化
いちょう計画によって設定された7つの職群と、それに対応する高等職業技術校は以下の通りです(障害者職業能力開発校を除く):①高度技術群(1~2年):横浜校 ②工業技術群(1年、6ヶ月):川崎校、秦野校、横須賀校、衣笠分校 ③建設技術群・建設サービス群(6ヶ月、1年):鶴見校、平塚校 ④社会サービス群(6ヶ月、1年):紅葉ヶ丘校、小田原校 ⑤情報技術群(6ヶ月、1~2年):藤沢校 ⑥保守技術群(6ヶ月、1年):京浜校、相模原校。情報技術群には藤沢校以外にも5校ありましたが、専門分野が他の職群に属するため、ここでは除外されています。職群制導入の目的は、職業能力開発校の専門校化と再配置です。訓練カリキュラムの多様化、共通訓練単位の合同授業化による効率化、設備の共同利用によるコスト削減などを目指しました。東部総合職業技術校の工業技術課長は、専門校化により専門指導員が集まり、訓練の質が向上したと述べています。
II. いちょう計画 後の高等職業技術校の再編と単位制訓練
「いちょう計画」後、高等職業技術校は再編整備計画(2004年)を経て、2006年までに9校体制へと縮小されました。職群数は7から3(工業技術群、社会サービス群、建築技術群)へと減少し、専門化・統合が進みました。しかし、単位制訓練は維持・発展し、基礎単位、選択基礎単位、選択応用単位の段階的な学習体系が特徴となっています。職群制の目的である「多能な職業人の育成」は、複数の専門コースや段階的な訓練体系を通じて継続されています。 東部校と西部校という2つの総合校を中心に、職系とコースがより重視されるようになりました。特に、チャレンジプロダクトやセレクトプロダクトなどのコースでは、デュアルシステム的な訓練や体験的訓練を取り入れ、実践的な技能習得を目指しています。これらのコースは、フリーター対策にも貢献しています。
1. 高等職業技術校の再編と職群数の減少
「いちょう計画」後の高等職業技術校は、2004年の「高等職業技術校再編整備計画」に基づき、大規模な再編が行われました。その結果、2006年までに学校数は12校から9校に減少し、従来の7職群は3職群(工業技術群、社会サービス群、建築技術群)に集約されました。 具体的には、京浜校と相模原校が保守技術群から工業技術群へ移行し、横浜校は産業技術短期大学校への昇格に伴い工業技術群から離脱しました。さらに、相模原校と衣笠分校(横須賀校分校)が廃校となり、京浜校は川崎校の分校に格下げされるなど、大幅な組織変更が行われました。この再編によって、各校における訓練内容の集約と専門性の強化が図られましたが、同時に、従来の職群構造は簡素化されました。この再編は、公共と民間の役割分担推進という観点からも行われたものであり、情報技術関連分野の訓練は、東部校の工業技術群における「コンピュータ組込み開発コース」として継続されています。このコースでは、オペレーティングシステムやネットワーク、システム設計などに関する教育が行われています。
2. 総合校化による訓練体制の変化と単位制の維持
小規模専門校から大規模総合校への再編に伴い、訓練体制にも変化が見られました。入校、修了、就職に関する事務作業や行事運営は入校・就職支援課が担当するようになり、職業訓練指導員は生徒募集、訓練指導、就職指導に専念できるようになりました。施設の大規模化と機器・指導員の集中化により、技能五輪全国大会などの開催が可能になり、県民の技能振興にも貢献しました。また、総合校化により、様々な職群・職系・コースが集まり、分野間の連携が促進されました。ただし、以前のように単位をともなった職系間・コース間の合同授業は、安全衛生や労働講座を除いて廃止され、職群制の特徴は薄れてきました。しかし、「広い視野をもった多能な職業人の育成」といういちょう計画の最大のねらいは、基礎単位、選択基礎単位、選択応用単位という段階的訓練や、複数の専門コースの設置を通じて継続されています。 教科担任制も、従来の複数コース担当制からコースごとの担当制へ移行しました。 職業能力開発促進法施行規則にも、職群制の中の職系とコースが取り入れられています。
3. 単位制訓練の特徴 基礎単位 選択基礎単位 選択応用単位
再編後も単位制訓練は維持され、授業時間20校時(1校時45分)を1単位とする技能要素に分割され、単位を確実に履修することで技能水準の到達を目指しています。訓練コースの単位構成は、基礎単位、選択基礎単位、選択応用単位の3つからなり、訓練期間の長短に関わらず全てのコースで実施されています。例えば、チャレンジプロダクトでは、基礎単位(20単位)、選択基礎単位(22単位)、選択応用単位(22単位)の構成となっており、訓練効果を高めるため、この割合は柔軟に変更可能です。 教科担任制は、複数コース担当制からコースごとの担当制へ移行し、教科の内容は教科担任者が決定するようになりました。職群制は後退したように見えますが、教科担任制や専攻コースの設定、段階的体系的訓練などは継続されています。 また、関連単位をパッケージ化し、効率的な訓練を行うラーニング・パッケージも運用されています。 職業能力開発促進法施行規則では、普通課程のカリキュラム編成の3分の2は国の基準によるものの、残りの3分の1は都道府県の裁量権に委ねられているため、セレクトプロダクトのような独自の訓練が可能となっています。
III.神奈川県産業技術短期大学校 高度技術者育成の中核
神奈川県には、高度な技術者の育成を目的とした産業技術短期大学校があります。この短期大学校は、「ものづくり」の中核となる実践技術者の育成に力を入れており、卒業生の約40%が「産業技術短期大学校職業能力開発推進協議会」会員企業へ就職しています。同協議会は298社(機械・製造分野114社など)で構成され、カリキュラムへの助言や就職支援など、多大な貢献を行っています。短期大学校では、専門知識・技能に加え、意欲やコミュニケーション能力の育成にも注力し、企業ニーズに対応した人材育成を目指しています。入学試験は推薦入試と一般入試があり、定員はほぼ充足しています。修了率は72%、就職率は全体平均で67.8%です。
1. 神奈川県産業技術短期大学校の目的と設置背景
神奈川県産業技術短期大学校は、実践技術者の養成を目的として1995年に開校しました。短期大学校長は、その目的を「製造現場の管理者をはじめとする製造中核技術者・技能者の養成」と述べています。神奈川県は製品出荷額全国2位の製造業県であるため、産業界の構造変化に対応した高度な技術者の育成が求められており、この短期大学校はそのニーズに応える形で設立されました。 他の職業能力開発大学校(国立、県立)と同様、実践技術者の育成を重視しており、公共職業能力開発の目的である「ものづくりの育成」に大きく貢献しています。 そのため、高度な専門知識や技術・技能の習得に加え、企業が求める人材育成のため、意欲(やる気)とコミュニケーション能力の向上にも力を入れています。意欲向上のためには競争を促し優秀者を表彰する仕組みがあり、コミュニケーション能力向上のためにはグループワークや発表会などを活用しています。 卒業研究会・卒業制作会での発表や表彰、企業ニーズに沿った提案を行う「企業とのコラボレーション」の開催、テクニカルショーヨコハマへの学生出展なども行われています。
2. 産業技術短期大学校と産学連携 職業能力開発推進協議会
短期大学校の運営には、「産業技術短期大学校職業能力開発推進協議会」が大きく関わっています。この協議会は神奈川県に拠点を置く企業で構成され、2012年度には298社(機械・製造分野114社、情報分野90社、電子・電機・制御・通信分野50社、印刷・広告・デザイン分野22社など)が会員となっています。卒業生の就職先の約40%が同協議会の企業であることから、産学連携の緊密さがわかります。協議会は、カリキュラムへの助言、各種大会への訓練生参加支援、学業報償金の補助、産学連携講座への支援など、多大な貢献と協力をしています。このような協議会との連携は、神奈川県におけるものづくり人材育成に、短期大学校が重要な役割を果たしていることを示しています。 短期大学校は、専門知識や技術・技能の習得に加え、意欲やコミュニケーション能力の育成にも力を注いでおり、企業が求める人材育成を目指しています。 具体的には、競争を促すことで意欲を高め、グループワークや発表会などを活用してコミュニケーション能力を育成しています。
3. 応募 入校状況と修了 就職状況
応募者数は定員の1.3~1.4倍となっており、一定の水準の訓練生を確保できているものの、「低学力、動機不明入学、メンタル脆弱」化といった課題も抱えています。入学試験は推薦入試と一般入試があり、定員の4分の3が推薦入試、4分の1が一般入試です。入学者数はほぼ定員通りで、男性75%、女性25%(女性の多くは産業デザイン科)です。年齢・学歴構成では新規高卒が圧倒的に多いです。修了者は144名、修了率は72%(定員に対する割合)です。未修了者の28%は、中退者または卒業延長者で、就職中退者は含まれていません。これは、就職中退者が多い高等職業技術校(普通課程)とは対照的です。未修了者の多くは授業についていけなかったことが原因と考えられます。就職率は全体平均で67.8%ですが、東京都(77%)や北海道(82%)を下回っており、就職率60%以下のコースも複数あります。 中退者の多くは就職活動のための中退で、就職率に含めると71.9%に上昇します。
IV.在職者訓練 メニュー型とオーダー型
神奈川県の在職者訓練は、メニュー型とオーダー型に分けられています。高等職業技術校の短期課程が圧倒的に多く、中小企業の従業員の訓練が中心ですが、大企業からのオーダー型訓練も増加傾向にあります。大企業は、企業ニーズに合わせたオーダー型訓練を企業内教育の一環として活用しています。訓練コースには、IT関連、中高年向け、介護福祉、保育士養成など、多様な分野が含まれています。入校率はコースによって異なり、「IT関連」が高く、「母子家庭」が低い傾向が見られます。
1. 在職者訓練の種類 メニュー型とオーダー型 専門短期課程
神奈川県の在職者訓練は、他県と同様にメニュー型とオーダー型の2種類があります。ただし、神奈川県独自の要素として、短期課程に加え、高度職業訓練施設(職業能力開発大学校、同短期大学校)で行われる専門短期課程も存在します。2011年度のデータによると、高等職業技術校の短期課程が圧倒的に多く、講座数・訓練日数で全体の80%強、定員・受講者数で70%を占めています。 メニュー型とオーダー型の違いは、訓練内容の選択方法にあります。メニュー型は、あらかじめ用意されたコースから選択する形式であるのに対し、オーダー型は企業のニーズに合わせて訓練内容をカスタマイズする形式です。 受講者の内訳を見ると、在職者受講者が87%を占め、そのうち71%は中小企業の従業員です。これは、公共職業能力開発施設が中小企業の人材育成機関として重要な役割を果たしていることを示しています。一方、大企業の在職者も全体の3割近くを占めており、これらの企業は、企業ニーズに柔軟に対応できるオーダー型訓練を多く利用しており、企業内教育の一環として位置づけていると考えられます。
2. 在職者訓練のコース内容と受講状況
在職者訓練のコース内容は多岐に渡り、期間も3ヶ月~2年と様々です。例えば、「中高年」向けのコースはビジネス基本ソフトやマンション管理員養成など3ヶ月コースが中心です。「デュアル」システムは若者の自立支援を目的とした座学と企業実習(4ヶ月、うち1ヶ月が企業実習)からなる訓練です。「介護福祉」と「保育士養成」は、国家資格取得を目指す2年制のコースです。その他、「IT関連」や「知識等」(医療事務、介護福祉、簿記、販売など)のコースもあります。 入校率はコースによって異なり、「母子家庭」向けコースは50%と低く、応募者数が実施最小人数に満たず中止になることもありました。一方、「IT関連」は90%、「中高年」は96%と高い入校率を示しています。修了率は全体平均で91%と高く、多くのコースで90%以上です。ただし、「デュアル」コースは82%とやや低くなっていますが、これは東京都のデュアルシステム訓練の修了率(78%)と比較して、5ポイント程度高い数値です。
3. 在職者訓練の特徴 中小企業と大企業のニーズへの対応
神奈川県の在職者訓練は、メニュー型とオーダー型の両方を実施しており、他県と同様に、企業のニーズに合わせた柔軟な対応が特徴です。しかし、他県にはない専門短期課程が、高度職業訓練施設(職業能力開発大学校、同短期大学校)で提供されています。受講者の多くは在職者で、特に中小企業からの受講者が71%と大半を占めています。これは、公共職業能力開発施設が中小企業の人材育成において重要な役割を担っていることを示しています。しかしながら、大企業からの受講者も約3割存在し、彼らはオーダー型訓練を多く利用しています。このことは、大企業において、在職者訓練が企業内教育の一環として位置づけられていることを示唆しています。 高等職業技術校では、大企業在職者のオーダー型訓練が68%(410人)を占めていることが、この傾向を明確に示しています。
